19 / 33
【第三章】影の踊り場
18 : 溶け合う輪郭
しおりを挟む
休日の午後。
エリオは自室のソファに腰掛け、ぼんやりと本を開いていた。
先ほどからまるで進まぬ頁は、そのまま意識の停滞を映し出している。
座学や訓練、任務がある間は、まだ動けた。
そうでない時間も、何かしら理由をつけて意識を逸らし、やり過ごしてきた。
しかし、すべきことは些細な雑務までやり尽くしてしまった。
積み上げていた私物のケースまで整理してしまっては、いよいよ意識を逸らす手段が尽きる。
手持ち無沙汰に適当に本を開いてみても、すでに読み込んだ内容では、意識を引き込む力もなく。
エリオは物憂げに、ひとつため息を落とした。
唐突に耳慣れた機械音が鳴る。
机の上の端末に目を向ける。
ありがたい、とばかりに、膝の上に広げていただけの本をソファへ放り出し、長い足で机に歩み寄る。
通知の中身を確認し、訝しげに眉間を寄せた、その時。
軽く、ドアをノックする音がした。
通知に気を取られながらも、反射的に返事をする。
「……失礼します」
「………………ルクス?」
数日ぶりに目にした顔と、机上の端末を、エリオは交互に見やった。
「……なぜ来た」
エリオの声には、明らかな戸惑いがにじんでいた。
「体調が回復したので、明日から通常の訓練に戻ります」
「……ああ、それは、今、カスパルから連絡が来た」
机をはさみ、ドアを背にしたルクスと、距離を保ったまま、視線だけが絡む。
エリオは逡巡の後、口を開いた。
「……君には、申し訳ないことをした。……これでも反省している。もう、二度と軽率に君に……あんなふうに触れたりはしない」
ルクスは黙ったまま、ほんのしばらく立ち尽くしていたが、やがて、ぽつりと呟いた。
「……してくれていいのに」
「……何?」
「カスパルも、試してみるのもいいかもって」
声音にはどこか照れが混じっていたが、確かな意志が含まれていた。
「君は、カスパルが言えば何でも聞くのか?」
自分の言葉に滲んだ苛立ちに、エリオは気付く。
「そういうわけじゃないけど」
ルクスは、ほんの少しだけ視線を落とした。
「……もう、欲しくなくなった?」
「君は……」
エリオはこめかみに手をあて、思わず顔をしかめる。
先ほどよりも長く思える逡巡の後、エリオはドアの前に立つルクスのそばへと歩み寄る。
そして、ルクスの頬に手を伸ばしーー止めた。
「……触れてもいいか?」
返事の代わりに、ルクスはそっとその手に頬を寄せる。
掌に伝わるぬくもりに、エリオの鼓動がひときわ強く跳ねた。
もう片方の頬にも手を添え、存在の重みを確かめるように、唇を近付ける。
かすかなためらいを孕んだ、最初のキス。
ルクスは目を伏せたまま、それを受け入れた。
二度、三度と重ねるうちに、息遣いが少しずつ変わっていく。
やがて、ルクスの唇がそっと応えるように動いた。
近付いてくる唇に気付いたとき、喉がわずかに鳴った。
最初のキスは、とても静かで、あたたかく、少しだけ震えが混じっていた。
ルクス自身のものか、エリオのものか、それはわからなかった。
二度、三度と唇が重なるうちに、息が浅くなるのが自分でもわかった。
気付けば、自ら唇をそっと動かしていた。
頬をなぞるエリオの指が、首筋へと滑る。
反射的に、身体がわずかにこわばった。
けれど、逃げようとは思わなかった。
鎖骨のすぐ下に落ちた唇に、身体がかすかに震える。
触れられた場所から、息が詰まるような熱がじんわりと広がっていく。
エリオの手が、首や、背中や、腰をなぞるたびに、思わず息を吸った。
自分の身体が、こんなにも敏感に反応することに戸惑いながらも、もっと知りたい、触れられたいーーそう求めている自分を、確かに感じていた。
「……もっと、触れても?」
囁かれたその声に、ルクスは思わずエリオの背に手をまわしていた。
それがどういう意味をもつのか、考えるより先に、身体が動いていた。
吐息が、耳もとをかすめる。
くすぐったさと、痺れるようなざわつきが混ざって、喉の奥がひくりと動いた。
流されそうになる意識を抑えて、ルクスは告げる。
「……ひとつだけ、約束してくれたら」
言えなくなってしまう前に、言っておかなければならないことがあった。
カスパルは氷のうを頭に乗せたまま、ベッドに沈み込んでいた。
ここ数日の〈演算〉の酷使に、さすがに限界がきた。
まして、これまで使ったことのない回路を必死に動かしたのだ。
反動でこうなることは、わかっていた。
薄く目を開け、時計の針に視線を向ける。
ルクスがエリオの部屋へ向かってから、小半時ーーまだ戻っていないということは、予定どおりに事が運んでいるのだろう。
試してみてもいいかもしれない、と言った。
もともと、ルクスにはエリオを意識していた節があったし、エリオは、初めての相手としては悪くない。
それに、エリオのほうから、欲しい、と言ったのだ。
「……本気で欲しい相手には、あんなふうになるのか」
ぽつりと落としたひとり言が、静まり返った室内に、妙に大きく響いた気がした。
カスパルとエリオは、どちらもかなり幼い頃から能力を発露させていた。
能力研究機関ではよく顔を合わせたし、士官学院に入る前の子どもたちが集められていた中でも、特に年が近かった。
いわば、幼馴染のようなものだった。
そんな頃から知っている相手の、初めて見る顔が、ここ数日で何度もあった。
「あんな条件、あいつに都合がよすぎるんじゃないかと思ったけど……」
欲しさに任せて無遠慮に手を出してしまったことは反省していたし、同じ過ちは繰り返さないーーこれまで見てきた人となりからも、それは信じられる。
けれど、エリオは根っからの高位貴族の嫡男だ。
〈家〉が己であり、己が〈家〉であるということに、疑問の余地などない。
本人もまた、それを当然の義務として受け入れている。
その事実が、エリオという人間をエリオたらしめている。
変えようのない道を歩むエリオを、時が来れば見送るために、ルクスは、自分のほうから境界線を引くことにしたのだーー手放すために。
「君が、少しでも傷つかないことを願うよ」
静かに呟くと、カスパルは目を閉じた。
寝室のベッドの上で、ふたりは睦み合っていた。
衣擦れの音も、浅く重なる息遣いも、くぐもった世界の中で柔らかく響く。
腰へと滑る手、膝裏に添えられる指ーーそのひとつひとつが、ルクスの知らなかった感覚を呼び覚ましていく。
腹部を撫でられ、太腿の内側をそっとなぞられるたびに、じわりと熱が灯っていった。
脚がゆるく開かれる。
その動きに導かれるように、意識も、身体も、開かれていく。
そして奥へと触れられた瞬間ーールクスは反射的に、エリオの手を掴んでいた。
エリオの動きが止まる。
「……ルクス」
名前を呼ぶ声が、肌を透かして、内側へと沁みてくる。
「……無理なら、言ってくれ」
声も、唇も、少しでも動けば触れられるほど近い距離にある。
「……やっぱり、まだ少し怖いかも」
そう伝えると、エリオはそっと額にキスを落とした。
頬へ、唇へと、止めた手の代わりのように、エリオの唇が静かに触れていく。
張りつめた膜をほどくように、優しく口付けを重ねていく。
熱が、喉の奥へ、胸の奥へと染みていく感覚の中で、ルクスは掴んでいた手を、おそるおそる離した。
エリオは、ゆっくりと動き始めた。
確かめるように、あてがった指で、慎重に、奥へと進んでいく。
激しく動くことはしない。
ただ、少しずつ、こわばりを溶かすように。
怖がらせないようにしてくれているーーそのことが、はっきりと伝わってきた。
息が跳ね、喉が震える。
痛みと熱、そして見たことのない景色が、ひとつひとつ、ひらかれていく。
堪えていた声は、唇を分け入るようなキスに攫われ、露わになった。
強い波に呑まれるような感覚の中で、ふたりの輪郭は密に溶け合っていった。
エリオは自室のソファに腰掛け、ぼんやりと本を開いていた。
先ほどからまるで進まぬ頁は、そのまま意識の停滞を映し出している。
座学や訓練、任務がある間は、まだ動けた。
そうでない時間も、何かしら理由をつけて意識を逸らし、やり過ごしてきた。
しかし、すべきことは些細な雑務までやり尽くしてしまった。
積み上げていた私物のケースまで整理してしまっては、いよいよ意識を逸らす手段が尽きる。
手持ち無沙汰に適当に本を開いてみても、すでに読み込んだ内容では、意識を引き込む力もなく。
エリオは物憂げに、ひとつため息を落とした。
唐突に耳慣れた機械音が鳴る。
机の上の端末に目を向ける。
ありがたい、とばかりに、膝の上に広げていただけの本をソファへ放り出し、長い足で机に歩み寄る。
通知の中身を確認し、訝しげに眉間を寄せた、その時。
軽く、ドアをノックする音がした。
通知に気を取られながらも、反射的に返事をする。
「……失礼します」
「………………ルクス?」
数日ぶりに目にした顔と、机上の端末を、エリオは交互に見やった。
「……なぜ来た」
エリオの声には、明らかな戸惑いがにじんでいた。
「体調が回復したので、明日から通常の訓練に戻ります」
「……ああ、それは、今、カスパルから連絡が来た」
机をはさみ、ドアを背にしたルクスと、距離を保ったまま、視線だけが絡む。
エリオは逡巡の後、口を開いた。
「……君には、申し訳ないことをした。……これでも反省している。もう、二度と軽率に君に……あんなふうに触れたりはしない」
ルクスは黙ったまま、ほんのしばらく立ち尽くしていたが、やがて、ぽつりと呟いた。
「……してくれていいのに」
「……何?」
「カスパルも、試してみるのもいいかもって」
声音にはどこか照れが混じっていたが、確かな意志が含まれていた。
「君は、カスパルが言えば何でも聞くのか?」
自分の言葉に滲んだ苛立ちに、エリオは気付く。
「そういうわけじゃないけど」
ルクスは、ほんの少しだけ視線を落とした。
「……もう、欲しくなくなった?」
「君は……」
エリオはこめかみに手をあて、思わず顔をしかめる。
先ほどよりも長く思える逡巡の後、エリオはドアの前に立つルクスのそばへと歩み寄る。
そして、ルクスの頬に手を伸ばしーー止めた。
「……触れてもいいか?」
返事の代わりに、ルクスはそっとその手に頬を寄せる。
掌に伝わるぬくもりに、エリオの鼓動がひときわ強く跳ねた。
もう片方の頬にも手を添え、存在の重みを確かめるように、唇を近付ける。
かすかなためらいを孕んだ、最初のキス。
ルクスは目を伏せたまま、それを受け入れた。
二度、三度と重ねるうちに、息遣いが少しずつ変わっていく。
やがて、ルクスの唇がそっと応えるように動いた。
近付いてくる唇に気付いたとき、喉がわずかに鳴った。
最初のキスは、とても静かで、あたたかく、少しだけ震えが混じっていた。
ルクス自身のものか、エリオのものか、それはわからなかった。
二度、三度と唇が重なるうちに、息が浅くなるのが自分でもわかった。
気付けば、自ら唇をそっと動かしていた。
頬をなぞるエリオの指が、首筋へと滑る。
反射的に、身体がわずかにこわばった。
けれど、逃げようとは思わなかった。
鎖骨のすぐ下に落ちた唇に、身体がかすかに震える。
触れられた場所から、息が詰まるような熱がじんわりと広がっていく。
エリオの手が、首や、背中や、腰をなぞるたびに、思わず息を吸った。
自分の身体が、こんなにも敏感に反応することに戸惑いながらも、もっと知りたい、触れられたいーーそう求めている自分を、確かに感じていた。
「……もっと、触れても?」
囁かれたその声に、ルクスは思わずエリオの背に手をまわしていた。
それがどういう意味をもつのか、考えるより先に、身体が動いていた。
吐息が、耳もとをかすめる。
くすぐったさと、痺れるようなざわつきが混ざって、喉の奥がひくりと動いた。
流されそうになる意識を抑えて、ルクスは告げる。
「……ひとつだけ、約束してくれたら」
言えなくなってしまう前に、言っておかなければならないことがあった。
カスパルは氷のうを頭に乗せたまま、ベッドに沈み込んでいた。
ここ数日の〈演算〉の酷使に、さすがに限界がきた。
まして、これまで使ったことのない回路を必死に動かしたのだ。
反動でこうなることは、わかっていた。
薄く目を開け、時計の針に視線を向ける。
ルクスがエリオの部屋へ向かってから、小半時ーーまだ戻っていないということは、予定どおりに事が運んでいるのだろう。
試してみてもいいかもしれない、と言った。
もともと、ルクスにはエリオを意識していた節があったし、エリオは、初めての相手としては悪くない。
それに、エリオのほうから、欲しい、と言ったのだ。
「……本気で欲しい相手には、あんなふうになるのか」
ぽつりと落としたひとり言が、静まり返った室内に、妙に大きく響いた気がした。
カスパルとエリオは、どちらもかなり幼い頃から能力を発露させていた。
能力研究機関ではよく顔を合わせたし、士官学院に入る前の子どもたちが集められていた中でも、特に年が近かった。
いわば、幼馴染のようなものだった。
そんな頃から知っている相手の、初めて見る顔が、ここ数日で何度もあった。
「あんな条件、あいつに都合がよすぎるんじゃないかと思ったけど……」
欲しさに任せて無遠慮に手を出してしまったことは反省していたし、同じ過ちは繰り返さないーーこれまで見てきた人となりからも、それは信じられる。
けれど、エリオは根っからの高位貴族の嫡男だ。
〈家〉が己であり、己が〈家〉であるということに、疑問の余地などない。
本人もまた、それを当然の義務として受け入れている。
その事実が、エリオという人間をエリオたらしめている。
変えようのない道を歩むエリオを、時が来れば見送るために、ルクスは、自分のほうから境界線を引くことにしたのだーー手放すために。
「君が、少しでも傷つかないことを願うよ」
静かに呟くと、カスパルは目を閉じた。
寝室のベッドの上で、ふたりは睦み合っていた。
衣擦れの音も、浅く重なる息遣いも、くぐもった世界の中で柔らかく響く。
腰へと滑る手、膝裏に添えられる指ーーそのひとつひとつが、ルクスの知らなかった感覚を呼び覚ましていく。
腹部を撫でられ、太腿の内側をそっとなぞられるたびに、じわりと熱が灯っていった。
脚がゆるく開かれる。
その動きに導かれるように、意識も、身体も、開かれていく。
そして奥へと触れられた瞬間ーールクスは反射的に、エリオの手を掴んでいた。
エリオの動きが止まる。
「……ルクス」
名前を呼ぶ声が、肌を透かして、内側へと沁みてくる。
「……無理なら、言ってくれ」
声も、唇も、少しでも動けば触れられるほど近い距離にある。
「……やっぱり、まだ少し怖いかも」
そう伝えると、エリオはそっと額にキスを落とした。
頬へ、唇へと、止めた手の代わりのように、エリオの唇が静かに触れていく。
張りつめた膜をほどくように、優しく口付けを重ねていく。
熱が、喉の奥へ、胸の奥へと染みていく感覚の中で、ルクスは掴んでいた手を、おそるおそる離した。
エリオは、ゆっくりと動き始めた。
確かめるように、あてがった指で、慎重に、奥へと進んでいく。
激しく動くことはしない。
ただ、少しずつ、こわばりを溶かすように。
怖がらせないようにしてくれているーーそのことが、はっきりと伝わってきた。
息が跳ね、喉が震える。
痛みと熱、そして見たことのない景色が、ひとつひとつ、ひらかれていく。
堪えていた声は、唇を分け入るようなキスに攫われ、露わになった。
強い波に呑まれるような感覚の中で、ふたりの輪郭は密に溶け合っていった。
0
あなたにおすすめの小説

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

何故よりにもよって恋愛ゲームの親友ルートに突入するのか
風
BL
平凡な学生だったはずの俺が転生したのは、恋愛ゲーム世界の“王子”という役割。
……けれど、攻略対象の女の子たちは次々に幸せを見つけて旅立ち、
気づけば残されたのは――幼馴染みであり、忠誠を誓った騎士アレスだけだった。
「僕は、あなたを守ると決めたのです」
いつも優しく、忠実で、完璧すぎるその親友。
けれど次第に、その視線が“友人”のそれではないことに気づき始め――?
身分差? 常識? そんなものは、もうどうでもいい。
“王子”である俺は、彼に恋をした。
だからこそ、全部受け止める。たとえ、世界がどう言おうとも。
これは転生者としての使命を終え、“ただの一人の少年”として生きると決めた王子と、
彼だけを見つめ続けた騎士の、
世界でいちばん優しくて、少しだけ不器用な、じれじれ純愛ファンタジー。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

僕の、しあわせ辺境暮らし
* ゆるゆ
BL
雪のなか3歳の僕を、ひろってくれたのは、やさしい16歳の男の子でした。
ふたりの、しあわせな辺境暮らし、はじまります!
ぽて と むーちゃんの動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵もあがります。
YouTube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。
プロフのwebサイトから飛べるので、もしよかったら!

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。
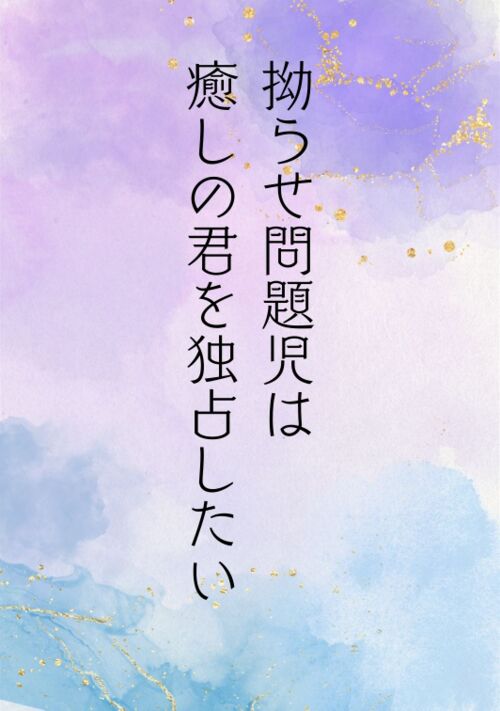
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















