12 / 14
12
しおりを挟む
当然のように自分の言葉を受け入れてもらえて、知花はほっと息を吐いた。
「他にも、心当たりってある?」
伊月は、知花を見つめたまま、たんたんと聴いてきた。
「他……。あえていうなら、ときどき、すごく寒く感じます。封筒が現れる前後に」
「ふうん……。面白いね」
伊月は小さくうなずいて、あらためて知花を見た。
「ほんとうに、面白い……」
言いながら、伊月はふらっと体勢を崩し、背後の梶にもたれかかるように倒れた。
「伊月……、ちょっと深追いしすぎだ」
梶は大きな体を縮めて、伊月を抱きとめる。
ハルは席を立ち、自分の椅子をずらして、伊月の椅子にぴったりと並べた。
「梶先輩、こっち座ってください」
「おー、わりぃな。ハル」
梶はハルの椅子に座ると、伊月の頭を抱え込んだ。
「アキ、はなして。だいじょうぶだから」
「黙れ、伊月。自分の限界超えたことして倒れ掛かってる人の話はききませーん」
梶の腕を外そうと首をふる伊月の頭を、梶はますます力を込めて抱きかかえた。
そして梶が座っていた席にうつったハルと知花に片手をあげた。
「ごめんな、伊月はちょっと休憩とらせるわ」
「もちろんです! ……でも伊月がそんなになるなんて、これ、わりとヤバい感じなんですね」
「べつに、その封筒はそんなヤバくないよ」
梶の腕の中から、伊月が疲れた声で言った。
「伊月。お前はしばらくおとなしくしてろ」
「話すくらいだいじょうぶだって……。アキは過保護すぎ」
「すぐ倒れそうになるお前が悪い」
「これくらい、もう平気だし」
ふてくされたように言う伊月を、梶は力任せに抱きしめた。
「ぐえっ」という小さな声が聞こえて、ハルはおろおろと二人を見ている。
「そんな青い顔色して、平気なわけないでしょ」
「アキが締め付けてくるからでしょ……。ていうか、あとちょっとでいろいろわかりそうなのに。邪魔しないでよ」
「その前にお前が倒れたらどうするんだよ。邪魔するに決まってるでしょーが」
伊月が赤い封筒を集中して視ようとするたび、梶は伊月を締め付けたり、つついたりしてその集中を妨げる。
「もー! 邪魔するなって!」
「お前、自分の顔色見てから言えよ。それに、その封筒自体はそう悪いものじゃなさそうって言っても、それを目印に悪い霊がくるかもしれないんだろ。そのうえ、他にもまだなんかあるっぽいって……。お前がそんな集中して視てもわからないなら大物って可能性もあるんだぞ」
「だーかーら。そういうんじゃないんだってば。大物とかじゃなくて、わかりにくいだけ! 手がかかりが少ないから、わかりにくいってだけなんだって」
伊月と梶が、もめ始めた。
べったりとくっついたまま言い争うふたりは、伊月はただただうっとうしそうで、梶は伊月を過剰に心配しているように見えた。
喧嘩のような怒りはどちらにも見えないので、怖くはない。
とはいえ、知り合ったばかりの男子の言い合いに割って入るのは難しく、そもそもどちらの言い分が正しいのかも知花にはわからない。
赤い封筒が危険を招くというのなら、それがどんなものなのか気にならないわけはない。
身勝手は承知だけれど、伊月にそれを探ってほしいという気持ちもあった。
だがそれも、伊月が危険だというのなら、お願いするのも躊躇する。
膠着した場を動かしたのは、夏山だった。
「じゃぁ、この封筒、俺が開けましょうか」
夏山は、山盛りに盛られていたどんぶりのごはんも、ヤンニョムチキンも食べきっていた。
満足げな笑みを浮かべ、上機嫌で梶を見た。
「夏山が……?」
梶が思案気にいうと、梶の腕の中から伊月が口をはさんだ。
「夏山はダメ。ハルが開けて」
「俺が……?」
ハルは不思議そうに首をかしげたが、「まぁ伊月がそういうなら」と知花のトレーに視線を移した。
「じゃ、開けるな」
悔しそうな表情の夏山の前で、ハルは結界の中の封筒へ手を伸ばす。
青白い光に囲われたところにハルの手が入っていくのを見て、知花は叫びそうになったが、ハルのすらりとした手はなんの抵抗もなく結界の中に入り、赤い封筒をつかんだ。
「なにも危険はないと思うけど、いちおうその結界の中で開けてね」
「おう!」
伊月の指示に短くうなずいて、ハルは封筒に手をかけた。
封筒は封もされていなかったらしく、折り返されている蓋の部分はなんの抵抗もなく開いた。
「うひー。伊月、これって中身だしたほうがいいよな?」
「うん、お願い」
「わー。なんか緊張する……」
ハルはおびえたような表情で言うが、手の動きはよどみない。
一瞬の間をおいて、封筒の中から一片の紙をとりだした。
突如あらわれる、赤い封筒。
ポストカードサイズのそれに入っていたのは、同じく深い赤色のポストカードのような紙だった。
「じゃぁ、開けるなー」
半分に折りたたまれたカードを持って、ハルは伊月の顔を見る。
伊月はまだ少し青ざめた顔色で、梶にもたれかかったままうなずいた。
そっとハルがカードを開いた。
「……っ」
その瞬間、知花の口から声にならない声が漏れた。
赤い封筒に入っていた、赤いポストカード。
そこには、黒々とした墨蹟で「相川友也」「久保知花」。
見知らぬ男の名前と、知花の名前だけが書かれていた。
「他にも、心当たりってある?」
伊月は、知花を見つめたまま、たんたんと聴いてきた。
「他……。あえていうなら、ときどき、すごく寒く感じます。封筒が現れる前後に」
「ふうん……。面白いね」
伊月は小さくうなずいて、あらためて知花を見た。
「ほんとうに、面白い……」
言いながら、伊月はふらっと体勢を崩し、背後の梶にもたれかかるように倒れた。
「伊月……、ちょっと深追いしすぎだ」
梶は大きな体を縮めて、伊月を抱きとめる。
ハルは席を立ち、自分の椅子をずらして、伊月の椅子にぴったりと並べた。
「梶先輩、こっち座ってください」
「おー、わりぃな。ハル」
梶はハルの椅子に座ると、伊月の頭を抱え込んだ。
「アキ、はなして。だいじょうぶだから」
「黙れ、伊月。自分の限界超えたことして倒れ掛かってる人の話はききませーん」
梶の腕を外そうと首をふる伊月の頭を、梶はますます力を込めて抱きかかえた。
そして梶が座っていた席にうつったハルと知花に片手をあげた。
「ごめんな、伊月はちょっと休憩とらせるわ」
「もちろんです! ……でも伊月がそんなになるなんて、これ、わりとヤバい感じなんですね」
「べつに、その封筒はそんなヤバくないよ」
梶の腕の中から、伊月が疲れた声で言った。
「伊月。お前はしばらくおとなしくしてろ」
「話すくらいだいじょうぶだって……。アキは過保護すぎ」
「すぐ倒れそうになるお前が悪い」
「これくらい、もう平気だし」
ふてくされたように言う伊月を、梶は力任せに抱きしめた。
「ぐえっ」という小さな声が聞こえて、ハルはおろおろと二人を見ている。
「そんな青い顔色して、平気なわけないでしょ」
「アキが締め付けてくるからでしょ……。ていうか、あとちょっとでいろいろわかりそうなのに。邪魔しないでよ」
「その前にお前が倒れたらどうするんだよ。邪魔するに決まってるでしょーが」
伊月が赤い封筒を集中して視ようとするたび、梶は伊月を締め付けたり、つついたりしてその集中を妨げる。
「もー! 邪魔するなって!」
「お前、自分の顔色見てから言えよ。それに、その封筒自体はそう悪いものじゃなさそうって言っても、それを目印に悪い霊がくるかもしれないんだろ。そのうえ、他にもまだなんかあるっぽいって……。お前がそんな集中して視てもわからないなら大物って可能性もあるんだぞ」
「だーかーら。そういうんじゃないんだってば。大物とかじゃなくて、わかりにくいだけ! 手がかかりが少ないから、わかりにくいってだけなんだって」
伊月と梶が、もめ始めた。
べったりとくっついたまま言い争うふたりは、伊月はただただうっとうしそうで、梶は伊月を過剰に心配しているように見えた。
喧嘩のような怒りはどちらにも見えないので、怖くはない。
とはいえ、知り合ったばかりの男子の言い合いに割って入るのは難しく、そもそもどちらの言い分が正しいのかも知花にはわからない。
赤い封筒が危険を招くというのなら、それがどんなものなのか気にならないわけはない。
身勝手は承知だけれど、伊月にそれを探ってほしいという気持ちもあった。
だがそれも、伊月が危険だというのなら、お願いするのも躊躇する。
膠着した場を動かしたのは、夏山だった。
「じゃぁ、この封筒、俺が開けましょうか」
夏山は、山盛りに盛られていたどんぶりのごはんも、ヤンニョムチキンも食べきっていた。
満足げな笑みを浮かべ、上機嫌で梶を見た。
「夏山が……?」
梶が思案気にいうと、梶の腕の中から伊月が口をはさんだ。
「夏山はダメ。ハルが開けて」
「俺が……?」
ハルは不思議そうに首をかしげたが、「まぁ伊月がそういうなら」と知花のトレーに視線を移した。
「じゃ、開けるな」
悔しそうな表情の夏山の前で、ハルは結界の中の封筒へ手を伸ばす。
青白い光に囲われたところにハルの手が入っていくのを見て、知花は叫びそうになったが、ハルのすらりとした手はなんの抵抗もなく結界の中に入り、赤い封筒をつかんだ。
「なにも危険はないと思うけど、いちおうその結界の中で開けてね」
「おう!」
伊月の指示に短くうなずいて、ハルは封筒に手をかけた。
封筒は封もされていなかったらしく、折り返されている蓋の部分はなんの抵抗もなく開いた。
「うひー。伊月、これって中身だしたほうがいいよな?」
「うん、お願い」
「わー。なんか緊張する……」
ハルはおびえたような表情で言うが、手の動きはよどみない。
一瞬の間をおいて、封筒の中から一片の紙をとりだした。
突如あらわれる、赤い封筒。
ポストカードサイズのそれに入っていたのは、同じく深い赤色のポストカードのような紙だった。
「じゃぁ、開けるなー」
半分に折りたたまれたカードを持って、ハルは伊月の顔を見る。
伊月はまだ少し青ざめた顔色で、梶にもたれかかったままうなずいた。
そっとハルがカードを開いた。
「……っ」
その瞬間、知花の口から声にならない声が漏れた。
赤い封筒に入っていた、赤いポストカード。
そこには、黒々とした墨蹟で「相川友也」「久保知花」。
見知らぬ男の名前と、知花の名前だけが書かれていた。
0
あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

皆さんは呪われました
禰津エソラ
ホラー
あなたは呪いたい相手はいますか?
お勧めの呪いがありますよ。
効果は絶大です。
ぜひ、試してみてください……
その呪いの因果は果てしなく絡みつく。呪いは誰のものになるのか。
最後に残るのは誰だ……

百物語 厄災
嵐山ノキ
ホラー
怪談の百物語です。一話一話は長くありませんのでお好きなときにお読みください。渾身の仕掛けも盛り込んでおり、最後まで読むと驚くべき何かが提示されます。
小説家になろう、エブリスタにも投稿しています。


なおこちゃんの手紙【モキュメンタリー】
武州青嵐(さくら青嵐)
ホラー
ある日、伊勢涼子のもとに、友人の優奈から「三沢久美の相談にのってあげてほしい」と連絡が入る。
三沢久美は子どもが持って帰ってきた「なおこちゃんの手紙」という手紙をもてあましていた。
その文面は、
「これは、なおこちゃんからの手紙です。
なおこちゃんは、パンがすきなおんなの子です。
かくれんぼをしています。ときどき、みつからないようにでてきます。
おともだちをぼしゅう中です。
だから、この手紙をもらったひとは、10日いないに、じぶんのともだち5人に、このなおこちゃんからの手紙をだしてください。文めんはおなじにしてください。
もし手紙をださなかったり、文めんを変えたら、なおこちゃんがやってきて、かくれんぼをするぞ。」
というもの。
三沢はこの手紙を写真に撮り、涼子にメールで送りつけてから連絡を絶つ。
数日後、近所の小学校でとある事件が発生。5人の女児がパニックを起こして怪我をする、というものだった。
その女児たちはいずれも、「なおこちゃんの手紙」を受け取っていた。
趣味で怪談実話をカクヨムで掲載している涼子は、この手紙を追っていくのだが……。
その彼女のもとに。
ひとりの女児が現れる。
※モキュメンタリー形式ですので、時系列に物語が進むわけではありません。
同名タイトルでカクヨムにも掲載
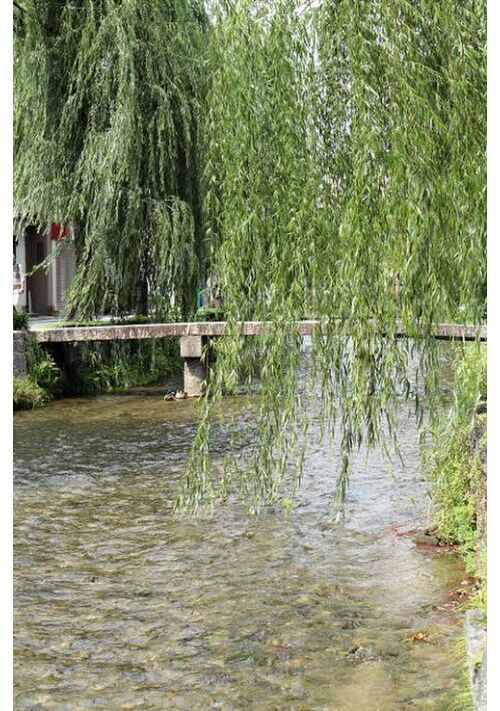

終焉列島:ゾンビに沈む国
ねむたん
ホラー
2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。
最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。
会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

偽夫婦お家騒動始末記
紫紺
歴史・時代
【第10回歴史時代大賞、奨励賞受賞しました!】
故郷を捨て、江戸で寺子屋の先生を生業として暮らす篠宮隼(しのみやはやて)は、ある夜、茶屋から足抜けしてきた陰間と出会う。
紫音(しおん)という若い男との奇妙な共同生活が始まるのだが。
隼には胸に秘めた決意があり、紫音との生活はそれを遂げるための策の一つだ。だが、紫音の方にも実は裏があって……。
江戸を舞台に様々な陰謀が駆け巡る。敢えて裏街道を走る隼に、念願を叶える日はくるのだろうか。
そして、拾った陰間、紫音の正体は。
活劇と謎解き、そして恋心の長編エンタメ時代小説です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















