あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

皆さんは呪われました
禰津エソラ
ホラー
あなたは呪いたい相手はいますか?
お勧めの呪いがありますよ。
効果は絶大です。
ぜひ、試してみてください……
その呪いの因果は果てしなく絡みつく。呪いは誰のものになるのか。
最後に残るのは誰だ……

意味がわかると怖い話
邪神 白猫
ホラー
【意味がわかると怖い話】解説付き
基本的には読めば誰でも分かるお話になっていますが、たまに激ムズが混ざっています。
※完結としますが、追加次第随時更新※
YouTubeにて、朗読始めました(*'ω'*)
お休み前や何かの作業のお供に、耳から読書はいかがですか?📕
https://youtube.com/@yuachanRio

百物語 厄災
嵐山ノキ
ホラー
怪談の百物語です。一話一話は長くありませんのでお好きなときにお読みください。渾身の仕掛けも盛り込んでおり、最後まで読むと驚くべき何かが提示されます。
小説家になろう、エブリスタにも投稿しています。
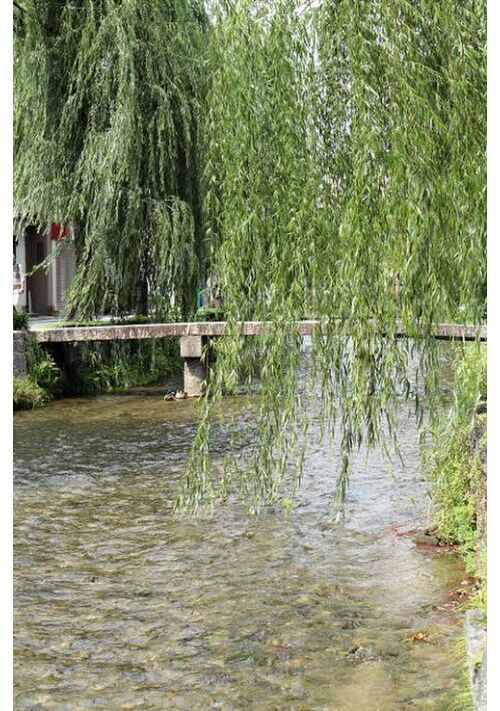

終焉列島:ゾンビに沈む国
ねむたん
ホラー
2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。
最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。
会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

偽夫婦お家騒動始末記
紫紺
歴史・時代
【第10回歴史時代大賞、奨励賞受賞しました!】
故郷を捨て、江戸で寺子屋の先生を生業として暮らす篠宮隼(しのみやはやて)は、ある夜、茶屋から足抜けしてきた陰間と出会う。
紫音(しおん)という若い男との奇妙な共同生活が始まるのだが。
隼には胸に秘めた決意があり、紫音との生活はそれを遂げるための策の一つだ。だが、紫音の方にも実は裏があって……。
江戸を舞台に様々な陰謀が駆け巡る。敢えて裏街道を走る隼に、念願を叶える日はくるのだろうか。
そして、拾った陰間、紫音の正体は。
活劇と謎解き、そして恋心の長編エンタメ時代小説です。

ヤンデレ美少女転校生と共に体育倉庫に閉じ込められ、大問題になりましたが『結婚しています!』で乗り切った嘘のような本当の話
桜井正宗
青春
――結婚しています!
それは二人だけの秘密。
高校二年の遙と遥は結婚した。
近年法律が変わり、高校生(十六歳)からでも結婚できるようになっていた。だから、問題はなかった。
キッカケは、体育倉庫に閉じ込められた事件から始まった。校長先生に問い詰められ、とっさに誤魔化した。二人は退学の危機を乗り越える為に本当に結婚することにした。
ワケありヤンデレ美少女転校生の『小桜 遥』と”新婚生活”を開始する――。
*結婚要素あり
*ヤンデレ要素あり
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















