7 / 10
■七 夏鈴
しおりを挟む
前のバイトで友達になった、一回り年上の岡本愛華さんと会っていた。愛華さんはとにかくゴシップが好きな人だった。アイドルの誰々はスポーツ選手と付き合ってるとか。そういう夢みたいな話ばっかり。だけど手の届く範囲の噂話も好きで、ホテル清掃のバイトをしていた時は同僚と上司の情事みたいなことも積極的に教えてくれた。別に知りたくはなかった。
ゴシップに命を賭けたパパラッチみたいな人だったけど、本人はジェームズ・ボンドに憧れてるって言ってた。自己紹介では必ず「愛華、宮本愛華」って名乗ってたし。スパイに憧れてるんだって。噂話を収集する癖も、情報戦に勝利する布石らしいよ。ちょっと変わってるよね。
一緒にバイトをしてた現役時代、愛華さんは職場の鼻つまみ者で、あたしも距離を置いて付き合ってた。四六時中他人の噂話をしている人なんてあんまり感じが良くないし。仲良くしようとは思わなかった。むしろ辞めてからの方が友情が深まった感じがある。彼女がスパイグッズの収集家だったから。ママと篤郎のことがなければ、愛華さんのことなんてすっかり忘れてたけど、秘密裏に動く必要に迫られて思い出した。そう言えばあの人、盗聴器とか詳しかったなって。それで連絡したの。「愛華さん、盗聴器とか持ってたら貸して」って。バイト時代のゴールデンコンビ再結成ってわけ。
盗聴器はある程度役に立ったけど、今度は小型カメラが必要になってさ。もう音声の時代じゃないって思った。そんな生ぬるいスパイ行為をしていても埒が明かない。今度は映像でもって、言い訳の効かない証拠をママに突きつけてやる。ってことで「愛華さん、あたしに小型カメラを貸したら良いことあるかも知んないよ」つってやった。愛華さんは多分友達が少ないんだと思う。そりゃそうだよね。ロン・ガレラみたいなパパラッチが身近にいたんじゃ皆警戒する。だから、あたしが彼女自慢のスパイグッズに興味を持ったことが嬉しかったんじゃないかな。ようやく同好の士が見つかった、みたいな気迫を感じるもの。
二つ返事で超高性能の小型カメラを貸してくれた。こんなに小さくなくてもいいんじゃないかってくらいに小さいカメラだった。多分頭痛薬一錠よりも小さい。それ二つ。愛華さんが言うにはそれでも高性能らしい。ママと篤郎の皺の奥まで録画したいわけじゃなかったから、性能は並って感じでも良かったんだけど、愛華さんが興奮しちゃってさ。カメラを借りるために、ホテル近くのカフェまで行ったんだけどこっちが恥ずかしくなるくらい早口で性能を説明された。
話している内容が盗撮用の小型カメラっていう非常にセンシティブなものなのに、あの人全然気にしないんだもん。あたしはまだ良いよ。バイトはクビになったし、もうあの高級ホテルには縁もゆかりも無いんだから。でもさ、愛華さんはまだ清掃係として働いてるわけじゃん。職場の近くでそんな話して、普通は気不味いと思うけど。でもまあ、スパイオタクの戯言にも腰を据えて付き合ったよ。無料で貸してくれるし、話くらいは黙って聞くのが筋かなって思ったから。愛華さんの休憩時間が終わったことで半ば強制的に与太話が打ち切られた瞬間、あたしは走って店を出たね。会計もせず。たとえ二人分のコーヒー代とはいえ、あたしに金の余裕なんてない。心の中で「ごめん」って呟きながら愛華さんのスパイ講座から脱出した。
借りたカメラを、今度はリビングと両親の寝室に仕掛けようと思った。もしかしたらクリティカルに考えたくもない盗撮ポルノを制作してしまう可能性はあった。万が一ママと篤郎が出演していたら最悪だけど、それはあんまり気にしてなかった。可能性は低いはずだ。いくらのぼせ上がっていても、パパが頻繁に出入りする母屋で性欲を抑えきれないほど二人共若くはない。むしろ、両親の情事をまざまざと見せつけられる可能性の方が高かった。あの二人が未だに愛し合っているかは分からないけど。自分ちの寝室ならそういうことだってあるだろう。あたしだって本当なら、こんなことはしたくない。でもさ、ママの態度に怪しさが払拭できないから。あたしに極端な行動を取らせたのはママのせい。もしバレたらそうやって自分を正当化するんだ。
カフェからの帰り道はるんるんだった。色んな問題を抱えているけど、まずはこれで篤郎をクビに出来るって思った。いくらママが庇おうとも、女房といかがわしいことをしていたならばパパだって黙っていないだろう。そのことを考えると自然と足取りが軽くなった。ママの弱みを握れるかもしれないし。こうなりゃ、ママと篤郎に関係があってほしいのか、なければいいと思っているのか自分でも分からなくなっていた。ただ最新のガジェットの威力を試してみたかっただけかもしれない。
倉庫には夢乃がいた。一人で丸椅子に座って、あたしの作品を眺めていた。意味あり気に顎の下に指を置いて、まるでレオ・キャステリみたいだった。あたしが背中を叩くと、心臓を掴まれたみたいな顔して「なんなの?」って飛び上がってた。いつものことだ。
「おつかれ、一人?」
「うん」夢乃は胸に手をおいて、鼓動を感じることで落ち着こうと努めていた。「篤郎はサボってたから外回りに行かせた。今日はそのまま帰っていいって言っといたから直帰するはず。おじさんはまだ帰ってきてないね。おばさんは分からないけど、多分買い物かなんかじゃないかな。店の方にもいなかったよ」
「へえ、チャンスじゃん」
「チャンスってなに? それよりさ、夏鈴さ、勝手にプレゼン終わらせちゃったんだって? 私資料準備してたんだよ。まあ良いけどさ、それで結果はどうだったの? 篤郎は物別れに終わったって言ってたけど」
「ああ、あれはね、まあジャブみたいなものだよね。これから渾身のストレートを放つからさ、距離感図ってたっていうか。だから夢乃の資料は無駄にならないよ。これから使う。大丈夫」
言いながらあたしは母屋の方へと足を向けた。夢乃との会議も重要だったけど、誰もいないこのチャンスを逃したくなかった。背後に夢乃の足音が聞こえた。
「ねえ、どこ行くの?」
「必要なことをするの。まずは篤郎をこの家から追い出さなきゃ。それと、常にあたし達の反対派に回るママの弱みを握るの」
店舗を抜けて、靴を脱いでから廊下に上がる。突き当りの階段をのぼった。
「どういうこと? それに篤郎は夏鈴が思うほど悪い人間じゃないかもよ」
その言葉に反応して振り返ると、眼下に迫る夢乃のつむじが見えた。
「懐柔されたのか?」
「そういうんじゃないけどさ」夢乃が上目遣いで答える。「でもさ、おばさんと篤郎のこと気にするより真っ直ぐに仕事のことを考えた方が建設的な気がするんだよね。ほら、私達ピンチなわけだし、あんまりそういうことに力を入れすぎない方が良いような気がして」
終盤にかけて段々と声が小さくなっていってた。あたしは嬉しさ半分、寂しさ半分っていう複雑な心境を抱いた。だって、あたしの言う事にはなんでも賛成っていうのが夢乃のスタイルのはずだったから。もちろんなんでも賛成の夢乃に不満なんてなかった。それが彼女の長所だし。でもさ、これでいいのかな? って考えたことならある。それで夢乃は楽しいのかなって。そんな夢乃が、あたしに意見してくるなんて。感慨深かった。反抗期の娘を見ているようだった。
だけど気にはなった。なんで突然、楯突いたんだ? なにかあったのか? 篤郎のことを庇ったりして。どういうつもりだろう。でもちょっと潔癖症気味の夢乃のことだ。ママと篤郎の本当の関係を炙り出すことができれば、きっと目を覚ますに違いない。「不潔」とか言って篤郎追放賛成派に回ってくれるはずだ。
「結論を出すのはまだ早いよ。取り敢えずあたしを信じて今まで通りついてきて」
しっかりと夢乃の目を見て言った。彼女が頷く前にこちらから首を縦に振る。つられて夢乃も頷いた。階段の途中で、中途半端なまま止めていた足を再び動かし二階にあがった。右側の扉を開くと、夢乃が「え?」と声を上げた。その扉の先は、両親の寝室だと分かっていたからだ。きっと左側にある扉から、あたしの部屋に入ると思い込んでいたのだろう。ふふふ。今日は違うんですよ。
寝室の中央にはベッドが置かれている。その上に、二人分のパジャマが申し訳程度に畳まれていた。ベッドの周りは全部ママのスペースだ。押し入れには入らなかった衣服を入れるタンスと化粧台が空間を圧迫している。つまり寝室はほとんどママのための部屋だった。
パパの私物はここにはない。昔は倉庫に置いてあったけど、あたし達の仕事場になってからはもうそこにもない。パパが仕事で使うバンに押し込んだから。パパはいつでも蒸発出来る体制で仕事に励んでるってこと。本当の意味でノマドって言えるかもしれない。元々パパに私物なんてほとんどないんだ。作業着と仕事道具だけ。仕事に命をかける昭和の男だから。
あたしはまず部屋を見回した。全体を俯瞰できる場所にカメラを仕掛ける必要があったから。ベッドに乗ってきょろきょろとしてる姿を、夢乃は不思議そうに眺めていた。
「ねえ、なにやってるの?」
「カメラを仕掛けようと思うんだよね。ベストポジションを探してるの」
夢乃はもう何も言わなかった。あたしがタンスの上に当たりをつけ、そこに置いてあった埃だらけのマックブックの空き箱をベッドに投げると、その放物線を目で追っていた。
「ちょっとそこ立ってくれる?」
カメラの角度を調整しつつ、スマホで映像を確認する。そう。この超小型カメラにはスマホ連動機能があるのだ。愛華さんに言わせれば、最近の業界では必須のオプションなんだとさ。あたしの言葉に反応して、戸惑いながらも立ち位置を調整する夢乃の姿がスマホに映った。
すると、夢乃がベッドを指さして「ねえ」と言った。スマホから目を離し、ベッドを見る。マックブックの空き箱に、スーサイドボムを食らった缶が蓋を開けて転がっていた。元はお菓子が入った缶だったのだろう。今では所々凹んでいたり、錆が浮いていたり、上からステッカーを貼られていたりと原型をとどめていない。あたしはそんなことよりも、画角が気になっていた。ベッド近くに移動する夢乃を無視してカメラの調整を進める。
「ねえ、夏鈴」
再び夢乃が声を上げた。見ると、缶からこぼれ落ちた中身を漁っている。あたしはタンスの上から空き箱しか投げなかった。ということは、缶は最初からベッドの上にあったのだろう。でも不思議だった。貼られたステッカーは昔のパンクバンドのロゴだったりして、ママの趣味とは合わないはずだったから。誰の物だろう? なんでベッドの上なんかにあったんだろう。興味が湧いた。あたしはカメラの設置を中断し、夢乃に近寄った。夢乃は何枚かの写真を手に持っていた。
「どうしたの?」
「これなんだろ?」
写真をあたしに見せる。古い写真だった。流行とはかけ離れた、悲しくなるほどダサい連中が数名こちらにピースサインをしている。すぐに視線を移し、缶の中を調べる。いつかのライブの半券だとか、時代遅れのフライヤーだとか、古臭いステッカーと一緒にカセットテープが入っていることに気付いた。
灰色のカセットテープで、透明なスリーブには『怒張』と手書きで書かれたシールが貼られていた。なんのこっちゃ? あたしはカセットテープを取り出して、下から覗き込んだりした。当然印象は変わらなかった。だけど分かったことならあった。もしかしてこれ、誰かの宝物入れなんじゃないのって。だって写真とか思い出の品を納めておくものっていったら宝物入れしかないでしょ。あたしの場合はディズニーのお菓子が入ってた缶を使ってるけど、中身は似たようなものだった。自分以外には価値のない奇妙な物を入れていた。思い出が形を変えた呪物みたいな物ばかりだった。
「宝物なんじゃないかな」
「ねえ、これってさ」
言いながら夢乃があたしの肩を叩いた。視界に無理矢理一枚の写真をねじ込んでくる。さっきの写真とは違うが、こちらも古い写真だった。品のない落書きがされたコンクリートの壁を背景に、男女が並んでいる。パンクスみたいなファッションだった。女が男の腕に絡みつくようなポーズを取っていた。
女の方はマーチンのエイトホールにレザーのミニスカート。白いタンクトップの裾は短く、切りっぱなしのような加工がされていた。おヘソが覗いている。髪型は金髪のショート。サイドが大胆に刈り上げられていた。目の周りを真っ黒にさせたメイクが印象的だった。単純に眉毛がないからそう見えるのかもしれない。首元にも手首にも耳にも鼻にも、アクセサリーがたくさんぶら下がっていた。どこにでもいるロック少女という様子だった。さっきの写真よりも古臭く感じなかったが、それはパンクスのファッションがここ五十年は進化していないからで、いにしえの空気感は拭えていない。多分同じ頃に撮影された写真なのだろう。
「これ、ママだ」
思わず吹き出してしまった。あの保守的なママにこんな過去があったとは。もしかしてこれ、パパには秘密の過去なんじゃないの? 今後この写真を使って、ママからどこまで譲歩を引き出すことが出来るかを皮算用すると胸が高鳴った。ということは、この缶はママの宝物入れなのだろうか。若い頃のママがパンクに傾倒していたと考えると、缶に貼られたステッカーにもライブの半券にも納得がいった。
「だよね?」
夢乃も興奮している様子だった。親友の母親が昔こんなだったと気付いたら、そりゃこういう態度になるだろう。「それでさ」と続ける。
「それでさ、こっちは篤郎だよね?」
「はあ?」言いながら写真の中の男を確認する。ダメージジーンズにヴァンズのエラ。黒い無地のTシャツを着ていた。坊主が伸びてきたみたいな無造作な髪型をしている。こちらもあまり古臭くはない。多分、シンプルなスタイルを好むメンズにファッションの進化なんて関係ないからだろう。現在の篤郎に水分を足して張りを取り戻したような姿だった。だけど確かに篤郎だ。ママほど恥ずかしい変化はなかったし、よく見れば今の篤郎とほとんど変わっていないのが悔しくもあった。何年前の写真かは分からないが、やはり風来坊で苦労していない人間には、年齢なりの変化が訪れないのだろう。そう考えることにした。「確かに篤郎だね」
「じゃあさ、これ二人が若い頃の写真だよね。やっぱり知り合いだったんじゃない?」
夢乃に言われて、改めて写真を確認する。ママは笑顔で篤郎の腕を抱いている。篤郎の馬鹿はその後何十年も同じ顔で過ごすことが分かっているような仏頂面だった。周囲の人間を不快にさせるような不機嫌な表情だった。これって知り合いどころの騒ぎじゃないんじゃない? そう思った。付き合っているのかは分からないが、かなり親しい関係だったのは確かだ。
一瞬でカメラの設置なんてどうでも良くなった。図らずも決定的証拠を掴んでしまった。愛華さんごめん。高性能カメラ、必要じゃなくなった。二人は昔からの知り合いだった。この写真ではっきりとした。考えたくはないけど、恋人同士だった可能性だってある。まさかあたしの本当の父親だったみたいな展開はないよね? もしそうだったらあたし、ここで腹を切る所存だよ。ま、それはないか。どっちかって言ったら、あたしはパパに似てるし。
とにかく、二人には何かしらの関係があった。篤郎がバイトの面接に来たのはただの偶然だったのかもしれない。だけど再会を果たす。それで盛り上がって今度は不倫をしようと距離を縮めてるんじゃないのか? もしくは、過去の出来事をネタに篤郎がママを強請っているのかもしれない。若い頃は誰だって一つや二つ秘密にしておきたい恥をかく。その恥を家族にバラされたくなければ特別扱いで雇ってくれってママを脅した。ママは言う事を聞くしかない。それでこの現状が出来上がっているということも考えられた。
どっちかを選ばなくてはいけないのなら、やっぱり篤郎を悪者にしたい。ママは脅されている説を採用したかったが、あたしは真実を見極めないといけない。家族だから。なんてこった。全部あたしの睨んだ通りじゃないか。ちょっと先走り過ぎか? いやあながち間違ってもいないだろう。そりゃママも隠すはずで、篤郎だってすっとぼけるはずだ。気軽に話せるような話じゃない。あたしは二人が映った写真を懐に入れた。これは証拠として没収しておこう。
夢乃の反応が気になった。突然ひどい羞恥心があたしを襲った。自分の家族が篤郎みたいな馬鹿と昔からの知り合いだったなんて。しかも付き合ってたかもしれないなんて。顔が熱い。きっと赤くなっているんだろうな。あたしは赤面に気付かれないよう、俯きながら夢乃を確認した。夢乃はカセットテープを手に持って、あたしがしたように角度を変えながら眺めている。本当に興味を持っているのかは分からない。ただあたしに気を使って、二人の関係には口を出さないという態度を貫いているだけかもしれなかった。その心遣いがありがたかった。
「これなんだろう?」ってまた夢乃が言った。今日はこの子、質問ばっかりだ。でも今度は心底不思議そうに呟いていた。カセットテープをこちらに向けて振る。もしかしたら夢乃はカセットテープがどんなものなのか分かっていないのかもしれない。家族の恥から話題を変えるちょうどいいタイミングだった。あたしは必死になって、カセットテープには音楽が入っているって説明した。レコードとかCDと同じようなもんだって。夢乃は再びカセットを色んな角度から眺めて「へえ」って感心したみたいな声を出した。
「よかったらそれ借りていきなよ。明日学校でさ、放送部にプレイヤー借りようよ。あいつらならきっと持ってるからさ」
「でも、いいの?」
ママの宝物を勝手に持ち出すことについて言っているのか、それとも放送部について言っているのかは分からなかった。それでもあたしは「いいのいいの」って言った。考えることはたくさんあったが、まずは夢乃をこの部屋から追い出さないと。
その時、階下から「ただいまあ」っていうママの声が聞こえた。あたしたちは慌てて寝室を飛び出し、向かい側のあたしの部屋へダイヴした。
ゴシップに命を賭けたパパラッチみたいな人だったけど、本人はジェームズ・ボンドに憧れてるって言ってた。自己紹介では必ず「愛華、宮本愛華」って名乗ってたし。スパイに憧れてるんだって。噂話を収集する癖も、情報戦に勝利する布石らしいよ。ちょっと変わってるよね。
一緒にバイトをしてた現役時代、愛華さんは職場の鼻つまみ者で、あたしも距離を置いて付き合ってた。四六時中他人の噂話をしている人なんてあんまり感じが良くないし。仲良くしようとは思わなかった。むしろ辞めてからの方が友情が深まった感じがある。彼女がスパイグッズの収集家だったから。ママと篤郎のことがなければ、愛華さんのことなんてすっかり忘れてたけど、秘密裏に動く必要に迫られて思い出した。そう言えばあの人、盗聴器とか詳しかったなって。それで連絡したの。「愛華さん、盗聴器とか持ってたら貸して」って。バイト時代のゴールデンコンビ再結成ってわけ。
盗聴器はある程度役に立ったけど、今度は小型カメラが必要になってさ。もう音声の時代じゃないって思った。そんな生ぬるいスパイ行為をしていても埒が明かない。今度は映像でもって、言い訳の効かない証拠をママに突きつけてやる。ってことで「愛華さん、あたしに小型カメラを貸したら良いことあるかも知んないよ」つってやった。愛華さんは多分友達が少ないんだと思う。そりゃそうだよね。ロン・ガレラみたいなパパラッチが身近にいたんじゃ皆警戒する。だから、あたしが彼女自慢のスパイグッズに興味を持ったことが嬉しかったんじゃないかな。ようやく同好の士が見つかった、みたいな気迫を感じるもの。
二つ返事で超高性能の小型カメラを貸してくれた。こんなに小さくなくてもいいんじゃないかってくらいに小さいカメラだった。多分頭痛薬一錠よりも小さい。それ二つ。愛華さんが言うにはそれでも高性能らしい。ママと篤郎の皺の奥まで録画したいわけじゃなかったから、性能は並って感じでも良かったんだけど、愛華さんが興奮しちゃってさ。カメラを借りるために、ホテル近くのカフェまで行ったんだけどこっちが恥ずかしくなるくらい早口で性能を説明された。
話している内容が盗撮用の小型カメラっていう非常にセンシティブなものなのに、あの人全然気にしないんだもん。あたしはまだ良いよ。バイトはクビになったし、もうあの高級ホテルには縁もゆかりも無いんだから。でもさ、愛華さんはまだ清掃係として働いてるわけじゃん。職場の近くでそんな話して、普通は気不味いと思うけど。でもまあ、スパイオタクの戯言にも腰を据えて付き合ったよ。無料で貸してくれるし、話くらいは黙って聞くのが筋かなって思ったから。愛華さんの休憩時間が終わったことで半ば強制的に与太話が打ち切られた瞬間、あたしは走って店を出たね。会計もせず。たとえ二人分のコーヒー代とはいえ、あたしに金の余裕なんてない。心の中で「ごめん」って呟きながら愛華さんのスパイ講座から脱出した。
借りたカメラを、今度はリビングと両親の寝室に仕掛けようと思った。もしかしたらクリティカルに考えたくもない盗撮ポルノを制作してしまう可能性はあった。万が一ママと篤郎が出演していたら最悪だけど、それはあんまり気にしてなかった。可能性は低いはずだ。いくらのぼせ上がっていても、パパが頻繁に出入りする母屋で性欲を抑えきれないほど二人共若くはない。むしろ、両親の情事をまざまざと見せつけられる可能性の方が高かった。あの二人が未だに愛し合っているかは分からないけど。自分ちの寝室ならそういうことだってあるだろう。あたしだって本当なら、こんなことはしたくない。でもさ、ママの態度に怪しさが払拭できないから。あたしに極端な行動を取らせたのはママのせい。もしバレたらそうやって自分を正当化するんだ。
カフェからの帰り道はるんるんだった。色んな問題を抱えているけど、まずはこれで篤郎をクビに出来るって思った。いくらママが庇おうとも、女房といかがわしいことをしていたならばパパだって黙っていないだろう。そのことを考えると自然と足取りが軽くなった。ママの弱みを握れるかもしれないし。こうなりゃ、ママと篤郎に関係があってほしいのか、なければいいと思っているのか自分でも分からなくなっていた。ただ最新のガジェットの威力を試してみたかっただけかもしれない。
倉庫には夢乃がいた。一人で丸椅子に座って、あたしの作品を眺めていた。意味あり気に顎の下に指を置いて、まるでレオ・キャステリみたいだった。あたしが背中を叩くと、心臓を掴まれたみたいな顔して「なんなの?」って飛び上がってた。いつものことだ。
「おつかれ、一人?」
「うん」夢乃は胸に手をおいて、鼓動を感じることで落ち着こうと努めていた。「篤郎はサボってたから外回りに行かせた。今日はそのまま帰っていいって言っといたから直帰するはず。おじさんはまだ帰ってきてないね。おばさんは分からないけど、多分買い物かなんかじゃないかな。店の方にもいなかったよ」
「へえ、チャンスじゃん」
「チャンスってなに? それよりさ、夏鈴さ、勝手にプレゼン終わらせちゃったんだって? 私資料準備してたんだよ。まあ良いけどさ、それで結果はどうだったの? 篤郎は物別れに終わったって言ってたけど」
「ああ、あれはね、まあジャブみたいなものだよね。これから渾身のストレートを放つからさ、距離感図ってたっていうか。だから夢乃の資料は無駄にならないよ。これから使う。大丈夫」
言いながらあたしは母屋の方へと足を向けた。夢乃との会議も重要だったけど、誰もいないこのチャンスを逃したくなかった。背後に夢乃の足音が聞こえた。
「ねえ、どこ行くの?」
「必要なことをするの。まずは篤郎をこの家から追い出さなきゃ。それと、常にあたし達の反対派に回るママの弱みを握るの」
店舗を抜けて、靴を脱いでから廊下に上がる。突き当りの階段をのぼった。
「どういうこと? それに篤郎は夏鈴が思うほど悪い人間じゃないかもよ」
その言葉に反応して振り返ると、眼下に迫る夢乃のつむじが見えた。
「懐柔されたのか?」
「そういうんじゃないけどさ」夢乃が上目遣いで答える。「でもさ、おばさんと篤郎のこと気にするより真っ直ぐに仕事のことを考えた方が建設的な気がするんだよね。ほら、私達ピンチなわけだし、あんまりそういうことに力を入れすぎない方が良いような気がして」
終盤にかけて段々と声が小さくなっていってた。あたしは嬉しさ半分、寂しさ半分っていう複雑な心境を抱いた。だって、あたしの言う事にはなんでも賛成っていうのが夢乃のスタイルのはずだったから。もちろんなんでも賛成の夢乃に不満なんてなかった。それが彼女の長所だし。でもさ、これでいいのかな? って考えたことならある。それで夢乃は楽しいのかなって。そんな夢乃が、あたしに意見してくるなんて。感慨深かった。反抗期の娘を見ているようだった。
だけど気にはなった。なんで突然、楯突いたんだ? なにかあったのか? 篤郎のことを庇ったりして。どういうつもりだろう。でもちょっと潔癖症気味の夢乃のことだ。ママと篤郎の本当の関係を炙り出すことができれば、きっと目を覚ますに違いない。「不潔」とか言って篤郎追放賛成派に回ってくれるはずだ。
「結論を出すのはまだ早いよ。取り敢えずあたしを信じて今まで通りついてきて」
しっかりと夢乃の目を見て言った。彼女が頷く前にこちらから首を縦に振る。つられて夢乃も頷いた。階段の途中で、中途半端なまま止めていた足を再び動かし二階にあがった。右側の扉を開くと、夢乃が「え?」と声を上げた。その扉の先は、両親の寝室だと分かっていたからだ。きっと左側にある扉から、あたしの部屋に入ると思い込んでいたのだろう。ふふふ。今日は違うんですよ。
寝室の中央にはベッドが置かれている。その上に、二人分のパジャマが申し訳程度に畳まれていた。ベッドの周りは全部ママのスペースだ。押し入れには入らなかった衣服を入れるタンスと化粧台が空間を圧迫している。つまり寝室はほとんどママのための部屋だった。
パパの私物はここにはない。昔は倉庫に置いてあったけど、あたし達の仕事場になってからはもうそこにもない。パパが仕事で使うバンに押し込んだから。パパはいつでも蒸発出来る体制で仕事に励んでるってこと。本当の意味でノマドって言えるかもしれない。元々パパに私物なんてほとんどないんだ。作業着と仕事道具だけ。仕事に命をかける昭和の男だから。
あたしはまず部屋を見回した。全体を俯瞰できる場所にカメラを仕掛ける必要があったから。ベッドに乗ってきょろきょろとしてる姿を、夢乃は不思議そうに眺めていた。
「ねえ、なにやってるの?」
「カメラを仕掛けようと思うんだよね。ベストポジションを探してるの」
夢乃はもう何も言わなかった。あたしがタンスの上に当たりをつけ、そこに置いてあった埃だらけのマックブックの空き箱をベッドに投げると、その放物線を目で追っていた。
「ちょっとそこ立ってくれる?」
カメラの角度を調整しつつ、スマホで映像を確認する。そう。この超小型カメラにはスマホ連動機能があるのだ。愛華さんに言わせれば、最近の業界では必須のオプションなんだとさ。あたしの言葉に反応して、戸惑いながらも立ち位置を調整する夢乃の姿がスマホに映った。
すると、夢乃がベッドを指さして「ねえ」と言った。スマホから目を離し、ベッドを見る。マックブックの空き箱に、スーサイドボムを食らった缶が蓋を開けて転がっていた。元はお菓子が入った缶だったのだろう。今では所々凹んでいたり、錆が浮いていたり、上からステッカーを貼られていたりと原型をとどめていない。あたしはそんなことよりも、画角が気になっていた。ベッド近くに移動する夢乃を無視してカメラの調整を進める。
「ねえ、夏鈴」
再び夢乃が声を上げた。見ると、缶からこぼれ落ちた中身を漁っている。あたしはタンスの上から空き箱しか投げなかった。ということは、缶は最初からベッドの上にあったのだろう。でも不思議だった。貼られたステッカーは昔のパンクバンドのロゴだったりして、ママの趣味とは合わないはずだったから。誰の物だろう? なんでベッドの上なんかにあったんだろう。興味が湧いた。あたしはカメラの設置を中断し、夢乃に近寄った。夢乃は何枚かの写真を手に持っていた。
「どうしたの?」
「これなんだろ?」
写真をあたしに見せる。古い写真だった。流行とはかけ離れた、悲しくなるほどダサい連中が数名こちらにピースサインをしている。すぐに視線を移し、缶の中を調べる。いつかのライブの半券だとか、時代遅れのフライヤーだとか、古臭いステッカーと一緒にカセットテープが入っていることに気付いた。
灰色のカセットテープで、透明なスリーブには『怒張』と手書きで書かれたシールが貼られていた。なんのこっちゃ? あたしはカセットテープを取り出して、下から覗き込んだりした。当然印象は変わらなかった。だけど分かったことならあった。もしかしてこれ、誰かの宝物入れなんじゃないのって。だって写真とか思い出の品を納めておくものっていったら宝物入れしかないでしょ。あたしの場合はディズニーのお菓子が入ってた缶を使ってるけど、中身は似たようなものだった。自分以外には価値のない奇妙な物を入れていた。思い出が形を変えた呪物みたいな物ばかりだった。
「宝物なんじゃないかな」
「ねえ、これってさ」
言いながら夢乃があたしの肩を叩いた。視界に無理矢理一枚の写真をねじ込んでくる。さっきの写真とは違うが、こちらも古い写真だった。品のない落書きがされたコンクリートの壁を背景に、男女が並んでいる。パンクスみたいなファッションだった。女が男の腕に絡みつくようなポーズを取っていた。
女の方はマーチンのエイトホールにレザーのミニスカート。白いタンクトップの裾は短く、切りっぱなしのような加工がされていた。おヘソが覗いている。髪型は金髪のショート。サイドが大胆に刈り上げられていた。目の周りを真っ黒にさせたメイクが印象的だった。単純に眉毛がないからそう見えるのかもしれない。首元にも手首にも耳にも鼻にも、アクセサリーがたくさんぶら下がっていた。どこにでもいるロック少女という様子だった。さっきの写真よりも古臭く感じなかったが、それはパンクスのファッションがここ五十年は進化していないからで、いにしえの空気感は拭えていない。多分同じ頃に撮影された写真なのだろう。
「これ、ママだ」
思わず吹き出してしまった。あの保守的なママにこんな過去があったとは。もしかしてこれ、パパには秘密の過去なんじゃないの? 今後この写真を使って、ママからどこまで譲歩を引き出すことが出来るかを皮算用すると胸が高鳴った。ということは、この缶はママの宝物入れなのだろうか。若い頃のママがパンクに傾倒していたと考えると、缶に貼られたステッカーにもライブの半券にも納得がいった。
「だよね?」
夢乃も興奮している様子だった。親友の母親が昔こんなだったと気付いたら、そりゃこういう態度になるだろう。「それでさ」と続ける。
「それでさ、こっちは篤郎だよね?」
「はあ?」言いながら写真の中の男を確認する。ダメージジーンズにヴァンズのエラ。黒い無地のTシャツを着ていた。坊主が伸びてきたみたいな無造作な髪型をしている。こちらもあまり古臭くはない。多分、シンプルなスタイルを好むメンズにファッションの進化なんて関係ないからだろう。現在の篤郎に水分を足して張りを取り戻したような姿だった。だけど確かに篤郎だ。ママほど恥ずかしい変化はなかったし、よく見れば今の篤郎とほとんど変わっていないのが悔しくもあった。何年前の写真かは分からないが、やはり風来坊で苦労していない人間には、年齢なりの変化が訪れないのだろう。そう考えることにした。「確かに篤郎だね」
「じゃあさ、これ二人が若い頃の写真だよね。やっぱり知り合いだったんじゃない?」
夢乃に言われて、改めて写真を確認する。ママは笑顔で篤郎の腕を抱いている。篤郎の馬鹿はその後何十年も同じ顔で過ごすことが分かっているような仏頂面だった。周囲の人間を不快にさせるような不機嫌な表情だった。これって知り合いどころの騒ぎじゃないんじゃない? そう思った。付き合っているのかは分からないが、かなり親しい関係だったのは確かだ。
一瞬でカメラの設置なんてどうでも良くなった。図らずも決定的証拠を掴んでしまった。愛華さんごめん。高性能カメラ、必要じゃなくなった。二人は昔からの知り合いだった。この写真ではっきりとした。考えたくはないけど、恋人同士だった可能性だってある。まさかあたしの本当の父親だったみたいな展開はないよね? もしそうだったらあたし、ここで腹を切る所存だよ。ま、それはないか。どっちかって言ったら、あたしはパパに似てるし。
とにかく、二人には何かしらの関係があった。篤郎がバイトの面接に来たのはただの偶然だったのかもしれない。だけど再会を果たす。それで盛り上がって今度は不倫をしようと距離を縮めてるんじゃないのか? もしくは、過去の出来事をネタに篤郎がママを強請っているのかもしれない。若い頃は誰だって一つや二つ秘密にしておきたい恥をかく。その恥を家族にバラされたくなければ特別扱いで雇ってくれってママを脅した。ママは言う事を聞くしかない。それでこの現状が出来上がっているということも考えられた。
どっちかを選ばなくてはいけないのなら、やっぱり篤郎を悪者にしたい。ママは脅されている説を採用したかったが、あたしは真実を見極めないといけない。家族だから。なんてこった。全部あたしの睨んだ通りじゃないか。ちょっと先走り過ぎか? いやあながち間違ってもいないだろう。そりゃママも隠すはずで、篤郎だってすっとぼけるはずだ。気軽に話せるような話じゃない。あたしは二人が映った写真を懐に入れた。これは証拠として没収しておこう。
夢乃の反応が気になった。突然ひどい羞恥心があたしを襲った。自分の家族が篤郎みたいな馬鹿と昔からの知り合いだったなんて。しかも付き合ってたかもしれないなんて。顔が熱い。きっと赤くなっているんだろうな。あたしは赤面に気付かれないよう、俯きながら夢乃を確認した。夢乃はカセットテープを手に持って、あたしがしたように角度を変えながら眺めている。本当に興味を持っているのかは分からない。ただあたしに気を使って、二人の関係には口を出さないという態度を貫いているだけかもしれなかった。その心遣いがありがたかった。
「これなんだろう?」ってまた夢乃が言った。今日はこの子、質問ばっかりだ。でも今度は心底不思議そうに呟いていた。カセットテープをこちらに向けて振る。もしかしたら夢乃はカセットテープがどんなものなのか分かっていないのかもしれない。家族の恥から話題を変えるちょうどいいタイミングだった。あたしは必死になって、カセットテープには音楽が入っているって説明した。レコードとかCDと同じようなもんだって。夢乃は再びカセットを色んな角度から眺めて「へえ」って感心したみたいな声を出した。
「よかったらそれ借りていきなよ。明日学校でさ、放送部にプレイヤー借りようよ。あいつらならきっと持ってるからさ」
「でも、いいの?」
ママの宝物を勝手に持ち出すことについて言っているのか、それとも放送部について言っているのかは分からなかった。それでもあたしは「いいのいいの」って言った。考えることはたくさんあったが、まずは夢乃をこの部屋から追い出さないと。
その時、階下から「ただいまあ」っていうママの声が聞こえた。あたしたちは慌てて寝室を飛び出し、向かい側のあたしの部屋へダイヴした。
0
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?


Hand in Hand - 二人で進むフィギュアスケート青春小説
宮 都
青春
幼なじみへの気持ちの変化を自覚できずにいた中2の夏。ライバルとの出会いが、少年を未知のスポーツへと向わせた。
美少女と手に手をとって進むその競技の名は、アイスダンス!!
【2022/6/11完結】
その日僕たちの教室は、朝から転校生が来るという噂に落ち着きをなくしていた。帰国子女らしいという情報も入り、誰もがますます転校生への期待を募らせていた。
そんな中でただ一人、果歩(かほ)だけは違っていた。
「制覇、今日は五時からだから。来てね」
隣の席に座る彼女は大きな瞳を輝かせて、にっこりこちらを覗きこんだ。
担任が一人の生徒とともに教室に入ってきた。みんなの目が一斉にそちらに向かった。それでも果歩だけはずっと僕の方を見ていた。
◇
こんな二人の居場所に現れたアメリカ帰りの転校生。少年はアイスダンスをするという彼に強い焦りを感じ、彼と同じ道に飛び込んでいく……
――小説家になろう、カクヨム(別タイトル)にも掲載――

学園のアイドルに、俺の部屋のギャル地縛霊がちょっかいを出すから話がややこしくなる。
たかなしポン太
青春
【第1回ノベルピアWEB小説コンテスト中間選考通過作品】
『み、見えるの?』
「見えるかと言われると……ギリ見えない……」
『ふぇっ? ちょっ、ちょっと! どこ見てんのよ!』
◆◆◆
仏教系学園の高校に通う霊能者、尚也。
劣悪な環境での寮生活を1年間終えたあと、2年生から念願のアパート暮らしを始めることになった。
ところが入居予定のアパートの部屋に行ってみると……そこにはセーラー服を着たギャル地縛霊、りんが住み着いていた。
後悔の念が強すぎて、この世に魂が残ってしまったりん。
尚也はそんなりんを無事に成仏させるため、りんと共同生活をすることを決意する。
また新学期の学校では、尚也は学園のアイドルこと花宮琴葉と同じクラスで席も近くなった。
尚也は1年生の時、たまたま琴葉が困っていた時に助けてあげたことがあるのだが……
霊能者の尚也、ギャル地縛霊のりん、学園のアイドル琴葉。
3人とその仲間たちが繰り広げる、ちょっと不思議な日常。
愉快で甘くて、ちょっと切ない、ライトファンタジーなラブコメディー!
※本作品はフィクションであり、実在の人物や団体、製品とは一切関係ありません。
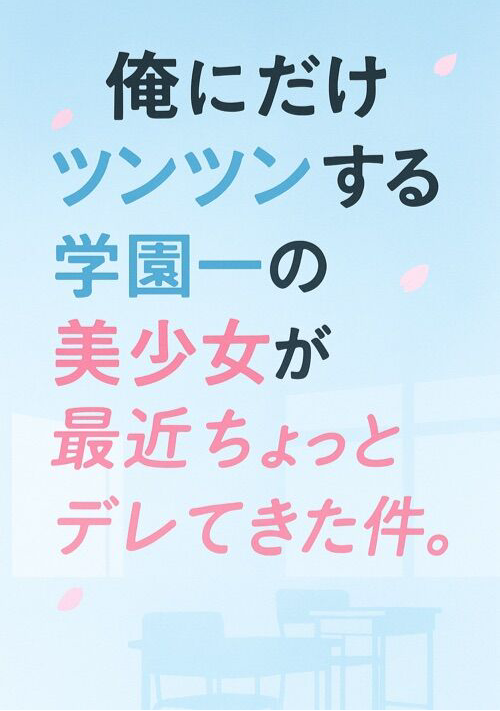
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。


『俺アレルギー』の抗体は、俺のことが好きな人にしか現れない?学園のアイドルから、幼馴染までノーマスク。その意味を俺は知らない
七星点灯
青春
雨宮優(あまみや ゆう)は、世界でたった一つしかない奇病、『俺アレルギー』の根源となってしまった。
彼の周りにいる人間は、花粉症の様な症状に見舞われ、マスク無しではまともに会話できない。
しかし、マスクをつけずに彼とラクラク会話ができる女の子達がいる。幼馴染、クラスメイトのギャル、先輩などなど……。
彼女達はそう、彼のことが好きすぎて、身体が勝手に『俺アレルギー』の抗体を作ってしまったのだ!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















