あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

王命って何ですか? 虐げられ才女は理不尽な我慢をやめることにした
まるまる⭐️
恋愛
【第18回恋愛小説大賞において優秀賞を頂戴致しました。応援頂いた読者の皆様に心よりの感謝を申し上げます。本当にありがとうございました】
その日、貴族裁判所前には多くの貴族達が傍聴券を求め、所狭しと行列を作っていた。
貴族達にとって注目すべき裁判が開かれるからだ。
現国王の妹王女の嫁ぎ先である建国以来の名門侯爵家が、新興貴族である伯爵家から訴えを起こされたこの裁判。
人々の関心を集めないはずがない。
裁判の冒頭、証言台に立った伯爵家長女は涙ながらに訴えた。
「私には婚約者がいました…。
彼を愛していました。でも、私とその方の婚約は破棄され、私は意に沿わぬ男性の元へと嫁ぎ、侯爵夫人となったのです。
そう…。誰も覆す事の出来ない王命と言う理不尽な制度によって…。
ですが、理不尽な制度には理不尽な扱いが待っていました…」
裁判開始早々、王命を理不尽だと公衆の面前で公言した彼女。裁判での証言でなければ不敬罪に問われても可笑しくはない発言だ。
だが、彼女はそんな事は全て承知の上であえてこの言葉を発した。
彼女はこれより少し前、嫁ぎ先の侯爵家から彼女の有責で離縁されている。原因は彼女の不貞行為だ。彼女はそれを否定し、この裁判に於いて自身の無実を証明しようとしているのだ。
次々に積み重ねられていく証言に次第に追い込まれていく侯爵家。明らかになっていく真実を傍聴席の貴族達は息を飲んで見守る。
裁判の最後、彼女は傍聴席に向かって訴えかけた。
「王命って何ですか?」と。
✳︎不定期更新、設定ゆるゆるです。

「無加護」で孤児な私は追い出されたのでのんびりスローライフ生活!…のはずが精霊王に甘く溺愛されてます!?
白井
恋愛
誰もが精霊の加護を受ける国で、リリアは何の精霊の加護も持たない『無加護』として生まれる。
「魂の罪人め、呪われた悪魔め!」
精霊に嫌われ、人に石を投げられ泥まみれ孤児院ではこき使われてきた。
それでも生きるしかないリリアは決心する。
誰にも迷惑をかけないように、森でスローライフをしよう!
それなのに―……
「麗しき私の乙女よ」
すっごい美形…。えっ精霊王!?
どうして無加護の私が精霊王に溺愛されてるの!?
森で出会った精霊王に愛され、リリアの運命は変わっていく。

男子高校生だった俺は異世界で幼児になり 訳あり筋肉ムキムキ集団に保護されました。
カヨワイさつき
ファンタジー
高校3年生の神野千明(かみの ちあき)。
今年のメインイベントは受験、
あとはたのしみにしている北海道への修学旅行。
だがそんな彼は飛行機が苦手だった。
電車バスはもちろん、ひどい乗り物酔いをするのだった。今回も飛行機で乗り物酔いをおこしトイレにこもっていたら、いつのまにか気を失った?そして、ちがう場所にいた?!
あれ?身の危険?!でも、夢の中だよな?
急死に一生?と思ったら、筋肉ムキムキのワイルドなイケメンに拾われたチアキ。
さらに、何かがおかしいと思ったら3歳児になっていた?!
変なレアスキルや神具、
八百万(やおよろず)の神の加護。
レアチート盛りだくさん?!
半ばあたりシリアス
後半ざまぁ。
訳あり幼児と訳あり集団たちとの物語。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
北海道、アイヌ語、かっこ良さげな名前
お腹がすいた時に食べたい食べ物など
思いついた名前とかをもじり、
なんとか、名前決めてます。
***
お名前使用してもいいよ💕っていう
心優しい方、教えて下さい🥺
悪役には使わないようにします、たぶん。
ちょっとオネェだったり、
アレ…だったりする程度です😁
すでに、使用オッケーしてくださった心優しい
皆様ありがとうございます😘
読んでくださる方や応援してくださる全てに
めっちゃ感謝を込めて💕
ありがとうございます💞
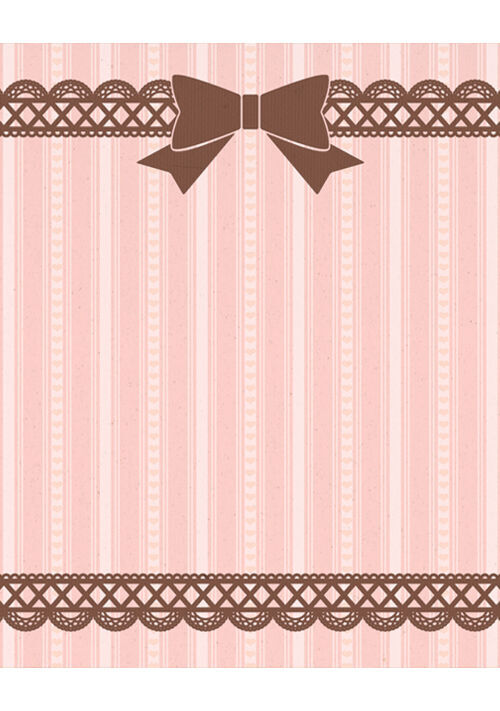
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

中身は80歳のおばあちゃんですが、異世界でイケオジ伯爵に溺愛されています
浅水シマ
ファンタジー
【完結しました】
ーー人生まさかの二週目。しかもお相手は年下イケオジ伯爵!?
激動の時代を生き、八十歳でその生涯を終えた早川百合子。
目を覚ますと、そこは異世界。しかも、彼女は公爵家令嬢“エマ”として新たな人生を歩むことに。
もう恋愛なんて……と思っていた矢先、彼女の前に現れたのは、渋くて穏やかなイケオジ伯爵・セイルだった。
セイルはエマに心から優しく、どこまでも真摯。
戸惑いながらも、エマは少しずつ彼に惹かれていく。
けれど、中身は人生80年分の知識と経験を持つ元おばあちゃん。
「乙女のときめき」にはとっくに卒業したはずなのに――どうしてこの人といると、胸がこんなに苦しいの?
これは、中身おばあちゃん×イケオジ伯爵の、
ちょっと不思議で切ない、恋と家族の物語。
※小説家になろうにも掲載中です。

宿敵の家の当主を妻に貰いました~妻は可憐で儚くて優しくて賢くて可愛くて最高です~
紗沙
恋愛
剣の名家にして、国の南側を支配する大貴族フォルス家。
そこの三男として生まれたノヴァは一族のみが扱える秘技が全く使えない、出来損ないというレッテルを貼られ、辛い子供時代を過ごした。
大人になったノヴァは小さな領地を与えられるものの、仕事も家族からの期待も、周りからの期待も0に等しい。
しかし、そんなノヴァに舞い込んだ一件の縁談話。相手は国の北側を支配する大貴族。
フォルス家とは長年の確執があり、今は栄華を極めているアークゲート家だった。
しかも縁談の相手は、まさかのアークゲート家当主・シアで・・・。
「あのときからずっと……お慕いしています」
かくして、何も持たないフォルス家の三男坊は性格良し、容姿良し、というか全てが良しの妻を迎え入れることになる。
ノヴァの運命を変える、全てを与えてこようとする妻を。
「人はアークゲート家の当主を恐ろしいとか、血も涙もないとか、冷酷とか散々に言うけど、
シアは可愛いし、優しいし、賢いし、完璧だよ」
あまり深く考えないノヴァと、彼にしか自分の素を見せないシア、二人の結婚生活が始まる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















