8 / 35
第二章 緑の上手な育て方
第八話 外堀はすでに埋まっている
しおりを挟む目の前の子供は、見れば見るほどドール・クリスティーナに、そしてスミレにそっくりだった。
とはいえ、いくらスミレが童顔とはいえ、さすがにこんな小さな子供ではない、とソフィリアもようやく冷静になる。
「スミレ……では、ないですよね……?」
まじまじと見つめつつそう問い直すソフィリアに、そのスミレに酷似した子供は、やはりスミレそっくりの仕草で唇を尖らせて答えた。
「違うよ、ソフィ。シオン君だよ」
とたん、ソフィリアは再び、まあ! と叫んで頬を両手で押さえた。
目の前の愛らしい膨れっ面の主は、スミレの七歳になる一人息子――シオン・ルト・レイスウェイクだったのだ。
何ということはない。
黒い髪はカツラで、彼の父親譲りの白銀の髪はその下に隠されているだけだった。
「シオンちゃん、お手伝いありがとうございます」
「どういたしまして、ルリ」
どういうわけか女の子の格好をしたシオンは、クッキーの載った皿を持っていた。
ルドヴィークにポットのトレイを預けて手が空いていたルリが、その皿を受け取る。
ルリのお礼に誇らしげな顔をするシオンの隣からは、もう一人の子供――こちらは正真正銘の女の子――が、長くまっすぐな金髪をさらりと流し、青い瞳をソフィリアとルドヴィークに向けて微笑んだ。
「陛下、ソフィリア様、ごきげんよう」
先ほど廊下で出会した令嬢達と同じ台詞であるが、こちらはソフィリアとルドヴィークに対する慕わしさに溢れていた。
金髪の女の子は、ルドヴィークの次姉ミリアニスと、騎士団長ジョルトの間に生まれたオルセオロ公爵家の一人娘、アリアーネ・フィア・オルセオロ。
シオンより一つ年上のアリアーネは、両親と同じくおっとりとした性格の少女である。
そんな可愛らしい子供達を前にして、ソフィリアの頬はもう為す術もなくゆるゆるになる。
対してルドヴィークは、口元を引き攣らせつつ甥っ子に尋ねた。
「シオン……その格好は、いったいどうしたんだ……」
「聞いてよ、ルド兄! おばあ様ったらひどいんだよっ!!」
不満顔のシオンが言うには、彼は今日、祖母である母后陛下にお茶に誘われたらしい。
お茶会には大好きな従姉のアリアーネも参加すると聞いていたため、皺一つないシャツを着て、襟もピシッと整えてきた。
父親譲りの白銀の髪には念入りに櫛を通し、革靴だって自分でピカピカに磨いたのだ。
それなのに――母后の前に出て行儀良く挨拶を述べたとたん、生温い笑みを浮かべた侍女達の手が一斉にシオンに伸びた。侍女頭までもそれを止めようとはしない。
そうして、あれよあれよという間に、これこの通り、女児用のドレスに着替えさせられてしまったのだという。
母后はシオンの膨らんだ頬を面白そうに眺めながら、ころころと笑った。
「だって、今日は女ばかりのお茶会なんですもの。女の子にならなければ、シオンは参加できませんわ」
「そんなの聞いてなかったし! それに、どうせおばあ様は最初から僕で遊ぶつもりだったんでしょ!?」
「あらあら、うふふふふふ」
「ちょっと! 嘘でも否定してよ!」
そんな二人のやりとりに、ソフィリアはルドヴィークと顔を見合わせ苦笑する。
すると、シオンの不満の矛先が、突然向きを変えた。
「おばあ様の理屈でいくなら、ルド兄だって女装しなきゃだめでしょ! ルド兄もドレス着てよっ!!」
「えっ!? いや、私は……」
小さな拳を振り上げて訴えるシオンに、ルドヴィークは困った顔をする。
「ルドヴィークは皇帝だからいいんですよ」
「そんなのずっるい!!」
母后が身も蓋もないことを告げると、シオンはますます眦を吊り上げた。
地団駄を踏むその姿は、まだまだ少女っぽいところのある彼の母親にそっくりだ。
「陛下も、きっとドレスがお似合いになると思いますのに……。そうだわ! お母様のを一着借りて参りましょうか!?」
「いや、アリアーネ……せっかくだが、遠慮しておくな」
冗談のようなことを本気で言うアリアーネも、天然なところがある彼女の母親によく似ている。
その母親達のことをよく知っているソフィリアとルドヴィークは、また顔を見合わせ苦笑を深めるのであった。
そんな一同を微笑ましく眺めていたルリが、ポットのお茶をカップに注ぐ。
湯気とともに辺りに広がる芳しい香りが、母后陛下主催のお茶会の始まりを告げた。
母后の私室のリビングには、ゆったりとしたソファが四つ、テーブルを囲んで置かれている。
そのうちの一つに、ルドヴィークと母后が並んで座った。
「ソフィ、こっちこっち。一緒に座ろう?」
「ソフィリア様、こちらにいらして」
一方ソフィリアは、シオンとアリアーネに両手を引かれてその向かいに座る。
人形のように愛らしい少女達――一人は少年であるが――に挟まれて、ソフィリアの頬はさっきからずっと緩みっぱなしだ。
全員に紅茶を配り終え、ルリも空いたソファに腰を下ろす。
それを見届けると、シオンが顔の前で両手を合わせて言った。
「いただきます」
それは、彼の母親であるスミレの故郷、異世界ニホンなる国における食事の作法なのだという。
生き物はみな、数々の命を糧にして生きている。命をいただくことへの感謝を表すため、さらには、食事を作ってくれる人への感謝の気持ちも込めた、〝いただきます〟なのだとか。
スミレがそう、ソフィリアの教えてくれたことがあった。
グラディアトリアでは馴染みのない作法を、グラディアトリアで生まれ育ったシオンが自然とやってのけるのは、スミレが彼の前でもずっとそれを実践しているからだろう。
普段はあまり母親らしい姿を見せないが、彼女もしっかりと我が子を育てているのだと分かる。
ソフィリアはそんな親友を頼もしく感じつつ、シオンを真似て両手を合わせ、いただきます、と呟いた。
大人達の手は、まず紅茶のカップを持つ。
対する子供達の手は、テーブルの上に置かれた皿からさっそくクッキーを掴み上げた。
クッキーは、プレーン、ショコラ、チーズとナッツ、それから紅茶の葉入り、最後にレモンのピール入り、と全部で五種類。
シオンはショコラ入り、アリアーネは紅茶のクッキーをそれぞれ口に含み、ソフィリアを挟んでにっこりと微笑み合う。
そんな子供達に促されるように、大人達の手もクッキーの皿へと伸びた。
ルドヴィークが好きなのは、柑橘系のピールが練り込まれたお菓子。一緒に過ごす時間の長いソフィリアがそれを思い出しながらふと見ると、案の定彼の手にはレモンピール入りのクッキーがあった。
ソフィリアはそんな分かりやすい主君にくすりとしてから、自分も同じものを手に取る。
さくっとした軽い歯触り、噛んだ瞬間に口の中に広がるバターの香り、鼻に抜ける爽やかなレモンの風味。
向かいの席では、それを一口で齧ったルドヴィークも眦を緩めている。
その素直な表情を愛おしく思いつつ、ソフィリアはクッキーを焼いた人物に声をかけた。
「とってもおいしいわ、ルリ」
「ふふ、ありがとう」
ルリははにかみつつ、紅茶のカップに口を付ける。
一方、子供らしく豪快にクッキーに齧り付きながら、そう言えば、と口を開いたのはシオンだった。
「ルド兄、カーティス伯父さんを生け贄にしてパトラーシュから逃げてきたって、ほんと?」
「生け贄って……」
幼子の遠慮のない言葉に、ルドヴィークは顔を引き攣らせる。
誰がそんなことを……と言いかけて、隣でにこにこしている母に気づき、彼は口を噤んだ。
そんなルドヴィークに、シオンは紅茶で口を潤してから続ける。
「でも、大丈夫なの? 伯父さんち、もうすぐ赤ちゃん生まれちゃうよ?」
「うん? ああ、そうか……そろそろか」
シオンの母方の伯父――スミレの義理の兄であるカーティスは、ルドヴィークにとっては従兄にあたる。
カーティスの父親であるヒルディベル・フィア・シュタイアー公爵は前宰相であり、母后の実の兄だった。
父親に似ず堅物と有名で、浮いた噂がなかなかなかったカーティスも、昨年ようやく身を固めた。
相手は、スミレがこのグラディアトリアにやってきた当初から贔屓にしていたお針子。手芸が趣味のシュタイアー公爵夫人――カーティスの実母とも、もともと親交が深かった女性である。
そしてシオンの言う通り、彼女は臨月を迎えており、赤子はもういつ生まれてもおかしくない状態だった。
さしあたっての問題が解決すれば、カーティスとソフィリアの弟ユリウスも馬車を駆ってグラディアトリアに戻ってくるはずなのだが、午後になってもその気配がない。
もしもパトラーシュでの滞在が長引いて、初めての我が子の誕生を遠く離れた地で知るようなことになっては、さすがにカーティスが気の毒だ。
彼に問題を押し付けてきてしまったことをルドヴィークが後悔し始めた、その時である。
コンコン、と母后の私室の扉をノックする者があった。
「――ご歓談中失礼いたします」
やってきたのは、つい先ほどまで宰相執務室でルドヴィークと会談していたクロヴィスだった。
もちろん母后は彼を歓迎し、ルリはソファから立ち上がって新しいカップを用意する。
そんな妻の姿に眼鏡の下で眦を緩めたクロヴィスだったが、すぐに視線をルドヴィークに移して口を開いた。
「カーティスとユリウスが乗った馬車が、本日正午前、無事国境を越えたそうですよ」
噂をすれば、である。
クロヴィスの話では、たった今、パトラーシュとの国境にある屯所から放たれた伝書鳩が到着したのだという。
皇帝執務室が空だったため、その伝令が宰相執務室に行ったそうだ。
昨日国境を越える際、屯所の者に二人のことを頼んでおいて正解だった、とルドヴィークが破顔する。
「やれやれ、これで、カーティスに恨まれずに済みそうだ」
胸を撫で下ろす彼の向かいでは、シオンとアリアーネが、よかったね、と微笑み合う。
二人に挟まれたソフィリアも、ほっと安堵のため息をついた。
「カーティスには、数日休暇を取らせよう。できることなら、出産が済むまで奥方の側にいさせてやりたいな」
「ああ、もうそんな時期でしたか……」
ルドヴィークの言葉に、クロヴィスもカーティスの妻が臨月であることを思い出したようだ。
そんなクロヴィスも、ルリと結婚してそろそろ六年になるが、二人の間にはまだ子供がいない。
そのため一時、余計な勘ぐりをする連中――子供ができないのはルリに原因があると決めつけ、リュネブルク公爵家の血を絶やさぬために、ぜひ自分の娘に寵愛を、と擦り寄ってくる愚か者も涌いた。
もちろん、そんな輩はクロヴィスの怒りを買い、二度と城の門をくぐれないようになったのだが。
幸い、クロヴィスもルリも、子供がいないことを殊更気にしている様子はない。それは、ロイズという少年の存在のおかげでもあった。
リュネブルク公爵家の養い子である彼を、二人は我が子のように可愛がっているのだ。
頭脳明晰なロイズは、十二歳を迎えた今年、リュネブルク公爵家を出て城の宿舎で生活を始めた。勉学に励む傍らクロヴィスに師事し、将来は王城での仕官を目指している。
ルリも、そんな彼の母親代わりを献身的に務めていた。
「カーティス様の奥様、心細いままのご出産にならず、ようございましたね」
「ええ、そうですね」
紅茶をカップに注ぎながら、ルリがにこりと微笑む。
クロヴィスは優しい声でそれに答えた。
そんな仲睦まじい次兄夫婦を眺めていたルドヴィークが、今度はソフィリアに向き直って言う。
「ユリウスにも申し訳ないことをしてしまったな。彼にもまとまった休暇を与えるよう、ジョルトに頼んでおこう」
「お気遣い感謝いたします。ですが、陛下……おそらく、ユリウスは休暇を喜ばないと思いますわ」
苦笑いを浮かべたソフィリアの言葉に、ルドヴィークが不思議そうな顔をする。
休暇をもらって家に戻ったところで、早く結婚しろと母にせっつかれるばかりでユリウスは居心地が悪いだろう。
それを告げると、ルドヴィークは同情するような顔をし、クロヴィスはくすりと笑った。
「ユリウスは、次期ロートリアス公爵ですからね。母御が気を揉むのも無理はない」
「そんなロートリアス公爵夫人のお気持ち、わたくしもよぉく分かりますわぁ。――ねえ? ルドヴィーク」
母后も俄然口を挟む。その視線は、ルドヴィークの横顔に突き刺さっていた。
ルドヴィークはそれに気づかないふりをしつつ、慌てて話題を変えようとする。
「それにしても、フランには困ったものだな。他国の馬車に人を忍ばせるなんて……普通なら国際問題だぞ」
無類の女好きと自他ともに認めるパトラーシュ皇帝フランディース。
彼は昨日、帰国しようとするルドヴィークの馬車に自国の女を潜り込ませ、強制的にグラディアトリアに連れ帰らせようとした。
ソフィリアにその日のうちに誕生日祝いを贈りたかったルドヴィークは、一向に譲らないフランディースとの話し合いを諦め、雨降りしきる中にもかかわらず馬車を捨て、自ら馬を駆って帰ってきたのだ。
それを思い出して疲れたようなため息をつく彼に、今度はクロヴィスの視線が突き刺さる。
「確かに、フランはめちゃくちゃですが……困ったものなのはルドも同じですよ」
「なに?」
「フランがそんなに強引かつ執拗に女性を紹介しようとするのは、なぜだと思います?」
「……」
軌道修正どころか、明らかに望まぬ方向へと展開していく話に、ルドヴィークはぐっと口を噤ぐ。
その時、はいっ、という声とともに小さな手が挙がった。
「はい、シオン君。早かった」
「ルド兄が、いつまでも婚活しないでのんびりしてるからいけないんだと思います!」
「ご名答。容赦のない言葉をありがとうございます」
「どういたしまして!」
得意げに胸を張るシオンに、クロヴィスはうんうんと頷き、ルドヴィークは苦虫を噛み潰したような顔になる。
しかし、クロヴィスは無情にも攻める手を緩めない。
「フランのありがた迷惑な行為をやめさせたいのなら、あなたもさっさ身を固めればいいんですよ」
「そう言う自分だって、今の私に近い年まで独身だったではないか」
「私とあなたとでは立場が違うんです。皇帝は世襲制なんですから、あなたには世継ぎを確保する義務があります」
「私はまだまだ玉座を降りる気はないぞ。跡継ぎなんか急がなくても……」
ルドヴィークは果敢にも言い返す。
しかし、この次兄に口で対抗しようとしたのがそもそもの間違いだった。
ソファの脇に立ったクロヴィスは、座ったままのルドヴィークを高い位置から見下ろしてぴしゃりと告げた。
「生意気に言い返してくる暇があるなら、さっさと義母上を安心させて差し上げなさい。あなたも、そろそろ親孝行をしてもいい頃合いではないですか?」
「ク、クロヴィス様……」
さすがに見兼ねたルリが、クロヴィスの腕に縋って宥めようとする。
だが彼は平然とその腰を抱き寄せると、ルドヴィークに向かって言葉を重ねた。
「何も、国のためだけを思って、あなたに早く結婚しろと言っているのではありませんよ」
自分にも他人にも厳しく、〝泣く子も黙る鬼宰相〟の異名をとるクロヴィスだが、実はたいそう家族思いな男でもあった。
中でも、末っ子ながら最も重い地位に就いているルドヴィークのことは、特に気に掛けている。
彼は宰相ではなく、兄の顔をして続けた。
「家族が増える幸せを、あなたにも知ってもらいたい。この大国を背負うあなたに、もっと多くの心の支えを得てほしい。私も義母上も、いつだってあなたの幸せを願っているのだということを、心に留めておいてください」
「……分かっている」
ルドヴィークは、とたんにばつが悪そうな顔をした。
そうして、どうにも居心地が悪くなってしまったのだろう。
紅茶を一気に飲み干すと、カップを置いて席を立つ。
「休憩は終わりだ。仕事に戻る」
「それでは、私もこれで失礼いたします」
彼の補佐官たるソフィリアも、必然的に腰を上げる。
結局二人は、紅茶を一杯とクッキーを一かけずつ摘んだだけで、慌ただしく執務室へと戻ることになった。
残された面々は、苦笑いを浮かべてその背中を見送る。
パタン、と扉が閉まって二人の姿が視界から消えると、シオンがクッキーをもぐもぐしながら呟いた。
「ねえ、あの二人……なんでまだ付き合ってないの?」
クロヴィスはルリと並んでソファに腰を下ろすと、両腕を組んでため息をついた。
「二人とも、お互いの気持ちばかりか自分の気持ちにさえ疎いのでしょうね。それと、ガキなんですよ」
「ふうん」
辛辣なクロヴィスの意見に、シオンは随分と気のない返事をする。
そのくせ、クロヴィスを真似るように両腕を組んだかと思うと、難しい顔をして続けた。
「のんびりしてるうちに、他の誰かに取られちゃうかも、とか思わないのかな?」
「おや、シオンはそんなことを思ったりするんですか?」
ませた七歳児の台詞に、クロヴィスが片眉を上げて尋ねる。
シオンはそれに、うん、と頷くと、ソフィリアが抜けて空いた分、アリアーネの方へ詰めて座り直した。
シオンがアリアーネに夢中なのは、二人の親族の間では大変有名な話である。
クロヴィスが、そんな彼を眺めてにやりと笑う。
「ところで、あなた……今更ですが、随分と可愛らしい格好をしているじゃありませんか?」
「ほんと今更だよね? 何で突っ込んだの? 大人なんだからスルーしてよ」
シオンとしては不本意ながら、アリアーネと並んだ今の姿はどう見ても少女二人組。
にやにやするクロヴィスの顔を睨みつけつつ、シオンは再び口を開いた。
「クロヴィス叔父さんもさぁ。ルリにちゃんと、愛してるって言ってるの?」
「はい?」
「どんなに長い時間一緒にいたって、所詮は他人なんだもん。言葉にしなくちゃ、本当の思いなんて伝わらないでしょ?」
「ふむ……」
それを聞いて、クロヴィスは隣に座ったルリと顔を見合わせる。
すると、ルリの頬はみるみる赤くなり、クロヴィスは愛おしげに目を細めた。
「……どうやら、言ってるみたいだね」
「ですねぇ」
そんな二人の様子に、シオンは隣に座ったアリアーネと顔を見合わせ頷く。
かと思ったら、大きな紫色の宝玉を半眼にして続けた。
「ちなみに、うちの父上も毎日スミレちゃんに言ってるからね。うんざりするほど言ってるからね」
シオンの父レイスウェイク大公爵の妻への愛情は、結婚八年目を迎えても衰えることを知らない。それどころか、増す一方であるという。
それをいつも一番近くで見せ付けられているシオンの言葉に、その場にいる大人達は苦笑を禁じ得なかった。
「あら……?」
そんな中、母后がふと、ソファの上に置かれた物に気づく。
「まあまあ、あの子達ったら、書物を忘れて行きましたわ」
ソファに置いたルドヴィークにも、図書館から借りてきた本人であるソフィリアにも、すっかり忘れ去られてしまった哀れな書物。母后は、その一番上に置かれていた一冊を手に取る。
後ほど自分が届けると申し出つつ、クロヴィスも母后の手元を覗き込んだ。
と、書物の題名を目にした二人が、思わずといったふうに顔を見合わせる。
そこには、こう書かれてあった。
『緑の上手な育て方』
「ええっと……土いじりの指南書でしょうか。それも、随分初歩的な……」
「あの子達、園芸でも始めるつもりかしらねぇ……」
クロヴィスも母后も、ソフィリアが昨日、誕生日祝いとしてポトスの若葉を貰い受けたことを知らない。
「いえ、人の趣味について、とやかく言うつもりはありませんが……」
「もっと他に育てるべきものがあるでしょう、とさすがに言ってやりたくなりますわね」
「「――たとえば、お互いの気持ちとか」」
母后とクロヴィスは、揃ってため息をついた。
そんなことがあった日の夕刻のことである。
真っ赤な夕焼けの空の下、カーティスとユリウスを乗せた馬車が、予想よりも大幅に遅れてグラディアトリア城の大門をくぐった。
ところがその馬車の中には、彼らの他にもう一人、往路には存在しなかった人物の姿があった。
10
あなたにおすすめの小説

愛する旦那様が妻(わたし)の嫁ぎ先を探しています。でも、離縁なんてしてあげません。
秘密 (秘翠ミツキ)
恋愛
【清い関係のまま結婚して十年……彼は私を別の男へと引き渡す】
幼い頃、大国の国王へ献上品として連れて来られリゼット。だが余りに幼く扱いに困った国王は末の弟のクロヴィスに下賜した。その為、王弟クロヴィスと結婚をする事になったリゼット。歳の差が9歳とあり、旦那のクロヴィスとは夫婦と言うよりは歳の離れた仲の良い兄妹の様に過ごして来た。
そんな中、結婚から10年が経ちリゼットが15歳という結婚適齢期に差し掛かると、クロヴィスはリゼットの嫁ぎ先を探し始めた。すると社交界は、その噂で持ちきりとなり必然的にリゼットの耳にも入る事となった。噂を聞いたリゼットはショックを受ける。
クロヴィスはリゼットの幸せの為だと話すが、リゼットは大好きなクロヴィスと離れたくなくて……。

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。
ラディ
恋愛
一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。
家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。
劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。
一人の男が現れる。
彼女の人生は彼の登場により一変する。
この機を逃さぬよう、彼女は。
幸せになることに、決めた。
■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!
■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!
■感想や御要望などお気軽にどうぞ!
■エールやいいねも励みになります!
■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。
※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。
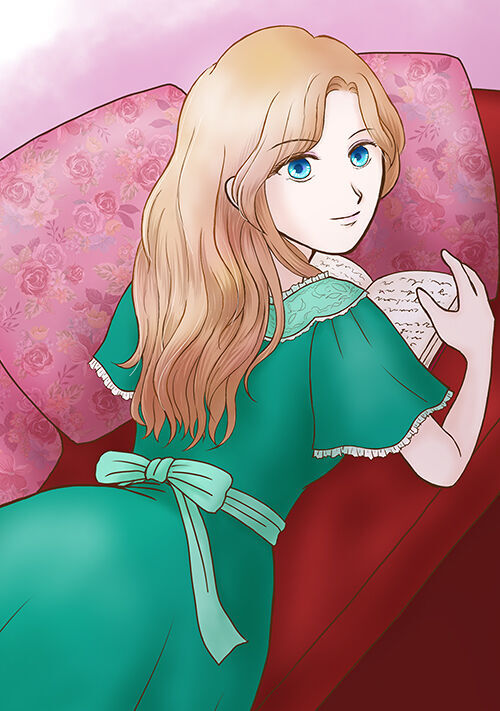
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか
まさかの
恋愛
皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。
己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。
カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。
誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。
ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。
シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。
そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。
嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。
カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。
小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

婚約者を妹に譲ったら、婚約者の兄に溺愛された
みみぢあん
恋愛
結婚式がまじかに迫ったジュリーは、幼馴染の婚約者ジョナサンと妹が裏庭で抱き合う姿を目撃する。 それがきっかけで婚約は解消され、妹と元婚約者が結婚することとなった。 落ち込むジュリーのもとへ元婚約者の兄、ファゼリー伯爵エドガーが謝罪をしに訪れた。 もう1人の幼馴染と再会し、ジュリーは子供の頃の初恋を思い出す。
大人になった2人は……

今宵、薔薇の園で
天海月
恋愛
早世した母の代わりに妹たちの世話に励み、婚期を逃しかけていた伯爵家の長女・シャーロットは、これが最後のチャンスだと思い、唐突に持ち込まれた気の進まない婚約話を承諾する。
しかし、一か月も経たないうちに、その話は先方からの一方的な申し出によって破談になってしまう。
彼女は藁にもすがる思いで、幼馴染の公爵アルバート・グレアムに相談を持ち掛けるが、新たな婚約者候補として紹介されたのは彼の弟のキースだった。
キースは長年、シャーロットに思いを寄せていたが、遠慮して距離を縮めることが出来ないでいた。
そんな弟を見かねた兄が一計を図ったのだった。
彼女はキースのことを弟のようにしか思っていなかったが、次第に彼の情熱に絆されていく・・・。

P.S. 推し活に夢中ですので、返信は不要ですわ
汐瀬うに
恋愛
アルカナ学院に通う伯爵令嬢クラリスは、幼い頃から婚約者である第一王子アルベルトと共に過ごしてきた。しかし彼は言葉を尽くさず、想いはすれ違っていく。噂、距離、役割に心を閉ざしながらも、クラリスは自分の居場所を見つけて前へ進む。迎えたプロムの夜、ようやく言葉を選び、追いかけてきたアルベルトが告げたのは――遅すぎる本心だった。
※こちらの作品はカクヨム・アルファポリス・小説家になろうに並行掲載しています。

残念な顔だとバカにされていた私が隣国の王子様に見初められました
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
公爵令嬢アンジェリカは六歳の誕生日までは天使のように可愛らしい子供だった。ところが突然、ロバのような顔になってしまう。残念な姿に成長した『残念姫』と呼ばれるアンジェリカ。友達は男爵家のウォルターただ一人。そんなある日、隣国から素敵な王子様が留学してきて……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















