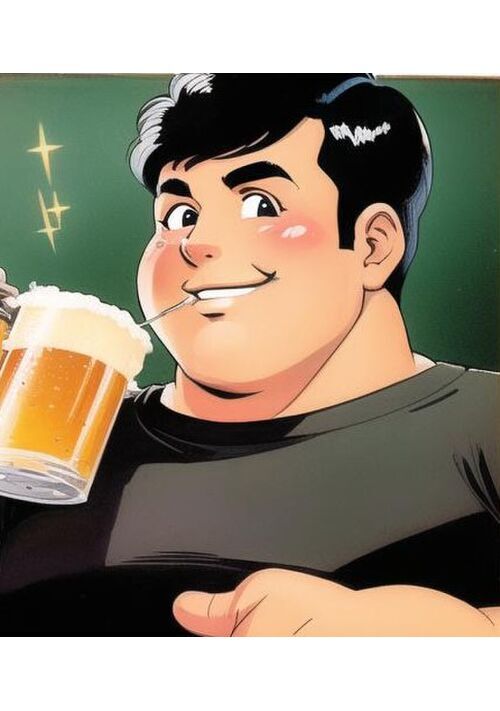32 / 33
32 城下へ
しおりを挟む
「ねぇ、一体何がどうしてこうなったのかしら……。」
「さぁ。ばあやには分かりませんが、お嬢様がお可愛らしいからでしょうね。ばあやはそう思いますよ。」
「……適当に言っているでしょう……。」
ふふふ、とばあやは嬉しそうに笑った。
今ロズリーは平民の中でも比較的暮らしの良い者が着るような、綿でできたワンピースを身に纏い、馬車に揺られている。その馬車も普段使う公爵家の紋章が入ったものではなくて、上等な辻馬車という程度のものだ。
ちなみにこの馬車は公爵家の下働きの者たちが買い出しに使うものなので、決してその辺の辻馬車と同じランクではない。それでも乗り心地が良いわけではなく、ロズリーは天井から吊り下げられたつり革を必死に掴んで耐えていた。
あの妙な約束から一夜明け、公爵家には早朝から王城の馬車がやって来ていた。何やら運び込まれた荷の中にこの衣装が入っていたというわけである。
いつも通りの礼拝だけ済ませ、家に戻ってみると、王城からの荷解きがすっかり終わり、種類別にずらりと並べられていた。両親の顔はホクホクである。
以前に話をしていた、王城に咲く花を豪華に束ねた花束。まぁこの位ならギリギリ許容できる、のか?というくらいの貴金属、そして様々な衣装。
最初は全てドレスなのかと冷や汗をかいた。しかしそのほとんどが平民や商人が着るような衣服だったので、使用人たちへの贈り物だろうか?と訝しんでいると、執事長のイレイスが手紙を持って来る。それによると、これらの衣装はロズリーと城下を視察する際に使う、とのこと。一体どういうつもりなのか。
で、本日分として指定された服を身に纏い今に至るというわけだ。
その服を身に着け、街外れの森まで来るようにという謎の指令を受けたため、ロズリーはこうして必死に馬車にしがみつく運びとなったのである。
「さ、お嬢様。そろそろ着きますよ。」
「そろそろ着いてもらわないと困るわ……!」
徐々に気持ち悪くなってきたロズリーがそう絞り出した途端、馬車はゆっくりと停車した。御者がひょこっと顔を出し、「お嬢さん、着きました!」と元気に言ってくる。少し前に公爵家へ来たばかりの御者なのだが、自治区の馬車組合に所属していた腕の良い御者たちに慣れすぎて、今回のはかなりきつかった。
ややふらつきながら馬車を降りる。一応御者が手を貸してくれたが、どうやら慣れていないらしい。手が離れそうになり、ロズリーは半分落ちるようにして馬車から降りた。
「こんなところまで済まなかったな。……大丈夫か?」
「で、殿下、お待たせして申し訳ございません。」
木陰で待っていたらしいアレクサンダーが駆け寄って来た。ロズリーは腰をさすりたくて出した手をそっと引っ込める。うぅ、痛い。
よく見ると、アレクサンダーは御者の恰好をしていた。自治区で、御者見習いをしていた時の出で立ちである。
自治区から戻ってさほど日が経っていないというのに、何だか妙に懐かしく思えた。
「せっかくの機会だから、街を端からゆっくり視察したいと思ってこんなところまで来てもらった。……遠すぎたか?」
「いえ、大丈夫です。本日は街を視察してからお芝居を見に行く、という流れなのでしょうか。」
「そうだな。皇室用の衣装室がある店に話を通してある。芝居の前にそこで着替えてから向かおう。それで良いか?」
アレクサンダーはロズリーの後ろに控えるイレイスに問うた。皇子が公爵家の使用人に是非を問うなど考えられられないことである。イレイスはただ深々と礼をした。
「まぁそう固くなるな。今の私はただの御者見習いだからな。念のため護衛は遠巻きに潜ませているゆえ、安心せよ。」
「お気遣いありがとうございます。」
「よし、では行こう。」
アレクサンダーは勝手知ったるといった感じで歩き出した。ロズリーは遅れないように着いていく。
普段のドレスに踵の高い靴では到底追いつける速さではないが、今ロズリーが履いているのは庶民たちと同じ簡素な靴だ。底に薄い木の板、それを覆うように藁が張られ、少し硬い布製。
そういえば野ばらの世界で履いた靴は底がゴムでできていた。こちらの世界でもゴムが手に入ると良いのだが。
そんなことを考えながらアレクサンダーの後を追う。街中に差し掛かってきて、人通りも割と多い。こんな街はずれに来た事が無かったロズリーは、きょろきょろと辺りを見回していた。
「ロージー、そんなにいろんなところを見ていたらはぐれるぞ?」
「仕方ないじゃない、私この辺に来るの初めてなんだもん。」
「せめて手つないでてくれ。」
「アレックスがゆっくり歩けばいいだけじゃないの?」
「ロージーに合わせてたらいくら時間があっても足りないよ。」
「失礼ねぇ!」
ぷぅっと膨れるロズリーの手をとったアレクサンダー、もといアレックスは、至極満足そうに微笑むと、そのまま手を引いて街中を進んでいった。
自然と、「ロズリーとアレクサンダー皇子」から「ロージーとアレックス」の関係になっている。
それが、不思議なまでに心地良い。
ふわふわするような気持ちを抱えて、ロズリー、もといロージーは街を観察した。
住宅街と言えば良いのだろうか、民家が立ち並ぶ通りを抜けると、何度か訪れたことのある市場に出る。
朝が一番活気づいているとはいえ、まだまだ人がごった返しているような通りだ。
アレックスは一本横の道に入った。
王都の市場は大きい。この国で一番の広さを誇り、商店の数も、客の数も明らかに他とは一線を画する。自治区で市場の一本脇の通りというとやや治安が悪いこともある(実際ロージーはそこで攫われた)が、王都の市場はそちらにもずらりと商店が並び、人通りもそれなりにあった。
「何か見たいものはあるか?」
「そうねぇ、せっかくだから屋台を見たいわ。それと、チェスの駒!」
「チェスの駒?」
「えぇ。王都で人気の品を確認したいの。」
それなら、とアレックスが向かったのはやや分かりづらい場所に位置する一件のチェス用品店だった。
カラン、とドアのベルが鳴る。中は少し薄暗く、そして埃っぽかった。
「店主、いるか?」
「あ、アレックスさん!!!お久しぶりですね、お元気でしたか!?」
「お元気でしたか、じゃないだろう。なんだ、まだ店そのままなのか?」
「ははは、妻がもう少しで起き上がれそうなんで、仕事場と家をずっと往復してまして。その節は本当にありがとうございました。」
「俺は仕事を頼んだだけだ。で、今日用事があるのは俺じゃない。ロージー、王都で人気の品、だったか?」
ロージーは慌てて店主の方へと駆け寄った。
「そうなんです、最近売れ筋のチェス用品を見たいのですが。」
「それは庶民に、ってことですかね?それとも貴族様に?」
「どちらもです。」
「そうだなぁ……。」
そういうと、店主は棚からいくつかのチェスセットを取り出してカウンターに並べた。
「この辺りが手頃な価格で庶民が手に取りやすいやつでさぁ。」
それは何の飾りもなく、ただの板に線が描かれただけのチェス盤と、最低限何の駒か分かるくらいのピースセットである。棘が刺さらないよう磨かれているので、その点はしっかり作りこまれているという印象だ。
「貴族様に人気の品はこちらですね。お嬢さんがお買い求めになるにはやや高価かと思いますよ。」
こちらは一見して高級なのが見て取れる作りのチェスセットだった。盤だけでなく駒のひとつひとつが丁寧に磨かれ、ニスを塗って光沢を出してある。そして、盤を縁取るように彫られた見事な装飾。これは貴族が好みそうだ。
ロージーは胸元のポケットから小さな袋を取り出すと、中身を出して店主に見せた。
「これ、この店だったらいくらで買い取ります?」
目に悪戯っ子のような光を宿らせながら不敵な笑みを浮かべるロージーを、アレックスは隣で新鮮な感動と共に見ていたのだった。
「さぁ。ばあやには分かりませんが、お嬢様がお可愛らしいからでしょうね。ばあやはそう思いますよ。」
「……適当に言っているでしょう……。」
ふふふ、とばあやは嬉しそうに笑った。
今ロズリーは平民の中でも比較的暮らしの良い者が着るような、綿でできたワンピースを身に纏い、馬車に揺られている。その馬車も普段使う公爵家の紋章が入ったものではなくて、上等な辻馬車という程度のものだ。
ちなみにこの馬車は公爵家の下働きの者たちが買い出しに使うものなので、決してその辺の辻馬車と同じランクではない。それでも乗り心地が良いわけではなく、ロズリーは天井から吊り下げられたつり革を必死に掴んで耐えていた。
あの妙な約束から一夜明け、公爵家には早朝から王城の馬車がやって来ていた。何やら運び込まれた荷の中にこの衣装が入っていたというわけである。
いつも通りの礼拝だけ済ませ、家に戻ってみると、王城からの荷解きがすっかり終わり、種類別にずらりと並べられていた。両親の顔はホクホクである。
以前に話をしていた、王城に咲く花を豪華に束ねた花束。まぁこの位ならギリギリ許容できる、のか?というくらいの貴金属、そして様々な衣装。
最初は全てドレスなのかと冷や汗をかいた。しかしそのほとんどが平民や商人が着るような衣服だったので、使用人たちへの贈り物だろうか?と訝しんでいると、執事長のイレイスが手紙を持って来る。それによると、これらの衣装はロズリーと城下を視察する際に使う、とのこと。一体どういうつもりなのか。
で、本日分として指定された服を身に纏い今に至るというわけだ。
その服を身に着け、街外れの森まで来るようにという謎の指令を受けたため、ロズリーはこうして必死に馬車にしがみつく運びとなったのである。
「さ、お嬢様。そろそろ着きますよ。」
「そろそろ着いてもらわないと困るわ……!」
徐々に気持ち悪くなってきたロズリーがそう絞り出した途端、馬車はゆっくりと停車した。御者がひょこっと顔を出し、「お嬢さん、着きました!」と元気に言ってくる。少し前に公爵家へ来たばかりの御者なのだが、自治区の馬車組合に所属していた腕の良い御者たちに慣れすぎて、今回のはかなりきつかった。
ややふらつきながら馬車を降りる。一応御者が手を貸してくれたが、どうやら慣れていないらしい。手が離れそうになり、ロズリーは半分落ちるようにして馬車から降りた。
「こんなところまで済まなかったな。……大丈夫か?」
「で、殿下、お待たせして申し訳ございません。」
木陰で待っていたらしいアレクサンダーが駆け寄って来た。ロズリーは腰をさすりたくて出した手をそっと引っ込める。うぅ、痛い。
よく見ると、アレクサンダーは御者の恰好をしていた。自治区で、御者見習いをしていた時の出で立ちである。
自治区から戻ってさほど日が経っていないというのに、何だか妙に懐かしく思えた。
「せっかくの機会だから、街を端からゆっくり視察したいと思ってこんなところまで来てもらった。……遠すぎたか?」
「いえ、大丈夫です。本日は街を視察してからお芝居を見に行く、という流れなのでしょうか。」
「そうだな。皇室用の衣装室がある店に話を通してある。芝居の前にそこで着替えてから向かおう。それで良いか?」
アレクサンダーはロズリーの後ろに控えるイレイスに問うた。皇子が公爵家の使用人に是非を問うなど考えられられないことである。イレイスはただ深々と礼をした。
「まぁそう固くなるな。今の私はただの御者見習いだからな。念のため護衛は遠巻きに潜ませているゆえ、安心せよ。」
「お気遣いありがとうございます。」
「よし、では行こう。」
アレクサンダーは勝手知ったるといった感じで歩き出した。ロズリーは遅れないように着いていく。
普段のドレスに踵の高い靴では到底追いつける速さではないが、今ロズリーが履いているのは庶民たちと同じ簡素な靴だ。底に薄い木の板、それを覆うように藁が張られ、少し硬い布製。
そういえば野ばらの世界で履いた靴は底がゴムでできていた。こちらの世界でもゴムが手に入ると良いのだが。
そんなことを考えながらアレクサンダーの後を追う。街中に差し掛かってきて、人通りも割と多い。こんな街はずれに来た事が無かったロズリーは、きょろきょろと辺りを見回していた。
「ロージー、そんなにいろんなところを見ていたらはぐれるぞ?」
「仕方ないじゃない、私この辺に来るの初めてなんだもん。」
「せめて手つないでてくれ。」
「アレックスがゆっくり歩けばいいだけじゃないの?」
「ロージーに合わせてたらいくら時間があっても足りないよ。」
「失礼ねぇ!」
ぷぅっと膨れるロズリーの手をとったアレクサンダー、もといアレックスは、至極満足そうに微笑むと、そのまま手を引いて街中を進んでいった。
自然と、「ロズリーとアレクサンダー皇子」から「ロージーとアレックス」の関係になっている。
それが、不思議なまでに心地良い。
ふわふわするような気持ちを抱えて、ロズリー、もといロージーは街を観察した。
住宅街と言えば良いのだろうか、民家が立ち並ぶ通りを抜けると、何度か訪れたことのある市場に出る。
朝が一番活気づいているとはいえ、まだまだ人がごった返しているような通りだ。
アレックスは一本横の道に入った。
王都の市場は大きい。この国で一番の広さを誇り、商店の数も、客の数も明らかに他とは一線を画する。自治区で市場の一本脇の通りというとやや治安が悪いこともある(実際ロージーはそこで攫われた)が、王都の市場はそちらにもずらりと商店が並び、人通りもそれなりにあった。
「何か見たいものはあるか?」
「そうねぇ、せっかくだから屋台を見たいわ。それと、チェスの駒!」
「チェスの駒?」
「えぇ。王都で人気の品を確認したいの。」
それなら、とアレックスが向かったのはやや分かりづらい場所に位置する一件のチェス用品店だった。
カラン、とドアのベルが鳴る。中は少し薄暗く、そして埃っぽかった。
「店主、いるか?」
「あ、アレックスさん!!!お久しぶりですね、お元気でしたか!?」
「お元気でしたか、じゃないだろう。なんだ、まだ店そのままなのか?」
「ははは、妻がもう少しで起き上がれそうなんで、仕事場と家をずっと往復してまして。その節は本当にありがとうございました。」
「俺は仕事を頼んだだけだ。で、今日用事があるのは俺じゃない。ロージー、王都で人気の品、だったか?」
ロージーは慌てて店主の方へと駆け寄った。
「そうなんです、最近売れ筋のチェス用品を見たいのですが。」
「それは庶民に、ってことですかね?それとも貴族様に?」
「どちらもです。」
「そうだなぁ……。」
そういうと、店主は棚からいくつかのチェスセットを取り出してカウンターに並べた。
「この辺りが手頃な価格で庶民が手に取りやすいやつでさぁ。」
それは何の飾りもなく、ただの板に線が描かれただけのチェス盤と、最低限何の駒か分かるくらいのピースセットである。棘が刺さらないよう磨かれているので、その点はしっかり作りこまれているという印象だ。
「貴族様に人気の品はこちらですね。お嬢さんがお買い求めになるにはやや高価かと思いますよ。」
こちらは一見して高級なのが見て取れる作りのチェスセットだった。盤だけでなく駒のひとつひとつが丁寧に磨かれ、ニスを塗って光沢を出してある。そして、盤を縁取るように彫られた見事な装飾。これは貴族が好みそうだ。
ロージーは胸元のポケットから小さな袋を取り出すと、中身を出して店主に見せた。
「これ、この店だったらいくらで買い取ります?」
目に悪戯っ子のような光を宿らせながら不敵な笑みを浮かべるロージーを、アレックスは隣で新鮮な感動と共に見ていたのだった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
38
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる