4 / 5
#4
しおりを挟む
******
きちんと視力検査をしてもらった結果、今の眼鏡が合っていないことが判明した。
毎日かけていたから気づかなかったが、そのせいで視神経はボケた分を調整しようと必死に働き、それに激務も手伝って首や肩まで影響が出たんだろうと話していた。
「仕事に一生懸命なのはいいけど、やっぱり疲れると仕事の質が落ちる。桜井もたまには鬼のいう事を聞くべきだな」
楠田がいうと、綾樹は「そうだろう、そうだろう?」うんうんと頷いていた。
――かくして1週間後。
今日は聡樹が休みだ。体調がすぐれないという。
そんなわけで、代理として綾樹が社長室で仕事をしている。
綾樹が注文した眼鏡が手元に届いたとのことで、社長室に呼び出され、桜井は今、綾樹の手でそれを掛けさせてもらったところだ。
自分で掛けると言ったのだが、綾樹が「よく見えていないのに落としたらどうする」と頑として聞かなかった。
冗談抜きで綾樹へのときめきが止まらない。
こんなふうに大切なお姫様のように扱われて、ずっとずっと閉じ込めていた片想いが綾樹へ向かって走り出そうとしている。
今の自分は普通に見えるだろうか。
「うん、耳にもちゃんとかかっている。桜井、かけ心地はどうだ?」
「ええ、ずれてもいないし、大丈夫です」
ちゃんと度を測ったレンズを入れているので、こんどは視界がはっきりと見えるし、なによりレンズが入ってもとても軽い。かけていることを忘れてしまいそうになるが、リムが目の端に見えていることで、眼鏡をかけているんだなと実感するくらいだ。
社長室には大きな姿見しか鏡がない。桜井は綾樹に断って、姿見の前に立った。
はっきり見える状態で、初めて自分の顔を見る。
「わあ……すごい……」
今までかけていた太いフレームと違い、自分の顔がすっきりとしていた。
それになんだか、細いフレームは見た目に「有能そう」で、ちょっと違う自分に出会えたようで、なんだか新鮮だ。
「どうだ、気に入ってくれたか?」
姿見に映る自分の後ろに、上質な黒のスーツにワインレッドのネクタイを締めた綾樹が立つ。
桜井より頭一つ分背が高い彼は、桜井の両肩に手をおくと、そのまま目線を桜井の高さに合わせた。
形がよくて、清潔感のある綾樹の長い指が触れる場所から熱が注ぎ込まれ、恋心がどんどん刺激されていく。
どきどきが止まらない。嬉しくてときめいて、そして少し恥ずかしくて。
ずっと綾樹と一緒に歩んできたのに、最近の彼はますますその男ぶりに磨きがかかっている。
「少しはこの肩の負担も少なくなるといいのだが」
耳元で囁かれる嬉しそうな、そしてほんの少し心配そうな綾樹の声。
彼は、桜井の気持ちをまだ知らない。
だけど、今はまだ綾樹への気持ちを伝えられない。
まだ、彼をちゃんと支えるだけの力が、桜井にはないから、真面目に頑張る綾樹を自分の気持ちで混乱させるわけにはいかないのだ。
ちゃんと綾樹の隣で歩いていけるようになるまでは、この恋は我慢すると決めている。
今は恋だ愛だにうつつを抜かしている場合じゃないのだ。
なのに……「好き」が止まらない。
「ありがとうございます」
桜井はぽてっと赤くなった顔を隠すように、少し俯いた。
が。
「俯くな。桜井の顔がよく見えない」
綾樹の手が桜井を頭を両端から掴んで、無理に鏡に向けさせる。
「あ、あやき……」
「うん、私の思った通りだ。桜井にはこのフレームが絶対に似合うと思っていた」
鏡に映る綾樹が満足そうに笑う。
もともと彼は、笑うと優しい顔になる。
彼の本質は心配性で、思いやりのある優しい男だというのを桜井は知っている。
だがいつしか綾樹は笑わなくなり、そのまま大人になってしまった。
だから本人は、その優しさを周囲に広げるのが本当に下手くそなのだ。
誤解されてばかりの鬼の副社長、その彼が桜井のことを思って、一生懸命選んでくれたフレームが似合わないはずがない。
「私には本当にもったいない。副社長にこんなに大切にしてもらえるなんて」
眼鏡をかけたまま、角度を変えてフレームを見ていると、「気に入ってくれて良かった」と綾樹も嬉しそうだ。
「桜井。このフレームはリンドバーグというデンマークのブランドだ」
「リンドバーグ……」
初めて聞いたブランドだ。
「リンドバーグと言えば、飛行機の方しか知りませんでした」
綾樹は「普通はそうだな」と笑った。
「桜井は、飛行機の方のリンドバーグのもう一つの偉業を知っているか?」
「偉業、ですか」
「リンドバーグには心臓を患っている姉がいて、彼は協力者を得て人工心臓のベースとなる研究を行ったとされている。私たちも医療の分野にかかる業務だ。そして願わくば、リンドバーグが協力者を見つけて、後世に受け継がれた製品を残したように、私も同じ目標に向かってくれる相手が欲しいと思っている。眼鏡をリンドバーグにしたのは、私の気持ちとブランドの名前を掛けたんだ」
「それ……」
「未来へ共に歩み、何かを残せる信頼できる相手……そういう人間にそばにいてほしい」
これは綾樹の告白なのか。綾樹は自分のことをそんなに思ってくれているのか。
だけど綾樹の真意は? これは「恋」なのか?
「副社長……」
「今は二人きりだ。副社長ではなく、綾樹でいい」
急に桜井の身体が背後に引き寄せられる。
「えっ……?」
何が起こったのか鏡を見れば、綾樹が桜井の身体を胸の中に抱きとめていた。
「あや……」
「桜井、少しだけこうしていてくれないか」
ぎゅっと目を閉じて、桜井の肩に顔をうずめ、桜井を離さないとばかりに背後から回される腕の力が強くて。
泣いているわけではなさそうだが、綾樹の大きな身体が震えている。
いったいどうしたというのか。
言葉を掛けようとした瞬間。
「おまえはちゃんと私についてこれているか?」
「え?」
綾樹が意図することがわからず、桜井は首をかしげる。
「正直言って、今の私では会社を守るには未熟すぎる。私はただ、新城聡樹の息子に生まれただけで、自分に父のような度量があるとも思えない」
「あなたは今までも十分頑張ってますよ。聡樹社長のかわりだって立派にこなしてらっしゃる」
「二世だから」「跡継ぎだから」――――どんなに綾樹が頑張っても、今は誰も綾樹を認めない。
聡樹を超えたときに、初めて綾樹は周囲から認めてもらえる。
副社長という肩書ではあるけれど、現場にも入り込んで、一生懸命会社全体の流れを掴もうと必死だ。
ただ、今は一生懸命ゆえに空回りしているところもある。
彼は彼なりに、会社と社員を守る術を模索しているのだ。
「私は将来、いやが応にも父の業務を継ぐことになる。だが……」
綾樹がゆっくりと顔をあげた。
「一人の人間も守れなくて、私は会社の全てを守ることなどできないと思っている」
「綾樹……」
桜井を抱きしめる綾樹の表情がぎこちなく不安に揺れていたが、視線の先は桜井に向けられている。
その熱情に、桜井の全てをがんじがらめにされてしまう。
「何があっても、私は桜井を守る。おまえだけには、辛い思いを絶対にさせない」
「綾樹……」
「だからこの先もずっと、私のそばにいて、ともに歩いてくれないか」
なんて告白。
眩暈が――しそうだ。
恋焦がれた人から、こんなふうに思われているなんて。
これが大人の関係を孕むものだということを理解できないほど、桜井は子どもじゃない。
「綾樹……ありがとうございます」
幸せすぎて怖くなる。綾樹の気持ちに飛び込んでいきたい。
あなたが好きだと、あなたがほしくてたまらないのだと、彼を抱きしめて伝えたい。
だが今の桜井では、綾樹になにもしてやれない。
綾樹は真面目だ。だからこそ、彼の要求はきっとすごくレベルが高いはずだ。
仕事もプライベートも……きっと恋愛も。
経験も何もないまま綾樹について行って、彼の足手まといになるなんて、それだけは嫌だ。
「私はまだ未熟者です。まだあなたの気持ちを受けるに足らない。私があなたと共に立てるその日が来るまで、その気持ちは綾樹にお預けしておきます」
綾樹が好きだから。桜井の心の中には、綾樹しかいないのだから。
綾樹が何も心配せずに、前に歩いていくために、自分は綾樹が歩む未来を整えなければならない。
だからこそ今は―――甘えられない。
「私はお調子者なんです。いま綾樹の気持ちを受け取ってしまったら、私はそちらばかりが気になって、やるべきことを疎かにしてしまう。あなたとともに並び立つ資格がなくなってしまう」
そのときにまだ、綾樹が私に今の気持ちを持ってくれているなら。
「私が一人前になったそのときに、また想いを聞かせてください」
その時は、綾樹の気持ちを受け取ろう。
今はまだ、綾樹を守れるように強くなるための時間がほしい。
――だけど本当は。
この後ろから回された腕を取って、綾樹に伝えたい。
誰よりもあなたが好き。大好き。
あなたのためなら、この命すら投げ出しても惜しくはないと――――。
きちんと視力検査をしてもらった結果、今の眼鏡が合っていないことが判明した。
毎日かけていたから気づかなかったが、そのせいで視神経はボケた分を調整しようと必死に働き、それに激務も手伝って首や肩まで影響が出たんだろうと話していた。
「仕事に一生懸命なのはいいけど、やっぱり疲れると仕事の質が落ちる。桜井もたまには鬼のいう事を聞くべきだな」
楠田がいうと、綾樹は「そうだろう、そうだろう?」うんうんと頷いていた。
――かくして1週間後。
今日は聡樹が休みだ。体調がすぐれないという。
そんなわけで、代理として綾樹が社長室で仕事をしている。
綾樹が注文した眼鏡が手元に届いたとのことで、社長室に呼び出され、桜井は今、綾樹の手でそれを掛けさせてもらったところだ。
自分で掛けると言ったのだが、綾樹が「よく見えていないのに落としたらどうする」と頑として聞かなかった。
冗談抜きで綾樹へのときめきが止まらない。
こんなふうに大切なお姫様のように扱われて、ずっとずっと閉じ込めていた片想いが綾樹へ向かって走り出そうとしている。
今の自分は普通に見えるだろうか。
「うん、耳にもちゃんとかかっている。桜井、かけ心地はどうだ?」
「ええ、ずれてもいないし、大丈夫です」
ちゃんと度を測ったレンズを入れているので、こんどは視界がはっきりと見えるし、なによりレンズが入ってもとても軽い。かけていることを忘れてしまいそうになるが、リムが目の端に見えていることで、眼鏡をかけているんだなと実感するくらいだ。
社長室には大きな姿見しか鏡がない。桜井は綾樹に断って、姿見の前に立った。
はっきり見える状態で、初めて自分の顔を見る。
「わあ……すごい……」
今までかけていた太いフレームと違い、自分の顔がすっきりとしていた。
それになんだか、細いフレームは見た目に「有能そう」で、ちょっと違う自分に出会えたようで、なんだか新鮮だ。
「どうだ、気に入ってくれたか?」
姿見に映る自分の後ろに、上質な黒のスーツにワインレッドのネクタイを締めた綾樹が立つ。
桜井より頭一つ分背が高い彼は、桜井の両肩に手をおくと、そのまま目線を桜井の高さに合わせた。
形がよくて、清潔感のある綾樹の長い指が触れる場所から熱が注ぎ込まれ、恋心がどんどん刺激されていく。
どきどきが止まらない。嬉しくてときめいて、そして少し恥ずかしくて。
ずっと綾樹と一緒に歩んできたのに、最近の彼はますますその男ぶりに磨きがかかっている。
「少しはこの肩の負担も少なくなるといいのだが」
耳元で囁かれる嬉しそうな、そしてほんの少し心配そうな綾樹の声。
彼は、桜井の気持ちをまだ知らない。
だけど、今はまだ綾樹への気持ちを伝えられない。
まだ、彼をちゃんと支えるだけの力が、桜井にはないから、真面目に頑張る綾樹を自分の気持ちで混乱させるわけにはいかないのだ。
ちゃんと綾樹の隣で歩いていけるようになるまでは、この恋は我慢すると決めている。
今は恋だ愛だにうつつを抜かしている場合じゃないのだ。
なのに……「好き」が止まらない。
「ありがとうございます」
桜井はぽてっと赤くなった顔を隠すように、少し俯いた。
が。
「俯くな。桜井の顔がよく見えない」
綾樹の手が桜井を頭を両端から掴んで、無理に鏡に向けさせる。
「あ、あやき……」
「うん、私の思った通りだ。桜井にはこのフレームが絶対に似合うと思っていた」
鏡に映る綾樹が満足そうに笑う。
もともと彼は、笑うと優しい顔になる。
彼の本質は心配性で、思いやりのある優しい男だというのを桜井は知っている。
だがいつしか綾樹は笑わなくなり、そのまま大人になってしまった。
だから本人は、その優しさを周囲に広げるのが本当に下手くそなのだ。
誤解されてばかりの鬼の副社長、その彼が桜井のことを思って、一生懸命選んでくれたフレームが似合わないはずがない。
「私には本当にもったいない。副社長にこんなに大切にしてもらえるなんて」
眼鏡をかけたまま、角度を変えてフレームを見ていると、「気に入ってくれて良かった」と綾樹も嬉しそうだ。
「桜井。このフレームはリンドバーグというデンマークのブランドだ」
「リンドバーグ……」
初めて聞いたブランドだ。
「リンドバーグと言えば、飛行機の方しか知りませんでした」
綾樹は「普通はそうだな」と笑った。
「桜井は、飛行機の方のリンドバーグのもう一つの偉業を知っているか?」
「偉業、ですか」
「リンドバーグには心臓を患っている姉がいて、彼は協力者を得て人工心臓のベースとなる研究を行ったとされている。私たちも医療の分野にかかる業務だ。そして願わくば、リンドバーグが協力者を見つけて、後世に受け継がれた製品を残したように、私も同じ目標に向かってくれる相手が欲しいと思っている。眼鏡をリンドバーグにしたのは、私の気持ちとブランドの名前を掛けたんだ」
「それ……」
「未来へ共に歩み、何かを残せる信頼できる相手……そういう人間にそばにいてほしい」
これは綾樹の告白なのか。綾樹は自分のことをそんなに思ってくれているのか。
だけど綾樹の真意は? これは「恋」なのか?
「副社長……」
「今は二人きりだ。副社長ではなく、綾樹でいい」
急に桜井の身体が背後に引き寄せられる。
「えっ……?」
何が起こったのか鏡を見れば、綾樹が桜井の身体を胸の中に抱きとめていた。
「あや……」
「桜井、少しだけこうしていてくれないか」
ぎゅっと目を閉じて、桜井の肩に顔をうずめ、桜井を離さないとばかりに背後から回される腕の力が強くて。
泣いているわけではなさそうだが、綾樹の大きな身体が震えている。
いったいどうしたというのか。
言葉を掛けようとした瞬間。
「おまえはちゃんと私についてこれているか?」
「え?」
綾樹が意図することがわからず、桜井は首をかしげる。
「正直言って、今の私では会社を守るには未熟すぎる。私はただ、新城聡樹の息子に生まれただけで、自分に父のような度量があるとも思えない」
「あなたは今までも十分頑張ってますよ。聡樹社長のかわりだって立派にこなしてらっしゃる」
「二世だから」「跡継ぎだから」――――どんなに綾樹が頑張っても、今は誰も綾樹を認めない。
聡樹を超えたときに、初めて綾樹は周囲から認めてもらえる。
副社長という肩書ではあるけれど、現場にも入り込んで、一生懸命会社全体の流れを掴もうと必死だ。
ただ、今は一生懸命ゆえに空回りしているところもある。
彼は彼なりに、会社と社員を守る術を模索しているのだ。
「私は将来、いやが応にも父の業務を継ぐことになる。だが……」
綾樹がゆっくりと顔をあげた。
「一人の人間も守れなくて、私は会社の全てを守ることなどできないと思っている」
「綾樹……」
桜井を抱きしめる綾樹の表情がぎこちなく不安に揺れていたが、視線の先は桜井に向けられている。
その熱情に、桜井の全てをがんじがらめにされてしまう。
「何があっても、私は桜井を守る。おまえだけには、辛い思いを絶対にさせない」
「綾樹……」
「だからこの先もずっと、私のそばにいて、ともに歩いてくれないか」
なんて告白。
眩暈が――しそうだ。
恋焦がれた人から、こんなふうに思われているなんて。
これが大人の関係を孕むものだということを理解できないほど、桜井は子どもじゃない。
「綾樹……ありがとうございます」
幸せすぎて怖くなる。綾樹の気持ちに飛び込んでいきたい。
あなたが好きだと、あなたがほしくてたまらないのだと、彼を抱きしめて伝えたい。
だが今の桜井では、綾樹になにもしてやれない。
綾樹は真面目だ。だからこそ、彼の要求はきっとすごくレベルが高いはずだ。
仕事もプライベートも……きっと恋愛も。
経験も何もないまま綾樹について行って、彼の足手まといになるなんて、それだけは嫌だ。
「私はまだ未熟者です。まだあなたの気持ちを受けるに足らない。私があなたと共に立てるその日が来るまで、その気持ちは綾樹にお預けしておきます」
綾樹が好きだから。桜井の心の中には、綾樹しかいないのだから。
綾樹が何も心配せずに、前に歩いていくために、自分は綾樹が歩む未来を整えなければならない。
だからこそ今は―――甘えられない。
「私はお調子者なんです。いま綾樹の気持ちを受け取ってしまったら、私はそちらばかりが気になって、やるべきことを疎かにしてしまう。あなたとともに並び立つ資格がなくなってしまう」
そのときにまだ、綾樹が私に今の気持ちを持ってくれているなら。
「私が一人前になったそのときに、また想いを聞かせてください」
その時は、綾樹の気持ちを受け取ろう。
今はまだ、綾樹を守れるように強くなるための時間がほしい。
――だけど本当は。
この後ろから回された腕を取って、綾樹に伝えたい。
誰よりもあなたが好き。大好き。
あなたのためなら、この命すら投げ出しても惜しくはないと――――。
0
あなたにおすすめの小説

もう観念しなよ、呆れた顔の彼に諦めの悪い僕は財布の3万円を机の上に置いた
谷地
BL
お昼寝コース(※2時間)8000円。
就寝コースは、8時間/1万5千円・10時間/2万円・12時間/3万円~お選びいただけます。
お好みのキャストを選んで御予約下さい。はじめてに限り2000円値引きキャンペーン実施中!
液晶の中で光るポップなフォントは安っぽくぴかぴかと光っていた。
完結しました *・゚
2025.5.10 少し修正しました。
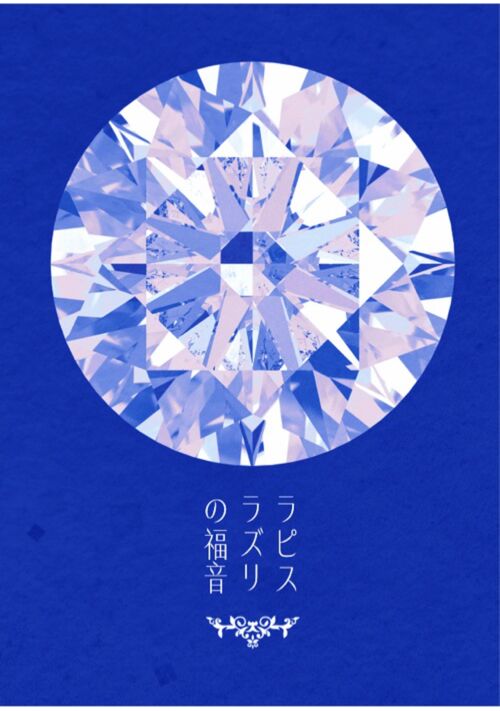
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

無口な愛情
結衣可
BL
『兄の親友』のスピンオフ。
葛城律は、部下からも信頼される責任感の強い兄貴肌の存在。ただ、人に甘えることが苦手。
そんな律の前に現れたのが、同年代の部下・桐生隼人。
大柄で無口、感情をあまり表に出さないが、実は誰よりも誠実で優しい男だった。
最初はただの同僚として接していた二人。
しかし、律が「寂しくて眠れない」と漏らした夜、隼人が迷わず会いに来たことで関係は大きく動き出す。
無口で不器用ながらも行動で示してくれる隼人に、律は次第に素直な弱さを見せるようになり、
日常の中に溶け込むささやかな出来事が、二人の絆を少しずつ深めていく。

あなたに捧ぐ愛の花
とうこ
BL
余命宣告を受けた青年はある日、風変わりな花屋に迷い込む。
そこにあったのは「心残りの種」から芽吹き咲いたという見たこともない花々。店主は言う。
「心残りの種を育てて下さい」
遺していく恋人への、彼の最後の希いとは。


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

王様の恋
うりぼう
BL
「惚れ薬は手に入るか?」
突然王に言われた一言。
王は惚れ薬を使ってでも手に入れたい人間がいるらしい。
ずっと王を見つめてきた幼馴染の側近と王の話。
※エセ王国
※エセファンタジー
※惚れ薬
※異世界トリップ表現が少しあります

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















