36 / 62
4章 人民よ、健やかに
36話 平焼きパン
しおりを挟む
村へ戻ると、三人の村人とナビゲーターは器を囲んでいた。辺りには黄土色の破片が散らばっている。当然彼等の服が難を逃れる筈がなく、ひどい有様であった。一連の作業に興味はあったが、席を外して正解だったかもしれない。
俺の気配を察したのか、ナビ子がパッと振り返る。短いツインテールが、傍らのクローイを掠めた。
「村長さん、朗報です。《麦粥》が作れるようになりました!」
「お粥?」
俺は首を捻る。
「パンとか作れるようになる訳じゃないんですね」
「そうなんだよ~! 分かるか、オレのがっかり具合! パン食えると思って頑張ったのに~」
すっかり落胆した様子でアランが身体を横たえる。頭の先から踵まで籾殻に沈み込むことなど、気にも止めていないようだ。
「《パン》を作るには、製粉の作業も必要です。また、パン焼き専用のかまども設置しなくてはなりません」
「かまど……はまだ作れませんかね?」
「はい。『石工師』の上級職である『陶芸師』が作成する《レンガ》が必要になりますので、もうしばらく先になりそうです」
「……現状、他に作れそうな物は?」
「《麦粥》のみです」
それを聞いて、俺は愕然とした。脱穀に籾摺りの工程を経てもなお、碌な食事にはありつけないのか。焼いただけの《ニンジン》や《キノコ》よりはまだマシかもしれないが、住民達には失望をさせてしまったかもしれない。
「じゃ、じゃあ、製粉をすれば、作れるものは増えますか?」
「はい。《平焼きパン》が作成可能となります」
パン、と食い付いたのはアランだ。
だが気になるのは、冠せられた「平焼き」である。おそらく、俺達が慣れ親しんだ、ふっくら柔らかいパンとは別物なのであろう。多分潰れている。
「製粉ということは、何か道具が必要ですね? すり鉢とか……もしかして、この前作った《薬研》を代用したりしますか?」
「いいえ、製粉には専用の道具が存在します。《石臼》です」
ナビ子が提示したのは、レシピを収録したファイルだった。『石工師』の作成可能アイテムの一覧。彼女の指は、一つの模範図を示す。《石臼》――そこには、そう書かれていた。
「石ならわたくしの出番ね!」
キリリと表情を引き締めて、ルシンダが胸を張る。早速彼女に作成の依頼を出すと、揚々とした足取りで女子部屋に入って行った。
《小麦》の利用の目途が立ったのならば、これを中心に食事のメニューを組み立てるのがよさそうだ。
「畑、拡張しましょうか」
現在この村にあるのは、およそ三メートル四方の畑が四面である。《小麦》に二面、《ニンジン》に二面を使用している。
畑からの収穫は定期的に望めるとは言え、貯蔵はほぼ不可能に近い。やっとのことで食い繋いでいる状態だ。
某プレイヤーのように一辺二十メートルの畑を作るつもりはないが、ある程度拡充する必要がある。
俺が提案すると、アランは打ち捨てられた汚物を見下ろすように顔を歪めた。
「明日にしようぜ」
「出来れば今日がいいんですけど……。人も増えましたし、マルケンさんから買った種も結局植えてないし。それから――そうそう、井戸とか必要なら、そろそろ作りたいんですけど、どうしたらいいんですかね?」
小屋に立て掛けてあった枝を手に、俺はナビ子に目を向ける。ナビ子はフンスとばかりに鼻を鳴らすと、
「《井戸》は《石材》を消費することで作ることが出来ます。現実のように水源を探し、地面を掘り下げる必要はなく、井戸の囲いを設置することで使用可能になります」
「不思議パワーで水が湧き出てくる訳ですか。ということは、一度作ってしまえば枯渇することもありませんか?」
「はい。御心配なく」
「じゃあルシンダさんにはその作成も……あ、《石材》足りるかな」
以前採取した《石材》は、ルシンダの活躍により大半を消費している。村が所有する資材一覧を覗いてみるも、やはり残部は心許ない。《石臼》ならまだしも、《井戸》の作成に足る資材は保有していなかった。
「じゃあおれ、作業に戻るね」
ひらひらと手を振って、イアンが《なめし台》の方へと向かう。
生皮の状態では、中間素材として使用できない。保存できるよう、また今後の加工を容易にする為、剥ぎ取った皮はなめしておく必要があるのだ。
部屋の中から「わたくしも作業見たい!」と悲鳴が聞こえたが、俺は無視しておくことにした。
「あの……今のうちに《石材》、集めておきます。在庫、もうないですよね?」
「ありがとうございます、クローイさん。じゃあ……そうですね、サミュエル君を連れて行ってください」
「一人で大丈夫です」
「念のためです。何があるか分かりませんから。――サミュエル君もいいですね?」
隻眼の少年に目を向けると、彼は迷う素振りを見せた。
丸一日持ち場を離れるという訳ではないのだ。たった数時間あるいは数分、村の護衛からクローイの警護に任を移す、ただそれだけである。
「お願いします」
「……分かった」
それだけ言うと、サミュエルは踵を返す。
彼の腰には石製の剣が差さっている。襲撃時に携えていた金属製の得物よりも、幾分かグレードを落とした品である。
少々心許ない出来であるが、それゆえか、少年の背は少し強張っていた。
俺の気配を察したのか、ナビ子がパッと振り返る。短いツインテールが、傍らのクローイを掠めた。
「村長さん、朗報です。《麦粥》が作れるようになりました!」
「お粥?」
俺は首を捻る。
「パンとか作れるようになる訳じゃないんですね」
「そうなんだよ~! 分かるか、オレのがっかり具合! パン食えると思って頑張ったのに~」
すっかり落胆した様子でアランが身体を横たえる。頭の先から踵まで籾殻に沈み込むことなど、気にも止めていないようだ。
「《パン》を作るには、製粉の作業も必要です。また、パン焼き専用のかまども設置しなくてはなりません」
「かまど……はまだ作れませんかね?」
「はい。『石工師』の上級職である『陶芸師』が作成する《レンガ》が必要になりますので、もうしばらく先になりそうです」
「……現状、他に作れそうな物は?」
「《麦粥》のみです」
それを聞いて、俺は愕然とした。脱穀に籾摺りの工程を経てもなお、碌な食事にはありつけないのか。焼いただけの《ニンジン》や《キノコ》よりはまだマシかもしれないが、住民達には失望をさせてしまったかもしれない。
「じゃ、じゃあ、製粉をすれば、作れるものは増えますか?」
「はい。《平焼きパン》が作成可能となります」
パン、と食い付いたのはアランだ。
だが気になるのは、冠せられた「平焼き」である。おそらく、俺達が慣れ親しんだ、ふっくら柔らかいパンとは別物なのであろう。多分潰れている。
「製粉ということは、何か道具が必要ですね? すり鉢とか……もしかして、この前作った《薬研》を代用したりしますか?」
「いいえ、製粉には専用の道具が存在します。《石臼》です」
ナビ子が提示したのは、レシピを収録したファイルだった。『石工師』の作成可能アイテムの一覧。彼女の指は、一つの模範図を示す。《石臼》――そこには、そう書かれていた。
「石ならわたくしの出番ね!」
キリリと表情を引き締めて、ルシンダが胸を張る。早速彼女に作成の依頼を出すと、揚々とした足取りで女子部屋に入って行った。
《小麦》の利用の目途が立ったのならば、これを中心に食事のメニューを組み立てるのがよさそうだ。
「畑、拡張しましょうか」
現在この村にあるのは、およそ三メートル四方の畑が四面である。《小麦》に二面、《ニンジン》に二面を使用している。
畑からの収穫は定期的に望めるとは言え、貯蔵はほぼ不可能に近い。やっとのことで食い繋いでいる状態だ。
某プレイヤーのように一辺二十メートルの畑を作るつもりはないが、ある程度拡充する必要がある。
俺が提案すると、アランは打ち捨てられた汚物を見下ろすように顔を歪めた。
「明日にしようぜ」
「出来れば今日がいいんですけど……。人も増えましたし、マルケンさんから買った種も結局植えてないし。それから――そうそう、井戸とか必要なら、そろそろ作りたいんですけど、どうしたらいいんですかね?」
小屋に立て掛けてあった枝を手に、俺はナビ子に目を向ける。ナビ子はフンスとばかりに鼻を鳴らすと、
「《井戸》は《石材》を消費することで作ることが出来ます。現実のように水源を探し、地面を掘り下げる必要はなく、井戸の囲いを設置することで使用可能になります」
「不思議パワーで水が湧き出てくる訳ですか。ということは、一度作ってしまえば枯渇することもありませんか?」
「はい。御心配なく」
「じゃあルシンダさんにはその作成も……あ、《石材》足りるかな」
以前採取した《石材》は、ルシンダの活躍により大半を消費している。村が所有する資材一覧を覗いてみるも、やはり残部は心許ない。《石臼》ならまだしも、《井戸》の作成に足る資材は保有していなかった。
「じゃあおれ、作業に戻るね」
ひらひらと手を振って、イアンが《なめし台》の方へと向かう。
生皮の状態では、中間素材として使用できない。保存できるよう、また今後の加工を容易にする為、剥ぎ取った皮はなめしておく必要があるのだ。
部屋の中から「わたくしも作業見たい!」と悲鳴が聞こえたが、俺は無視しておくことにした。
「あの……今のうちに《石材》、集めておきます。在庫、もうないですよね?」
「ありがとうございます、クローイさん。じゃあ……そうですね、サミュエル君を連れて行ってください」
「一人で大丈夫です」
「念のためです。何があるか分かりませんから。――サミュエル君もいいですね?」
隻眼の少年に目を向けると、彼は迷う素振りを見せた。
丸一日持ち場を離れるという訳ではないのだ。たった数時間あるいは数分、村の護衛からクローイの警護に任を移す、ただそれだけである。
「お願いします」
「……分かった」
それだけ言うと、サミュエルは踵を返す。
彼の腰には石製の剣が差さっている。襲撃時に携えていた金属製の得物よりも、幾分かグレードを落とした品である。
少々心許ない出来であるが、それゆえか、少年の背は少し強張っていた。
0
あなたにおすすめの小説

おっさん武闘家、幼女の教え子達と十年後に再会、実はそれぞれ炎・氷・雷の精霊の王女だった彼女達に言い寄られつつ世界を救い英雄になってしまう
お餅ミトコンドリア
ファンタジー
パーチ、三十五歳。五歳の時から三十年間修行してきた武闘家。
だが、全くの無名。
彼は、とある村で武闘家の道場を経営しており、〝拳を使った戦い方〟を弟子たちに教えている。
若い時には「冒険者になって、有名になるんだ!」などと大きな夢を持っていたものだが、自分の道場に来る若者たちが全員〝天才〟で、自分との才能の差を感じて、もう諦めてしまった。
弟子たちとの、のんびりとした穏やかな日々。
独身の彼は、そんな彼ら彼女らのことを〝家族〟のように感じており、「こんな毎日も悪くない」と思っていた。
が、ある日。
「お久しぶりです、師匠!」
絶世の美少女が家を訪れた。
彼女は、十年前に、他の二人の幼い少女と一緒に山の中で獣(とパーチは思い込んでいるが、実はモンスター)に襲われていたところをパーチが助けて、その場で数時間ほど稽古をつけて、自分たちだけで戦える力をつけさせた、という女の子だった。
「私は今、アイスブラット王国の〝守護精霊〟をやっていまして」
精霊を自称する彼女は、「ちょ、ちょっと待ってくれ」と混乱するパーチに構わず、ニッコリ笑いながら畳み掛ける。
「そこで師匠には、私たちと一緒に〝魔王〟を倒して欲しいんです!」
これは、〝弟子たちがあっと言う間に強くなるのは、師匠である自分の特殊な力ゆえ〟であることに気付かず、〝実は最強の実力を持っている〟ことにも全く気付いていない男が、〝実は精霊だった美少女たち〟と再会し、言い寄られ、弟子たちに愛され、弟子以外の者たちからも尊敬され、世界を救って英雄になってしまう物語。
(※第18回ファンタジー小説大賞に参加しています。
もし宜しければ【お気に入り登録】で応援して頂けましたら嬉しいです!
何卒宜しくお願いいたします!)

追放勇者の土壌改良は万物進化の神スキル!女神に溺愛され悪役令嬢と最強国家を築く
黒崎隼人
ファンタジー
勇者として召喚されたリオンに与えられたのは、外れスキル【土壌改良】。役立たずの烙印を押され、王国から追放されてしまう。時を同じくして、根も葉もない罪で断罪された「悪役令嬢」イザベラもまた、全てを失った。
しかし、辺境の地で死にかけたリオンは知る。自身のスキルが、実は物質の構造を根源から組み替え、万物を進化させる神の御業【万物改良】であったことを!
石ころを最高純度の魔石に、ただのクワを伝説級の戦斧に、荒れ地を豊かな楽園に――。
これは、理不尽に全てを奪われた男が、同じ傷を持つ気高き元悪役令嬢と出会い、過保護な女神様に見守られながら、無自覚に世界を改良し、自分たちだけの理想郷を創り上げ、やがて世界を救うに至る、壮大な逆転成り上がりファンタジー!

『異世界庭付き一戸建て』を相続した仲良し兄妹は今までの不幸にサヨナラしてスローライフを満喫できる、はず?
釈 余白(しやく)
ファンタジー
毒親の父が不慮の事故で死亡したことで最後の肉親を失い、残された高校生の小村雷人(こむら らいと)と小学生の真琴(まこと)の兄妹が聞かされたのは、父が家を担保に金を借りていたという絶望の事実だった。慣れ親しんだ自宅から早々の退去が必要となった二人は家の中で金目の物を探す。
その結果見つかったのは、僅かな現金に空の預金通帳といくつかの宝飾品、そして家の権利書と見知らぬ文字で書かれた書類くらいだった。謎の書類には祖父のサインが記されていたが内容は読めず、頼みの綱は挟まれていた弁護士の名刺だけだ。
最後の希望とも言える名刺の電話番号へ連絡した二人は、やってきた弁護士から契約書の内容を聞かされ唖然とする。それは祖父が遺産として残した『異世界トラス』にある土地と建物を孫へ渡すというものだった。もちろん現地へ行かなければ遺産は受け取れないが。兄妹には他に頼れるものがなく、思い切って異世界へと赴き新生活をスタートさせるのだった。
連載時、HOT 1位ありがとうございました!
その他、多数投稿しています。
こちらもよろしくお願いします!
https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/398438394
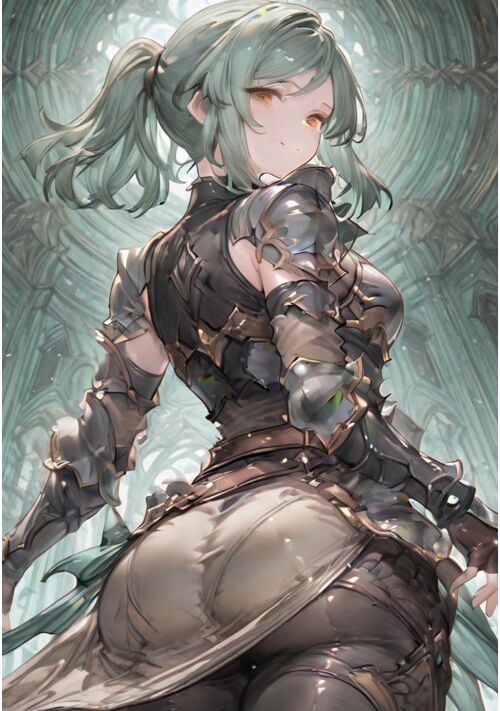
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――


お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

死んだはずの貴族、内政スキルでひっくり返す〜辺境村から始める復讐譚〜
のらねこ吟醸
ファンタジー
帝国の粛清で家族を失い、“死んだことにされた”名門貴族の青年は、
偽りの名を与えられ、最果ての辺境村へと送り込まれた。
水も農具も未来もない、限界集落で彼が手にしたのは――
古代遺跡の力と、“俺にだけ見える内政スキル”。
村を立て直し、仲間と絆を築きながら、
やがて帝国の陰謀に迫り、家を滅ぼした仇と対峙する。
辺境から始まる、ちょっぴりほのぼの(?)な村興しと、
静かに進む策略と復讐の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















