36 / 55
第5章 カゲイシオオカミの急襲
36
しおりを挟む
ミチはカゲイシオオカミを見上げた。
カゲイシオオカミは何も言わず、ただ顎をしゃくってみせた。どうもこれはナナカマドウシに話のつづきをうながすしぐさらしい。その通りに、ナナカマドウシは話をつづけた。
「狭間嘉右衛門の誘導によって、ミマネイケは池に投げられる願いをかなえることが人をまねることだと考えるようになったのだよ。するとそれが重なるにつれて変化が起きた。ミマネイケがゆっくりと変わっていったのだ」
「あっ」
声をあげた者がいた。快斗だ。
「池が小さくなったんだっ。あの池、前はもっと深かったっ」
「わかるのか、快斗」
「いまの池って屋根つき橋の半分くらいから先にあるだろ。あれは、おれが幼稚園のころはもっと水があった、だんだん減ってるっ」
「きみのいう通りだ。つけ加えると、きみの生まれる前には、池はもっとずっと大きかった。おかしいと感じないかね、橋の途中から水があることを。はじめにあの屋根つき橋をかけたときには橋のすぐたもとまで水がたゆたっていたのだよ」
ミチは外を見た。
ナナカマドウシの姿を見たかった。だけど床に倒れたミチの目に見えるのは壊れた窓の向こうに見える木の幹だけだった。それだってナナカマドウシにちがいないが、そうしてみるとただの木の幹に見えた。
カゲイシオオカミが低くうなり、それから言葉を発した。
「お前の話は奇妙だぞ、ナナカマドウシ。あの石はほとんど残っていないはずだ」
「ひごめ石のことかね」
「そうだ、人間どもがそう呼ぶ、あの赤い石だ。あの石は嘉右衛門が採りつくした。いまでもときどきは欠片が土にまぎれていることがある、だがそれだけだ。人間の子らは人間の道具で文字を書いているはずだ。あの石ではない」
(なんの話だろう、ひごめ石がどうしたんだ)
ミチはアヤたちの会話に必死で耳を傾けた。
なんだかすごく重要な話を耳にしているような気がしたからだ。
ナナカマドウシがこたえた。
「そう、きみの言うとおり、人の子らはひごめ石を使って文字を書くわけではない。赤い文字にはちがいないが、それだけだ」
「それなのにミマネイケに対して効力があるというのか。書かれたものが我らに力を及ぼすのは、あの石があってこそだ。あの石で書かれたものだけが、こちらの世界と我らをつなぐ、それは今も昔もおなじはず」
ミチは思わずアッと声をあげそうになって、だけどどうにかそれをこらえた。津江さんがミチの額に書いたまじないを思いだした。
(あれはひごめ石だったんだ、石の欠片。いまカゲイシオオカミが言った、ときどき石の欠片が土にまぎれているって。まじないに使ったのがひごめ石だったから、効きめがあったんだ)
どうやら、ひごめ石はただ単に美しくて高価な顔料になるだけでは、ないようだ。アヤたちとこの世界をつなぐはたらきや、アヤたちになんらかの影響をおよぼす力があるようだった。
ナナカマドウシの考え深い声が周りに、しずかにひびいた。
「きみが効力というのは、それを受ける者の意思にかかわらず及ぶ力のことだろう。だがミマネイケは自らが望んで人の子が書く文字を読んだ。おそらく、だからこそ、ひごめ石で書いた文字かどうかは関係ないのだよ。もっといえばミマネイケが読んだのは文字ですらなく、子どもの願いそのものかもしれない、私はそう考える」
その声がゆっくりとあたりに満ちると、やがてミチの体の上で低い笑い声がした。
「フ、フフ、ククク」
声とともにカゲイシオオカミがかすかにゆれた。
黒い石のかたまりが、わらっていた。
「おもしろい、実におもしろい話だ。」
「私にはこの話のどこがそれほどおもしろいのか、わからない」
「うすのろな貴様にとってはそうだろうとも」
カゲイシオオカミが前足をミチの喉からおろした。そして言った。
「かつてないことが起きている、つまりはそうなのだな。」
圧迫感から解放されてミチは息をついだ。カゲイシオオカミがくいっと顎でミチに指図をした。
「起きろ、子ども」
ミチはその通りにした。
体を起こしたら、自分がこきざみにふるえていることに初めて気づいた。
雨のなかを快斗と歩いたのは、ほんの三十分くらい前のことだ。
それなのにそのときといまはまるでべつの、まったくつながりのない時間のように感じた。何もかもが変わってしまった。
カゲイシオオカミがミチに向かって命令した。
「子ども、立て。外へ出ろ。お前はおれの前を歩け。逃げられると思うな、おれから逃げようとしたら八つ裂きにしてやるからな」
もしもカゲイシオオカミが本気でそうしようと思えば、それはとても簡単だろう、ミチはそう思った。ミチの体のふるえは途切れることなくつづいた。
「ミチ、おれも一緒に行くっ」
快斗の声がした。ミチは快斗を見た。快斗は口をへの字に曲げて、ミチを見つめていた。快斗の体もこきざみにふるえていた。こわいのだ、とミチは思った。明るくて元気な快斗がこわがっている。そしてそれは無理もないのだ。
ミチと快斗はとなりの部屋へ移動した。
学習室はぐちゃぐちゃになっていた。
三頭のカゲイシオオカミが乱入したために図書室の机や椅子、それに木の扉が学習室へなだれこみ、それが学習室の机や椅子をなぎ倒し、見わたすかぎりすべての机と椅子が部屋の端に寄っていた。
そして机の向こうに人が倒れていた。
ミチはハッとした。
(机のなだれに巻きこまれたんだ)
ミチは顔から血の気が引くのを感じた。
黒い靴と灰色の生地が見えた。山橋という男だ。
山橋には悪いがミチはホッとした。これが他の、みれや紗や砂森だったら――だがそう思った直後、山橋の体のさらに奥に砂森の横顔が見えて、ミチは今度こそ生きた心地が失せた。
砂森は膝を床についているようだ。
下を見つめている。
「砂森さん」
ミチの声はかすれた。
その声に反応して砂森が顔を上げ、ミチを見た。そして言った。
「根島先生が、みれちゃんたちをかばって、いま意識がありません。救急車を呼びましたが、時間がかかりそうです」
砂森は一言一言をことさらゆっくりと話した。
そうすることで自分自身を落ちつかせたいかのようだった。
ミチは短くたずねた。
「どうして。」
「この大雨のために先に他へ出動している、という説明でした。どうも、ひごめの数か所で同時に崖崩れが発生したらしい。……今日はなんて日だ、そう思いますよ」
ミチは気づいた。
砂森はミチを見ている、そしてそれだけだ。その態度はまるでカゲイシオオカミがこの場に存在しないかのようだった。
ミチはあらためて思った。
(砂森さんには本当に見えないんだ)
カゲイシオオカミがミチをうながした。
「進め、子ども」
ミチはとなりにいる快斗の腕を引くと砂森に声をかけた。
「砂森さん、快斗も紗ちゃんたちと一緒に」
「バカ、ミチ、お前なに言ってるんだ。おれミチと一緒に行くってば!」
「だめだ、危ないから」
「だからだろっ、ミチだけ危ない目に合うなんてもっとダメだよっ」
こんなときなのに、ミチは(快斗はいいやつだな)と思った。こんなときなので、それだけで泣きそうな気分になった。日常が一瞬で吹き飛ばされぐちゃぐちゃになり得体の知れないことに巻きこまれてしまったのに。
昨日の津江さんたちの話をきいていないぶん、快斗のほうがミチよりずっとわけがわからないはずだ。それなのにミチを心配している快斗。
カゲイシオオカミは何も言わず、ただ顎をしゃくってみせた。どうもこれはナナカマドウシに話のつづきをうながすしぐさらしい。その通りに、ナナカマドウシは話をつづけた。
「狭間嘉右衛門の誘導によって、ミマネイケは池に投げられる願いをかなえることが人をまねることだと考えるようになったのだよ。するとそれが重なるにつれて変化が起きた。ミマネイケがゆっくりと変わっていったのだ」
「あっ」
声をあげた者がいた。快斗だ。
「池が小さくなったんだっ。あの池、前はもっと深かったっ」
「わかるのか、快斗」
「いまの池って屋根つき橋の半分くらいから先にあるだろ。あれは、おれが幼稚園のころはもっと水があった、だんだん減ってるっ」
「きみのいう通りだ。つけ加えると、きみの生まれる前には、池はもっとずっと大きかった。おかしいと感じないかね、橋の途中から水があることを。はじめにあの屋根つき橋をかけたときには橋のすぐたもとまで水がたゆたっていたのだよ」
ミチは外を見た。
ナナカマドウシの姿を見たかった。だけど床に倒れたミチの目に見えるのは壊れた窓の向こうに見える木の幹だけだった。それだってナナカマドウシにちがいないが、そうしてみるとただの木の幹に見えた。
カゲイシオオカミが低くうなり、それから言葉を発した。
「お前の話は奇妙だぞ、ナナカマドウシ。あの石はほとんど残っていないはずだ」
「ひごめ石のことかね」
「そうだ、人間どもがそう呼ぶ、あの赤い石だ。あの石は嘉右衛門が採りつくした。いまでもときどきは欠片が土にまぎれていることがある、だがそれだけだ。人間の子らは人間の道具で文字を書いているはずだ。あの石ではない」
(なんの話だろう、ひごめ石がどうしたんだ)
ミチはアヤたちの会話に必死で耳を傾けた。
なんだかすごく重要な話を耳にしているような気がしたからだ。
ナナカマドウシがこたえた。
「そう、きみの言うとおり、人の子らはひごめ石を使って文字を書くわけではない。赤い文字にはちがいないが、それだけだ」
「それなのにミマネイケに対して効力があるというのか。書かれたものが我らに力を及ぼすのは、あの石があってこそだ。あの石で書かれたものだけが、こちらの世界と我らをつなぐ、それは今も昔もおなじはず」
ミチは思わずアッと声をあげそうになって、だけどどうにかそれをこらえた。津江さんがミチの額に書いたまじないを思いだした。
(あれはひごめ石だったんだ、石の欠片。いまカゲイシオオカミが言った、ときどき石の欠片が土にまぎれているって。まじないに使ったのがひごめ石だったから、効きめがあったんだ)
どうやら、ひごめ石はただ単に美しくて高価な顔料になるだけでは、ないようだ。アヤたちとこの世界をつなぐはたらきや、アヤたちになんらかの影響をおよぼす力があるようだった。
ナナカマドウシの考え深い声が周りに、しずかにひびいた。
「きみが効力というのは、それを受ける者の意思にかかわらず及ぶ力のことだろう。だがミマネイケは自らが望んで人の子が書く文字を読んだ。おそらく、だからこそ、ひごめ石で書いた文字かどうかは関係ないのだよ。もっといえばミマネイケが読んだのは文字ですらなく、子どもの願いそのものかもしれない、私はそう考える」
その声がゆっくりとあたりに満ちると、やがてミチの体の上で低い笑い声がした。
「フ、フフ、ククク」
声とともにカゲイシオオカミがかすかにゆれた。
黒い石のかたまりが、わらっていた。
「おもしろい、実におもしろい話だ。」
「私にはこの話のどこがそれほどおもしろいのか、わからない」
「うすのろな貴様にとってはそうだろうとも」
カゲイシオオカミが前足をミチの喉からおろした。そして言った。
「かつてないことが起きている、つまりはそうなのだな。」
圧迫感から解放されてミチは息をついだ。カゲイシオオカミがくいっと顎でミチに指図をした。
「起きろ、子ども」
ミチはその通りにした。
体を起こしたら、自分がこきざみにふるえていることに初めて気づいた。
雨のなかを快斗と歩いたのは、ほんの三十分くらい前のことだ。
それなのにそのときといまはまるでべつの、まったくつながりのない時間のように感じた。何もかもが変わってしまった。
カゲイシオオカミがミチに向かって命令した。
「子ども、立て。外へ出ろ。お前はおれの前を歩け。逃げられると思うな、おれから逃げようとしたら八つ裂きにしてやるからな」
もしもカゲイシオオカミが本気でそうしようと思えば、それはとても簡単だろう、ミチはそう思った。ミチの体のふるえは途切れることなくつづいた。
「ミチ、おれも一緒に行くっ」
快斗の声がした。ミチは快斗を見た。快斗は口をへの字に曲げて、ミチを見つめていた。快斗の体もこきざみにふるえていた。こわいのだ、とミチは思った。明るくて元気な快斗がこわがっている。そしてそれは無理もないのだ。
ミチと快斗はとなりの部屋へ移動した。
学習室はぐちゃぐちゃになっていた。
三頭のカゲイシオオカミが乱入したために図書室の机や椅子、それに木の扉が学習室へなだれこみ、それが学習室の机や椅子をなぎ倒し、見わたすかぎりすべての机と椅子が部屋の端に寄っていた。
そして机の向こうに人が倒れていた。
ミチはハッとした。
(机のなだれに巻きこまれたんだ)
ミチは顔から血の気が引くのを感じた。
黒い靴と灰色の生地が見えた。山橋という男だ。
山橋には悪いがミチはホッとした。これが他の、みれや紗や砂森だったら――だがそう思った直後、山橋の体のさらに奥に砂森の横顔が見えて、ミチは今度こそ生きた心地が失せた。
砂森は膝を床についているようだ。
下を見つめている。
「砂森さん」
ミチの声はかすれた。
その声に反応して砂森が顔を上げ、ミチを見た。そして言った。
「根島先生が、みれちゃんたちをかばって、いま意識がありません。救急車を呼びましたが、時間がかかりそうです」
砂森は一言一言をことさらゆっくりと話した。
そうすることで自分自身を落ちつかせたいかのようだった。
ミチは短くたずねた。
「どうして。」
「この大雨のために先に他へ出動している、という説明でした。どうも、ひごめの数か所で同時に崖崩れが発生したらしい。……今日はなんて日だ、そう思いますよ」
ミチは気づいた。
砂森はミチを見ている、そしてそれだけだ。その態度はまるでカゲイシオオカミがこの場に存在しないかのようだった。
ミチはあらためて思った。
(砂森さんには本当に見えないんだ)
カゲイシオオカミがミチをうながした。
「進め、子ども」
ミチはとなりにいる快斗の腕を引くと砂森に声をかけた。
「砂森さん、快斗も紗ちゃんたちと一緒に」
「バカ、ミチ、お前なに言ってるんだ。おれミチと一緒に行くってば!」
「だめだ、危ないから」
「だからだろっ、ミチだけ危ない目に合うなんてもっとダメだよっ」
こんなときなのに、ミチは(快斗はいいやつだな)と思った。こんなときなので、それだけで泣きそうな気分になった。日常が一瞬で吹き飛ばされぐちゃぐちゃになり得体の知れないことに巻きこまれてしまったのに。
昨日の津江さんたちの話をきいていないぶん、快斗のほうがミチよりずっとわけがわからないはずだ。それなのにミチを心配している快斗。
0
あなたにおすすめの小説

大人で子供な師匠のことを、つい甘やかす僕がいる。
takemot
児童書・童話
薬草を採りに入った森で、魔獣に襲われた僕。そんな僕を助けてくれたのは、一人の女性。胸のあたりまである長い白銀色の髪。ルビーのように綺麗な赤い瞳。身にまとうのは、真っ黒なローブ。彼女は、僕にいきなりこう尋ねました。
「シチュー作れる?」
…………へ?
彼女の正体は、『森の魔女』。
誰もが崇拝したくなるような魔女。とんでもない力を持っている魔女。魔獣がわんさか生息する森を牛耳っている魔女。
そんな噂を聞いて、目を輝かせていた時代が僕にもありました。
どういうわけか、僕は彼女の弟子になったのですが……。
「うう。早くして。お腹がすいて死にそうなんだよ」
「あ、さっきよりミルク多めで!」
「今日はダラダラするって決めてたから!」
はあ……。師匠、もっとしっかりしてくださいよ。
子供っぽい師匠。そんな師匠に、今日も僕は振り回されっぱなし。
でも時折、大人っぽい師匠がそこにいて……。
師匠と弟子がおりなす不思議な物語。師匠が子供っぽい理由とは。そして、大人っぽい師匠の壮絶な過去とは。
表紙のイラストは大崎あむさん(https://twitter.com/oosakiamu)からいただきました。

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

少年騎士
克全
児童書・童話
「第1回きずな児童書大賞参加作」ポーウィス王国という辺境の小国には、12歳になるとダンジョンか魔境で一定の強さになるまで自分を鍛えなければいけないと言う全国民に対する法律があった。周囲の小国群の中で生き残るため、小国を狙う大国から自国を守るために作られた法律、義務だった。領地持ち騎士家の嫡男ハリー・グリフィスも、その義務に従い1人王都にあるダンジョンに向かって村をでた。だが、両親祖父母の計らいで平民の幼馴染2人も一緒に12歳の義務に同行する事になった。将来救国の英雄となるハリーの物語が始まった。
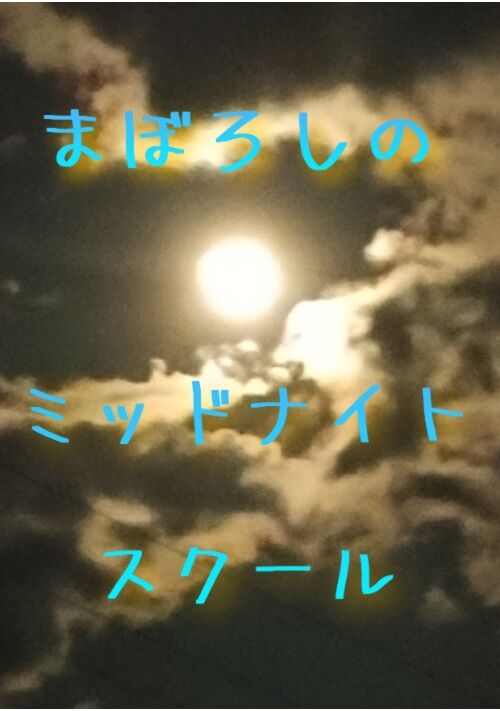
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

ナナの初めてのお料理
いぬぬっこ
児童書・童話
ナナは七歳の女の子。
ある日、ナナはお母さんが仕事から帰ってくるのを待っていました。
けれど、お母さんが帰ってくる前に、ナナのお腹はペコペコになってしまいました。
もう我慢できそうにありません。
だというのに、冷蔵庫の中には、すぐ食べれるものがありません。
ーーそうだ、お母さんのマネをして、自分で作ろう!
ナナは、初めて自分一人で料理をすることを決めたのでした。
これは、ある日のナナのお留守番の様子です。

少年イシュタと夜空の少女 ~死なずの村 エリュシラーナ~
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
イシュタは病の妹のため、誰も死なない村・エリュシラーナへと旅立つ。そして、夜空のような美しい少女・フェルルと出会い……
「昔話をしてあげるわ――」
フェルルの口から語られる、村に隠された秘密とは……?
☆…☆…☆
※ 大人でも楽しめる児童文学として書きました。明確な記述は避けておりますので、大人になって読み返してみると、また違った風に感じられる……そんな物語かもしれません……♪
※ イラストは、親友の朝美智晴さまに描いていただきました。


未来スコープ ―キスした相手がわからないって、どういうこと!?―
米田悠由
児童書・童話
「あのね、すごいもの見つけちゃったの!」
平凡な女子高生・月島彩奈が偶然手にした謎の道具「未来スコープ」。
それは、未来を“見る”だけでなく、“課題を通して導く”装置だった。
恋の予感、見知らぬ男子とのキス、そして次々に提示される不可解な課題──
彩奈は、未来スコープを通して、自分の運命に深く関わる人物と出会っていく。
未来スコープが映し出すのは、甘いだけではない未来。
誰かを想う気持ち、誰かに選ばれない痛み、そしてそれでも誰かを支えたいという願い。
夢と現実が交錯する中で、彩奈は「自分の気持ちを信じること」の意味を知っていく。
この物語は、恋と選択、そしてすれ違う想いの中で、自分の軸を見つけていく少女たちの記録です。
感情の揺らぎと、未来への確信が交錯するSFラブストーリー、シリーズ第2作。
読後、きっと「誰かを想うとはどういうことか」を考えたくなる一冊です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















