47 / 55
第6章 願いごとは赤い文字で
47
しおりを挟む
ミチは耳をすませた。
はじめに聞こえたのはビョウッという空気のはげしく流れる音だ。
出どころはすぐにわかった。
赤い眼球だ。
まるで、ありえないような特大の掃除機が動いてゴミを吸い取るようにして、古い紙を巻き上げている。
(この音がどうしたというんだろう)
とミチは内心でいぶかしく思った。
それからようやく気づいた。
水の音がする。
ジャバジャバ、ジャバジャバ、という、水が流れる音。
津江さんの声も聞こえた。
「地面がぬれてきたぞな」
ミチはハッとして地面を見おろした。古い紙きれが一枚また一枚とはがれ、いつの間にか地肌がずいぶんあらわになってきたのが見えた。その地肌の色がやけに黒々としているのも見えた。津江さんのいうとおりだ。
進一郎が言った。
「水が入ってきたんだ」
ミチは思わずキョロキョロとあたりを見回した。一体どこから水が入ってきたのか知りたかったのだ。地面近くから水が湧いているのを見つけ、ミチは指さした。
「あそこからです」
「それだけじゃない、あっちにも――他にもだ」
進一郎の言う通りだった。
ジャバジャバ、ジャバジャバ、という音は何か所かから聞こえてくるようだった。
外が大雨だとミチは思いだした。
わずかな距離を歩いただけでシャツや靴下までずぶぬれにしたあのはげしい雨は、おそらくまだ降り続いているはずだ。そしてミチたちは書庫のあった場所の奥、古い墳からずっと下ってここまで来たのだ。ここはひごめ館のなかでも低い場所だ。
「雨がここへ流れこんできたってことですか?」
ミチが進一郎にたずねるのと、ミチの鼻先をバサッと紙きれが飛んでいくのが同時だった。さっきまでよりも水を吸って重くなった紙が、その重さにもかかわらず赤い眼球に引き寄せられたのだ。
ミチは思わず頭上を見上げた。
そしてギョッとした。
引き寄せられた紙がひとかたまりにかたまりつつあった。
古ぼけた、黄ばんだ、だけど本は白かった紙。
茶ばんだ文字はぜんぶ赤い文字だった。
変色した紙と紙に書かれた文字が一つに集まって、丸いかたちを作りかけていた。
「もしかして、目」
ミチはつぶやいた。
進一郎にはそのつぶやきが聞こえたようだ。進一郎がまじまじとミチを見つめた。が、ミチはそれに気づかないまま口だけ動かした。
ミチの口からひとりでに言葉がついて出た。
「目を作ろうとしている――」
洞穴のなか、空中で、乾いたままの紙、水を含んだ紙、宙に舞ったたくさんの紙がいくつも球体になりかけていた。
どうやってか茶ばんだ文字の部分がくしゃりと固まった。
まるで赤い目の虹彩のように。
それはひどくお粗末であったけれど、赤い眼球に似た形になりつつあった。
「まね よ」
声がとどろいた。
「われ を まね よ」
(何を言っているんだ)
はじめミチはその言葉の意味がまったくわからなかった。
「われ は アヤ」
力強いとどろきだった。
「アヤ の まま の アヤ かつてなき アヤ」
「ん、あれ?」
ミチは一瞬、自分の耳がおかしくなったのかと思った。
知らず知らずのうちに耳をそばだて、集中してその声を聞こうとした。
声はつづいた。
「あまねく もの ひとつの もの であり すべての もの」
とどろく声にべつの声が重なって聞こえる。
少なくともミチの耳にはそう聞こえた。ミチは混乱した。
(なんだ、この声は。だれの声なんだろう?)
「かたちなき もの また かたちある もの」
赤い眼球のとどろく声に重なる声は、一つではなかった。
二つ、三つ、四つ――ミチの耳には次第に重なりが増していくように聞こえた。
だんだん数が増えていく。
声はいつの間にか唱和になった。大勢の声だ。
「だれより も つよく ひるいなき もの」
「ちから」
「ちから を あたえる」
「だれより も つよく なる」
いつの間にかたくさんの声がおなじ一つの言葉を唱和していた。
(この声は一体どこから聞こえてくるんだろう?)
ミチは集中して耳をはたらかせた。
「まねよ」
「まねよ まねびよ」
(あっ)
ミチはハッとした。
声の聞こえる場所がわかったように感じて自分の真上を見上げた。
そして大きく目を見開いた。
「なんだ、これ……」
洞穴の頭上に影が生えていた。
そう、『生えた』としかいいようがない。
黒々とした染みのようなものが、頭上のあちこちの岩に生まれつつあった。
いくつも、いくつもだ。
染みのようなものはミチが見ている前で一つ一つじわじわと広がり、しだいに形をなした。
あるものはかぎ爪に見えた。あるものは魚の形になりかけていた。あるものは翼だった。また、あるものは影のなかに鱗が見えた。蛇のようだった。
細い足がたくさん生えているものもあった。
ミチは墳の壁画をはじめて見たときのことを思いだした。(この絵は一体だれが描いたんだろう?)と首をかしげたことを。
そのときにはわからなかったことの答えがいまミチの眼前に繰り広げられていく。
壁画は人の描いたものではなかったのだ。
いや、絵でさえない。
津江さんの声が聞こえた。
「あれはアヤ――紋え。」
ミチはハッとして津江さんを見た。津江さんもミチとおなじように頭上を、黒々とした影のような、絵のようなそれらを、ひたりと見すえていた。
「たくさんのアヤが元いた世界からやって来つつあるぞ。こちらで生まれようとしておるえ」
「生まれる。アヤが」
ミチは津江さんの言葉をオウム返しにつぶやいた。この洞穴に広がっていく光景に圧倒されて他に言葉が出なかった。ミチは頭上へ視線をもどした。そしてあることに気づいた。
しだいに形を明瞭に整えながら、黒々とした影にはやがて二つ、あるいは四つと、影のなかに穴があきはじめた。
(穴、ううん、ちがう、穴じゃない。あれは――目だ)
影絵のなかの空洞のような目の部分に、やがて色がにじみはじめた。
赤い色だ。
「まねびよ われ を」
ミチはふと、前日に聞いたさまざまな言葉を思いだした。ナナカマドウシの言葉、それを聞いた進一郎の言葉、それに津江さんの言葉。
『私たちアヤはこの世界のものをまねる』
『まねることは増えることだ』
『増えることは進むことだ』
『まねると――それが更新されるってことか』
『まねにアヤも人もないぞえ』
「まねれば ちから が て に はいる」
「あっ……」
ミチは声をあげ、しかしその先をつづけることができずに絶句した。
赤い眼球がなにをしようとしているか、ミチはわかった気がした。
そしてミチとほとんど同時に津江さんもそのことに思い当たったようだ。
津江さんの声がミチの耳に届いた。
「まさか、寄主――お前さまは寄主になろうというのか。自らを寄主として、あちらからアヤたちを呼び入れる気かえ」
ざわり、と何かがうごめく気配がした。ざわり、ざわり、ざわり。
それは生きものの気配、たとえじっとしても否応なく生じる気配だ。呼吸をして、わずかにでも動き、目や耳をそばだてる、音よりもかすかだけれど、たしかに感じる気配。
その気配が洞穴に充満しはじめた。
昨日聞いた津江さんの言葉がミチの耳をかすめた。
『あれは『とても悪いもの』をまねて生まれた者ぞな――』
『悪いものがまねると、いっそう悪いものになる――』
ミマネイケをまねた赤い眼球、アヤをまねたアヤ。
そのアヤが実体化し、新たなアヤに自身をまねることを求めている。
ななかまどの大木をまねながら、元いた世界の姿がなかば残ったナナカマドウシのように、黒い岩をまねながら、こちらも元の姿が残ったカゲイシオオカミのように、赤い眼球をまねながら、元の姿の残るアヤが、たくさん生まれようとしていた
はじめに聞こえたのはビョウッという空気のはげしく流れる音だ。
出どころはすぐにわかった。
赤い眼球だ。
まるで、ありえないような特大の掃除機が動いてゴミを吸い取るようにして、古い紙を巻き上げている。
(この音がどうしたというんだろう)
とミチは内心でいぶかしく思った。
それからようやく気づいた。
水の音がする。
ジャバジャバ、ジャバジャバ、という、水が流れる音。
津江さんの声も聞こえた。
「地面がぬれてきたぞな」
ミチはハッとして地面を見おろした。古い紙きれが一枚また一枚とはがれ、いつの間にか地肌がずいぶんあらわになってきたのが見えた。その地肌の色がやけに黒々としているのも見えた。津江さんのいうとおりだ。
進一郎が言った。
「水が入ってきたんだ」
ミチは思わずキョロキョロとあたりを見回した。一体どこから水が入ってきたのか知りたかったのだ。地面近くから水が湧いているのを見つけ、ミチは指さした。
「あそこからです」
「それだけじゃない、あっちにも――他にもだ」
進一郎の言う通りだった。
ジャバジャバ、ジャバジャバ、という音は何か所かから聞こえてくるようだった。
外が大雨だとミチは思いだした。
わずかな距離を歩いただけでシャツや靴下までずぶぬれにしたあのはげしい雨は、おそらくまだ降り続いているはずだ。そしてミチたちは書庫のあった場所の奥、古い墳からずっと下ってここまで来たのだ。ここはひごめ館のなかでも低い場所だ。
「雨がここへ流れこんできたってことですか?」
ミチが進一郎にたずねるのと、ミチの鼻先をバサッと紙きれが飛んでいくのが同時だった。さっきまでよりも水を吸って重くなった紙が、その重さにもかかわらず赤い眼球に引き寄せられたのだ。
ミチは思わず頭上を見上げた。
そしてギョッとした。
引き寄せられた紙がひとかたまりにかたまりつつあった。
古ぼけた、黄ばんだ、だけど本は白かった紙。
茶ばんだ文字はぜんぶ赤い文字だった。
変色した紙と紙に書かれた文字が一つに集まって、丸いかたちを作りかけていた。
「もしかして、目」
ミチはつぶやいた。
進一郎にはそのつぶやきが聞こえたようだ。進一郎がまじまじとミチを見つめた。が、ミチはそれに気づかないまま口だけ動かした。
ミチの口からひとりでに言葉がついて出た。
「目を作ろうとしている――」
洞穴のなか、空中で、乾いたままの紙、水を含んだ紙、宙に舞ったたくさんの紙がいくつも球体になりかけていた。
どうやってか茶ばんだ文字の部分がくしゃりと固まった。
まるで赤い目の虹彩のように。
それはひどくお粗末であったけれど、赤い眼球に似た形になりつつあった。
「まね よ」
声がとどろいた。
「われ を まね よ」
(何を言っているんだ)
はじめミチはその言葉の意味がまったくわからなかった。
「われ は アヤ」
力強いとどろきだった。
「アヤ の まま の アヤ かつてなき アヤ」
「ん、あれ?」
ミチは一瞬、自分の耳がおかしくなったのかと思った。
知らず知らずのうちに耳をそばだて、集中してその声を聞こうとした。
声はつづいた。
「あまねく もの ひとつの もの であり すべての もの」
とどろく声にべつの声が重なって聞こえる。
少なくともミチの耳にはそう聞こえた。ミチは混乱した。
(なんだ、この声は。だれの声なんだろう?)
「かたちなき もの また かたちある もの」
赤い眼球のとどろく声に重なる声は、一つではなかった。
二つ、三つ、四つ――ミチの耳には次第に重なりが増していくように聞こえた。
だんだん数が増えていく。
声はいつの間にか唱和になった。大勢の声だ。
「だれより も つよく ひるいなき もの」
「ちから」
「ちから を あたえる」
「だれより も つよく なる」
いつの間にかたくさんの声がおなじ一つの言葉を唱和していた。
(この声は一体どこから聞こえてくるんだろう?)
ミチは集中して耳をはたらかせた。
「まねよ」
「まねよ まねびよ」
(あっ)
ミチはハッとした。
声の聞こえる場所がわかったように感じて自分の真上を見上げた。
そして大きく目を見開いた。
「なんだ、これ……」
洞穴の頭上に影が生えていた。
そう、『生えた』としかいいようがない。
黒々とした染みのようなものが、頭上のあちこちの岩に生まれつつあった。
いくつも、いくつもだ。
染みのようなものはミチが見ている前で一つ一つじわじわと広がり、しだいに形をなした。
あるものはかぎ爪に見えた。あるものは魚の形になりかけていた。あるものは翼だった。また、あるものは影のなかに鱗が見えた。蛇のようだった。
細い足がたくさん生えているものもあった。
ミチは墳の壁画をはじめて見たときのことを思いだした。(この絵は一体だれが描いたんだろう?)と首をかしげたことを。
そのときにはわからなかったことの答えがいまミチの眼前に繰り広げられていく。
壁画は人の描いたものではなかったのだ。
いや、絵でさえない。
津江さんの声が聞こえた。
「あれはアヤ――紋え。」
ミチはハッとして津江さんを見た。津江さんもミチとおなじように頭上を、黒々とした影のような、絵のようなそれらを、ひたりと見すえていた。
「たくさんのアヤが元いた世界からやって来つつあるぞ。こちらで生まれようとしておるえ」
「生まれる。アヤが」
ミチは津江さんの言葉をオウム返しにつぶやいた。この洞穴に広がっていく光景に圧倒されて他に言葉が出なかった。ミチは頭上へ視線をもどした。そしてあることに気づいた。
しだいに形を明瞭に整えながら、黒々とした影にはやがて二つ、あるいは四つと、影のなかに穴があきはじめた。
(穴、ううん、ちがう、穴じゃない。あれは――目だ)
影絵のなかの空洞のような目の部分に、やがて色がにじみはじめた。
赤い色だ。
「まねびよ われ を」
ミチはふと、前日に聞いたさまざまな言葉を思いだした。ナナカマドウシの言葉、それを聞いた進一郎の言葉、それに津江さんの言葉。
『私たちアヤはこの世界のものをまねる』
『まねることは増えることだ』
『増えることは進むことだ』
『まねると――それが更新されるってことか』
『まねにアヤも人もないぞえ』
「まねれば ちから が て に はいる」
「あっ……」
ミチは声をあげ、しかしその先をつづけることができずに絶句した。
赤い眼球がなにをしようとしているか、ミチはわかった気がした。
そしてミチとほとんど同時に津江さんもそのことに思い当たったようだ。
津江さんの声がミチの耳に届いた。
「まさか、寄主――お前さまは寄主になろうというのか。自らを寄主として、あちらからアヤたちを呼び入れる気かえ」
ざわり、と何かがうごめく気配がした。ざわり、ざわり、ざわり。
それは生きものの気配、たとえじっとしても否応なく生じる気配だ。呼吸をして、わずかにでも動き、目や耳をそばだてる、音よりもかすかだけれど、たしかに感じる気配。
その気配が洞穴に充満しはじめた。
昨日聞いた津江さんの言葉がミチの耳をかすめた。
『あれは『とても悪いもの』をまねて生まれた者ぞな――』
『悪いものがまねると、いっそう悪いものになる――』
ミマネイケをまねた赤い眼球、アヤをまねたアヤ。
そのアヤが実体化し、新たなアヤに自身をまねることを求めている。
ななかまどの大木をまねながら、元いた世界の姿がなかば残ったナナカマドウシのように、黒い岩をまねながら、こちらも元の姿が残ったカゲイシオオカミのように、赤い眼球をまねながら、元の姿の残るアヤが、たくさん生まれようとしていた
0
あなたにおすすめの小説

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

アリアさんの幽閉教室
柚月しずく
児童書・童話
この学校には、ある噂が広まっていた。
「黒い手紙が届いたら、それはアリアさんからの招待状」
招かれた人は、夜の学校に閉じ込められて「恐怖の時間」を過ごすことになる……と。
招待状を受け取った人は、アリアさんから絶対に逃れられないらしい。
『恋の以心伝心ゲーム』
私たちならこんなの楽勝!
夜の学校に閉じ込められた杏樹と星七くん。
アリアさんによって開催されたのは以心伝心ゲーム。
心が通じ合っていれば簡単なはずなのに、なぜかうまくいかなくて……??
『呪いの人形』
この人形、何度捨てても戻ってくる
体調が悪くなった陽菜は、原因が突然現れた人形のせいではないかと疑いはじめる。
人形の存在が恐ろしくなって捨てることにするが、ソレはまた家に現れた。
陽菜にずっと付き纏う理由とは――。
『恐怖の鬼ごっこ』
アリアさんに招待されたのは、美亜、梨々花、優斗。小さい頃から一緒にいる幼馴染の3人。
突如アリアさんに捕まってはいけない鬼ごっこがはじまるが、美亜が置いて行かれてしまう。
仲良し3人組の幼馴染に一体何があったのか。生き残るのは一体誰――?
『招かれざる人』
新聞部の七緒は、アリアさんの記事を書こうと自ら夜の学校に忍び込む。
アリアさんが見つからず意気消沈する中、代わりに現れたのは同じ新聞部の萌香だった。
強がっていたが、夜の学校に一人でいるのが怖かった七緒はホッと安心する。
しかしそこで待ち受けていたのは、予想しない出来事だった――。
ゾクッと怖くて、ハラハラドキドキ。
最後には、ゾッとするどんでん返しがあなたを待っている。

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

星降る夜に落ちた子
千東風子
児童書・童話
あたしは、いらなかった?
ねえ、お父さん、お母さん。
ずっと心で泣いている女の子がいました。
名前は世羅。
いつもいつも弟ばかり。
何か買うのも出かけるのも、弟の言うことを聞いて。
ハイキングなんて、来たくなかった!
世羅が怒りながら歩いていると、急に体が浮きました。足を滑らせたのです。その先は、とても急な坂。
世羅は滑るように落ち、気を失いました。
そして、目が覚めたらそこは。
住んでいた所とはまるで違う、見知らぬ世界だったのです。
気が強いけれど寂しがり屋の女の子と、ワケ有りでいつも諦めることに慣れてしまった綺麗な男の子。
二人がお互いの心に寄り添い、成長するお話です。
全年齢ですが、けがをしたり、命を狙われたりする描写と「死」の表現があります。
苦手な方は回れ右をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私が子どもの頃から温めてきたお話のひとつで、小説家になろうの冬の童話際2022に参加した作品です。
石河 翠さまが開催されている個人アワード『石河翠プレゼンツ勝手に冬童話大賞2022』で大賞をいただきまして、イラストはその副賞に相内 充希さまよりいただいたファンアートです。ありがとうございます(^-^)!
こちらは他サイトにも掲載しています。

『異世界庭付き一戸建て』を相続した仲良し兄妹は今までの不幸にサヨナラしてスローライフを満喫できる、はず?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
毒親の父が不慮の事故で死亡したことで最後の肉親を失い、残された高校生の小村雷人(こむら らいと)と小学生の真琴(まこと)の兄妹が聞かされたのは、父が家を担保に金を借りていたという絶望の事実だった。慣れ親しんだ自宅から早々の退去が必要となった二人は家の中で金目の物を探す。
その結果見つかったのは、僅かな現金に空の預金通帳といくつかの宝飾品、そして家の権利書と見知らぬ文字で書かれた書類くらいだった。謎の書類には祖父のサインが記されていたが内容は読めず、頼みの綱は挟まれていた弁護士の名刺だけだ。
最後の希望とも言える名刺の電話番号へ連絡した二人は、やってきた弁護士から契約書の内容を聞かされ唖然とする。それは祖父が遺産として残した『異世界トラス』にある土地と建物を孫へ渡すというものだった。もちろん現地へ行かなければ遺産は受け取れないが。兄妹には他に頼れるものがなく、思い切って異世界へと赴き新生活をスタートさせるのだった。
連載時、HOT 1位ありがとうございました!
その他、多数投稿しています。
こちらもよろしくお願いします!
https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/398438394
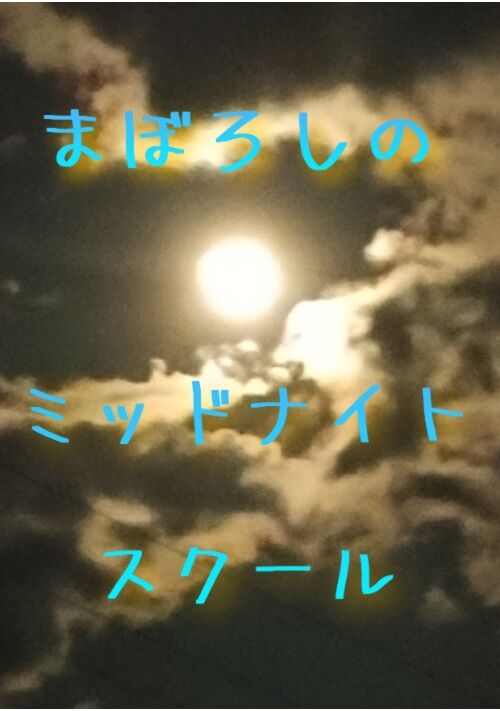
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

ナナの初めてのお料理
いぬぬっこ
児童書・童話
ナナは七歳の女の子。
ある日、ナナはお母さんが仕事から帰ってくるのを待っていました。
けれど、お母さんが帰ってくる前に、ナナのお腹はペコペコになってしまいました。
もう我慢できそうにありません。
だというのに、冷蔵庫の中には、すぐ食べれるものがありません。
ーーそうだ、お母さんのマネをして、自分で作ろう!
ナナは、初めて自分一人で料理をすることを決めたのでした。
これは、ある日のナナのお留守番の様子です。

少年イシュタと夜空の少女 ~死なずの村 エリュシラーナ~
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
イシュタは病の妹のため、誰も死なない村・エリュシラーナへと旅立つ。そして、夜空のような美しい少女・フェルルと出会い……
「昔話をしてあげるわ――」
フェルルの口から語られる、村に隠された秘密とは……?
☆…☆…☆
※ 大人でも楽しめる児童文学として書きました。明確な記述は避けておりますので、大人になって読み返してみると、また違った風に感じられる……そんな物語かもしれません……♪
※ イラストは、親友の朝美智晴さまに描いていただきました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















