50 / 55
第7章 決着をつける
50
しおりを挟む
台風は時速四十五キロメートルの速さで北北西に進み、夜のあいだずっと暴風雨がつづいた。ひごめ市を流れる知戸川の水かさがどんどん増した。川はいつ氾濫してもおかしくないほどの濁流となり、消防に携わる大人たちは一晩中緊張しつづけた。
激しい、激しすぎる濁流は、山から集まる雨水とはべつの要因もあった。
メガネ池から知戸川へ向かって水が流れたのだ。
もともとメガネ池は知戸川とはつながっていない。ひとつの独立した水のかたまりだった。
だがこの夜、メガネ池からひとすじの水の流れが生まれて知戸川とつながった。
水は池から川へ、あとからあとから流れつづけた。夜の間ずっとそれがつづいた。
ただし人々の注意は崩れた崖や氾濫寸前だった知戸川と吹川の合流点へ向けられたので、そのことに気づく者はだれもいなかった。
メガネ池のうち片方の池の水がすべて流れて、池そのものが消滅したことを人々が発見したのは、翌日のことだった。ふたつの池がひとつだけになってしまった。
そして、夜のうちに濁流に飲みこまれた不幸な人たちが、日付が変わり明るくなってから遺体で発見された。県内で三人の死者が出た。
そのうちの一人が、ひごめ高校一年の狭間進一郎だった。
彼の遺体は消滅した池の跡で見つかった。
狭間進一郎の葬式は、彼が遺体で見つかった四日後に執り行われた。
その日は、あのひどい台風などなかったかのようによく晴れ、乾いた空気が辺りを覆った。風は冷たいが日ざしはまだ暖かい、そんな秋の日だった。
場所は狭間家の古い母屋。
葬儀会場を使わず家で行うのは近頃ではめずらしい。だが、もともとこの屋敷では何百年も前から嫁入りも弔いも座敷の襖を取りはらって大広間をしつらえることで、当たり前に行ってきたのだ。
昔ながらのひごめの仕来りにのっとった葬送になった。
狭間家は土地に根ざした古い血筋の家だったから、親戚を含めた地元の人たちが、おおぜい集まった。
ひごめ館の関係者はほとんど全員やってきた。黒い着物姿の津江さんもだ。それに高校からも道場からもたくさん参列者がおとずれて、そのなかには未成年も多かったので、ミチが混ざっても違和感はなかった。
ほんの数日会っただけの間柄だったが、砂森や羽根島先生のはからいでミチも参列したのだ。
参列する者全員を屋敷に入れるのは無理だったので、座敷に連なる縁側を開放して庭に折り畳みの椅子が並べられた。
ミチは進一郎の両親を、その場で初めて見た。
父親と母親どちらにも進一郎や聖のおもかげがあり、そしてどちらもひどくやつれているように見えた。入院していたという母親のほうは特にそうだった。
会長もいた。大きな体をせかせかと動かして葬式を取り仕切っていた。
その場にいない進一郎の親族はただ一人、弟の聖だけだった。
参列したのは人間だけではなかった。
古い日本家屋の屋根の上には黄色い鳥がたくさんとまっていた。
屋敷の外から見える一ツ目山のふもとでは、ななかまどの大きな木が、ときに吹く風で紅葉を散らしていた。
どっちみち、木は木にしか見えなかった。これまでその場所にななかまどの木など立っていたのかなどということを気にする大人は、一人を除いて存在しなかった。
その一人、羽根島先生は屋敷に入る前にその木をちらりと見て目を細めただけで、口に出してはなにも言わなかった。
もっとも羽根島先生はあのとき骨折した体のあちこちの骨、鎖骨や肋骨などがまだひどく痛むために、そしておそらく体とはべつのところにも生まれた痛みのために、日ごろほがらかなこの人にしてはめずらしいほど無口だった。
ミチはななかまどの木のそばに、黒い岩が転がっているのも見た。
日に当たった個所が黒光りする岩だ。ミチはそのことを意外に感じた。
棺桶のなかの進一郎は目を閉じ、表情だけを見たらまるで眠っているようだった。でも顔色はうっすらと緑味をおび血の気がまったくなくて、その顔色が生死の区別を明確につけていた。
お焼香をすませて縁側から庭へ出たミチの肩をとんとんと指でつついた者がいた。
「ミチどの」
津江さんだ。津江さんがミチより先にお焼香をあげたのをミチはさっき見ていた。その津江さんがミチにだけ聞こえる小声でささやいた。
「一緒に来やれ」
ミチはなるべくそっと立ち上がった。
津江さんはお焼香の列を作るために並ぶ人々の流れとは逆の方向へ進んだ。母屋に沿ってまっすぐに進み、端まで来るとそこを母屋の縁側に沿って曲がった。
そうするのが当然といった様子の、自然な足取りだった。
だれも津江さんに声をかけなかった。
ともすれば立ち止まりたい気持ちをおさえつけて、ミチは津江さんの後を追った。
母屋の端を曲がると津江さんは一ツ目山の山すそにあたる木々のなかへ分け入ろうとしているところだった。
ミチの足が落ち葉の固まりを踏んでガサリと音を立てた。
津江さんが振りかえった。
「ミチどの」
話しかけないでほしいとミチは思った。
だけど声の主は、ミチの気持ちなんかまったく無視した。
あの日、ミチの手を強く引いて歩いたときとおなじだ。
「まだ終わっておらぬえ、ミチどの」
ミチは津江さんを強い目でぎゅっと見すえた。
四日のあいだ泣きはらしたせいで、ミチの白目は赤く、腫れぼったかった。だからにらみつけてもぜんぜん迫力がなかった。それでもミチはそうした。
ミチは言った。
「ぼくはいま津江さんと話をしたくないです」
だって話したら津江さんを責めてしまいそうだった。
進一郎が死んだことを津江さんのせいにしてしまいそうだった。
べつに津江さんが進一郎を殺したわけじゃない、もちろんちがう。
そんなことはミチだってよくわかっていた、頭では。
でも、と、頭で割り切れない気持ちの部分が津江さんを責めたがっていた。
津江さんだったら、もしかしたら何とかできたのじゃないか、そう思ってしまう、いや、そう思いたがっている。
激しい、激しすぎる濁流は、山から集まる雨水とはべつの要因もあった。
メガネ池から知戸川へ向かって水が流れたのだ。
もともとメガネ池は知戸川とはつながっていない。ひとつの独立した水のかたまりだった。
だがこの夜、メガネ池からひとすじの水の流れが生まれて知戸川とつながった。
水は池から川へ、あとからあとから流れつづけた。夜の間ずっとそれがつづいた。
ただし人々の注意は崩れた崖や氾濫寸前だった知戸川と吹川の合流点へ向けられたので、そのことに気づく者はだれもいなかった。
メガネ池のうち片方の池の水がすべて流れて、池そのものが消滅したことを人々が発見したのは、翌日のことだった。ふたつの池がひとつだけになってしまった。
そして、夜のうちに濁流に飲みこまれた不幸な人たちが、日付が変わり明るくなってから遺体で発見された。県内で三人の死者が出た。
そのうちの一人が、ひごめ高校一年の狭間進一郎だった。
彼の遺体は消滅した池の跡で見つかった。
狭間進一郎の葬式は、彼が遺体で見つかった四日後に執り行われた。
その日は、あのひどい台風などなかったかのようによく晴れ、乾いた空気が辺りを覆った。風は冷たいが日ざしはまだ暖かい、そんな秋の日だった。
場所は狭間家の古い母屋。
葬儀会場を使わず家で行うのは近頃ではめずらしい。だが、もともとこの屋敷では何百年も前から嫁入りも弔いも座敷の襖を取りはらって大広間をしつらえることで、当たり前に行ってきたのだ。
昔ながらのひごめの仕来りにのっとった葬送になった。
狭間家は土地に根ざした古い血筋の家だったから、親戚を含めた地元の人たちが、おおぜい集まった。
ひごめ館の関係者はほとんど全員やってきた。黒い着物姿の津江さんもだ。それに高校からも道場からもたくさん参列者がおとずれて、そのなかには未成年も多かったので、ミチが混ざっても違和感はなかった。
ほんの数日会っただけの間柄だったが、砂森や羽根島先生のはからいでミチも参列したのだ。
参列する者全員を屋敷に入れるのは無理だったので、座敷に連なる縁側を開放して庭に折り畳みの椅子が並べられた。
ミチは進一郎の両親を、その場で初めて見た。
父親と母親どちらにも進一郎や聖のおもかげがあり、そしてどちらもひどくやつれているように見えた。入院していたという母親のほうは特にそうだった。
会長もいた。大きな体をせかせかと動かして葬式を取り仕切っていた。
その場にいない進一郎の親族はただ一人、弟の聖だけだった。
参列したのは人間だけではなかった。
古い日本家屋の屋根の上には黄色い鳥がたくさんとまっていた。
屋敷の外から見える一ツ目山のふもとでは、ななかまどの大きな木が、ときに吹く風で紅葉を散らしていた。
どっちみち、木は木にしか見えなかった。これまでその場所にななかまどの木など立っていたのかなどということを気にする大人は、一人を除いて存在しなかった。
その一人、羽根島先生は屋敷に入る前にその木をちらりと見て目を細めただけで、口に出してはなにも言わなかった。
もっとも羽根島先生はあのとき骨折した体のあちこちの骨、鎖骨や肋骨などがまだひどく痛むために、そしておそらく体とはべつのところにも生まれた痛みのために、日ごろほがらかなこの人にしてはめずらしいほど無口だった。
ミチはななかまどの木のそばに、黒い岩が転がっているのも見た。
日に当たった個所が黒光りする岩だ。ミチはそのことを意外に感じた。
棺桶のなかの進一郎は目を閉じ、表情だけを見たらまるで眠っているようだった。でも顔色はうっすらと緑味をおび血の気がまったくなくて、その顔色が生死の区別を明確につけていた。
お焼香をすませて縁側から庭へ出たミチの肩をとんとんと指でつついた者がいた。
「ミチどの」
津江さんだ。津江さんがミチより先にお焼香をあげたのをミチはさっき見ていた。その津江さんがミチにだけ聞こえる小声でささやいた。
「一緒に来やれ」
ミチはなるべくそっと立ち上がった。
津江さんはお焼香の列を作るために並ぶ人々の流れとは逆の方向へ進んだ。母屋に沿ってまっすぐに進み、端まで来るとそこを母屋の縁側に沿って曲がった。
そうするのが当然といった様子の、自然な足取りだった。
だれも津江さんに声をかけなかった。
ともすれば立ち止まりたい気持ちをおさえつけて、ミチは津江さんの後を追った。
母屋の端を曲がると津江さんは一ツ目山の山すそにあたる木々のなかへ分け入ろうとしているところだった。
ミチの足が落ち葉の固まりを踏んでガサリと音を立てた。
津江さんが振りかえった。
「ミチどの」
話しかけないでほしいとミチは思った。
だけど声の主は、ミチの気持ちなんかまったく無視した。
あの日、ミチの手を強く引いて歩いたときとおなじだ。
「まだ終わっておらぬえ、ミチどの」
ミチは津江さんを強い目でぎゅっと見すえた。
四日のあいだ泣きはらしたせいで、ミチの白目は赤く、腫れぼったかった。だからにらみつけてもぜんぜん迫力がなかった。それでもミチはそうした。
ミチは言った。
「ぼくはいま津江さんと話をしたくないです」
だって話したら津江さんを責めてしまいそうだった。
進一郎が死んだことを津江さんのせいにしてしまいそうだった。
べつに津江さんが進一郎を殺したわけじゃない、もちろんちがう。
そんなことはミチだってよくわかっていた、頭では。
でも、と、頭で割り切れない気持ちの部分が津江さんを責めたがっていた。
津江さんだったら、もしかしたら何とかできたのじゃないか、そう思ってしまう、いや、そう思いたがっている。
0
あなたにおすすめの小説

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

星降る夜に落ちた子
千東風子
児童書・童話
あたしは、いらなかった?
ねえ、お父さん、お母さん。
ずっと心で泣いている女の子がいました。
名前は世羅。
いつもいつも弟ばかり。
何か買うのも出かけるのも、弟の言うことを聞いて。
ハイキングなんて、来たくなかった!
世羅が怒りながら歩いていると、急に体が浮きました。足を滑らせたのです。その先は、とても急な坂。
世羅は滑るように落ち、気を失いました。
そして、目が覚めたらそこは。
住んでいた所とはまるで違う、見知らぬ世界だったのです。
気が強いけれど寂しがり屋の女の子と、ワケ有りでいつも諦めることに慣れてしまった綺麗な男の子。
二人がお互いの心に寄り添い、成長するお話です。
全年齢ですが、けがをしたり、命を狙われたりする描写と「死」の表現があります。
苦手な方は回れ右をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私が子どもの頃から温めてきたお話のひとつで、小説家になろうの冬の童話際2022に参加した作品です。
石河 翠さまが開催されている個人アワード『石河翠プレゼンツ勝手に冬童話大賞2022』で大賞をいただきまして、イラストはその副賞に相内 充希さまよりいただいたファンアートです。ありがとうございます(^-^)!
こちらは他サイトにも掲載しています。


14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

少年騎士
克全
児童書・童話
「第1回きずな児童書大賞参加作」ポーウィス王国という辺境の小国には、12歳になるとダンジョンか魔境で一定の強さになるまで自分を鍛えなければいけないと言う全国民に対する法律があった。周囲の小国群の中で生き残るため、小国を狙う大国から自国を守るために作られた法律、義務だった。領地持ち騎士家の嫡男ハリー・グリフィスも、その義務に従い1人王都にあるダンジョンに向かって村をでた。だが、両親祖父母の計らいで平民の幼馴染2人も一緒に12歳の義務に同行する事になった。将来救国の英雄となるハリーの物語が始まった。
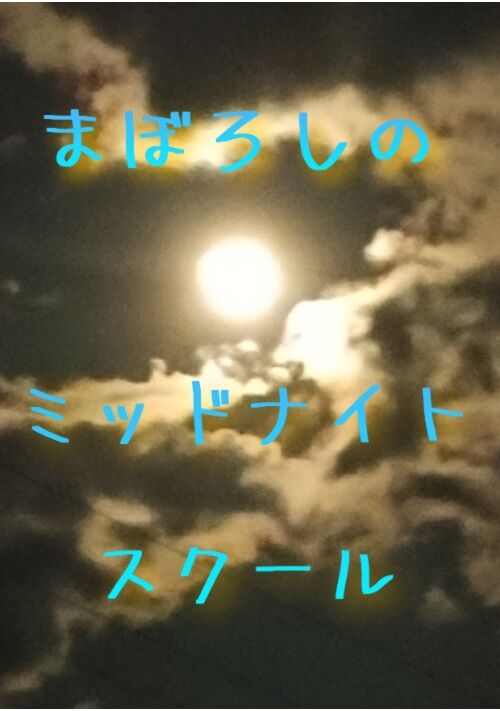
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

『異世界庭付き一戸建て』を相続した仲良し兄妹は今までの不幸にサヨナラしてスローライフを満喫できる、はず?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
毒親の父が不慮の事故で死亡したことで最後の肉親を失い、残された高校生の小村雷人(こむら らいと)と小学生の真琴(まこと)の兄妹が聞かされたのは、父が家を担保に金を借りていたという絶望の事実だった。慣れ親しんだ自宅から早々の退去が必要となった二人は家の中で金目の物を探す。
その結果見つかったのは、僅かな現金に空の預金通帳といくつかの宝飾品、そして家の権利書と見知らぬ文字で書かれた書類くらいだった。謎の書類には祖父のサインが記されていたが内容は読めず、頼みの綱は挟まれていた弁護士の名刺だけだ。
最後の希望とも言える名刺の電話番号へ連絡した二人は、やってきた弁護士から契約書の内容を聞かされ唖然とする。それは祖父が遺産として残した『異世界トラス』にある土地と建物を孫へ渡すというものだった。もちろん現地へ行かなければ遺産は受け取れないが。兄妹には他に頼れるものがなく、思い切って異世界へと赴き新生活をスタートさせるのだった。
連載時、HOT 1位ありがとうございました!
その他、多数投稿しています。
こちらもよろしくお願いします!
https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/398438394

ナナの初めてのお料理
いぬぬっこ
児童書・童話
ナナは七歳の女の子。
ある日、ナナはお母さんが仕事から帰ってくるのを待っていました。
けれど、お母さんが帰ってくる前に、ナナのお腹はペコペコになってしまいました。
もう我慢できそうにありません。
だというのに、冷蔵庫の中には、すぐ食べれるものがありません。
ーーそうだ、お母さんのマネをして、自分で作ろう!
ナナは、初めて自分一人で料理をすることを決めたのでした。
これは、ある日のナナのお留守番の様子です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















