79 / 102
四章 王の影
四章十七話 『精霊or悪魔』
しおりを挟むバシレとの会話を済ませた後、ルークは一旦傷の治療をしてから客人用の部屋でゆっくりと休んでいた。
いつもならティアニーズ辺りが突撃して来そうなのだが、重要な任務を前にして精神統一でもしているのだろう。
なので、ルークは夜まで一人で睡眠の世界を楽しむ……の予定だったのだが、
「なんでお前がここに居んだよ」
「私は貴様の側を離れる訳にはいかないからだ」
「お前の部屋だって用意されてんだろ、そっちに行け」
「断る、私も寝たいからもう少しつめろ」
ベッドに横たわるルークの横で、何故か当たり前のようにソラが居座っている。しかもどうやら一緒に寝るつもりらしく、そのまま寝転んで狭いと言いたげにルークを手で押しやる。
「押すんじゃねぇよオイ。狭いのが嫌なら出てけ、これは俺のベッドだ」
「違う、私が寝ると決めた瞬間からこのベッドは私の物だ。すなわち床で寝るべきは貴様なのだ」
「なら俺がお前の部屋に行く。お前はここでゆっくり寝てろ」
「良し分かった、私も移動しよう」
「だから! 着いて来んなって言ってんの!」
ルークは体を起こして部屋を出て行こうとするが、とんでも理論を展開するソラがその後をつけ回す。
全力で押さえつけようとするが、ソラは蛇のようなその腕に絡み付いてきた。
「離せクソが、寝る時くらい一人にさせやがれッ」
「断る、私は貴様の側に居ると決めたんだ」
「だから迷惑だっつってんだよ、これじゃ休憩の意味ねぇじゃん!」
全力で引き剥がそうとするも、謎の腕力でソラは拒否。そのまま器用にルークの体を移動し、背中と合体した。手足をロックされ、幼女がルークの背中にまとわりつくという異様な光景がここに誕生した。
「貴様も今回の件で分かった筈だ。どこへ行こうが奴らは必ず貴様と遭遇する、その悪運を呪うんだな」
「うっせぇな、城の中なんだからへーきだろ」
「先ほど魔獣が城内に侵入したばかりだろ。もっと危機感を持て」
「んな事は分かってんだよ。んで、それは俺の背中でするべき話なのか」
「こうでもしなければ貴様は逃げるだろう」
ソラの言い分はもっともであるが、これでは休憩どころの話ではない。傷は治っているものの、消費した大量は未だ補充されてはいないのだ。
魔元帥との戦闘を後に控えているというのに、その危機感などは微塵も感じられないのである。
まぁ、いつも通りと言えばそうなのだが。
「それで、奴と一対一で戦える場面まで持ち込んだとして、勝てる算段はあるのか?」
「殴って斬る」
「話にならんな、それは戦法とは言わない」
ソラを引き剥がすのを諦め、ルークはベッドに腰を下ろした。
いつものように顔は見えないものの、憎たらしい顔で呆れながらソラをは耳元で言葉を続ける。
「現状、分かっているのは奴が武器を造る事が出来るという事だ。逃げ出した事も加味すると、恐らくなにかしらの制約、もしくは上限があるのだろう」
「んなのどうだって良いだろ。力でねじ伏せればアイツがどんな力を持っていようが関係ない」
「今まではそれでどうにかなっていたが……いや、どうにかしていたと言った方が正しいか。今回もそう上手くいくとは限らんぞ」
「分からねぇ事を考えたって答えは出ねぇだろ。考えるんなら戦いながらやれば良い」
「それが通用すれば良いのだがな。今まで通りにはいかんぞ。奴らだってバカじゃない、仲間が殺されている事には気付いている筈だ。それをやっているのが、勇者だという事にもな」
デストにしろウェロディエにしろ、相手の油断ありきで勝った事は認めざるを得ないだろう。
デストは人間を見下し、自分の力を過信していた。
ウェロディエは自分の食事を優先し、ソラの存在を除いて戦いを行っていた。
どちらにせよ、初めから警戒心があって本気で来られていた場合、勝てたにしてももっと激しい戦いになっていただろう。
しかし、今回のウルスは訳が違う。
自分の力量を理解しているからこそ逃げるという手段をとり、無闇に攻める事はしなかった。
ちゃらんぽらんに見えて、意外と頭のきれる男らしい。
「わーってるよ。一応考えてるには考えてる」
「ほう、聞かせてもらおうか」
「アイツが力を使えなくなるまで粘る」
「……はぁ、ここまでバカだとはな。長期戦になれば時間制限のある私達が圧倒的に不利、それを忘れてはいないか?」
「忘れてねーよ。逃げるのは得意なんだ、泥臭くてもなんだろうが、勝ちゃ良いだけの話だろ」
「ま、私に出来るのはサポートだけだ。戦い方は貴様に任せるよ、死ななければなんだって良いさ」
やれやれといった様子でため息をこぼし、ソラは力を抜いてルークの背中に体を預ける。
どうやら普通に背負っているよりも、力を抜いた人間を背負う方が重さを感じるらしい。ルークは体をねじり、
「おうコラ、まさかそこで寝るとかアホな事言わねぇよな?」
「そのまさかだ。目を離せば貴様は勝手に出歩くだろう?」
「どこにも行かねーよ、ウゼェからさっさと退け」
「断る。貴様の背中はほど良く筋肉がついていて寝心地が良いのだ。それに、私の胸の感触を背中越しに味わえるんだ、悪い事ばかりではないだろう?」
「え? 胸? 絶壁過ぎてなんも感じなーー」
ルークがなにかを良い終えるよりも早く、ソラの腕が首に巻き付いた。完璧な流れでチョークスリパーが決まり、気道を塞がれたルークの顔が段々と青ざめていく。
ルークの発言は、ソラの逆鱗に触れたらしい。
「悪いなぁ、最後まで聞こえなかったぞ? 壁がなんだって? 私の胸がなんだって? アァ?」
「ギ、ギブッ。死ぬから、戦う前に死んじゃうから! 俺の英雄譚ここで終わっちゃうから!」
「ほら、言ってみろ。私の胸はなんだって?」
「デカ、デカいから! めっちゃデカいっす、巨乳っす!」
「そうだろそうだろ、私の胸は大きいだろう。ならなんと言えば良いんだ? 言うべき事があるだろう?」
「あ、ありがとゴザイマス……!」
背後から溢れ出す邪悪なオーラと、時間を増す事に首を締め付ける腕力。その姿は幼女でも精霊でもなんでもなく、ただの悪魔である。
全力のタップの末、飛びかけた意識が肉体へと戻る。
そのまま顔を上げると、
「あの、なにをしているんですか?」
どのタイミングで扉を開けたのかは不明だが、ゴミでも見るかのような目でルークを眺めるティアニーズが立っていた。
端から見れば被害者は間違いなくルークの筈なのだが、
「胸がどうとか聞こえてきたんですけど」
「ルークが私の胸は小さいと抜かしたんだ。だから今、精霊のありがたい天誅を下していた」
「なにがありがたい天誅だ! こっちは死にかけてんだよ。あと、お前勘違いしてるみたいだから言っとくぞ、これは俺の趣味じゃない。俺はロリコンーー」
「ふん!」
「ふべッ!」
その言葉は、恐らく貧乳よりもソラの怒りを刺激するものなのだろう。
喋り終えるよりも早く、ソラの腕が的確に動脈を締め上げた。首から変な音が響いてから数秒後、白目を向いてルークはダラリとベッドに倒れこんだ。
それから数分後、
「まったく、これから大事な任務が控えてるって分かっているんですか?」
「その前に体の心配しろや。俺今完全に落ちてたよね? なんか体の力抜けてちょっと気持ちよかったんだけど」
「それになれると終わりだぞ」
「お前がやってんだよ、なんでそんなに他人事っぽく振る舞えるのかな?」
ルークが目を覚ますと既にソラが離れており、寝転ぶその横にティアニーズが座っていた。まだ視界が歪んでクラクラとするが、生きているので問題はないだろう。
ティアニーズは呆れたように視線を落とし、
「ルークさんが不安になってないか見に来てあげたのに、心配はいりませんでしたね」
「いや心配してよ。今心配する出来事が目の前で起きた筈なんだけど?」
「私達は王の護衛を任されたんですよ? もう少し緊張感を持つべきです」
「無視ですか? ッたく、別に心配なんていらねーよ。俺はいつも通りにやらなきゃいけねぇ事をやるだけだ」
華麗なスルー文句を言うけれど、やはらこれも無視。体を起こしてうつ向くティアニーズの顔を覗き込むと、ルークはある事に気付いた。
「不安なのはお前の方だろ。顔にめっちゃ不安ですって書いてあんぞ」
「そ、そんな事ないです。私はいつ何時でもこういった非常事態に備えて心の準備はしてあります!」
「どうだか。あれ、もしかして不安だから俺に会いに来ちゃった感じ? 俺の顔が見たくなっちゃった感じ?」
「殴りますよ?」
「いやもう殴ってる」
相変わらずのウザさ全開の挑発に、ティアニーズのビンタが頬を揺らした。
強がってはいるけれど、やはり十六歳の少女には荷が重いのかもしれない。それもその筈、自分が失敗すればこの国の王が命を落とすのだから。
「不安がないと言えば嘘になります。けど、それ以上にどうにかしなければ、という思いの方が強いんです」
「なるようにしかならねぇよ。どんなに頑張ったって限界はある、やれる事をやるしかねぇだろ」
「なんで、ルークさんはいつもそう楽観的なんですか?」
「なんでって、そりゃ失敗しねぇし。俺は自分に出来る事しかやらねぇ、だから不安なんてねぇよ」
「その自信を少し分けて欲しいです」
別にルークは自信がある訳ではない。自分の力を過信している訳でもないし、慢心している訳でもない。
それでも、やらければいけない事だから。
やれる事だと信じたから、ルークは不安を持つ事はない。
「この任務に失敗すれば王と姫様を死なせてしまう。そして、奴らに魔王の封印場所を知られてしまう。絶対に、失敗は出来ないんです」
「失敗しなきゃ良いだけの話だろ。ウルスの野郎をぶっ潰せばそれで良いだけの話だろ」
「そんな事分かってます! けど……」
「面倒くせぇ奴だな。お前はお前に出来る事をやれ。おっさんと姫さんを守って、なおかつウルスを倒そうなんて考えるから不安になるんだろ」
どこまでもネガティブなティアニーズに、ルークが痺れを切らしてその後頭部を叩く。
振り返り、ティアニーズは今にも泣き出しそうな目をしていた。不安に押し潰されそうなほどに。
「う……泣くなよ。泣いてる奴見ると苛々する」
「泣いてなんていません」
「さいですか」
サリーの言葉を思い出し、ルークは少しだけしどろもどろになる。頭を振り、一方的に押し付けられた約束を弾き出すと、目を合わせる事はせずに、
「良いか、一回しか言わねぇから良く聞け」
「はい?」
「俺は誰かを守るのはすげぇ苦手だ。でも、お前はそれが出来るしそうしたいと思ってんだろ? だったらそうしろ、守る事だけに集中しろ」
今までの人生、そしてこれからの人生で、ルークが自分の得する事以外で率先して人を守る事はないだろう。
ただ単純に苦手なのだ。誰かのためになにかをする行動自体が。だから、
「俺はウルスをぶっ潰す事だけに集中する。お前がおっさんと姫さんを必ず守る。そうすりゃ失敗する事なんてねぇだろ」
「そんな簡単にいきませんよ……」
「出来る。ゼッテーにだ」
ティアニーズは口を開かず、瞳だけで『なんでですか?』という疑問を伝えているようだ。
ちらほらと出現するサリーの顔に苛立ちながら、頭をかきむしって恥ずかしさを誤魔化し、ルークはこう言った。
「お前は強い奴だからだ」
「ーーーー」
「ふん、ルークがデレた」
「黙れロリ貧乳」
「な、なに! もう一回言ってみろ! ぶっ殺してやる!」
鼻を鳴らして雰囲気をぶち壊すソラ。
そんなソラに対して一番ダメージがあるであろう発言を迷わず口にすると、案の定ベッドのバネを使って大ジャンプし、二人は縺れ合いながらベッドから転落した。
「私のどこがロリ貧乳なんだ、アァ? 歳は貴様よりはるか上だぞ!」
「見た目の話をしてるんだよバーカ!」
「誰がバカだこのアホ!」
「アホって言う奴がアホなんですぅ!」
今時の子供でもこんな醜い争いはしないと思うが、お互いの頬を引っ張りあいながら二人は死闘を繰り広げる。
そんな二人を見て、口を開けてポカンとしていたティアニーズが思わず吹き出した。
「プッ……フフフ、アハハハハ!」
「あ? なに笑ってんだ」
「隙ありだバカ者!」
ティアニーズの笑いに一瞬気をとられた時、ルークの金的にソラの膝の皿がめり込んだ。
勝負ありである。ルークは再び白目を向いて力が抜けたようにその場に倒れ、ピクピクと全身を震え上がらせている。
「ふぅ、私の勝ちだな。私に逆らおうなどと千年早いわ」
「もう、本当にバカですね、お二人は。こんな事で悩んでいた私はもっとバカですけど」
「……痛いよ、マジでやべぇって。首絞めとか比べ物にならねぇよ」
あまりの痛さに跳ねて痛みを中和する事も出来ず、ベッドにしがみつきながらなんとか立ち上がるルーク。生まれたての小鹿のように震える足を、自分の力では押さえる事が出来ない。
しかし、ティアニーズはルークを気にせずに扉の方へと行き、
「ルークさん、ありがとうございます。私頑張りますね、貴方の隣に並べるように」
「い、いや待って、こいつと二人きりにしないで」
「夜までしっかり休んで下さいね。足手まといになったら許しませんよ」
不安が晴れたようで、いつも通りの笑顔を浮かべてティアニーズは部屋を出て行ってしまった。
残されたルークは悪魔の顔を見る。
「さて、お仕置きの時間だ」
「え、ちょ、これ以上は……いやぁぁぁぁ!」
この日、その叫びを最後にルークの姿を夜まで見た者はいなかった。あとから辺りを歩いていた兵士によれば、それはそれはこの世の終わりのような叫び声だったらしい。
そしてもう一つ。
廊下をスキップするティアニーズの姿を見た者によれば、『私は強い』と何度も呟き、嬉しそうに微笑んでいたという。
0
あなたにおすすめの小説

九尾と契約した日。霊力ゼロの陰陽師見習いが大成するまで。
三科異邦
ファンタジー
「霊力も使えない。術式も出せない。
……西園寺玄弥、お前は本当に陰陽師か?」
その言葉は、もう何度聞いたか分からない。
霊術学院の訓練場で、俺はただ立ち尽くしていた。
周囲では炎が舞い、水がうねり、風が刃のように走る。
同年代の陰陽師たちが、当たり前のように霊を操っている。
――俺だけが、何もできない。
反論したい気持ちはある。
でも、できない事実は変わらない。
そんな俺が、
世界最強クラスの妖怪と契約することになるなんて――
この時は、まだ知る由もなかった。
これは――
妖怪の王を倒すべく、九尾の葛葉や他の仲間達と力を合わせて成長していく陰陽師見習いの物語。

なぜ、最強の勇者は無一文で山に消えたのか? ──世界に忘れられ、ひび割れた心のまま始めたダークスローライフ。 そして、虹の種は静かに育ち始め
イニシ原
ファンタジー
ダークスローライフで癒しに耐えろ。
孤独になった勇者。
人と出会わないことで進む時間がスローになるのがダークスローライフ。
ベストな組み合わせだった。
たまに来る行商人が、唯一の接点だった。
言葉は少なく、距離はここちよかった。
でも、ある日、虹の種で作ったお茶を飲んだ。
それが、すべての始まりだった。
若者が来た。
食料を抱えて、笑顔で扉を叩く。
断っても、また来る。
石を渡せば帰るが、次はもっと持ってくる。
優しさは、静けさを壊す。
逃げても、追いつかれる。
それでも、ほんの少しだけ、
誰かと生きたいと思ってしまう。
これは、癒しに耐える者の物語。
***
登場人物の紹介
■ アセル
元勇者。年齢は40に近いが、見た目は16歳。森の奥でひとり暮らしている。
■ アーサー
初老の男性。アセルが唯一接点を持つ人物。たまに森を訪れる。
■ トリス
若者。20代前半。アーサー行方不明後、食料を抱えて森の家を訪れる。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

老衰で死んだ僕は異世界に転生して仲間を探す旅に出ます。最初の武器は木の棒ですか!? 絶対にあきらめない心で剣と魔法を使いこなします!
菊池 快晴
ファンタジー
10代という若さで老衰により病気で死んでしまった主人公アイレは
「まだ、死にたくない」という願いの通り異世界転生に成功する。
同じ病気で亡くなった親友のヴェルネルとレムリもこの世界いるはずだと
アイレは二人を探す旅に出るが、すぐに魔物に襲われてしまう
最初の武器は木の棒!?
そして謎の人物によって明かされるヴェネルとレムリの転生の真実。
何度も心が折れそうになりながらも、アイレは剣と魔法を使いこなしながら
困難に立ち向かっていく。
チート、ハーレムなしの王道ファンタジー物語!
異世界転生は2話目です! キャラクタ―の魅力を味わってもらえると嬉しいです。
話の終わりのヒキを重要視しているので、そこを注目して下さい!
****** 完結まで必ず続けます *****
****** 毎日更新もします *****
他サイトへ重複投稿しています!

【コミカライズ決定】勇者学園の西園寺オスカー~実力を隠して勇者学園を満喫する俺、美人生徒会長に目をつけられたので最強ムーブをかましたい~
エース皇命
ファンタジー
【HOTランキング2位獲得作品】
【第5回一二三書房Web小説大賞コミカライズ賞】
~ポルカコミックスでの漫画化(コミカライズ)決定!~
ゼルトル勇者学園に通う少年、西園寺オスカーはかなり変わっている。
学園で、教師をも上回るほどの実力を持っておきながらも、その実力を隠し、他の生徒と同様の、平均的な目立たない存在として振る舞うのだ。
何か実力を隠す特別な理由があるのか。
いや、彼はただ、「かっこよさそう」だから実力を隠す。
そんな中、隣の席の美少女セレナや、生徒会長のアリア、剣術教師であるレイヴンなどは、「西園寺オスカーは何かを隠している」というような疑念を抱き始めるのだった。
貴族出身の傲慢なクラスメイトに、彼と対峙することを選ぶ生徒会〈ガーディアンズ・オブ・ゼルトル〉、さらには魔王まで、西園寺オスカーの前に立ちはだかる。
オスカーはどうやって最強の力を手にしたのか。授業や試験ではどんなムーブをかますのか。彼の実力を知る者は現れるのか。
世界を揺るがす、最強中二病主人公の爆誕を見逃すな!
※小説家になろう、カクヨム、pixivにも投稿中。

異世界に召喚されたが勇者ではなかったために放り出された夫婦は拾った赤ちゃんを守り育てる。そして3人の孤児を弟子にする。
お小遣い月3万
ファンタジー
異世界に召喚された夫婦。だけど2人は勇者の資質を持っていなかった。ステータス画面を出現させることはできなかったのだ。ステータス画面が出現できない2人はレベルが上がらなかった。
夫の淳は初級魔法は使えるけど、それ以上の魔法は使えなかった。
妻の美子は魔法すら使えなかった。だけど、のちにユニークスキルを持っていることがわかる。彼女が作った料理を食べるとHPが回復するというユニークスキルである。
勇者になれなかった夫婦は城から放り出され、見知らぬ土地である異世界で暮らし始めた。
ある日、妻は川に洗濯に、夫はゴブリンの討伐に森に出かけた。
夫は竹のような植物が光っているのを見つける。光の正体を確認するために植物を切ると、そこに現れたのは赤ちゃんだった。
夫婦は赤ちゃんを育てることになった。赤ちゃんは女の子だった。
その子を大切に育てる。
女の子が5歳の時に、彼女がステータス画面を発現させることができるのに気づいてしまう。
2人は王様に子どもが奪われないようにステータス画面が発現することを隠した。
だけど子どもはどんどんと強くなって行く。
大切な我が子が魔王討伐に向かうまでの物語。世界で一番大切なモノを守るために夫婦は奮闘する。世界で一番愛しているモノの幸せのために夫婦は奮闘する。
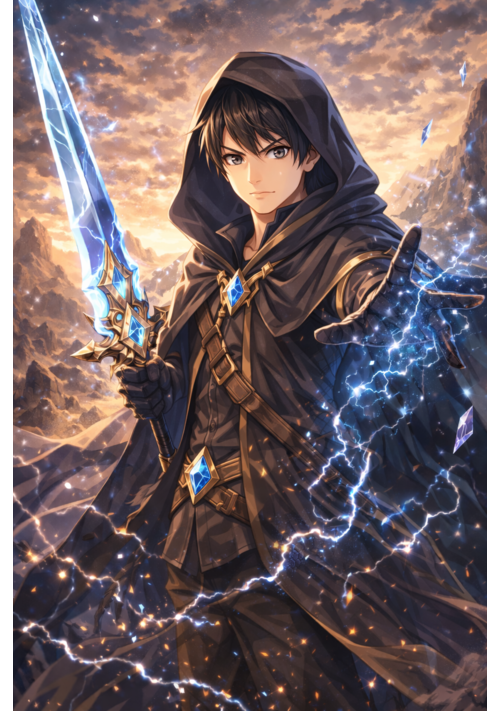
R・P・G ~転生して不死にされた俺は、最強の英雄たちと滅ぼすはずだった異世界を統治する~
イット
ファンタジー
オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の取材中、異世界の大地の女神と接触する。
そのまま半ば強制的に異世界へと転生させられた彼は、惑星そのものと同化し、“星骸の主”として不死の存在へと変貌した。
だが女神から与えられた使命は、この世界の生命を滅ぼし、星を「リセット」すること。
凛人はその命令を、拒否する。
不死であっても無敵ではない。
戦いでは英雄王に殴り倒される始末。しかし一つ選択を誤れば国が滅びる危うい存在。
それでも彼は、星を守るために戦う道を選んだ。
女神の使命を「絶対拒否」する不死者と、裏ボス級の従者たち。
これは、世界を滅ぼさず、統治することを選んだ男の英雄譚である。

ギャルい女神と超絶チート同盟〜女神に贔屓されまくった結果、主人公クラスなチート持ち達の同盟リーダーとなってしまったんだが〜
平明神
ファンタジー
ユーゴ・タカトー。
それは、女神の「推し」になった男。
見た目ギャルな女神ユーラウリアの色仕掛けに負け、何度も異世界を救ってきた彼に新たに下った女神のお願いは、転生や転移した者達を探すこと。
彼が出会っていく者たちは、アニメやラノベの主人公を張れるほど強くて魅力的。だけど、みんなチート的な能力や武器を持つ濃いキャラで、なかなか一筋縄ではいかない者ばかり。
彼らと仲間になって同盟を組んだユーゴは、やがて彼らと共に様々な異世界を巻き込む大きな事件に関わっていく。
その過程で、彼はリーダーシップを発揮し、新たな力を開花させていくのだった!
女神から貰ったバラエティー豊かなチート能力とチートアイテムを駆使するユーゴは、どこへ行ってもみんなの度肝を抜きまくる!
さらに、彼にはもともと特殊な能力があるようで……?
英雄、聖女、魔王、人魚、侍、巫女、お嬢様、変身ヒーロー、巨大ロボット、歌姫、メイド、追放、ざまあ───
なんでもありの異世界アベンジャーズ!
女神の使徒と異世界チートな英雄たちとの絆が紡ぐ、運命の物語、ここに開幕!
※不定期更新。
※感想やお気に入り登録をして頂けますと、作者のモチベーションがあがり、エタることなくもっと面白い話が作れます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















