1 / 9
- 壹 -
迎えを待つ
しおりを挟む
もうすぐ、鐘煕佑が迎えに来る。
それを待ちながら、用綉葩は椅子に腰かけ、夜気に震えていた。
身につけているのは、透ける薄衣一枚だけ。
その姿で、慶邁帝の寝所へと参じるための迎えを待っているのだ。
世界有数の大国のひとつ、晟大帝国の首都の中心にある普照城。
塀に囲まれた広大な敷地には、前面には皇帝の執務室や、それを補助する役所、大広場といったものが並ぶ『前宮』がある。
そして後ろ半分の敷地はプライベートな空間とされ、皇帝の住む主宮を中心にして、各地から集められた后妃たちが、それぞれ与えられた宮に住む『後宮』となっていた。
綉葩が暮らすのは、その宮のひとつ、瑯鑽宮だった。
烋貴人と呼ばれる地位を与えられているが、後宮での階級としては、あまり高くはない。
そのため、主宮からはあまり近くないし、大きさも正妃である皇后の富華宮に比べるとひとまわり小さい。
とはいえ、塀の外に暮らす人々に比べれば、数倍贅沢な暮らしではあった。
ただ、今この瞬間は、その恩恵はあまり関係していなかった。
今いる部屋が、あまりにも寒々としているせいだ。
ここは、宮の最奥にある『待機の間』だった。
この部屋は、皇帝の寝所への廊下へと繋がっている。
そこへの扉がすでに開けられているので、暖房がほとんど役にたっていないのだ。
普段ならうるさいほどに世話をやく侍女たちも、部屋の隅にかしずいているだけで、誰ひとり、近づこうとはしなかった。
沐浴を済ませた後は自分たちの女主人ではなく、あくまで帝ただひとりのものとされるので、彼以外の人間が触れることは許されていないのだ。
ただ、ひとりだけ例外があった。
皇帝の住む主宮の寝室まで、后妃を送り届ける役目の宦官だ。
綉葩の場合、それを担当しているのが、煕佑だった。
昔なら、皇帝が后妃たちそれぞれの住む宮へと、表の路を輿で通ったそうだ。
しかし三代前の寛治帝の時に待ち伏せ事件が起こり、死にかけるほどの大怪我を皇帝が負った。
それ以来、用心のために后妃たちのほうから、裏の廊下を使って帝の寝所へと参じる方式に変わったという。
しかし、それにはひとつ問題があった。
実は后妃たちは、自力でまともに歩くことができない。
後宮へ入るときに通過儀礼として、足の前半分の部分を切られてしまうせいだ。
そのため后妃たちが移動するときには、必ず他人の力や専用の道具が必要だった。
小さな足が美しいとされるうえ、移動に輿や人を使う者こそ高貴だとされるので、自分で歩くための足は必要ない、という理論だった。
だが本当は、後宮から逃げ出すことができないようにするためではないのか。
綉葩はそんな風に考えたこともある。
実際のところ、たしかに後宮に入った后妃の生活は、己自身でする事など、たかが知れていた。
日々の細々としたことや身の回りの世話はすべて女官が取り仕切っている。
そのせいか、むしろ、自分のことを自分でやろうとすると、叱られる始末だった。
我々の仕事を奪い、辞めさせるつもりか、とまで言われれば、引くしかない。
そうなると、綉葩本人がすることといえば、せいぜい凝った刺繍をすることか、窓辺に座って庭を眺めることだけ。
せめて書物でも読もうとしたが、禁じられていると教えられた。
后妃に、皇帝の機嫌を取る以外の知性は必要ない、という理屈だった。
豪勢な料理も、華美な衣装も、はじめこそ心が揺さぶられたものだが、そんな時期はあっという間に過ぎ去った。
あとに残されたのは、退屈を持てあますだけの膨大な無為の時間だった。
この宮に来てから、約二年。
そのあいだ、伽に呼ばれたことは数回しかなかった。
つまり、皇帝からの覚えがめでたいというわけでもない。
そんな存在なのに、一度後宮に入ったなら、もう一生ここから出ることはない。
なんとも虚しい人生だと、綉葩は思う。
他の后妃たちは権勢争いに夢中なようだが、自分はどうにもその手のことは苦手だ。
しかし、この足では逃げ出すこともかなわない。
ここで生き続けていくことを受け入れるしかなかった。
それを待ちながら、用綉葩は椅子に腰かけ、夜気に震えていた。
身につけているのは、透ける薄衣一枚だけ。
その姿で、慶邁帝の寝所へと参じるための迎えを待っているのだ。
世界有数の大国のひとつ、晟大帝国の首都の中心にある普照城。
塀に囲まれた広大な敷地には、前面には皇帝の執務室や、それを補助する役所、大広場といったものが並ぶ『前宮』がある。
そして後ろ半分の敷地はプライベートな空間とされ、皇帝の住む主宮を中心にして、各地から集められた后妃たちが、それぞれ与えられた宮に住む『後宮』となっていた。
綉葩が暮らすのは、その宮のひとつ、瑯鑽宮だった。
烋貴人と呼ばれる地位を与えられているが、後宮での階級としては、あまり高くはない。
そのため、主宮からはあまり近くないし、大きさも正妃である皇后の富華宮に比べるとひとまわり小さい。
とはいえ、塀の外に暮らす人々に比べれば、数倍贅沢な暮らしではあった。
ただ、今この瞬間は、その恩恵はあまり関係していなかった。
今いる部屋が、あまりにも寒々としているせいだ。
ここは、宮の最奥にある『待機の間』だった。
この部屋は、皇帝の寝所への廊下へと繋がっている。
そこへの扉がすでに開けられているので、暖房がほとんど役にたっていないのだ。
普段ならうるさいほどに世話をやく侍女たちも、部屋の隅にかしずいているだけで、誰ひとり、近づこうとはしなかった。
沐浴を済ませた後は自分たちの女主人ではなく、あくまで帝ただひとりのものとされるので、彼以外の人間が触れることは許されていないのだ。
ただ、ひとりだけ例外があった。
皇帝の住む主宮の寝室まで、后妃を送り届ける役目の宦官だ。
綉葩の場合、それを担当しているのが、煕佑だった。
昔なら、皇帝が后妃たちそれぞれの住む宮へと、表の路を輿で通ったそうだ。
しかし三代前の寛治帝の時に待ち伏せ事件が起こり、死にかけるほどの大怪我を皇帝が負った。
それ以来、用心のために后妃たちのほうから、裏の廊下を使って帝の寝所へと参じる方式に変わったという。
しかし、それにはひとつ問題があった。
実は后妃たちは、自力でまともに歩くことができない。
後宮へ入るときに通過儀礼として、足の前半分の部分を切られてしまうせいだ。
そのため后妃たちが移動するときには、必ず他人の力や専用の道具が必要だった。
小さな足が美しいとされるうえ、移動に輿や人を使う者こそ高貴だとされるので、自分で歩くための足は必要ない、という理論だった。
だが本当は、後宮から逃げ出すことができないようにするためではないのか。
綉葩はそんな風に考えたこともある。
実際のところ、たしかに後宮に入った后妃の生活は、己自身でする事など、たかが知れていた。
日々の細々としたことや身の回りの世話はすべて女官が取り仕切っている。
そのせいか、むしろ、自分のことを自分でやろうとすると、叱られる始末だった。
我々の仕事を奪い、辞めさせるつもりか、とまで言われれば、引くしかない。
そうなると、綉葩本人がすることといえば、せいぜい凝った刺繍をすることか、窓辺に座って庭を眺めることだけ。
せめて書物でも読もうとしたが、禁じられていると教えられた。
后妃に、皇帝の機嫌を取る以外の知性は必要ない、という理屈だった。
豪勢な料理も、華美な衣装も、はじめこそ心が揺さぶられたものだが、そんな時期はあっという間に過ぎ去った。
あとに残されたのは、退屈を持てあますだけの膨大な無為の時間だった。
この宮に来てから、約二年。
そのあいだ、伽に呼ばれたことは数回しかなかった。
つまり、皇帝からの覚えがめでたいというわけでもない。
そんな存在なのに、一度後宮に入ったなら、もう一生ここから出ることはない。
なんとも虚しい人生だと、綉葩は思う。
他の后妃たちは権勢争いに夢中なようだが、自分はどうにもその手のことは苦手だ。
しかし、この足では逃げ出すこともかなわない。
ここで生き続けていくことを受け入れるしかなかった。
0
あなたにおすすめの小説

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

愛人を選んだ夫を捨てたら、元婚約者の公爵に捕まりました
由香
恋愛
伯爵夫人リュシエンヌは、夫が公然と愛人を囲う結婚生活を送っていた。
尽くしても感謝されず、妻としての役割だけを求められる日々。
けれど彼女は、泣きわめくことも縋ることもなく、静かに離婚を選ぶ。
そうして“捨てられた妻”になったはずの彼女の前に現れたのは、かつて婚約していた元婚約者――冷静沈着で有能な公爵セドリックだった。
再会とともに始まるのは、彼女の価値を正しく理解し、決して手放さない男による溺愛の日々。
一方、彼女を失った元夫は、妻が担っていたすべてを失い、社会的にも転落していく。
“尽くすだけの妻”から、“選ばれ、守られる女性”へ。
静かに離婚しただけなのに、
なぜか元婚約者の公爵に捕まりました。

元公爵令嬢は年下騎士たちに「用済みのおばさん」と捨てられる 〜今更戻ってこいと泣きつかれても献身的な美少年に溺愛されているのでもう遅いです〜
日々埋没。
ファンタジー
「新しい従者を雇うことにした。おばさんはもう用済みだ。今すぐ消えてくれ」
かつて婚約破棄され、実家を追放された元公爵令嬢のレアーヌ。
その身分を隠し、年下の冒険者たちの身の回りを世話する『メイド』として献身的に尽くしてきた彼女に突きつけられたのは、あまりに非情な追放宣告だった。
レアーヌがこれまで教育し、支えてきた若い男たちは、新しく現れた他人の物を欲しがり子悪魔メイドに骨抜きにされ、彼女を「加齢臭のする汚いおばさん」と蔑み、笑いながら追い出したのだ。
地位も、居場所も、信じていた絆も……すべてを失い、絶望する彼女の前に現れたのは、一人の美少年だった。
「僕とパーティーを組んでくれませんか? 貴方が必要なんです」
新米ながら将来の可能性を感じさせる彼は、レアーヌを「おばさん」ではなく「一人の女性」として、甘く狂おしく溺愛し始める。
一方でレアーヌという『真の支柱』を失った元パーティーは、自分たちがどれほど愚かな選択をしたかを知る由もなかった。
やがて彼らが地獄の淵で「戻ってきてくれ」と泣きついてきても、もう遅い。
レアーヌの隣には、彼女を離さないと誓った執着愛の化身が微笑んでいるのだから。

人間嫌いの狐王に、契約妻として嫁いだら溺愛が止まりません
由香
ファンタジー
人間嫌いで知られる狐族の王・玄耀に、“契約上の妻”として嫁いだ少女・紗夜。
「感情は不要。契約が終われば離縁だ」
そう告げられたはずなのに、共に暮らすうち、冷酷な王は彼女だけに甘さを隠さなくなっていく。
やがて結ばれる“番”の契約、そして王妃宣言――。
契約結婚から始まる、人外王の溺愛が止まらない和風あやかし恋愛譚。


どうやらお前、死んだらしいぞ? ~変わり者令嬢は父親に報復する~
野菜ばたけ@既刊5冊📚好評発売中!
ファンタジー
「ビクティー・シークランドは、どうやら死んでしまったらしいぞ?」
「はぁ? 殿下、アンタついに頭沸いた?」
私は思わずそう言った。
だって仕方がないじゃない、普通にビックリしたんだから。
***
私、ビクティー・シークランドは少し変わった令嬢だ。
お世辞にも淑女然としているとは言えず、男が好む政治事に興味を持ってる。
だから父からも煙たがられているのは自覚があった。
しかしある日、殺されそうになった事で彼女は決める。
「必ず仕返ししてやろう」って。
そんな令嬢の人望と理性に支えられた大勝負をご覧あれ。

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。
沼野 花
恋愛
私は、夫にも子供にも選ばれなかった。
その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。
そこで待っていたのは、最悪の出来事――
けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。
夫は愛人と共に好きに生きればいい。
今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。
でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。
妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。
過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――
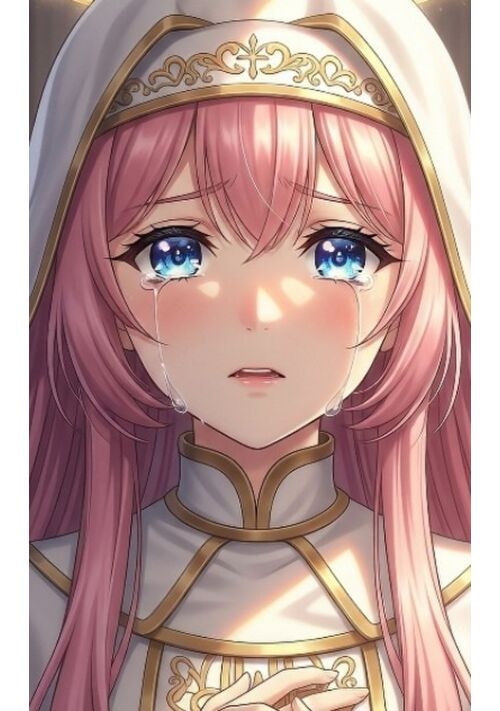
聖女は聞いてしまった
夕景あき
ファンタジー
「道具に心は不要だ」
父である国王に、そう言われて育った聖女。
彼女の周囲には、彼女を心を持つ人間として扱う人は、ほとんどいなくなっていた。
聖女自身も、自分の心の動きを無視して、聖女という治癒道具になりきり何も考えず、言われた事をただやり、ただ生きているだけの日々を過ごしていた。
そんな日々が10年過ぎた後、勇者と賢者と魔法使いと共に聖女は魔王討伐の旅に出ることになる。
旅の中で心をとり戻し、勇者に恋をする聖女。
しかし、勇者の本音を聞いてしまった聖女は絶望するのだった·····。
ネガティブ思考系聖女の恋愛ストーリー!
※ハッピーエンドなので、安心してお読みください!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















