1 / 77
1.コンニャク妖怪と巫女の謎
1-1
しおりを挟む
巨大なコンニャクの妖怪が、太くて長い腕を野球のバットのように大きくスイングさせる。刀を振りかざして飛びかかってきた侍の胴を横からなぎ払うと、そのまま野球のボールみたいに吹き飛ばしてしまった。
「メイくん!」
思わず現実世界でのニックネームをさけびながら後を追った僕の目の前で、侍がべしゃりと音を立てながら落下する。普通なら大事故だし、大けがをしているところだ。けれど、地面に仰向けに転がった侍は空を見上げたまま、自分がホームランになったことなど忘れたかのように淡々と口を開いた。
「こらこら。オンラインで軽々しく個人情報を口に出すなって、先生にも言われたでしょ。オレのことは、ちゃんとシュレットガルドさんと呼んでくださいよ」
「長いんだってば。前も聞いたと思うけど、もう一回だけ聞いてもいい? このゲームは和風の世界観なのに、どうしてメイくんのアバターは名前も見た目も外国人風なの?」
「オレも何度も答えたと思うけど、もう一回だけ答えとくよ。金髪で青い目のサムライが、今のオレのマイブームなんだって。だいたい、そっちこそどうなの」
それを言われてしまうと、僕はのどを空気の固まりでふさがれたかのように言葉が出なくなってしまう。
だって知らなかったんだ。このゲームのアバターが、自分が心の底から望んでいる姿を投影して自動的に作られてしまうなんて。それを知っていたら――いや、それでこの姿になることを事前に知っていたら、僕はこのゲームを絶対にやらなかったのに。
「って、のんきに話してる場合じゃなかった。早く立って、メイくん。コンニャク妖怪が、またこっちに来るよ」
「あー、無理。今ので瀕死になった」
「えっ」
慌てた僕は眼球だけを左側に動かして、視界の隅を確認する。そこには、ほんのりと淡い光を帯びた半透明の図形が浮かび上がっていた。細長い四角の中に、文字や数字が敷きつめられている。
一般的にステータスウインドウと呼ばれる、ゲームではおなじみのシステムだ。自分やパーティを組んでいる仲間の情報がひと目でわかるように常に表示されている。もうその状態にも慣れてしまったので、邪魔だと思うことはない。
シュレットガルドという名前の下にある細長いゲージは残りわずかで消えてしまうところまで減っていて、色も緑から赤に変わっていた。これは体力が少なくて危険な状態だということを表している。
コンニャク妖怪との戦闘前には、たしかに僕がメイくんを回復してゲージを満タンにしたはず。つまり、あのたった一撃で、ここまでのダメージを受けてしまったということになる。フニャフニャのコンニャクとは思えない、おそるべき破壊力だ。
「……うわー、こわ。前衛職のメイくんがこれなら、僕が攻撃を受けていたら完全に戦闘不能だったよ。やっぱり、コンニャク妖怪と戦うのは早かったんだって」
「んー。塗り壁はまだ無理でも、塗り壁の亜種くらいなら倒せると思ったのに」
「僕たち、レベル十になったばかりだよ? どうして討伐推奨レベル二十のコンニャク妖怪に挑戦しようと思えたの?」
「レベルの差が二倍ってことは、相手より二倍オレが頑張れば勝てるってことでしょ?」
「ごめん、ちょっとよくわからない」
ステータス上では《瀕死》――死んでしまう寸前という意味。もちろん、現実の自分が本当に死んでしまったりはしない――という状態異常にかかっているメイくんだけど、そもそもゲームなので痛みは感じない。体を動かしにくくなるというペナルティはあるものの、本人はいたって元気だ。回復系の処置を行って、ゲージを赤から緑に戻してあげれば、すぐになんでもなかったように飛び起きるだろう。
そのために、やらなければいけないことがある。僕はちらりと首をめぐらせて、周囲の様子を確認した。
「メイくん!」
思わず現実世界でのニックネームをさけびながら後を追った僕の目の前で、侍がべしゃりと音を立てながら落下する。普通なら大事故だし、大けがをしているところだ。けれど、地面に仰向けに転がった侍は空を見上げたまま、自分がホームランになったことなど忘れたかのように淡々と口を開いた。
「こらこら。オンラインで軽々しく個人情報を口に出すなって、先生にも言われたでしょ。オレのことは、ちゃんとシュレットガルドさんと呼んでくださいよ」
「長いんだってば。前も聞いたと思うけど、もう一回だけ聞いてもいい? このゲームは和風の世界観なのに、どうしてメイくんのアバターは名前も見た目も外国人風なの?」
「オレも何度も答えたと思うけど、もう一回だけ答えとくよ。金髪で青い目のサムライが、今のオレのマイブームなんだって。だいたい、そっちこそどうなの」
それを言われてしまうと、僕はのどを空気の固まりでふさがれたかのように言葉が出なくなってしまう。
だって知らなかったんだ。このゲームのアバターが、自分が心の底から望んでいる姿を投影して自動的に作られてしまうなんて。それを知っていたら――いや、それでこの姿になることを事前に知っていたら、僕はこのゲームを絶対にやらなかったのに。
「って、のんきに話してる場合じゃなかった。早く立って、メイくん。コンニャク妖怪が、またこっちに来るよ」
「あー、無理。今ので瀕死になった」
「えっ」
慌てた僕は眼球だけを左側に動かして、視界の隅を確認する。そこには、ほんのりと淡い光を帯びた半透明の図形が浮かび上がっていた。細長い四角の中に、文字や数字が敷きつめられている。
一般的にステータスウインドウと呼ばれる、ゲームではおなじみのシステムだ。自分やパーティを組んでいる仲間の情報がひと目でわかるように常に表示されている。もうその状態にも慣れてしまったので、邪魔だと思うことはない。
シュレットガルドという名前の下にある細長いゲージは残りわずかで消えてしまうところまで減っていて、色も緑から赤に変わっていた。これは体力が少なくて危険な状態だということを表している。
コンニャク妖怪との戦闘前には、たしかに僕がメイくんを回復してゲージを満タンにしたはず。つまり、あのたった一撃で、ここまでのダメージを受けてしまったということになる。フニャフニャのコンニャクとは思えない、おそるべき破壊力だ。
「……うわー、こわ。前衛職のメイくんがこれなら、僕が攻撃を受けていたら完全に戦闘不能だったよ。やっぱり、コンニャク妖怪と戦うのは早かったんだって」
「んー。塗り壁はまだ無理でも、塗り壁の亜種くらいなら倒せると思ったのに」
「僕たち、レベル十になったばかりだよ? どうして討伐推奨レベル二十のコンニャク妖怪に挑戦しようと思えたの?」
「レベルの差が二倍ってことは、相手より二倍オレが頑張れば勝てるってことでしょ?」
「ごめん、ちょっとよくわからない」
ステータス上では《瀕死》――死んでしまう寸前という意味。もちろん、現実の自分が本当に死んでしまったりはしない――という状態異常にかかっているメイくんだけど、そもそもゲームなので痛みは感じない。体を動かしにくくなるというペナルティはあるものの、本人はいたって元気だ。回復系の処置を行って、ゲージを赤から緑に戻してあげれば、すぐになんでもなかったように飛び起きるだろう。
そのために、やらなければいけないことがある。僕はちらりと首をめぐらせて、周囲の様子を確認した。
0
あなたにおすすめの小説

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

黒地蔵
紫音みけ🐾書籍発売中
児童書・童話
友人と肝試しにやってきた中学一年生の少女・ましろは、誤って転倒した際に頭を打ち、人知れず幽体離脱してしまう。元に戻る方法もわからず孤独に怯える彼女のもとへ、たったひとり救いの手を差し伸べたのは、自らを『黒地蔵』と名乗る不思議な少年だった。黒地蔵というのは地元で有名な『呪いの地蔵』なのだが、果たしてこの少年を信じても良いのだろうか……。目には見えない真実をめぐる現代ファンタジー。
※表紙イラスト=ミカスケ様

クールな幼なじみの許嫁になったら、甘い溺愛がはじまりました
藤永ゆいか
児童書・童話
中学2年生になったある日、澄野星奈に許嫁がいることが判明する。
相手は、頭が良くて運動神経抜群のイケメン御曹司で、訳あって現在絶交中の幼なじみ・一之瀬陽向。
さらに、週末限定で星奈は陽向とふたり暮らしをすることになって!?
「俺と許嫁だってこと、絶対誰にも言うなよ」
星奈には、いつも冷たくてそっけない陽向だったが……。
「星奈ちゃんって、ほんと可愛いよね」
「僕、せーちゃんの彼氏に立候補しても良い?」
ある時から星奈は、バスケ部エースの水上虹輝や
帰国子女の秋川想良に甘く迫られるようになり、徐々に陽向にも変化が……?
「星奈は可愛いんだから、もっと自覚しろよ」
「お前のこと、誰にも渡したくない」
クールな幼なじみとの、逆ハーラブストーリー。

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。
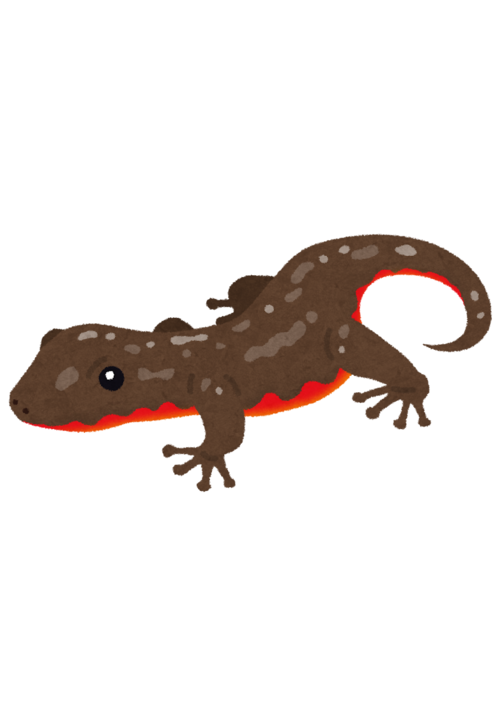

【完結】夫に穢された純愛が兄に止めを刺されるまで
猫都299
児童書・童話
タイムリープしたかもしれない。中学生に戻っている? 夫に愛されなかった惨めな人生をやり直せそうだ。彼を振り向かせたい。しかしタイムリープ前の夫には多くの愛人がいた。純愛信者で奥手で恋愛経験もほぼない喪女にはハードルが高過ぎる。まずは同じ土俵で向き合えるように修行しよう。この際、己の理想もかなぐり捨てる。逆ハーレムを作ってメンバーが集まったら告白する! 兄(血は繋がっていない)にも色々教えてもらおう。…………メンバーが夫しか集まらなかった。
※小説家になろう、カクヨム、アルファポリス、Nolaノベル、Tales、ツギクルの6サイトに投稿しています。
※ノベルアップ+にて不定期に進捗状況を報告しています。
※文字数を調整した【応募版】は2026年1月3日より、Nolaノベル、ツギクル、ベリーズカフェ、野いちごに投稿中です。
※2026.1.5に完結しました! 修正中です。

アリアさんの幽閉教室
柚月しずく
児童書・童話
この学校には、ある噂が広まっていた。
「黒い手紙が届いたら、それはアリアさんからの招待状」
招かれた人は、夜の学校に閉じ込められて「恐怖の時間」を過ごすことになる……と。
招待状を受け取った人は、アリアさんから絶対に逃れられないらしい。
『恋の以心伝心ゲーム』
私たちならこんなの楽勝!
夜の学校に閉じ込められた杏樹と星七くん。
アリアさんによって開催されたのは以心伝心ゲーム。
心が通じ合っていれば簡単なはずなのに、なぜかうまくいかなくて……??
『呪いの人形』
この人形、何度捨てても戻ってくる
体調が悪くなった陽菜は、原因が突然現れた人形のせいではないかと疑いはじめる。
人形の存在が恐ろしくなって捨てることにするが、ソレはまた家に現れた。
陽菜にずっと付き纏う理由とは――。
『恐怖の鬼ごっこ』
アリアさんに招待されたのは、美亜、梨々花、優斗。小さい頃から一緒にいる幼馴染の3人。
突如アリアさんに捕まってはいけない鬼ごっこがはじまるが、美亜が置いて行かれてしまう。
仲良し3人組の幼馴染に一体何があったのか。生き残るのは一体誰――?
『招かれざる人』
新聞部の七緒は、アリアさんの記事を書こうと自ら夜の学校に忍び込む。
アリアさんが見つからず意気消沈する中、代わりに現れたのは同じ新聞部の萌香だった。
強がっていたが、夜の学校に一人でいるのが怖かった七緒はホッと安心する。
しかしそこで待ち受けていたのは、予想しない出来事だった――。
ゾクッと怖くて、ハラハラドキドキ。
最後には、ゾッとするどんでん返しがあなたを待っている。

【もふもふ手芸部】あみぐるみ作ってみる、だけのはずが勇者ってなんなの!?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
網浜ナオは勉強もスポーツも中の下で無難にこなす平凡な少年だ。今年はいよいよ最高学年になったのだが過去5年間で100点を取ったことも運動会で1等を取ったこともない。もちろん習字や美術で賞をもらったこともなかった。
しかしそんなナオでも一つだけ特技を持っていた。それは編み物、それもあみぐるみを作らせたらおそらく学校で一番、もちろん家庭科の先生よりもうまく作れることだった。友達がいないわけではないが、人に合わせるのが苦手なナオにとっては一人でできる趣味としてもいい気晴らしになっていた。
そんなナオがあみぐるみのメイキング動画を動画サイトへ投稿したり動画配信を始めたりしているうちに奇妙な場所へ迷い込んだ夢を見る。それは現実とは思えないが夢と言うには不思議な感覚で、沢山のぬいぐるみが暮らす『もふもふの国』という場所だった。
そのもふもふの国で、元同級生の丸川亜矢と出会いもふもふの国が滅亡の危機にあると聞かされる。実はその国の王女だと言う亜美の願いにより、もふもふの国を救うべく、ナオは立ち上がった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















