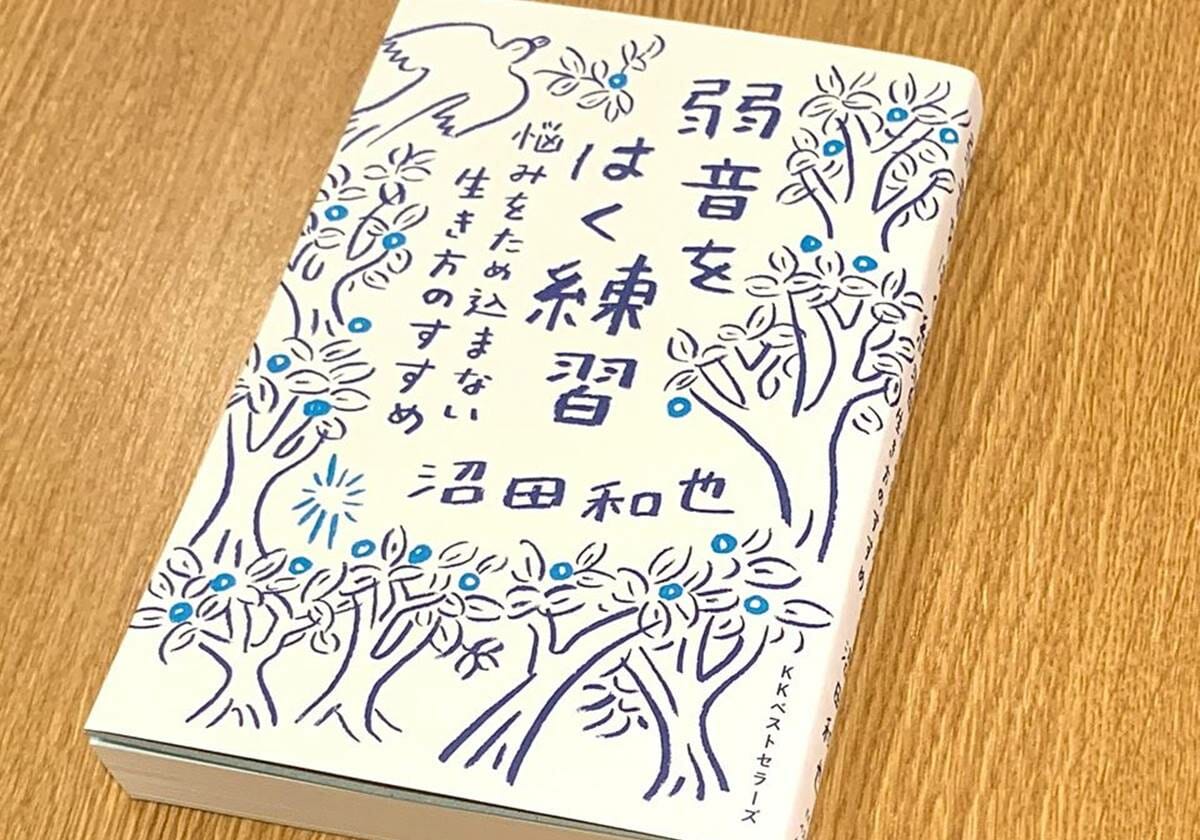
“無”通勤の時代、首都圏の郊外衛星都市に脚光…立川、八王子、浦和、大宮、船橋など
2021.01.18
ビジネスジャーナル

コロナ禍は依然として終息の気配を見せないなか、この冬場に再び大流行する予兆すら見せている。緊急事態宣言が発せられた今春の頃に比べれば、人々は冷静にコロナに対処しているようにも見えるが、当初言われたような早期終息と、その後の経済のV字回復といった楽観的なシナリオを語る人は少なくなった。
今後もある程度の期間、コロナと否が応でも付き合わざるを得なくなった状況下、日本社会や社会インフラを構成する不動産はどのようになっていくのであろうか。
コロナ禍は、訪日外国人(インバウンド)などの観光客で潤っていた宿泊業や、飛行機、鉄道などの輸送業、物販飲食業などに大きな影響を与えてきた。人々が移動すること、外に出て歩き回ることをやめた結果、当然のことながらこうした業種に影響が出ることは理解しやすい。
だが、コロナは感染症のひとつであり、これまでの歴史を振り返っても、おおむね1年から2年程度で終息している。中小資本にとっては茨の道だが、ここは我慢の時である。インバウンドが昨年並みの3000万人程度に戻るにはおそらく3年程度かかるとみてよい。日本は島国なので、インバウンドのほとんどは飛行機でやってくる。コロナが終息しても海外の航空会社の多くが機材を売り払い、多くのパイロットやキャビンアテンダントの首を切っているため、回復には若干のタイムラグが出るだろうが、いずれにしても需要は復活するとみて間違いはない。
コロナ禍の影響として今後もっとも注目したいのは、人々の「働く」ということに対する意識の変化である。緊急事態宣言が解除されたのち、一部の企業では社員が会社に戻り、通常業務を行うようになったいっぽうで、IT系、情報通信、ソフトウェア系の企業を中心に、業務を全部、または多くを在宅勤務にし、コロナとは関係なく、働き方そのものを変えてしまう企業が続出している。こうした企業はさっさとオフィスを解約または縮小移転している。IT系のテナントが集積する渋谷区のオフィスマーケットで11月の空室率がついに5%を上回る大幅な上昇をみせていることからも、その傾向がうかがえる。
だが、働き方の変化は何も中小のIT系企業だけに起こっている現象ではない。大手企業でも、現在も社員の多くが在宅勤務を続けるか、または社員をシフト制にして週2回、あるいは月数回程度の勤務体制を崩さず、今後もそうした勤務体制を継続する企業が増えている。とりわけ、法律や会計系の事務所やコンサルティング会社などにはこの傾向は顕著で、都心の大型オフィスビルに複数階を賃借している企業の中には、今後賃貸借契約の期限を迎えるにしたがってオフィス床を順次解約または賃借面積を減じていくことは避けられそうにない。
「会社ファースト」から「生活ファースト」へ
ポスト・コロナにおいて、都心に「通勤」しなくてもよいという社会がどうやら到来しそうなのである。通勤をしない、あるいは、たまにしかしないというと、人々はこれからどこに家を求めるようになるだろうか。これまでは夫婦共働きであれば、とにかく会社に通勤しやすいという観点から家選びを行ってきた。いわば「会社ファースト」の家選びだ。都心に近い湾岸部などで既存の工場がアジアなどに移転したり撤退した跡地に建つタワーマンションなどがその好例だ。
ところが今後は、夫婦は自宅ないしは近所のコワーキング施設で働けばよく、子供も近所に保育所があれば、そこに預ける。通勤という行為に毎日往復で1時間半や2時間も費やしていた時間を子供との時間や自分の趣味の時間に充当できる。それならば、地価の高い都心部よりも郊外の自然環境の良いエリアの家を選ぶようになるのは自然な流れだろう。





























