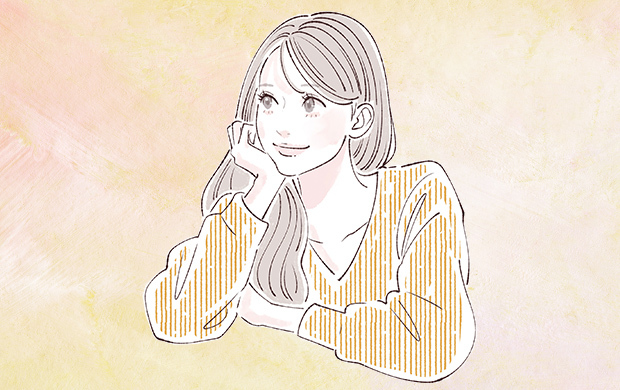仙台駅前が“巨大な空き地”に…全国で進む「大型再開発の停止ドミノ」の真相
2025.11.18
ビジネスジャーナル
こうした事例に共通するのは、“建て替えをする合理性”が崩れていることである。老朽化による更新需要があっても、建設費高騰や人手不足、需要の不確実性が事業計画を簡単に不成立へと追い込んでしまう。かつては自治体やデベロッパーの強い意志によって推進できた大型再開発も、今や“やりたくてもできない”状況に変わった。仙台駅前の“空地化”は、この全国的な潮流と明確に同じ線上にある」(不動産アナリスト・秋田智樹氏)
計画が成り立たなくなる「建設費の急騰」と「人手不足」
建設業界が今回の現象の最大要因として口をそろえるのが、建設費の急激な上昇だ。資材価格は2021年以降、鋼材を中心に高騰し、ピーク時には60%近い値上がりを記録した。労務費も10年間で3割超上昇し、円安の影響も加わり、マンション・ホテル・オフィスといった大型建築の総工費は、2015年比で4~5割増になっている。
「これほど建設費が跳ね上がると、どれほど立地が優れていても採算計画が成り立ちにくい。仙台駅前のような一等地であっても、建設費が数十億~数百億円単位で膨らむと、テナント家賃や商業収益での回収が困難になる。特にPPIHは小売利益で採算を組むため、建設コストの増加分を家賃に転嫁しづらい。2020年時点で想定した建設費と、2024~25年の実勢価格では、もはや別次元の数字になっていた可能性が高い」(同)
建設費高騰に輪をかけているのが、深刻な人手不足である。技能労働者の平均年齢は高く、55歳以上が3割を占める一方、29歳以下は1割しかいない。高齢化と新規参入の低調によって業界全体の施工能力は低下している。
さらに2024年からは建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、いわゆる「2025年の崖」が顕在化した。従来のように、繁忙期に長時間労働で対応するやり方が不可能になったことで、施工体制そのものが制約されている。ゼネコン各社は無理な受注を控えるようになり、複数の大型プロジェクトを並行して処理する能力が制限されている。
仙台駅前クラスの大規模再開発では、長期にわたり大量の技能者を確保する必要がある。しかし現実には、地方都市で150メートル級の高層建築のための人員を確実に確保できる保証はなく、工期遅延によるコスト膨張リスクは過去に例がないほど高まっている。
不動産需要の変化…「何を建てても儲からない」時代へ
かつての駅前再開発は、オフィス・商業・ホテルなどどれを建てても需要があり、建てた分だけ価値が高まる時代だった。しかし現在は潮目が大きく変わった。企業のリモートワーク定着により、地方都市を含むオフィス需要は伸び悩んでいる。商業施設は、ネット通販の拡大でテナント誘致の難易度が上がった。ホテルはインバウンド復調で表面上活況に見えるが、建設費の高騰で経済性が成立しにくい。
需要の鈍化と建設費の異常な膨張が同時進行する中で、「建てれば価値が出る」時代は終わった。再開発が成立するのは、本当に収支が成立する一部の案件だけになりつつある。仙台駅前も例外ではなく、「用途変更しても採算が合わない」という深刻なジレンマに直面したと考えられる。
ここまでの状況を踏まえると、PPIHが再開発を断念した理由は、単なる企業側の都合ではなく、むしろ合理的な判断に見えてくる。土地取得費や解体費を既に支出しているとはいえ、建設費のさらなる上昇や人員確保の不確実性を考えれば、「撤退する損失」と「継続するリスク」を比較したとき、後者の方が大きいと判断した可能性が高い。
実際、業界関係者の間では、「いま最も危険なのは、大型プロジェクトを強引に続けること」という声が多い。収支計画が崩れたにもかかわらず着工すれば、途中で資金がショートしたり、工期が大幅に遅れたりするリスクがある。PPIHは、こうした負のスパイラルに入る前に撤退を選んだと解釈できる。