16 / 31
第四章(1)
しおりを挟む
彰は自宅のパソコンで、友哉と打ち合わせをしていた。
「――っていう、ことなんだけど、プログラムは組めそうか?」
『どこまで要望通りにできるかは分からないけど、一応やってみるよ』
「そうか、助かる」
友哉はいつでもこちらの希望に添ったものを出してくれる。ただ本人が完璧主義者なので、締め切りに関してはかなりコントロールする必要がある。システムを組むのは突き詰めようと思えばいくらでも時間がかかってしまう分野だということを、友哉との付き合いで学んだ。
「それはそれとしてさ。お前、好きな奴いないのか?」
『あ? 何、いきなり? その顔すげーウザいんだけど』
「その顔ってなんだよ」
彰としては真面目な顔をしていたつもりだったのだが。
『高校の時にフられた子とうまくいっててチョー機嫌のいい顔』
「どんな顔だよ」
『うーん。オスの顔?』
「っ!」
すんぜんのところでコーヒーを飲んだから良かったものの、一つ間違ってたらパソコンめがけコーヒーを吹き出していたところだ。
『でもお前もそういう顔するんだ。女に全く興味がなかったくせに』
「女に興味はない。興味があるのは由季だけだ」
『はいはい。ごちそうさま。じゃ、お前のその顔、見続けるのウザすぎだから切る」
――そうか。俺、オスの顔してたか……。
由季を愛しくてたまらない。時間さえ許せば二十四時間、彼女を抱いていたい。
そんなことを提案したら怒られるだろうが。
――由季になら怒られたいな。
そんな変態めいたことを、つい考えてしまう。
「はぁ。由季と数日で良いから一緒に過ごしたい」
旅行を提案してみようか。いや、由季はフリーランスだ。おいそれと旅行に出かけるのは難しかったりするかもしれない。
――待てよ……。
彰の頭にとあるアイディアが浮かぶ。これだったら由季も断れないはず。
彰はすぐにその下準備を進めるため、メールを送る。
送信した直後、スマホが着信を知らせる。
「はい」
誰かも確認せず、反射的に出てしまう。業者だったら面倒だなと頭の片隅で考える。
『彰? 今大丈夫?』
「由季か!」
つい大きな声が出てしまい、電話の向こうで由季は「び、びっくりした……」とぽつりと呟く。
「悪い。つい。今、お前のことを考えてたから」
『私のことってどんなこと?』
「お前に怒られたいな、とか?」
『……もう二度とそんな変なことを考えないで』
「難しいけど、善処する。それで、どうした?」
『この間のパーティー、連れて行ってくれてありがとう。実はあそこで名刺を渡したいくつかの会社からライティングの仕事をもらえて……』
「良かったじゃないか」
自分のことのように嬉しかった。
『うん。それでお礼がてら、何かして欲しいことはないかなって』
「何でも?」
自然と口元が緩んだ。
『え、エッチなこと以外なら……』
「なんだよ、エッチなこと考えてたのか?」
『そうじゃないけど! ……あ、彰なら考えそうだなって』
「ちょっと考えた。でも普通にデートがしたいな。明後日の夜はどうだ?」
『大丈夫。デートってレイトショーとか?』
「映画なぁ」
『駄目?』
「駄目じゃないけど、せっかくお前と出かけるんだからもっと話せる場所が良いな。水族館はどうだ?」
『……夜に?』
「そう。夜だけの特別なイベントもやってるみたいだし、それに……思い出さないか? 俺たちの初デート。水族館だっただろ?」
『覚えてる。私が夏期講習帰りに合流して……』
「あの頃の気持ちが思い出せて若返りそうじゃないか?」
由季が笑う。
『もう、私たちはまだ若いよ。分かった。じゃあ、水族館で決まりね』
「よし。詳しいスケジュールはまた後で送る。じゃあ、楽しみにしてる」
『私も』
――水族館デートか。あの時はがらにもなく緊張したんだよな。私服姿の由季を初めて見たのはあの時か。
シアーストライプシャツにデニム姿。普段の制服姿とは雰囲気ががらっと変わった服装で可愛かった。
※
午後六時半。
待ち合わせの水族館前に由季はシフォンプリーツのブラウスに、パンツ姿で現れた。
彰は仕事帰りだから、スーツ姿。
「ごめん、待った?」
「いや。そうでもない」
手を繋ぎ、オンラインチケットで館内に入る。外の蒸し暑さが嘘のように涼しい。
普段は暖色系のライトアップなのだろうが、夜は照明全体が控えめで、ブルーのLEDライトで水槽が照らされる。
場内の照明が落とされたことで、水族館のぼんやりとした明かりの中を泳ぐ魚たちのシルエットがより幻想的に見える。
「展示そのものは昼間と同じみたいだけど、私が知ってる水族館とはぜんぜん雰囲気がちがう」
まるで自分たちまで、静かな深い海の底にいるような気持ちになった。
「お、ホオジロザメ」
大きな影が、由季たちの体を横切る。小魚たちの群れがさあっと左右に散っていく。
「うわ、すごい迫力……」
――ち、近い。
彰は由季に寄り添うように一緒に大型水槽を見ているのだが、手を繋いだまま、背後から彰に抱きしめられているような格好だった。
館内の照明が絞られているし、入場者もそれほどいないということもあってか、誰も由季たちを気にしてはいない。
「ちょっと、彰ってば」
「どうした?」
「ち、近すぎるよ……」
「腕が寒そうだなって思ったから、温めてたんだけどな」
「だ、大丈夫」
「ふうん、残念」
「……普通そう言ったら離れると思うんだけど」
「つれいないなぁ」
彰は苦笑し、しぶしぶ離れる。でも決して手は離さない。というよりさっきまでは普通に繋いでいるだけだったのに、今はしっかり指を絡めている。
「……これは注意されないのか」
「ふ、ふざけてるなら」
「ペンギンだぞ、ペンギン」
「もう……」
ペンギンゾーンも綺麗にライトアップされている。
「ケープペンギンだね。見て。あのよちよち歩き。本当ペンギンって癒される」
陸でひょこひょこ歩いてたと思えば、海に行くと弾丸のように突き進む。そのギャップがまた可愛い。
まるで彰みたいだなと思う。由季と一緒にいる時は飄々として掴み所がないのに、ビジネスの時の目つきはとても鋭く、格好いい。
次はクラゲエリア。
筒型の水槽にいろいろな種類のクラゲが浮いているのだが、そこはついっさきのエリアとは違って、赤や緑、オレンジなど原色のLEDのイルミネーションによって、鮮やかにライトアップされている。
ライトアップの中を、半透明のクラゲがふわふわと舞うように漂う様子は、それだけで絵になった。
「んー。クラゲも良いなぁ。癒される~」
「だな」
「もう、さっきからリアクション薄いよ。ごめんね。一人で盛り上がってて」
「そんなことない。俺だって楽しんでる」
「でもさっきから彰、私の顔ばっかり見てない? ちゃんと水槽を見てる?」
「まあ、目の端で。俺は海の生き物より、大好きな人の観察のほうが性に合ってるみたいだ。ペンギンやクラゲより由季のほうがずっとずっと興味をそそられる」
「!」
「……赤いLEDが反射してるみたいだぞ。顔が真っ赤だ」
「か、からかわないでったら……」
彰は腕を組み、訳知り顔でうなずく。
「由季の専門家として、今はかなり照れてるな?」
「いつから私の専門家になったのよ」
「はじめて付き合った時から、かな?」
「もう」
悪い、と彰はまったく悪びれずに微笑む。
彰の一言にいちいち反応してしまう自分がとてつもなく恥ずかしかった。
さらに進むと、『ナイトイルカショー』という掲示があった。
「せっかくだから見ていくか」
「うん!」
すり鉢状にもうけられた座席の半ばあたりに席を確保する。
ショーの開始時刻を迎えると、軽快な音楽と一緒にイルカたちが、トレーナーの人たちと一緒に入ってくる。
同時に、天井から滝のように大量の水が降り注ぐ。
――何?
昼間のイルカショーでは見たことがない演出だ。
その時、LEDライトが反射し、その水で出来た壁に映像が投影される。
「これって……」
「プロジェクションマッピングってやつだな」
青や赤、黄色などの色で映し出される映像は、無数の魚たち。
トレーナーの指示に合わせ、大ジャンプを決めたイルカが魚たちの群れめがけ飛びかかる。イルカたちの動きに合わせ、映像が切り替わる。
空だったり、宇宙だったり。まるでイルカが飛んでいるかのような印象を受ける。
「すごい!」
今日一の興奮の声をあげ、由季は目を輝かせた。
さらにライトがイルカのつるつるした体に当たって、イルカを七色に輝かせる。
童話の世界にでも迷い込んだような光景だ。
三十分のショーがあっという間だ。
「すごい満足!」
イルカショーが終わっても、なかなか興奮が冷めやらなかった。
彰もこれまでとはリアクションが違っていた。
「甘く見てたな。ただの夜の水族館だろって思ってたけど……あんな隠し球もあったのか」
「すごく綺麗だったよね。プロジェクションマッピングまで使ってるとか、イルカショーも最先端かぁ」
「夜だからこそできることだよな」
「ほんとう。楽しかったぁ!」
「まだ終わりじゃないけどな」
「まだ見るものあったっけ?」
彰に手を引かれて向かったのは、一階にあるカフェ。
カフェ全体も照明が絞られ、カフェというよりバーの雰囲気だ。
そしてクラシックだろうか、落ち着いた曲がうっすらと流れていた。
カフェでは、夕方以降限定のカクテルを飲むことができるらしい。
彰はブルーキュラソーをつかったイルカをモチーフにしたカクテルを、由季はホワイトラムをベースにしたベルーガをモチーフにしたカクテルをそれぞれ注文する。
夜はどうやらテーブル席の間隔が昼間より開いているらしく照明が絞られていることもあいまって、まるで個室にいるような気分になった。
カフェにも小さな水槽が備え付けられていて、そこにはクマノミとチンアナゴが飼育されていた。
「乾杯」
グラスをそっと打ち付け合う。
「ん、美味しい」
「俺のも飲んでみるか?」
「うん。じゃあ、私のも」
交換して飲んでみる。
「はぁ。オレンジの良い香り。夏って感じでこっちも好き」
「由季のほうは甘く仕立てられるな。底にあるのは、ベリーか」
「ま、結局はどっちも美味しいってことよね」
カクテルを味わい、そうし水族館を後にした。
「明日も平日じゃなかったら……このままお前をマンションに連れ去りたいんだけどな」
「……怒られたい?」
「うん、悪くない」
彰は大真面目に頷く。
「……そうだった。この間、私に怒られたいとか想像してたんだっけ」
彰はタクシーを止め、一緒に乗った。最初に距離の近い由季の自宅へ寄ってもらう。
彰は色々と言っていたけどタクシー代をしっかり支払い、車を出た。すると、彰も一緒に下りてきた。
「ちょ、ちょっと、今日は泊まれないって……」
「勘違いするなって。水族館前は人出があったし、お前が嫌がると思ってずっと我慢してたんだよ」
彰に強く抱きしめられ、唇を塞がれた。
「ん……」
唇を擦り合わせ、名残惜しそうに離れる。彼の息づかいが顔に触れる。彰はそっと額を押し上げ、くすぐるように鼻先を触れあわせた。すぐ間近に、掘りの深い端正な顔があって、鼓動が暴れてしまう。
「……これで明日も頑張れそうだ」
「あ、え……」
うまく返せない。ただ自分の顔が湯気がでそうなくらい真っ赤になってることは容易に分かった。
「おやすみ、由季」
「お、おやすみ……なさい」
彰は微笑み、タクシーに乗り込んでいった。全身に今さら酔いが回ったような気がして、ぽうっとしたままタクシーが見えなくなるまで玄関前で立ち尽くしてしまった。
――もう……。
由季は自分の体が火照るのを意識してしまう。
「――っていう、ことなんだけど、プログラムは組めそうか?」
『どこまで要望通りにできるかは分からないけど、一応やってみるよ』
「そうか、助かる」
友哉はいつでもこちらの希望に添ったものを出してくれる。ただ本人が完璧主義者なので、締め切りに関してはかなりコントロールする必要がある。システムを組むのは突き詰めようと思えばいくらでも時間がかかってしまう分野だということを、友哉との付き合いで学んだ。
「それはそれとしてさ。お前、好きな奴いないのか?」
『あ? 何、いきなり? その顔すげーウザいんだけど』
「その顔ってなんだよ」
彰としては真面目な顔をしていたつもりだったのだが。
『高校の時にフられた子とうまくいっててチョー機嫌のいい顔』
「どんな顔だよ」
『うーん。オスの顔?』
「っ!」
すんぜんのところでコーヒーを飲んだから良かったものの、一つ間違ってたらパソコンめがけコーヒーを吹き出していたところだ。
『でもお前もそういう顔するんだ。女に全く興味がなかったくせに』
「女に興味はない。興味があるのは由季だけだ」
『はいはい。ごちそうさま。じゃ、お前のその顔、見続けるのウザすぎだから切る」
――そうか。俺、オスの顔してたか……。
由季を愛しくてたまらない。時間さえ許せば二十四時間、彼女を抱いていたい。
そんなことを提案したら怒られるだろうが。
――由季になら怒られたいな。
そんな変態めいたことを、つい考えてしまう。
「はぁ。由季と数日で良いから一緒に過ごしたい」
旅行を提案してみようか。いや、由季はフリーランスだ。おいそれと旅行に出かけるのは難しかったりするかもしれない。
――待てよ……。
彰の頭にとあるアイディアが浮かぶ。これだったら由季も断れないはず。
彰はすぐにその下準備を進めるため、メールを送る。
送信した直後、スマホが着信を知らせる。
「はい」
誰かも確認せず、反射的に出てしまう。業者だったら面倒だなと頭の片隅で考える。
『彰? 今大丈夫?』
「由季か!」
つい大きな声が出てしまい、電話の向こうで由季は「び、びっくりした……」とぽつりと呟く。
「悪い。つい。今、お前のことを考えてたから」
『私のことってどんなこと?』
「お前に怒られたいな、とか?」
『……もう二度とそんな変なことを考えないで』
「難しいけど、善処する。それで、どうした?」
『この間のパーティー、連れて行ってくれてありがとう。実はあそこで名刺を渡したいくつかの会社からライティングの仕事をもらえて……』
「良かったじゃないか」
自分のことのように嬉しかった。
『うん。それでお礼がてら、何かして欲しいことはないかなって』
「何でも?」
自然と口元が緩んだ。
『え、エッチなこと以外なら……』
「なんだよ、エッチなこと考えてたのか?」
『そうじゃないけど! ……あ、彰なら考えそうだなって』
「ちょっと考えた。でも普通にデートがしたいな。明後日の夜はどうだ?」
『大丈夫。デートってレイトショーとか?』
「映画なぁ」
『駄目?』
「駄目じゃないけど、せっかくお前と出かけるんだからもっと話せる場所が良いな。水族館はどうだ?」
『……夜に?』
「そう。夜だけの特別なイベントもやってるみたいだし、それに……思い出さないか? 俺たちの初デート。水族館だっただろ?」
『覚えてる。私が夏期講習帰りに合流して……』
「あの頃の気持ちが思い出せて若返りそうじゃないか?」
由季が笑う。
『もう、私たちはまだ若いよ。分かった。じゃあ、水族館で決まりね』
「よし。詳しいスケジュールはまた後で送る。じゃあ、楽しみにしてる」
『私も』
――水族館デートか。あの時はがらにもなく緊張したんだよな。私服姿の由季を初めて見たのはあの時か。
シアーストライプシャツにデニム姿。普段の制服姿とは雰囲気ががらっと変わった服装で可愛かった。
※
午後六時半。
待ち合わせの水族館前に由季はシフォンプリーツのブラウスに、パンツ姿で現れた。
彰は仕事帰りだから、スーツ姿。
「ごめん、待った?」
「いや。そうでもない」
手を繋ぎ、オンラインチケットで館内に入る。外の蒸し暑さが嘘のように涼しい。
普段は暖色系のライトアップなのだろうが、夜は照明全体が控えめで、ブルーのLEDライトで水槽が照らされる。
場内の照明が落とされたことで、水族館のぼんやりとした明かりの中を泳ぐ魚たちのシルエットがより幻想的に見える。
「展示そのものは昼間と同じみたいだけど、私が知ってる水族館とはぜんぜん雰囲気がちがう」
まるで自分たちまで、静かな深い海の底にいるような気持ちになった。
「お、ホオジロザメ」
大きな影が、由季たちの体を横切る。小魚たちの群れがさあっと左右に散っていく。
「うわ、すごい迫力……」
――ち、近い。
彰は由季に寄り添うように一緒に大型水槽を見ているのだが、手を繋いだまま、背後から彰に抱きしめられているような格好だった。
館内の照明が絞られているし、入場者もそれほどいないということもあってか、誰も由季たちを気にしてはいない。
「ちょっと、彰ってば」
「どうした?」
「ち、近すぎるよ……」
「腕が寒そうだなって思ったから、温めてたんだけどな」
「だ、大丈夫」
「ふうん、残念」
「……普通そう言ったら離れると思うんだけど」
「つれいないなぁ」
彰は苦笑し、しぶしぶ離れる。でも決して手は離さない。というよりさっきまでは普通に繋いでいるだけだったのに、今はしっかり指を絡めている。
「……これは注意されないのか」
「ふ、ふざけてるなら」
「ペンギンだぞ、ペンギン」
「もう……」
ペンギンゾーンも綺麗にライトアップされている。
「ケープペンギンだね。見て。あのよちよち歩き。本当ペンギンって癒される」
陸でひょこひょこ歩いてたと思えば、海に行くと弾丸のように突き進む。そのギャップがまた可愛い。
まるで彰みたいだなと思う。由季と一緒にいる時は飄々として掴み所がないのに、ビジネスの時の目つきはとても鋭く、格好いい。
次はクラゲエリア。
筒型の水槽にいろいろな種類のクラゲが浮いているのだが、そこはついっさきのエリアとは違って、赤や緑、オレンジなど原色のLEDのイルミネーションによって、鮮やかにライトアップされている。
ライトアップの中を、半透明のクラゲがふわふわと舞うように漂う様子は、それだけで絵になった。
「んー。クラゲも良いなぁ。癒される~」
「だな」
「もう、さっきからリアクション薄いよ。ごめんね。一人で盛り上がってて」
「そんなことない。俺だって楽しんでる」
「でもさっきから彰、私の顔ばっかり見てない? ちゃんと水槽を見てる?」
「まあ、目の端で。俺は海の生き物より、大好きな人の観察のほうが性に合ってるみたいだ。ペンギンやクラゲより由季のほうがずっとずっと興味をそそられる」
「!」
「……赤いLEDが反射してるみたいだぞ。顔が真っ赤だ」
「か、からかわないでったら……」
彰は腕を組み、訳知り顔でうなずく。
「由季の専門家として、今はかなり照れてるな?」
「いつから私の専門家になったのよ」
「はじめて付き合った時から、かな?」
「もう」
悪い、と彰はまったく悪びれずに微笑む。
彰の一言にいちいち反応してしまう自分がとてつもなく恥ずかしかった。
さらに進むと、『ナイトイルカショー』という掲示があった。
「せっかくだから見ていくか」
「うん!」
すり鉢状にもうけられた座席の半ばあたりに席を確保する。
ショーの開始時刻を迎えると、軽快な音楽と一緒にイルカたちが、トレーナーの人たちと一緒に入ってくる。
同時に、天井から滝のように大量の水が降り注ぐ。
――何?
昼間のイルカショーでは見たことがない演出だ。
その時、LEDライトが反射し、その水で出来た壁に映像が投影される。
「これって……」
「プロジェクションマッピングってやつだな」
青や赤、黄色などの色で映し出される映像は、無数の魚たち。
トレーナーの指示に合わせ、大ジャンプを決めたイルカが魚たちの群れめがけ飛びかかる。イルカたちの動きに合わせ、映像が切り替わる。
空だったり、宇宙だったり。まるでイルカが飛んでいるかのような印象を受ける。
「すごい!」
今日一の興奮の声をあげ、由季は目を輝かせた。
さらにライトがイルカのつるつるした体に当たって、イルカを七色に輝かせる。
童話の世界にでも迷い込んだような光景だ。
三十分のショーがあっという間だ。
「すごい満足!」
イルカショーが終わっても、なかなか興奮が冷めやらなかった。
彰もこれまでとはリアクションが違っていた。
「甘く見てたな。ただの夜の水族館だろって思ってたけど……あんな隠し球もあったのか」
「すごく綺麗だったよね。プロジェクションマッピングまで使ってるとか、イルカショーも最先端かぁ」
「夜だからこそできることだよな」
「ほんとう。楽しかったぁ!」
「まだ終わりじゃないけどな」
「まだ見るものあったっけ?」
彰に手を引かれて向かったのは、一階にあるカフェ。
カフェ全体も照明が絞られ、カフェというよりバーの雰囲気だ。
そしてクラシックだろうか、落ち着いた曲がうっすらと流れていた。
カフェでは、夕方以降限定のカクテルを飲むことができるらしい。
彰はブルーキュラソーをつかったイルカをモチーフにしたカクテルを、由季はホワイトラムをベースにしたベルーガをモチーフにしたカクテルをそれぞれ注文する。
夜はどうやらテーブル席の間隔が昼間より開いているらしく照明が絞られていることもあいまって、まるで個室にいるような気分になった。
カフェにも小さな水槽が備え付けられていて、そこにはクマノミとチンアナゴが飼育されていた。
「乾杯」
グラスをそっと打ち付け合う。
「ん、美味しい」
「俺のも飲んでみるか?」
「うん。じゃあ、私のも」
交換して飲んでみる。
「はぁ。オレンジの良い香り。夏って感じでこっちも好き」
「由季のほうは甘く仕立てられるな。底にあるのは、ベリーか」
「ま、結局はどっちも美味しいってことよね」
カクテルを味わい、そうし水族館を後にした。
「明日も平日じゃなかったら……このままお前をマンションに連れ去りたいんだけどな」
「……怒られたい?」
「うん、悪くない」
彰は大真面目に頷く。
「……そうだった。この間、私に怒られたいとか想像してたんだっけ」
彰はタクシーを止め、一緒に乗った。最初に距離の近い由季の自宅へ寄ってもらう。
彰は色々と言っていたけどタクシー代をしっかり支払い、車を出た。すると、彰も一緒に下りてきた。
「ちょ、ちょっと、今日は泊まれないって……」
「勘違いするなって。水族館前は人出があったし、お前が嫌がると思ってずっと我慢してたんだよ」
彰に強く抱きしめられ、唇を塞がれた。
「ん……」
唇を擦り合わせ、名残惜しそうに離れる。彼の息づかいが顔に触れる。彰はそっと額を押し上げ、くすぐるように鼻先を触れあわせた。すぐ間近に、掘りの深い端正な顔があって、鼓動が暴れてしまう。
「……これで明日も頑張れそうだ」
「あ、え……」
うまく返せない。ただ自分の顔が湯気がでそうなくらい真っ赤になってることは容易に分かった。
「おやすみ、由季」
「お、おやすみ……なさい」
彰は微笑み、タクシーに乗り込んでいった。全身に今さら酔いが回ったような気がして、ぽうっとしたままタクシーが見えなくなるまで玄関前で立ち尽くしてしまった。
――もう……。
由季は自分の体が火照るのを意識してしまう。
26
あなたにおすすめの小説

とろける程の甘美な溺愛に心乱されて~契約結婚でつむぐ本当の愛~
けいこ
恋愛
「絶対に後悔させない。今夜だけは俺に全てを委ねて」
燃えるような一夜に、私は、身も心も蕩けてしまった。
だけど、大学を卒業した記念に『最後の思い出』を作ろうなんて、あなたにとって、相手は誰でも良かったんだよね?
私には、大好きな人との最初で最後の一夜だったのに…
そして、あなたは海の向こうへと旅立った。
それから3年の時が過ぎ、私は再びあなたに出会う。
忘れたくても忘れられなかった人と。
持ちかけられた契約結婚に戸惑いながらも、私はあなたにどんどん甘やかされてゆく…
姉や友人とぶつかりながらも、本当の愛がどこにあるのかを見つけたいと願う。
自分に全く自信の無いこんな私にも、幸せは待っていてくれますか?
ホテル リベルテ 鳳条グループ 御曹司
鳳条 龍聖 25歳
×
外車販売「AYAI」受付
桜木 琴音 25歳

初色に囲われた秘書は、蜜色の秘処を暴かれる
ささゆき細雪
恋愛
樹理にはかつてひとまわり年上の婚約者がいた。けれど樹理は彼ではなく彼についてくる母親違いの弟の方に恋をしていた。
だが、高校一年生のときにとつぜん幼い頃からの婚約を破棄され、兄弟と逢うこともなくなってしまう。
あれから十年、中小企業の社長をしている父親の秘書として結婚から逃げるように働いていた樹理のもとにあらわれたのは……
幼馴染で初恋の彼が新社長になって、専属秘書にご指名ですか!?
これは、両片想いでゆるふわオフィスラブなひしょひしょばなし。
※ムーンライトノベルズで開催された「昼と夜の勝負服企画」参加作品です。他サイトにも掲載中。
「Grand Duo * グラン・デュオ ―シューベルトは初恋花嫁を諦めない―」で当て馬だった紡の弟が今回のヒーローです(未読でもぜんぜん問題ないです)。





苦手な冷徹専務が義兄になったかと思ったら極あま顔で迫ってくるんですが、なんででしょう?~偽家族恋愛~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
「こちら、再婚相手の息子の仁さん」
母に紹介され、なにかの間違いだと思った。
だってそこにいたのは、私が敵視している専務だったから。
それだけでもかなりな不安案件なのに。
私の住んでいるマンションに下着泥が出た話題から、さらに。
「そうだ、仁のマンションに引っ越せばいい」
なーんて義父になる人が言い出して。
結局、反対できないまま専務と同居する羽目に。
前途多難な同居生活。
相変わらず専務はなに考えているかわからない。
……かと思えば。
「兄妹ならするだろ、これくらい」
当たり前のように落とされる、額へのキス。
いったい、どうなってんのー!?
三ツ森涼夏
24歳
大手菓子メーカー『おろち製菓』営業戦略部勤務
背が低く、振り返ったら忘れられるくらい、特徴のない顔がコンプレックス。
小1の時に両親が離婚して以来、母親を支えてきた頑張り屋さん。
たまにその頑張りが空回りすることも?
恋愛、苦手というより、嫌い。
淋しい、をちゃんと言えずにきた人。
×
八雲仁
30歳
大手菓子メーカー『おろち製菓』専務
背が高く、眼鏡のイケメン。
ただし、いつも無表情。
集中すると周りが見えなくなる。
そのことで周囲には誤解を与えがちだが、弁明する気はない。
小さい頃に母親が他界し、それ以来、ひとりで淋しさを抱えてきた人。
ふたりはちゃんと義兄妹になれるのか、それとも……!?
*****
千里専務のその後→『絶対零度の、ハーフ御曹司の愛ブルーの瞳をゲーヲタの私に溶かせとか言っています?……』
*****
表紙画像 湯弐様 pixiv ID3989101
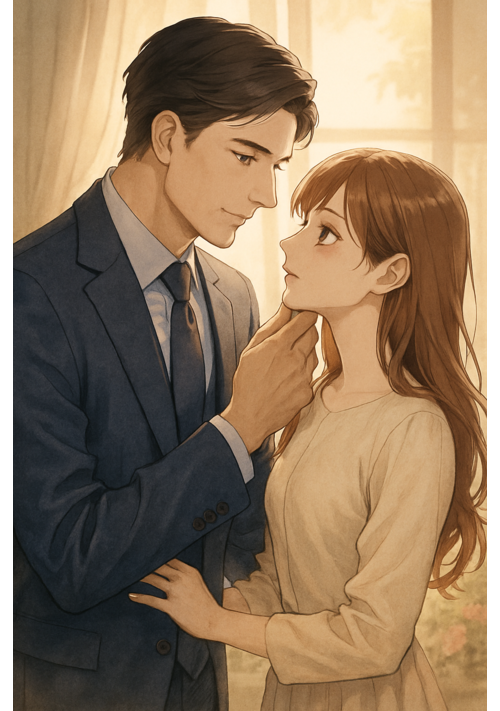
15歳差の御曹司に甘やかされています〜助けたはずがなぜか溺愛対象に〜 【完結】
日下奈緒
恋愛
雨の日の交差点。
車に轢かれそうになったスーツ姿の男性を、とっさに庇った大学生のひより。
そのまま病院へ運ばれ、しばらくの入院生活に。
目を覚ました彼女のもとに毎日現れたのは、助けたあの男性――そして、大手企業の御曹司・一ノ瀬玲央だった。
「俺にできることがあるなら、なんでもする」
花や差し入れを持って通い詰める彼に、戸惑いながらも心が惹かれていくひより。
けれど、退院の日に告げられたのは、彼のひとことだった。
「君、大学生だったんだ。……困ったな」
15歳という年の差、立場の違い、過去の恋。
簡単に踏み出せない距離があるのに、気づけばお互いを想う気持ちは止められなくなっていた――
「それでも俺は、君が欲しい」
助けたはずの御曹司から、溺れるほどに甘やかされる毎日が始まる。
これは、15歳差から始まる、不器用でまっすぐな恋の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















