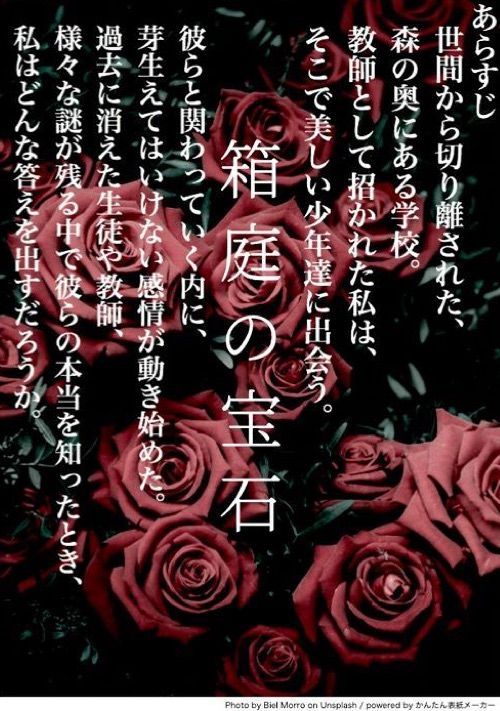31 / 36
31.月日は流れ
しおりを挟むエクランド王国西部の主要地方都市・リウォット領アーディレスト。
周囲になだらかな丘陵が広がる穀倉地帯は、古くから王国の食糧庫として重宝されており、幾度かの政争の果てにオルデアス家が長年預かる領地の一つとなっている。
収穫を終えた今の季節は徐々に気温が下がりつつはあるものの、雨も少なく日中は比較的温暖な日々がもうしばらく続くという。
そんな田舎町に滞在して一週間となるキオは、今日も広い書斎で淡々と作業を進めていた。
「――トドリス殿。この年から市場税が王国通達分よりも過剰税率で計上されていますが、何かご存じで?当主宛の報告書では、適正税率で記載されてますね」
「……失礼、拝見いたします……」
四方の壁面を天井近くまで埋める書架が示す通り、書庫も兼ねている部屋には最低限の窓しかなく薄暗い一角もあるが、その中で唯一窓辺近くに設置されている執務机の周りは朝からの晴天もあって、自然な明るさに包まれている。
だからキオには、机を挟んで立つ相手の顔色もよくわかった。
白髪交じりの茶髪を短く切り揃えた初老の男、丸眼鏡がよく似合う柔和な家令の表情が見る間に固く強張っていく様を眺めながら、キオは椅子に腰かけたまま穏やかな笑みを纏って話しかける。
「今ここでお話し頂ければ、何も大きな問題にはなりませんよ。ユンドの血統がこの地を代々よく治めてきてくれたことは、当主もご存知ですから」
静かに響く落ち着いたその声音には、敵意の欠片どころかいっそ好意的な響きすら滲んでいた。
それもあってか、このアーディレストの街を治めるオルデアスに仕える家令は、多少の逡巡の後に重いため息と共に口を開き始めた。
「この頃は……数年に渡り寒冷な気候が続き、諸般の対策にお館様が手を焼かれておりました。有事用の積立も底をつきかけ、致し方なくその補填に――」
「あぁ、やはり臨時用の裏金行きでしたか。それならいいです。市場税自体は領主の裁量の一部ですし、当主もそこまで厳正に締め付ける気はおありではないようですから。ただし、この運用が恒例化すれば後の禍根となりかねませんが」
「今年分より必ずや、本邸宛ての書類にも正しく記載いたします」
「よろしくお願いします。では、これで監査は一通り終了です。何日もお付き合い頂き、ありがとうございました」
その言葉に家令のトドリスは、あからさまにほっとした顔をしながら深く深くキオに対して腰を折った。
対するキオも変わらぬ笑みを浮かべてはいたが、ここ数日かけて幾度かのやり取りの後にやっと提出させた帳簿を返却しながらこっそりと息をつく。
今回はそう揉めずに事の決着がついた、と。
(だいぶ慣れてきたとはいえ、裏帳簿関連の駆け引きはやっぱり疲れるな……)
そう胸の内でぼやくキオはいそいそと書斎から去る黒い背を見送るなかで、なぜ自分がこんなことをしているのかとぼんやりと思いを馳せる。
切っ掛けは、足も悪く異能すら失った欠陥品の弟を、異母兄が自らの遠征先にまで連れ回し始めたことだった。
初めて同行したガレン領を皮切りに、行く先々で滞在先――多くは一族が治める領地にて財務監査の手伝いをする、という仕事がキオには与えられた。
それは過去数年分に渡り、本邸へと提出された報告書と現地保管の帳簿とを突き合わせ、内容に齟齬がないか確認するだけの簡単な作業。
の、はずだったのだ。基本的には。
だが実際は、行く先々で大なり小なり不自然な痕跡が見つかるばかり。
貴族というもの、なかでも領地を預かる者ともなれば、帳簿外の資産を有する必要性もその理由もキオはよくよく理解している。
慣例として多少のズレであれば見逃す、という取り決めがあることも同僚から最初に教わったものの、精査してみれば『多少』どころでは収まらない金額が隠されていたこともあった。
最初はその全てをジルヴェストへ報告するだけで、キオの仕事は終わりだったのだが……。
遠征先でのオルデアス家当主は、移動時間を除けば余暇などほぼないほどの多忙さなのだ。
そもそも当主自らが王国内を巡るのは、魔獣討伐の依頼に応える為というよりも他の貴族勢力や国境を接する周辺国に対する示威行為の側面も大きい。
実際にジルヴェストが前線に出ることもあるが、それと同じかより高い頻度で多種の会合や夜会に連日臨席するのが、遠征先でのオルデアス家当主の日常である。
そんな異母兄の仕事をただ増やすことになるだけ、というのはキオにとって非常に心苦しいことだった。
いくら当のジルヴェストが表情一つ変えず、その顔に疲労の色を滲ませることもなく機械的に対処していようとも。
何しろ、帳簿の確認が終わってしまえば後は戦力外の欠陥品は手持ち無沙汰だというのに、その飼い主は休息も程々に指示や判断に追われているのだから。
少しでも当主の負担が軽減されれば、とキオがジルヴェストの承諾を得たうえで、監査結果を基に相手方と折衝じみたやり取りまで行い始めたのは自然なことだった。
そうした歳月を積み重ねた結果、いつしかキオは遠征先での監査業務を一手に引き受けるようになり、今では行く先々でそれなりの対応をされるまでになっている。
勿論それには『現当主の異母弟』という肩書きの影響も、決して小さくはない。
表舞台に滅多と姿を現すことはなくとも、当主がその存在を僻地まで連れ歩いていることは既に一族内では広く知られてもいるのだから。
なかには、キオがジルヴェストの懐刀的な存在だと認識している人間までいるらしい。
そんな噂をキオ本人が知った時には、ただ呆れの混じったため息を零すしかなかった。
当主がその異母弟を決して前線には出さず、駐留拠点での監査や後方事務にのみ従事させているのは、単純に欠陥品の使い所など、それくらいしかないからに過ぎない。
七年。
異能と片足を代償に、小さな主を守り切ったあの日からそれだけの時間が経とうとも、オルデアスの血はキオに未だ応えることはなく沈黙したままだ。
なのに、毒として体へ負担を強いてくることだけは変わらないのだ。
その欠陥品の体で今も息をしていられるのは、飼い主である異母兄との関係にも何一つ、変化がないからに過ぎない。
「キオ様。一度ご休息を」
「……あぁ、そうします」
約六日間ほど従事していた一仕事を無事に終えたことで、しばしぼうっとしていたキオはそう声を掛けられたことで我に返った。
声の主は執務机の後方、書架の陰に隠れるように佇んでいる馴染みの侍女である。
オルデアス家本邸からわざわざキオに同行させられている彼女は、当然ディークの血統の傍系にあたる一族で、正確には侍女の役も担う護衛と呼ぶ方が正しい。
キオにはそのような護衛兼侍女が何名か持ち回りで傍についており、今回の遠征には彼女が帯同しているのだが、雑談じみた会話はほとんどない。
傍系とはいえ充分に使える異能を持った一族と、当主の異母弟でありながら、誰もが知る欠陥品の自分。
血統と異能に価値を置くオルデアスのなかで、本来なら自分など誰からも捨て置かれて当然の存在だという認識は、キオの中でより強固なものになっているからだ。
だから侍女相手であろうとも丁寧な口調は決して崩さないし、どんな些細な呼びかけにも微笑を添えて、キオは答えてみせる。
それは、遠征先で初めて言葉を交わす相手に対しても同じこと。
ただ、当主秘蔵の異母弟のその振る舞いが、周囲からはどう見えるか、という点においてまでキオの関心はなかった。
その結果が巡り巡って、王宮でひと騒動を巻き起こしたこともあったのだが……ジルヴェストの完全な情報統制によって、それが本人の耳に届くことはなかった。
何はともあれ、この七年の間のキオは、絶対の飼い主の手元でほぼ軟禁されながら限定された人間関係の中で生きていた。
まるで、異母兄に引き取られた頃のように。
それは王都オルデアス家本邸から遠征地へ場所を移そうとも、変わらない。
アーディレストの地で仕事部屋代わりにしていた書斎を後にし、杖をつきながらややゆっくりとした速さで歩を進めたキオが向かった先は、この館で最も格式の高い貴賓室である。
当然ながらその部屋は、オルデアス家当主が逗留するために設えられたものだが、今となってはそれ即ち、キオにとっても仮の自室ということだ。
本邸では言うに及ばず、遠征先でもこうして異母兄と生活空間を共にしているのは、偏に飼い主たる男の執着が理由――だと明らかであったならば、キオももう少し平穏な心で日々を過ごせただろう。
「お加減はいかがでしょうか、キオ様」
豪奢な気品漂う調度品に囲まれた広い部屋の一角、染み一つない深紅のソファーへ自力でノロノロと腰を落ち着けたところで、そう問いかける侍女の言葉にキオは深まるため息を何とか押し止め、また小さく笑う。
「大丈夫です。今日も問題ありませんから」
わざわざそんなやり取りをしなければならないのは、この七年の間にキオが予兆なく体調を崩すことが幾度も起きているからだ。
始まりは今となっては遠い昔、キオの小さな主がわざわざ人目を忍んでまで見舞いに来てくれた翌日のこと。
それ以降、定期的に異母兄と躰を繋いでいようとも、ある日突然前触れもなくあの特有の苦痛に苛まれることがあった。
しかも体を動かすのが多少怠いくらいの軽度なものから、数日間昏睡するほどの深刻な状態になる場合もあり、症状も安定しない。
そんな欠陥品の生命維持を課せられた当主だからこそ、ジルヴェストは遠征先にまで自分を伴い、逗留時には必ず目の届く範囲に置いているに過ぎない。
そう理解しているキオにとって、いまだ実兄へ向かう決して叶わない歪な恋心と、どんな形であれ傍に置いてもらえることを密やかに喜ぶ感情の板挟みに、疲弊していないと言えば噓になる。
それでも狭い世界の中で与えられた仕事を一つずつこなし、できることに手を出し、作り笑いを絶やさずに足掻いてこれたのは、心の拠り所がまた別にあったからだ。
少なくとも、今までは。
「ロザリー、今日は本邸からの書簡はありますか?」
「はい、五十通ほどこちらへ届けられております」
「では仕分けをしておきます。その間は貴女も休んで下さい」
「承知いたしました、キオ様」
白いレースのクロスで覆われたローテーブルの上にティーセットを用意してくれた侍女にそう声を掛ければ、程なくしてキオの前には王都から転送されてきた書簡の束が用意される。
静かに一礼し、貴賓室に併設された使用人向けの小部屋へと姿を消す侍女を横目で見送った後、キオは当主へ宛てられた多くの手紙の中から無造作に二、三通をまとめて手に取ると、その封蝋を確認しながら文箱の中へ選り分けていく。
こうして遠征に出向いている当主の下には、定期的に王都本邸から書簡が転送されてくるのだが、火急の連絡であれば異能の手段を用いるのが当然のオルデアスなのだから、その重要性自体あまり高くない。
ほとんどが、時期が合えば王都での夜会に参列してほしいといった類の話や、何かと理由をつけて機嫌伺いをしてくる他の貴族からの手紙か、王都で留守を預かっている一族からの変わりない定期報告なのだから。
開封して中身を検めるまではさすがにやらないが、一族かそれ以外からの書簡かを確認しながら文箱の中に二つの山を作るだけの、単純な雑用。
だが、キオはできるだけその作業に携わりたいのだ。
いつの間にかすっかり大人と変わらない、流麗な書き文字を綴るようになった筆跡で、自分宛てに送られてくる手紙がひっそりとその中に混じっていることがあるから。
勿論その送り主は、精一杯の求愛を手酷く拒絶されようとも変わることなくキオへ恋文を送り続ける、奇特な王子様である。
ただ――。
(……やっぱり、ないか……)
かつての小さな主、今は十九の青年となっている第五王子からの手紙は、この七年の間に少しずつ届けられる間隔が空くようになった。
かつては一月に一度は必ずキオの下へ送られていた恋文も、一月半に一度、やがて二か月に一度と遠のき始め、今では半年前に届いた簡単な内容の手紙が最後の一通だ。
誰の目もないこともあって、つい寂し気な顔をしてしまいながらも、それも無理もないとキオは胸の内で考える。
キオの主――いや元主は、あれから劇的な成長を遂げたのだから。
わかりやすく言えば、今では王位継承権第二位の位置に滑り込むほどに。
ひっそりと捨て置かれ、閉じられた小さな離宮が世界の全てだった少年が、王太子たる第一王子と、その腹違いの弟である第二王子との王位継承争いに割って入る未来など、誰に予想できただろう。
それは王国の情勢変化も大きく影響してのことだが、フレデリックという王子は、もうキオのような欠陥品を必要とする子供ではなくなったのだ。
(今の殿下は多くの人から必要とされて、頼りにされている。第五王子が次期国王の座を争うまでになるなんて、利害関係だけでなく本心から応援されなければ到底無理なことだし……)
変わらぬ好意が記され続けた手紙と、キオのもとまで時折聞こえてくるほどの、目覚ましい活躍。
それがあったからこそ、キオもどうにか前向きに生きてこれたのだ。
自分が変わることのない欠陥品であろうと、躰だけの関係に不毛にも愛を乞い続けようと、突き放したくせに気に掛けていてほしいと醜く願ってしまおうとも。
けれど七年も経てば、もう充分だ。
あの小さな主は有り余るほど自分を支えてくれていたのだから、元護衛に過ぎない年上の男への関心がやっと薄れたことを、喜んでやらなくてはいけない。
きっと見た目も、健やかに成長していることだろう。
それこそ、年頃の貴族令嬢たちが放っておかないほどに。
そう思いながら、整理し終えた文箱を手元から遠ざけたキオは、微かに暖かさの残る冷めたカップに手を伸ばす。
だが、赤茶けた小さな水面に映る自分の顔がふと目に入った途端に、思わず苦笑した。
その拍子に長い蒼黒髪の横髪が一筋、頬をくすぐっていく。
子供が大人へと変わる年月が経ち、キオももう二十六になったというのに、その見た目はまだ二十歳程度の若造のままなのだ。
あまつ最後に言葉を交わした折に、フレンが短い髪の自分を見て『ちょっと寂しい』と零したことが胸に残った結果、また髪を伸ばして昔のように項で一つに括っている。
七年前から姿も中身もそう成長のない自分と、今や王国の中心に食い込む王子との差は歴然としており、自嘲の笑みも深まるしかない。
しかしそれも長続きしなかったのは、貴賓室の両開きの扉がノックもなしに廊下側からゆっくりと開け放たれたからだ。
それは部屋の主の帰還であり、キオもカップを静かにテーブルに戻しながら座ったまま飼い主へと顔を向けた。
「お疲れ様です、兄上。何か御用はありますか?」
他人へ見せる作り笑いではなく、かといって昔のように感情を殺した無表情でもなく、少し困ったように微笑む異母弟を夕焼け色の瞳が一瞥する。
不惑が近づくジルヴェストも相変わらず年齢不詳のあの美貌を保っているとはいえ、欠陥品と比べようもなくオルデアスの血に愛されている男なのだから、それも不思議ではないだろう。
豪奢な黒衣を翻しながら室内へと歩を進める異母兄の、白銀の雪に似た長い後ろ髪を揺らす背に追従する者は誰もいない。
昼食前のこの時間は、アーディレスト郊外の視察が今日のジルヴェストの予定であることを記憶していたキオは、小さく首を傾げた。
そのうえ部屋の扉が閉ざされる僅かな合間に、廊下からは人が慌ただしく早足で行き交う気配まで漂ってくるとなれば……。
(これは何かあったな。王都へ急遽帰還……だろうか)
今までの経験から、そう当たりをつけたキオだったが、対面のソファーに腰かけた飼い主からの言葉に、つい本音をもらしてしまった。
「ノーヴォルとの開戦が濃厚となった。明日、北方のダスティンに経つ」
「オルデアスが――兄上がいると知りながら開戦とか、正気の沙汰ではないと思いますけど」
「踊らされている奴らにそう言え」
常と変わらず無表情な美貌ながらも、珍しく苛立ちが滲むため息と共に足を組むジルヴェストに、キオも小さく肩を竦めた。
七年前と今では、王国の情勢は変わったのだ。
その変化がもたらす結果が隣国との開戦となるならば、それも致し方ないのだろう、と。
応援ありがとうございます!
1
お気に入りに追加
665
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる