あなたにおすすめの小説
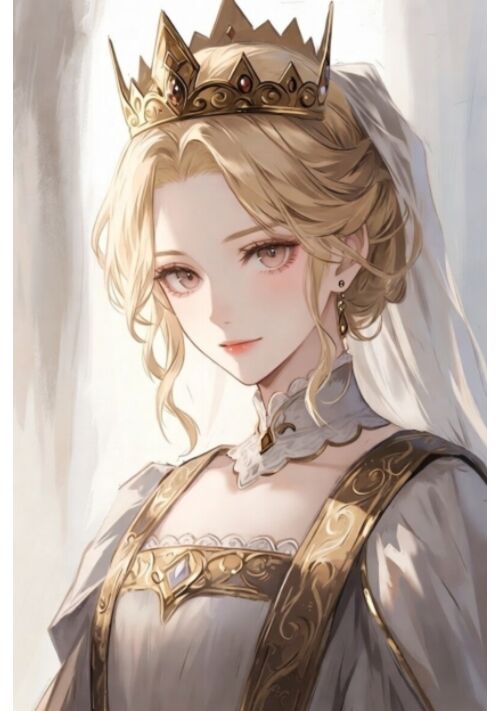
スキルなし王妃の逆転劇―妹に婚約破棄を囁かれましたが、冷酷王と無音の結婚式へ向かいます
雪城 冴
恋愛
聖歌もファンファーレもない無音の結婚式。
「誓いの言葉は省略する」
冷酷王の宣言に、リリアナは言葉を失った。
スキル名を持たないという理由だけで“無能”と蔑まれてきたリリアナ。
ある日、隣国の王・オスカーとの婚約が決まる。
義妹は悪魔のような笑みで言う。
「婚約破棄されないようにお気をつけてね」
リリアナに残されたのは、自分を慰めるように歌うことだけ。
ところが、魔力が満ちるはずの王国には、舞踏会すら開かれない不気味な静寂が広がっていた。
――ここは〈音のない国〉
冷酷王が隠している“真実”とは?
そして、リリアナの本当のスキルとは――。
勇気と知性で運命を覆す、
痛快逆転ファンタジー。
※表紙絵はAI生成

『嫌われ令嬢ですが、最終的に溺愛される予定です』
由香
恋愛
貴族令嬢エマは、自分が周囲から嫌われていると信じて疑わなかった。
婚約者である侯爵令息レオンからも距離を取られ、冷たい視線を向けられている――そう思っていたのに。
ある日、思いがけず聞いてしまった彼の本音。
「君を嫌ったことなど、一度もない」
それは誤解とすれ違いが重なっただけの、両片思いだった。
勘違いから始まる、甘くて優しい溺愛恋物語。

『婚約破棄された令嬢ですが、名も残さず街を支えています』
ふわふわ
恋愛
婚約破棄された伯爵令嬢コルネリア・フォン・ヴァルデン。
名誉も立場も失いかけた彼女が選んだのは、誰かに勝つことでも、名を取り戻すことでもなかった。
前に立たず、声高に語らず、ただ「判断が続く仕組み」を街に残すこと。
現場に任せ、失敗を隠さず、問いを残し、そして最後には自ら手を離す――。
名を呼ばれず、称賛もされない。
それでも街は止まらず、確かに良くなっていく。
これは、ざまぁの先で「勝たなかった令嬢」が、
静かに世界を変え、そして正しく消えていく物語。

【完結】捨てられ令嬢の冒険譚 〜婚約破棄されたので、伝説の精霊女王として生きていきます〜
きゅちゃん
恋愛
名門エルトリア公爵家レオンと婚約していた伯爵令嬢のエレナ・ローズウッドは、レオンから婚約破棄を宣言される。屈辱に震えるエレナだが、その瞬間、彼女にしか見えない精霊王アキュラが現れて...?!地味で魔法の才能にも恵まれなかったエレナが、新たな自分と恋を見つけていくうちに、大冒険に巻き込まれてしまう物語。

星屑を紡ぐ令嬢と、色を失った魔法使い
希羽
恋愛
子爵令嬢のルチアは、継母と義姉に虐げられ、屋根裏部屋でひっそりと暮らしていた。彼女には、夜空に輝く星屑を集めて、触れた者の心を癒す不思議な力を持つ「銀色の糸」を紡ぎ出すという、秘密の能力があった。しかし、その力で生み出された美しい刺繍の手柄は、いつも華やかな義姉のものとされていた。
一方、王国には「灰色の魔法使い」と畏れられる英雄、アークライト公爵がいた。彼はかつて国を救った代償として、世界の色彩と感情のすべてを失い、孤独な日々を送っている。
ある夜会で、二人の運命が交差する。義姉が手にしたルチアの刺繍にアークライトが触れた瞬間、彼の灰色だった世界に、一瞬だけ鮮やかな色彩が流れ込むという奇跡が起きた。
その光の本当の作り手を探し出したアークライトは、ルチアを自身の屋敷へと迎え入れる。「私のために刺繍をしろ」──その強引な言葉の裏にある深い孤独を知ったルチアは、戸惑いながらも、初めて自分の力を認められたことに喜びを感じ、彼のために星屑を紡ぎ始める。
彼女の刺繍は、凍てついていた公爵の心を少しずつ溶かし、二人の間には静かな絆が芽生えていく。
しかし、そんな穏やかな日々は長くは続かない。ルチアの持つ力の価値に気づいた過去の人々が、彼女を再び絶望へ引き戻そうと、卑劣な陰謀を企てていた。

婚約破棄されましたが、隣国の大将軍に溺愛されて困ってます
有賀冬馬
恋愛
「君といると退屈だ」
幼い頃からの許嫁・エドワルドにそう言われ、婚約破棄された令嬢リーナ。
王都では“平凡で地味な娘”と陰口を叩かれてきたけれど、もう我慢しない。
わたしはこの国を離れて、隣国の親戚のもとへ――
……だったはずが、なぜか最強でイケメンな大将軍グレイ様に気に入られて、
まさかの「お前は俺の妻になる運命だ」と超スピード展開で屋敷に招かれることに!?
毎日「可愛い」「お前がいないと寂しい」と甘やかされて、気づけば心も体も恋に落ちて――
そして訪れた国際会議での再会。
わたしの姿に愕然とするエドワルドに、わたしは言う。
「わたし、今とっても幸せなの」

十年間虐げられたお針子令嬢、冷徹侯爵に狂おしいほど愛される。
er
恋愛
十年前に両親を亡くしたセレスティーナは、後見人の叔父に財産を奪われ、物置部屋で使用人同然の扱いを受けていた。義妹ミレイユのために毎日ドレスを縫わされる日々——でも彼女には『星霜の記憶』という、物の過去と未来を視る特別な力があった。隠されていた舞踏会の招待状を見つけて決死の潜入を果たすと、冷徹で美しいヴィルフォール侯爵と運命の再会! 義妹のドレスが破れて大恥、叔父も悪事を暴かれて追放されるはめに。失われた伝説の刺繍技術を復活させたセレスティーナは宮廷筆頭職人に抜擢され、「ずっと君を探していた」と侯爵に溺愛される——
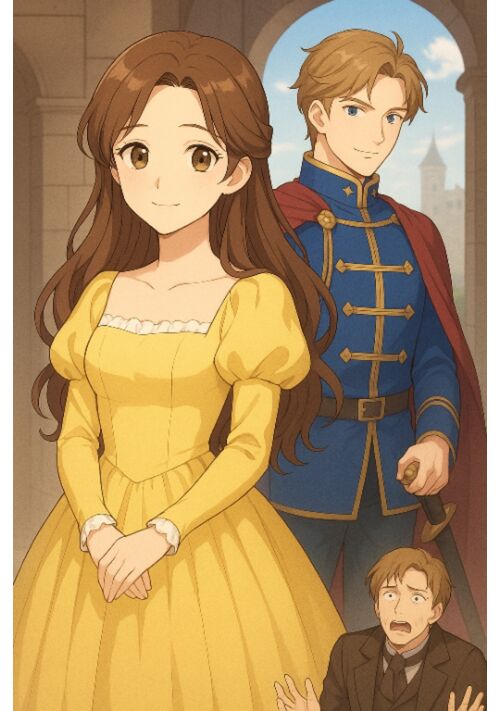
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
有賀冬馬
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















