10 / 11
流転編
山脈を越えて
しおりを挟む
◆
風竜帝の羽ばたき一つで、馬車が倒れそうになる。それを抑えるエヴァリーナは、導甲殻の無機質なレンズをダーリヤに向けた。
(私が時間を稼ぐから、逃げて)
風に乗せて、エヴァリーナは声をダーリヤの耳に入れる。
しかしダーリヤは、小さく首を横に振った。そして視線をルフィーネに向けると、
「姫が、何かを為そうとしています。私は乳母として、それを見届けなければなりません」
ある意味でダーリヤは誰よりもルフィーネを理解していた。そして期待してもいたのである。
しかし外に出たルフィーネは上空を見上げると、小さな口をあんぐりと開けて、
「ぴぎゃああああああ」
と、泣き出した。案の定のことだ。
ダメなおっさんが戦艦クラスに大きい竜を目の当たりにして、泣かない訳が無い。そこに救いがあるとすれば、絵面がおっさんの泣き顔ではなく、一歳児の泣き顔という程度だろう。
しかし困ったのはダーリヤだ。
(確かに外へ出たいと、姫は言ったはず)
ダーリヤは風竜帝の巨大な口と顔に吸い込まれそうな感覚を抱きつつ、ルフィーネの命だけは助けてもらおうと、跪く。
やはりエヴァリーナの言うとおり、逃げておけば良かったか――? そう思うが、逃げた所で助かるとも思えないダーリヤだ。
その時――。
「か、え、れ! ――おま、かえれぇぇえええ!」
ルフィーネは言葉にならない声で、確かにいった。
瞳に涙をいっぱいに溜めて、それでも風竜帝の巨大な目を見据えてルフィーネは言ったのだ。
もう、恐すぎて思考回路がぶっ壊れてしまったルフィーネである。
”ゴウゥゥ――”
大気の流れが変わり、突風が雪を舞い上げる。
風竜帝の鼻息だった。
そして風竜帝は、その長く大きな首を縦に振ったのだ。
「――我が愛しき姫よ――我は――そなたの仰せのままに」
ルフィーネを見つめた風竜帝の瞳が、瞬間、真紅に染まる。
同時にルフィーネの左目も紅玉の如く赤々と輝いていたが、それに気付ける者はいない。誰もが余裕を失っていたのだ。
――――
風竜帝は、眼下で泣き喚く幼女が悪魔付きだと認識していた。
喰らうもよし――焼き尽くすもよし――そう考えていた。
しかし、幼女は内心で何かを考えているようにも見える。
(――言い訳があるのなら、一言位聞いてやってもいい――)
それは圧倒的強者の傲慢かも知れない。だが、風竜帝はそう思った。
その時――彼の心に一陣の風が吹いた。
それは爽やかにして甘い――そして何より、とろけるように柔らかかった。
眼下で泣く幼女が――何よりも大切に思えた瞬間である。
今、風竜帝の目にルフィーネは、艶やかな肢体を持つ絶世の美女に見えていた。そしてそれは――ルフィーネが成長した姿に違いなく、それゆえにこそ風竜帝の心を捕らえたのである。
人はこれを”サキュバスの幻惑”という。
だが風竜帝はこの時思った――。
(久しいな、我が恋とは――)
と。
風竜帝は遥かな昔、自分を裏切った悪魔公爵の女を思い出していた。
そう――風竜帝はかつて、悪魔に恋をしたのだ。
だが、それは報われない恋だった――。
彼女は魔王を目指し、そしてその為には多くの男を虜にせねばならなかったのだから。
風竜帝が恋した悪魔――その名をミスティ・ハーティスという――彼女の死を、風竜帝は未だ知らなかった。
それはともかく、一歳児に鼻息を荒くする帝を見た竜王達は皆、複雑な心境だったに違いない。
(ギリアスさま、ないわー。これだったら、我だけで来たほうがよかったわー)
(まただよ、この色ボケ。抗魔くらいしろっつの)
(ギリアスさまってロリコン、通り越してねえっすか? しかもまた悪魔だし――)
しかし彼らが内心を口にする事は、永遠にないだろう。竜達の忠誠とは、そういうものなのだから。
こうして竜達は飛び退り、ルフィーネ達一向は災禍を逃れたのである。
◆◆
およそ一月の旅も、漸く終わりを告げる。季節も巡り、春が訪れようとしていた。
アントネスク領に入った一行は、その最初の街で歓待を受け、百人からなる護衛団をつけてもらった。それらはすべて、領主である公爵ブルクハルト・アントネスクの計らいだという。
また、護衛団を率いていた人物こそがブルクハルト本人だったのだから、エヴァリーナも肩の荷が下りた思いだった。
「ルフィーネが眼光のみで竜帝を退けたと聞いたが、真か!?」
「はい、私も驚きましたが――しかもどうやら竜帝は姫に忠誠を誓った様子。不思議な事もあるものです――」
エヴァリーナから道中の苦労を聞くブルクハルトは、馬を魔導甲殻に並べて、しきりに頷いていた。
もっともエヴァリーナは、肝心なことをボカしている。正確に言えば、ルフィーネは竜帝を”幻惑”したのだから。
「悪魔付きというが、竜人かも知れんな、この子は! わははは!」
愉快そうに声を上げて笑うブルクハルトは、ルフィーネにとって叔父に当たる人物だ。クセのある金髪は獅子の鬣を思わせ、髪と同色の髭を口の周りに蓄えている。
鎧は鈍く光る銀色のフルプレートメイルを着用し、まさに無骨な武人――といった佇まいを見せるブルクハルト・アントネスクだ。
当年二十八歳となる彼は、マッティア、ゴードの両名とも同年齢で面識もあり、十年前にには次世代の三剣士と持て囃されたものだった。
――ただブルクハルトは魔法がからっきしだった為、その名声において、現在ではマッティアやゴードに及ばないのである。
そんなブルクハルトだが、彼はとても子供が好きだった。
何しろ首都へ向かう道すがら、度々ルフィーネの馬車に乗り込み、頬擦りを敢行するのだ。
「おお、おお、マルガリータの子、ルフィーネ! 可愛いのう! 可愛いのう! どうだ、ワシの筋肉! 見事だろう!」
頬擦りは、やがて必ず大胸筋擦りに変わる。それを経て腹筋や上腕筋を触らせるブルクハルトは、実にナイスバルクな男であった。
(な、なんで鎧をわざわざ脱ぐんだ……脱ぐのは、ダーリヤだけでいいのに……あ、暑苦しい……)
ルフィーネとしては、とても辛い。
ウットリと眺めるダーリヤは国にいる夫が思わず恋しくなるが、ここはぐっと我慢する。
だがしかし、頬擦りから大胸筋擦りに変わった辺りで、ルフィーネは幾度となく泡を吹いて倒れた。
しかし気にしないブルクハルトは、懲りることなく二の腕にルフィーネを乗せたりする。なのでアントネスクに入国以来、ルフィーネのテンションはダダ下がりであった。
「お、おぱーい……」
その上、吸えない、揉めない、舐められない、という非ぱい三原則を突きつけられたルフィーネは、将来がたまらなく不安になる。
何しろブルクハルトは、大量の離乳食を持っていたのだ。こうなってはダーリヤといえども、容易くおぱーいを飲ませてはくれなかった。
「む? ワシの乳で我慢するか? 父の乳だ、どうだ? といっても出ぬがな! わははは!」
(じょ、冗談じゃない……こいつ、何を考えていやがる……)
徐に胸を差し出すブルクハルトを見て、ルフィーネは白目を剥く。
そしてついに、アントネスクの首都ナルドリアへ到着したのだった。
◆◆
ナルドリアの城市を囲む城壁は聖王都リヒテンシュタインに比べれば、薄く低い。しかしだからといってアントネスクの防御が手薄かといえば、そんな事は無かった。
アントネスクはいわゆる半島の国であり、むしろ堅牢なことで有名だ。
何より西と南を断崖に囲まれ、東に広がるのは魔物が住まう森――北には天然の要害であるブルーギュリア山脈が横たわっているのだ。
つまりアントネスクは自然のままで、難攻不落を誇る要塞なのである。
「お帰りなさいませ、公爵閣下!」
「うむ、変わりなかったか?」
「はっ! 閣下のご威光の下、ナルドリアは如何なる時も平穏無事にございます!」
城壁の門で、ブルクハルトが門衛と二言三言、会話をした。
それだけで門が開くのだから、やはり公爵というのは立派なものである。
魔導甲殻も悠々と門を潜ると、エヴァリーナはホッと息をついた。
「それにしても、私、酔わなくなったなぁ。慣れって恐いわねー。こんな事ならヒスイに付いて行ってあげてもよかったかも? 今度、手紙でも書いてみようっと。ていうか彼女――魔王達を倒したんだから、ニホンって国に帰っちゃったのかな?」
不意にエヴァリーナは、黒髪で金色の瞳を持った旧友を思い出した。
転移した影響で茶色の瞳が金色になり、膨大な魔力を手に入れたヒスイは当初、それを嘆いていただけだ。
転移は――リヒター王国の軍事力増強が目的で定期的に行っている。だからヒスイは、ある意味で強引に連れてこられただけの被害者だった。
そんな彼女に齎されたのは、神託――勇者としての運命を自覚したのは、それからのことだ。
おりしも魔導甲殻の開発が進み、実戦投入が開始された丁度その頃のこと。
ヒスイに与えられた魔導甲殻は”ルドミラ”。暗黒騎士であるゴードの魔導甲殻”ヴァーツラフ”の姉妹騎だった。
それは優れた格闘性能と、使用者の魔力を極限にまで高める魔導核を備えた騎体で、未だこれを越える騎体をリヒター王国も作れていない。
ともかく勇者となったヒスイはゴードと共に”ルドミラ型”魔導甲殻十三騎で、七王魔国を陥落せしめたのである。
「まあいいわ。帰ったなら帰ったで、それは彼女の望むところだし――帰っていないなら、友達として、泣き虫ヒスイを慰めてあげるくらい、してあげなくっちゃ――」
あっさりと魔王討伐を断った割に友人として勇者ヒスイを心配するエヴァリーナは、正直な所、自分が誰も友人の居ない地に来て、初めてヒスイの気持ちが分かったのかも知れない。
城門を潜り、石畳の街並みを馬車は進む。
アントネスクの人々は”魔導甲殻”が珍しいらしく、その姿を目にする度に、二度、三度と振り返っていた。
流石にこれではエヴァリーナといえども顔を晒し続ける気になれず、甲殻の前面を閉じ、移動方法を歩行に切り替えた。
◆◆◆
「我が城の名は、ローレライという――かつてこの湖には、そんな名前の魔物が住んでおってな。我が祖先がそれを打ち倒し、泉の中央に居館を作ったのが始まりだ」
ルフィーネを抱き、口髭を震わせて説明をする屈強な武人は、ブルクハルト・アントネスクという。
抱かれたルフィーネは眠っているというより、気を失っていた。何しろここ数日、ずっとブルクハルトに抱かれているのだから、精神も病みそうである。
「やみ、や、みルフィーネたん、ばくたん……」
乾いた口をぱくぱくと動かしながら、ルフィーネがこんな言葉を漏らす。いよいよ末期のようだ。
ローレライ城はリヒテンシュタインの王城に比べれば大分小さいが、それでも湖の中ほどに聳える白亜の城は、幻想的で美しい。
さらに泉の上には、幾つもの巨大な船が浮いていた。これもまた、不思議な雰囲気を醸し出している。
「あれは飛空艦。我がアントネスクが誇る無敵の空中要塞だ――興味があるなら、いずれルフィーネ、お前も乗せてやろう」
「ひくーかん?」
流線型の船体を眺めたルフィーネは、少しだけ生気を取り戻した。
白に青に赤――それから黄色の艦が湖に浮いている。
(どこの戦隊の船体だよっ!)
と、オヤジギャグが脳裏を過ぎる実年齢三十六歳のルフィーネは、ニヤリと笑っていた。
そうしているうちに、ブルクハルトが湖の上を歩いている。
ルフィーネは下を見下ろし、
「ひぃぃ!」
と、情けない悲鳴を上げた。
しかしエヴァリーナも魔導甲殻に乗ったまま、悠々と湖の上を進んでいる事を見れば、
(これも、何かの魔法?)
そう考えて、なんとなく納得をしたルフィーネだ。
こうしてルフィーネは無事、アントネスク公国に保護されることとなった。
同時にダーリヤと護衛の騎士達は、リヒター王国へと引き返す。
「姫を、姫をどうかよろしくお願い致します……」
ダーリヤはブルクハルトに涙を流して懇願したという。
護衛の兵達も――ルフィーネは竜帝さえ従えた――そう考えていたから、リヒター王国の宝ではないかと考え始めていた。
「我等、一朝事ある時は、ルフィーネ姫を主君と仰ぐ所存――」
そう言って、帰路についたという事である。
彼らもまた――やがて来る動乱の気配を感じ、暗雲が立ち込めるであろう未来を予見しているのだった。
風竜帝の羽ばたき一つで、馬車が倒れそうになる。それを抑えるエヴァリーナは、導甲殻の無機質なレンズをダーリヤに向けた。
(私が時間を稼ぐから、逃げて)
風に乗せて、エヴァリーナは声をダーリヤの耳に入れる。
しかしダーリヤは、小さく首を横に振った。そして視線をルフィーネに向けると、
「姫が、何かを為そうとしています。私は乳母として、それを見届けなければなりません」
ある意味でダーリヤは誰よりもルフィーネを理解していた。そして期待してもいたのである。
しかし外に出たルフィーネは上空を見上げると、小さな口をあんぐりと開けて、
「ぴぎゃああああああ」
と、泣き出した。案の定のことだ。
ダメなおっさんが戦艦クラスに大きい竜を目の当たりにして、泣かない訳が無い。そこに救いがあるとすれば、絵面がおっさんの泣き顔ではなく、一歳児の泣き顔という程度だろう。
しかし困ったのはダーリヤだ。
(確かに外へ出たいと、姫は言ったはず)
ダーリヤは風竜帝の巨大な口と顔に吸い込まれそうな感覚を抱きつつ、ルフィーネの命だけは助けてもらおうと、跪く。
やはりエヴァリーナの言うとおり、逃げておけば良かったか――? そう思うが、逃げた所で助かるとも思えないダーリヤだ。
その時――。
「か、え、れ! ――おま、かえれぇぇえええ!」
ルフィーネは言葉にならない声で、確かにいった。
瞳に涙をいっぱいに溜めて、それでも風竜帝の巨大な目を見据えてルフィーネは言ったのだ。
もう、恐すぎて思考回路がぶっ壊れてしまったルフィーネである。
”ゴウゥゥ――”
大気の流れが変わり、突風が雪を舞い上げる。
風竜帝の鼻息だった。
そして風竜帝は、その長く大きな首を縦に振ったのだ。
「――我が愛しき姫よ――我は――そなたの仰せのままに」
ルフィーネを見つめた風竜帝の瞳が、瞬間、真紅に染まる。
同時にルフィーネの左目も紅玉の如く赤々と輝いていたが、それに気付ける者はいない。誰もが余裕を失っていたのだ。
――――
風竜帝は、眼下で泣き喚く幼女が悪魔付きだと認識していた。
喰らうもよし――焼き尽くすもよし――そう考えていた。
しかし、幼女は内心で何かを考えているようにも見える。
(――言い訳があるのなら、一言位聞いてやってもいい――)
それは圧倒的強者の傲慢かも知れない。だが、風竜帝はそう思った。
その時――彼の心に一陣の風が吹いた。
それは爽やかにして甘い――そして何より、とろけるように柔らかかった。
眼下で泣く幼女が――何よりも大切に思えた瞬間である。
今、風竜帝の目にルフィーネは、艶やかな肢体を持つ絶世の美女に見えていた。そしてそれは――ルフィーネが成長した姿に違いなく、それゆえにこそ風竜帝の心を捕らえたのである。
人はこれを”サキュバスの幻惑”という。
だが風竜帝はこの時思った――。
(久しいな、我が恋とは――)
と。
風竜帝は遥かな昔、自分を裏切った悪魔公爵の女を思い出していた。
そう――風竜帝はかつて、悪魔に恋をしたのだ。
だが、それは報われない恋だった――。
彼女は魔王を目指し、そしてその為には多くの男を虜にせねばならなかったのだから。
風竜帝が恋した悪魔――その名をミスティ・ハーティスという――彼女の死を、風竜帝は未だ知らなかった。
それはともかく、一歳児に鼻息を荒くする帝を見た竜王達は皆、複雑な心境だったに違いない。
(ギリアスさま、ないわー。これだったら、我だけで来たほうがよかったわー)
(まただよ、この色ボケ。抗魔くらいしろっつの)
(ギリアスさまってロリコン、通り越してねえっすか? しかもまた悪魔だし――)
しかし彼らが内心を口にする事は、永遠にないだろう。竜達の忠誠とは、そういうものなのだから。
こうして竜達は飛び退り、ルフィーネ達一向は災禍を逃れたのである。
◆◆
およそ一月の旅も、漸く終わりを告げる。季節も巡り、春が訪れようとしていた。
アントネスク領に入った一行は、その最初の街で歓待を受け、百人からなる護衛団をつけてもらった。それらはすべて、領主である公爵ブルクハルト・アントネスクの計らいだという。
また、護衛団を率いていた人物こそがブルクハルト本人だったのだから、エヴァリーナも肩の荷が下りた思いだった。
「ルフィーネが眼光のみで竜帝を退けたと聞いたが、真か!?」
「はい、私も驚きましたが――しかもどうやら竜帝は姫に忠誠を誓った様子。不思議な事もあるものです――」
エヴァリーナから道中の苦労を聞くブルクハルトは、馬を魔導甲殻に並べて、しきりに頷いていた。
もっともエヴァリーナは、肝心なことをボカしている。正確に言えば、ルフィーネは竜帝を”幻惑”したのだから。
「悪魔付きというが、竜人かも知れんな、この子は! わははは!」
愉快そうに声を上げて笑うブルクハルトは、ルフィーネにとって叔父に当たる人物だ。クセのある金髪は獅子の鬣を思わせ、髪と同色の髭を口の周りに蓄えている。
鎧は鈍く光る銀色のフルプレートメイルを着用し、まさに無骨な武人――といった佇まいを見せるブルクハルト・アントネスクだ。
当年二十八歳となる彼は、マッティア、ゴードの両名とも同年齢で面識もあり、十年前にには次世代の三剣士と持て囃されたものだった。
――ただブルクハルトは魔法がからっきしだった為、その名声において、現在ではマッティアやゴードに及ばないのである。
そんなブルクハルトだが、彼はとても子供が好きだった。
何しろ首都へ向かう道すがら、度々ルフィーネの馬車に乗り込み、頬擦りを敢行するのだ。
「おお、おお、マルガリータの子、ルフィーネ! 可愛いのう! 可愛いのう! どうだ、ワシの筋肉! 見事だろう!」
頬擦りは、やがて必ず大胸筋擦りに変わる。それを経て腹筋や上腕筋を触らせるブルクハルトは、実にナイスバルクな男であった。
(な、なんで鎧をわざわざ脱ぐんだ……脱ぐのは、ダーリヤだけでいいのに……あ、暑苦しい……)
ルフィーネとしては、とても辛い。
ウットリと眺めるダーリヤは国にいる夫が思わず恋しくなるが、ここはぐっと我慢する。
だがしかし、頬擦りから大胸筋擦りに変わった辺りで、ルフィーネは幾度となく泡を吹いて倒れた。
しかし気にしないブルクハルトは、懲りることなく二の腕にルフィーネを乗せたりする。なのでアントネスクに入国以来、ルフィーネのテンションはダダ下がりであった。
「お、おぱーい……」
その上、吸えない、揉めない、舐められない、という非ぱい三原則を突きつけられたルフィーネは、将来がたまらなく不安になる。
何しろブルクハルトは、大量の離乳食を持っていたのだ。こうなってはダーリヤといえども、容易くおぱーいを飲ませてはくれなかった。
「む? ワシの乳で我慢するか? 父の乳だ、どうだ? といっても出ぬがな! わははは!」
(じょ、冗談じゃない……こいつ、何を考えていやがる……)
徐に胸を差し出すブルクハルトを見て、ルフィーネは白目を剥く。
そしてついに、アントネスクの首都ナルドリアへ到着したのだった。
◆◆
ナルドリアの城市を囲む城壁は聖王都リヒテンシュタインに比べれば、薄く低い。しかしだからといってアントネスクの防御が手薄かといえば、そんな事は無かった。
アントネスクはいわゆる半島の国であり、むしろ堅牢なことで有名だ。
何より西と南を断崖に囲まれ、東に広がるのは魔物が住まう森――北には天然の要害であるブルーギュリア山脈が横たわっているのだ。
つまりアントネスクは自然のままで、難攻不落を誇る要塞なのである。
「お帰りなさいませ、公爵閣下!」
「うむ、変わりなかったか?」
「はっ! 閣下のご威光の下、ナルドリアは如何なる時も平穏無事にございます!」
城壁の門で、ブルクハルトが門衛と二言三言、会話をした。
それだけで門が開くのだから、やはり公爵というのは立派なものである。
魔導甲殻も悠々と門を潜ると、エヴァリーナはホッと息をついた。
「それにしても、私、酔わなくなったなぁ。慣れって恐いわねー。こんな事ならヒスイに付いて行ってあげてもよかったかも? 今度、手紙でも書いてみようっと。ていうか彼女――魔王達を倒したんだから、ニホンって国に帰っちゃったのかな?」
不意にエヴァリーナは、黒髪で金色の瞳を持った旧友を思い出した。
転移した影響で茶色の瞳が金色になり、膨大な魔力を手に入れたヒスイは当初、それを嘆いていただけだ。
転移は――リヒター王国の軍事力増強が目的で定期的に行っている。だからヒスイは、ある意味で強引に連れてこられただけの被害者だった。
そんな彼女に齎されたのは、神託――勇者としての運命を自覚したのは、それからのことだ。
おりしも魔導甲殻の開発が進み、実戦投入が開始された丁度その頃のこと。
ヒスイに与えられた魔導甲殻は”ルドミラ”。暗黒騎士であるゴードの魔導甲殻”ヴァーツラフ”の姉妹騎だった。
それは優れた格闘性能と、使用者の魔力を極限にまで高める魔導核を備えた騎体で、未だこれを越える騎体をリヒター王国も作れていない。
ともかく勇者となったヒスイはゴードと共に”ルドミラ型”魔導甲殻十三騎で、七王魔国を陥落せしめたのである。
「まあいいわ。帰ったなら帰ったで、それは彼女の望むところだし――帰っていないなら、友達として、泣き虫ヒスイを慰めてあげるくらい、してあげなくっちゃ――」
あっさりと魔王討伐を断った割に友人として勇者ヒスイを心配するエヴァリーナは、正直な所、自分が誰も友人の居ない地に来て、初めてヒスイの気持ちが分かったのかも知れない。
城門を潜り、石畳の街並みを馬車は進む。
アントネスクの人々は”魔導甲殻”が珍しいらしく、その姿を目にする度に、二度、三度と振り返っていた。
流石にこれではエヴァリーナといえども顔を晒し続ける気になれず、甲殻の前面を閉じ、移動方法を歩行に切り替えた。
◆◆◆
「我が城の名は、ローレライという――かつてこの湖には、そんな名前の魔物が住んでおってな。我が祖先がそれを打ち倒し、泉の中央に居館を作ったのが始まりだ」
ルフィーネを抱き、口髭を震わせて説明をする屈強な武人は、ブルクハルト・アントネスクという。
抱かれたルフィーネは眠っているというより、気を失っていた。何しろここ数日、ずっとブルクハルトに抱かれているのだから、精神も病みそうである。
「やみ、や、みルフィーネたん、ばくたん……」
乾いた口をぱくぱくと動かしながら、ルフィーネがこんな言葉を漏らす。いよいよ末期のようだ。
ローレライ城はリヒテンシュタインの王城に比べれば大分小さいが、それでも湖の中ほどに聳える白亜の城は、幻想的で美しい。
さらに泉の上には、幾つもの巨大な船が浮いていた。これもまた、不思議な雰囲気を醸し出している。
「あれは飛空艦。我がアントネスクが誇る無敵の空中要塞だ――興味があるなら、いずれルフィーネ、お前も乗せてやろう」
「ひくーかん?」
流線型の船体を眺めたルフィーネは、少しだけ生気を取り戻した。
白に青に赤――それから黄色の艦が湖に浮いている。
(どこの戦隊の船体だよっ!)
と、オヤジギャグが脳裏を過ぎる実年齢三十六歳のルフィーネは、ニヤリと笑っていた。
そうしているうちに、ブルクハルトが湖の上を歩いている。
ルフィーネは下を見下ろし、
「ひぃぃ!」
と、情けない悲鳴を上げた。
しかしエヴァリーナも魔導甲殻に乗ったまま、悠々と湖の上を進んでいる事を見れば、
(これも、何かの魔法?)
そう考えて、なんとなく納得をしたルフィーネだ。
こうしてルフィーネは無事、アントネスク公国に保護されることとなった。
同時にダーリヤと護衛の騎士達は、リヒター王国へと引き返す。
「姫を、姫をどうかよろしくお願い致します……」
ダーリヤはブルクハルトに涙を流して懇願したという。
護衛の兵達も――ルフィーネは竜帝さえ従えた――そう考えていたから、リヒター王国の宝ではないかと考え始めていた。
「我等、一朝事ある時は、ルフィーネ姫を主君と仰ぐ所存――」
そう言って、帰路についたという事である。
彼らもまた――やがて来る動乱の気配を感じ、暗雲が立ち込めるであろう未来を予見しているのだった。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します
namisan
ファンタジー
バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。
マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。
その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。
「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。
しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。
「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」
公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。
前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。
これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

転生したら名家の次男になりましたが、俺は汚点らしいです
NEXTブレイブ
ファンタジー
ただの人間、野上良は名家であるグリモワール家の次男に転生したが、その次男には名家の人間でありながら、汚点であるが、兄、姉、母からは愛されていたが、父親からは嫌われていた
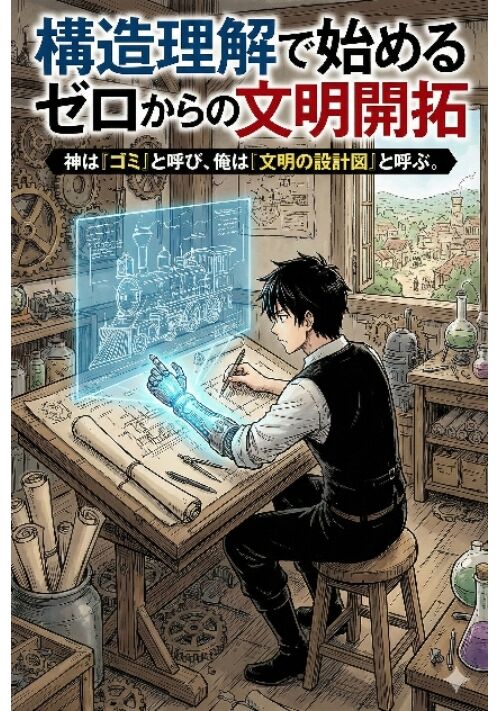
構造理解で始めるゼロからの文明開拓
TEKTO
ファンタジー
ブラック企業勤めのサラリーマン・シュウが転生したのは、人間も街も存在しない「完全未開の大陸」だった。
適当な神から与えられたのは、戦闘力ゼロ、魔法適性ゼロのゴミスキル《構造理解》。
だが、物の仕組みを「作れるレベル」で把握できるその力は、現代知識を持つ俺にとっては、最強の「文明構築ツール」だった――!
――これは、ゴミと呼ばれたスキルとガラクタと呼ばれた石で、世界を切り拓く男の物語。

冷遇王妃はときめかない
あんど もあ
ファンタジー
幼いころから婚約していた彼と結婚して王妃になった私。
だが、陛下は側妃だけを溺愛し、私は白い結婚のまま離宮へ追いやられる…って何てラッキー! 国の事は陛下と側妃様に任せて、私はこのまま離宮で何の責任も無い楽な生活を!…と思っていたのに…。

1歳児天使の異世界生活!
春爛漫
ファンタジー
夫に先立たれ、女手一つで子供を育て上げた皇 幸子。病気にかかり死んでしまうが、天使が迎えに来てくれて天界へ行くも、最高神の創造神様が一方的にまくしたてて、サチ・スメラギとして異世界アラタカラに創造神の使徒(天使)として送られてしまう。1歳の子供の身体になり、それなりに人に溶け込もうと頑張るお話。
※心は大人のなんちゃって幼児なので、あたたかい目で見守っていてください。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















