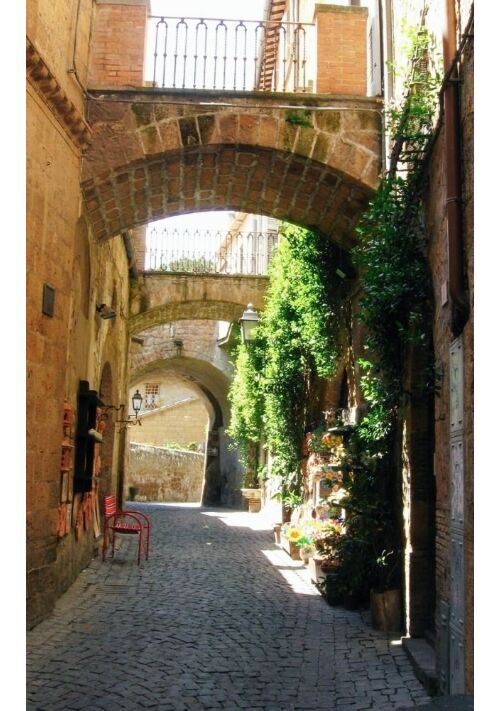56 / 57
第二章「別宮編」
分岐点
しおりを挟む
ああ、疲れた。
本当に疲れた。
家に帰ろう。
そうだ、家に帰ろう……。
「サーク!お帰り!」
「サーク!お帰り!」
リリとムクが満面の笑顔で迎えてくれた。
俺はふたりを抱き締めた。
ああ、家に帰って来たんだ……。
「ただいま、リリ。ただいま、ムク。」
「サーク、疲れてるね。」
「うん、もう疲れすぎて、こっちに帰って来たんだ。」
「ご飯食べる?」
「ん~ん、ご飯は起きてからでいい~。寝たい~。」
俺はそう言うと、ふたりを抱き上げた。
きゃっきゃ笑うリリとムク。
俺はそのままベッドに倒れ込んだ。
リリとムクが俺の頭を撫でてくれる。
「お疲れ様、サーク。」
「お疲れ様。ムクがお歌を歌ってあげる。」
「リリも歌う。」
ふたりはそういって歌いだした。
それは、声と言うより音に近くて、歌と言うより、静かな音楽だった。
それは、ここに始めてきた日。
あの森で眠くなった感覚にとてもよく似ていて、俺は何かを考える前に眠りに落ちていった。
「隊長、失礼しま~す!」
俺はそう言うと、ノックもせずにずかずかと隊長の部屋に入った。
昨日の今日で、こんなあっさり俺が来るとは思っていなかったのだろう。
隊長は死ぬほどびっくりした顔をしていた。
「……どうした、サーク。」
「話があって。」
「なんだ?」
「……当初の話と変わって悪いが、ひとまず魔術本部に行って修行してこようと思う。」
書類に目を落としていた隊長の肩が、ピクッと微かに震える。
俺の言葉に一度目を伏せ、そして言ったら。
「……わかった。対応しよう。」
それにほっと息を吐く。
隊長も俺にそう言われ気持ちが楽になると同時に、しかないとはいえ傷付いたという顔をした。
あの話し合いの時、俺達はどこか分かり合っていた。
たった一度、拳を交えただけなのに。
だが多分、今の俺達は、時間的にも距離的にも離れた時間を持った方がいい。
昨日の事で自分としては頭で理屈を理解していても、心が冷静にそれに納得し、自分の中に馴染むには時間がかかるからだ。
隊長の方は鉄の騎士精神があるからそれでもやっていけるかもしれないが、俺の方は多分無理だ。
自分の辛さや苦しさに素直にならず、無理をするとろくな事がないのはここしばらくで嫌というほど理解した。
だから俺は、自分の気持ちが安らげ楽な方法を取る事にしたのだ。
「悪いな。まだちょっと、ここにいると不安定になるんでね。」
「……すまない。」
「だから!もうそれやめろよ?!もうアレについては昨日のでおしまい。どんなに苦しくても、俺たちは背負うもん背負って前に進むんだ。」
「……そうだな。」
俺はさらりと言い切った。
それに隊長が下手くそな顔で笑う。
普段から無表情だから、ぎこちない笑顔というヤツが、他の人の何杯もぎこちなくて変だ。
でも、それで十分だった。
隊長が何を考え、自分の中でどんな結論を出したのかは知らない。
だが、ぎこちなくとも笑おうとしたという事は、隊長なりに前に進む覚悟があるのだろう。
それに安心し、俺は部屋を出ようとした。
「じゃ、よろしく。」
「……サーク。」
「何だよ?」
話はついたのだから、サクッと終わらせたい。
なのに隊長は俺を呼び止める。
少しイラッとして顔を向けると、隊長は少し言い淀んでから言った。
「……お前とレオンハルド氏は、どういう関係なんだ?」
突然出てきたその名前にカッと顔に血が登る。
名前を聞いただけでもう、条件反射で赤面してしまう。
え?!何で??
何で執事さんの名前がここで出てくるんだ?!
俺はそう言われ、少し困ってしまった。
気恥ずかしくなって、顔を掻いた。
いやだって!!
今その名前聞いちゃうと!!
あああぁぁぁ!!
待って?!
待ってくれ!!
俺は「おまじない」を思い出してもじもじしてしまう。
「……前、言ったじゃん。俺、好きな人がいるって……。とはいえ、ただの片想いだけど……。」
その時、変な事が起きた。
好きな人……。
その言葉を口にした時、俺は何故かもう一人、他の人物も一緒に思い浮かべていた。
その人の事を思い出すと、執事さんの名前を聞いて落ち着かなかった浮ついた気持ちが鎮まっていく。
それは夜の静けさのように心地良かった。
そして何かストンと腑に落ちた。
でもだからって、好きな人がふたりって……。
それでいいのか?俺!?
少し前までは、恋すら理解できていなかったのに……。
そんな自分がちょっとおかしい。
しかし隊長はそんなことには気づかず、難しい顔つきで続けた。
「お前はあの人が何者なのか知っているのか?」
「殿下の執事長だろ?」
「……表向きはな。」
その言葉に俺は眉を顰める。
表向き、と言う事は本来は違うという意味だ。
「……どういう事だ?」
俺の知っているあの人は、いつだってスマートだった。
「執事」という俺のイメージを完璧に纏っていた完全無欠な人。
所作も優雅で美しく、静かで物事の機転が利く。
穏やかなのに隙がなくて、ユーモアもある。
俺の初恋の執事さんなのだ。
なのに、あの人がそれ以外の何かだなんて……。
複雑な顔をする俺を、隊長はじっと見つめた後、言った。
「あの人はこの国のみならず、世界に名の知れた諜報員であり……アサシンだ。」
ビクッと俺の肩が震える。
肩というより、体の芯の方が震えた。
本当はどこかでわかっていた。
でも知りたくなかった。
思うところがなかった訳じゃない。
いつだって気配なく現れたその人。
その動き、美しい所作の中にある鋭さ。
だって俺はあの人が好きだった。
だから会えた時は誰よりもあの人を見ていたのだ。
だから気づいてた。
でも、見ないふりをした。
だってあの人が好きだから。
俺の初恋の「執事さん」でいて欲しかったんだ。
だから見ないふりをしてきた。
気づかない事にしてきた。
なのに……。
「……うそ……。」
「近々、その任を果たすことになる。」
「そんな……じゃあ……。」
呆然とする俺に、隊長は淡々と告げる。
言葉無く取り乱す俺をじっと見つめた後、言った。
「……おそらくもう、会うことはない。」
俺はそれを知って愕然とした。
自分の中が暗くなり、何かが崩れていった。
「サーク様。」
そう声が聞こえ、俺は振り向いた。
いつもなら飛び上がるほど嬉しいのに、今日はただ悲しかった。
「……あなたはいつも、音もなく現れるんですね……。」
俺は困ったように笑った。
そんな俺の顔から、レオンハルドさんは何かを読み解いたようだった。
「そのご様子ですと、既に知っておられるのですね?私の事を……。」
レオンハルドさんは、少し寂しげに笑った。
多分、レオンハルドさんも、俺と同じ様に思っていたのだと思う。
「あなたには最後まで、優しくてお茶目な執事さんとして覚えていて頂きたかったのですけどね……。」
残念そうな言葉。
俺も、あなたの事は「初恋の執事さん」として見続けていたかった。
でも……。
俺は本当は知っていた。
本当は気づいていた。
だって……。
「あなただったんですね、あの時、アサシンの首を斬ったのは……。」
そう、銀色。
あの日、俺が王子を狙った暗殺者の前に飛び出して死にかけた時、すんでのところで俺の体を引っ張ってその刃から救おうとしてくれた人。
俺を抱き寄せながら、暗殺者の首を一撃で跳ねた誰か。
青空に映えた、銀色。
俺が恋に落ちたのは病室じゃない。
多分、この時だ。
あの時それに強く惹かれたから、病室で再会してトドメを刺されたんだ。
でも「執事さん」と「銀色の人」があまりにイメージが重ならなくて。
俺は「執事さん」に恋をしていたから、それを気づかないふりをしたんだ。
「………ええ、そうです。私です。」
残念そうな言葉。
いつもは穏やかな表情が僅かに曇り眉を寄せている。
レオンハルドさんが何故それを俺に知られたくなかったのかはわからない。
でも、俺が気づかないふりをしていた理由は知ってる。
「ごめんなさい!俺は余計な事を……!!」
激しい後悔。
自分が愚かで恥ずかしい。
いたたまれなくて頭を下げる。
「どうされたのです?」
「あの時、俺が飛び込む必要なんかなかった!かえってあなたの邪魔をした!」
そう、俺は思わずあの時王子とアサシンの間に魔術で飛び込んだがレオンハルドさんからみれば、斬りにいこうとしたところに障害物が現れた様に見えたはずだ。
俺が飛び込まなくても、レオンハルドさんなら容易くアサシンを斬っていただろう。
俺が気づきながらも、無自覚に二つを結び付けなかった理由。
カッコつけてあんな事をしたのに、好きな人にとっては邪魔でしかなかった自分がいたたまれないからだ。
俺の言いたい事が見えたのだろう。
レオンハルドさんはすっと俺の側に来ると、優しく頭に手を置いた。
「……あの時、私は天使を見ました。」
己の愚かさに俯き苦々しく語る俺とは対照的に、レオンハルドさんは穏やかに言った。
顔を上げると、いつものように優しく微笑んでくれる。
「傷付いた仲間の仇を取るため、何の迷いもなく、あなたは敵の刃の前にその身を差し出した。何の見返りも求めず、ただ、己の信念の赴くままにその命を掲げたのです。」
レオンハルドさんはじっと俺の顔を覗き込む。
俺もその目の中を見つめ返した。
「私の上部だけの心に、それは奥まで刺さり深みを与えました。どう効率よく相手を殺すかしか考えられない私には、あなたは眩しかった。あなたのそれは無鉄砲な事かもしれない。でも私利私欲など欠片も持たず、仲間の為、己が信念の為に剥き出しの魂そのもので立ち向かったあなたは美しく、そして眩しかった。」
レオンハルドさんがすっと俺の手を握った。
驚きと気恥ずかしさで思わず引っ込めようとしたが、彼はしっかりと俺の手を握って離さなかった。
そして強い視線で俺の双眸を見つめる。
「これから色々とお辛いこともあるでしょう。その中で騎士として人として成長していくであろう貴方を、お側で見守ることができず残念です。ですがどうか、あなたのその真っ直ぐな信念をなくさないで下さい。」
レオンハルドさんはそう言うと、握っていた俺の手の甲にそっと口付けた。
大事そうに俺の手を包んでくれるレオンハルドさんの、少し節くれだった手。
真似ではなく、本当に手の甲に口付ける意味を俺はぼんやりと考えた。
俺の好きな人。
初恋の人。
その人の温かく優しく、そして哀しげな眼をじっと見つめる。
「それからお願いです。どうか私の事はお忘れ下さい。私は私がいるべき闇に還ります。もう、サーク様にお会いすることはないでしょう。」
俺は何も言わなかった。
嫌だともわかったとも言わなかった。
「行かれるんですね、遠くに……。」
代わりにそう言った。
少し鼻の奥がツンとした。
「ええ、サーク様が決して来られない場所に行きます。」
もう会えない。
その言葉を否定したいのに、今のひ弱な俺にはできなかった。
だからって何もしないで終わる訳にはいかない。
俺は自分の意思を強く込めて、レオンハルドさんを見つめた。
「では、もらって頂きたいものがあります。」
「何でしょう?」
「……私の初恋です。」
俺はそう言うと、勢いをつけてレオンハルドさんにキスをした。
好きな人に口付けなんてしたことがないから感覚が掴めなくて、初々しく可愛いどころか、勢い余ってガツンと衝突したみたいなキスになってしまった。
下手くそな口付け。
それでも驚くレオンハルドさんに、してやったりと俺は微笑んだ。
そして告げる。
「……あなたが忘れろと言うのなら、どうかこの恋をお持ちください。たとえ私が忘れても、私の初恋がこの世界に残れるように……。」
レオンハルドさんは、意表を突かれたような顔をした。
そしてしばらく俺の目を覗き込んでいた。
その表情がふっと緩む。
「……全く。サーク様は、いつも私の予想をはるかに越えて来られる。……だから目が離せないのです。」
そう言って笑った。
それは俺の知っている「初恋の執事さん」のものだった。
「……わかりました。サーク様の初恋、このレオンハルド、確かに受けとりました。これから私は影なる暗き場所へと行きますが、あなたからの贈り物がきっと私の支えとなるでしょう。」
レオンハルドさんはそういって、俺の額にキスしてくれた。
ちょっとチクチクとした口ひげの感覚がおでこに残る。
さよならは言わなかった。
鼻の奥がツンと痛かったが、俺はできるだけ、その人の前では笑っていた。
本当に疲れた。
家に帰ろう。
そうだ、家に帰ろう……。
「サーク!お帰り!」
「サーク!お帰り!」
リリとムクが満面の笑顔で迎えてくれた。
俺はふたりを抱き締めた。
ああ、家に帰って来たんだ……。
「ただいま、リリ。ただいま、ムク。」
「サーク、疲れてるね。」
「うん、もう疲れすぎて、こっちに帰って来たんだ。」
「ご飯食べる?」
「ん~ん、ご飯は起きてからでいい~。寝たい~。」
俺はそう言うと、ふたりを抱き上げた。
きゃっきゃ笑うリリとムク。
俺はそのままベッドに倒れ込んだ。
リリとムクが俺の頭を撫でてくれる。
「お疲れ様、サーク。」
「お疲れ様。ムクがお歌を歌ってあげる。」
「リリも歌う。」
ふたりはそういって歌いだした。
それは、声と言うより音に近くて、歌と言うより、静かな音楽だった。
それは、ここに始めてきた日。
あの森で眠くなった感覚にとてもよく似ていて、俺は何かを考える前に眠りに落ちていった。
「隊長、失礼しま~す!」
俺はそう言うと、ノックもせずにずかずかと隊長の部屋に入った。
昨日の今日で、こんなあっさり俺が来るとは思っていなかったのだろう。
隊長は死ぬほどびっくりした顔をしていた。
「……どうした、サーク。」
「話があって。」
「なんだ?」
「……当初の話と変わって悪いが、ひとまず魔術本部に行って修行してこようと思う。」
書類に目を落としていた隊長の肩が、ピクッと微かに震える。
俺の言葉に一度目を伏せ、そして言ったら。
「……わかった。対応しよう。」
それにほっと息を吐く。
隊長も俺にそう言われ気持ちが楽になると同時に、しかないとはいえ傷付いたという顔をした。
あの話し合いの時、俺達はどこか分かり合っていた。
たった一度、拳を交えただけなのに。
だが多分、今の俺達は、時間的にも距離的にも離れた時間を持った方がいい。
昨日の事で自分としては頭で理屈を理解していても、心が冷静にそれに納得し、自分の中に馴染むには時間がかかるからだ。
隊長の方は鉄の騎士精神があるからそれでもやっていけるかもしれないが、俺の方は多分無理だ。
自分の辛さや苦しさに素直にならず、無理をするとろくな事がないのはここしばらくで嫌というほど理解した。
だから俺は、自分の気持ちが安らげ楽な方法を取る事にしたのだ。
「悪いな。まだちょっと、ここにいると不安定になるんでね。」
「……すまない。」
「だから!もうそれやめろよ?!もうアレについては昨日のでおしまい。どんなに苦しくても、俺たちは背負うもん背負って前に進むんだ。」
「……そうだな。」
俺はさらりと言い切った。
それに隊長が下手くそな顔で笑う。
普段から無表情だから、ぎこちない笑顔というヤツが、他の人の何杯もぎこちなくて変だ。
でも、それで十分だった。
隊長が何を考え、自分の中でどんな結論を出したのかは知らない。
だが、ぎこちなくとも笑おうとしたという事は、隊長なりに前に進む覚悟があるのだろう。
それに安心し、俺は部屋を出ようとした。
「じゃ、よろしく。」
「……サーク。」
「何だよ?」
話はついたのだから、サクッと終わらせたい。
なのに隊長は俺を呼び止める。
少しイラッとして顔を向けると、隊長は少し言い淀んでから言った。
「……お前とレオンハルド氏は、どういう関係なんだ?」
突然出てきたその名前にカッと顔に血が登る。
名前を聞いただけでもう、条件反射で赤面してしまう。
え?!何で??
何で執事さんの名前がここで出てくるんだ?!
俺はそう言われ、少し困ってしまった。
気恥ずかしくなって、顔を掻いた。
いやだって!!
今その名前聞いちゃうと!!
あああぁぁぁ!!
待って?!
待ってくれ!!
俺は「おまじない」を思い出してもじもじしてしまう。
「……前、言ったじゃん。俺、好きな人がいるって……。とはいえ、ただの片想いだけど……。」
その時、変な事が起きた。
好きな人……。
その言葉を口にした時、俺は何故かもう一人、他の人物も一緒に思い浮かべていた。
その人の事を思い出すと、執事さんの名前を聞いて落ち着かなかった浮ついた気持ちが鎮まっていく。
それは夜の静けさのように心地良かった。
そして何かストンと腑に落ちた。
でもだからって、好きな人がふたりって……。
それでいいのか?俺!?
少し前までは、恋すら理解できていなかったのに……。
そんな自分がちょっとおかしい。
しかし隊長はそんなことには気づかず、難しい顔つきで続けた。
「お前はあの人が何者なのか知っているのか?」
「殿下の執事長だろ?」
「……表向きはな。」
その言葉に俺は眉を顰める。
表向き、と言う事は本来は違うという意味だ。
「……どういう事だ?」
俺の知っているあの人は、いつだってスマートだった。
「執事」という俺のイメージを完璧に纏っていた完全無欠な人。
所作も優雅で美しく、静かで物事の機転が利く。
穏やかなのに隙がなくて、ユーモアもある。
俺の初恋の執事さんなのだ。
なのに、あの人がそれ以外の何かだなんて……。
複雑な顔をする俺を、隊長はじっと見つめた後、言った。
「あの人はこの国のみならず、世界に名の知れた諜報員であり……アサシンだ。」
ビクッと俺の肩が震える。
肩というより、体の芯の方が震えた。
本当はどこかでわかっていた。
でも知りたくなかった。
思うところがなかった訳じゃない。
いつだって気配なく現れたその人。
その動き、美しい所作の中にある鋭さ。
だって俺はあの人が好きだった。
だから会えた時は誰よりもあの人を見ていたのだ。
だから気づいてた。
でも、見ないふりをした。
だってあの人が好きだから。
俺の初恋の「執事さん」でいて欲しかったんだ。
だから見ないふりをしてきた。
気づかない事にしてきた。
なのに……。
「……うそ……。」
「近々、その任を果たすことになる。」
「そんな……じゃあ……。」
呆然とする俺に、隊長は淡々と告げる。
言葉無く取り乱す俺をじっと見つめた後、言った。
「……おそらくもう、会うことはない。」
俺はそれを知って愕然とした。
自分の中が暗くなり、何かが崩れていった。
「サーク様。」
そう声が聞こえ、俺は振り向いた。
いつもなら飛び上がるほど嬉しいのに、今日はただ悲しかった。
「……あなたはいつも、音もなく現れるんですね……。」
俺は困ったように笑った。
そんな俺の顔から、レオンハルドさんは何かを読み解いたようだった。
「そのご様子ですと、既に知っておられるのですね?私の事を……。」
レオンハルドさんは、少し寂しげに笑った。
多分、レオンハルドさんも、俺と同じ様に思っていたのだと思う。
「あなたには最後まで、優しくてお茶目な執事さんとして覚えていて頂きたかったのですけどね……。」
残念そうな言葉。
俺も、あなたの事は「初恋の執事さん」として見続けていたかった。
でも……。
俺は本当は知っていた。
本当は気づいていた。
だって……。
「あなただったんですね、あの時、アサシンの首を斬ったのは……。」
そう、銀色。
あの日、俺が王子を狙った暗殺者の前に飛び出して死にかけた時、すんでのところで俺の体を引っ張ってその刃から救おうとしてくれた人。
俺を抱き寄せながら、暗殺者の首を一撃で跳ねた誰か。
青空に映えた、銀色。
俺が恋に落ちたのは病室じゃない。
多分、この時だ。
あの時それに強く惹かれたから、病室で再会してトドメを刺されたんだ。
でも「執事さん」と「銀色の人」があまりにイメージが重ならなくて。
俺は「執事さん」に恋をしていたから、それを気づかないふりをしたんだ。
「………ええ、そうです。私です。」
残念そうな言葉。
いつもは穏やかな表情が僅かに曇り眉を寄せている。
レオンハルドさんが何故それを俺に知られたくなかったのかはわからない。
でも、俺が気づかないふりをしていた理由は知ってる。
「ごめんなさい!俺は余計な事を……!!」
激しい後悔。
自分が愚かで恥ずかしい。
いたたまれなくて頭を下げる。
「どうされたのです?」
「あの時、俺が飛び込む必要なんかなかった!かえってあなたの邪魔をした!」
そう、俺は思わずあの時王子とアサシンの間に魔術で飛び込んだがレオンハルドさんからみれば、斬りにいこうとしたところに障害物が現れた様に見えたはずだ。
俺が飛び込まなくても、レオンハルドさんなら容易くアサシンを斬っていただろう。
俺が気づきながらも、無自覚に二つを結び付けなかった理由。
カッコつけてあんな事をしたのに、好きな人にとっては邪魔でしかなかった自分がいたたまれないからだ。
俺の言いたい事が見えたのだろう。
レオンハルドさんはすっと俺の側に来ると、優しく頭に手を置いた。
「……あの時、私は天使を見ました。」
己の愚かさに俯き苦々しく語る俺とは対照的に、レオンハルドさんは穏やかに言った。
顔を上げると、いつものように優しく微笑んでくれる。
「傷付いた仲間の仇を取るため、何の迷いもなく、あなたは敵の刃の前にその身を差し出した。何の見返りも求めず、ただ、己の信念の赴くままにその命を掲げたのです。」
レオンハルドさんはじっと俺の顔を覗き込む。
俺もその目の中を見つめ返した。
「私の上部だけの心に、それは奥まで刺さり深みを与えました。どう効率よく相手を殺すかしか考えられない私には、あなたは眩しかった。あなたのそれは無鉄砲な事かもしれない。でも私利私欲など欠片も持たず、仲間の為、己が信念の為に剥き出しの魂そのもので立ち向かったあなたは美しく、そして眩しかった。」
レオンハルドさんがすっと俺の手を握った。
驚きと気恥ずかしさで思わず引っ込めようとしたが、彼はしっかりと俺の手を握って離さなかった。
そして強い視線で俺の双眸を見つめる。
「これから色々とお辛いこともあるでしょう。その中で騎士として人として成長していくであろう貴方を、お側で見守ることができず残念です。ですがどうか、あなたのその真っ直ぐな信念をなくさないで下さい。」
レオンハルドさんはそう言うと、握っていた俺の手の甲にそっと口付けた。
大事そうに俺の手を包んでくれるレオンハルドさんの、少し節くれだった手。
真似ではなく、本当に手の甲に口付ける意味を俺はぼんやりと考えた。
俺の好きな人。
初恋の人。
その人の温かく優しく、そして哀しげな眼をじっと見つめる。
「それからお願いです。どうか私の事はお忘れ下さい。私は私がいるべき闇に還ります。もう、サーク様にお会いすることはないでしょう。」
俺は何も言わなかった。
嫌だともわかったとも言わなかった。
「行かれるんですね、遠くに……。」
代わりにそう言った。
少し鼻の奥がツンとした。
「ええ、サーク様が決して来られない場所に行きます。」
もう会えない。
その言葉を否定したいのに、今のひ弱な俺にはできなかった。
だからって何もしないで終わる訳にはいかない。
俺は自分の意思を強く込めて、レオンハルドさんを見つめた。
「では、もらって頂きたいものがあります。」
「何でしょう?」
「……私の初恋です。」
俺はそう言うと、勢いをつけてレオンハルドさんにキスをした。
好きな人に口付けなんてしたことがないから感覚が掴めなくて、初々しく可愛いどころか、勢い余ってガツンと衝突したみたいなキスになってしまった。
下手くそな口付け。
それでも驚くレオンハルドさんに、してやったりと俺は微笑んだ。
そして告げる。
「……あなたが忘れろと言うのなら、どうかこの恋をお持ちください。たとえ私が忘れても、私の初恋がこの世界に残れるように……。」
レオンハルドさんは、意表を突かれたような顔をした。
そしてしばらく俺の目を覗き込んでいた。
その表情がふっと緩む。
「……全く。サーク様は、いつも私の予想をはるかに越えて来られる。……だから目が離せないのです。」
そう言って笑った。
それは俺の知っている「初恋の執事さん」のものだった。
「……わかりました。サーク様の初恋、このレオンハルド、確かに受けとりました。これから私は影なる暗き場所へと行きますが、あなたからの贈り物がきっと私の支えとなるでしょう。」
レオンハルドさんはそういって、俺の額にキスしてくれた。
ちょっとチクチクとした口ひげの感覚がおでこに残る。
さよならは言わなかった。
鼻の奥がツンと痛かったが、俺はできるだけ、その人の前では笑っていた。
応援ありがとうございます!
20
お気に入りに追加
34
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる