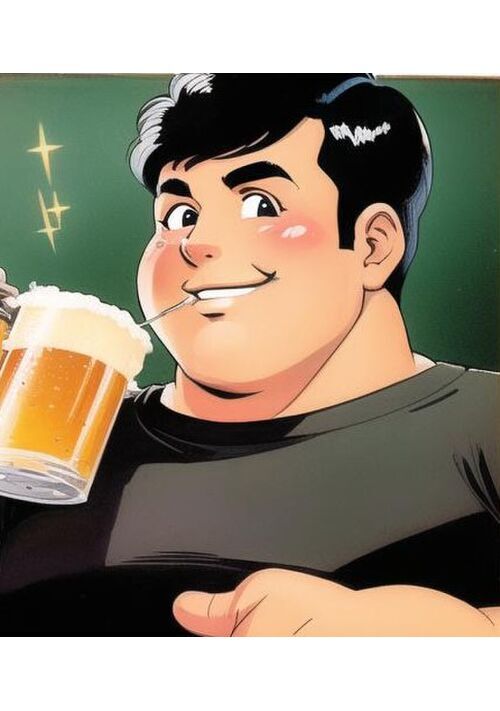122 / 129
111~120
(116)白留
しおりを挟む
蟲が発生した日、白花は留理に助けられた。それから二人は共に蟲を退治し、唯一無二の親友となっていったのだが――。
白花×留理。つよつよニコイチズッ友コンビにヒビが入るのが好きです!
留理(るり):「悍ましき日」に白花と出会い、現在はコンビで蟲討伐にあたっている。基本に無表情クール。白花には緩め。マフラーを大事にしている。長い黒髪を一つに束ねている。瞳は瑠璃色。ネーミングはルリアゲハ。
白花(はっか):基地の女性から絶大な人気を誇るイケメン。留理の前では割とおちゃらける。緑髪白眼。ネーミングはペパーミント(殺虫作用)。
火鋸(かのこ):前髪が長く、顔の見えない関西弁男子。強いので普段は討伐に引っ張りだこ。宮真と仲良し。ネーミングはひのき(殺虫作用)。
宮真(みやま):中性的な容姿と声でよく女の子に間違われるが男。火鋸のことが好き。ネーミングはミヤマカラスアゲハ。
クロエ:基地内一の美少女。白花のことが好き。留理と白花の仲を疑う。ネーミングは(白に対して)黒。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とある未来の話。地球はほぼほぼ侵略された。地球外からやってきた蟲によって追い詰められた。
残った人類は、必死に抵抗した。なんとか蟲たちを殺す兵器も作り上げた。
だけど戦いは長期戦へと縺れ込み、気付けば人間ももう千人程しか残っていなかった。
それでも、彼らは生きることを諦めてはいなかった。地球を守るために、蟲たちと懸命に戦った。戦って、傷つき、傷つけ合い。愚かな抵抗を続けていた。
*
「ほんと、次から次へと湧いてくる。まさに虫だな」
青年が緑髪を靡かせながら振るった剣は、衝撃波を生み、廃墟に巣食う蟲を一掃する。
その白眼に映し出されるものは、嫌悪であり憎悪であり。彼が蟲をどれほど憎んでいるのかが伺い知れる程、強い意志を宿していた。
「ほら、悪態ばっか吐いてないで。増援が来るよ、っと!」
黒髪の青年が、手に持ったリボルバーの引き金を引く。もぞりもぞりと悍ましい動きで前進してきた蟲に銃弾が命中し、さらに誘爆する。
「ヒュ~。相変わらずやるぅ」
焦げた蟲たちを覗き込みながら、緑髪の青年は口笛を吹く。
「白花、お喋りはいいから手を動かせ」
「ハイハイ。ってかその名前、呼ぶなって言ったろ」
白花と呼ばれた彼は、再び剣を振るいながら抗議する。
「名前が女っぽいから、だっけ?」
「そ。親がさ、女の子に用意してた名前をそのまま俺につけたんだよな~。女の子しか望んでなかったみたい。酷いだろ?」
「う~ん。わかんないな。僕は親に捨てられた身だし」
淡白に答えた青年に、白花は気まずそうな顔をしながらも、地面から這い出た蟲をぐしゃりと潰す。
「それを言われちゃアレだけど、さ。少なくとも昔の俺は親を恨んでた。クラスメイトからよく名前を揶揄われたし。男だったせいか、親に愛情注がれた記憶もないし」
「それは悲しいね」
「お前も『留理』ってさ、まあ女っぽい名前だよな。虐められたりしなかったか?」
「僕はそうでもないよ。この名前、結構気に入ってる」
瑠璃色に透き通った瞳が蟲の動きを察知して、白花に合図を送る。
「ま、俺もお前の名前、好きだけどっ!」
「じゃあ僕も君の名前、好きだよっと」
二人同時に放った攻撃が、辺りの蟲を薙ぎ払う。
「でもまあ、今となってはそう文句も言えねえけどな」
遠くの方を見つめ、寂しそうに呟いた白花を見て、留理は押し黙る。
(仕方のないことだ。彼の家族もクラスメイトも今はもういない。寂しさを感じない方がどうかしている。……もしかすると、僕の返答は少し冷たかったかもしれない)
留理が何と言葉を掛けようか考えあぐねていると、白花はそれに気づいてにこりと笑う。こういうところが今や数の少ない女性を虜にする所以だろう。
「それに。まぁ、留理に呼ばれるのは悪くないかな、なんて……」
「よし、ここらの蟲は片付いたな。戻るぞ」
キメ顔で芝居がかった台詞を吐いた白花に背を向け、留理が歩き出す。
「酷い! 俺の告白を無視するなんて!」
「蟲退治だけにか?」
「……留理のセンスって時々ズレてるよな」
「そうか?」
一瞬の沈黙の後、お互い顔を見合わせてくすりと笑う。
「戻ろう。今日は疲れた」
剣を仕舞った白花が、大きく伸びをしてズカズカと歩き出す。その足下には先の戦闘で殺した蟲たちの破片が、ゴミのように散らかっていた。
「ん、それは同感。最近、僕たち働き過ぎだよ」
留理はそれらをなるべく踏まないように注意しながら、銃をがちゃがちゃと調整して歩く。
「まぁな。蟲は増える一方でも、俺たち人間はそう簡単にゃ増えないしなぁ」
「……噂じゃ、上はクローンや合成獣みたいな禁忌に関わる研究を急いでるみたいだしね」
「はは……。笑えねぇよな。でも、いよいよそうせざるを得ないとこまで来てんだよなぁ」
「……」
(栄えていたであろう街並みも、ほんの数年の間で寂れ荒れ果ててこのザマだ。上の連中が焦る気持ちもわかる。でも……。やはりその結論は愚か過ぎる)
「俺らも数少ない女の子とそういうこと勧められてるしね」
「君はモテるもんな。白花の子どもなら産んでいいって皆言ってる」
基地内で一番女性からの人気があると言っても過言ではないくらい、白花の顔は整っているし、性格も申し分ない。それなのに、彼は一向に女性とどうこうなる気配がなく。平等に愛嬌を振りまく姿を、王子だなんだと持て囃される始末だ。
「俺にだって選ぶ権利があるだろ。そうじゃなきゃ何が人間だっての」
「人間、か」
「なんだよ」
吐き捨てた言葉にケチをつけられると思ったのか、白花は留理を睨みつける。しかし、留理は手に持った銃をそっと撫で、困ったように微笑んだ。
「いや、僕らはさ、子孫を残すという本能が生命に刻まれてる。はずなのに、さ。なんで、無意味な恋をするのかな、なんて……」
「無意味な恋……?」
「叶わない恋、っていうべきかな……。いや効率的でない恋、かな……」
珍しく煮え切らない様子の留理に、白花が目を丸くする。
「え、何、お前、好きな子いんの?」
「……いないよ。うん。やっぱり無意味ってのがしっくりくる。僕が好きになっても意味がない」
「恋に意味なんているのかよ」
「はは。詩人だね」
「茶化すなよ。俺はお前を心配して……」
「わかってるよ。でもね、どうしたって意味がないんだ」
「何だよ、一人じゃ叶わないってんなら、俺が手助けでもするし」
「ううん。駄目なんだよ。僕はね、子孫を残せる体じゃあないんだ」
「え?」
綺麗な声で告げられた言葉に、白花がどきりとして聞き返す。
「簡単に言うと精子が作れないんだ」
「そ、そう、なのか。それは、なんていうか……」
「白花、狼狽えすぎ」
「わ、悪い」
「はは。別に僕は何とも思ってないよ。そういうの、ほんと僕には要らないものだから」
「……」
「まぁ、そのせいで君に迷惑掛けてんのは、悪いと思ってるけどね」
「俺に迷惑?」
「僕は子孫繁栄の期待に応えられないからさ、きっとその分もお前に話が行ってるだろうなって」
「なんだ。んなこと気にしてんな、馬鹿。大体、子どもが出来なくたっていいだろ。いや、良くはないかもだけど、だからってお前の気持ちを隠すことは……」
「はは。白花は優しすぎるよ」
留理は後ろめたそうに弱く微笑み、首元のマフラーを握りしめる。留理の瞳の色によく似た蒼いそれは、どうやら留理のお気に入りらしい。
「そりゃ優しくもするさ。お前とはあの“悍ましき日”からずっと一緒なんだし」
悍ましき日。それは勿論、この地球に蟲たちがやってきた忌まわしき日のことを指していた。人々は、あらん限りの憎悪を込めてそう呼ぶようになったのだ。
「あの日から、もう三年は経つんだっけ」
「あぁ。俺たち、まだ十五そこそこだったもんな。いつも通りに家族と朝食を食べて、学校で他愛のないことをくっちゃべって。んで、帰ろうって時に、それは起こって……。商店街のテレビに映る光景はまるで映画の出来事のようで。でもそれは、すぐ側にまで来ていて……」
「白花」
「もぞりもぞりと黒く蠢めく蟲が、幾多の人々を飲み込んで。世界はすぐに黒く染まって。どこに行っても聞こえる鳴り止まない悲鳴、そして蟲たちの這う音。足を取られながらなんとか家に帰ってみたけど、そこにあったのは――」
「白花、顔色、悪い」
気づくと目の前にいる留理が心配そうに覗き込んでいた。その透き通るような碧い瞳がサンゴ礁の綺麗な海を思わせる。
一度だけ家族旅行に行ったときに見たあの海も、きっと今は黒く染まっているのだろう。また行きたかったんだけどな。家族みんな気に入って。珍しく母さんも上機嫌で。また行く約束、してたんだけどな……。
「白花?」
「ごめん、また思い出し過ぎちまった。あの日のこと」
「……」
留理の瞳がまた困惑したように揺れる。気を使わせたかな。
「俺に言わせれば、お前の方がよっぽど優しいぞ?」
茶化し気味に先ほどの言葉をとって返すと、留理は曖昧な笑みを浮かべた後、一呼吸置いてから「心配して損した」と俺の背中をばしりと叩いた。
*
あの日、家に帰って見たものは、まぁ、蟲に食い散らかされた両親の姿だったわけで。
その時、俺は初めて物を吐いた。
気持ちが悪かった。
ただただ、体は震えるばかりで。どうしようもなく怖かった。
それから暫くして、俺は恐怖を飲み込んで学校に向かった。
彼女が心配だった。友人が心配だった。
「アイツらはまだ残って補習を受けてるはずだ。何もなければいいけど……」
いつの間にか足は駆け、風を切っていた。
その頃にはもう、街は不気味なくらい静かになっていて。
襲い来る底知れない不安を払って、学校の門をくぐった。
そこここに散らばる人だったものの残骸。吐きそうになるのを堪えながら、それらを踏み俺は進んだ。
ただ、知人の声を聞きたくて。生きている人間の声が聞きたくて。
教室のドアを開け、俺は膝から崩れ落ちた。
そこにあったのは、今まで見てきたものと何ら変わりのない残骸だった。
血の匂いが鼻腔を突き、再び吐いた。もう吐ける物は胃に残ってなくて、唾だけが口から流れていった。
ややあって、ふと側にリングが落ちているのに気づく。
それは、自分のはめている物と同じ、ペアリングで。
これ、彼女との一周年記念に買った……。
伸ばしかけた手が止まる。銀色が見えないくらいに赤く染まったそれは、血だまりの中に落ちていて。
拾えはしなかった。
ああ。情けない。
自分の指からリングを外し、握りしめる。
ごめん、ごめんごめんごめん。
止めどなく溢れる感情と共に、涙が伝う。
ああ、このまま俺もここで……。
もぞり。
「っ!」
俺の心を読んだみたいにタイミングよく視界の端で黒い何が蠢めく。
目を向けると、丁度それもこっちに気づいたように動きを止め、凝視している。
く、来るな……。
声も出せずに心の中で願ってみたものの、それはキチキチと嬉しそうに触覚やら口やらを震わし、こちらに向かって這い出して……。
「く、くそっ!」
近くにあった教科書を投げつける。しかし、それは少し動きを止めただけで、また這い、当然のようにこちらに向かってくる。
「くそったれ! よくも! くそ! くそ!」
躍起になって片っ端から手に掴んだものを投げてゆくが、それは、気づけばもう目の前に来ていて……。
ぐわりと黒い口が開かれる。
「あ……」
立ち上がろうとしているのに、手は血だまりで滑り、足は竦んで動かない。
ああ、今死んだら、みんなとまた会えるだろうか……。
カタカタと震える歯を噛みしめる。
「う……」
ぐちゃりとした感触が手に張り付く。手が、それに食われてゆく。
ああ、気持ち悪い。こんなのに食われて終わりだなんて、そんなの……。俺は……。
「嫌だ! 俺は、俺はッ! こんなところでくたばりたくないッ……!」
『ギギャ!』
「え?」
半狂乱になりながら、張り付いたそれを剥がそうと腕を振り回していたところ、何かが鋭く掠めてゆく。
視線を落とすと、自分を食わんとしていたそれは床に転がっていた。その背にはコンパスの針が刺さっていた。
「危なかった」
『グジュッ!』
ぼそりと呟き、目の前に現れた少年が、モップの柄でその物体を潰す。動かなくなったそれを凝視していると、少年が俺に手を差し出す。
「な、に……」
「怖がらなくていい。僕もここの生徒だから」
少年は口元のマフラーを手で押さえ、俺を安心させるように微笑んだ。
そう言われてみると、少年の蒼いマフラーには見覚えがある気がした。それに加えて、制服とシューズの学年カラーが自分の物と同じことを確認し少し安堵する。
「なん、だよ、もう俺だけかと思った。生きてる人間がさ。ああ、良かった……」
「僕も、君が無事で良かった」
「ん、もしかして俺のこと知ってる?」
「まぁ。君、モテるから有名だし」
「……」
確かに俺、女子からの評判は悪くなかったもんな。
死んでしまった彼女も、告白してくれた子の中の一人だった。
可愛くて、タイプだったから付き合うことにして。
だんだん好きになっていってたのに。このまま将来結婚したら幸せだろうなって思ってたのに。
「俺は……」
「……とりあえず、一緒に逃げよう」
「逃げるって、どこへ」
「これ」
ポケットから端末を取り出した彼は、座り込んだまま動かない俺に画面を見せる。
そこには、生き残った人への非難指示が出されていて。
そこから、避難場所へと集まった人々と共に更に遠くの仲間を目指し、戦い、進み。
多くの仲間が失われた。
そして今、俺たちは人類最後の組織に保護され、上の指示に従って、戦いに明け暮れる毎日だ。
そういえば、あのペアリング、きっと落としたんだろうな。
握りしめていたはずだった。でも、結局は自分の身を守るのに必死で、自分の未来が大事で。すっかりと記憶から抜けてしまっていた。今頃気づくなんて。いや、それどころか最近は、めっきり彼女のことを思い出しもしなくなったなんて……。
「最低だな、俺」
ぽつりと呟いてから首を振る。目の前を歩く留理の黒髪を目で追い、ため息を吐く。
死んだ奴をどれだけ想っても還りはしない。例え最低でも、今を精一杯足掻いて生きる方がよっぽど俺らしいさ。
*
「二人ともお疲れさま!」
基地に戻ると、いつものように可愛らしい声が出迎える。
「宮真、ただいま」「ただいま」
宮真は僕たちに微笑んだ後、可愛らしい顔で白花を覗き込む。
「あれ、シロくんお疲れ?」
「あ~、ちょっとな。留理、悪いけど俺もう寝るわ」
無理に宮真に微笑み返した後、白花は僕に断ってから部屋に戻る。
「ん。お疲れ」
「……なんかあった?」
直球で尋ねてきた宮真に首を振る。
「何も。ただ働き過ぎただけさ。僕も疲れたから休むよ」
「そう」
「宮真は火鋸待っとくの?」
「そ。戦えないボクにはそれくらいしかできないから、ね」
「……」
僕と同じく黒髪に瑠璃色の瞳を持った彼は、僕よりも中性的で愛らしい見た目をしていた。そのおかげで、最初はよく兄妹に間違えられた。
宮真は生まれつき病弱らしく、自分でも生き残っているのが不思議だと言う。なんでも運が良かったのと、途中から火鋸が守ってくれたお陰でここに辿り着けたそうで……。
「まぁ、ボクが少しでも長く火鋸と話したいってのが大きいんだけどね」
宮真はえへへと笑いながらそう付け加える。その真っ直ぐな気持ちが僕には眩しい。
「本当に火鋸のこと気に入ってるんだな」
「そういう留理も、シロくんのこと……」
「僕は! ッ……、僕は、違うから……」
マフラーで口元を覆いながら、自分を律する。いちいち宮真の揶揄いに付き合っていたらキリがないことぐらいわかっている。はずなのに、毎度過敏に反応しては宮真を面白がらせてしまう。
「今のうち素直になっといた方がいいのに。いつ死ぬかわかんないんだからさ、やりたいことはやんなきゃ、後悔するよ? キミもわかってるだろ?」
僕を見た宮真が、呆れたように何度目かわからない説教をする。
「……とにかく、今日は疲れたからもう寝る。おやすみ」
「あっ。また逃げる~!」
ぷぅと頬を膨らませる宮真に、ひらりと手を振り背を向ける。
僕だって、時間がないことくらいわかってる。
僕と白花のどちらが死んでもおかしくない。
だけど、でも。
「伝えたって意味がないじゃないか……」
ため息と共に漏れた言葉は、我ながら弱々しくてみっともなかった。
あれから数回ため息を吐いた後、部屋に戻り寝る支度を整える。
最後に、メンテナンスした銃器を置き、ベッドで休む彼に目をやる。
僕たちの部屋は二人部屋で、二段ベッドに眠る。
僕は上の方だから、上がる時にどうしても彼の寝顔が見えるわけで。
「……」
言い訳がましく盗み見た彼の顔は、寝ているというのに澄ましたように整っていて。
戦闘のときのクールな表情も、女の子たちにする甘い表情も、どれもどこか冷たい気がした。
いや、冷たいという表現がぴたりとくるのは、むしろ僕の方なのだけど。
こう、なんというか。疲れそうだなって思う時があるのだ。
あの日、あの”悍ましき日”に見た彼の表情は、確かに本当の彼だった。
蟲に怯え、絶望し、それでも尚抗わんとする彼は本当に人間らしくて……。
だから、あの彼を知っているからこそ、今の彼は疲れそうだなと思うのだ。
いや、元から彼はああなのかもしれない。みんなに愛嬌を振りまいている王子様だということは知っていた。
だけど、僕は思うのだ。彼はあの日から特に無理をしてると。勿論そんなの、この基地にいるみんながそうだけど。でも。
僕は彼が弱音を吐いているところを一度も見たことがなかった。
未来への不安、襲いくる敵への恐怖、大切な人を失った悲しみ、怒り、憎しみ。誰もがそれを抱えきれずに零す。しかし、白花はそれをせずとも強く生きてきた。
それなのに。
「今日は僕が余計なこと、思い出させちゃったよね……」
ごめんと呟き、白花に手を伸ばす。
白花は、僕といるときは、少し気を緩めてくれている気がする。
そりゃあ二人でいることが多いから当たり前といえばそうだけど……。
僕は、白花と居る心地よい時間が好きだ。このままずっと互いに深入りしないで冗談を言い合う今の関係でいたいと思う。
だけど。
それと同時に、もっと白花のことを知りたいと思ってしまう自分がいることに、嫌でも気づく。
もっと白花の弱いところを曝け出してくれてもいいのに。もっと僕のことを頼ってくれてもいいのに。
そんな思いが胸を過ってしまう。……つまらない葛藤だ。
頬に伸ばしかけた手を引き、自分のベッドへ上る。
だって。僕じゃ彼を救えないのだから。
*
寂れた廃墟をざくざくと進む。時々かさかさと音がするのだが、それが鼠などの生き物なのか蟲たちなのかはわからない。
ただ響くのは、それと地を踏みしめる自分の足音。他はもう時間が止まってしまったように静まりかえっていて。
一人きりの任務は久々だ。これまで幾度となく任務をこなしてきたけれど、殆どが白花と一緒だったから……。
「薄気味悪いな」
寒気を感じて首元のマフラーを口に寄せる。銃を正してそのまま進んでいると。
「よぉ」
「……どうも」
瓦礫に腰掛けた男に声をかけられる。
「驚かないのかよ」
「いることはわかってましたから」
「チッ、相変わらず優秀なことで」
舌打ちをした男は、僕たちと同じ討伐隊のメンバーで、上司にあたる人物。名前は覚えてないが、そのチャラついた容姿は嫌でも覚えている。
「今日はシロと一緒じゃないんだな」
「えぇ、まぁ」
シロというのは白花のことだ。白花は自分の名前を呼ばれるのが嫌いだ。だから周りも自然と"シロ"と呼ぶようになった。
でも、僕はそれが何だか勿体無くて。嫌がるだろうとわかっていながら、白花と呼び続けた。
『それに。まぁ、留理に呼ばれるのは悪くないかな、なんて……』
先日の彼との会話が頭を過る。例え冗談だったとしても、その言葉がどれだけ嬉しかったことか。彼に認められたようで、特別なようで。くすぐったくて、思わずそっけない態度を取ってしまったわけだけど……。
「相変わらずシロ以外には冷てーな」
吐き捨てるように目の前の上司が呟く。
「……すみません。任務があるのでこれで」
「仕事だけ出来たって生きてけねーぞ」
背を向け去ろうとした僕に野次が飛ぶ。
「……蟲に殺されたら意味ないと思いますが」
「お前が生きてたとしても、どうせ子ども作れねーだろ? 上が言ってたぜ」
「子どもを作るのは義務ですか?」
「あ? こんな状況だぞ。嫌でも作んだよ」
「疑問はないんですか?」
「あ~あ、お前甘いね~。そんな甘っチョロいこと言ってっと……」
背後からマフラーの端を掴もうと、男の手が伸びる。その気配を察し、それを紙一重でひらりと躱すと男の舌打ちが響く。
「そういやマフラー、お気に入りなんだっけ? ママの手編みかなんかか?」
「まぁ、そんなところです」
下卑た笑いを浮かべる男を感情のない瞳で見つめて、マフラーを整える。
「ケッ、本当のとこは何だ? 女からのプレゼントか? それとも、愛しのシロ君か?」
「……」
「はっ、シカトかよ」
「……」
「お前のその態度、ほんっと前から気に入らねぇんだよ。いい加減ッ!」
「!」
「序列ってモンを教えてやんないとなァ!!」
言葉と共に剣が振るわれる。しかし、それも予測の範囲内だ。
その狂気をもひらりとかわすと、男はとうとう手加減することをやめ、こちらに本気で斬り掛かる。
「クソが!」
「もうやめてください」
静かに、これ以上刺激しないように努めた言葉も虚しく、却って攻撃を加速させてしまう。
「澄ましやがって! ガキのクセにムカつくんだよ。上から特別扱いされやがって!」
「特別扱いなんて……」
「オレが生き残ったブスと無理やりヤらされて子ども作らされてんのに、お前らは……!」
「そんなの、拒否すればいいじゃないですか!」
振るわれた剣を躱し、護身用のナイフで逸らし、受け止める。しかし、男の怒りはまだ収まらない。
「ンなことできるかよ! オレだって嫌だけど、でも仕方ないだろ。人類のためなんだよ!」
「僕には、理解できない」
「だからそれが甘いって言ってんだよ!」
がむしゃらな斬り込みが続き、それが当たることもない内に、威力がそろそろと弱まってゆく。
……弱い。上司と言っても、隊に所属したのが僕らよりも早かったというだけ。戦闘力に優れている僕や白花と与えられる役が違うのは当然のことだ。
「クソ、当たんねぇ!」
「あの、本当にやめてください。こんなことをしている時間は……」
「シロも、お前のことウザいって言ってたぜ?」
「え……?」
突然白花のことを言われて、頭を殴られたように時が止まる。
「ほら、甘いっ!」
「!」
「嘘だっての!」
「っ!」
男の剣が肩を切り裂く。今までの攻撃は避けきれていたのに。こんなことで隙を作ってしまうなんて……。
傷を負った肩を押さえる。傷自体はギリギリで回避し損ねた程度の浅い傷だが……。
「律儀に動揺しちゃって。お前、シロのこと大好きだもんな。気持ち悪いくらいに。ていうか、やっぱソッチの人だから勃たないとか?」
「……」
「アハ! やっぱそうなのかよ! 留理ちゃんはホモか、怖い怖い! あ、じゃあこんな人気のない場所じゃ、オレも狙われちゃうかな、コエ~!」
「……」
「ってなると、じゃあシロもホモか? うわ~、引くわ」
「……」
「お前ら気持ち悪いと思ってたんだよ! 可愛い子に寄られても平然としてるシロなんかは、もっと気持ち悪い! なあ、これ、上に言ったらどうなるかな? こんなときに男同士でどうこうやってたらさ、流石に引き離されるっしょ。上もお前らを正気に戻すために女を宛がってくれるかもよ? そうなりゃ、オレの負担が減って最高だよなァ?」
「……」
ぺらぺらと喋る男から目を逸らし、地面を見つめる。
「さーて、楽しい土産話もできたし、帰るか、な……、って、ヒッ?!」
「?」
男の悲鳴に顔を上げる。
「な、なんで、いつの間にこんなに蟲が……?!」
見ると、地面から這い出してきた蟲たちがじわりじわりとにじり寄ってきていた。
「おい、お前、いつまでもしょげてないで手伝えって……」
自分のことをどう言われたって構わなかった。でも、白花のことを言われたら。奈落に落とされたように思考が真っ暗になって……。
上だってこの男の話を本気にする訳ない。だけど、もし。もしも、この男の言うように、僕のせいで白花が本当に女とどうこうするようになってしまえば……。
そんなのは嫌だ。
今はいい。まだ男は残っているし、未成年で戦闘要員の僕たちにはお付き合いごっこを推奨されるだけだ。白花もそれに乗り気じゃないから、悉くそれを断っている。だけど、もし、この男のように白花が強制的に人間たちのエゴに巻き込まれてしまうのであれば……。
僕はきっと、気が狂ってしまう。
それに、この気持ちが、周りや白花にバレてしまったら……。こんなものが、白花に知れてしまったら、僕は一体どうすればいい? こんな浅ましい感情で白花を汚していいわけがない。絶対に知られるわけにはいかないんだ。だから……。
ああ、ああ! 気が狂う。狂ってしまう……! 僕は――!
「おいっ、さっきのは謝るから、なあ、おいって、クソ、やめろ、食うな、た、助け……!」
「……」
ぼんやりとする視界の中、マフラーの切れ端を拾い上げ、頬に寄せる。
「うあああああああ」
大切なそれは、先ほどの男の不意打ちですぱりと切れてしまっていた。僕の肩なぞどうでもいい。それよりも、このマフラーを切られたことが、どうしようもなく腹立たしくて。
「痛ぇ、痛ぇよぉ、助けてくれ、助けてくれぇ……」
「……」
「あああ、頼む、助けてくれ、謝るから、おい、助け――」
「あ」
男の悲痛な呻きに、ようやく現実に引き戻され、ハッとして手を伸ばす。が。
ぐしゃり。蟲に噛まれて飛び散った男の血が頬にかかる。
「あ……、僕は……」
*
割り当てられた地区を調査した帰り。辺りは暮れて、暗い空に月明かりだけが煌々と輝く。森の中、月光だけを頼りに歩くのも風情なもんだとは思うけど……。
「やっぱ、一人は嫌なもんだな……」
いつもならば留理がいて、背中を預け合える。なにより、無駄口を心置きなく叩ける。
だから、こんなにも静かな空間に独りきりだなんて、気がおかしくなってしまいそうだ。
ああ、早く帰ってアイツと話したいな……。
無意識に留理の姿を思い浮かべる。あの一つに束ねられた長髪が揺れるのを、後ろから見つめるのが好きだった。
アイツも今日は単独任務だったはず。留理がやられるわけないとわかっていても不安が募る。だって、この世界はもう平和だったあの頃とは違う。何が起こるかわからないから。だから、早く帰ってアイツの無事を確認したい。
「少し、依存し過ぎてるかもな……」
一緒に行動することが多いからといって、こんなにベタベタ甘えられちゃ、アイツも苦い顔するかもな……。
なんて、己の呟きに嘲笑しかけたそのとき――。
ぱしゃん。
「ん?」
近いところから聞こえた音に剣を握りなおす。
「湖、か……?」
音を頼りに少し歩くと森が開け、ひっそりとした湖が現れる。月明かりを浴び、きらきらと光る水面は、まるでおとぎ話の一場面のように美しい。
ばしゃり。
足を止め、再び水音のした方を見る。そこにいたのは。
「留理……」
呟いてから息を飲む。闇を照らしたように艶やかな黒髪、水と共に透き通るような白い肌、そして、水面のように揺らめく伏し目がちな瑠璃色の瞳。水の中を優雅に揺蕩うその姿は、森の精なのだと言われたらその存在を認めてしまうほどに美しく。浮世離れした何かを秘めていて……。
一体、留理は何をしてるのだろう。下はズボンを履いているみたいだけど……。上には何も羽織っていない。ふと、留理がマフラーを手に、思いつめた顔をしていることに気づく。
「留理……?」
少し不安になって彼の名をもう一度呼ぶ。すると。
「え、はっ、わ……!」
こちらに気づいた留理は、途端に顔を赤くして……。それからバランスを崩し、バシャバシャと溺れかけた。
「留理!」
「留理、ハァ、ほんと、びっくりさせやがって……」
「それは、僕の台詞だろ、全く……」
あの後、慌てて湖に飛び込もうとしたが、結局留理は持ち直し、俺を制して自力で水から上がってきた。
「ごめんて。でもお前、何してんだよ、こんなとこで……」
「あ~。それは。ちょっと、シャツに蟲の血がついたから、落とそうと思って……」
そう言って後ろを向いた留理がシャツを絞り、そのまま羽織る。そしてその首にマフラーを巻く。
「蟲って、大丈夫か?!」
「いや、ごめん。大丈夫なんだ。心配させるつもりはなくて……」
「でも、これ……」
制服にべったりとついた赤色を見て、留理の右肩を掴んだ手に力を込める。左の肩は留理が片手で押さえているため、触れないが、恐らく傷を負ったのを隠しているのだろう。
「あ~、うん。“僕は”大した怪我してないから……」
肩に置かれた俺の手をやんわりと外し、留理が静かに作り笑いを浮かべる。確かに彼の言う通り、深く傷を負った訳ではなさそうだ。でも。
「あ、ちょっと、白花。そんなにあちこち触らないで……」
「お前、これ」
他に傷跡がないか念入りに調べていると、水を吸い込み、ずっしりと重くなったマフラーが千切れていることに気づき、手を止める。途中で千切れたのを雑に結んでつなぎ合わせてあるのだ。
「あ~、それ、は。ちょっと、ミスったんだよね……」
はは、と乾いた笑みを浮かべる留理を見て、拳を握りしめる。それが、泣きそうなのをぐっと堪えているのだと知っているから。だから。
「俺が直してやるから」
「え?」
ぽん、と留理の頭に手を乗せてやると同時に、自然と言葉が口を衝いた。
「あ、でも触られんの嫌なんだっけ?」
留理は、人にマフラーを触られることを嫌う。きっと、それほどまでにこのマフラーが大切なのだろう。詳しく話して貰えたことはないが、何でも昔、恩人から貰ったらしい。……俺は、留理がマフラーを大切そうに握り絞めるのを見る度に、どうしてだか苛ついた。……きっと、指輪を簡単に捨ててしまった俺と違って、いつまでも思い出を大切にできる留理が羨ましいのだろう。
「いや、白花なら大丈夫。お願い、したい……」
伏し目がちに紡がれた信頼に優越感を覚える。さっきまでのモヤが晴れる。きっとその恩人とやらも死んでいるのだろう。だったら、今、留理が頼れる存在は、俺しかいない。
「留理、左肩、ちゃんと見せて?」
「……なんだ、バレてたか」
留理の手をずらすと、その白い肌には浅い傷がついていた。それに、横に垂らした髪も、左側だけスパリと途中で切れている。
「へ、変異種で……。芋虫型じゃなくて、カマキリ型で……。油断しちゃったんだ……」
髪を弄んだ俺に、言い訳するように留理が言い募る。確かに、最近の蟲は進化している。留理でさえ傷を負ってしまうなんて……。
「留理、俺、お前と一緒に行けばよかった」
「……僕も、そう思ったよ」
色の悪くなった頬を撫でる。冷たい。俺が一緒に行けば、留理にこんな顔させなくてよかっただろうに。マフラーだって、守ってやるのに……。
「あ、でも俺、裁縫とかできな……」
「は、れ……?」
「留理!」
ふらり、と留理がいきなり倒れ込む。それを地面につくぎりぎりで掴み、抱き寄せる。
「ごめん、ちょっと、気が緩んだら疲れが……」
「大丈夫か?」
「うん」
「ほら、背負ってやるから」
「悪いね……」
本当に。俺が一緒にいたならばきっとコイツを守れたのに。だから単独任務なんて嫌だったんだ。
ぴぴっ。タブレットに電波が届く範囲に来たところで、通信が入る。
どうやら上司が一人、蟲に襲われて亡くなったらしい。その報告を見て、思わずにはいられなかった。……留理でなくて良かった、と。
*
基地に着いた頃には、すっかり夜中になっていた。
もう大丈夫だから、と白花の背中から降ろしてもらったところで足音が聞こえてくる。パタパタと慌ただしく音を立てて近づいてきたそれは、勢いよく白花に飛びついて……。
「シロくん!」
「わ、クロエ」
白花が抱きとめると、クロエと呼ばれた少女は顔を赤く染め、はにかむ。
「あのね、シロくんを待ってる間、私ね……!」
「ごめん。クロエ、今はちょっと」
言葉を続けようとする彼女に、白花が申し訳なさそうに謝罪する。労わるように僕の肩に置かれたままの白花の手。鋭く突き刺さる彼女の視線。
「白花、僕、先に部屋戻っとくから」
「あ~、ごめん。すぐ行くから」
別に急がなくてもと思ったが、口に出せばきっとまた彼女に睨まれる羽目になりそうだったので飲み込み、背を向ける。
「あ、留理、帰ってたんだ! 遅いから心配してたんだよ?」
部屋に戻る途中、ばったり会った宮真は相変わらず可愛い声で、さえずるように僕の心配をしてくれた。
「ごめん、ちょっと色々あって」
「うわ、エライびしょびしょやん。雨なんて降ってなかったやろ?」
珍しく僕らより早く帰っていたらしい火鋸が、宮真の隣で特徴のある言葉を紡ぎ、こちらを覗き込む。
「あ~、湖に浸かっちゃって」
「ヒェ~。見てるこっちが寒ぅなるわ~!」
寒い寒い、と腕を摩る火鋸の……名前の通り温かそうな色をした髪が、炎のように揺れる。
「火鋸ってば、ほんとにちゃんと見えてるんだ?」
「見えてないと戦えへんやろ?」
大げさに溜息を吐き、肩を竦めた火鋸。その腕を引き、自分の腕へと絡める宮真。この二人はいつ見ても仲が良い。
「ん~、でもさすがに伸ばしすぎだよぅ」
火鋸の目は長い前髪に覆われているため、その瞳を僕はまだ一度も見たことがない。それがどうにも不思議でならないのは、僕だけではないらしい。
ここぞとばかりに前髪を押し上げようとする宮真。見られまいと抵抗する火鋸。
「だ~から、やめろって言ってるやろ毎度!」
「だって! いっつも顔見せてくんないし! 気になるよ~!」
「んなことより、今は留理の心配やろ!」
言い争っていても、二人は本当に仲睦まじく、傍から見れば青春を謳歌する恋人同士のようで……。
宮真は本当に火鋸のことが好きなのだろう。その真っ直ぐな好意がやはり僕にはひたすら眩しかった。
「あ~、僕ならちょっと休めば平気だから」
少し休んだくらいで気分が晴れるとは思えないけれど、二人の邪魔をするわけにはいかない。
「せやな。まあ、早う休んだ方がええやんな」
「あ、ごめん。そうだよね、早く着替えないとだよね」
「うん、ごめんね。二人とも、おやすみ」
二人に背を向け、再び部屋へと歩みを進める。その間にも、二人の会話が耳に入る。
「にしても確かにな、今日は何や蟲の動きが活発っぽかったもんなぁ」
「え、そうなの?」
「おー。そんな日に単独はキツイやろ」
「あ、今日はシロくんと留理、別行動だったんだ?」
「らしいな。珍しく」
「そういえばシロくんはもう帰ってきたのかな?」
「まだ見てへんけどな……ってあ。なんや、帰ってきとるやん」
「う、うん。ほんとだ」
宮真の言葉に戸惑いが生じる。ああ、きっと……。
「あの二人、ほんと白黒でお似合いやな」
「わ~! 火鋸、それ言っちゃ……」
僕のことを気にして宮真が狼狽える様子が目に浮かぶ。
白花とクロエ。きっと、彼らの姿が見えたのだろう。
マフラーを口元に寄せようとして眉を顰める。そういえば、マフラーは白花に預けたんだった。
行き場をなくした右手を握りしめる。そして、僕は少しだけ歩調を速めた。
わかってる。白花とクロエ。あの二人がお似合いだって。ブロンドの腰まである長い髪、そしてくりくりとした黒い瞳。お人形みたいに可愛らしい同世代の彼女が白花の隣に立つだけで、おとぎ話の王子様とお姫様のようにしっくりくる。こんな二人が生き残ったのは神様のご加護があるからだと、誰もが囁き、羨み尊敬した。だから、僕なんかが僻んでいいものではない。
「くそ……」
枕を殴る。何度目かわからないその行為にため息をつく。
自分でも呆れるくらい寝付けなかった。シャワーを浴びて温まったはずの身体もすっかり冷めてしまった。
時計はカチコチと音をたて、時を刻む。どれだけ規則正しい音を聞いても同居人が帰ってくる気配はなく、僕が深く眠りにつく気配もない。
酷く疲れているはずなのに。眠りへの誘いに乗ろうとするのに。うとうととした瞬間、映し出される悪夢がそれを邪魔するのだ。
『あの二人、ほんと白黒でお似合いやな』
どこからともなく聞こえてくる火鋸の声に、クロエが微笑み、白花の手を取る。
二人は指を絡め合い、笑いあう。
天国のように明るい花園で、花びらが舞い、二人の仲睦まじい笑い声が響く。
純白のドレスにタキシード。ああ、幸せそうだな。
僕がそう思った瞬間、二人は白く塗り潰されて、見えなくなる。眩しい。とてつもなく眩しい。
僕は、二人から遠く離れた暗闇で、一人寂しく蹲る。大丈夫。どうせ泣いたって、暗い闇じゃ見えもしない。ああ、惨めだな。僕には白花を想う資格がないのに。そんな感情を持っている暇はないのに。ああ、信じてよ、白花……。僕はただ、本当に……。
「う、あ……ッ」
悪夢から目を覚まし、少し濡れた目の端を拭う。
またさっきの夢だ。同じ夢ばかり見るなんて、本当に僕は馬鹿だ。馬鹿でいて……。
「情けないなぁ」
そう独りごちて身を起こす。と、そのとき。
「何が情けないんだ?」
「!」
咄嗟のことに心臓が飛び跳ねる。生きた心地がしなかった。すぐ傍に白花がいるなんて、予想してなくて……。
「あ……」
喉が渇いたように声が出なくて。眩しさから逃れるようにして、すぐさま彼から視線を外す。
「留理、大丈夫か?」
「あ……、うん。ごめん……。ちょっと、まだ寝ぼけてて……」
「起こしちゃったよな。ごめん」
「いや……。変な夢見て、起きただけだし……」
「変な夢?」
「や、くだらないやつだから……。それより、どうしたの? こんな夜中に」
「ああ、これ」
額の汗を拭いながら白花に問うと、彼は手に持っていた物をこちらに見せる。
ああ、なるほど。
「マフラー……」
「そ。ほら、すっかり元通り……とまではいかないけど」
渡されたそれは破れたところがわからないほどきちんと編み直されていた。
「これ、白花が?」
「うん、クロエに教えてもらって直したんだ」
「……そう」
「あ、やっぱ嬉しくなかった?」
「いや、そんなことはないよ。ありがとう、白花!」
くだらない感情を飲み込んで、マフラーを頬にあてる。僕にはこれがあればいい。これさえあれば、僕は満足だ。
「……クロエにはそれ、触らせてないから安心しろ。まあ、俺の手は加わっちゃったわけだけどさ」
「……そうなんだ。ごめんね、ありがとう。大事にするよ。もう誰にも汚させない」
マフラーを抱いて目を瞑る。良かった。これで本当に僕は大丈夫だ。
「……なあ、留理。それ、さ。そんなに大事なの?」
「え? うん。僕の、一番の宝物だよ。白花もよく知ってるだろう?」
僕の手からマフラーを取り上げ、優しく首に巻いてくれた白花に首を傾げる。どうして、彼はそんなことを今更聞くのだろう。
「大事だったらさ、俺なんかに触らせちゃ駄目じゃん」
「……? どうして?」
「どうしてって、そりゃ……。いや、何でもない。留理がいいなら、それで……」
複雑な表情を浮かべた白花に眉を顰める。僕は何か変なことを言ってしまったのだろうか。
「白花……?」
「さ、もう早く寝ろ。これがあったら、もう変な夢も見ないだろ?」
「うん……」
その表情の訳を問おうとした途端、白花が僕に布団を被せる。そして、優しく髪を撫でられ、額に口づけを落とされる。まるで赤子のような扱いだな、と文句を言おうと思ったけれど、存外心地よいそれに微睡を覚えたので大人しく目を瞑る。
よかった。今度はよく眠れそうだ。
*
「お願いだから、これ以上シロくんを惑わさないで頂戴!」
唐突に投げかけられた言葉に振り返ると、少女が憎悪を露わに立っていた。その黒い瞳は僕を睨みつける。
「僕? 悪いけど、きっとそれは君の勘違いだよ」
面倒なことになったな、と内心ため息を吐きながらクロエを見つめる。彼女が白花に執着していることは気づいていた。だから、なるべく彼女の前では白花と距離を取るようにしていたのだが……。この前の一件が彼女の逆鱗に触れてしまったらしい。
「この前のことだけじゃないわ……。シロくんは、いつもアンタのこと見てるのよ?!」
「ああ、なんだ。そんなことか」
「そんなことって! シロくんは、いつもアンタのことしか話さないし……」
「ごめん。言い方が悪かったよ。でもね、それは白花と僕は一緒にいる時間長いから、話題もそうなるだけで。あと僕を見てるってのも多分違う。それ、そういう意味じゃない」
「じゃあ、どういう……」
「僕は、嫉妬されているだけに過ぎないんだよ。白花の本命は恐らく、宮真だ」
クロエが見ているとき、僕は意識的に宮真と話をすることが多かった。勿論、僕が白花と近づいて在らぬ誤解を招かないようにという配慮の上だ。
宮真と話しているとき、白花の視線を何度か感じたことがあった。僕だって、最初は僕に向けられた視線の意味を勘違いしそうになったけれど。……あれは、間違いなく嫉妬を含んでいる瞳だった。
『あら~、留理も気づいてたんだ。好きなんだろうね』
その視線に気づいたとき、それとなく探りを入れた僕に宮真はケロリとして言った。
『僕は火鋸一筋なのにさ』
舌を出し、いたずらっぽくそう言った宮真の言葉に、僕は確信を持った。
その真っ直ぐな恋が羨ましかった。それと同時に、白花の恋が叶わないことにホッとしてしまった自分が浅ましかった。
「じゃあアンタは一体何なのよ」
唐突な質問に面を食らう。見当外れの嫉妬を披露してしまったせいか、彼女はその目に涙を溜めて、なおも食い下がる。
「僕は白花の……」
……あれ。僕は白花の何だろうか。何だか、友達というのもおこがましいような気がして。
「何でもないよ。ただの任務上のパートナーだ。君が気にするようなものじゃない」
そう口にするのが精一杯だった。
「それじゃあアンタは私を応援してくれるの?」
「勿論。応援するさ。白花には幸せになってほしいんだ」
結婚して、幸せな家庭を築く。そんな“人”としての幸せ。この限られた世界の中で、せめて白花にだけはそれを忘れないでいて欲しい。その願いは本物だ。もし、彼女が白花にそれをもたらすのであれば。もし、白花が自分の意思でそれに応じるのであれば、僕はきっとそれを応援できる。
「本当に……?」
「ああ。神に誓おう」
信仰している神なんていないけれど、彼女を安心させるためにはこの言葉が相応しい。
「なんだ……。私ってばシロくんが留理くんのこと、好きなんじゃないかって……。本当にヒヤヒヤしたのよ? 男同士なんて不潔ですもの。でも、そうね、宮真ちゃんだったのね。ああ、シロくんを少しでも疑ってしまった自分が恥ずかしい!」
「え~っと」
宮真も一応男なんだけど、という言葉を飲み込む。どうやら彼女は宮真のことを女の子だと思っているらしい。でもまあ、仕方のないことだ。宮真は小柄で可愛らしい顔に声を持ち合わせている。言われなければ男だなんてわからない。そんな中性的なスタイルを宮真自身が楽しんでいる節すらあるのだから。
「宮真ちゃんはあれでしょ。火鋸くんが好きなんでしょ。わかるわよ、あんなんじゃ」
ま、好きならあれくらいやらないとだわね、と呆れたようにクロエはため息を吐く。そう、あの二人のことは彼女も認めている。だから、宮真に嫉妬がいくことはないはずだ。
「宮真の恋を応援することはもう随分と昔に約束してるんだ。だから、どの道僕は君の恋を応援せざるを得ないよ」
「……安心したわ。ごめんなさい。貴方に当たるような真似をしてしまって。私、どうかしてたわ。あ、でもほら、マフラー。ちゃんと直ってたでしょう?」
口元のマフラーを整えようとした手が止まる。
「ああ、君と白花が直してくれたんだったね。ありがとう」
「ええ。こちらこそ、二人きりの時間をどうも」
「言っただろう? 僕は君たちを応援してるって」
冗談交じりの彼女の言葉に、愛想笑いを浮かべて答える。
そう。僕の気持ちなんて要らないんだ。だって、僕のこの気持ちはきっと汚いものだから。
*
「留理……」
「ごめん、上に呼ばれてるんだ」
「留理、一緒に夕食……」
「ごめん、今日はもう眠いんだ」
「留理、ちょっと話を……」
「ごめん、忙しいから」
「留理、この書類って……」
「ああ、報告書なら僕が書いておくから。君は先に上がっていいよ」
「いや、手伝うけど。暇だし」
「ほんといいって」
「留理」
「だから、君は早く宿舎に……、痛ッ」
「留理」
唐突に腕を取られ、力任せに棚に押し付けられる。その強さにびっくりして白花を見る。
「ちょ、いきなり何するん……」
「留理こそ何?」
白花と目が合い、すぐに逸らす。珍しく怒りを湛えたその瞳を見続けられるほど、僕の肝は据わっていない。
クロエと話をしてから、意識的に白花のことを避けてきた。だけど、どうやらそれも限界らしい。もっと上手く避けられると思っていたんだけど……。少し露骨過ぎたようだ。
「これ、隈が出来てるけど」
詰問するような白花の声音に怖気付きそうになる。普段の白花が温厚な分、どうにも慣れない。
「あ~、ちょっと、最近寝付きが悪くて……」
目の下を指でなぞられ、身じろぐ。白花の白い瞳に自分が映る。それが何ともいたたまれなくて。
「じゃあこれは何?」
「?」
何のことかわからずに何も言えないでいると、白花は僕の手を取り擦る。
「留理、ストレス感じると手の甲を引っ掻く癖あるから」
「え……?」
意識して見ると、確かに僕の手は傷だらけだった。言われてみれば、無意識ではあったが、さっきまで手の甲に爪を食い込ませていたかもしれない。
「気づいてなかった?」
「これは……、ッ」
まじないでもかけるように、ゆっくりとねっとりと僕の手を撫で始めた白花に、心臓が跳ねる。急いで手を引っ込めようとするが……。
「逃げないで」
それを察した白花が強く僕の手を握り、口元に引き寄せ……。
「ッ!」
おとぎ話の王子様がお姫様に向かってするみたいに、手の甲に口づけを落とした。
「ね、留理さ、最近冷たくない?」
「気のせいじゃ……、ちょっと、君、何して……?」
平静を装おうとしたところで、白花の舌が手の甲を舐め始める。
「気のせい?」
「え? うん、そう。えっと、だから、君の気のせいだって……」
白花の行為にどうしていいかわからないまま、適当な返事で濁す。が。
「ね、留理」
「ひっ」
顔のすぐ横、もたれかかっていた棚に白花が勢いよく手をつく。
「何で白花って呼ばなくなったの?」
息遣いがわかるほどに近づいた白花の顔は、全く笑っていなくて……。
「それ、は……、君が、嫌だって言うから……」
「俺は留理ならいいって言ったんだけど?」
「……そんなに僕のこと、特別扱いするもんじゃないよ」
「特別扱い、か。確かに、俺は留理のこと特別扱いし過ぎかもなぁ」
そう言いながら、白花が再び手の甲を舐める。
「そ、それ止めてくれる?」
「どうして?」
「どうしてって……」
恐らく、白花は治療をしているつもりなのだろう。「唾をつけておけば治る」という古い言葉があることを僕は、最近映画の中で知った。実際には逆に菌が入ってしまう恐れがある民間療法なんだけど……。
「とにかく、ほんと大丈夫だから……」
ちろちろと未だに舐め続ける彼から目を逸らす。でも、白花はすぐにそれに気づき、僕の顎を掴み、視線を無理やり合わせる。
「留理。俺、お前になんかした?」
「そんなんじゃ、ないって……」
そんなんじゃない。そう。僕の気持ちは、要らない。この感情は間違っている。僕は、白花の良き仕事上のパートナー。その役になりきるのが僕の役目。だから、僕はクロエとの約束を果たさなくちゃ。応援するって、言ったんだから。
「あ~、僕の心配してる暇あったら、さ、その……。例えばクロエをデートに誘う、とかさ……、時間を有意義に使う方法が他に……」
「留理は全然わかってないね」
しどろもどろな下手くそアピールが終わるより前に、今度は目の下に口づけられる。
「えっ、な、なに……?! そんなことしても、隈は治らないよ……!」
「やっぱりわかってない」
「っ、やめ、やめろって……、白花ッ!」
生暖かい舌が瞼を撫で始めたところで、白花を本気で突き飛ばす。
「痛いなぁ。でもまぁ、やっと呼んでくれた。ね、留理」
「あ……」
白花の目に射抜かれて、口元に手を当てる。意識的に名前を呼ばないようにしていたというのに……。
「留理は一体何を考えてるの? ね、俺に少しくらい、いや、全部、教えてよ」
「それは……」
マフラーを掴もうとした手が強く引き寄せられて、白花の顔が一気に近づく。
「留理」
「は、白花? ちょっと、放して……」
「留理、俺は……」
「おー、白花、留理。こんなとこにおったんか!」
「「!」」
がちゃり、と突然開かれたドアの音と大声に、慌てて白花に頭突きを食らわす。
「って、大丈夫か?」
ノックなしで入ってきた火鋸が、不思議そうに僕たちを見つめる。
「痛ッ~、大丈夫じゃ、ない!」
白花は頭を抱え、唸りながら答える。
「ご、ごめん、白花……」
自分の額を擦りながら、とりあえず白花に謝る。自分がこれだけ痛いんだ。白花はもっと痛かっただろう。
「なに、喧嘩か?」
頭を擦る僕たちに向かって、火鋸が心配そうに声をかける。
「そ、そんなんじゃないけど……」
「火鋸は何か用事があったんじゃないの?」
言い澱む僕に、白花が助け舟を出す。すると火鋸はぽん、と手を打って、「あ、そうそう。上が「大事な話がある」って呼んでるから、はよ行った方がええで」と笑った。
*
生き残った人間だけで作られた組織の拠点最奥。いくつものモニターを背に、最高司令官である男は厳かに二人を迎え、重い口を開いた。
「どうやら、蟲がこの拠点にも入ってきたようだ」
「そんなまさか!」
白花の悲鳴が広い部屋に虚しく響く。白花が狼狽えるのも無理はない。この拠点は蟲が侵入しないようにと数多のセキュリティが敷かれている。それを突破する蟲が出てきたということは……。
「とにかく、今は混乱を招かないように防壁で蟲を遮断してある。だから、君たちには至急駆除に向かってもらう。勿論、皆には気づかれないよう頼む」
白花と顔を見合わせ、頷く。どうやら怖気づいている暇はないらしい。
「いやああああ! 早く、早く助けてえええ!」
「ッ……」
蟲が出たという地下食糧庫に女の悲鳴が響く。
「どうして、人がまだいるんだ……?!」
「俺に聞くなって!」
防壁のロックを解除した瞬間に僕らが見たものは、料理担当だった数人の無残な死体と、不自然に追い回されている女の姿だった。
『キチチチチチ!』
蟲は、明らかに女を甚振って遊んでいた。わざと最後の一人を生かして楽しんでいた。
「ああ! お願い、助けて! 私、死にたくない!」
僕たちの存在に気づいた女が、こちらに向かって死に物狂いで近づいてくる。
「留理、援護を頼む」
「うん。任せて!」
白花が女を飛び越え、蟲に向かって一太刀浴びせる。
『グギィ……?!』
そして、僕は蟲が起き上がるより前に、女の前に躍り出て蟲に銃弾を容赦なく叩きつける。あと少しで倒し切る。そう思ったそのとき。
「ッ、きゃあああ!」
女の悲鳴に振り返ると、その足元からぼこりと床を押し上げて、蟲が顔を覗かせていた。
「た、助け……」
女は真っ青な顔をしながら、よろよろと僕のマフラーに手を伸ばす。
「っ!」
「留理!」
ふいに白花の手が僕の首根っこを掴む。白花に引き寄せられたお陰で、女の手は空を切る。
それと同時に、白花がもう片方の手で剣を振り、衝撃波で蟲にダメージを与える。
「よかった……」
マフラーの裾を手繰り寄せ、撫でる。ああ、触られなくてよかった。また傷つけられるんじゃないかと思ったけど……、じゃなくて!
「蟲は?!」
僕の肩を抱いたままでいる白花の手を振り払って、辺りを見回す。
「今ので倒したよ」
「そう。とりあえず一安心……」
安堵の息を吐こうとしたが、女を見た瞬間、凍りつく。
「あ、あああ、痛いッ……! 助けて……ッ!」
血に塗れた女の足は、蟲に食い千切られていた。その声は、その目は、その伸ばされた血まみれの手は、僕の方に真っ直ぐ向けられていて……。
「ひっ……」
一歩後ずさり、マフラーをぎゅっと掴む。
「僕は、っう……」
己のことを優先させてしまった後悔と、女の惨状に吐き気が込み上げてくる。その隙をついて女が僕の足を掴む。耳を劈く女の悲鳴が僕を責める。でも、恐らくその怪我では、もう彼女は助からない。動けているのが不思議なくらいで……。
「っ、放し……」
「放せ」
短く吐かれた言葉と共に、ざくりと女の体に剣が突き刺さる。
「う、アアアアアアアアアア!」
さっきまでとは比べ物にならないぐらい悲痛な女の悲鳴が部屋を占める。そして、数秒もしないうちに、部屋は静寂に満たされる。
「はっ、か……」
女の体に突き刺した剣を抜き、白花がこちらを向く。その瞳が、得体のしれないものに思えて、後ずさり、蟲の死体を踏み、バランスを崩す。
「あっ……」
倒れる、と思った瞬間、手を掴まれ、引っ張られる。
「留理、大丈夫?」
白花の手が優しく僕の手を包む。握り返した白花の手は、いつも通り温かかった。それに、こちらを気遣う穏やかな声色も、透き通った白い瞳も、全部いつもと変わりなくて。
「僕は、大丈夫だけど……。この人が……」
動かなくなった女に移した視線を遮るようにして、白花が僕を抱きしめる。
「残念だけど。どの道この人は助からなかったよ。俺たちが来た時にはもう蟲の毒にやられてたし。だから、留理は気にしなくていい」
「……でも」
僕が白花の剣を汚してしまったことに違いはない。いたたまれなくなって、白花の腕から抜け出そうとする。が。
「白花?」
ふいに白花が僕の髪に口づける。その突飛な行動に一瞬呆然とするが、頭を撫でられた途端、羞恥が生まれる。そうか、白花は僕をあやしてくれているのか。僕は、責められてもおかしくないことをしたのに。白花は、僕を静かに許してくれたのだ。
「僕、かっこ悪いよな……」
「そんなことない。留理は偉いよ」
甘く囁かれた言葉に、弱い心が本音を零す。
「……僕は、本当は、嫌なんだ」
「うん。あと少し、きっと、あと少しだから。それまでは、一緒に頑張ろう?」
「……うん」
白花の胸にしがみつきながら、僕は静かに目を閉じた。一番大好きなその懐かしい香りが、初心を思い起こさせる。
大丈夫。ここで挫けるわけにはいかないだろう? 僕は、白花を守ると誓ったんだから――。
*
「いや、ありがとう白花、留理。君たちのお陰で大事にならずに済んだ」
最高司令官である男は、部下に命令を下しながら、合間に礼を述べた。
「わかっているとは思うが、この件は内密に。この件の被害者は皆、外で殺されたこととして扱うように」
「あの。蟲はどこから現れたんですか?」
白花が手を上げながら真面目に質問をする。その顔は凛々しく整っていて、未だに青白い顔をしている僕とは大違いだ。
「どうやら食糧庫の物陰に潜んでいたらしい」
それに気づいた料理番が通信を取ったが、無情にも遮断されて蟲の餌食になったのだろう。まあ、見捨ての判断が間違っていたとは言い難い。この男も全て覚悟の上で今こうして強く振る舞っているのだろう。……僕も見習いたいものだ。
「もう一つ。どうして蟲が基地内にいたんですか? セキュリティの故障ですか?」
「それは、調査中だ」
「……そうですか」
男のわずかな表情の変化を見て、確信を得る。どうやらセキュリティが故障していたわけじゃないらしい。
「留理はどう思う?」
「どうって?」
宿舎に向かいながら、白花の質問を聞き返す。
「蟲は知能を持っていないとされていた」
「うん」
「でも、どうやらセキュリティを突破することが出来たらしい」
「そうみたいだね」
「それに、討伐遠征でこの拠点が手薄になったタイミングだった」
「僕らより強い人間が残っていなかったから、僕らが駆り出された訳だもんね」
「それに、あの蟲。最後の女性を甚振って遊んでいたように見えた」
「……つまり、知能を持った蟲が現れたかもしれないってこと?」
「いや、もしくは……」
「よう、お二人! お疲れさんッ!」
「うわっ、火鋸」「お、驚かさないでくれる……?」
宿舎の玄関に辿り着いた途端、物陰からいきなり飛び出し、二人に抱きついてきた火鋸に心臓を押さえる。
「ちょっと、火鋸! 抱きつくんならボクだけにしてよ!!」
「何だよ、嫉妬か~? 可愛い奴め~」
「ボクが可愛いのは当たり前だもん!」
怒った宮真にニヤニヤしながら、火鋸が抱きつく。ほっぽり出された僕たちは顔を見合わせてから肩を竦め、談話室へと足を運ぶ。
「あれ、他の皆は?」
いつもなら深夜まで賑わっているはずのそこは、誰もいない寂しい場所になっていた。
「それが、みんな部屋に篭っちゃって」
「蟲がとうとう基地内にも出たんやろ?」
「……」
「どうやら本当みたいだね」
僕らの反応を見た宮真が、困ったように眉を顰める。どうやら、早速情報が漏れてしまっているようだ。
「ちょっとした騒ぎになってな」
「誰かが言い出したんだよ。もしかして蟲がセキュリティを解除したんじゃないかって。知能を持った蟲が現れたんじゃないかって」
「それで皆、部屋で待機してるってわけか」
「そういうこと」
皆がそう考えるのも無理はない。僕らは先日、瓦礫の中から見つけた古い映画を持ち帰り鑑賞した。それは、地球外生命体と人類が戦う内容で。図らずも今の状況に似通っていたそれは、宿舎内で連日流された。何故なら、それは人間が勝利を収めるハッピーエンドだったから。ここに寝泊まりしているそれなりの数の人間がゲン担ぎにと観たはずだ。それがよくなかったのだろう。
映画の中の地球外生命体は、見た目こそ違えど蟲のように知能がなく、ただ人間を攻撃するだけだった。が、しかし。物語が進むにつれ、彼らは進化していき、人間以上の知能を手に入れ……という設定があったのだ。映画の中では、人間が強力な兵器を完成させて倒していたが……。
現実では倒してもキリのない蟲の数に、自分たちの身を守りつつ、少しずつその生態を研究するので精いっぱいだった。
「まあ、実際、セキュリティは何者かによって解除されていたらしいんや。オレが上に問い詰めた話じゃ、セキュリティ担当者の人為的ミスやて。セキュリティが解除されたタイミングで不幸にも蟲が入ってきたんやて言い張ってたけど……」
「確かに人間だからミスはするだろうけどね……。ただ、そのセキュリティが解除されてた時間が、数秒程度だったらしいんだよ」
「ま、これは噂にしか過ぎんから何とも言えんけど。まあ皆、不審に思ったっちゅーわけや」
「なるほど。その数秒に乗じて蟲が侵入するのはいささか出来過ぎている、と」
二人の話に神妙に頷いた白花が唸りながら腕を組む。
普段ならば、生体登録されていない生物が自動ドアを通った瞬間、レーザーに焼かれて死ぬ。今迄に数匹の迷い込んできた蟲がそれで犠牲になった。
「見張りはいたんだろう?」
「セキュリティが解除されていた日、妙に眠かったらしいねん。耐え切れんで、数分の間だけ転寝したみたいや。起きてから慌てて辺りを伺ったけど、特に荒らされた形跡もなかったもんやから、黙ってたらしいで」
「その人、可哀そうに自分を責めて寝込んじゃってるんだ」
「いつもなら居眠りするような奴やないで。そこがみょ~に引っかかんねん」
「だからボクたち、睡眠薬でも入れられたんじゃないかって。蟲はこっち側にもいるんじゃないかって……」
「スパイがいる、ってことか」
「まさか。蟲と人間じゃあまりに違いすぎるよ」
白花の言葉に反論する。白花までそんな妄言に同調してしまうのは見過ごせない。
「まぁ、蟲の中にも知能を持ってて、更に人間に化けられるのがいてもおかしくないのかもしれん。それか、いつの間にか寄生して人間を操ってるかもわからんからな」
「そんな無茶苦茶なことを皆信じてるの?」
両手を前に出して幽霊のジャスチャーをしてみせた火鋸に眉を顰める。
「疑ってるんや。今ここに残ってるのは、ほとんどが弱い奴らや。もうずっと外に出てないせいで、精神も参ってる」
「皆、お互いを蟲じゃないだろうかって探り出して、それで……」
「この通り。み~んな部屋に籠っちまったんや」
確かに、大半の精鋭が討伐で不在の今、笑っていられる人間はいないだろう。
「お前らはいいのか?」
白花に問われた二人が顔を見合わせる。
「火鋸が蟲だなんてありえない」
「そうだな。オレも、お前を信じてる」
「はは。相変わらず仲がいいな~」
白花の言葉に胸が痛む。彼はどんな気持ちでいるのだろうか。その笑顔の裏にどんな痛みがあるのだろうか。僕はどうすれば彼を救えるのだろうか。
「んで、どうするんや? お前らも部屋に籠るか?」
「籠ったって意味ないだろ」
「うん。どうあれ、僕たちは戦わなきゃいけないからね。怯えてる暇なんかないさ」
「お前ららしい答えやな~」
「ボクも、戦えたらなぁ……」
「お前はここで皆を励ますんが仕事やで」
宮真の頭に火鋸の手が乗せられる。その仲睦まじい二人に、僕はどうしても複雑な感情を抱かざるを得なかった。
*
それから数日。俺たちは苦戦を強いられていた。
「駄目です! 北第一防壁、破られました!」「南第一防壁も同じくです!」
「二手に分かれて向かい撃て! 絶対に奴らを基地に近づけるな!」「ハイッ!」
今までの蟲は、手あたり次第に生き物を食べ、彷徨う存在だった。が、ここ数日で蟲たちは統率を得たように皆、基地を目指しはじめたのだ。
「シロは北ゲート。留理は南ゲートを守れとの命令や!」
「白花とは別行動なのか……」
留理が不安そうにマフラーを口元に寄せる。
「やっぱり、さ……。俺も留理と一緒になるよう、上に掛け合ってみようか……?」
「いや。ごめん。弱気になった。けど、僕なら平気」
「留理……」
ぱちりと自分の頬を叩いて見せた留理に寂しさを覚える。
「言っただろう? 戦わなきゃいけないんだよ、僕たちは。覚悟なら、とうに出来てるさ」
瑠璃色の瞳が燃えるように揺らめく。これが最後の戦いなのだと嫌でもわかってしまう。
「……無理はするなよ?」
「そっちこそ」
掲げた拳をぶつけ合い、見つめ合う。
「シロくん! お願い、行かないで! 私、どうしていいか……」
「うわ、クロエ……!」
突然抱きついてきたクロエに困っていると、留理が静かに背を向けて歩き出す。
「あ、留理、待っ……」
「シロくん! 聞いてほしいことがあるの。私、私ね。シロくんのことが――」
「ごめん、クロエ。俺、わかったかもしれない」
「わかった……?」
「うん。俺が守りたい奴が誰かってこと」
「……宮真ちゃんのこと?」
「なんで宮真?」
「だって、留理くんがそう言ったのよ」
「留理が?」
「宮真ちゃんと話してると、いつも嫉妬で睨まれるって」
「ぷ。あはは! 何それ。俺、そんなことしてたんだ?」
突然笑い出した俺に、クロエが目を丸くする。
「え、うん。なんだ、無自覚だったんだ……。私も、留理くんに熱視線を送ってたのかと思って。馬鹿みたいだけど、留理くんに嫉妬しちゃってね……」
「はは。それ、勘違いじゃないよ」
「え?」
「嫌だったんだよ。宮真と楽しそうに話す留理を見るのが。うん、確かに俺は、宮真に嫉妬してた。そうだよ、やっぱり留理は僕と一緒にいなきゃ」
「それって、もしかして……。やっぱり、シロくんは、留理くんのことが……?」
「じゃあね、クロエ。気持ちに応えられなくてごめんね」
「シロくん!」
可愛らしい少女に心の中で再び別れを告げる。そして、前を見て走り出す。留理の向かった南ゲートを目指して。
*
「これは……」
南ゲートに辿り着いた僕は息を飲み、マフラーを握りしめる。
「ルリ。君には死んで貰わねばならないんだよ」
辿り着くなり僕をずらりと囲んだ人間たちが、一斉にその銃口を僕に向ける。
ゲート付近には、たくさんの蟲たちの死骸が転がっていた。
「さるお方のお陰で、対蟲兵器がようやく完成してねぇ。この通り、どんな蟲でもイチコロだ」
なるほど。映画が現実になったというわけか。
「君のもう一人のお仲間も、今頃は駆逐されていることだろう」
「そう、ですか」
それならば、僕はもういいのだろうか。
だらりと腕の力を抜き、銃を落とす。
「ふん、諦めたか。殊勝な心掛けだな。総員撃てェ!」
目を瞑る。最後に思い浮かべるのは、勿論白花の姿。ああ、どうか、白花が無事でありますように。この先、幸せに暮らせますように――。
「留理、逃げろっ!」
「は……?!」
聞きなれた声に目を開ける。銃弾が放たれるより前に、白花が目の前に躍り出る。
どうして、ここに白花がいるんだ! やめろ! やめてくれ! このままじゃ、白花が死ぬ。僕の代わりに。そんなの、いけない。意味がない。やめろ、やめろ……。
「やめろオオオオオオオ!」
どっ。一陣の風が吹く。それは、瞬く間に全てを宙に巻き上げて……。
「る、り……?」
振り返った白花と目が合い、我に返る。それと同時に、巻き上げた者たちが支えを失い、地面に叩きつけられて……。
ぐしゃり。悲鳴と共に、嫌な音がして人間たちは動かなくなる。
「あ……。ちが、僕は、こんなこと、するつもりじゃ、なくて……」
白花の見開かれた瞳に映る自分の翅を見て、口を噤む。もう駄目だ。こんな言い訳したって、意味がない。
ぐっと手の甲に爪を食い込ませて、目を瞑る。そして、覚悟を決めて白花を睨む。
ばさり。背中の翅を震わせて、人間たちの屍の山に舞い降りる。それは、紛れもなく蟲の翅だ。
「あーあ。きっと火鋸だよね。人間たちに入れ知恵したのは。早く殺しとけば良かったなぁ」
「留理、本当にお前は……」
「見てわかるでしょう? 僕は人間じゃない。そう、君たちが恐れる蟲なんだ」
「騙していたのか」
「そ。宮真と一緒にね。白花は本当に馬鹿だね。わざわざ敵を庇っちゃうなんてさ」
「それは……」
「今頃はきっと基地内も大変なことになってるかもね。対蟲兵器って言ったって、撃たれる前に人間を殺しちゃえばいいんだからさ。宮真だって僕と同じように生きてるかも。本来の宮真は僕と違って気性が荒いからね。早くしないとみんな死んじゃうかもしれないよ?」
「……」
「火鋸も、クロエも、みーんなぐちゃぐちゃになって幼虫たちの美味しいご飯になってるかも」
「それは……」
「なんなら僕も加勢に行こうか? こいつらみたいにさ、一瞬でさ、楽にしてあげられるよ」
僕が地面に向かって指をさすと、白花が顔を青くする。僕が乗った屍の山は、少しずつ幼虫たちに食い荒らされ始めていた。
「うっ……」
白花が口に手を当て、目を逸らす。無理もない。幼虫が人間を貪る姿なんて、僕でさえ見ていて気持ちが悪い。
「みんな良かったねぇ。いっぱい食べて早く大きくなるんだよ。……アレかい? お兄ちゃんが殺してあげるから。待っててごらん」
「留理、何言って……」
食べ盛りの幼虫たちの催促を律してから、白花に向かって微笑んでみせる。
「白花、君は僕たちにとって、餌でしかないんだ、ごめんね!」
「っ……!」
地面に落ちた愛銃を拾い上げ、白花に向かって撃つ。白花はそれを剣で防ぎ、後ろに飛びのく。飛びのいた地面には、間髪入れずに銃弾が注がれる。
「ほらほら、防いでばっかじゃ仲間は助けらんないよ。僕を殺して助けに行かなきゃ」
「俺は!」
白花が振るった剣は、次々に銃弾を弾き返してゆく。いくら人の動きを補助する機能がついているとはいえ、その動きは人並み外れている。全く人間にしておくのが勿体ない。
「留理が!」
素早い動きで目の前に躍り出た白花に標準を合わせる。距離を、取らなければ……。そう思い、翅を広げた瞬間、白花の足が砂を蹴る。
「!」
一瞬だけ視界が砂埃に覆われる。その隙を突いて放たれた白花の蹴りが銃を地面に弾き飛ばす。
「チッ」
すぐさま腰からナイフを抜き、剣戟を受け止める。そして、後ろに飛び退き立て直そうとする。が。
「あっ!」
白花に掴まれ、首から解けかけたマフラーに手を伸ばす。その無意識の行動に、マズイと思った瞬間……。
手を強く引かれ、白花に倒れ込む。かと思うと、すぐさまぐるりと視界が回る。
「痛っ……」
地面に後頭部をぶつけた痛みに、目を閉じる。そして、次に目を開けたときには。
「っ……」
喉に剣を突きつけられていた。
はらり、と真横に落とされたマフラーに手を伸ばす。掴んだ瞬間、心のざわめきが幾分かマシになる。
「やっぱり、俺は留理が悪なんて信じられないな」
僕の喉から剣を退かした白花が肩を竦める。
「……何を今更」
ゆっくりと身を起こし、白花に吐き捨てる。そう、今更だ。僕が悪でないはずがない。
「これ、こんなに大事にしてるのに?」
「別に、そんなことは……。あッ」
口に寄せたマフラーを白花が掴む。そして、冷めた目でマフラーに剣をあてがう。
「じゃあ、今ここで引き裂こうか?」
「っ……」
「ははっ。嘘だよ。俺は留理を殺せないし、留理の嫌がることなんかしたくない」
「お友達だから? 優しいもんだね」
「そんなんじゃあないよ」
「え?」
いつもより低く、闇を含んだ声音が耳朶を打つ。白花の悲しそうに微笑んだ瞳から目を逸らせない。
「留理、俺は優しくない」
「っ!」
白花の手が、突然翅を撫でる。他人に触らせたことのないそこを白花の指が滑る度に、ぞわぞわとした恐怖を覚える。
「綺麗な翅。ね、これ千切ったら、留理はずっと俺といてくれる?」
「……やれるもんなら、やってみなよ」
恐らく今、僕の声は震えているのだろう。だって、こんな薄い翅、白花の剣で裂けば一発だ。だけど、それは決して怖いだけじゃない。……望んでいたことでもある。
「怖がらないでくれよ、留理。俺はそんなこと、やれないよ。ごめんね。やっぱり俺は留理を傷つけられない」
白花は謝った。僕を傷つけられないことを。まさか、気づいているのだろうか。
「僕はお前を騙してたんだ。僕はもう何人もの人間を殺して……ッ」
白花の手が、今度は僕の頬を撫で始める。その手つきが酷く優しいことに気づいて、唇を噛む。
「留理が蟲も人も殺したくないと思ってることはわかってる」
「馬鹿だな。そんなわけ……」
「留理」
「僕は蟲だから、人間を殺すのは当たり前で……」
「じゃあやってみなよ。なんなら俺を食べたっていい」
「……後悔するなよ」
手を広げ、目を瞑る彼にナイフを翳す。胸をひと突きするだけで、僕は蟲としての暮らしに戻れるのだろう。だけど。
「っ……」
「ほらできない」
「僕をそんな目で見るな」
「ほら、ここをひと突きすれば終わるでしょ?」
白花は、僕の震える手を自分の心臓に誘導する。それだけで、呼吸が苦しくなる。
「僕は……」
「留理」
「僕はッ……!」
白花の瞳から目を逸らし、自分の胸に向かってナイフを突き立てる。が。
「止めるなっ! 僕はっ……!」
「人魚姫にでもなったつもり? 泡になって消えるなんて終わり方、俺は許さないよ?」
ナイフが刺さる寸前で僕の手を掴んで止めた白花が、僕に向かって微笑む。その目は勿論笑っていない。気づいているのだ。僕が死にたがっていることを。
「なんだよ、それ。訳わかんないこと言うな」
「ああ、留理は知らないのか人魚姫。まあ、知らなくていいよ。あんな悲しいお話で君の心を傷つけたくないからね」
馬鹿みたいな力で手からナイフを奪われる。蟲といっても、僕は中途半端だ。成虫になってからずっと人間に擬態していたこともあり、本来の姿に戻れやしない。出来て、今みたいに翅を出す程度だ。風を起こす力だって、連続では使えない。つまり、僕は弱い。銃抜きで平均的に見ると、幼虫たちよりも弱いかもしれない。
「君は、僕を何だと思ってるんだ……」
「俺のパートナーだろ?」
「いつまで幻を信じているつもりだ? 君の良き友である留理はもういない。今、お前の目の前にいるのは、人類の敵である蟲で……」
「留理、一人でそんなに背負い込むな」
「は?」
白花が僕を抱き寄せる。その温かさに今までの日々が蘇り、終わらせたくないという愚かな我儘が胸を焼く。
「留理が死にたがってるのだって、わかってるさ。でもさせない」
「っ?」
白花の言葉と、その鋭い瞳にぞくりとして、ボロボロになったマフラーを握りしめる。間違えるな。僕は、これさえあれば平気なんだ。だから……。
「そんなにマフラー大事にしてさ、ほんと、可愛いよ。でも……」
「え……、あっ」
「もうこんなもの、要らないだろ? 俺がここにいるんだからさ」
「は?」
白花に取られたマフラーが剣で引き裂かれるのを呆然と見つめる。
「なんで……。さっきは、嫌がることしないって……」
「うん。ごめんね。でもさ、何だかマフラーにまで嫉妬しちゃって。……ねえ留理。俺があげたマフラー、何でこんなに大事にしててくれたの?」
「え、あ……。いつから、気づいて……」
「やっぱり。あの時の虫は留理だったんだね」
「!」
誘導されたことに気づき、唇を噛む。それを見て、白花は微笑む。
「最初は全然気づかなかったよ。それどころか、あの時、虫に会ったことさえ忘れてた。でも、マフラーに見覚えがあってさ。あんまり留理が大事そうにしてるもんだから……。じわじわと思い出して……。もしかしたら、そうじゃないかって。カマを掛けてみたんだよ」
更にマフラーを引き裂きながら、白花は言葉を続ける。
「もし、留理があのときの虫なら、蟲たちの仲間だったら、どうすればいいかわかんなかった。でも、さ。マフラー大事にしてくれてんの見てたら、悪い奴じゃないだろうなって思ってさ。黙ってたんだよ。てか、それどころか可愛く思えてきちゃって」
「なに、言って……」
白花に手を取られ、手の甲に爪を食い込ませていたことに気づく。
「留理はどうしてまた僕の前に現れたの?」
「それは……」
地面に転がった無残な姿のマフラーに目を落とし、考える。
僕は、どうするのが正解なんだろう。どうすれば、白花は傷つかないだろう。
どんっ、と鈍い地響きがして、基地から煙が上がる。そうだ、もうそんなことを考えている段階ではないのだ。
「始まっちゃったね」
「僕たちも、始めよう。これは、戦争だ。人か蟲。どちらが生きるかの競争なんだ。無駄な考えは要らない」
「そうだね。全く留理が正しいよ」
マフラーだったものを踏みにじってから白花が笑う。
ああ。そうだ。僕が甘かったんだ。僕はあのマフラーを手にする資格すらないのに。それをお守りみたいに縋って。僕のこういう弱さがなければ、気づかれることもなかったのに。
「そう。無駄なことはもう、考えないでいいんだ……」
疲れ切った頭は、考えることを辞める。計画通りにやればいい。大丈夫。僕は今までこの時のためにやってきたんじゃないか……。
白花が静かに身を離し、地面に落とした銃とナイフを拾い上げ、僕に渡す。
「本当に、いいんだね? 留理」
「うん。どうせなら、本気でやろう。僕たちができることは、もう殺し合うことだけなんだからさ」
ナイフを仕舞い、愛銃を優しく撫でる。コイツを使うのももうこれで最後だ。
どっ、と再びどこかから爆発音が聞こえてくる。
それを合図に、白花が剣を振り上げ、こちらに突っ込んでくる。僕は翅をはばたかせて後方に下がり、白花に向かって銃弾を放つ。
避け、弾き、薙ぎはらう。互いに譲らない本気の戦いに汗が滲む。白花は本当に強くなったものだ。
*
十数年前の話。幼虫の中でも特に弱かった僕は、実験体だと言わんばかりに僕らの星から遠い未踏の星……地球に落とされた。
幼く弱い僕は怖かった。とても人間を食らおうとは思えなかった。逆に殺されてしまいそうだった。
町を行き交うたくさんの人間が怖くて。冷たい雪が降り注ぐ中、僕はずっと隠れてた。
そうやって、このままひっそりと死ぬんだと思うと、すごく惨めで情けなくて、寂しかった。
そんなある日。僕は人間の子どもに見つかってしまった。そのときの僕は、お腹が空き過ぎて、一人が寂し過ぎて、寒さでどうしようもなくなって、公園の茂みの草を一生懸命食んでいた。草なんて、食べれやしない癖に。
「わ、なんだこのでっかい芋虫……!」
『ぴぎゃ……』
茂みを掻きわけて近づいてくる少年に、逃げることもできない僕は、その場に丸まって震えた。
「怖がってんの? 俺、怖くないよ?」
『ぎゃ……』
恐る恐る目を開くと、少年がこちらに向かって微笑んでいた。
「俺ね、今かくれんぼ中。お前もかくれんぼしてんの?」
『ぴぃ……』
少年の手がそっと近づいてくる。僕は、怖くて、やっぱり逃げられなくて、ぎゅっと目を瞑る。
「俺ね、虫好きだからお前も好きだよ。お前の目、瑠璃アゲハみたいで綺麗だな」
『ぴぎゃ……?』
赤子をあやすように穏やかな声音と、優しく背中を撫でる手が、あまりに不思議で首を傾げる。それに。
ルリアゲハ……。確か、この星の虫の名前……。綺麗……。この星の誉め言葉……。
久々に自分に向けられた言葉を口の中で転がすと、何だかこそばゆい気持ちがした。
「白花~!」
「げ、母さんだ。俺の名前、呼ぶなって言ってんのに!」
女性の声がして、少年が悪態を吐く。少年の母親。それが、こちらに向かって駆けてくるのを察知して、体が再び震え出す。
「ああ、怖いよな……。母さんに見つからない方がいい。母さんは、虫が嫌いだから。今も、そのことで喧嘩中」
『ぴっ……?』
ふいに、少年は巻いていた蒼いマフラーを外し、僕の体に被せた。
「お前が見つかる訳にはいかないもんな。俺、出ていくよ。喧嘩上等だ」
そう言って笑った少年が、僕の頭をぽんぽんと優しく撫でる。
「お前も、誰かに見つからないうちに、早く帰るんだぞ」
『ぴぎゅ……』
「白花~!」
「あ~。ハイハイ。ここにいるってば!」
少年が、茂みを出て母親の前に姿を現す。
「白花、なんかいたの?」
「ううん。何も。てか、俺が飼ってたカブトムシ、母さんが勝手に逃がしたこと、まだ怒ってるんだけど?」
「だって、あんなのゴキブリと同じじゃない! 全く、これだから男の子は嫌なのよ」
「なんだよ。いつもそればっかだ……」
「なあに? 声が小さくて聞こえないわ。白花、そんなとこだけ女の子らしくしないでちょうだい」
「ハイハイ。だったら存分にヤンチャな男の子でいてやるよ、クソババア!」
「白花!」
母親に向かってあっかんべーをしてみせた白花が、素早く駆けだす。それを見て、母親は怒鳴り声をあげて追いかける。
ようやく静けさを取り戻した公園で、僕はマフラーの温かさに目を瞑る。顔を擦りつけると、少年の匂いがして安心する。
僕はきっと帰れない。帰る場所などどこにもない。
だけど。もう少しだけこの星で生きていきたいと思った。
あの、神様みたいな少年に、もう一度だけ会って、ちゃんとお礼を言いたかった。
優しくて、眩しくて、死しかなかった僕に光をくれた彼に、成虫になった姿を見て欲しかった。だって、成虫になった翅は、ルリアゲハよりもずっと綺麗だから。
それから、僕は頑張った。どうにか人間を食べて、寒い冬を越えて。数年を経て、僕は自力で成虫になった。
そうして早速、僕は少年にこの姿を見てもらおうと人間に擬態して、町中を探し回った。けれど、残念ながら少年は見つけられなかった。
僕の星のお偉いさんは、僕が成虫になったのを知ると、地球に数匹の幼虫たちを送り込んできた。そして、僕はその幼虫たちを育てる役を命じられた。
僕は、命じられるがままに、しばらく地球で幼虫たちを育てた。人間を狩り、彼らに与え。狩り方を教えた。そうすると、幼虫たちはみるみる内に立派に成長していった。
そしてついに、全ての幼虫が地球に送られることになった。地球は僕の星に、格好の狩場だと認識されてしまったのだ。
別に、地球がどうなったって僕は一向にかまわない。が、どうしてもあの少年だけは助けたかった。あの少年が食われるのだけは、何としても阻止したかった。
だから、僕はもう一度彼を探した。そして、見つけた。
彼は、遠い町に引っ越していた。高校の制服に身を包んだ彼は、可愛い女の子と並んで歩いていた。笑い合う二人の指に同じ指輪がはまっていることに気づく。人間の番がそういう風に同じものを身につけることは知っていた。
僕は、気づいたらしゃがみ込んでいた。息が苦しくて、心臓が痛くて。ぽたぽたと地面が濡れてゆく。僕たち蟲が感情で涙を流すなんてあり得ない。それなのに……、どうやら僕は、人間に擬態し過ぎたらしい。お蔭で、蟲の姿に戻れやしない。翅を出すのが精いっぱいだ。
異常種。そんな言葉が頭を過る。
僕たち蟲は、主に上位種と普通種に分けられる。
上位種は、蟲全体を管理する役目を担うお偉いさん。血で決まっているその数匹は、蟲の未来を見据えた策を練り、普通種に命令をする。その数は全体の一パーセントにも満たない。
普通種は、ただの虫と変わらない。本能に従い、食い、育ち、子孫を残す。それだけのために生きている。そこに余計な感情や思考はない。
そして、それらに当てはまらない者も僅かに存在する。
それが異常種だ。
本能に逆らう者、本能に従えない者。それらが皮肉を込めて異常種と呼ばれていた。
僕もそう。
僕の場合は、上手く餌が食べられなくて。力が弱くて。あっという間に異常種のレッテルを貼られて実験体に使われた。
でも、それはあながち間違いではなかったのかもしれない。
僕はこの星での指導者としての権限を利用して、幼虫たちに彼を殺さないよう指令を出した。
僕は気づいていた。自分が異常であることに。だけど、どうしたって彼を守りたいという気持ちが変えられなかった。例え、彼に会えなくとも、彼に忘れられていようとも、自己満足として彼を助けたかった。
だけど、幼虫たちを一斉に放ってからしばらく。命令を無視して彼に近づく幼虫がいた。
幼虫は、初めて餌を大量に食べ、興奮しているようだった。
「嫌だ! 俺は、俺はッ! こんなところでくたばりたくないッ……!」
咄嗟に落ちていたコンパスを投げ、幼虫を彼の腕から退かす。幼虫に食まれた彼の腕は、服が溶け、皮膚が少し爛れていた。
それを見た瞬間、ふつふつと怒りが沸き起こり、気づいたらモップで幼虫を潰していた。
ああ、やってしまった……。仲間を殺してしまうなんて。本当に異常だ。でも、彼が守れたんだ。なんでもいい。
動かなくなったそれを凝視している彼に、手を差し出す。
「な、に……」
「怖がらなくていい。僕もここの生徒だから」
僕は、口元のマフラーを手で押さえ、彼を安心させるように微笑んだ。
彼を真似て全く同じ格好に擬態したのが良かったのだろう。彼は、僕の服装を見て、安堵の息を吐いた。
「なん、だよ、もう俺だけかと思った。生きてる人間がさ。ああ、良かった……」
「僕も、君が無事で良かった」
本当に。間に合ってよかった。
「ん、もしかして俺のこと知ってる?」
……知っているに決まっている。君は僕の恩人なんだから。一生忘れない。
「まぁ。君、モテるから有名だし」
適当にお茶を濁す。彼がモテるというのは間違いではないだろう。なんせ、あの子は人間の中でも特に可愛い子だった。ああいう上玉を選べるのは、やはりそれに相応しい位置にいる人間だ。
「……とりあえず、一緒に逃げよう」
「逃げるって、どこへ」
「これ」
ポケットから端末を取り出した僕は、座り込んだまま動かない彼に画面を見せる。
元々、人間に擬態して、生き残った人間を吟味する役も命じられている。
だったら、彼の安全を確保するまで彼の隣にいても大丈夫だろう。
そうこじつけて自分を納得させ、僕は彼の相棒として振る舞った。
幸せだった。好きな人と話すのがこんなに楽しいだなんて。知らなかった。ずっとこのまま彼の味方として人間を演じていたかった。
だけど。彼があの“悍ましき日”のことを思い出し、顔を青くする度、僕の心は悲鳴を上げた。
いつまでも騙せない! 彼は蟲が嫌いだ! この気持ちをこれ以上強めてはいけない! 終わりはそう遠くない内にやってくる! 嫌われるのは嫌だ! でも、どんどん好きになってゆく……! いや、僕の気持ちなんてどうでもいい! 重要なのは彼を救うこと、その一点のみだ……。無駄なことは要らないのに……。
「最低だな、俺」
青い顔をした彼の呟きに、聞こえないフリをして歩く。
無意識なのだろうか。彼は左の薬指を撫でながら虚ろな目をしていた。
恐らく、彼女のことを後悔しているのだろう。
本当はあの日、僕は魔物に腕を振るう彼の手から指輪が落ちたことに気づいた。けど、教えなかった。
最低なのは僕だ。
既に彼女が蟲に食われていたことに安堵したし、そのまま彼が、彼女のことなど忘れてしまえばいいと思った。愛の証とされる指輪が無ければ、忘れてくれるだろうと思った。だから、言わなかった。
でも、彼は新たに恋をした。よりにもよって、僕と同じ蟲である宮真に。
止めようと思った。そんな意味のない恋をしてほしくなかった。僕みたいに異常であってほしくなかった。彼には、人間として真っ当な恋をしてほしかった。
宮真は、どうやら白花の気持ちに気づいているようだった。そして、僕の気持ちにも。
宮真は、どういう訳か火鋸を偉く気に入っていて、恋愛ごっこにうつつを抜かしていた。
異常種と呼ばれるだけある。
そう自分と同じ括りにしていたが、後に思い直した。
きっと、宮真は火鋸が普通の人間でないことに気づいていたのだろう。だから、傍で監視していたのだろう。
火鋸は、人間にしてはどこか不自然だ。ふとした瞬間、人間離れした妙に強い力の気配を感じることがあるのだ。それも、宮真よりも強い力を。
だったら、と思った。
僕をここに送った上位種たちより、宮真よりも、僕の願いを叶えてくれるかもしれないと思った。
*
「……どうして」
掠れた声で呟いてから、うじゃうじゃと寄ってくる幼虫たちから白花を庇う。
「どうして、お前たちは僕の言うことを聞かない!」
血走った目で同胞を睨みつけ、叫びながら銃で撃つ。
僕ら二人の勝負は真剣だった。互いに譲らない攻防を楽しみさえしていた。でも、やはり僕より白花の方が少し強かった。
それは“悍ましき日”から白花が目を見張るほどの成長を遂げたから。それと。
僕の体はもう限界だったから。
僕が蟲の姿になれないのは、長いこと人間に「擬態」し過ぎたせいだ。
もっと言うと、成虫になって以来、「人間の血を全く吸わずに生きてきた」せいだ。
普通、成虫になった蟲は生き物の血を吸い、生きてゆく。でも、僕はそれをしなかった。その必要がないと思っていたから。
最初、僕はただ白花に翅を見せて、あの時のお礼を告げて、ひっそりと死ぬつもりだった。
弱い僕が成虫になれたことだけで、もう十分だった。だから、上位種への報告もするつもりはなかった。
でも、彼らは僕に気づき、この星の価値に気づいてしまった。
そこからは、白花を守るために人間擬態をより心掛けた。確かに、力は大分弱まったが、それでも……。
「白花は殺させやしない……」
銃を手に、幼虫たちを白花から引き剥がす。
せっかく終わるところだったのに。せっかく、死ねるところだったのに……!
幼虫たちは、僕らの戦いに割って入り、白花を襲い始めた。
勿論、僕は幼虫たちを殺した。けど、あまりにも数が多過ぎる。白花も幼虫たちを躱すのがやっとのようで……。
このままだとマズイ。
汗を拭い、手の甲を爪で掻く。またやってしまったが、無論今は白花も説教どころではない。
「ッ、くそ、離れろ……!」
「白花!」
白花の腕にくっついた幼虫を剥ぎ取り、白花に覆い被さる。尚も襲い掛かってくる幼虫が体当たりしてくる度、歯を食いしばる。
「留理、やめろ! お前が死んだら意味がない!」
「ふ、はは。やっぱり白花は優しいなぁ……。本当は、死ぬまで吸わないつもりだったけど……。そんなこと、言ってられないよね」
「留理?」
「……ごめん。でも、最後にもう少しだけ守らせて」
「……ッ!」
白花の首筋に牙を突き立てる。成虫になって初めて味わうそれは、本当に美味しくて。気づけば、白花が気絶するまで飲んでしまっていた。
「ああ、でも……。これは……。力が……、溢れる!」
抑えきれない破壊衝動を幼虫に向ける。羽ばたかせた翅から無数の針が飛び、幼虫たちを串刺しにする。
『ギシャアア!』
生き残った幼虫が仲間を呼び出す。ボコボコと土から出てきた幼虫たちで、再び辺りが埋め尽くされる。
「好都合だ。せめてこの力が持つ限り、蟲の数を減らすつもりだからね。裏切り者? 何とでも言いなよ。僕は、白花さえ無事ならなんでもいいんだ……!」
幼虫たちからの罵詈雑言を聞き流し、次々とその体を貫いてゆく。
その返り血でいくら汚れようが、もう構わない。あのマフラーのことを気にする必要もないのだから。
「……終わった、か」
静まり返った辺り一面に、積み重なる死骸。それらから目を逸らし、息を吐く。どうやら、増援ももうないらしい。それに、遠くで響く爆音も次第に小さくなっている。
「あっちも、決着がついたころかな」
宮真は、無事だろうか。いや、僕にとって……白花にとっては彼が無事でない方がいい。
「白花……。血、吸ってごめんね……。今まで、付き纏ってごめんね……。でもね、もう大丈夫だから。だから、最後に、少しだけ……」
横たわる彼の手を握りしめ、目を閉じる。温かい。僕は、この温もりに救われた。
「やっぱり、好きだなぁ……。ごめんね……」
白花の手を引き寄せて、額に押し当てる。
ああ、このままずっと時が止まればいいのに。
「なんて。許されるわけ、ないのにね」
白花の手に落ちてしまった涙を袖で拭ってから、自分の目元も拭う。そして、地面に落ちていたマフラーの端っこを拾い上げ、額に押し当ててからそっとポケットに仕舞う。
「ごめん……。もう少しだけ……、これに縋らせて……」
*
幼虫たちが蠢く基地の宿舎。ボクはついに火鋸と対峙する。
「さて、宮真。なんか言い訳したいっちゅうんなら、聞くで?」
火鋸は顔色一つ変えずに、いつもと変わらない軽い口調で聞いた。やはり、ボクの正体に気づいていたらしい。
「この状況で言い訳したとして、キミはボクを許してくれるのかな?」
ばさり、と翅を広げ、火鋸を威嚇する。今のボクは蟲そのもの。だというのに、火鋸は迷わずボクを宮真と呼んだ。
「わかってんなら、降参することをお勧めするわ」
「降参しても、殺すんでしょ?」
「当たり前や。お前のような危険な蟲を生かしておくわけないやろ。仕損じたらオレが上に怒られるわ」
「あんなに恋人ごっこしてたのに、ボクを殺そうって言うの……?」
「ああ。それがオレの使命だからな」
可愛い子ぶった声を出して演技した僕に反応もせず、火鋸は冷めた声でただそう返す。
「……つまらない」
心の底からそんな言葉が這い上がってくる。
「人間の味方なんかして、何になるのさ! 弱い生命体がボクらに食われるのは当たり前だ! それなのに、どうしてキミは……」
「オレの星がお前ら蟲を良く思ってないからだ」
「……はは、やっぱり火鋸は人間じゃないんだ」
「何を今更」
火鋸の冷めた声に唇を噛む。
何を今更。そんなこと、ボクだって自分に言いたい。どうしてボクは今、そんなわかりきったことを呟いたのだろうか。どうして、火鋸が人間だったら良かったのに、なんて……。
「それで。どうするか決めたんか? 降参して苦しまずに死ぬのと、抵抗してたっぷり苦しんで死ぬのと」
「……るさい」
「なんて?」
「うるさい! 火鋸一人で何ができるのさ! まさか、このボクが簡単に殺されるとでも? ハッ、冗談……」
「出来る。オレ一人で充分だ」
「は?」
『ギシャアアアアアア!』
ぼっ、と火鋸の手から放たれた炎が、宿舎の人間を食らっていた幼虫たちを燃やす。その炎は、一瞬でそこにいた幼虫全てを灰に変えた。
「わかっただろ?」
「嘘だ……」
「まだ信じない、か。じゃあ、これでどうだ?」
「え……?」
火鋸が軽々と炎を放る。それは、避ける間もなくボクの左の翅に灯り……。
「あ、アアアアアアアア! 翅、がッ……! や、熱い、は、あ……、ひっ……」
いくら羽ばたいても、地面に擦りつけても炎は消えない。翅が焦げつく臭いに怖くなって、意味もなくくるくると空を飛び回る。
「……あ、落ちる」
「え……、うぐっ!」
火鋸の呟きと共に、体が落下する。左の翅が、燃え尽きたのだ。
「ッ、うう……」
そんな、わけない……。
左の翅を動かそうと力を籠めるが、動くのは右だけ。片方だけ羽ばたかせても、体は空に上がれない。
どうして……。蟲の翅は見た目よりも頑丈で、ボクの翅なら炎にも耐えられるはずなのに……。
「オレらが使う炎は特別強い。もうわかるだろ?」
「ひっ」
地面に這いつくばるボクに火鋸が近づく。そして、左の少し焼け残った翅の淵をわからせるように、そっと指でなぞってゆく。
ああ、こんなに、燃えてしまったのか……。これじゃあ、ボクはもう……。
「どうして、ボクが、こんな……。これでも、ボクは、強い、はず、だったのに……」
幼虫だった頃、ボクはこの地球とよく似た星に落とされ、同胞たちと共にそこにいる生命体を食い荒らした。
ボクはよく食べ、よく眠り……周りの仲間より強い個体に育った。
食べた分だけ、ボクはこの餌たちのことが気になっていった。
彼らは、やはり地球の人間とよく似ていた。彼らが他人を助け、自らを犠牲にするような場面を幾度となく見てきた。どうしてそんなことをするのか不思議でならなかった。
子を産み終わっていない番や子を守る行動は蟲もする。だが、それ以外は身を挺して助ける意味はない。
もっと不思議なのは、歪な番がいることだった。
少数ではあったけれど、同性個体や様々な理由で生殖機能がない個体、まだ育ち切っていない個体、明らかに弱い個体などを番として選んでいる者がいて、どうやらその星ではそれが公に認められているらしかった。
その星の者は、愛という言葉を多く口にした。
ボクは、それが必ずしも生殖を目的としない言葉だということに気づき、どうしてだかもっとよく知りたくなった。
愛とは一体なんなのか。
気づいたら、ボクは餌を食べる片手間に、その星の本や映像を調べ、感情を学んでいた。
そして。
成虫になったボクは、地球での任務に立候補した。
ボクは異端と言われる趣向や行動のため、煙たがられてはいたものの、能力としては最高レベル。上位種たちもボクの任務参加を渋々承諾してくれた。
地球は蟲たちにとって重要な拠点だ。
最近になって食い荒らすだけでは駄目だと気づいた上位種たちは、ある程度まで地球人を減らした後、生き残った強い遺伝子を持つ人間をクローン栽培すると決めていた。
なんでも、この星の人間と増殖技術は相性が良かったらしく、上はこの星を幼虫たちの餌場として永久に使うつもりだ。
蟲の歴史を揺るがすほど重要なミッション。上も少しでも戦力が欲しいところだろう。
勿論、ボクが立候補したのはそれに貢献したいなどという崇高な考えがあってのことではない。
ただ、知りたかったのだ。この星で。愛を。
あの星に似ているこの地球ならば、その答えが見つかると思った。人間に擬態しての任務ならば、尚更理解できるのではないかと思った。
そして。その結果が、これだ。
「諦めろ。アンタには死しか残されてない」
「……さっきから、喋り方、違うじゃないか」
「ああ、あれな。一番親しみやすい喋り方やったやろ? これ、中々好きやったんやけどな。あ~、名残惜しいわぁ」
白々しい声音を聞きながら、恋愛ごっこを思い出す。
わかった気になっていた。ボクにも愛することができるのだと、夢に浸っていた。
本当のことを言うと、ボクは最近まで火鋸が人間じゃないなんて、気づいてもなかった。
恋は盲目。よく言ったものだ。ただただ恋愛ごっこが楽しくて。気づかないふりをしていたのかもしれない。
「ねえ、火鋸……。ボクは、キミが好きなんだ……。キミに殺されたくなんかないよ……」
「アンタのそんな言葉、信じられるわけないだろ。どうせオレのことも、最後には殺すつもりだったんだろ?」
「それは……」
あれ。ボクはどうするつもりだったんだっけ。確かに、最初は恋愛ごっこを楽しんだ後、情緒たっぷりに殺すつもりだった。でも……。
「まあ、どっちでもいい。オレはアンタを殺すだけだ」
ボクの名前も呼ばなくなった火鋸が軽く頭を振るい、髪を掻き上げる。
露わになったその瞳は紅く、彼の使った炎のように妖しく、鋭く、悍ましい。
「はは……。初めて見た……。それ、ずっと、見たかったんだよ……」
ああ、綺麗だ。流石、ボクが惚れただけある。
殺されたくない、なんて言ったけど。彼に殺されるのも悪くない。
「火鋸に、なら、殺されても、いいや……」
「……どうして、笑う? それは、どういう感情だ?」
「……さあ。わかんない!」
ああ、留理。ごめん。キミには散々素直になれと言ったけど。今ならわかるかもしれない。キミがその想いを伝えなかった訳が。
ああ、苦しいな……。どうしてボクは蟲に生まれたんだろう。
ああ、人間ごっこをしていたあの頃に戻りたいな……。
ああ、愛なんてもの、知らない方がよかったのかな……。
*
「ああ……。宮真、死んじゃったんだね……」
背負っていた白花を丁寧に地面に降ろしてから、宮真に近づく。
うつ伏せに倒れた宮真の翅は、片方が見事に焦げていた。
「お前、白花を殺したんか?」
傍で佇んでいた火鋸の問いに、静かに首を振る。
「気を失ってるだけ。だから、火鋸に守ってほしい」
「蟲」
「……」
「アンタは蟲やろ?」
火鋸の冷たい声に頷く。そして、頭を下げる。
「どうか白花を、助けてやってほしい」
「何か、企んどるんか?」
「何も。ただ、火鋸に頼めば、きっと守ってくれると思ってたから……」
「じゃあアンタにはここで死んでもらおか。そしたら白花は助かる」
「……わかった」
手に炎を灯した火鋸を見て、目を閉じる。宮真でさえ死んだんだ。きっと、僕は跡形も残らないだろう。
でも。それでいい。それの方がいい。
「何か仕掛けてあるんか? ……まぁいいか。こっちも、蟲は始末せぇ言われてるんでねッ!」
ポケットの中でマフラーの切れ端を握りしめる。
さよなら、白花。
どっ。
炎の熱が顔に迫る。熱い。けど、これで――。
「やめろッ!」
「え……?」
白花の声がして、体が横に飛ぶ。炎が当たる直前で、目覚めた白花が僕に体当たりをしてきたのだ。
「何考えてんだ! この馬鹿!」
「はっ、か……?」
僕に跨ったままの白花に怒鳴られ、胸倉を掴まれる。
「おい。馬鹿はお前や、シロ。コイツは蟲や。お前たちの敵やぞ?」
「違う。留理は違う」
「あのなあ。どこが違うんや。寝惚けとるんか?」
「留理は、俺を守ってくれた。確かに留理は蟲だけど、俺の大事な人なんだ」
大事な人。そう言われて、思わずマフラーの切れ端を握りしめる。
「お前……。コイツに洗脳でもされたんか?」
「そんなわけ――」
「よくわかったね、火鋸」
白花が何か言い出す前に、先手を打って嘘を吐く。
「おい。ふざけるなよ、留理……!」
「蟲の常套手段だよ。吸血した際に対象の感情を乱すことが出来るんだ。だから、さ。白花、君も宮真に好意を寄せていたんだろう?」
「は? 何言って……」
そういうことにしてあげれば、きっと白花の人間性を疑われることはない。宮真には悪いが、死人に口なしだ。白花の恋を否定することにはなるが、これからの白花にとって蟲に恋をしたという事実はきっと忌まわしい記憶になるだろうから仕方がない。僕の手で消してあげた方がいいだろう。
「君が僕に対して友好的だったのも、なんてことはない。こっそり血を吸って乱していたんだよ。宮真もこっそり君の血を吸っていたんだろう。君は優良個体だからね」
「……なるほどな。確かにアンタらにそういう能力があるんやったら、辻褄が合うわな」
「いい加減にしろよ、留理。そんな嘘吐いて俺を助けたって、お前が死んだら意味ないだろ! 俺が、どれだけお前を想ってるか、知らないくせに……」
知ってるさ。白花が友達思いだってことぐらい。僕なんかを特別扱いしてくれて。本当に楽しかった。
「だから、それが洗脳なんだって。もういいだろ? 火鋸。さっさと終わらせてくれ」
「……まあ、どうせオレは殺るしかないしな」
「おい、火鋸。留理に手ぇ出したら、お前が何であろうと、殺す」
「おっかないなぁ」
「留理。嘘を吐くんだったら、まずこれを捨ててからにしろ。お前が何言っても、悪い奴に思えない」
「……っ」
ポケットからマフラーの切れ端を取り出され、下を向く。反論しようとするのに、口を開けない。
本当は、今すぐ取り返して握りしめたかった。でも、それが駄目なことぐらい、わかってる。わかってるから、仕方なく手の甲を引っ搔いて気持ちを落ち着ける。
ああ、どうして僕はいつまでもこんなに弱いままなのか。
「留理。どうしてお前はそんなに我慢するんだよ。確かに、俺は頼りないかもしれない。でも、俺はお前に死んでほしくない。一緒に生きる方法がきっとある。だから、もう嘘を吐くな。留理が何を考えているのか、教えてくれ」
白花の誠実な瞳が僕を見つめる。それを前にして嘘が付ける程僕は器用じゃない。
「はは。駄目だよ……。僕は許されない……。お願いだから、これ以上僕を弱くしないで……。優しくされたら、また勘違いしてしまう……。僕は蟲なのに……。ああ、どうしたら正解なんだろう……」
がりがりと手の甲を掻く強さが増してゆく。だけど、その痛みはなんの解決にも繋がらない。不甲斐ない。どうして僕はこんなに心が弱いのだろう。
「留理。教えて? 留理が考えてること。俺に全部話してよ」
甘く優しい囁きに眩暈がする。そっと重ねられた手の温かさに泣きそうになる。
もう、自分の気持ちを隠してはおけなかった。
白花をそっと翅で抱き包み、二人だけの空間を作り出す。まるでステンドグラスのように光を通した瑠璃色の翅は、我ながら美しいと思えた。これで外に会話が聞こえないはずだ。
「あの、ね。ごめん。本当は、ね。僕は、白花が好き、なんだ……。僕は、白花が、優しいから……。好きに、なっちゃって……。ごめん、ね。蟲に好かれても、気持ち悪い、よね……」
「留理……」
言ってるうちに、涙がぼたぼたと地面を濡らす。泣くつもりなんかなかったのに。やっぱり駄目だ。色んな思い出がない交ぜになって僕の心を締め付ける。
「でもさ、だから、守りたいんだよ……。白花だけは、僕が守りたい。お願い、守らせて。他の蟲になんて食べさせない。白花には幸せな未来を歩んでほしいんだ。だから、僕を邪魔しないで。どの道死ぬんだ。だったら僕は白花のために死にたい。だから……」
涙を拭い、口を大きく開く。吸血して黙らせよう。話が拗れる前に、火鋸を説得して白花を保護してもらわなくちゃ。そのために僕は、あの悍ましき日から今に至るまで死に損なってきたのだから――。
「ねえ、留理。俺だってそうだよ。俺だって、留理が好きだ」
「え?」
白花の言葉に動きを止める。そして、意味を理解する間もなく静かに落とされた口づけに驚いて、涙が引っ込む。
「留理は俺が宮真を好きだと勘違いしてたみたいだけど……。俺が好きなのは留理だよ。宮真には嫉妬してただけ」
「は……?」
「信じられない? もっとする? ていうか、俺はもっとしたい」
「え、待って、んむ。んんっ。白花、待って! 僕、蟲だよ……?!」
「うん。綺麗な翅だよね。今まで見た中で一番。他のと比べ物にならないぐらい綺麗だ」
「……ルリアゲハより?」
恐る恐る尋ねてみる。今聞くべきことじゃないんだろうけど、聞かずにはいられなかった。
「勿論。ずっと眺めていたいぐらい綺麗だよ」
さらりと返ってきた言葉を聞いて、幼い頃の馬鹿々々しい決意が報われた気持ちになる。
「……あのさ、言いたいことはたくさんあるんだけどさ。とりあえず、改めてお礼を言わせてくれ。白花、幼虫だった僕を助けてくれてありがとう。僕は、あのマフラーと君の優しさのお陰で生きてこられたから」
「うん。留理が生きてて本当に良かった。昔の俺、グッジョブだね」
白花のおどけた表情に微笑みを返す。だけど、どうしたってもう本気では笑えない。
「白花が僕のことを好きだなんて……、まだ信じられないけどさ……。本当、なんだよね?」
「やっぱり足りなかった?」
「わ、待って。これ以上は、心臓が持たないから!」
「留理は相変わらず可愛いなぁ」
「蟲に可愛いはおかしいでしょ。それに……。うん。僕はやっぱり蟲だから。こういうのは間違ってるよ。僕じゃ君を幸せにはできない。だから……」
「だから嘘吐いて俺を守るために死ぬっての? それで俺が喜ぶと思ってる?」
白花が真剣な顔で僕を見つめる。静かな怒りが妙に恐ろしい。
「でも……。君は僕じゃなくても……」
「留理じゃなきゃ嫌だよ。なんで留理を諦めないといけないの? ねえ、留理は知ってるよね? 俺があの悍ましき日に全部失ったこと」
「……でも」
「留理は、俺にまたあんな思いをさせるつもりなの?」
「それは……」
いつもの癖でマフラーを押さえようとする手が空を切る。
「これ、持ってていいけどさ。もっと本体に縋ってよ」
そう言って、白花が僕の手にマフラーの切れ端を渡す。それを握りしめることも躊躇われて、のろのろとポケットに入れる。
「だけど……。でも……」
「やっぱり分かるまでチューする?」
「んう、違、んん、ちょっと!」
「あ~。お二人さん、おめでとうなんやけど、そろそろこっちのことも考えてほしいわな」
横から入ってきた火鋸の台詞にぎょっとする。
色々あって力が抜けたせいで、翅はいつの間にか地面についていた。つまり、僕らは火鋸から見られてる中でキスしてたってわけだ。
「あの、これは、違くて……。白花は、僕のせいでおかしくなってるだけで……」
「火鋸。わかるだろ? 留理は違う。血を吸ったのだって、俺を助ける為だったし……。多分だけどさ、留理は今まで人間の血を吸うこと、ずっと我慢してきたんじゃない?」
「……それは」
「火鋸、いい加減認めろよ。留理は害のある蟲じゃない。お前だって気づいてるんだろ?」
仄暗い圧を潜ませた白花の言葉に、火鋸は両手を挙げて肩を竦める。
「あ~。わかったわかった。確かにな、留理はオレが監視してる時も人を襲ってなかったみたいやし、力も弱い。どうやら、宮真みたいに完全な蟲の姿になれるわけじゃなさそうだしなぁ~。なんて――!」
「あっ」
一瞬のうちに、火鋸が僕のすぐ後ろに移動する。
「許すわけないやろ。宮真かて殺したんや。蟲である限り、オレは留理も許すわけにはいかんのや!」
火鋸の手のひらから炎が生まれる。僕には、それを防ぐ術がない。
マフラーの切れ端を握り込もうとして、思いとどまる。代わりに、掠れた声ですぐ傍にいる愛しい人の名を呼ぶ。
「やっと、頼ってくれた」
目にも留まらぬ速さで火鋸の手を捻り上げた白花が、こちらに向かって満足そうに微笑む。
「なっ。シロ、待て。これはお前の為でもあるんや。邪魔を……」
「邪魔してるのはそっちだろ?」
「あ……? 嘘、やろ……?」
「白花……!」
白花の剣が、火鋸の体を貫いていた。白花は、それを引き抜きもしないで再び僕を抱きしめる。
「待って、駄目だよ……。どうして……。彼は、地球人の救世主だ。なのに、こんなこと……」
「留理、俺は別に正義のために生きてるわけじゃない。わかったんだ。俺にとって留理が一番なんだ。留理以外もうどうでもいい。留理は、そうじゃないの?」
「……そんなの」
「素直に言って。ね、お互いに本当のことを言い合わないと」
「狡いよ……。僕だってずっと、白花のことだけを思ってやってきたのに……」
白花のシャツを思い切り握りしめ、額を擦りつける。ああ、この匂い、やっぱり安心する。マフラーなんかより、ずっといい。
「行こう、留理。遠くに行けば、きっと誰にも見つからないさ。大丈夫。だから、ね?」
「うん」
優しく取られた手に指を絡ませ、頷く。例えこの先に何が待っていようと、もうこの手を離したくないと思った。思ってしまったから、僕はもう戻れない。
「白花。ありがとう」
「それは、なんのお礼?」
「僕を、好きだって言ってくれたことへのお礼」
「……待って、それじゃあ俺もありがとうじゃん」
「ふふ」
おどけた白花に堪らず微笑む。ああ、この何気ないやり取りが好きだ。平和というのはきっとこういうことなのだろう。
「あ~。度々お取り込み中申し訳ないんやけど……。オレ、まだ死んでないで。てか、流石にこれぐらいじゃ死ねんわ」
「っ!」
起き上がり、体から剣を抜いた火鋸が怠そうに首を回す。その隙に、白花が僕を後ろに隠す。
「ああ、そう警戒せんと。試しただけやんか~」
「試す……?」
「ホンマに愛し合ってんのか。あと、留理がホンマに危険じゃないか、よ。オレを殺した後、豹変とかせんかな~、と思ったんやけど……。どう見てもラブラブ甘々やん。留理は良い子過ぎやし……。うん合格や」
「合格……?」
頷きながら、友好的に近づいてくる火鋸に、二人で後ずさる。
「そないに避けられると傷つくわぁ。オレ、大分アンタらに入れ込んでるつもりなんやけど?」
「……アンタは、留理を殺す気じゃないのか?」
「そのつもりやったけど、よ? 結構長いこと一緒におったら情も移るって。オレかて友達を殺したくないわ」
「……信用しろと?」
「ま、そりゃ信じないわな。けど、オレにはアンタらの気持ち、わからんでもないからな……。応援したくなるやんか……」
「火鋸……」
火鋸が目をやった先には、倒れたままの宮真の姿があった。
「お前は、あいつを守らなくて良かったのかよ……」
「あれは、危険やったからな……。しゃーない。アイツの場合は自業自得や」
言葉の割に、火鋸の声は弱々しく響いた。そのやりきれない表情は嘘偽りに見えない。
「……宮真は本当に火鋸のことが好きだったんだと思う。君といるときの宮真は、本当に楽しそうだったから」
「オレかて、好きやったわ……。楽しかったわ……。けど、もうどうしようもない。オレはあいつを守れんかった。情けない。クソ、オレだって、殺したくなかったっての……。宮真、ごめん、ごめんな……」
火鋸が膝をつき、宮真の頬にそっと触れる。それは、僕たちが辿るかもしれなかった未来だ。
「火鋸……」
何と声を掛ければいいのか迷ったところで、白花にそっと手を繋がれる。
そうだね。僕らが何を言ったってきっと――。
「勝手に人を殺さないでよね」
「「「え?」」」
聞き違いだろうか。今、宮真の声が、確かに……。
「火鋸さ、酷いよ。ボクが死んでから告白なんてさ」
「うわっ! え、いや……! 宮真、お前、死んだんじゃ……?!」
悲鳴を上げた火鋸を見て、宮真が可愛らしい笑い声をたてる。
「これぐらいじゃ死ねないっての。ボク、こう見えて優秀なんだってば」
「んなアホな!」
ぱっちりと目を開けた宮真が、よいしょと起き上がり、僕たちに軽く手を振る。
「それに火鋸、めちゃくちゃトドメが甘かった。多分、無意識なんだろうけど……。その、本当にボク、愛されてたりするのかな、なんて……」
「……っ、はは! なんやねん、それ……。オレらかて甘々やん。はあ……、ホンマ敵わんわ」
観念したと言わんばかりに、火鋸が宮真の膝に突っ伏す。それに目を丸くした後、宮真は火鋸の頭を撫でる。
「ね、火鋸。ボクはずっと知りたかった愛を知れた。もう満足。だから、今度こそボクを殺すべきだ。火鋸は、せめてボクの首を取っとかなきゃ。立場がないんじゃないの?」
「……随分と物分かりがいいやん」
「面倒な恋人になる気はないからね」
「でも残念。オレはやっぱりお前を殺す気がない」
「え? でも……。ボクは……」
起き上がった火鋸が戸惑う宮真の頬を優しく撫でる。
「お前が凶暴な蟲だとしても、オレが生かすと決めたんや。他に手出しはさせないし、勝手に死なせたりしない」
「あ~、もう! ボクは火鋸のためを思って言ってるの! 火鋸の独断で決めていいことじゃないでしょ?!」
「なんでや?」
「なんでって……。火鋸が、上に逆らって殺されでもしたら、意味ないし……」
「ふは。なんや、自分そんな心配しとったんか! 心配せんでも、オレの星で一番偉いんはオレやから。気まぐれで方針変えても許されるわ」
「……一番、偉い?」
宮真が反芻した言葉に、僕と白花も思わず顔を見合わせる。
「言ってなかったか? オレ、星を統べる王様やってんねん」
「いや、聞いてないよ……!」
宮真のここ一番の大声に僕らもこくこくと同意する。
「あ~。まあそういうことなんで。わかったやろ? 誰を生かすかってのは割とオレの独断で決めれんねん」
「いや、なんで王様が直々にスパイやってんのさ!」
「最前線で動いていたい性質なんや」
「なんで王様がボクなんかを気に入るのさ!」
「そりゃ宮真、お前が可愛いからやろ」
「ッ~!」
「あ~。お二人さんおめでとう」「一応俺たちもいるってこと考えて欲しいけどね」
顔を赤くした宮真に向かって、ここぞと二人で合の手を入れる。
「なら折角やしオレらも一丁見せつけとこか」
「は? 待て、火鋸ッむ」
口づけを交わした二人から目を逸らしながら苦笑する。当初の計画とは大分異なるが、どうやら丸く収まりそうだ。
*
「ちゅーわけで。蟲に壊されたこの星が元に戻るまで、今日も元気に仲良くボランティアやってこうな!」
「故郷滅ぼしといて、殺さず奉仕させようなんて、恐ろしい王様もいたもんだ」
「はは。世間様からはそう思われてるみたいやな。結構結構。いい宣伝になるわ」
結局、僕ら以外の蟲たちは駆除され、僕らの星も制圧された。それに関して、僕が思うところはない。宮真も口では文句を言ってはいるが、火鋸の判断に異論はないはずだ。
「で。修繕が必要な場所のデータを取るために、俺らはこうして彷徨ってるわけだけどさ」
「やっぱり、結構な時間がかかりそうだけど……?」
「そうやな。終わるころにゃ、シロはじいさんになっとるかもしれん」
「シロくんがおじいさんになっちゃうんなら、ボクらもおじいさんだよ……」
「え? 待て待て、蟲の寿命てそんなに短いん?」
「僕らの寿命も、この星の人間と大体同じだもんね」
「そーそー。上位種だったらもうちょい長いんだけどね」
「そうなんだ、意外。てっきり俺も一人だけおじいさんパターンかなって」
「逆に火鋸は長生きなのか~。良かった」
「よくない。宮真が死んだらオレも死ぬ」
「ベタ惚れだね」「だな」
「真面目な話、火鋸はボクが死んだらちゃんとした人を作りなよ?」
「……は?」
「だってそうでしょ? 王様なんだから跡継ぎを作らなきゃ」
「……王様やめる」
「ベタ惚れだね」「だな」
「ま、いっか。どうせボクが年老いたら流石の火鋸も萎えるだろうしね」
「どうだかね」
「どう思う?」「絶対無い。骨になっても愛し続けますって顔してるって」
白花の返答に心から同意する。多分、火鋸は宮真が思っている以上に本気だ。
「シロくん! 留理くん! あ、宮真ちゃんに火鋸くんも! 早くしないと始まっちゃうわよ!」
ぱたぱたと駆けてきた少女が息を切らしながら叫ぶ。
「あ、もうそんな時間か。ありがとうクロエ」
「もう。イチャつくのはいいけど、時間ぐらい守ってよね!」
お礼を告げた白花にクロエはぷくりと頬を膨らませる。パーティードレスに身を包んだ彼女は、いつもより華やかで可愛らしい。
「行こっか、留理」
「う、うん」
白花がクロエに見惚れでもしたらどうしようかと気を揉んでいたが、どうやら杞憂だったらしい。
「清々しいほど留理くんしか見てないし、見せつけるように恋人繋ぎはするし。やってらんないわよ」
肩を竦めたクロエに苦笑しながら、口元のマフラーを整える。
クロエは運良く生き残った人間の内の一人だ。僕たちは、数える程しか残らなかった人間を集め、地球を元に戻すための活動を続けている。
彼ら人間は未だに僕らを人間だと信じて疑わない。……色々見てしまった人間の記憶は火鋸たちが弄ったようだ。お蔭で僕たちも、前の生活と遜色ない日々を送れている。
「しっかし、生き残った人間同士の結婚式が拝めるとはなぁ」
急ごしらえした会場に着いて、火鋸が感慨深げに数回頷く。
自由になった人間たちは、もう誰も無理やり子を成そうとはしなかった。火鋸も人間の種が滅びてもそれは仕方のないことだ、と無理やり数を増やそうとはしなかった。どうやら、本能に逆らっているのは僕らだけではないらしい。
でも、そんな中で新たな番が生まれたことは喜ばしいことに変わりない。
『おめでと~!』『幸せになれよ~!』
『ありがとう!』『幸せになりま~す!』
きゃあきゃあと浮かれた人間たちが幸せそうに微笑む。
「スーツにマフラーってどうなの、って思ったけどさ。意外と似合う。っていうか留理は何着ても似合うね」
「……もしかして、マフラーしてるの嫌だった?」
不安になってマフラーに手をかける。新しく白花が編んでプレゼントしてくれたそれは、やっぱり僕の大切な宝物になってしまった。依存していると言われれば否定できない。
「まさか。マフラーに嫉妬するのはやめたよ。今や留理のトレードマークみたいなもんだし。留理も、ちゃんと俺に甘えてくれるし」
「……あ~。ほら、なんか始まるみたいだよ」
花嫁の周りに群がる人間たちを見て指をさす。……適当に話題を逸らしたはいいが、彼女たちが何をしているのかよくわからない。
「あれはね、ブーケトスだよ」
「ブーケトス?」
割って入ってきた宮真に聞き返す。
「あれやろ。結婚式の目玉。花嫁が投げた花束をキャッチした人間は次に結婚できるとかいう……迷信や」
「宮真ちゃん、留理くん! ぼやぼやしてないで並んだ並んだ!」
「え」「うわっ」
クロエに引っ張られた僕たちは、若い女の子たちの輪に入り込む。そして。
『せーのっ!』
高らかに放られた花束目掛けて、人間たちが手を伸ばす。
『掴んだ!』『アタシのよ!』『あ、ちょっと!』『ああっ!』
まるで、バレーボールみたいに人の手で押し上げられた花束が、僕目掛けて飛んでくる。
「あ……」
「わお。ナイスキャッチ留理!」
宮真が拍手した途端、会場からぱちぱちと拍手が沸き起こる。
「おめでとう、留理」
そう言って白花が、申し訳ない気持ちでおろおろしていた僕の手から花束を取り、自然な流れで口づけを落とす。
『ッきゃああああああああ!』『ヒュー、やる~!』『おめでと~!』『結婚式続けてやるやつ?!』
「あ、いや、えっと、これは……」
思っていたよりも好意的な反応に困惑しながらクロエを見る。
「馬鹿ね。みんな何となく察してたみたいよ。どうやら私は頭が固い方だったみたい。だから、これからはもっと堂々とイチャつきなさいな」
「や~。めでたいわ~。なんていうか、オレ父親の気分や」
「ボクも。応援した甲斐があったってもんだよ」
ふっきれた様子のクロエと涙ぐむ二人に困惑しながら白花を見る。
「ん? おかわり?」
「……ホントにしちゃう? 結婚式」
「えっ?!」
悪戯に微笑んでやると、白花が顔を真っ赤にして驚く。その顔があんまりにも嬉しそうだったから、僕もつられて頬を染める。
僕には宮真が追い求めていたという愛の概念がイマイチわからない。人間たちが結婚式でこんなにはしゃぐ気持ちもわからない。
きっとこれからも僕の本質は蟲であり、白花の血を吸うことで生かされ、人間に擬態したまま過ごすだろう。もしかしたら、また人間たちとすれ違う未来もあるかもしれない。
だけど、僕はきっと白花を裏切れない。この幸せを知ってしまったからには、簡単には死なない。
「白花」
マフラーを掴みかけた手を止め、白花の裾を掴む。その甘えた仕草に応えるように白花が僕を抱きしめる。
「ブーケの力、すごい」
「ふふ。白花が喜ぶなら、僕、本当に結婚式挙げてもいいよ」
「えっ?!」
驚く白花に今度は僕から口づけを落とす。会場が更に沸く。地面に落ちた白い花束には、いつの間にか綺麗な蝶が止まっていた。
白花×留理。つよつよニコイチズッ友コンビにヒビが入るのが好きです!
留理(るり):「悍ましき日」に白花と出会い、現在はコンビで蟲討伐にあたっている。基本に無表情クール。白花には緩め。マフラーを大事にしている。長い黒髪を一つに束ねている。瞳は瑠璃色。ネーミングはルリアゲハ。
白花(はっか):基地の女性から絶大な人気を誇るイケメン。留理の前では割とおちゃらける。緑髪白眼。ネーミングはペパーミント(殺虫作用)。
火鋸(かのこ):前髪が長く、顔の見えない関西弁男子。強いので普段は討伐に引っ張りだこ。宮真と仲良し。ネーミングはひのき(殺虫作用)。
宮真(みやま):中性的な容姿と声でよく女の子に間違われるが男。火鋸のことが好き。ネーミングはミヤマカラスアゲハ。
クロエ:基地内一の美少女。白花のことが好き。留理と白花の仲を疑う。ネーミングは(白に対して)黒。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とある未来の話。地球はほぼほぼ侵略された。地球外からやってきた蟲によって追い詰められた。
残った人類は、必死に抵抗した。なんとか蟲たちを殺す兵器も作り上げた。
だけど戦いは長期戦へと縺れ込み、気付けば人間ももう千人程しか残っていなかった。
それでも、彼らは生きることを諦めてはいなかった。地球を守るために、蟲たちと懸命に戦った。戦って、傷つき、傷つけ合い。愚かな抵抗を続けていた。
*
「ほんと、次から次へと湧いてくる。まさに虫だな」
青年が緑髪を靡かせながら振るった剣は、衝撃波を生み、廃墟に巣食う蟲を一掃する。
その白眼に映し出されるものは、嫌悪であり憎悪であり。彼が蟲をどれほど憎んでいるのかが伺い知れる程、強い意志を宿していた。
「ほら、悪態ばっか吐いてないで。増援が来るよ、っと!」
黒髪の青年が、手に持ったリボルバーの引き金を引く。もぞりもぞりと悍ましい動きで前進してきた蟲に銃弾が命中し、さらに誘爆する。
「ヒュ~。相変わらずやるぅ」
焦げた蟲たちを覗き込みながら、緑髪の青年は口笛を吹く。
「白花、お喋りはいいから手を動かせ」
「ハイハイ。ってかその名前、呼ぶなって言ったろ」
白花と呼ばれた彼は、再び剣を振るいながら抗議する。
「名前が女っぽいから、だっけ?」
「そ。親がさ、女の子に用意してた名前をそのまま俺につけたんだよな~。女の子しか望んでなかったみたい。酷いだろ?」
「う~ん。わかんないな。僕は親に捨てられた身だし」
淡白に答えた青年に、白花は気まずそうな顔をしながらも、地面から這い出た蟲をぐしゃりと潰す。
「それを言われちゃアレだけど、さ。少なくとも昔の俺は親を恨んでた。クラスメイトからよく名前を揶揄われたし。男だったせいか、親に愛情注がれた記憶もないし」
「それは悲しいね」
「お前も『留理』ってさ、まあ女っぽい名前だよな。虐められたりしなかったか?」
「僕はそうでもないよ。この名前、結構気に入ってる」
瑠璃色に透き通った瞳が蟲の動きを察知して、白花に合図を送る。
「ま、俺もお前の名前、好きだけどっ!」
「じゃあ僕も君の名前、好きだよっと」
二人同時に放った攻撃が、辺りの蟲を薙ぎ払う。
「でもまあ、今となってはそう文句も言えねえけどな」
遠くの方を見つめ、寂しそうに呟いた白花を見て、留理は押し黙る。
(仕方のないことだ。彼の家族もクラスメイトも今はもういない。寂しさを感じない方がどうかしている。……もしかすると、僕の返答は少し冷たかったかもしれない)
留理が何と言葉を掛けようか考えあぐねていると、白花はそれに気づいてにこりと笑う。こういうところが今や数の少ない女性を虜にする所以だろう。
「それに。まぁ、留理に呼ばれるのは悪くないかな、なんて……」
「よし、ここらの蟲は片付いたな。戻るぞ」
キメ顔で芝居がかった台詞を吐いた白花に背を向け、留理が歩き出す。
「酷い! 俺の告白を無視するなんて!」
「蟲退治だけにか?」
「……留理のセンスって時々ズレてるよな」
「そうか?」
一瞬の沈黙の後、お互い顔を見合わせてくすりと笑う。
「戻ろう。今日は疲れた」
剣を仕舞った白花が、大きく伸びをしてズカズカと歩き出す。その足下には先の戦闘で殺した蟲たちの破片が、ゴミのように散らかっていた。
「ん、それは同感。最近、僕たち働き過ぎだよ」
留理はそれらをなるべく踏まないように注意しながら、銃をがちゃがちゃと調整して歩く。
「まぁな。蟲は増える一方でも、俺たち人間はそう簡単にゃ増えないしなぁ」
「……噂じゃ、上はクローンや合成獣みたいな禁忌に関わる研究を急いでるみたいだしね」
「はは……。笑えねぇよな。でも、いよいよそうせざるを得ないとこまで来てんだよなぁ」
「……」
(栄えていたであろう街並みも、ほんの数年の間で寂れ荒れ果ててこのザマだ。上の連中が焦る気持ちもわかる。でも……。やはりその結論は愚か過ぎる)
「俺らも数少ない女の子とそういうこと勧められてるしね」
「君はモテるもんな。白花の子どもなら産んでいいって皆言ってる」
基地内で一番女性からの人気があると言っても過言ではないくらい、白花の顔は整っているし、性格も申し分ない。それなのに、彼は一向に女性とどうこうなる気配がなく。平等に愛嬌を振りまく姿を、王子だなんだと持て囃される始末だ。
「俺にだって選ぶ権利があるだろ。そうじゃなきゃ何が人間だっての」
「人間、か」
「なんだよ」
吐き捨てた言葉にケチをつけられると思ったのか、白花は留理を睨みつける。しかし、留理は手に持った銃をそっと撫で、困ったように微笑んだ。
「いや、僕らはさ、子孫を残すという本能が生命に刻まれてる。はずなのに、さ。なんで、無意味な恋をするのかな、なんて……」
「無意味な恋……?」
「叶わない恋、っていうべきかな……。いや効率的でない恋、かな……」
珍しく煮え切らない様子の留理に、白花が目を丸くする。
「え、何、お前、好きな子いんの?」
「……いないよ。うん。やっぱり無意味ってのがしっくりくる。僕が好きになっても意味がない」
「恋に意味なんているのかよ」
「はは。詩人だね」
「茶化すなよ。俺はお前を心配して……」
「わかってるよ。でもね、どうしたって意味がないんだ」
「何だよ、一人じゃ叶わないってんなら、俺が手助けでもするし」
「ううん。駄目なんだよ。僕はね、子孫を残せる体じゃあないんだ」
「え?」
綺麗な声で告げられた言葉に、白花がどきりとして聞き返す。
「簡単に言うと精子が作れないんだ」
「そ、そう、なのか。それは、なんていうか……」
「白花、狼狽えすぎ」
「わ、悪い」
「はは。別に僕は何とも思ってないよ。そういうの、ほんと僕には要らないものだから」
「……」
「まぁ、そのせいで君に迷惑掛けてんのは、悪いと思ってるけどね」
「俺に迷惑?」
「僕は子孫繁栄の期待に応えられないからさ、きっとその分もお前に話が行ってるだろうなって」
「なんだ。んなこと気にしてんな、馬鹿。大体、子どもが出来なくたっていいだろ。いや、良くはないかもだけど、だからってお前の気持ちを隠すことは……」
「はは。白花は優しすぎるよ」
留理は後ろめたそうに弱く微笑み、首元のマフラーを握りしめる。留理の瞳の色によく似た蒼いそれは、どうやら留理のお気に入りらしい。
「そりゃ優しくもするさ。お前とはあの“悍ましき日”からずっと一緒なんだし」
悍ましき日。それは勿論、この地球に蟲たちがやってきた忌まわしき日のことを指していた。人々は、あらん限りの憎悪を込めてそう呼ぶようになったのだ。
「あの日から、もう三年は経つんだっけ」
「あぁ。俺たち、まだ十五そこそこだったもんな。いつも通りに家族と朝食を食べて、学校で他愛のないことをくっちゃべって。んで、帰ろうって時に、それは起こって……。商店街のテレビに映る光景はまるで映画の出来事のようで。でもそれは、すぐ側にまで来ていて……」
「白花」
「もぞりもぞりと黒く蠢めく蟲が、幾多の人々を飲み込んで。世界はすぐに黒く染まって。どこに行っても聞こえる鳴り止まない悲鳴、そして蟲たちの這う音。足を取られながらなんとか家に帰ってみたけど、そこにあったのは――」
「白花、顔色、悪い」
気づくと目の前にいる留理が心配そうに覗き込んでいた。その透き通るような碧い瞳がサンゴ礁の綺麗な海を思わせる。
一度だけ家族旅行に行ったときに見たあの海も、きっと今は黒く染まっているのだろう。また行きたかったんだけどな。家族みんな気に入って。珍しく母さんも上機嫌で。また行く約束、してたんだけどな……。
「白花?」
「ごめん、また思い出し過ぎちまった。あの日のこと」
「……」
留理の瞳がまた困惑したように揺れる。気を使わせたかな。
「俺に言わせれば、お前の方がよっぽど優しいぞ?」
茶化し気味に先ほどの言葉をとって返すと、留理は曖昧な笑みを浮かべた後、一呼吸置いてから「心配して損した」と俺の背中をばしりと叩いた。
*
あの日、家に帰って見たものは、まぁ、蟲に食い散らかされた両親の姿だったわけで。
その時、俺は初めて物を吐いた。
気持ちが悪かった。
ただただ、体は震えるばかりで。どうしようもなく怖かった。
それから暫くして、俺は恐怖を飲み込んで学校に向かった。
彼女が心配だった。友人が心配だった。
「アイツらはまだ残って補習を受けてるはずだ。何もなければいいけど……」
いつの間にか足は駆け、風を切っていた。
その頃にはもう、街は不気味なくらい静かになっていて。
襲い来る底知れない不安を払って、学校の門をくぐった。
そこここに散らばる人だったものの残骸。吐きそうになるのを堪えながら、それらを踏み俺は進んだ。
ただ、知人の声を聞きたくて。生きている人間の声が聞きたくて。
教室のドアを開け、俺は膝から崩れ落ちた。
そこにあったのは、今まで見てきたものと何ら変わりのない残骸だった。
血の匂いが鼻腔を突き、再び吐いた。もう吐ける物は胃に残ってなくて、唾だけが口から流れていった。
ややあって、ふと側にリングが落ちているのに気づく。
それは、自分のはめている物と同じ、ペアリングで。
これ、彼女との一周年記念に買った……。
伸ばしかけた手が止まる。銀色が見えないくらいに赤く染まったそれは、血だまりの中に落ちていて。
拾えはしなかった。
ああ。情けない。
自分の指からリングを外し、握りしめる。
ごめん、ごめんごめんごめん。
止めどなく溢れる感情と共に、涙が伝う。
ああ、このまま俺もここで……。
もぞり。
「っ!」
俺の心を読んだみたいにタイミングよく視界の端で黒い何が蠢めく。
目を向けると、丁度それもこっちに気づいたように動きを止め、凝視している。
く、来るな……。
声も出せずに心の中で願ってみたものの、それはキチキチと嬉しそうに触覚やら口やらを震わし、こちらに向かって這い出して……。
「く、くそっ!」
近くにあった教科書を投げつける。しかし、それは少し動きを止めただけで、また這い、当然のようにこちらに向かってくる。
「くそったれ! よくも! くそ! くそ!」
躍起になって片っ端から手に掴んだものを投げてゆくが、それは、気づけばもう目の前に来ていて……。
ぐわりと黒い口が開かれる。
「あ……」
立ち上がろうとしているのに、手は血だまりで滑り、足は竦んで動かない。
ああ、今死んだら、みんなとまた会えるだろうか……。
カタカタと震える歯を噛みしめる。
「う……」
ぐちゃりとした感触が手に張り付く。手が、それに食われてゆく。
ああ、気持ち悪い。こんなのに食われて終わりだなんて、そんなの……。俺は……。
「嫌だ! 俺は、俺はッ! こんなところでくたばりたくないッ……!」
『ギギャ!』
「え?」
半狂乱になりながら、張り付いたそれを剥がそうと腕を振り回していたところ、何かが鋭く掠めてゆく。
視線を落とすと、自分を食わんとしていたそれは床に転がっていた。その背にはコンパスの針が刺さっていた。
「危なかった」
『グジュッ!』
ぼそりと呟き、目の前に現れた少年が、モップの柄でその物体を潰す。動かなくなったそれを凝視していると、少年が俺に手を差し出す。
「な、に……」
「怖がらなくていい。僕もここの生徒だから」
少年は口元のマフラーを手で押さえ、俺を安心させるように微笑んだ。
そう言われてみると、少年の蒼いマフラーには見覚えがある気がした。それに加えて、制服とシューズの学年カラーが自分の物と同じことを確認し少し安堵する。
「なん、だよ、もう俺だけかと思った。生きてる人間がさ。ああ、良かった……」
「僕も、君が無事で良かった」
「ん、もしかして俺のこと知ってる?」
「まぁ。君、モテるから有名だし」
「……」
確かに俺、女子からの評判は悪くなかったもんな。
死んでしまった彼女も、告白してくれた子の中の一人だった。
可愛くて、タイプだったから付き合うことにして。
だんだん好きになっていってたのに。このまま将来結婚したら幸せだろうなって思ってたのに。
「俺は……」
「……とりあえず、一緒に逃げよう」
「逃げるって、どこへ」
「これ」
ポケットから端末を取り出した彼は、座り込んだまま動かない俺に画面を見せる。
そこには、生き残った人への非難指示が出されていて。
そこから、避難場所へと集まった人々と共に更に遠くの仲間を目指し、戦い、進み。
多くの仲間が失われた。
そして今、俺たちは人類最後の組織に保護され、上の指示に従って、戦いに明け暮れる毎日だ。
そういえば、あのペアリング、きっと落としたんだろうな。
握りしめていたはずだった。でも、結局は自分の身を守るのに必死で、自分の未来が大事で。すっかりと記憶から抜けてしまっていた。今頃気づくなんて。いや、それどころか最近は、めっきり彼女のことを思い出しもしなくなったなんて……。
「最低だな、俺」
ぽつりと呟いてから首を振る。目の前を歩く留理の黒髪を目で追い、ため息を吐く。
死んだ奴をどれだけ想っても還りはしない。例え最低でも、今を精一杯足掻いて生きる方がよっぽど俺らしいさ。
*
「二人ともお疲れさま!」
基地に戻ると、いつものように可愛らしい声が出迎える。
「宮真、ただいま」「ただいま」
宮真は僕たちに微笑んだ後、可愛らしい顔で白花を覗き込む。
「あれ、シロくんお疲れ?」
「あ~、ちょっとな。留理、悪いけど俺もう寝るわ」
無理に宮真に微笑み返した後、白花は僕に断ってから部屋に戻る。
「ん。お疲れ」
「……なんかあった?」
直球で尋ねてきた宮真に首を振る。
「何も。ただ働き過ぎただけさ。僕も疲れたから休むよ」
「そう」
「宮真は火鋸待っとくの?」
「そ。戦えないボクにはそれくらいしかできないから、ね」
「……」
僕と同じく黒髪に瑠璃色の瞳を持った彼は、僕よりも中性的で愛らしい見た目をしていた。そのおかげで、最初はよく兄妹に間違えられた。
宮真は生まれつき病弱らしく、自分でも生き残っているのが不思議だと言う。なんでも運が良かったのと、途中から火鋸が守ってくれたお陰でここに辿り着けたそうで……。
「まぁ、ボクが少しでも長く火鋸と話したいってのが大きいんだけどね」
宮真はえへへと笑いながらそう付け加える。その真っ直ぐな気持ちが僕には眩しい。
「本当に火鋸のこと気に入ってるんだな」
「そういう留理も、シロくんのこと……」
「僕は! ッ……、僕は、違うから……」
マフラーで口元を覆いながら、自分を律する。いちいち宮真の揶揄いに付き合っていたらキリがないことぐらいわかっている。はずなのに、毎度過敏に反応しては宮真を面白がらせてしまう。
「今のうち素直になっといた方がいいのに。いつ死ぬかわかんないんだからさ、やりたいことはやんなきゃ、後悔するよ? キミもわかってるだろ?」
僕を見た宮真が、呆れたように何度目かわからない説教をする。
「……とにかく、今日は疲れたからもう寝る。おやすみ」
「あっ。また逃げる~!」
ぷぅと頬を膨らませる宮真に、ひらりと手を振り背を向ける。
僕だって、時間がないことくらいわかってる。
僕と白花のどちらが死んでもおかしくない。
だけど、でも。
「伝えたって意味がないじゃないか……」
ため息と共に漏れた言葉は、我ながら弱々しくてみっともなかった。
あれから数回ため息を吐いた後、部屋に戻り寝る支度を整える。
最後に、メンテナンスした銃器を置き、ベッドで休む彼に目をやる。
僕たちの部屋は二人部屋で、二段ベッドに眠る。
僕は上の方だから、上がる時にどうしても彼の寝顔が見えるわけで。
「……」
言い訳がましく盗み見た彼の顔は、寝ているというのに澄ましたように整っていて。
戦闘のときのクールな表情も、女の子たちにする甘い表情も、どれもどこか冷たい気がした。
いや、冷たいという表現がぴたりとくるのは、むしろ僕の方なのだけど。
こう、なんというか。疲れそうだなって思う時があるのだ。
あの日、あの”悍ましき日”に見た彼の表情は、確かに本当の彼だった。
蟲に怯え、絶望し、それでも尚抗わんとする彼は本当に人間らしくて……。
だから、あの彼を知っているからこそ、今の彼は疲れそうだなと思うのだ。
いや、元から彼はああなのかもしれない。みんなに愛嬌を振りまいている王子様だということは知っていた。
だけど、僕は思うのだ。彼はあの日から特に無理をしてると。勿論そんなの、この基地にいるみんながそうだけど。でも。
僕は彼が弱音を吐いているところを一度も見たことがなかった。
未来への不安、襲いくる敵への恐怖、大切な人を失った悲しみ、怒り、憎しみ。誰もがそれを抱えきれずに零す。しかし、白花はそれをせずとも強く生きてきた。
それなのに。
「今日は僕が余計なこと、思い出させちゃったよね……」
ごめんと呟き、白花に手を伸ばす。
白花は、僕といるときは、少し気を緩めてくれている気がする。
そりゃあ二人でいることが多いから当たり前といえばそうだけど……。
僕は、白花と居る心地よい時間が好きだ。このままずっと互いに深入りしないで冗談を言い合う今の関係でいたいと思う。
だけど。
それと同時に、もっと白花のことを知りたいと思ってしまう自分がいることに、嫌でも気づく。
もっと白花の弱いところを曝け出してくれてもいいのに。もっと僕のことを頼ってくれてもいいのに。
そんな思いが胸を過ってしまう。……つまらない葛藤だ。
頬に伸ばしかけた手を引き、自分のベッドへ上る。
だって。僕じゃ彼を救えないのだから。
*
寂れた廃墟をざくざくと進む。時々かさかさと音がするのだが、それが鼠などの生き物なのか蟲たちなのかはわからない。
ただ響くのは、それと地を踏みしめる自分の足音。他はもう時間が止まってしまったように静まりかえっていて。
一人きりの任務は久々だ。これまで幾度となく任務をこなしてきたけれど、殆どが白花と一緒だったから……。
「薄気味悪いな」
寒気を感じて首元のマフラーを口に寄せる。銃を正してそのまま進んでいると。
「よぉ」
「……どうも」
瓦礫に腰掛けた男に声をかけられる。
「驚かないのかよ」
「いることはわかってましたから」
「チッ、相変わらず優秀なことで」
舌打ちをした男は、僕たちと同じ討伐隊のメンバーで、上司にあたる人物。名前は覚えてないが、そのチャラついた容姿は嫌でも覚えている。
「今日はシロと一緒じゃないんだな」
「えぇ、まぁ」
シロというのは白花のことだ。白花は自分の名前を呼ばれるのが嫌いだ。だから周りも自然と"シロ"と呼ぶようになった。
でも、僕はそれが何だか勿体無くて。嫌がるだろうとわかっていながら、白花と呼び続けた。
『それに。まぁ、留理に呼ばれるのは悪くないかな、なんて……』
先日の彼との会話が頭を過る。例え冗談だったとしても、その言葉がどれだけ嬉しかったことか。彼に認められたようで、特別なようで。くすぐったくて、思わずそっけない態度を取ってしまったわけだけど……。
「相変わらずシロ以外には冷てーな」
吐き捨てるように目の前の上司が呟く。
「……すみません。任務があるのでこれで」
「仕事だけ出来たって生きてけねーぞ」
背を向け去ろうとした僕に野次が飛ぶ。
「……蟲に殺されたら意味ないと思いますが」
「お前が生きてたとしても、どうせ子ども作れねーだろ? 上が言ってたぜ」
「子どもを作るのは義務ですか?」
「あ? こんな状況だぞ。嫌でも作んだよ」
「疑問はないんですか?」
「あ~あ、お前甘いね~。そんな甘っチョロいこと言ってっと……」
背後からマフラーの端を掴もうと、男の手が伸びる。その気配を察し、それを紙一重でひらりと躱すと男の舌打ちが響く。
「そういやマフラー、お気に入りなんだっけ? ママの手編みかなんかか?」
「まぁ、そんなところです」
下卑た笑いを浮かべる男を感情のない瞳で見つめて、マフラーを整える。
「ケッ、本当のとこは何だ? 女からのプレゼントか? それとも、愛しのシロ君か?」
「……」
「はっ、シカトかよ」
「……」
「お前のその態度、ほんっと前から気に入らねぇんだよ。いい加減ッ!」
「!」
「序列ってモンを教えてやんないとなァ!!」
言葉と共に剣が振るわれる。しかし、それも予測の範囲内だ。
その狂気をもひらりとかわすと、男はとうとう手加減することをやめ、こちらに本気で斬り掛かる。
「クソが!」
「もうやめてください」
静かに、これ以上刺激しないように努めた言葉も虚しく、却って攻撃を加速させてしまう。
「澄ましやがって! ガキのクセにムカつくんだよ。上から特別扱いされやがって!」
「特別扱いなんて……」
「オレが生き残ったブスと無理やりヤらされて子ども作らされてんのに、お前らは……!」
「そんなの、拒否すればいいじゃないですか!」
振るわれた剣を躱し、護身用のナイフで逸らし、受け止める。しかし、男の怒りはまだ収まらない。
「ンなことできるかよ! オレだって嫌だけど、でも仕方ないだろ。人類のためなんだよ!」
「僕には、理解できない」
「だからそれが甘いって言ってんだよ!」
がむしゃらな斬り込みが続き、それが当たることもない内に、威力がそろそろと弱まってゆく。
……弱い。上司と言っても、隊に所属したのが僕らよりも早かったというだけ。戦闘力に優れている僕や白花と与えられる役が違うのは当然のことだ。
「クソ、当たんねぇ!」
「あの、本当にやめてください。こんなことをしている時間は……」
「シロも、お前のことウザいって言ってたぜ?」
「え……?」
突然白花のことを言われて、頭を殴られたように時が止まる。
「ほら、甘いっ!」
「!」
「嘘だっての!」
「っ!」
男の剣が肩を切り裂く。今までの攻撃は避けきれていたのに。こんなことで隙を作ってしまうなんて……。
傷を負った肩を押さえる。傷自体はギリギリで回避し損ねた程度の浅い傷だが……。
「律儀に動揺しちゃって。お前、シロのこと大好きだもんな。気持ち悪いくらいに。ていうか、やっぱソッチの人だから勃たないとか?」
「……」
「アハ! やっぱそうなのかよ! 留理ちゃんはホモか、怖い怖い! あ、じゃあこんな人気のない場所じゃ、オレも狙われちゃうかな、コエ~!」
「……」
「ってなると、じゃあシロもホモか? うわ~、引くわ」
「……」
「お前ら気持ち悪いと思ってたんだよ! 可愛い子に寄られても平然としてるシロなんかは、もっと気持ち悪い! なあ、これ、上に言ったらどうなるかな? こんなときに男同士でどうこうやってたらさ、流石に引き離されるっしょ。上もお前らを正気に戻すために女を宛がってくれるかもよ? そうなりゃ、オレの負担が減って最高だよなァ?」
「……」
ぺらぺらと喋る男から目を逸らし、地面を見つめる。
「さーて、楽しい土産話もできたし、帰るか、な……、って、ヒッ?!」
「?」
男の悲鳴に顔を上げる。
「な、なんで、いつの間にこんなに蟲が……?!」
見ると、地面から這い出してきた蟲たちがじわりじわりとにじり寄ってきていた。
「おい、お前、いつまでもしょげてないで手伝えって……」
自分のことをどう言われたって構わなかった。でも、白花のことを言われたら。奈落に落とされたように思考が真っ暗になって……。
上だってこの男の話を本気にする訳ない。だけど、もし。もしも、この男の言うように、僕のせいで白花が本当に女とどうこうするようになってしまえば……。
そんなのは嫌だ。
今はいい。まだ男は残っているし、未成年で戦闘要員の僕たちにはお付き合いごっこを推奨されるだけだ。白花もそれに乗り気じゃないから、悉くそれを断っている。だけど、もし、この男のように白花が強制的に人間たちのエゴに巻き込まれてしまうのであれば……。
僕はきっと、気が狂ってしまう。
それに、この気持ちが、周りや白花にバレてしまったら……。こんなものが、白花に知れてしまったら、僕は一体どうすればいい? こんな浅ましい感情で白花を汚していいわけがない。絶対に知られるわけにはいかないんだ。だから……。
ああ、ああ! 気が狂う。狂ってしまう……! 僕は――!
「おいっ、さっきのは謝るから、なあ、おいって、クソ、やめろ、食うな、た、助け……!」
「……」
ぼんやりとする視界の中、マフラーの切れ端を拾い上げ、頬に寄せる。
「うあああああああ」
大切なそれは、先ほどの男の不意打ちですぱりと切れてしまっていた。僕の肩なぞどうでもいい。それよりも、このマフラーを切られたことが、どうしようもなく腹立たしくて。
「痛ぇ、痛ぇよぉ、助けてくれ、助けてくれぇ……」
「……」
「あああ、頼む、助けてくれ、謝るから、おい、助け――」
「あ」
男の悲痛な呻きに、ようやく現実に引き戻され、ハッとして手を伸ばす。が。
ぐしゃり。蟲に噛まれて飛び散った男の血が頬にかかる。
「あ……、僕は……」
*
割り当てられた地区を調査した帰り。辺りは暮れて、暗い空に月明かりだけが煌々と輝く。森の中、月光だけを頼りに歩くのも風情なもんだとは思うけど……。
「やっぱ、一人は嫌なもんだな……」
いつもならば留理がいて、背中を預け合える。なにより、無駄口を心置きなく叩ける。
だから、こんなにも静かな空間に独りきりだなんて、気がおかしくなってしまいそうだ。
ああ、早く帰ってアイツと話したいな……。
無意識に留理の姿を思い浮かべる。あの一つに束ねられた長髪が揺れるのを、後ろから見つめるのが好きだった。
アイツも今日は単独任務だったはず。留理がやられるわけないとわかっていても不安が募る。だって、この世界はもう平和だったあの頃とは違う。何が起こるかわからないから。だから、早く帰ってアイツの無事を確認したい。
「少し、依存し過ぎてるかもな……」
一緒に行動することが多いからといって、こんなにベタベタ甘えられちゃ、アイツも苦い顔するかもな……。
なんて、己の呟きに嘲笑しかけたそのとき――。
ぱしゃん。
「ん?」
近いところから聞こえた音に剣を握りなおす。
「湖、か……?」
音を頼りに少し歩くと森が開け、ひっそりとした湖が現れる。月明かりを浴び、きらきらと光る水面は、まるでおとぎ話の一場面のように美しい。
ばしゃり。
足を止め、再び水音のした方を見る。そこにいたのは。
「留理……」
呟いてから息を飲む。闇を照らしたように艶やかな黒髪、水と共に透き通るような白い肌、そして、水面のように揺らめく伏し目がちな瑠璃色の瞳。水の中を優雅に揺蕩うその姿は、森の精なのだと言われたらその存在を認めてしまうほどに美しく。浮世離れした何かを秘めていて……。
一体、留理は何をしてるのだろう。下はズボンを履いているみたいだけど……。上には何も羽織っていない。ふと、留理がマフラーを手に、思いつめた顔をしていることに気づく。
「留理……?」
少し不安になって彼の名をもう一度呼ぶ。すると。
「え、はっ、わ……!」
こちらに気づいた留理は、途端に顔を赤くして……。それからバランスを崩し、バシャバシャと溺れかけた。
「留理!」
「留理、ハァ、ほんと、びっくりさせやがって……」
「それは、僕の台詞だろ、全く……」
あの後、慌てて湖に飛び込もうとしたが、結局留理は持ち直し、俺を制して自力で水から上がってきた。
「ごめんて。でもお前、何してんだよ、こんなとこで……」
「あ~。それは。ちょっと、シャツに蟲の血がついたから、落とそうと思って……」
そう言って後ろを向いた留理がシャツを絞り、そのまま羽織る。そしてその首にマフラーを巻く。
「蟲って、大丈夫か?!」
「いや、ごめん。大丈夫なんだ。心配させるつもりはなくて……」
「でも、これ……」
制服にべったりとついた赤色を見て、留理の右肩を掴んだ手に力を込める。左の肩は留理が片手で押さえているため、触れないが、恐らく傷を負ったのを隠しているのだろう。
「あ~、うん。“僕は”大した怪我してないから……」
肩に置かれた俺の手をやんわりと外し、留理が静かに作り笑いを浮かべる。確かに彼の言う通り、深く傷を負った訳ではなさそうだ。でも。
「あ、ちょっと、白花。そんなにあちこち触らないで……」
「お前、これ」
他に傷跡がないか念入りに調べていると、水を吸い込み、ずっしりと重くなったマフラーが千切れていることに気づき、手を止める。途中で千切れたのを雑に結んでつなぎ合わせてあるのだ。
「あ~、それ、は。ちょっと、ミスったんだよね……」
はは、と乾いた笑みを浮かべる留理を見て、拳を握りしめる。それが、泣きそうなのをぐっと堪えているのだと知っているから。だから。
「俺が直してやるから」
「え?」
ぽん、と留理の頭に手を乗せてやると同時に、自然と言葉が口を衝いた。
「あ、でも触られんの嫌なんだっけ?」
留理は、人にマフラーを触られることを嫌う。きっと、それほどまでにこのマフラーが大切なのだろう。詳しく話して貰えたことはないが、何でも昔、恩人から貰ったらしい。……俺は、留理がマフラーを大切そうに握り絞めるのを見る度に、どうしてだか苛ついた。……きっと、指輪を簡単に捨ててしまった俺と違って、いつまでも思い出を大切にできる留理が羨ましいのだろう。
「いや、白花なら大丈夫。お願い、したい……」
伏し目がちに紡がれた信頼に優越感を覚える。さっきまでのモヤが晴れる。きっとその恩人とやらも死んでいるのだろう。だったら、今、留理が頼れる存在は、俺しかいない。
「留理、左肩、ちゃんと見せて?」
「……なんだ、バレてたか」
留理の手をずらすと、その白い肌には浅い傷がついていた。それに、横に垂らした髪も、左側だけスパリと途中で切れている。
「へ、変異種で……。芋虫型じゃなくて、カマキリ型で……。油断しちゃったんだ……」
髪を弄んだ俺に、言い訳するように留理が言い募る。確かに、最近の蟲は進化している。留理でさえ傷を負ってしまうなんて……。
「留理、俺、お前と一緒に行けばよかった」
「……僕も、そう思ったよ」
色の悪くなった頬を撫でる。冷たい。俺が一緒に行けば、留理にこんな顔させなくてよかっただろうに。マフラーだって、守ってやるのに……。
「あ、でも俺、裁縫とかできな……」
「は、れ……?」
「留理!」
ふらり、と留理がいきなり倒れ込む。それを地面につくぎりぎりで掴み、抱き寄せる。
「ごめん、ちょっと、気が緩んだら疲れが……」
「大丈夫か?」
「うん」
「ほら、背負ってやるから」
「悪いね……」
本当に。俺が一緒にいたならばきっとコイツを守れたのに。だから単独任務なんて嫌だったんだ。
ぴぴっ。タブレットに電波が届く範囲に来たところで、通信が入る。
どうやら上司が一人、蟲に襲われて亡くなったらしい。その報告を見て、思わずにはいられなかった。……留理でなくて良かった、と。
*
基地に着いた頃には、すっかり夜中になっていた。
もう大丈夫だから、と白花の背中から降ろしてもらったところで足音が聞こえてくる。パタパタと慌ただしく音を立てて近づいてきたそれは、勢いよく白花に飛びついて……。
「シロくん!」
「わ、クロエ」
白花が抱きとめると、クロエと呼ばれた少女は顔を赤く染め、はにかむ。
「あのね、シロくんを待ってる間、私ね……!」
「ごめん。クロエ、今はちょっと」
言葉を続けようとする彼女に、白花が申し訳なさそうに謝罪する。労わるように僕の肩に置かれたままの白花の手。鋭く突き刺さる彼女の視線。
「白花、僕、先に部屋戻っとくから」
「あ~、ごめん。すぐ行くから」
別に急がなくてもと思ったが、口に出せばきっとまた彼女に睨まれる羽目になりそうだったので飲み込み、背を向ける。
「あ、留理、帰ってたんだ! 遅いから心配してたんだよ?」
部屋に戻る途中、ばったり会った宮真は相変わらず可愛い声で、さえずるように僕の心配をしてくれた。
「ごめん、ちょっと色々あって」
「うわ、エライびしょびしょやん。雨なんて降ってなかったやろ?」
珍しく僕らより早く帰っていたらしい火鋸が、宮真の隣で特徴のある言葉を紡ぎ、こちらを覗き込む。
「あ~、湖に浸かっちゃって」
「ヒェ~。見てるこっちが寒ぅなるわ~!」
寒い寒い、と腕を摩る火鋸の……名前の通り温かそうな色をした髪が、炎のように揺れる。
「火鋸ってば、ほんとにちゃんと見えてるんだ?」
「見えてないと戦えへんやろ?」
大げさに溜息を吐き、肩を竦めた火鋸。その腕を引き、自分の腕へと絡める宮真。この二人はいつ見ても仲が良い。
「ん~、でもさすがに伸ばしすぎだよぅ」
火鋸の目は長い前髪に覆われているため、その瞳を僕はまだ一度も見たことがない。それがどうにも不思議でならないのは、僕だけではないらしい。
ここぞとばかりに前髪を押し上げようとする宮真。見られまいと抵抗する火鋸。
「だ~から、やめろって言ってるやろ毎度!」
「だって! いっつも顔見せてくんないし! 気になるよ~!」
「んなことより、今は留理の心配やろ!」
言い争っていても、二人は本当に仲睦まじく、傍から見れば青春を謳歌する恋人同士のようで……。
宮真は本当に火鋸のことが好きなのだろう。その真っ直ぐな好意がやはり僕にはひたすら眩しかった。
「あ~、僕ならちょっと休めば平気だから」
少し休んだくらいで気分が晴れるとは思えないけれど、二人の邪魔をするわけにはいかない。
「せやな。まあ、早う休んだ方がええやんな」
「あ、ごめん。そうだよね、早く着替えないとだよね」
「うん、ごめんね。二人とも、おやすみ」
二人に背を向け、再び部屋へと歩みを進める。その間にも、二人の会話が耳に入る。
「にしても確かにな、今日は何や蟲の動きが活発っぽかったもんなぁ」
「え、そうなの?」
「おー。そんな日に単独はキツイやろ」
「あ、今日はシロくんと留理、別行動だったんだ?」
「らしいな。珍しく」
「そういえばシロくんはもう帰ってきたのかな?」
「まだ見てへんけどな……ってあ。なんや、帰ってきとるやん」
「う、うん。ほんとだ」
宮真の言葉に戸惑いが生じる。ああ、きっと……。
「あの二人、ほんと白黒でお似合いやな」
「わ~! 火鋸、それ言っちゃ……」
僕のことを気にして宮真が狼狽える様子が目に浮かぶ。
白花とクロエ。きっと、彼らの姿が見えたのだろう。
マフラーを口元に寄せようとして眉を顰める。そういえば、マフラーは白花に預けたんだった。
行き場をなくした右手を握りしめる。そして、僕は少しだけ歩調を速めた。
わかってる。白花とクロエ。あの二人がお似合いだって。ブロンドの腰まである長い髪、そしてくりくりとした黒い瞳。お人形みたいに可愛らしい同世代の彼女が白花の隣に立つだけで、おとぎ話の王子様とお姫様のようにしっくりくる。こんな二人が生き残ったのは神様のご加護があるからだと、誰もが囁き、羨み尊敬した。だから、僕なんかが僻んでいいものではない。
「くそ……」
枕を殴る。何度目かわからないその行為にため息をつく。
自分でも呆れるくらい寝付けなかった。シャワーを浴びて温まったはずの身体もすっかり冷めてしまった。
時計はカチコチと音をたて、時を刻む。どれだけ規則正しい音を聞いても同居人が帰ってくる気配はなく、僕が深く眠りにつく気配もない。
酷く疲れているはずなのに。眠りへの誘いに乗ろうとするのに。うとうととした瞬間、映し出される悪夢がそれを邪魔するのだ。
『あの二人、ほんと白黒でお似合いやな』
どこからともなく聞こえてくる火鋸の声に、クロエが微笑み、白花の手を取る。
二人は指を絡め合い、笑いあう。
天国のように明るい花園で、花びらが舞い、二人の仲睦まじい笑い声が響く。
純白のドレスにタキシード。ああ、幸せそうだな。
僕がそう思った瞬間、二人は白く塗り潰されて、見えなくなる。眩しい。とてつもなく眩しい。
僕は、二人から遠く離れた暗闇で、一人寂しく蹲る。大丈夫。どうせ泣いたって、暗い闇じゃ見えもしない。ああ、惨めだな。僕には白花を想う資格がないのに。そんな感情を持っている暇はないのに。ああ、信じてよ、白花……。僕はただ、本当に……。
「う、あ……ッ」
悪夢から目を覚まし、少し濡れた目の端を拭う。
またさっきの夢だ。同じ夢ばかり見るなんて、本当に僕は馬鹿だ。馬鹿でいて……。
「情けないなぁ」
そう独りごちて身を起こす。と、そのとき。
「何が情けないんだ?」
「!」
咄嗟のことに心臓が飛び跳ねる。生きた心地がしなかった。すぐ傍に白花がいるなんて、予想してなくて……。
「あ……」
喉が渇いたように声が出なくて。眩しさから逃れるようにして、すぐさま彼から視線を外す。
「留理、大丈夫か?」
「あ……、うん。ごめん……。ちょっと、まだ寝ぼけてて……」
「起こしちゃったよな。ごめん」
「いや……。変な夢見て、起きただけだし……」
「変な夢?」
「や、くだらないやつだから……。それより、どうしたの? こんな夜中に」
「ああ、これ」
額の汗を拭いながら白花に問うと、彼は手に持っていた物をこちらに見せる。
ああ、なるほど。
「マフラー……」
「そ。ほら、すっかり元通り……とまではいかないけど」
渡されたそれは破れたところがわからないほどきちんと編み直されていた。
「これ、白花が?」
「うん、クロエに教えてもらって直したんだ」
「……そう」
「あ、やっぱ嬉しくなかった?」
「いや、そんなことはないよ。ありがとう、白花!」
くだらない感情を飲み込んで、マフラーを頬にあてる。僕にはこれがあればいい。これさえあれば、僕は満足だ。
「……クロエにはそれ、触らせてないから安心しろ。まあ、俺の手は加わっちゃったわけだけどさ」
「……そうなんだ。ごめんね、ありがとう。大事にするよ。もう誰にも汚させない」
マフラーを抱いて目を瞑る。良かった。これで本当に僕は大丈夫だ。
「……なあ、留理。それ、さ。そんなに大事なの?」
「え? うん。僕の、一番の宝物だよ。白花もよく知ってるだろう?」
僕の手からマフラーを取り上げ、優しく首に巻いてくれた白花に首を傾げる。どうして、彼はそんなことを今更聞くのだろう。
「大事だったらさ、俺なんかに触らせちゃ駄目じゃん」
「……? どうして?」
「どうしてって、そりゃ……。いや、何でもない。留理がいいなら、それで……」
複雑な表情を浮かべた白花に眉を顰める。僕は何か変なことを言ってしまったのだろうか。
「白花……?」
「さ、もう早く寝ろ。これがあったら、もう変な夢も見ないだろ?」
「うん……」
その表情の訳を問おうとした途端、白花が僕に布団を被せる。そして、優しく髪を撫でられ、額に口づけを落とされる。まるで赤子のような扱いだな、と文句を言おうと思ったけれど、存外心地よいそれに微睡を覚えたので大人しく目を瞑る。
よかった。今度はよく眠れそうだ。
*
「お願いだから、これ以上シロくんを惑わさないで頂戴!」
唐突に投げかけられた言葉に振り返ると、少女が憎悪を露わに立っていた。その黒い瞳は僕を睨みつける。
「僕? 悪いけど、きっとそれは君の勘違いだよ」
面倒なことになったな、と内心ため息を吐きながらクロエを見つめる。彼女が白花に執着していることは気づいていた。だから、なるべく彼女の前では白花と距離を取るようにしていたのだが……。この前の一件が彼女の逆鱗に触れてしまったらしい。
「この前のことだけじゃないわ……。シロくんは、いつもアンタのこと見てるのよ?!」
「ああ、なんだ。そんなことか」
「そんなことって! シロくんは、いつもアンタのことしか話さないし……」
「ごめん。言い方が悪かったよ。でもね、それは白花と僕は一緒にいる時間長いから、話題もそうなるだけで。あと僕を見てるってのも多分違う。それ、そういう意味じゃない」
「じゃあ、どういう……」
「僕は、嫉妬されているだけに過ぎないんだよ。白花の本命は恐らく、宮真だ」
クロエが見ているとき、僕は意識的に宮真と話をすることが多かった。勿論、僕が白花と近づいて在らぬ誤解を招かないようにという配慮の上だ。
宮真と話しているとき、白花の視線を何度か感じたことがあった。僕だって、最初は僕に向けられた視線の意味を勘違いしそうになったけれど。……あれは、間違いなく嫉妬を含んでいる瞳だった。
『あら~、留理も気づいてたんだ。好きなんだろうね』
その視線に気づいたとき、それとなく探りを入れた僕に宮真はケロリとして言った。
『僕は火鋸一筋なのにさ』
舌を出し、いたずらっぽくそう言った宮真の言葉に、僕は確信を持った。
その真っ直ぐな恋が羨ましかった。それと同時に、白花の恋が叶わないことにホッとしてしまった自分が浅ましかった。
「じゃあアンタは一体何なのよ」
唐突な質問に面を食らう。見当外れの嫉妬を披露してしまったせいか、彼女はその目に涙を溜めて、なおも食い下がる。
「僕は白花の……」
……あれ。僕は白花の何だろうか。何だか、友達というのもおこがましいような気がして。
「何でもないよ。ただの任務上のパートナーだ。君が気にするようなものじゃない」
そう口にするのが精一杯だった。
「それじゃあアンタは私を応援してくれるの?」
「勿論。応援するさ。白花には幸せになってほしいんだ」
結婚して、幸せな家庭を築く。そんな“人”としての幸せ。この限られた世界の中で、せめて白花にだけはそれを忘れないでいて欲しい。その願いは本物だ。もし、彼女が白花にそれをもたらすのであれば。もし、白花が自分の意思でそれに応じるのであれば、僕はきっとそれを応援できる。
「本当に……?」
「ああ。神に誓おう」
信仰している神なんていないけれど、彼女を安心させるためにはこの言葉が相応しい。
「なんだ……。私ってばシロくんが留理くんのこと、好きなんじゃないかって……。本当にヒヤヒヤしたのよ? 男同士なんて不潔ですもの。でも、そうね、宮真ちゃんだったのね。ああ、シロくんを少しでも疑ってしまった自分が恥ずかしい!」
「え~っと」
宮真も一応男なんだけど、という言葉を飲み込む。どうやら彼女は宮真のことを女の子だと思っているらしい。でもまあ、仕方のないことだ。宮真は小柄で可愛らしい顔に声を持ち合わせている。言われなければ男だなんてわからない。そんな中性的なスタイルを宮真自身が楽しんでいる節すらあるのだから。
「宮真ちゃんはあれでしょ。火鋸くんが好きなんでしょ。わかるわよ、あんなんじゃ」
ま、好きならあれくらいやらないとだわね、と呆れたようにクロエはため息を吐く。そう、あの二人のことは彼女も認めている。だから、宮真に嫉妬がいくことはないはずだ。
「宮真の恋を応援することはもう随分と昔に約束してるんだ。だから、どの道僕は君の恋を応援せざるを得ないよ」
「……安心したわ。ごめんなさい。貴方に当たるような真似をしてしまって。私、どうかしてたわ。あ、でもほら、マフラー。ちゃんと直ってたでしょう?」
口元のマフラーを整えようとした手が止まる。
「ああ、君と白花が直してくれたんだったね。ありがとう」
「ええ。こちらこそ、二人きりの時間をどうも」
「言っただろう? 僕は君たちを応援してるって」
冗談交じりの彼女の言葉に、愛想笑いを浮かべて答える。
そう。僕の気持ちなんて要らないんだ。だって、僕のこの気持ちはきっと汚いものだから。
*
「留理……」
「ごめん、上に呼ばれてるんだ」
「留理、一緒に夕食……」
「ごめん、今日はもう眠いんだ」
「留理、ちょっと話を……」
「ごめん、忙しいから」
「留理、この書類って……」
「ああ、報告書なら僕が書いておくから。君は先に上がっていいよ」
「いや、手伝うけど。暇だし」
「ほんといいって」
「留理」
「だから、君は早く宿舎に……、痛ッ」
「留理」
唐突に腕を取られ、力任せに棚に押し付けられる。その強さにびっくりして白花を見る。
「ちょ、いきなり何するん……」
「留理こそ何?」
白花と目が合い、すぐに逸らす。珍しく怒りを湛えたその瞳を見続けられるほど、僕の肝は据わっていない。
クロエと話をしてから、意識的に白花のことを避けてきた。だけど、どうやらそれも限界らしい。もっと上手く避けられると思っていたんだけど……。少し露骨過ぎたようだ。
「これ、隈が出来てるけど」
詰問するような白花の声音に怖気付きそうになる。普段の白花が温厚な分、どうにも慣れない。
「あ~、ちょっと、最近寝付きが悪くて……」
目の下を指でなぞられ、身じろぐ。白花の白い瞳に自分が映る。それが何ともいたたまれなくて。
「じゃあこれは何?」
「?」
何のことかわからずに何も言えないでいると、白花は僕の手を取り擦る。
「留理、ストレス感じると手の甲を引っ掻く癖あるから」
「え……?」
意識して見ると、確かに僕の手は傷だらけだった。言われてみれば、無意識ではあったが、さっきまで手の甲に爪を食い込ませていたかもしれない。
「気づいてなかった?」
「これは……、ッ」
まじないでもかけるように、ゆっくりとねっとりと僕の手を撫で始めた白花に、心臓が跳ねる。急いで手を引っ込めようとするが……。
「逃げないで」
それを察した白花が強く僕の手を握り、口元に引き寄せ……。
「ッ!」
おとぎ話の王子様がお姫様に向かってするみたいに、手の甲に口づけを落とした。
「ね、留理さ、最近冷たくない?」
「気のせいじゃ……、ちょっと、君、何して……?」
平静を装おうとしたところで、白花の舌が手の甲を舐め始める。
「気のせい?」
「え? うん、そう。えっと、だから、君の気のせいだって……」
白花の行為にどうしていいかわからないまま、適当な返事で濁す。が。
「ね、留理」
「ひっ」
顔のすぐ横、もたれかかっていた棚に白花が勢いよく手をつく。
「何で白花って呼ばなくなったの?」
息遣いがわかるほどに近づいた白花の顔は、全く笑っていなくて……。
「それ、は……、君が、嫌だって言うから……」
「俺は留理ならいいって言ったんだけど?」
「……そんなに僕のこと、特別扱いするもんじゃないよ」
「特別扱い、か。確かに、俺は留理のこと特別扱いし過ぎかもなぁ」
そう言いながら、白花が再び手の甲を舐める。
「そ、それ止めてくれる?」
「どうして?」
「どうしてって……」
恐らく、白花は治療をしているつもりなのだろう。「唾をつけておけば治る」という古い言葉があることを僕は、最近映画の中で知った。実際には逆に菌が入ってしまう恐れがある民間療法なんだけど……。
「とにかく、ほんと大丈夫だから……」
ちろちろと未だに舐め続ける彼から目を逸らす。でも、白花はすぐにそれに気づき、僕の顎を掴み、視線を無理やり合わせる。
「留理。俺、お前になんかした?」
「そんなんじゃ、ないって……」
そんなんじゃない。そう。僕の気持ちは、要らない。この感情は間違っている。僕は、白花の良き仕事上のパートナー。その役になりきるのが僕の役目。だから、僕はクロエとの約束を果たさなくちゃ。応援するって、言ったんだから。
「あ~、僕の心配してる暇あったら、さ、その……。例えばクロエをデートに誘う、とかさ……、時間を有意義に使う方法が他に……」
「留理は全然わかってないね」
しどろもどろな下手くそアピールが終わるより前に、今度は目の下に口づけられる。
「えっ、な、なに……?! そんなことしても、隈は治らないよ……!」
「やっぱりわかってない」
「っ、やめ、やめろって……、白花ッ!」
生暖かい舌が瞼を撫で始めたところで、白花を本気で突き飛ばす。
「痛いなぁ。でもまぁ、やっと呼んでくれた。ね、留理」
「あ……」
白花の目に射抜かれて、口元に手を当てる。意識的に名前を呼ばないようにしていたというのに……。
「留理は一体何を考えてるの? ね、俺に少しくらい、いや、全部、教えてよ」
「それは……」
マフラーを掴もうとした手が強く引き寄せられて、白花の顔が一気に近づく。
「留理」
「は、白花? ちょっと、放して……」
「留理、俺は……」
「おー、白花、留理。こんなとこにおったんか!」
「「!」」
がちゃり、と突然開かれたドアの音と大声に、慌てて白花に頭突きを食らわす。
「って、大丈夫か?」
ノックなしで入ってきた火鋸が、不思議そうに僕たちを見つめる。
「痛ッ~、大丈夫じゃ、ない!」
白花は頭を抱え、唸りながら答える。
「ご、ごめん、白花……」
自分の額を擦りながら、とりあえず白花に謝る。自分がこれだけ痛いんだ。白花はもっと痛かっただろう。
「なに、喧嘩か?」
頭を擦る僕たちに向かって、火鋸が心配そうに声をかける。
「そ、そんなんじゃないけど……」
「火鋸は何か用事があったんじゃないの?」
言い澱む僕に、白花が助け舟を出す。すると火鋸はぽん、と手を打って、「あ、そうそう。上が「大事な話がある」って呼んでるから、はよ行った方がええで」と笑った。
*
生き残った人間だけで作られた組織の拠点最奥。いくつものモニターを背に、最高司令官である男は厳かに二人を迎え、重い口を開いた。
「どうやら、蟲がこの拠点にも入ってきたようだ」
「そんなまさか!」
白花の悲鳴が広い部屋に虚しく響く。白花が狼狽えるのも無理はない。この拠点は蟲が侵入しないようにと数多のセキュリティが敷かれている。それを突破する蟲が出てきたということは……。
「とにかく、今は混乱を招かないように防壁で蟲を遮断してある。だから、君たちには至急駆除に向かってもらう。勿論、皆には気づかれないよう頼む」
白花と顔を見合わせ、頷く。どうやら怖気づいている暇はないらしい。
「いやああああ! 早く、早く助けてえええ!」
「ッ……」
蟲が出たという地下食糧庫に女の悲鳴が響く。
「どうして、人がまだいるんだ……?!」
「俺に聞くなって!」
防壁のロックを解除した瞬間に僕らが見たものは、料理担当だった数人の無残な死体と、不自然に追い回されている女の姿だった。
『キチチチチチ!』
蟲は、明らかに女を甚振って遊んでいた。わざと最後の一人を生かして楽しんでいた。
「ああ! お願い、助けて! 私、死にたくない!」
僕たちの存在に気づいた女が、こちらに向かって死に物狂いで近づいてくる。
「留理、援護を頼む」
「うん。任せて!」
白花が女を飛び越え、蟲に向かって一太刀浴びせる。
『グギィ……?!』
そして、僕は蟲が起き上がるより前に、女の前に躍り出て蟲に銃弾を容赦なく叩きつける。あと少しで倒し切る。そう思ったそのとき。
「ッ、きゃあああ!」
女の悲鳴に振り返ると、その足元からぼこりと床を押し上げて、蟲が顔を覗かせていた。
「た、助け……」
女は真っ青な顔をしながら、よろよろと僕のマフラーに手を伸ばす。
「っ!」
「留理!」
ふいに白花の手が僕の首根っこを掴む。白花に引き寄せられたお陰で、女の手は空を切る。
それと同時に、白花がもう片方の手で剣を振り、衝撃波で蟲にダメージを与える。
「よかった……」
マフラーの裾を手繰り寄せ、撫でる。ああ、触られなくてよかった。また傷つけられるんじゃないかと思ったけど……、じゃなくて!
「蟲は?!」
僕の肩を抱いたままでいる白花の手を振り払って、辺りを見回す。
「今ので倒したよ」
「そう。とりあえず一安心……」
安堵の息を吐こうとしたが、女を見た瞬間、凍りつく。
「あ、あああ、痛いッ……! 助けて……ッ!」
血に塗れた女の足は、蟲に食い千切られていた。その声は、その目は、その伸ばされた血まみれの手は、僕の方に真っ直ぐ向けられていて……。
「ひっ……」
一歩後ずさり、マフラーをぎゅっと掴む。
「僕は、っう……」
己のことを優先させてしまった後悔と、女の惨状に吐き気が込み上げてくる。その隙をついて女が僕の足を掴む。耳を劈く女の悲鳴が僕を責める。でも、恐らくその怪我では、もう彼女は助からない。動けているのが不思議なくらいで……。
「っ、放し……」
「放せ」
短く吐かれた言葉と共に、ざくりと女の体に剣が突き刺さる。
「う、アアアアアアアアアア!」
さっきまでとは比べ物にならないぐらい悲痛な女の悲鳴が部屋を占める。そして、数秒もしないうちに、部屋は静寂に満たされる。
「はっ、か……」
女の体に突き刺した剣を抜き、白花がこちらを向く。その瞳が、得体のしれないものに思えて、後ずさり、蟲の死体を踏み、バランスを崩す。
「あっ……」
倒れる、と思った瞬間、手を掴まれ、引っ張られる。
「留理、大丈夫?」
白花の手が優しく僕の手を包む。握り返した白花の手は、いつも通り温かかった。それに、こちらを気遣う穏やかな声色も、透き通った白い瞳も、全部いつもと変わりなくて。
「僕は、大丈夫だけど……。この人が……」
動かなくなった女に移した視線を遮るようにして、白花が僕を抱きしめる。
「残念だけど。どの道この人は助からなかったよ。俺たちが来た時にはもう蟲の毒にやられてたし。だから、留理は気にしなくていい」
「……でも」
僕が白花の剣を汚してしまったことに違いはない。いたたまれなくなって、白花の腕から抜け出そうとする。が。
「白花?」
ふいに白花が僕の髪に口づける。その突飛な行動に一瞬呆然とするが、頭を撫でられた途端、羞恥が生まれる。そうか、白花は僕をあやしてくれているのか。僕は、責められてもおかしくないことをしたのに。白花は、僕を静かに許してくれたのだ。
「僕、かっこ悪いよな……」
「そんなことない。留理は偉いよ」
甘く囁かれた言葉に、弱い心が本音を零す。
「……僕は、本当は、嫌なんだ」
「うん。あと少し、きっと、あと少しだから。それまでは、一緒に頑張ろう?」
「……うん」
白花の胸にしがみつきながら、僕は静かに目を閉じた。一番大好きなその懐かしい香りが、初心を思い起こさせる。
大丈夫。ここで挫けるわけにはいかないだろう? 僕は、白花を守ると誓ったんだから――。
*
「いや、ありがとう白花、留理。君たちのお陰で大事にならずに済んだ」
最高司令官である男は、部下に命令を下しながら、合間に礼を述べた。
「わかっているとは思うが、この件は内密に。この件の被害者は皆、外で殺されたこととして扱うように」
「あの。蟲はどこから現れたんですか?」
白花が手を上げながら真面目に質問をする。その顔は凛々しく整っていて、未だに青白い顔をしている僕とは大違いだ。
「どうやら食糧庫の物陰に潜んでいたらしい」
それに気づいた料理番が通信を取ったが、無情にも遮断されて蟲の餌食になったのだろう。まあ、見捨ての判断が間違っていたとは言い難い。この男も全て覚悟の上で今こうして強く振る舞っているのだろう。……僕も見習いたいものだ。
「もう一つ。どうして蟲が基地内にいたんですか? セキュリティの故障ですか?」
「それは、調査中だ」
「……そうですか」
男のわずかな表情の変化を見て、確信を得る。どうやらセキュリティが故障していたわけじゃないらしい。
「留理はどう思う?」
「どうって?」
宿舎に向かいながら、白花の質問を聞き返す。
「蟲は知能を持っていないとされていた」
「うん」
「でも、どうやらセキュリティを突破することが出来たらしい」
「そうみたいだね」
「それに、討伐遠征でこの拠点が手薄になったタイミングだった」
「僕らより強い人間が残っていなかったから、僕らが駆り出された訳だもんね」
「それに、あの蟲。最後の女性を甚振って遊んでいたように見えた」
「……つまり、知能を持った蟲が現れたかもしれないってこと?」
「いや、もしくは……」
「よう、お二人! お疲れさんッ!」
「うわっ、火鋸」「お、驚かさないでくれる……?」
宿舎の玄関に辿り着いた途端、物陰からいきなり飛び出し、二人に抱きついてきた火鋸に心臓を押さえる。
「ちょっと、火鋸! 抱きつくんならボクだけにしてよ!!」
「何だよ、嫉妬か~? 可愛い奴め~」
「ボクが可愛いのは当たり前だもん!」
怒った宮真にニヤニヤしながら、火鋸が抱きつく。ほっぽり出された僕たちは顔を見合わせてから肩を竦め、談話室へと足を運ぶ。
「あれ、他の皆は?」
いつもなら深夜まで賑わっているはずのそこは、誰もいない寂しい場所になっていた。
「それが、みんな部屋に篭っちゃって」
「蟲がとうとう基地内にも出たんやろ?」
「……」
「どうやら本当みたいだね」
僕らの反応を見た宮真が、困ったように眉を顰める。どうやら、早速情報が漏れてしまっているようだ。
「ちょっとした騒ぎになってな」
「誰かが言い出したんだよ。もしかして蟲がセキュリティを解除したんじゃないかって。知能を持った蟲が現れたんじゃないかって」
「それで皆、部屋で待機してるってわけか」
「そういうこと」
皆がそう考えるのも無理はない。僕らは先日、瓦礫の中から見つけた古い映画を持ち帰り鑑賞した。それは、地球外生命体と人類が戦う内容で。図らずも今の状況に似通っていたそれは、宿舎内で連日流された。何故なら、それは人間が勝利を収めるハッピーエンドだったから。ここに寝泊まりしているそれなりの数の人間がゲン担ぎにと観たはずだ。それがよくなかったのだろう。
映画の中の地球外生命体は、見た目こそ違えど蟲のように知能がなく、ただ人間を攻撃するだけだった。が、しかし。物語が進むにつれ、彼らは進化していき、人間以上の知能を手に入れ……という設定があったのだ。映画の中では、人間が強力な兵器を完成させて倒していたが……。
現実では倒してもキリのない蟲の数に、自分たちの身を守りつつ、少しずつその生態を研究するので精いっぱいだった。
「まあ、実際、セキュリティは何者かによって解除されていたらしいんや。オレが上に問い詰めた話じゃ、セキュリティ担当者の人為的ミスやて。セキュリティが解除されたタイミングで不幸にも蟲が入ってきたんやて言い張ってたけど……」
「確かに人間だからミスはするだろうけどね……。ただ、そのセキュリティが解除されてた時間が、数秒程度だったらしいんだよ」
「ま、これは噂にしか過ぎんから何とも言えんけど。まあ皆、不審に思ったっちゅーわけや」
「なるほど。その数秒に乗じて蟲が侵入するのはいささか出来過ぎている、と」
二人の話に神妙に頷いた白花が唸りながら腕を組む。
普段ならば、生体登録されていない生物が自動ドアを通った瞬間、レーザーに焼かれて死ぬ。今迄に数匹の迷い込んできた蟲がそれで犠牲になった。
「見張りはいたんだろう?」
「セキュリティが解除されていた日、妙に眠かったらしいねん。耐え切れんで、数分の間だけ転寝したみたいや。起きてから慌てて辺りを伺ったけど、特に荒らされた形跡もなかったもんやから、黙ってたらしいで」
「その人、可哀そうに自分を責めて寝込んじゃってるんだ」
「いつもなら居眠りするような奴やないで。そこがみょ~に引っかかんねん」
「だからボクたち、睡眠薬でも入れられたんじゃないかって。蟲はこっち側にもいるんじゃないかって……」
「スパイがいる、ってことか」
「まさか。蟲と人間じゃあまりに違いすぎるよ」
白花の言葉に反論する。白花までそんな妄言に同調してしまうのは見過ごせない。
「まぁ、蟲の中にも知能を持ってて、更に人間に化けられるのがいてもおかしくないのかもしれん。それか、いつの間にか寄生して人間を操ってるかもわからんからな」
「そんな無茶苦茶なことを皆信じてるの?」
両手を前に出して幽霊のジャスチャーをしてみせた火鋸に眉を顰める。
「疑ってるんや。今ここに残ってるのは、ほとんどが弱い奴らや。もうずっと外に出てないせいで、精神も参ってる」
「皆、お互いを蟲じゃないだろうかって探り出して、それで……」
「この通り。み~んな部屋に籠っちまったんや」
確かに、大半の精鋭が討伐で不在の今、笑っていられる人間はいないだろう。
「お前らはいいのか?」
白花に問われた二人が顔を見合わせる。
「火鋸が蟲だなんてありえない」
「そうだな。オレも、お前を信じてる」
「はは。相変わらず仲がいいな~」
白花の言葉に胸が痛む。彼はどんな気持ちでいるのだろうか。その笑顔の裏にどんな痛みがあるのだろうか。僕はどうすれば彼を救えるのだろうか。
「んで、どうするんや? お前らも部屋に籠るか?」
「籠ったって意味ないだろ」
「うん。どうあれ、僕たちは戦わなきゃいけないからね。怯えてる暇なんかないさ」
「お前ららしい答えやな~」
「ボクも、戦えたらなぁ……」
「お前はここで皆を励ますんが仕事やで」
宮真の頭に火鋸の手が乗せられる。その仲睦まじい二人に、僕はどうしても複雑な感情を抱かざるを得なかった。
*
それから数日。俺たちは苦戦を強いられていた。
「駄目です! 北第一防壁、破られました!」「南第一防壁も同じくです!」
「二手に分かれて向かい撃て! 絶対に奴らを基地に近づけるな!」「ハイッ!」
今までの蟲は、手あたり次第に生き物を食べ、彷徨う存在だった。が、ここ数日で蟲たちは統率を得たように皆、基地を目指しはじめたのだ。
「シロは北ゲート。留理は南ゲートを守れとの命令や!」
「白花とは別行動なのか……」
留理が不安そうにマフラーを口元に寄せる。
「やっぱり、さ……。俺も留理と一緒になるよう、上に掛け合ってみようか……?」
「いや。ごめん。弱気になった。けど、僕なら平気」
「留理……」
ぱちりと自分の頬を叩いて見せた留理に寂しさを覚える。
「言っただろう? 戦わなきゃいけないんだよ、僕たちは。覚悟なら、とうに出来てるさ」
瑠璃色の瞳が燃えるように揺らめく。これが最後の戦いなのだと嫌でもわかってしまう。
「……無理はするなよ?」
「そっちこそ」
掲げた拳をぶつけ合い、見つめ合う。
「シロくん! お願い、行かないで! 私、どうしていいか……」
「うわ、クロエ……!」
突然抱きついてきたクロエに困っていると、留理が静かに背を向けて歩き出す。
「あ、留理、待っ……」
「シロくん! 聞いてほしいことがあるの。私、私ね。シロくんのことが――」
「ごめん、クロエ。俺、わかったかもしれない」
「わかった……?」
「うん。俺が守りたい奴が誰かってこと」
「……宮真ちゃんのこと?」
「なんで宮真?」
「だって、留理くんがそう言ったのよ」
「留理が?」
「宮真ちゃんと話してると、いつも嫉妬で睨まれるって」
「ぷ。あはは! 何それ。俺、そんなことしてたんだ?」
突然笑い出した俺に、クロエが目を丸くする。
「え、うん。なんだ、無自覚だったんだ……。私も、留理くんに熱視線を送ってたのかと思って。馬鹿みたいだけど、留理くんに嫉妬しちゃってね……」
「はは。それ、勘違いじゃないよ」
「え?」
「嫌だったんだよ。宮真と楽しそうに話す留理を見るのが。うん、確かに俺は、宮真に嫉妬してた。そうだよ、やっぱり留理は僕と一緒にいなきゃ」
「それって、もしかして……。やっぱり、シロくんは、留理くんのことが……?」
「じゃあね、クロエ。気持ちに応えられなくてごめんね」
「シロくん!」
可愛らしい少女に心の中で再び別れを告げる。そして、前を見て走り出す。留理の向かった南ゲートを目指して。
*
「これは……」
南ゲートに辿り着いた僕は息を飲み、マフラーを握りしめる。
「ルリ。君には死んで貰わねばならないんだよ」
辿り着くなり僕をずらりと囲んだ人間たちが、一斉にその銃口を僕に向ける。
ゲート付近には、たくさんの蟲たちの死骸が転がっていた。
「さるお方のお陰で、対蟲兵器がようやく完成してねぇ。この通り、どんな蟲でもイチコロだ」
なるほど。映画が現実になったというわけか。
「君のもう一人のお仲間も、今頃は駆逐されていることだろう」
「そう、ですか」
それならば、僕はもういいのだろうか。
だらりと腕の力を抜き、銃を落とす。
「ふん、諦めたか。殊勝な心掛けだな。総員撃てェ!」
目を瞑る。最後に思い浮かべるのは、勿論白花の姿。ああ、どうか、白花が無事でありますように。この先、幸せに暮らせますように――。
「留理、逃げろっ!」
「は……?!」
聞きなれた声に目を開ける。銃弾が放たれるより前に、白花が目の前に躍り出る。
どうして、ここに白花がいるんだ! やめろ! やめてくれ! このままじゃ、白花が死ぬ。僕の代わりに。そんなの、いけない。意味がない。やめろ、やめろ……。
「やめろオオオオオオオ!」
どっ。一陣の風が吹く。それは、瞬く間に全てを宙に巻き上げて……。
「る、り……?」
振り返った白花と目が合い、我に返る。それと同時に、巻き上げた者たちが支えを失い、地面に叩きつけられて……。
ぐしゃり。悲鳴と共に、嫌な音がして人間たちは動かなくなる。
「あ……。ちが、僕は、こんなこと、するつもりじゃ、なくて……」
白花の見開かれた瞳に映る自分の翅を見て、口を噤む。もう駄目だ。こんな言い訳したって、意味がない。
ぐっと手の甲に爪を食い込ませて、目を瞑る。そして、覚悟を決めて白花を睨む。
ばさり。背中の翅を震わせて、人間たちの屍の山に舞い降りる。それは、紛れもなく蟲の翅だ。
「あーあ。きっと火鋸だよね。人間たちに入れ知恵したのは。早く殺しとけば良かったなぁ」
「留理、本当にお前は……」
「見てわかるでしょう? 僕は人間じゃない。そう、君たちが恐れる蟲なんだ」
「騙していたのか」
「そ。宮真と一緒にね。白花は本当に馬鹿だね。わざわざ敵を庇っちゃうなんてさ」
「それは……」
「今頃はきっと基地内も大変なことになってるかもね。対蟲兵器って言ったって、撃たれる前に人間を殺しちゃえばいいんだからさ。宮真だって僕と同じように生きてるかも。本来の宮真は僕と違って気性が荒いからね。早くしないとみんな死んじゃうかもしれないよ?」
「……」
「火鋸も、クロエも、みーんなぐちゃぐちゃになって幼虫たちの美味しいご飯になってるかも」
「それは……」
「なんなら僕も加勢に行こうか? こいつらみたいにさ、一瞬でさ、楽にしてあげられるよ」
僕が地面に向かって指をさすと、白花が顔を青くする。僕が乗った屍の山は、少しずつ幼虫たちに食い荒らされ始めていた。
「うっ……」
白花が口に手を当て、目を逸らす。無理もない。幼虫が人間を貪る姿なんて、僕でさえ見ていて気持ちが悪い。
「みんな良かったねぇ。いっぱい食べて早く大きくなるんだよ。……アレかい? お兄ちゃんが殺してあげるから。待っててごらん」
「留理、何言って……」
食べ盛りの幼虫たちの催促を律してから、白花に向かって微笑んでみせる。
「白花、君は僕たちにとって、餌でしかないんだ、ごめんね!」
「っ……!」
地面に落ちた愛銃を拾い上げ、白花に向かって撃つ。白花はそれを剣で防ぎ、後ろに飛びのく。飛びのいた地面には、間髪入れずに銃弾が注がれる。
「ほらほら、防いでばっかじゃ仲間は助けらんないよ。僕を殺して助けに行かなきゃ」
「俺は!」
白花が振るった剣は、次々に銃弾を弾き返してゆく。いくら人の動きを補助する機能がついているとはいえ、その動きは人並み外れている。全く人間にしておくのが勿体ない。
「留理が!」
素早い動きで目の前に躍り出た白花に標準を合わせる。距離を、取らなければ……。そう思い、翅を広げた瞬間、白花の足が砂を蹴る。
「!」
一瞬だけ視界が砂埃に覆われる。その隙を突いて放たれた白花の蹴りが銃を地面に弾き飛ばす。
「チッ」
すぐさま腰からナイフを抜き、剣戟を受け止める。そして、後ろに飛び退き立て直そうとする。が。
「あっ!」
白花に掴まれ、首から解けかけたマフラーに手を伸ばす。その無意識の行動に、マズイと思った瞬間……。
手を強く引かれ、白花に倒れ込む。かと思うと、すぐさまぐるりと視界が回る。
「痛っ……」
地面に後頭部をぶつけた痛みに、目を閉じる。そして、次に目を開けたときには。
「っ……」
喉に剣を突きつけられていた。
はらり、と真横に落とされたマフラーに手を伸ばす。掴んだ瞬間、心のざわめきが幾分かマシになる。
「やっぱり、俺は留理が悪なんて信じられないな」
僕の喉から剣を退かした白花が肩を竦める。
「……何を今更」
ゆっくりと身を起こし、白花に吐き捨てる。そう、今更だ。僕が悪でないはずがない。
「これ、こんなに大事にしてるのに?」
「別に、そんなことは……。あッ」
口に寄せたマフラーを白花が掴む。そして、冷めた目でマフラーに剣をあてがう。
「じゃあ、今ここで引き裂こうか?」
「っ……」
「ははっ。嘘だよ。俺は留理を殺せないし、留理の嫌がることなんかしたくない」
「お友達だから? 優しいもんだね」
「そんなんじゃあないよ」
「え?」
いつもより低く、闇を含んだ声音が耳朶を打つ。白花の悲しそうに微笑んだ瞳から目を逸らせない。
「留理、俺は優しくない」
「っ!」
白花の手が、突然翅を撫でる。他人に触らせたことのないそこを白花の指が滑る度に、ぞわぞわとした恐怖を覚える。
「綺麗な翅。ね、これ千切ったら、留理はずっと俺といてくれる?」
「……やれるもんなら、やってみなよ」
恐らく今、僕の声は震えているのだろう。だって、こんな薄い翅、白花の剣で裂けば一発だ。だけど、それは決して怖いだけじゃない。……望んでいたことでもある。
「怖がらないでくれよ、留理。俺はそんなこと、やれないよ。ごめんね。やっぱり俺は留理を傷つけられない」
白花は謝った。僕を傷つけられないことを。まさか、気づいているのだろうか。
「僕はお前を騙してたんだ。僕はもう何人もの人間を殺して……ッ」
白花の手が、今度は僕の頬を撫で始める。その手つきが酷く優しいことに気づいて、唇を噛む。
「留理が蟲も人も殺したくないと思ってることはわかってる」
「馬鹿だな。そんなわけ……」
「留理」
「僕は蟲だから、人間を殺すのは当たり前で……」
「じゃあやってみなよ。なんなら俺を食べたっていい」
「……後悔するなよ」
手を広げ、目を瞑る彼にナイフを翳す。胸をひと突きするだけで、僕は蟲としての暮らしに戻れるのだろう。だけど。
「っ……」
「ほらできない」
「僕をそんな目で見るな」
「ほら、ここをひと突きすれば終わるでしょ?」
白花は、僕の震える手を自分の心臓に誘導する。それだけで、呼吸が苦しくなる。
「僕は……」
「留理」
「僕はッ……!」
白花の瞳から目を逸らし、自分の胸に向かってナイフを突き立てる。が。
「止めるなっ! 僕はっ……!」
「人魚姫にでもなったつもり? 泡になって消えるなんて終わり方、俺は許さないよ?」
ナイフが刺さる寸前で僕の手を掴んで止めた白花が、僕に向かって微笑む。その目は勿論笑っていない。気づいているのだ。僕が死にたがっていることを。
「なんだよ、それ。訳わかんないこと言うな」
「ああ、留理は知らないのか人魚姫。まあ、知らなくていいよ。あんな悲しいお話で君の心を傷つけたくないからね」
馬鹿みたいな力で手からナイフを奪われる。蟲といっても、僕は中途半端だ。成虫になってからずっと人間に擬態していたこともあり、本来の姿に戻れやしない。出来て、今みたいに翅を出す程度だ。風を起こす力だって、連続では使えない。つまり、僕は弱い。銃抜きで平均的に見ると、幼虫たちよりも弱いかもしれない。
「君は、僕を何だと思ってるんだ……」
「俺のパートナーだろ?」
「いつまで幻を信じているつもりだ? 君の良き友である留理はもういない。今、お前の目の前にいるのは、人類の敵である蟲で……」
「留理、一人でそんなに背負い込むな」
「は?」
白花が僕を抱き寄せる。その温かさに今までの日々が蘇り、終わらせたくないという愚かな我儘が胸を焼く。
「留理が死にたがってるのだって、わかってるさ。でもさせない」
「っ?」
白花の言葉と、その鋭い瞳にぞくりとして、ボロボロになったマフラーを握りしめる。間違えるな。僕は、これさえあれば平気なんだ。だから……。
「そんなにマフラー大事にしてさ、ほんと、可愛いよ。でも……」
「え……、あっ」
「もうこんなもの、要らないだろ? 俺がここにいるんだからさ」
「は?」
白花に取られたマフラーが剣で引き裂かれるのを呆然と見つめる。
「なんで……。さっきは、嫌がることしないって……」
「うん。ごめんね。でもさ、何だかマフラーにまで嫉妬しちゃって。……ねえ留理。俺があげたマフラー、何でこんなに大事にしててくれたの?」
「え、あ……。いつから、気づいて……」
「やっぱり。あの時の虫は留理だったんだね」
「!」
誘導されたことに気づき、唇を噛む。それを見て、白花は微笑む。
「最初は全然気づかなかったよ。それどころか、あの時、虫に会ったことさえ忘れてた。でも、マフラーに見覚えがあってさ。あんまり留理が大事そうにしてるもんだから……。じわじわと思い出して……。もしかしたら、そうじゃないかって。カマを掛けてみたんだよ」
更にマフラーを引き裂きながら、白花は言葉を続ける。
「もし、留理があのときの虫なら、蟲たちの仲間だったら、どうすればいいかわかんなかった。でも、さ。マフラー大事にしてくれてんの見てたら、悪い奴じゃないだろうなって思ってさ。黙ってたんだよ。てか、それどころか可愛く思えてきちゃって」
「なに、言って……」
白花に手を取られ、手の甲に爪を食い込ませていたことに気づく。
「留理はどうしてまた僕の前に現れたの?」
「それは……」
地面に転がった無残な姿のマフラーに目を落とし、考える。
僕は、どうするのが正解なんだろう。どうすれば、白花は傷つかないだろう。
どんっ、と鈍い地響きがして、基地から煙が上がる。そうだ、もうそんなことを考えている段階ではないのだ。
「始まっちゃったね」
「僕たちも、始めよう。これは、戦争だ。人か蟲。どちらが生きるかの競争なんだ。無駄な考えは要らない」
「そうだね。全く留理が正しいよ」
マフラーだったものを踏みにじってから白花が笑う。
ああ。そうだ。僕が甘かったんだ。僕はあのマフラーを手にする資格すらないのに。それをお守りみたいに縋って。僕のこういう弱さがなければ、気づかれることもなかったのに。
「そう。無駄なことはもう、考えないでいいんだ……」
疲れ切った頭は、考えることを辞める。計画通りにやればいい。大丈夫。僕は今までこの時のためにやってきたんじゃないか……。
白花が静かに身を離し、地面に落とした銃とナイフを拾い上げ、僕に渡す。
「本当に、いいんだね? 留理」
「うん。どうせなら、本気でやろう。僕たちができることは、もう殺し合うことだけなんだからさ」
ナイフを仕舞い、愛銃を優しく撫でる。コイツを使うのももうこれで最後だ。
どっ、と再びどこかから爆発音が聞こえてくる。
それを合図に、白花が剣を振り上げ、こちらに突っ込んでくる。僕は翅をはばたかせて後方に下がり、白花に向かって銃弾を放つ。
避け、弾き、薙ぎはらう。互いに譲らない本気の戦いに汗が滲む。白花は本当に強くなったものだ。
*
十数年前の話。幼虫の中でも特に弱かった僕は、実験体だと言わんばかりに僕らの星から遠い未踏の星……地球に落とされた。
幼く弱い僕は怖かった。とても人間を食らおうとは思えなかった。逆に殺されてしまいそうだった。
町を行き交うたくさんの人間が怖くて。冷たい雪が降り注ぐ中、僕はずっと隠れてた。
そうやって、このままひっそりと死ぬんだと思うと、すごく惨めで情けなくて、寂しかった。
そんなある日。僕は人間の子どもに見つかってしまった。そのときの僕は、お腹が空き過ぎて、一人が寂し過ぎて、寒さでどうしようもなくなって、公園の茂みの草を一生懸命食んでいた。草なんて、食べれやしない癖に。
「わ、なんだこのでっかい芋虫……!」
『ぴぎゃ……』
茂みを掻きわけて近づいてくる少年に、逃げることもできない僕は、その場に丸まって震えた。
「怖がってんの? 俺、怖くないよ?」
『ぎゃ……』
恐る恐る目を開くと、少年がこちらに向かって微笑んでいた。
「俺ね、今かくれんぼ中。お前もかくれんぼしてんの?」
『ぴぃ……』
少年の手がそっと近づいてくる。僕は、怖くて、やっぱり逃げられなくて、ぎゅっと目を瞑る。
「俺ね、虫好きだからお前も好きだよ。お前の目、瑠璃アゲハみたいで綺麗だな」
『ぴぎゃ……?』
赤子をあやすように穏やかな声音と、優しく背中を撫でる手が、あまりに不思議で首を傾げる。それに。
ルリアゲハ……。確か、この星の虫の名前……。綺麗……。この星の誉め言葉……。
久々に自分に向けられた言葉を口の中で転がすと、何だかこそばゆい気持ちがした。
「白花~!」
「げ、母さんだ。俺の名前、呼ぶなって言ってんのに!」
女性の声がして、少年が悪態を吐く。少年の母親。それが、こちらに向かって駆けてくるのを察知して、体が再び震え出す。
「ああ、怖いよな……。母さんに見つからない方がいい。母さんは、虫が嫌いだから。今も、そのことで喧嘩中」
『ぴっ……?』
ふいに、少年は巻いていた蒼いマフラーを外し、僕の体に被せた。
「お前が見つかる訳にはいかないもんな。俺、出ていくよ。喧嘩上等だ」
そう言って笑った少年が、僕の頭をぽんぽんと優しく撫でる。
「お前も、誰かに見つからないうちに、早く帰るんだぞ」
『ぴぎゅ……』
「白花~!」
「あ~。ハイハイ。ここにいるってば!」
少年が、茂みを出て母親の前に姿を現す。
「白花、なんかいたの?」
「ううん。何も。てか、俺が飼ってたカブトムシ、母さんが勝手に逃がしたこと、まだ怒ってるんだけど?」
「だって、あんなのゴキブリと同じじゃない! 全く、これだから男の子は嫌なのよ」
「なんだよ。いつもそればっかだ……」
「なあに? 声が小さくて聞こえないわ。白花、そんなとこだけ女の子らしくしないでちょうだい」
「ハイハイ。だったら存分にヤンチャな男の子でいてやるよ、クソババア!」
「白花!」
母親に向かってあっかんべーをしてみせた白花が、素早く駆けだす。それを見て、母親は怒鳴り声をあげて追いかける。
ようやく静けさを取り戻した公園で、僕はマフラーの温かさに目を瞑る。顔を擦りつけると、少年の匂いがして安心する。
僕はきっと帰れない。帰る場所などどこにもない。
だけど。もう少しだけこの星で生きていきたいと思った。
あの、神様みたいな少年に、もう一度だけ会って、ちゃんとお礼を言いたかった。
優しくて、眩しくて、死しかなかった僕に光をくれた彼に、成虫になった姿を見て欲しかった。だって、成虫になった翅は、ルリアゲハよりもずっと綺麗だから。
それから、僕は頑張った。どうにか人間を食べて、寒い冬を越えて。数年を経て、僕は自力で成虫になった。
そうして早速、僕は少年にこの姿を見てもらおうと人間に擬態して、町中を探し回った。けれど、残念ながら少年は見つけられなかった。
僕の星のお偉いさんは、僕が成虫になったのを知ると、地球に数匹の幼虫たちを送り込んできた。そして、僕はその幼虫たちを育てる役を命じられた。
僕は、命じられるがままに、しばらく地球で幼虫たちを育てた。人間を狩り、彼らに与え。狩り方を教えた。そうすると、幼虫たちはみるみる内に立派に成長していった。
そしてついに、全ての幼虫が地球に送られることになった。地球は僕の星に、格好の狩場だと認識されてしまったのだ。
別に、地球がどうなったって僕は一向にかまわない。が、どうしてもあの少年だけは助けたかった。あの少年が食われるのだけは、何としても阻止したかった。
だから、僕はもう一度彼を探した。そして、見つけた。
彼は、遠い町に引っ越していた。高校の制服に身を包んだ彼は、可愛い女の子と並んで歩いていた。笑い合う二人の指に同じ指輪がはまっていることに気づく。人間の番がそういう風に同じものを身につけることは知っていた。
僕は、気づいたらしゃがみ込んでいた。息が苦しくて、心臓が痛くて。ぽたぽたと地面が濡れてゆく。僕たち蟲が感情で涙を流すなんてあり得ない。それなのに……、どうやら僕は、人間に擬態し過ぎたらしい。お蔭で、蟲の姿に戻れやしない。翅を出すのが精いっぱいだ。
異常種。そんな言葉が頭を過る。
僕たち蟲は、主に上位種と普通種に分けられる。
上位種は、蟲全体を管理する役目を担うお偉いさん。血で決まっているその数匹は、蟲の未来を見据えた策を練り、普通種に命令をする。その数は全体の一パーセントにも満たない。
普通種は、ただの虫と変わらない。本能に従い、食い、育ち、子孫を残す。それだけのために生きている。そこに余計な感情や思考はない。
そして、それらに当てはまらない者も僅かに存在する。
それが異常種だ。
本能に逆らう者、本能に従えない者。それらが皮肉を込めて異常種と呼ばれていた。
僕もそう。
僕の場合は、上手く餌が食べられなくて。力が弱くて。あっという間に異常種のレッテルを貼られて実験体に使われた。
でも、それはあながち間違いではなかったのかもしれない。
僕はこの星での指導者としての権限を利用して、幼虫たちに彼を殺さないよう指令を出した。
僕は気づいていた。自分が異常であることに。だけど、どうしたって彼を守りたいという気持ちが変えられなかった。例え、彼に会えなくとも、彼に忘れられていようとも、自己満足として彼を助けたかった。
だけど、幼虫たちを一斉に放ってからしばらく。命令を無視して彼に近づく幼虫がいた。
幼虫は、初めて餌を大量に食べ、興奮しているようだった。
「嫌だ! 俺は、俺はッ! こんなところでくたばりたくないッ……!」
咄嗟に落ちていたコンパスを投げ、幼虫を彼の腕から退かす。幼虫に食まれた彼の腕は、服が溶け、皮膚が少し爛れていた。
それを見た瞬間、ふつふつと怒りが沸き起こり、気づいたらモップで幼虫を潰していた。
ああ、やってしまった……。仲間を殺してしまうなんて。本当に異常だ。でも、彼が守れたんだ。なんでもいい。
動かなくなったそれを凝視している彼に、手を差し出す。
「な、に……」
「怖がらなくていい。僕もここの生徒だから」
僕は、口元のマフラーを手で押さえ、彼を安心させるように微笑んだ。
彼を真似て全く同じ格好に擬態したのが良かったのだろう。彼は、僕の服装を見て、安堵の息を吐いた。
「なん、だよ、もう俺だけかと思った。生きてる人間がさ。ああ、良かった……」
「僕も、君が無事で良かった」
本当に。間に合ってよかった。
「ん、もしかして俺のこと知ってる?」
……知っているに決まっている。君は僕の恩人なんだから。一生忘れない。
「まぁ。君、モテるから有名だし」
適当にお茶を濁す。彼がモテるというのは間違いではないだろう。なんせ、あの子は人間の中でも特に可愛い子だった。ああいう上玉を選べるのは、やはりそれに相応しい位置にいる人間だ。
「……とりあえず、一緒に逃げよう」
「逃げるって、どこへ」
「これ」
ポケットから端末を取り出した僕は、座り込んだまま動かない彼に画面を見せる。
元々、人間に擬態して、生き残った人間を吟味する役も命じられている。
だったら、彼の安全を確保するまで彼の隣にいても大丈夫だろう。
そうこじつけて自分を納得させ、僕は彼の相棒として振る舞った。
幸せだった。好きな人と話すのがこんなに楽しいだなんて。知らなかった。ずっとこのまま彼の味方として人間を演じていたかった。
だけど。彼があの“悍ましき日”のことを思い出し、顔を青くする度、僕の心は悲鳴を上げた。
いつまでも騙せない! 彼は蟲が嫌いだ! この気持ちをこれ以上強めてはいけない! 終わりはそう遠くない内にやってくる! 嫌われるのは嫌だ! でも、どんどん好きになってゆく……! いや、僕の気持ちなんてどうでもいい! 重要なのは彼を救うこと、その一点のみだ……。無駄なことは要らないのに……。
「最低だな、俺」
青い顔をした彼の呟きに、聞こえないフリをして歩く。
無意識なのだろうか。彼は左の薬指を撫でながら虚ろな目をしていた。
恐らく、彼女のことを後悔しているのだろう。
本当はあの日、僕は魔物に腕を振るう彼の手から指輪が落ちたことに気づいた。けど、教えなかった。
最低なのは僕だ。
既に彼女が蟲に食われていたことに安堵したし、そのまま彼が、彼女のことなど忘れてしまえばいいと思った。愛の証とされる指輪が無ければ、忘れてくれるだろうと思った。だから、言わなかった。
でも、彼は新たに恋をした。よりにもよって、僕と同じ蟲である宮真に。
止めようと思った。そんな意味のない恋をしてほしくなかった。僕みたいに異常であってほしくなかった。彼には、人間として真っ当な恋をしてほしかった。
宮真は、どうやら白花の気持ちに気づいているようだった。そして、僕の気持ちにも。
宮真は、どういう訳か火鋸を偉く気に入っていて、恋愛ごっこにうつつを抜かしていた。
異常種と呼ばれるだけある。
そう自分と同じ括りにしていたが、後に思い直した。
きっと、宮真は火鋸が普通の人間でないことに気づいていたのだろう。だから、傍で監視していたのだろう。
火鋸は、人間にしてはどこか不自然だ。ふとした瞬間、人間離れした妙に強い力の気配を感じることがあるのだ。それも、宮真よりも強い力を。
だったら、と思った。
僕をここに送った上位種たちより、宮真よりも、僕の願いを叶えてくれるかもしれないと思った。
*
「……どうして」
掠れた声で呟いてから、うじゃうじゃと寄ってくる幼虫たちから白花を庇う。
「どうして、お前たちは僕の言うことを聞かない!」
血走った目で同胞を睨みつけ、叫びながら銃で撃つ。
僕ら二人の勝負は真剣だった。互いに譲らない攻防を楽しみさえしていた。でも、やはり僕より白花の方が少し強かった。
それは“悍ましき日”から白花が目を見張るほどの成長を遂げたから。それと。
僕の体はもう限界だったから。
僕が蟲の姿になれないのは、長いこと人間に「擬態」し過ぎたせいだ。
もっと言うと、成虫になって以来、「人間の血を全く吸わずに生きてきた」せいだ。
普通、成虫になった蟲は生き物の血を吸い、生きてゆく。でも、僕はそれをしなかった。その必要がないと思っていたから。
最初、僕はただ白花に翅を見せて、あの時のお礼を告げて、ひっそりと死ぬつもりだった。
弱い僕が成虫になれたことだけで、もう十分だった。だから、上位種への報告もするつもりはなかった。
でも、彼らは僕に気づき、この星の価値に気づいてしまった。
そこからは、白花を守るために人間擬態をより心掛けた。確かに、力は大分弱まったが、それでも……。
「白花は殺させやしない……」
銃を手に、幼虫たちを白花から引き剥がす。
せっかく終わるところだったのに。せっかく、死ねるところだったのに……!
幼虫たちは、僕らの戦いに割って入り、白花を襲い始めた。
勿論、僕は幼虫たちを殺した。けど、あまりにも数が多過ぎる。白花も幼虫たちを躱すのがやっとのようで……。
このままだとマズイ。
汗を拭い、手の甲を爪で掻く。またやってしまったが、無論今は白花も説教どころではない。
「ッ、くそ、離れろ……!」
「白花!」
白花の腕にくっついた幼虫を剥ぎ取り、白花に覆い被さる。尚も襲い掛かってくる幼虫が体当たりしてくる度、歯を食いしばる。
「留理、やめろ! お前が死んだら意味がない!」
「ふ、はは。やっぱり白花は優しいなぁ……。本当は、死ぬまで吸わないつもりだったけど……。そんなこと、言ってられないよね」
「留理?」
「……ごめん。でも、最後にもう少しだけ守らせて」
「……ッ!」
白花の首筋に牙を突き立てる。成虫になって初めて味わうそれは、本当に美味しくて。気づけば、白花が気絶するまで飲んでしまっていた。
「ああ、でも……。これは……。力が……、溢れる!」
抑えきれない破壊衝動を幼虫に向ける。羽ばたかせた翅から無数の針が飛び、幼虫たちを串刺しにする。
『ギシャアア!』
生き残った幼虫が仲間を呼び出す。ボコボコと土から出てきた幼虫たちで、再び辺りが埋め尽くされる。
「好都合だ。せめてこの力が持つ限り、蟲の数を減らすつもりだからね。裏切り者? 何とでも言いなよ。僕は、白花さえ無事ならなんでもいいんだ……!」
幼虫たちからの罵詈雑言を聞き流し、次々とその体を貫いてゆく。
その返り血でいくら汚れようが、もう構わない。あのマフラーのことを気にする必要もないのだから。
「……終わった、か」
静まり返った辺り一面に、積み重なる死骸。それらから目を逸らし、息を吐く。どうやら、増援ももうないらしい。それに、遠くで響く爆音も次第に小さくなっている。
「あっちも、決着がついたころかな」
宮真は、無事だろうか。いや、僕にとって……白花にとっては彼が無事でない方がいい。
「白花……。血、吸ってごめんね……。今まで、付き纏ってごめんね……。でもね、もう大丈夫だから。だから、最後に、少しだけ……」
横たわる彼の手を握りしめ、目を閉じる。温かい。僕は、この温もりに救われた。
「やっぱり、好きだなぁ……。ごめんね……」
白花の手を引き寄せて、額に押し当てる。
ああ、このままずっと時が止まればいいのに。
「なんて。許されるわけ、ないのにね」
白花の手に落ちてしまった涙を袖で拭ってから、自分の目元も拭う。そして、地面に落ちていたマフラーの端っこを拾い上げ、額に押し当ててからそっとポケットに仕舞う。
「ごめん……。もう少しだけ……、これに縋らせて……」
*
幼虫たちが蠢く基地の宿舎。ボクはついに火鋸と対峙する。
「さて、宮真。なんか言い訳したいっちゅうんなら、聞くで?」
火鋸は顔色一つ変えずに、いつもと変わらない軽い口調で聞いた。やはり、ボクの正体に気づいていたらしい。
「この状況で言い訳したとして、キミはボクを許してくれるのかな?」
ばさり、と翅を広げ、火鋸を威嚇する。今のボクは蟲そのもの。だというのに、火鋸は迷わずボクを宮真と呼んだ。
「わかってんなら、降参することをお勧めするわ」
「降参しても、殺すんでしょ?」
「当たり前や。お前のような危険な蟲を生かしておくわけないやろ。仕損じたらオレが上に怒られるわ」
「あんなに恋人ごっこしてたのに、ボクを殺そうって言うの……?」
「ああ。それがオレの使命だからな」
可愛い子ぶった声を出して演技した僕に反応もせず、火鋸は冷めた声でただそう返す。
「……つまらない」
心の底からそんな言葉が這い上がってくる。
「人間の味方なんかして、何になるのさ! 弱い生命体がボクらに食われるのは当たり前だ! それなのに、どうしてキミは……」
「オレの星がお前ら蟲を良く思ってないからだ」
「……はは、やっぱり火鋸は人間じゃないんだ」
「何を今更」
火鋸の冷めた声に唇を噛む。
何を今更。そんなこと、ボクだって自分に言いたい。どうしてボクは今、そんなわかりきったことを呟いたのだろうか。どうして、火鋸が人間だったら良かったのに、なんて……。
「それで。どうするか決めたんか? 降参して苦しまずに死ぬのと、抵抗してたっぷり苦しんで死ぬのと」
「……るさい」
「なんて?」
「うるさい! 火鋸一人で何ができるのさ! まさか、このボクが簡単に殺されるとでも? ハッ、冗談……」
「出来る。オレ一人で充分だ」
「は?」
『ギシャアアアアアア!』
ぼっ、と火鋸の手から放たれた炎が、宿舎の人間を食らっていた幼虫たちを燃やす。その炎は、一瞬でそこにいた幼虫全てを灰に変えた。
「わかっただろ?」
「嘘だ……」
「まだ信じない、か。じゃあ、これでどうだ?」
「え……?」
火鋸が軽々と炎を放る。それは、避ける間もなくボクの左の翅に灯り……。
「あ、アアアアアアアア! 翅、がッ……! や、熱い、は、あ……、ひっ……」
いくら羽ばたいても、地面に擦りつけても炎は消えない。翅が焦げつく臭いに怖くなって、意味もなくくるくると空を飛び回る。
「……あ、落ちる」
「え……、うぐっ!」
火鋸の呟きと共に、体が落下する。左の翅が、燃え尽きたのだ。
「ッ、うう……」
そんな、わけない……。
左の翅を動かそうと力を籠めるが、動くのは右だけ。片方だけ羽ばたかせても、体は空に上がれない。
どうして……。蟲の翅は見た目よりも頑丈で、ボクの翅なら炎にも耐えられるはずなのに……。
「オレらが使う炎は特別強い。もうわかるだろ?」
「ひっ」
地面に這いつくばるボクに火鋸が近づく。そして、左の少し焼け残った翅の淵をわからせるように、そっと指でなぞってゆく。
ああ、こんなに、燃えてしまったのか……。これじゃあ、ボクはもう……。
「どうして、ボクが、こんな……。これでも、ボクは、強い、はず、だったのに……」
幼虫だった頃、ボクはこの地球とよく似た星に落とされ、同胞たちと共にそこにいる生命体を食い荒らした。
ボクはよく食べ、よく眠り……周りの仲間より強い個体に育った。
食べた分だけ、ボクはこの餌たちのことが気になっていった。
彼らは、やはり地球の人間とよく似ていた。彼らが他人を助け、自らを犠牲にするような場面を幾度となく見てきた。どうしてそんなことをするのか不思議でならなかった。
子を産み終わっていない番や子を守る行動は蟲もする。だが、それ以外は身を挺して助ける意味はない。
もっと不思議なのは、歪な番がいることだった。
少数ではあったけれど、同性個体や様々な理由で生殖機能がない個体、まだ育ち切っていない個体、明らかに弱い個体などを番として選んでいる者がいて、どうやらその星ではそれが公に認められているらしかった。
その星の者は、愛という言葉を多く口にした。
ボクは、それが必ずしも生殖を目的としない言葉だということに気づき、どうしてだかもっとよく知りたくなった。
愛とは一体なんなのか。
気づいたら、ボクは餌を食べる片手間に、その星の本や映像を調べ、感情を学んでいた。
そして。
成虫になったボクは、地球での任務に立候補した。
ボクは異端と言われる趣向や行動のため、煙たがられてはいたものの、能力としては最高レベル。上位種たちもボクの任務参加を渋々承諾してくれた。
地球は蟲たちにとって重要な拠点だ。
最近になって食い荒らすだけでは駄目だと気づいた上位種たちは、ある程度まで地球人を減らした後、生き残った強い遺伝子を持つ人間をクローン栽培すると決めていた。
なんでも、この星の人間と増殖技術は相性が良かったらしく、上はこの星を幼虫たちの餌場として永久に使うつもりだ。
蟲の歴史を揺るがすほど重要なミッション。上も少しでも戦力が欲しいところだろう。
勿論、ボクが立候補したのはそれに貢献したいなどという崇高な考えがあってのことではない。
ただ、知りたかったのだ。この星で。愛を。
あの星に似ているこの地球ならば、その答えが見つかると思った。人間に擬態しての任務ならば、尚更理解できるのではないかと思った。
そして。その結果が、これだ。
「諦めろ。アンタには死しか残されてない」
「……さっきから、喋り方、違うじゃないか」
「ああ、あれな。一番親しみやすい喋り方やったやろ? これ、中々好きやったんやけどな。あ~、名残惜しいわぁ」
白々しい声音を聞きながら、恋愛ごっこを思い出す。
わかった気になっていた。ボクにも愛することができるのだと、夢に浸っていた。
本当のことを言うと、ボクは最近まで火鋸が人間じゃないなんて、気づいてもなかった。
恋は盲目。よく言ったものだ。ただただ恋愛ごっこが楽しくて。気づかないふりをしていたのかもしれない。
「ねえ、火鋸……。ボクは、キミが好きなんだ……。キミに殺されたくなんかないよ……」
「アンタのそんな言葉、信じられるわけないだろ。どうせオレのことも、最後には殺すつもりだったんだろ?」
「それは……」
あれ。ボクはどうするつもりだったんだっけ。確かに、最初は恋愛ごっこを楽しんだ後、情緒たっぷりに殺すつもりだった。でも……。
「まあ、どっちでもいい。オレはアンタを殺すだけだ」
ボクの名前も呼ばなくなった火鋸が軽く頭を振るい、髪を掻き上げる。
露わになったその瞳は紅く、彼の使った炎のように妖しく、鋭く、悍ましい。
「はは……。初めて見た……。それ、ずっと、見たかったんだよ……」
ああ、綺麗だ。流石、ボクが惚れただけある。
殺されたくない、なんて言ったけど。彼に殺されるのも悪くない。
「火鋸に、なら、殺されても、いいや……」
「……どうして、笑う? それは、どういう感情だ?」
「……さあ。わかんない!」
ああ、留理。ごめん。キミには散々素直になれと言ったけど。今ならわかるかもしれない。キミがその想いを伝えなかった訳が。
ああ、苦しいな……。どうしてボクは蟲に生まれたんだろう。
ああ、人間ごっこをしていたあの頃に戻りたいな……。
ああ、愛なんてもの、知らない方がよかったのかな……。
*
「ああ……。宮真、死んじゃったんだね……」
背負っていた白花を丁寧に地面に降ろしてから、宮真に近づく。
うつ伏せに倒れた宮真の翅は、片方が見事に焦げていた。
「お前、白花を殺したんか?」
傍で佇んでいた火鋸の問いに、静かに首を振る。
「気を失ってるだけ。だから、火鋸に守ってほしい」
「蟲」
「……」
「アンタは蟲やろ?」
火鋸の冷たい声に頷く。そして、頭を下げる。
「どうか白花を、助けてやってほしい」
「何か、企んどるんか?」
「何も。ただ、火鋸に頼めば、きっと守ってくれると思ってたから……」
「じゃあアンタにはここで死んでもらおか。そしたら白花は助かる」
「……わかった」
手に炎を灯した火鋸を見て、目を閉じる。宮真でさえ死んだんだ。きっと、僕は跡形も残らないだろう。
でも。それでいい。それの方がいい。
「何か仕掛けてあるんか? ……まぁいいか。こっちも、蟲は始末せぇ言われてるんでねッ!」
ポケットの中でマフラーの切れ端を握りしめる。
さよなら、白花。
どっ。
炎の熱が顔に迫る。熱い。けど、これで――。
「やめろッ!」
「え……?」
白花の声がして、体が横に飛ぶ。炎が当たる直前で、目覚めた白花が僕に体当たりをしてきたのだ。
「何考えてんだ! この馬鹿!」
「はっ、か……?」
僕に跨ったままの白花に怒鳴られ、胸倉を掴まれる。
「おい。馬鹿はお前や、シロ。コイツは蟲や。お前たちの敵やぞ?」
「違う。留理は違う」
「あのなあ。どこが違うんや。寝惚けとるんか?」
「留理は、俺を守ってくれた。確かに留理は蟲だけど、俺の大事な人なんだ」
大事な人。そう言われて、思わずマフラーの切れ端を握りしめる。
「お前……。コイツに洗脳でもされたんか?」
「そんなわけ――」
「よくわかったね、火鋸」
白花が何か言い出す前に、先手を打って嘘を吐く。
「おい。ふざけるなよ、留理……!」
「蟲の常套手段だよ。吸血した際に対象の感情を乱すことが出来るんだ。だから、さ。白花、君も宮真に好意を寄せていたんだろう?」
「は? 何言って……」
そういうことにしてあげれば、きっと白花の人間性を疑われることはない。宮真には悪いが、死人に口なしだ。白花の恋を否定することにはなるが、これからの白花にとって蟲に恋をしたという事実はきっと忌まわしい記憶になるだろうから仕方がない。僕の手で消してあげた方がいいだろう。
「君が僕に対して友好的だったのも、なんてことはない。こっそり血を吸って乱していたんだよ。宮真もこっそり君の血を吸っていたんだろう。君は優良個体だからね」
「……なるほどな。確かにアンタらにそういう能力があるんやったら、辻褄が合うわな」
「いい加減にしろよ、留理。そんな嘘吐いて俺を助けたって、お前が死んだら意味ないだろ! 俺が、どれだけお前を想ってるか、知らないくせに……」
知ってるさ。白花が友達思いだってことぐらい。僕なんかを特別扱いしてくれて。本当に楽しかった。
「だから、それが洗脳なんだって。もういいだろ? 火鋸。さっさと終わらせてくれ」
「……まあ、どうせオレは殺るしかないしな」
「おい、火鋸。留理に手ぇ出したら、お前が何であろうと、殺す」
「おっかないなぁ」
「留理。嘘を吐くんだったら、まずこれを捨ててからにしろ。お前が何言っても、悪い奴に思えない」
「……っ」
ポケットからマフラーの切れ端を取り出され、下を向く。反論しようとするのに、口を開けない。
本当は、今すぐ取り返して握りしめたかった。でも、それが駄目なことぐらい、わかってる。わかってるから、仕方なく手の甲を引っ搔いて気持ちを落ち着ける。
ああ、どうして僕はいつまでもこんなに弱いままなのか。
「留理。どうしてお前はそんなに我慢するんだよ。確かに、俺は頼りないかもしれない。でも、俺はお前に死んでほしくない。一緒に生きる方法がきっとある。だから、もう嘘を吐くな。留理が何を考えているのか、教えてくれ」
白花の誠実な瞳が僕を見つめる。それを前にして嘘が付ける程僕は器用じゃない。
「はは。駄目だよ……。僕は許されない……。お願いだから、これ以上僕を弱くしないで……。優しくされたら、また勘違いしてしまう……。僕は蟲なのに……。ああ、どうしたら正解なんだろう……」
がりがりと手の甲を掻く強さが増してゆく。だけど、その痛みはなんの解決にも繋がらない。不甲斐ない。どうして僕はこんなに心が弱いのだろう。
「留理。教えて? 留理が考えてること。俺に全部話してよ」
甘く優しい囁きに眩暈がする。そっと重ねられた手の温かさに泣きそうになる。
もう、自分の気持ちを隠してはおけなかった。
白花をそっと翅で抱き包み、二人だけの空間を作り出す。まるでステンドグラスのように光を通した瑠璃色の翅は、我ながら美しいと思えた。これで外に会話が聞こえないはずだ。
「あの、ね。ごめん。本当は、ね。僕は、白花が好き、なんだ……。僕は、白花が、優しいから……。好きに、なっちゃって……。ごめん、ね。蟲に好かれても、気持ち悪い、よね……」
「留理……」
言ってるうちに、涙がぼたぼたと地面を濡らす。泣くつもりなんかなかったのに。やっぱり駄目だ。色んな思い出がない交ぜになって僕の心を締め付ける。
「でもさ、だから、守りたいんだよ……。白花だけは、僕が守りたい。お願い、守らせて。他の蟲になんて食べさせない。白花には幸せな未来を歩んでほしいんだ。だから、僕を邪魔しないで。どの道死ぬんだ。だったら僕は白花のために死にたい。だから……」
涙を拭い、口を大きく開く。吸血して黙らせよう。話が拗れる前に、火鋸を説得して白花を保護してもらわなくちゃ。そのために僕は、あの悍ましき日から今に至るまで死に損なってきたのだから――。
「ねえ、留理。俺だってそうだよ。俺だって、留理が好きだ」
「え?」
白花の言葉に動きを止める。そして、意味を理解する間もなく静かに落とされた口づけに驚いて、涙が引っ込む。
「留理は俺が宮真を好きだと勘違いしてたみたいだけど……。俺が好きなのは留理だよ。宮真には嫉妬してただけ」
「は……?」
「信じられない? もっとする? ていうか、俺はもっとしたい」
「え、待って、んむ。んんっ。白花、待って! 僕、蟲だよ……?!」
「うん。綺麗な翅だよね。今まで見た中で一番。他のと比べ物にならないぐらい綺麗だ」
「……ルリアゲハより?」
恐る恐る尋ねてみる。今聞くべきことじゃないんだろうけど、聞かずにはいられなかった。
「勿論。ずっと眺めていたいぐらい綺麗だよ」
さらりと返ってきた言葉を聞いて、幼い頃の馬鹿々々しい決意が報われた気持ちになる。
「……あのさ、言いたいことはたくさんあるんだけどさ。とりあえず、改めてお礼を言わせてくれ。白花、幼虫だった僕を助けてくれてありがとう。僕は、あのマフラーと君の優しさのお陰で生きてこられたから」
「うん。留理が生きてて本当に良かった。昔の俺、グッジョブだね」
白花のおどけた表情に微笑みを返す。だけど、どうしたってもう本気では笑えない。
「白花が僕のことを好きだなんて……、まだ信じられないけどさ……。本当、なんだよね?」
「やっぱり足りなかった?」
「わ、待って。これ以上は、心臓が持たないから!」
「留理は相変わらず可愛いなぁ」
「蟲に可愛いはおかしいでしょ。それに……。うん。僕はやっぱり蟲だから。こういうのは間違ってるよ。僕じゃ君を幸せにはできない。だから……」
「だから嘘吐いて俺を守るために死ぬっての? それで俺が喜ぶと思ってる?」
白花が真剣な顔で僕を見つめる。静かな怒りが妙に恐ろしい。
「でも……。君は僕じゃなくても……」
「留理じゃなきゃ嫌だよ。なんで留理を諦めないといけないの? ねえ、留理は知ってるよね? 俺があの悍ましき日に全部失ったこと」
「……でも」
「留理は、俺にまたあんな思いをさせるつもりなの?」
「それは……」
いつもの癖でマフラーを押さえようとする手が空を切る。
「これ、持ってていいけどさ。もっと本体に縋ってよ」
そう言って、白花が僕の手にマフラーの切れ端を渡す。それを握りしめることも躊躇われて、のろのろとポケットに入れる。
「だけど……。でも……」
「やっぱり分かるまでチューする?」
「んう、違、んん、ちょっと!」
「あ~。お二人さん、おめでとうなんやけど、そろそろこっちのことも考えてほしいわな」
横から入ってきた火鋸の台詞にぎょっとする。
色々あって力が抜けたせいで、翅はいつの間にか地面についていた。つまり、僕らは火鋸から見られてる中でキスしてたってわけだ。
「あの、これは、違くて……。白花は、僕のせいでおかしくなってるだけで……」
「火鋸。わかるだろ? 留理は違う。血を吸ったのだって、俺を助ける為だったし……。多分だけどさ、留理は今まで人間の血を吸うこと、ずっと我慢してきたんじゃない?」
「……それは」
「火鋸、いい加減認めろよ。留理は害のある蟲じゃない。お前だって気づいてるんだろ?」
仄暗い圧を潜ませた白花の言葉に、火鋸は両手を挙げて肩を竦める。
「あ~。わかったわかった。確かにな、留理はオレが監視してる時も人を襲ってなかったみたいやし、力も弱い。どうやら、宮真みたいに完全な蟲の姿になれるわけじゃなさそうだしなぁ~。なんて――!」
「あっ」
一瞬のうちに、火鋸が僕のすぐ後ろに移動する。
「許すわけないやろ。宮真かて殺したんや。蟲である限り、オレは留理も許すわけにはいかんのや!」
火鋸の手のひらから炎が生まれる。僕には、それを防ぐ術がない。
マフラーの切れ端を握り込もうとして、思いとどまる。代わりに、掠れた声ですぐ傍にいる愛しい人の名を呼ぶ。
「やっと、頼ってくれた」
目にも留まらぬ速さで火鋸の手を捻り上げた白花が、こちらに向かって満足そうに微笑む。
「なっ。シロ、待て。これはお前の為でもあるんや。邪魔を……」
「邪魔してるのはそっちだろ?」
「あ……? 嘘、やろ……?」
「白花……!」
白花の剣が、火鋸の体を貫いていた。白花は、それを引き抜きもしないで再び僕を抱きしめる。
「待って、駄目だよ……。どうして……。彼は、地球人の救世主だ。なのに、こんなこと……」
「留理、俺は別に正義のために生きてるわけじゃない。わかったんだ。俺にとって留理が一番なんだ。留理以外もうどうでもいい。留理は、そうじゃないの?」
「……そんなの」
「素直に言って。ね、お互いに本当のことを言い合わないと」
「狡いよ……。僕だってずっと、白花のことだけを思ってやってきたのに……」
白花のシャツを思い切り握りしめ、額を擦りつける。ああ、この匂い、やっぱり安心する。マフラーなんかより、ずっといい。
「行こう、留理。遠くに行けば、きっと誰にも見つからないさ。大丈夫。だから、ね?」
「うん」
優しく取られた手に指を絡ませ、頷く。例えこの先に何が待っていようと、もうこの手を離したくないと思った。思ってしまったから、僕はもう戻れない。
「白花。ありがとう」
「それは、なんのお礼?」
「僕を、好きだって言ってくれたことへのお礼」
「……待って、それじゃあ俺もありがとうじゃん」
「ふふ」
おどけた白花に堪らず微笑む。ああ、この何気ないやり取りが好きだ。平和というのはきっとこういうことなのだろう。
「あ~。度々お取り込み中申し訳ないんやけど……。オレ、まだ死んでないで。てか、流石にこれぐらいじゃ死ねんわ」
「っ!」
起き上がり、体から剣を抜いた火鋸が怠そうに首を回す。その隙に、白花が僕を後ろに隠す。
「ああ、そう警戒せんと。試しただけやんか~」
「試す……?」
「ホンマに愛し合ってんのか。あと、留理がホンマに危険じゃないか、よ。オレを殺した後、豹変とかせんかな~、と思ったんやけど……。どう見てもラブラブ甘々やん。留理は良い子過ぎやし……。うん合格や」
「合格……?」
頷きながら、友好的に近づいてくる火鋸に、二人で後ずさる。
「そないに避けられると傷つくわぁ。オレ、大分アンタらに入れ込んでるつもりなんやけど?」
「……アンタは、留理を殺す気じゃないのか?」
「そのつもりやったけど、よ? 結構長いこと一緒におったら情も移るって。オレかて友達を殺したくないわ」
「……信用しろと?」
「ま、そりゃ信じないわな。けど、オレにはアンタらの気持ち、わからんでもないからな……。応援したくなるやんか……」
「火鋸……」
火鋸が目をやった先には、倒れたままの宮真の姿があった。
「お前は、あいつを守らなくて良かったのかよ……」
「あれは、危険やったからな……。しゃーない。アイツの場合は自業自得や」
言葉の割に、火鋸の声は弱々しく響いた。そのやりきれない表情は嘘偽りに見えない。
「……宮真は本当に火鋸のことが好きだったんだと思う。君といるときの宮真は、本当に楽しそうだったから」
「オレかて、好きやったわ……。楽しかったわ……。けど、もうどうしようもない。オレはあいつを守れんかった。情けない。クソ、オレだって、殺したくなかったっての……。宮真、ごめん、ごめんな……」
火鋸が膝をつき、宮真の頬にそっと触れる。それは、僕たちが辿るかもしれなかった未来だ。
「火鋸……」
何と声を掛ければいいのか迷ったところで、白花にそっと手を繋がれる。
そうだね。僕らが何を言ったってきっと――。
「勝手に人を殺さないでよね」
「「「え?」」」
聞き違いだろうか。今、宮真の声が、確かに……。
「火鋸さ、酷いよ。ボクが死んでから告白なんてさ」
「うわっ! え、いや……! 宮真、お前、死んだんじゃ……?!」
悲鳴を上げた火鋸を見て、宮真が可愛らしい笑い声をたてる。
「これぐらいじゃ死ねないっての。ボク、こう見えて優秀なんだってば」
「んなアホな!」
ぱっちりと目を開けた宮真が、よいしょと起き上がり、僕たちに軽く手を振る。
「それに火鋸、めちゃくちゃトドメが甘かった。多分、無意識なんだろうけど……。その、本当にボク、愛されてたりするのかな、なんて……」
「……っ、はは! なんやねん、それ……。オレらかて甘々やん。はあ……、ホンマ敵わんわ」
観念したと言わんばかりに、火鋸が宮真の膝に突っ伏す。それに目を丸くした後、宮真は火鋸の頭を撫でる。
「ね、火鋸。ボクはずっと知りたかった愛を知れた。もう満足。だから、今度こそボクを殺すべきだ。火鋸は、せめてボクの首を取っとかなきゃ。立場がないんじゃないの?」
「……随分と物分かりがいいやん」
「面倒な恋人になる気はないからね」
「でも残念。オレはやっぱりお前を殺す気がない」
「え? でも……。ボクは……」
起き上がった火鋸が戸惑う宮真の頬を優しく撫でる。
「お前が凶暴な蟲だとしても、オレが生かすと決めたんや。他に手出しはさせないし、勝手に死なせたりしない」
「あ~、もう! ボクは火鋸のためを思って言ってるの! 火鋸の独断で決めていいことじゃないでしょ?!」
「なんでや?」
「なんでって……。火鋸が、上に逆らって殺されでもしたら、意味ないし……」
「ふは。なんや、自分そんな心配しとったんか! 心配せんでも、オレの星で一番偉いんはオレやから。気まぐれで方針変えても許されるわ」
「……一番、偉い?」
宮真が反芻した言葉に、僕と白花も思わず顔を見合わせる。
「言ってなかったか? オレ、星を統べる王様やってんねん」
「いや、聞いてないよ……!」
宮真のここ一番の大声に僕らもこくこくと同意する。
「あ~。まあそういうことなんで。わかったやろ? 誰を生かすかってのは割とオレの独断で決めれんねん」
「いや、なんで王様が直々にスパイやってんのさ!」
「最前線で動いていたい性質なんや」
「なんで王様がボクなんかを気に入るのさ!」
「そりゃ宮真、お前が可愛いからやろ」
「ッ~!」
「あ~。お二人さんおめでとう」「一応俺たちもいるってこと考えて欲しいけどね」
顔を赤くした宮真に向かって、ここぞと二人で合の手を入れる。
「なら折角やしオレらも一丁見せつけとこか」
「は? 待て、火鋸ッむ」
口づけを交わした二人から目を逸らしながら苦笑する。当初の計画とは大分異なるが、どうやら丸く収まりそうだ。
*
「ちゅーわけで。蟲に壊されたこの星が元に戻るまで、今日も元気に仲良くボランティアやってこうな!」
「故郷滅ぼしといて、殺さず奉仕させようなんて、恐ろしい王様もいたもんだ」
「はは。世間様からはそう思われてるみたいやな。結構結構。いい宣伝になるわ」
結局、僕ら以外の蟲たちは駆除され、僕らの星も制圧された。それに関して、僕が思うところはない。宮真も口では文句を言ってはいるが、火鋸の判断に異論はないはずだ。
「で。修繕が必要な場所のデータを取るために、俺らはこうして彷徨ってるわけだけどさ」
「やっぱり、結構な時間がかかりそうだけど……?」
「そうやな。終わるころにゃ、シロはじいさんになっとるかもしれん」
「シロくんがおじいさんになっちゃうんなら、ボクらもおじいさんだよ……」
「え? 待て待て、蟲の寿命てそんなに短いん?」
「僕らの寿命も、この星の人間と大体同じだもんね」
「そーそー。上位種だったらもうちょい長いんだけどね」
「そうなんだ、意外。てっきり俺も一人だけおじいさんパターンかなって」
「逆に火鋸は長生きなのか~。良かった」
「よくない。宮真が死んだらオレも死ぬ」
「ベタ惚れだね」「だな」
「真面目な話、火鋸はボクが死んだらちゃんとした人を作りなよ?」
「……は?」
「だってそうでしょ? 王様なんだから跡継ぎを作らなきゃ」
「……王様やめる」
「ベタ惚れだね」「だな」
「ま、いっか。どうせボクが年老いたら流石の火鋸も萎えるだろうしね」
「どうだかね」
「どう思う?」「絶対無い。骨になっても愛し続けますって顔してるって」
白花の返答に心から同意する。多分、火鋸は宮真が思っている以上に本気だ。
「シロくん! 留理くん! あ、宮真ちゃんに火鋸くんも! 早くしないと始まっちゃうわよ!」
ぱたぱたと駆けてきた少女が息を切らしながら叫ぶ。
「あ、もうそんな時間か。ありがとうクロエ」
「もう。イチャつくのはいいけど、時間ぐらい守ってよね!」
お礼を告げた白花にクロエはぷくりと頬を膨らませる。パーティードレスに身を包んだ彼女は、いつもより華やかで可愛らしい。
「行こっか、留理」
「う、うん」
白花がクロエに見惚れでもしたらどうしようかと気を揉んでいたが、どうやら杞憂だったらしい。
「清々しいほど留理くんしか見てないし、見せつけるように恋人繋ぎはするし。やってらんないわよ」
肩を竦めたクロエに苦笑しながら、口元のマフラーを整える。
クロエは運良く生き残った人間の内の一人だ。僕たちは、数える程しか残らなかった人間を集め、地球を元に戻すための活動を続けている。
彼ら人間は未だに僕らを人間だと信じて疑わない。……色々見てしまった人間の記憶は火鋸たちが弄ったようだ。お蔭で僕たちも、前の生活と遜色ない日々を送れている。
「しっかし、生き残った人間同士の結婚式が拝めるとはなぁ」
急ごしらえした会場に着いて、火鋸が感慨深げに数回頷く。
自由になった人間たちは、もう誰も無理やり子を成そうとはしなかった。火鋸も人間の種が滅びてもそれは仕方のないことだ、と無理やり数を増やそうとはしなかった。どうやら、本能に逆らっているのは僕らだけではないらしい。
でも、そんな中で新たな番が生まれたことは喜ばしいことに変わりない。
『おめでと~!』『幸せになれよ~!』
『ありがとう!』『幸せになりま~す!』
きゃあきゃあと浮かれた人間たちが幸せそうに微笑む。
「スーツにマフラーってどうなの、って思ったけどさ。意外と似合う。っていうか留理は何着ても似合うね」
「……もしかして、マフラーしてるの嫌だった?」
不安になってマフラーに手をかける。新しく白花が編んでプレゼントしてくれたそれは、やっぱり僕の大切な宝物になってしまった。依存していると言われれば否定できない。
「まさか。マフラーに嫉妬するのはやめたよ。今や留理のトレードマークみたいなもんだし。留理も、ちゃんと俺に甘えてくれるし」
「……あ~。ほら、なんか始まるみたいだよ」
花嫁の周りに群がる人間たちを見て指をさす。……適当に話題を逸らしたはいいが、彼女たちが何をしているのかよくわからない。
「あれはね、ブーケトスだよ」
「ブーケトス?」
割って入ってきた宮真に聞き返す。
「あれやろ。結婚式の目玉。花嫁が投げた花束をキャッチした人間は次に結婚できるとかいう……迷信や」
「宮真ちゃん、留理くん! ぼやぼやしてないで並んだ並んだ!」
「え」「うわっ」
クロエに引っ張られた僕たちは、若い女の子たちの輪に入り込む。そして。
『せーのっ!』
高らかに放られた花束目掛けて、人間たちが手を伸ばす。
『掴んだ!』『アタシのよ!』『あ、ちょっと!』『ああっ!』
まるで、バレーボールみたいに人の手で押し上げられた花束が、僕目掛けて飛んでくる。
「あ……」
「わお。ナイスキャッチ留理!」
宮真が拍手した途端、会場からぱちぱちと拍手が沸き起こる。
「おめでとう、留理」
そう言って白花が、申し訳ない気持ちでおろおろしていた僕の手から花束を取り、自然な流れで口づけを落とす。
『ッきゃああああああああ!』『ヒュー、やる~!』『おめでと~!』『結婚式続けてやるやつ?!』
「あ、いや、えっと、これは……」
思っていたよりも好意的な反応に困惑しながらクロエを見る。
「馬鹿ね。みんな何となく察してたみたいよ。どうやら私は頭が固い方だったみたい。だから、これからはもっと堂々とイチャつきなさいな」
「や~。めでたいわ~。なんていうか、オレ父親の気分や」
「ボクも。応援した甲斐があったってもんだよ」
ふっきれた様子のクロエと涙ぐむ二人に困惑しながら白花を見る。
「ん? おかわり?」
「……ホントにしちゃう? 結婚式」
「えっ?!」
悪戯に微笑んでやると、白花が顔を真っ赤にして驚く。その顔があんまりにも嬉しそうだったから、僕もつられて頬を染める。
僕には宮真が追い求めていたという愛の概念がイマイチわからない。人間たちが結婚式でこんなにはしゃぐ気持ちもわからない。
きっとこれからも僕の本質は蟲であり、白花の血を吸うことで生かされ、人間に擬態したまま過ごすだろう。もしかしたら、また人間たちとすれ違う未来もあるかもしれない。
だけど、僕はきっと白花を裏切れない。この幸せを知ってしまったからには、簡単には死なない。
「白花」
マフラーを掴みかけた手を止め、白花の裾を掴む。その甘えた仕草に応えるように白花が僕を抱きしめる。
「ブーケの力、すごい」
「ふふ。白花が喜ぶなら、僕、本当に結婚式挙げてもいいよ」
「えっ?!」
驚く白花に今度は僕から口づけを落とす。会場が更に沸く。地面に落ちた白い花束には、いつの間にか綺麗な蝶が止まっていた。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
41
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる