36 / 56
第36話:甘味屋を手放す覚悟
第36話:甘味屋を手放す覚悟
しおりを挟む
王都の外れにある小さな甘味工房《Elysia Sweets》の朝は、今日も甘い匂いとともに始まった。
まだ太陽が石畳を斜めに照らしているだけの時間帯だというのに、店の前にはすでに人だかりができている。
木製の看板にかかった「本日分限定」の札を、じいっと見上げている子ども。
腕を組んで、列の長さを見て、まだ買えるかどうかを計算している商人。
昨夜のクエスト帰りらしく、鎧の一部に血と土を残したまま、甘い匂いに惹かれてきた冒険者たち。
ここは、派手な王都の大通りから少し外れた、生活の匂いが色濃く残る一角。
だが、その片隅に――甘味の誘惑に勝てない人間たちが、毎朝こうして列を作るようになってしまったのは、完全に俺の責任だ。
俺は、二階の小さな窓から、その光景を見下ろしていた。
木枠の窓を開けると、ひんやりした朝の風と一緒に、下から焼き立てのスポンジとキャラメルの香りが立ち上ってくる。
階段の下からは、すでに忙しない物音が聞こえていた。
金属同士が触れ合うカランという音、ボウルを回すシャカシャカという音、オーブンの扉が開いたときの熱気を含んだ空気の揺らぎ――そのすべてが、一日の始まりを告げている。
「⋯⋯今日も、地獄だな」
思わずそう呟くと、階段の途中から元気な声が飛んできた。
「地獄じゃないよ兄ちゃん! 天国だよ! 甘い匂いの天国!」
ネロが、まだ寝癖の残る茶髪を揺らしながら、パンをかじったまま階段を駆け上がってくる。
後ろからリオが少し遅れて上がってきて、ぼそりと付け足した。
「⋯⋯でも、忙しさだけは地獄寄り」
「お前も冷静にえぐいこと言うな」
ネロとリオは、森の拠点からしばらくの間、俺と一緒にここで寝泊まりしている。
二階には簡易ベッドがいくつか並べられ、俺と子供二人、たまにヨシュアやアレンも混ざって雑魚寝状態だ。
異世界に来てまで、学生時代の合宿みたいな生活をする羽目になるとは思わなかったが――悪くない。
悪くないが、俺の肉体は16歳でも、中身は55歳のおっさんだ。
毎日朝から晩まで店に張り付いているのは、正直、そろそろきつい。
俺が窓から目を離して階段を降りると、一階の厨房では、すでに二人のコックが戦場のような手際で動いていた。
「カイル、次のスポンジ、焼き上がり四分前!」
「了解! クリームの泡、あと少し締める!」
短く刈った茶髪に、真面目そうな瞳。
元パン職人見習いのカイルは、大きなボウルを抱え、汗を額に滲ませながらも、泡立て器のリズムを崩さない。
腕の筋肉がしなやかに動き、泡立つ卵と砂糖の表面に、きめ細かな光沢が生まれていく。
「レオン、苺のカット終わったら、プリンのカラメル確認頼む。焦がしすぎるなよ」
「大丈夫ですよシュウさん、昨日みたいに黒焦げにしませんって」
栗色の髪を後ろで束ねたレオンは、細身の体を器用に動かしながら、包丁を滑らせて苺を均一な厚さに切り揃えていく。
彼の指先は木工職人だった頃に鍛えられたもので、その感覚は今や繊細なケーキの飾り付けに存分に活かされていた。
まな板の上に並ぶ苺は、赤い宝石のように均一に整列し、そのままショーケースに飾っても絵になるほどだ。
オーブンからは、焼き立てのスポンジのふわりとした甘い匂いが漂い、鍋の中では、プリン用のカスタードがとろりと光沢を帯びながら温度を上げている。
別のカウンターでは、ヨーグルト用の牛乳と種菌を調合したボウルが並べられ、布で覆われて静かに眠っていた。
この小さな厨房は、もう完全に、“俺ひとりの作業場”ではなくなっていた。
「おはよう、シュウさん」
カイルが手を止めずに挨拶してくる。
レオンも手元から目を離さないまま、「おはようございます」と短く言った。
「おはよう。今日の仕込み、どこまで進んでる?」
「ショートケーキのスポンジ、一番目の分がもうすぐ。プリンは一回戦目が型に入って、冷ましてます。ババロアのベースは昨日の夜に仕込んでおいた分が冷蔵庫に。ヨーグルトは、森の拠点から持ってきた種で、今朝の分が寝てます」
「バターケーキは昨日焼き終わってるから、今日はデコレーションだけだね」とレオンが付け足す。
「あと、今日はレモンタルトの予約が多かったから、レモンの皮、いつもより多めに削っておきました」
その報告の正確さに、俺は内心でうなった。
――完全に、現場を把握してやがる。
つい数日前まで、「スポンジってふわふわに焼く意味あるんですか?」とか言っていたカイルが、今は焼き上がり時間まで秒単位で管理している。
レオンはレオンで、「飾りは見た目が大事です」と言って、苺の向きやクリームの絞り方にこだわりを見せるようになった。
店が回っている。
俺の意識がそこに集中していなくても、勝手に。
それは嬉しいことだ。
だが同時に、心のどこかで、「そろそろ決断の時期だぞ」と囁く声もあった。
――いつまで、ここに張り付いているつもりだ。
俺には、この店以外にもやるべきことがある。
森の拠点に戻って、ネロとリオたちとの生活を整えること。
王都に流通させる「安全な甘味」の基準を作ること。
場合によっては、他の街にも簡易的な甘味工房を立ち上げること――この世界に、少しずつ“甘い日常”を広げていくこと。
そのためには、この店を俺が手放さなければならない。
もちろん、所有権を完全に渡すわけじゃない。
だが、運営の現場からは、一歩引く必要がある。
「兄ちゃん、今日もオレ、客の列の整理する!」
ネロが元気よくエプロンをつけて飛び出していく。
リオは静かについていきながら、「今日はひとり三個までってちゃんと言わないと、絶対もめる」と真顔で呟いた。
フェイは、半ば儀礼的にではあるが、店の前に立って「本日は甘味の暴走を防ぐため、おひとり様のご購入数に制限を設けております」とかなんとか、立派な声で告げている。
お前、意味は分かってるんだろうな。
カウンターの向こうでは、ヨシュアが今日は普通の服――王子らしい装飾のないシャツとズボンにエプロンを重ねた姿で、皿を並べていた。
彼は王宮に戻る日も増えたが、それでも時間を見つけてはこうして店に顔を出し、「僕がここにいると、心が落ち着くんです」とか言いながら皿洗いや配膳を手伝っている。
王子としてどうなんだそれ、と思いつつも、働きぶりは文句なしだ。
少なくとも、昔の甥っ子の反抗期よりは、よほど扱いやすい。
そして――カウンターの端の席には、すでに銀色の大きな影が陣取っていた。
「⋯⋯開店前から来るの、やめてくれないか」
俺が顔をしかめると、巨大なフェンリル――銀狼ウォルフが、鼻先をふんと鳴らした。
「列に並ぶという行為は、人間の文化だ。森の王たる俺に求めるな」
「でも、毎回一番いい焼き加減のアップルパイを確保していくのは、さすがにどうかと思うぞ?」
「⋯⋯味に妥協はしない主義だ」
堂々と言い切りやがった。
九尾の銀狐ラムは、その横で優雅に尾を揺らしながら、静かに笑っている。
「よいではないか、シュウよ。森の守護者に甘味を供えるのは、古来より続く儀礼だ」
「そんな儀礼は知らん」
「今ここで決めれば、“古来より”になる」
「詐欺師の発想だな、ラム」
だが、ウォルフとラムがここに居座ってくれるおかげで、店の周辺に魔獣が寄り付きにくいというのも事実だ。
甘味の匂いにつられて野生の魔物が押し寄せてきてもおかしくない状況で、こうして“抑止力”がいてくれるのはありがたい。
――だからこそ、この店を、俺ひとりの手から離してもいいと、ようやく思えるようになった。
昼前、ひと段落ついたタイミングで、俺は厨房にいるカイルとレオンを呼び止めた。
「ちょっと二人とも、休憩がてら話をしようか」
カイルがボウルを片付けながら振り返る。
「何か問題でもありましたか? 今日の焼き色、少し薄かったですか?」
「いや、そういうんじゃない。レオン、お前も手を止めていい」
レオンは最後のひと切りを終えて包丁を置き、タオルで手を拭いた。
「⋯⋯なんだか、少し怖いですね。怒られるんでしょうか?」
「怒られないからそんな顔すんな。怒るときはもっと前の段階で怒る」
二人を店の奥、狭い休憩スペースに連れていく。
木の椅子が三つと、小さなテーブルがひとつ。
壁には、開店当初にネロが描いた、妙にデフォルメされたケーキと狼と狐の絵が貼ってある。
そこに腰を下ろし、俺は深呼吸をした。
「まず、最初に言っておく。二人とも、本当によくやってくれている。ここしばらく、仕込みも営業も、俺が細かく指示しなくても回るようになった。これは、俺にとってすごく大きい」
カイルとレオンは目を見合わせ、少し照れくさそうに笑った。
「いえ、シュウさんのレシピと教え方があったからです。僕たちは、その通りにやってるだけで⋯⋯」
「その“通りにやる”ってのが、難しいんだよ」
俺は、昔のことを思い出す。
前世で、甥っ子のために弁当を作り始めた頃。
最初はレシピ通りに作っても、同じ味にならず、何度もやり直した。
だが、ある時ふと、「レシピ通りにできるってこと自体が、技術なんだ」と気づかされた。
ましてこの世界では、オーブンの癖も材料の質も、地球のそれとは違う。
そんな中で、俺の感覚を自分のものにしようとした二人の努力は、本当に大したものだ。
「それでだ。単刀直入に言う。⋯⋯そろそろ、この店を、お前たちに任せたいと思ってる」
カイルの眉がぴくりと動き、レオンがわずかに息を呑んだ。
「任せる、というのは⋯⋯」
「俺が毎日、昼から閉店まで現場にいるんじゃなくてだな。仕込みの一部と新作の開発、材料の調達と全体の監修はやる。だが、日々の営業――どのケーキを何台焼いて、どのタイミングで出して、客の注文をさばいて、売り切れの判断をして⋯⋯そういう“店を回す作業”の主導権は、完全にお前たちに渡したい」
二人は真剣な顔で俺の言葉を聞いていた。
カイルが、ゆっくりと口を開く。
「それは⋯⋯その⋯⋯シュウさんは、ここからいなくなる、ということですか?」
「いなくはならないさ。王都に来るたびに顔を出すし、週のうち何日かは仕込みに付き合う。それに、この店の看板は俺の名前でもある。《Elysia Sweets》は、俺が最初に始めた店だ。その責任から完全に逃げるわけじゃない。ただ――」
ただ。
その先の言葉を、俺は一瞬飲み込んだ。
「⋯⋯俺には、この店以外にもやることがある。この国全体の甘味の安全基準を考えたり、他の街にも小規模な甘味工房を作ることを王と相談したり。森の拠点のほうも、いつまでも放っておけない。ネロやリオ、ミラたちとの生活もある。だから、この店を“俺がいなくても動く店”にしなきゃいけないんだ」
レオンが、テーブルの上に視線を落としたまま、ぽつりと呟いた。
「⋯⋯寂しくなりますね」
その正直な一言に、胸が少し締め付けられる。
「俺だって寂しいさ。ここは、俺にとっても“居場所”だからな」
だが、それでも――手放さなきゃいけない居場所というものもある。
甥っ子が独り立ちしたときのことを思い出す。
いつまでも、手を引いて歩かせるわけにはいかない。
今度は、店を育てた“親”として、俺が一歩引く番だ。
「もちろん、いきなり全部任せるわけじゃない。まずは一週間、俺が裏に引っ込んで、お前たちだけで営業をやってみる。その間、俺は口出ししない。その代わり、閉店後に反省会をして、気づいたことを全部洗い出す。それを何度か繰り返して――“ああ、もう大丈夫だな”ってなったら、本格的に俺は森の拠点に戻る」
カイルは、しばらく黙って考えていたが、やがて顔を上げて、真っ直ぐな目で俺を見た。
「⋯⋯俺に、できるでしょうか」
「できるかどうかじゃない。やるんだよ」
俺は、わざと少しだけ意地悪く笑ってみせた。
「怖いのは分かる。俺がいないと、何かあったときに頼れないって思うだろう。でもな、カイル――お前、もう俺がいなくても、スポンジの焼き加減で迷わなくなってるだろ」
「それは⋯⋯まあ⋯⋯」
「レオン、お前もだ。飾り付けで迷ったとき、以前は毎回俺に“これで大丈夫ですか?”って聞いてきてた。今は、自分で“この方がこの客は喜ぶ”って判断して動いてる」
レオンが、少しだけ頬を赤くした。
「⋯⋯気づいてたんですか」
「気づくわ。いちおう俺、店主だぞ」
カイルとレオンは目を見合わせ、同時に小さく笑った。
その笑いには、不安と、期待と、少しの誇りが混ざっている。
「やってみたいです、シュウさん」
「怖いですけど⋯⋯やってみたいです」
二人の返事を聞いて、俺は深く頷いた。
「よし。じゃあ、決まりだ。今日から一週間――俺は、基本的に“客席側”にいる。厨房の指示は、カイル、お前が出せ。レオンはサポート。店全体の動きを見る役目は、二人で分担しろ」
「はい!」
その力強い返事に、胸の奥がじんわりと熱くなる。
――ああ、こいつらに任せて大丈夫だ。
休憩スペースを出ると、ちょうど扉の向こうで聞き耳を立てていたらしいネロとリオが、ばつの悪そうな顔で飛び退いた。
「兄ちゃん、店任せちゃうの?」
「俺たち、もうここにずっといないの?」
「聞き耳を立てるなっていつも言ってるだろうが⋯⋯まあいい」
俺は二人の頭に軽く手を置いた。
「森の家も、ここも、どっちも俺たちの場所だ。行ったり来たりすればいいさ。ただ、ここはもう、“俺が守らなきゃいけない場所”じゃなくなる。守るのは――カイルとレオンたちだ」
フェイがいつの間にか背後に立っていて、真剣な顔で頷いた。
「では、私は“店の外”を守ります。シュウ様が店から一歩引かれたあとも、不審者やトラブルがあれば、私が対処します」
「お前はすぐ斬ろうとするから、その辺は加減しろよ」
「善処します」
善処の方向性が一番怖い。
その日の午後、俺は本当に、厨房に立つのをやめた。
仕込みは午前中のうちに終わらせ、営業開始の合図とともに、カウンターの端の席――ウォルフとラムが陣取っている少し離れたテーブルに腰を下ろした。
「⋯⋯本当に、見てるだけなんだな」
ウォルフが半眼で俺を見ながら、アップルパイを一口かじる。
パイ生地がサク、と軽い音を立て、中から熱々のリンゴとシナモンの香りが立ち上った。
「ああ。手を出したくなるけどな。今日は我慢だ」
「ふむ。お前が手を出さない分、人間たちの“成長”がよく見える」
ラムが紅茶のカップを指先で支えながら、優雅に言った。
「見よ、あの青年。注文が重なっても焦っていない。声を出し、動線を意識して配置を変え、客の流れを詰まらせぬようにしている」
ラムの視線の先では、カイルが厨房の中で「ショートケーキあと二台! プリン、手前から出して!」と声を張り上げていた。
レオンがそれに即座に反応し、ショーケースの中身を入れ替えながら、後ろに並ぶ皿の位置を調整している。
ネロとリオは客の列の整理と配膳を手伝い、ヨシュアは落ち着いた声で注文を復唱しながら、間違いを防いでいた。
「⋯⋯やるじゃないか」
思わず、そう呟いた。
客の中には、初日に来てくれたあの少女と父親の姿もあった。
少女は、ショートケーキを大事そうに抱えながら、嬉しそうに列に並んでいる。
別のテーブルでは、冒険者たちが「今日もあの“月の光みたいなババロア”あるか?」と盛り上がり、隣の席の商人が「この前の取引先に持っていったら、一発で契約が決まったんだ」と、ケーキのビジネス的効能まで語っている。
俺が厨房に立っていたときと、店の雰囲気は変わらない。
いや、むしろ――俺があれこれ口を出していた頃よりも、客と店の距離が近くなっている気がする。
カイルやレオンが、客のちょっとした一言に反応して新しい提案をしたり、次回の予約を取ったり。
そういう「関係性」が、自然に紡がれていっている。
夕方、日が少し傾いた頃、ようやく「本日分完売」の札が店の扉にかけられた。
店内に残っているのは、わずかな甘い匂いと、疲労と、達成感だけだ。
「⋯⋯死ぬかと思いました」
カイルが、椅子に座った瞬間に背もたれにぐったりと倒れ込んだ。
レオンもテーブルに突っ伏しながら、それでも口元は笑っている。
「でも⋯⋯なんとか、できましたね」
ネロは床に大の字になり、リオはその隣で静かに息を整えている。
ヨシュアは皿洗いを終えて、ふぅ、と息を吐いた。
「シュウさん⋯⋯今日は、本当に見てるだけでしたね」
「約束だからな」
カウンターから立ち上がり、俺は厨房の入り口に立った。
「さて――じゃあ、今日の反省会といくか」
全員が顔を上げる。その目は、疲れているのに、どこか期待に満ちていた。
俺はテーブルの上に紙とペンを広げ、ひとつずつ、今日の流れを振り返っていく。
どの時間帯に混雑したか。
どの甘味が一番早く売り切れたか。
客の反応はどうだったか。
厨房の動線でつまづいたところはないか。
カイルもレオンも、自分から「ここで手が足りなくなった」「次はこう動いたほうがいい」と提案を出してくる。
ネロとリオも、「子ども連れの人はもう少し座れる場所があったほうがいい」とか、「冒険者は甘いものの後にジャーキーも欲しがってた」とか、地味に核心を突く意見を言ってくる。
フェイはと言えば、「シュウ様、どうか店の前に“本日分を超えたら魔力暴走の危険があります”と書いた札を⋯⋯」と真顔で提案してきたので、「余計に客が殺到するからやめろ」と全力で却下した。
反省会が終わる頃には、外はすっかり暗くなっていた。
ウォルフとラムは、いつの間にか店の外で夜風に当たりながら、静かに星を眺めていた。
甘味屋の明かりが、王都の外れの一角を柔らかく照らし、遠くのほうからは、今日も甘い一日が終わったことを喜ぶような、人々の笑い声がかすかに届く。
皆がそれぞれ寝床に向かったあと、俺はひとり、まだ温かさの残るカウンターに肘をついて、静かに目を閉じた。
――店は、動いた。
俺が前に立たなくても。
俺が声を張り上げなくても。
甘味は、ちゃんと人の手で、人の口へと届けられていった。
それは、少しだけ寂しくて、けれど、何よりも誇らしい光景だった。
「⋯⋯よくやったな、みんな」
小さくそう呟いてから、俺は二階へと続く階段を上がった。
明日もまた、一日中甘い匂いに包まれるだろう。
だが、その中心に立つのは、もう俺ではない。
俺はこれから少しずつ、この店から離れ――代わりに、この世界全体を見ていくつもりだ。
王都の外れの夜空は、星がよく見える。
窓を開けると、遠く森のほうから、銀狼の吠え声が静かに響いた。
それは、まるで「行ってこい」と背中を押してくれているように聞こえた。
「⋯⋯ああ、分かったよ」
俺は小さく笑い、窓を閉めた。
甘味屋《Elysia Sweets》は、今日を境に――俺の店から、“みんなの店”へと変わり始めた。
そしてその変化は、きっとこの国の甘い未来へと、静かにつながっていくのだろう。
まだ太陽が石畳を斜めに照らしているだけの時間帯だというのに、店の前にはすでに人だかりができている。
木製の看板にかかった「本日分限定」の札を、じいっと見上げている子ども。
腕を組んで、列の長さを見て、まだ買えるかどうかを計算している商人。
昨夜のクエスト帰りらしく、鎧の一部に血と土を残したまま、甘い匂いに惹かれてきた冒険者たち。
ここは、派手な王都の大通りから少し外れた、生活の匂いが色濃く残る一角。
だが、その片隅に――甘味の誘惑に勝てない人間たちが、毎朝こうして列を作るようになってしまったのは、完全に俺の責任だ。
俺は、二階の小さな窓から、その光景を見下ろしていた。
木枠の窓を開けると、ひんやりした朝の風と一緒に、下から焼き立てのスポンジとキャラメルの香りが立ち上ってくる。
階段の下からは、すでに忙しない物音が聞こえていた。
金属同士が触れ合うカランという音、ボウルを回すシャカシャカという音、オーブンの扉が開いたときの熱気を含んだ空気の揺らぎ――そのすべてが、一日の始まりを告げている。
「⋯⋯今日も、地獄だな」
思わずそう呟くと、階段の途中から元気な声が飛んできた。
「地獄じゃないよ兄ちゃん! 天国だよ! 甘い匂いの天国!」
ネロが、まだ寝癖の残る茶髪を揺らしながら、パンをかじったまま階段を駆け上がってくる。
後ろからリオが少し遅れて上がってきて、ぼそりと付け足した。
「⋯⋯でも、忙しさだけは地獄寄り」
「お前も冷静にえぐいこと言うな」
ネロとリオは、森の拠点からしばらくの間、俺と一緒にここで寝泊まりしている。
二階には簡易ベッドがいくつか並べられ、俺と子供二人、たまにヨシュアやアレンも混ざって雑魚寝状態だ。
異世界に来てまで、学生時代の合宿みたいな生活をする羽目になるとは思わなかったが――悪くない。
悪くないが、俺の肉体は16歳でも、中身は55歳のおっさんだ。
毎日朝から晩まで店に張り付いているのは、正直、そろそろきつい。
俺が窓から目を離して階段を降りると、一階の厨房では、すでに二人のコックが戦場のような手際で動いていた。
「カイル、次のスポンジ、焼き上がり四分前!」
「了解! クリームの泡、あと少し締める!」
短く刈った茶髪に、真面目そうな瞳。
元パン職人見習いのカイルは、大きなボウルを抱え、汗を額に滲ませながらも、泡立て器のリズムを崩さない。
腕の筋肉がしなやかに動き、泡立つ卵と砂糖の表面に、きめ細かな光沢が生まれていく。
「レオン、苺のカット終わったら、プリンのカラメル確認頼む。焦がしすぎるなよ」
「大丈夫ですよシュウさん、昨日みたいに黒焦げにしませんって」
栗色の髪を後ろで束ねたレオンは、細身の体を器用に動かしながら、包丁を滑らせて苺を均一な厚さに切り揃えていく。
彼の指先は木工職人だった頃に鍛えられたもので、その感覚は今や繊細なケーキの飾り付けに存分に活かされていた。
まな板の上に並ぶ苺は、赤い宝石のように均一に整列し、そのままショーケースに飾っても絵になるほどだ。
オーブンからは、焼き立てのスポンジのふわりとした甘い匂いが漂い、鍋の中では、プリン用のカスタードがとろりと光沢を帯びながら温度を上げている。
別のカウンターでは、ヨーグルト用の牛乳と種菌を調合したボウルが並べられ、布で覆われて静かに眠っていた。
この小さな厨房は、もう完全に、“俺ひとりの作業場”ではなくなっていた。
「おはよう、シュウさん」
カイルが手を止めずに挨拶してくる。
レオンも手元から目を離さないまま、「おはようございます」と短く言った。
「おはよう。今日の仕込み、どこまで進んでる?」
「ショートケーキのスポンジ、一番目の分がもうすぐ。プリンは一回戦目が型に入って、冷ましてます。ババロアのベースは昨日の夜に仕込んでおいた分が冷蔵庫に。ヨーグルトは、森の拠点から持ってきた種で、今朝の分が寝てます」
「バターケーキは昨日焼き終わってるから、今日はデコレーションだけだね」とレオンが付け足す。
「あと、今日はレモンタルトの予約が多かったから、レモンの皮、いつもより多めに削っておきました」
その報告の正確さに、俺は内心でうなった。
――完全に、現場を把握してやがる。
つい数日前まで、「スポンジってふわふわに焼く意味あるんですか?」とか言っていたカイルが、今は焼き上がり時間まで秒単位で管理している。
レオンはレオンで、「飾りは見た目が大事です」と言って、苺の向きやクリームの絞り方にこだわりを見せるようになった。
店が回っている。
俺の意識がそこに集中していなくても、勝手に。
それは嬉しいことだ。
だが同時に、心のどこかで、「そろそろ決断の時期だぞ」と囁く声もあった。
――いつまで、ここに張り付いているつもりだ。
俺には、この店以外にもやるべきことがある。
森の拠点に戻って、ネロとリオたちとの生活を整えること。
王都に流通させる「安全な甘味」の基準を作ること。
場合によっては、他の街にも簡易的な甘味工房を立ち上げること――この世界に、少しずつ“甘い日常”を広げていくこと。
そのためには、この店を俺が手放さなければならない。
もちろん、所有権を完全に渡すわけじゃない。
だが、運営の現場からは、一歩引く必要がある。
「兄ちゃん、今日もオレ、客の列の整理する!」
ネロが元気よくエプロンをつけて飛び出していく。
リオは静かについていきながら、「今日はひとり三個までってちゃんと言わないと、絶対もめる」と真顔で呟いた。
フェイは、半ば儀礼的にではあるが、店の前に立って「本日は甘味の暴走を防ぐため、おひとり様のご購入数に制限を設けております」とかなんとか、立派な声で告げている。
お前、意味は分かってるんだろうな。
カウンターの向こうでは、ヨシュアが今日は普通の服――王子らしい装飾のないシャツとズボンにエプロンを重ねた姿で、皿を並べていた。
彼は王宮に戻る日も増えたが、それでも時間を見つけてはこうして店に顔を出し、「僕がここにいると、心が落ち着くんです」とか言いながら皿洗いや配膳を手伝っている。
王子としてどうなんだそれ、と思いつつも、働きぶりは文句なしだ。
少なくとも、昔の甥っ子の反抗期よりは、よほど扱いやすい。
そして――カウンターの端の席には、すでに銀色の大きな影が陣取っていた。
「⋯⋯開店前から来るの、やめてくれないか」
俺が顔をしかめると、巨大なフェンリル――銀狼ウォルフが、鼻先をふんと鳴らした。
「列に並ぶという行為は、人間の文化だ。森の王たる俺に求めるな」
「でも、毎回一番いい焼き加減のアップルパイを確保していくのは、さすがにどうかと思うぞ?」
「⋯⋯味に妥協はしない主義だ」
堂々と言い切りやがった。
九尾の銀狐ラムは、その横で優雅に尾を揺らしながら、静かに笑っている。
「よいではないか、シュウよ。森の守護者に甘味を供えるのは、古来より続く儀礼だ」
「そんな儀礼は知らん」
「今ここで決めれば、“古来より”になる」
「詐欺師の発想だな、ラム」
だが、ウォルフとラムがここに居座ってくれるおかげで、店の周辺に魔獣が寄り付きにくいというのも事実だ。
甘味の匂いにつられて野生の魔物が押し寄せてきてもおかしくない状況で、こうして“抑止力”がいてくれるのはありがたい。
――だからこそ、この店を、俺ひとりの手から離してもいいと、ようやく思えるようになった。
昼前、ひと段落ついたタイミングで、俺は厨房にいるカイルとレオンを呼び止めた。
「ちょっと二人とも、休憩がてら話をしようか」
カイルがボウルを片付けながら振り返る。
「何か問題でもありましたか? 今日の焼き色、少し薄かったですか?」
「いや、そういうんじゃない。レオン、お前も手を止めていい」
レオンは最後のひと切りを終えて包丁を置き、タオルで手を拭いた。
「⋯⋯なんだか、少し怖いですね。怒られるんでしょうか?」
「怒られないからそんな顔すんな。怒るときはもっと前の段階で怒る」
二人を店の奥、狭い休憩スペースに連れていく。
木の椅子が三つと、小さなテーブルがひとつ。
壁には、開店当初にネロが描いた、妙にデフォルメされたケーキと狼と狐の絵が貼ってある。
そこに腰を下ろし、俺は深呼吸をした。
「まず、最初に言っておく。二人とも、本当によくやってくれている。ここしばらく、仕込みも営業も、俺が細かく指示しなくても回るようになった。これは、俺にとってすごく大きい」
カイルとレオンは目を見合わせ、少し照れくさそうに笑った。
「いえ、シュウさんのレシピと教え方があったからです。僕たちは、その通りにやってるだけで⋯⋯」
「その“通りにやる”ってのが、難しいんだよ」
俺は、昔のことを思い出す。
前世で、甥っ子のために弁当を作り始めた頃。
最初はレシピ通りに作っても、同じ味にならず、何度もやり直した。
だが、ある時ふと、「レシピ通りにできるってこと自体が、技術なんだ」と気づかされた。
ましてこの世界では、オーブンの癖も材料の質も、地球のそれとは違う。
そんな中で、俺の感覚を自分のものにしようとした二人の努力は、本当に大したものだ。
「それでだ。単刀直入に言う。⋯⋯そろそろ、この店を、お前たちに任せたいと思ってる」
カイルの眉がぴくりと動き、レオンがわずかに息を呑んだ。
「任せる、というのは⋯⋯」
「俺が毎日、昼から閉店まで現場にいるんじゃなくてだな。仕込みの一部と新作の開発、材料の調達と全体の監修はやる。だが、日々の営業――どのケーキを何台焼いて、どのタイミングで出して、客の注文をさばいて、売り切れの判断をして⋯⋯そういう“店を回す作業”の主導権は、完全にお前たちに渡したい」
二人は真剣な顔で俺の言葉を聞いていた。
カイルが、ゆっくりと口を開く。
「それは⋯⋯その⋯⋯シュウさんは、ここからいなくなる、ということですか?」
「いなくはならないさ。王都に来るたびに顔を出すし、週のうち何日かは仕込みに付き合う。それに、この店の看板は俺の名前でもある。《Elysia Sweets》は、俺が最初に始めた店だ。その責任から完全に逃げるわけじゃない。ただ――」
ただ。
その先の言葉を、俺は一瞬飲み込んだ。
「⋯⋯俺には、この店以外にもやることがある。この国全体の甘味の安全基準を考えたり、他の街にも小規模な甘味工房を作ることを王と相談したり。森の拠点のほうも、いつまでも放っておけない。ネロやリオ、ミラたちとの生活もある。だから、この店を“俺がいなくても動く店”にしなきゃいけないんだ」
レオンが、テーブルの上に視線を落としたまま、ぽつりと呟いた。
「⋯⋯寂しくなりますね」
その正直な一言に、胸が少し締め付けられる。
「俺だって寂しいさ。ここは、俺にとっても“居場所”だからな」
だが、それでも――手放さなきゃいけない居場所というものもある。
甥っ子が独り立ちしたときのことを思い出す。
いつまでも、手を引いて歩かせるわけにはいかない。
今度は、店を育てた“親”として、俺が一歩引く番だ。
「もちろん、いきなり全部任せるわけじゃない。まずは一週間、俺が裏に引っ込んで、お前たちだけで営業をやってみる。その間、俺は口出ししない。その代わり、閉店後に反省会をして、気づいたことを全部洗い出す。それを何度か繰り返して――“ああ、もう大丈夫だな”ってなったら、本格的に俺は森の拠点に戻る」
カイルは、しばらく黙って考えていたが、やがて顔を上げて、真っ直ぐな目で俺を見た。
「⋯⋯俺に、できるでしょうか」
「できるかどうかじゃない。やるんだよ」
俺は、わざと少しだけ意地悪く笑ってみせた。
「怖いのは分かる。俺がいないと、何かあったときに頼れないって思うだろう。でもな、カイル――お前、もう俺がいなくても、スポンジの焼き加減で迷わなくなってるだろ」
「それは⋯⋯まあ⋯⋯」
「レオン、お前もだ。飾り付けで迷ったとき、以前は毎回俺に“これで大丈夫ですか?”って聞いてきてた。今は、自分で“この方がこの客は喜ぶ”って判断して動いてる」
レオンが、少しだけ頬を赤くした。
「⋯⋯気づいてたんですか」
「気づくわ。いちおう俺、店主だぞ」
カイルとレオンは目を見合わせ、同時に小さく笑った。
その笑いには、不安と、期待と、少しの誇りが混ざっている。
「やってみたいです、シュウさん」
「怖いですけど⋯⋯やってみたいです」
二人の返事を聞いて、俺は深く頷いた。
「よし。じゃあ、決まりだ。今日から一週間――俺は、基本的に“客席側”にいる。厨房の指示は、カイル、お前が出せ。レオンはサポート。店全体の動きを見る役目は、二人で分担しろ」
「はい!」
その力強い返事に、胸の奥がじんわりと熱くなる。
――ああ、こいつらに任せて大丈夫だ。
休憩スペースを出ると、ちょうど扉の向こうで聞き耳を立てていたらしいネロとリオが、ばつの悪そうな顔で飛び退いた。
「兄ちゃん、店任せちゃうの?」
「俺たち、もうここにずっといないの?」
「聞き耳を立てるなっていつも言ってるだろうが⋯⋯まあいい」
俺は二人の頭に軽く手を置いた。
「森の家も、ここも、どっちも俺たちの場所だ。行ったり来たりすればいいさ。ただ、ここはもう、“俺が守らなきゃいけない場所”じゃなくなる。守るのは――カイルとレオンたちだ」
フェイがいつの間にか背後に立っていて、真剣な顔で頷いた。
「では、私は“店の外”を守ります。シュウ様が店から一歩引かれたあとも、不審者やトラブルがあれば、私が対処します」
「お前はすぐ斬ろうとするから、その辺は加減しろよ」
「善処します」
善処の方向性が一番怖い。
その日の午後、俺は本当に、厨房に立つのをやめた。
仕込みは午前中のうちに終わらせ、営業開始の合図とともに、カウンターの端の席――ウォルフとラムが陣取っている少し離れたテーブルに腰を下ろした。
「⋯⋯本当に、見てるだけなんだな」
ウォルフが半眼で俺を見ながら、アップルパイを一口かじる。
パイ生地がサク、と軽い音を立て、中から熱々のリンゴとシナモンの香りが立ち上った。
「ああ。手を出したくなるけどな。今日は我慢だ」
「ふむ。お前が手を出さない分、人間たちの“成長”がよく見える」
ラムが紅茶のカップを指先で支えながら、優雅に言った。
「見よ、あの青年。注文が重なっても焦っていない。声を出し、動線を意識して配置を変え、客の流れを詰まらせぬようにしている」
ラムの視線の先では、カイルが厨房の中で「ショートケーキあと二台! プリン、手前から出して!」と声を張り上げていた。
レオンがそれに即座に反応し、ショーケースの中身を入れ替えながら、後ろに並ぶ皿の位置を調整している。
ネロとリオは客の列の整理と配膳を手伝い、ヨシュアは落ち着いた声で注文を復唱しながら、間違いを防いでいた。
「⋯⋯やるじゃないか」
思わず、そう呟いた。
客の中には、初日に来てくれたあの少女と父親の姿もあった。
少女は、ショートケーキを大事そうに抱えながら、嬉しそうに列に並んでいる。
別のテーブルでは、冒険者たちが「今日もあの“月の光みたいなババロア”あるか?」と盛り上がり、隣の席の商人が「この前の取引先に持っていったら、一発で契約が決まったんだ」と、ケーキのビジネス的効能まで語っている。
俺が厨房に立っていたときと、店の雰囲気は変わらない。
いや、むしろ――俺があれこれ口を出していた頃よりも、客と店の距離が近くなっている気がする。
カイルやレオンが、客のちょっとした一言に反応して新しい提案をしたり、次回の予約を取ったり。
そういう「関係性」が、自然に紡がれていっている。
夕方、日が少し傾いた頃、ようやく「本日分完売」の札が店の扉にかけられた。
店内に残っているのは、わずかな甘い匂いと、疲労と、達成感だけだ。
「⋯⋯死ぬかと思いました」
カイルが、椅子に座った瞬間に背もたれにぐったりと倒れ込んだ。
レオンもテーブルに突っ伏しながら、それでも口元は笑っている。
「でも⋯⋯なんとか、できましたね」
ネロは床に大の字になり、リオはその隣で静かに息を整えている。
ヨシュアは皿洗いを終えて、ふぅ、と息を吐いた。
「シュウさん⋯⋯今日は、本当に見てるだけでしたね」
「約束だからな」
カウンターから立ち上がり、俺は厨房の入り口に立った。
「さて――じゃあ、今日の反省会といくか」
全員が顔を上げる。その目は、疲れているのに、どこか期待に満ちていた。
俺はテーブルの上に紙とペンを広げ、ひとつずつ、今日の流れを振り返っていく。
どの時間帯に混雑したか。
どの甘味が一番早く売り切れたか。
客の反応はどうだったか。
厨房の動線でつまづいたところはないか。
カイルもレオンも、自分から「ここで手が足りなくなった」「次はこう動いたほうがいい」と提案を出してくる。
ネロとリオも、「子ども連れの人はもう少し座れる場所があったほうがいい」とか、「冒険者は甘いものの後にジャーキーも欲しがってた」とか、地味に核心を突く意見を言ってくる。
フェイはと言えば、「シュウ様、どうか店の前に“本日分を超えたら魔力暴走の危険があります”と書いた札を⋯⋯」と真顔で提案してきたので、「余計に客が殺到するからやめろ」と全力で却下した。
反省会が終わる頃には、外はすっかり暗くなっていた。
ウォルフとラムは、いつの間にか店の外で夜風に当たりながら、静かに星を眺めていた。
甘味屋の明かりが、王都の外れの一角を柔らかく照らし、遠くのほうからは、今日も甘い一日が終わったことを喜ぶような、人々の笑い声がかすかに届く。
皆がそれぞれ寝床に向かったあと、俺はひとり、まだ温かさの残るカウンターに肘をついて、静かに目を閉じた。
――店は、動いた。
俺が前に立たなくても。
俺が声を張り上げなくても。
甘味は、ちゃんと人の手で、人の口へと届けられていった。
それは、少しだけ寂しくて、けれど、何よりも誇らしい光景だった。
「⋯⋯よくやったな、みんな」
小さくそう呟いてから、俺は二階へと続く階段を上がった。
明日もまた、一日中甘い匂いに包まれるだろう。
だが、その中心に立つのは、もう俺ではない。
俺はこれから少しずつ、この店から離れ――代わりに、この世界全体を見ていくつもりだ。
王都の外れの夜空は、星がよく見える。
窓を開けると、遠く森のほうから、銀狼の吠え声が静かに響いた。
それは、まるで「行ってこい」と背中を押してくれているように聞こえた。
「⋯⋯ああ、分かったよ」
俺は小さく笑い、窓を閉めた。
甘味屋《Elysia Sweets》は、今日を境に――俺の店から、“みんなの店”へと変わり始めた。
そしてその変化は、きっとこの国の甘い未来へと、静かにつながっていくのだろう。
0
あなたにおすすめの小説

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。

99歳で亡くなり異世界に転生した老人は7歳の子供に生まれ変わり、召喚魔法でドラゴンや前世の世界の物を召喚して世界を変える
ハーフのクロエ
ファンタジー
夫が病気で長期入院したので夫が途中まで書いていた小説を私なりに書き直して完結まで投稿しますので応援よろしくお願いいたします。
主人公は建築会社を55歳で取り締まり役常務をしていたが惜しげもなく早期退職し田舎で大好きな農業をしていた。99歳で亡くなった老人は前世の記憶を持ったまま7歳の少年マリュウスとして異世界の僻地の男爵家に生まれ変わる。10歳の鑑定の儀で、火、水、風、土、木の5大魔法ではなく、この世界で初めての召喚魔法を授かる。最初に召喚出来たのは弱いスライム、モグラ魔獣でマリウスはガッカリしたが優しい家族に見守られ次第に色んな魔獣や地球の、物などを召喚出来るようになり、僻地の男爵家を発展させ気が付けば大陸一豊かで最強の小さい王国を起こしていた。

異世界へ行って帰って来た
バルサック
ファンタジー
ダンジョンの出現した日本で、じいさんの形見となった指輪で異世界へ行ってしまった。
そして帰って来た。2つの世界を往来できる力で様々な体験をする神須勇だった。

ボクが追放されたら飢餓に陥るけど良いですか?
音爽(ネソウ)
ファンタジー
美味しい果実より食えない石ころが欲しいなんて、人間て変わってますね。
役に立たないから出ていけ?
わかりました、緑の加護はゴッソリ持っていきます!
さようなら!
5月4日、ファンタジー1位!HOTランキング1位獲得!!ありがとうございました!
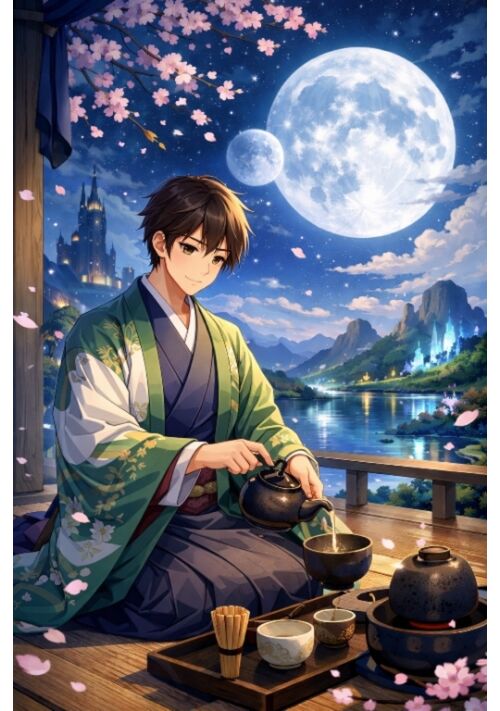
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

異世界転生したらたくさんスキルもらったけど今まで選ばれなかったものだった~魔王討伐は無理な気がする~
宝者来価
ファンタジー
俺は異世界転生者カドマツ。
転生理由は幼い少女を交通事故からかばったこと。
良いとこなしの日々を送っていたが女神様から異世界に転生すると説明された時にはアニメやゲームのような展開を期待したりもした。
例えばモンスターを倒して国を救いヒロインと結ばれるなど。
けれど与えられた【今まで選ばれなかったスキルが使える】 戦闘はおろか日常の役にも立つ気がしない余りものばかり。
同じ転生者でイケメン王子のレイニーに出迎えられ歓迎される。
彼は【スキル:水】を使う最強で理想的な異世界転生者に思えたのだが―――!?
※小説家になろう様にも掲載しています。

スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜
かの
ファンタジー
世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。
スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。
偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。
スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!
冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!

セーブポイント転生 ~寿命が無い石なので千年修行したらレベル上限突破してしまった~
空色蜻蛉
ファンタジー
枢は目覚めるとクリスタルの中で魂だけの状態になっていた。どうやらダンジョンのセーブポイントに転生してしまったらしい。身動きできない状態に悲嘆に暮れた枢だが、やがて開き直ってレベルアップ作業に明け暮れることにした。百年経ち、二百年経ち……やがて国の礎である「聖なるクリスタル」として崇められるまでになる。
もう元の世界に戻れないと腹をくくって自分の国を見守る枢だが、千年経った時、衝撃のどんでん返しが待ち受けていて……。
【お知らせ】6/22 完結しました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















