あなたにおすすめの小説
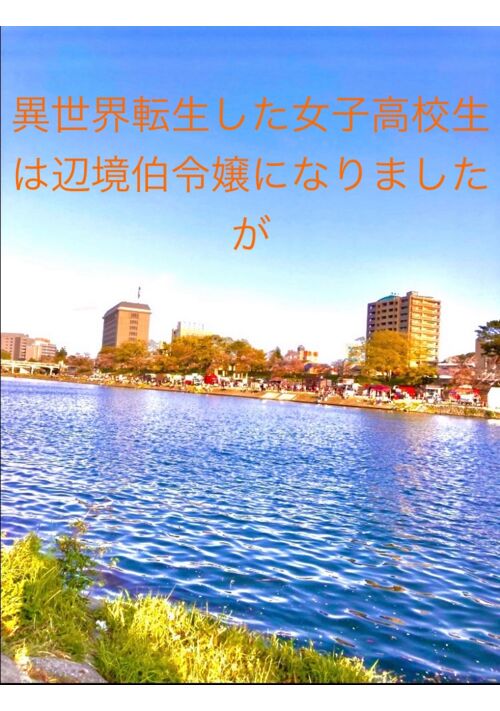
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

魔力値1の私が大賢者(仮)を目指すまで
ひーにゃん
ファンタジー
誰もが魔力をもち魔法が使える世界で、アンナリーナはその力を持たず皆に厭われていた。
運命の【ギフト授与式】がやってきて、これでまともな暮らしが出来るかと思ったのだが……
与えられたギフトは【ギフト】というよくわからないもの。
だが、そのとき思い出した前世の記憶で【ギフト】の使い方を閃いて。
これは少し歪んだ考え方の持ち主、アンナリーナの一風変わった仲間たちとの日常のお話。
冒険を始めるに至って、第1章はアンナリーナのこれからを書くのに外せません。
よろしくお願いします。
この作品は小説家になろう様にも掲載しています。

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。

第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

SSSレア・スライムに転生した魚屋さん ~戦うつもりはないけど、どんどん強くなる~
草笛あたる(乱暴)
ファンタジー
転生したらスライムの突然変異だった。
レアらしくて、成長が異常に早いよ。
せっかくだから、自分の特技を活かして、日本の魚屋技術を異世界に広めたいな。
出刃包丁がない世界だったので、スライムの体内で作ったら、名刀に仕上がっちゃった。

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

掃除婦に追いやられた私、城のゴミ山から古代兵器を次々と発掘して国中、世界中?がざわつく
タマ マコト
ファンタジー
王立工房の魔導測量師見習いリーナは、誰にも測れない“失われた魔力波長”を感じ取れるせいで奇人扱いされ、派閥争いのスケープゴートにされて掃除婦として城のゴミ置き場に追いやられる。
最底辺の仕事に落ちた彼女は、ゴミ山の中から自分にだけ見える微かな光を見つけ、それを磨き上げた結果、朽ちた金属片が古代兵器アークレールとして完全復活し、世界の均衡を揺るがす存在としての第一歩を踏み出す。

99歳で亡くなり異世界に転生した老人は7歳の子供に生まれ変わり、召喚魔法でドラゴンや前世の世界の物を召喚して世界を変える
ハーフのクロエ
ファンタジー
夫が病気で長期入院したので夫が途中まで書いていた小説を私なりに書き直して完結まで投稿しますので応援よろしくお願いいたします。
主人公は建築会社を55歳で取り締まり役常務をしていたが惜しげもなく早期退職し田舎で大好きな農業をしていた。99歳で亡くなった老人は前世の記憶を持ったまま7歳の少年マリュウスとして異世界の僻地の男爵家に生まれ変わる。10歳の鑑定の儀で、火、水、風、土、木の5大魔法ではなく、この世界で初めての召喚魔法を授かる。最初に召喚出来たのは弱いスライム、モグラ魔獣でマリウスはガッカリしたが優しい家族に見守られ次第に色んな魔獣や地球の、物などを召喚出来るようになり、僻地の男爵家を発展させ気が付けば大陸一豊かで最強の小さい王国を起こしていた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















