あなたにおすすめの小説

奪う人たちは放っておいて私はお菓子を焼きます
タマ マコト
ファンタジー
伯爵家の次女クラリス・フォン・ブランディエは、姉ヴィオレッタと常に比較され、「控えめでいなさい」と言われ続けて育った。やがて姉の縁談を機に、母ベアトリスの価値観の中では自分が永遠に“引き立て役”でしかないと悟ったクラリスは、父が遺した領都の家を頼りに自ら家を出る。
領都の端でひとり焼き菓子を焼き始めた彼女は、午後の光が差す小さな店『午後の窓』を開く。そこへ、紅茶の香りに異様に敏感な謎の青年が現れる。名も素性も明かさぬまま、ただ菓子の味を静かに言い当てる彼との出会いが、クラリスの新しい人生をゆっくりと動かし始める。
奪い合う世界から離れ、比較されない場所で生きると決めた少女の、静かな再出発の物語。

このわたくしが、婚約者になるはずでしょう!?
碧井 汐桜香
恋愛
先々代の王女が降嫁したほどの筆頭公爵家に産まれた、ルティアヌール公爵家の唯一の姫、メリアッセンヌ。
産まれた時から当然に王子と結婚すると本人も思っていたし、周囲も期待していた。
それは、身内のみと言っても、王宮で行われる王妃主催のお茶会で、本人が公言しても不敬とされないほどの。
そのためにメリアッセンヌ自身も大変努力し、勉学に励み、健康と美容のために毎日屋敷の敷地内をランニングし、外国語も複数扱えるようになった。
ただし、実際の内定発表は王子が成年を迎えた時に行うのが慣習だった。
第一王子を“ルーおにいさま”と慕う彼女に、第一王子は婚約内定発表の数日前、呼び出しをかける。
別の女性を隣に立たせ、「君とは結婚できない」と告げる王子の真意とは?
7話完結です

婚約破棄は構いませんが、私が管理していたものは全て引き上げます 〜成金伯爵家令嬢は、もう都合のいい婚約者ではありません〜
藤原遊
ファンタジー
成金と揶揄される伯爵家の令嬢である私は、
名門だが実情はジリ貧な公爵家の令息と婚約していた。
公爵家の財政管理、契約、商会との折衝――
そのすべてを私が担っていたにもかかわらず、
彼は隣国の王女と結ばれることになったと言い出す。
「まあ素敵。では、私たちは円満に婚約解消ですね」
そう思っていたのに、返ってきたのは
「婚約破棄だ。君の不出来が原因だ」という言葉だった。
……はぁ?
有責で婚約破棄されるのなら、
私が“善意で管理していたもの”を引き上げるのは当然でしょう。
資金も、契約も、人脈も――すべて。
成金伯爵家令嬢は、
もう都合のいい婚約者ではありません。

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~
放浪人
恋愛
「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」
大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。
生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。
しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。
「すまない。私は父としての責任を果たす」
かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。
だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。
これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。
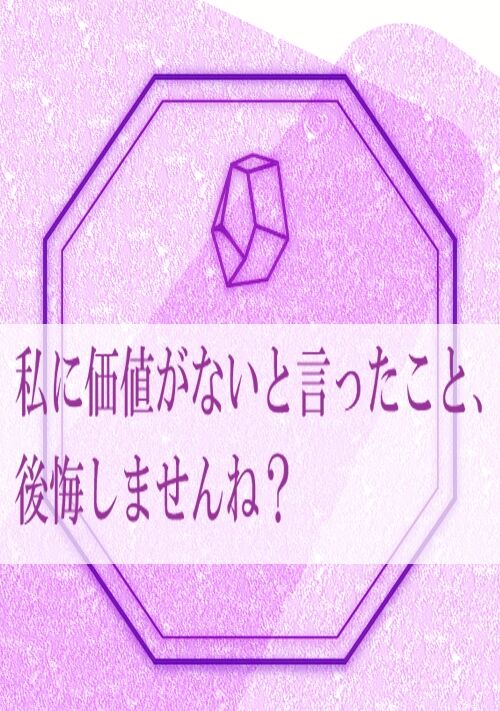
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。

無魔力の令嬢、婚約者に裏切られた瞬間、契約竜が激怒して王宮を吹き飛ばしたんですが……
タマ マコト
ファンタジー
王宮の祝賀会で、無魔力と蔑まれてきた伯爵令嬢エリーナは、王太子アレクシオンから突然「婚約破棄」を宣告される。侍女上がりの聖女セレスが“新たな妃”として選ばれ、貴族たちの嘲笑がエリーナを包む。絶望に胸が沈んだ瞬間、彼女の奥底で眠っていた“竜との契約”が目を覚まし、空から白銀竜アークヴァンが降臨。彼はエリーナの涙に激怒し、王宮を半壊させるほどの力で彼女を守る。王国は震え、エリーナは自分が竜の真の主であるという運命に巻き込まれていく。

婚約破棄された竜好き令嬢は黒竜様に溺愛される。残念ですが、守護竜を捨てたこの国は滅亡するようですよ
水無瀬
ファンタジー
竜が好きで、三度のご飯より竜研究に没頭していた侯爵令嬢の私は、婚約者の王太子から婚約破棄を突きつけられる。
それだけでなく、この国をずっと守護してきた黒竜様を捨てると言うの。
黒竜様のことをずっと研究してきた私も、見せしめとして処刑されてしまうらしいです。
叶うなら、死ぬ前に一度でいいから黒竜様に会ってみたかったな。
ですが、私は知らなかった。
黒竜様はずっと私のそばで、私を見守ってくれていたのだ。
残念ですが、守護竜を捨てたこの国は滅亡するようですよ?

公爵令嬢は婚約破棄に微笑む〜かつて私を見下した人たちよ、後悔する準備はできてる?〜
sika
恋愛
婚約者に裏切られ、社交界で笑い者にされた公爵令嬢リリアナ。
しかし彼女には、誰も知らない“逆転の手札”があった。
婚約破棄を機に家を離れ、彼女は隣国の次期宰相に招かれる。
そこで出会った冷徹な青年公爵・アルヴェンが、彼女を本気で求めるようになり——?
誰もが後悔し、彼女だけが幸福を掴む“ざまぁ”と“溺愛”が交錯する、痛快な王道ラブロマンス!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















