1 / 4
第1章:婚約破棄と“白い結婚”
しおりを挟む
朝の光が差し込む窓辺に、静寂が満ちていた。
空には雲ひとつなく、青く澄んだ空気が広がっている。どこか祝福のようにすら思える穏やかな陽の中で、私はひとり鏡台の前に立っていた。
名はクレスタ・エルバンシュ。
エルバンシュ侯爵家の令嬢として、私は幼少の頃から厳格な教育を受けてきた。貴族令嬢としての作法、礼節、言葉遣い──。社交界に出る日を夢見ながらも、当主である父の教えを守り、決して恥をかかぬよう日々を過ごしてきた。
そして、長く続いていた王太子アレクシオン殿下との婚約。
名門侯爵家と王太子殿下の婚約は、周囲から“この国で最も相応しい結びつき”と言われ、誰もが祝福していた。いつか私は、王太子妃になり、将来は王妃となる。その道を、疑いなく歩むと信じていたのだ。
しかし──。
その未来は、ある日、唐突に失われた。
「クレスタ、すまない。僕は本当に愛する人と結ばれたいんだ」
王太子殿下は私にそう告げ、私を見つめた。その目には、かつて向けられていた優しさではなく、どこか思い詰めたような決意が宿っていた。
「愛する人……とは」
問い返す私に、アレクシオン殿下は言ったのだ。平民の少女ミーナという女性を愛している、と。
聞けば、近頃の殿下は城下町の視察や慈善活動に積極的に赴き、その過程で出会った少女に心惹かれたらしい。私との婚約は“義務”であり、真実の愛はその平民の少女にこそあるのだ、と。
私は、一瞬、言葉を失った。
愛のない結婚は確かに苦しいものかもしれない。けれど、王家と侯爵家の婚約は国家にとって重要な意味を持つ。
その責任を投げ出して、私との縁を切り捨てるというのか。
怒りというよりは、現実感のない虚脱感。ずっと続いていた“当然の未来”が、あっけなく崩れ去る。私はただ、それを見ているしかなかった。
けれど、その場で涙を流すことはしなかった。
泣いてすがったところで、殿下の意思が変わることはないだろう。むしろ私がみっともなく取り乱したとあっては、エルバンシュ家の誇りにも傷がつく。
「……わかりました」
それだけを答えるのが、精いっぱいだった。
それからしばらくして、アレクシオン殿下は宮廷を通じて正式に私との婚約破棄を宣言した。
名門侯爵家の令嬢と婚約破棄してまで、平民の少女を娶ると決めた殿下の行動は、瞬く間に王都全体の話題となった。
ある者は“愛に生きる王太子”と美談のように語り、ある者は“無責任すぎる”と非難する。どちらにせよ、私の元には同情や興味本位の視線が降りかかり、それを避ける日々が続いた。
そして、“元婚約者”という立場になった私には、冷たい噂の視線もある。
「平民の少女に負けた可哀想な令嬢」
「王太子様から愛されなかった女」
そんな囁きを耳にするたび、胸がきゅっと締めつけられる。
でも、それでも私は泣かない。私はエルバンシュの令嬢として誇りを持ち、決して人前では卑屈にならないと決めていたから。
転機は、私が宮廷を極力避けていたある日のこと。
父、エルバンシュ侯爵が慌ただしい足取りで私の部屋を訪れた。
「クレスタ……今度、新たな縁談の話が浮上している。おまえはどう思う?」
そう切り出した父の顔には、深い苦悩の色が浮かんでいた。
聞けば、相手は男爵家の当主。名をジークフリート・アルグレインといい、まだ二十代後半の若き男爵だという。
だが、彼にはあまり良い噂はない。
「冷血」「非情」「近寄りがたい」──そんな評判ばかり。
なのになぜ、わざわざ私との結婚を希望しているのか。誰もその真意を測りかねているらしい。
「政略結婚、ということか……」
私はそう呟いた。いや、実際には政略というより“救済”に近いのかもしれない。婚約破棄で立場を落とした私を、ある程度の地位を持つ男爵家が迎え入れる。それによって私の家の面目は守られ、相手にも何らかのメリットがあるのだろう。
父も、ジークフリート男爵が私を道具扱いしているわけではなさそうだ、と言うが、それはただの希望的観測にすぎない。
それでも、私に断るという選択肢はほぼなかった。
王家との結びつきが消えた今、侯爵家の名誉を守る道は限られている。父の顔を思えば、この話に乗るほうが得策だろう。私自身も、自宅に閉じこもり“元婚約者”のまま生きていくことに意味を見出せなくなっていた。
こうして、私はあっさりと第二の結婚話を受け入れた。
「わかりました、お父様。お引き受けいたします」
そう告げたとき、父は複雑そうな表情をしながら、それでもほっと安堵の息を吐いた。
「すまない、クレスタ……。だが、おまえの幸せを願っていることに嘘はない」
「わかっています」
私も、父を責めることはできない。誰もがこの嵐の中で必死なのだ。
それから一週間も経たないうちに、私とジークフリート・アルグレインとの結婚が決まった。
本来ならもっと時間をかけて婚約期間を経るものだが、焦るように急いでいるのはアルグレイン男爵家のほうらしい。理由はわからない。
ただ一つ言えるのは、私に選択肢などない、ということ。
私が生きていくうえで、今はこの政略結婚を受け入れ、次の人生を歩む以外の道が見えないのだから。
さて、そうして迎えた結婚式当日。
私はこう考えていた。「きっとこれは、一種の仮面夫婦にすぎない」。
噂に聞く男爵は冷酷で非情。周囲に対しても近寄りがたい雰囲気を纏っているという。
私もまた、彼に心を預ける気はない。これは飽くまで政略結婚。形式だけのもの。それでいい。お互い干渉せずにいられれば、それでかまわない……。
結婚式は小規模ながらも滞りなく行われた。
王太子殿下との婚約時には、より大掛かりで華やかな式を準備するはずだったが、今回の式はそれに比べてはるかに質素だ。出席者も、エルバンシュ侯爵家の関係者や、アルグレイン男爵家のごく身内の人々だけ。
だが、その小ささがむしろ私にはありがたかった。大勢の人々から好奇の視線を向けられることもなく、無駄に疲弊しないですむ。
祭壇に立つ私の隣で、ジークフリート・アルグレインは微かに口を結んでいた。
浅黒い髪、やや吊り上がった鋭い瞳、引き締まった体躯。まるで訓練を積んだ軍人のような印象を受ける。なるほど、噂の「冷血」とやらは、その鋭い目つきから来るものかもしれない。
表情には感情の起伏が乏しく、私に対しても特別な感情を見せることはなかった。ただ、時折私を見やるとき、その瞳の奥で何かが揺れているようにも感じる……が、気のせいかもしれない。
「……これより、アルグレイン男爵ジークフリートと、エルバンシュ侯爵令嬢クレスタの婚姻を宣言する」
司祭の重々しい声に続き、誓いの言葉を交わす。
ジークフリートは終始無表情で、私もまた努めて感情を表に出さず、ただ毅然と振る舞った。
式の途中、ちらりと参列席に目をやると、父が瞳を潤ませていた。隣には私の妹がいて、こちらを心配そうに見ている。
けれど、祝いの場であるはずなのに、そこに心からの幸福感はない。私の胸にも、ぽっかりとした空洞が広がるばかりだった。
そして、式が終わると同時に、私は“アルグレイン男爵夫人”となった。
かつて王太子妃になるはずだった身でありながら、今こうして、別の相手の妻になるという現実。何とも言えない寂寞を感じるが、それでも運命を受け入れるしかない。
私は心を固く閉ざしながら、新居であるアルグレイン邸に向かった。
アルグレイン邸は、男爵領の管理を行いつつ、王都でも屋敷を構えている。その一つがこの街はずれにあるらしい。
黒鉄の門をくぐると、石造りの重厚な建物が迎えてくれた。外観こそ質実剛健だが、敷地はかなり広い。さすがに貴族の邸宅だけあり、周囲には手入れされた庭木が整然と立ち並んでいた。
玄関では、使用人たちが一列に並んで私たちを出迎えた。
「お帰りなさいませ、旦那様。そして……奥様」
皆、一斉に頭を下げる。その様子には一切の乱れがなく、きびきびとした雰囲気だ。
ジークフリートは特に言葉を発することもなく、一度だけうなずいた。私も「はじめまして」とだけ挨拶する。
私は勝手に“もっと冷たい空気”を想像していたが、使用人たちは意外なほど親切そうな目で私を見つめていた。
(……なんだろう、この感じ)
私は戸惑いを覚えながらも、素直に微笑みを返してしまう。
その後、私たちは新婚の“お披露目”として、邸宅内を一通り案内された。
重厚な内装の応接室や書斎、奥に控える秘書室、広々としたダイニングとキッチン。食器の数々も上等で、少なくとも男爵家としてはかなり裕福な部類だろうとわかる。
「こちらが、奥様のお部屋になります」
侍女のひとりが案内してくれた部屋は、私が普段暮らす寝室であるらしい。薄いピンク色のカーテンと柔らかな絨毯が敷き詰められ、家具類には上品な彫刻が施されている。まるで私好みに合わせたかのような優美な雰囲気だった。
「あの……こちらのお部屋は、もとからこういう内装だったのですか?」
思わず尋ねると、侍女は微笑んで首を横に振る。
「いえ、数日前まで空き部屋でしたので、一から準備いたしました。旦那様が『暖色系で落ち着ける雰囲気にしてほしい』とおっしゃったのですよ」
「……ジークフリート様が?」
少なからず驚きだった。冷血だとばかり噂されている夫が、私のために気を配ったというのだろうか。いや、政略結婚とわかっていても、最低限の礼儀だと言われればそれまでかもしれない。
だが、これは正直、礼儀としては上出来すぎる対応だ。
私はなんとも言えない気持ちで、その部屋を見回した。
確かに、私が好む淡い色合いと、落ち着いた調度品の組み合わせ。かといって派手すぎない。気味が悪いほどに私の好みが反映されているのを感じる。
心のどこかで「こんなはずはない」という疑念が渦巻きつつも、「これは何かの間違いかも」と思わずにいられない。
夕方になり、使用人が夕食の準備を整えたと知らせに来た。
私は侍女の助けを借りて、軽く着替えてから食堂へと向かう。
そこには先に席についていたジークフリートの姿があった。
私の足音に気づいたのか、彼は顔を上げて目が合う。ほんの一瞬だけ、ジークフリートの眉がわずかに和らいだように見えたが、すぐに無表情に戻ってしまった。
夕食は豪華すぎず、けれど充実したメニューが並んでいた。ローストした肉料理や新鮮な野菜、温かいスープに香り高いパン。デザートには優しい甘さのフルーツタルトが添えられている。
私は黙々とナイフとフォークを動かしながら、ちらりとジークフリートの様子をうかがった。すると彼は、私がタルトにフォークを入れるのを確認してから、低く静かな声で尋ねてきた。
「……そのタルトの味はどうだ?」
「え?」
思いがけない問いかけに、つい声が裏返りそうになってしまう。
「気に入らなければ、別の菓子も用意させる」
「いえ、美味しいです」
私は慌てて答える。事実、とても美味しかった。フルーツの香りが口いっぱいに広がって、程よい甘さが疲れを和らげてくれるようだった。
すると、ジークフリートはそれ以上何も言わなかった。ただ、その表情がほんのわずか緩んだようにも見える。
(……本当に無表情だな、この人)
内心、そう思わずにはいられない。だが、少なくとも嫌味を言ってくるわけでもないし、私を追い詰めるような態度もない。
むしろ、私が喜んでいることを少しだけ嬉しく思っているような──そんな雰囲気すら感じるのは気のせいなのだろうか。
食事を終える頃には、日はすっかり暮れていた。
侍女が明日の予定を説明しに来る。どうやら明日から早速、男爵夫人としての挨拶回りが始まるらしい。もっとも、男爵家というのは公爵や侯爵に比べれば下の階級。挨拶回りの相手も数は多くないと聞く。
「ですが、奥様のことをお待ちしている方も多いかと。皆さまにぜひ、ご挨拶をなさってくださいね」
まるで歓迎されているかのような言い方だったが、それが真実なのかはわからない。
私は小さくうなずいて了承した。
夕食後、廊下を歩いて寝室へ戻ろうとしたとき、ジークフリートが私の名を呼び止める。
「……クレスタ」
初めて直接、名前を呼ばれた気がして、なぜか胸が微かに高鳴る。でもその理由は自分でもわからない。
「な、なんでしょうか」
振り向いた私に、ジークフリートは言いにくそうに切り出した。
「その……何か困ったことがあれば、遠慮なく言ってくれ。できることなら、手を貸す」
「え……」
一瞬、私は返事に詰まった。あまりに意外な申し出だったからだ。
「私との結婚は、そちらにとっても思惑があってのことでしょう? お気遣いは無用ですわ」
「そういうわけでもない。……確かに俺には俺の事情があるが、君を道具扱いするつもりはない」
それだけ言うと、ジークフリートはどこか急いでいるように踵を返した。
私はその背中を見送りながら、言い表せない胸のざわめきを抱え込む。
政略結婚、それも急いで決まった結婚。私はてっきり、もっと無関心に扱われると思っていた。けれど、そうではないらしい。
“道具扱いするつもりはない”と言ったあの言葉は、どれほどの真実味を伴っているのだろう。
私は少し疲れを覚えながら、自室に戻り、ゆっくりとドレスを脱いで眠りの支度を始めた。
ベッドに横たわると、柔らかな寝具が私の身体を優しく包む。
それなのに、不思議と眠れない。
頭に浮かぶのは、王太子殿下のこと。そして今こうして私の夫となったジークフリートのこと。
(私は、どうなるんだろう……)
心配の種は尽きないが、今日はもう考えないようにしよう。私は無理やり目を閉じた。
翌朝、侍女が起こしに来てから、早速挨拶回りが始まった。
アルグレイン邸の車に乗って、私は幾つかの男爵領近くの貴族家や関連施設を訪れる。ジークフリートは同席しない。どうやら公務のようなものがあって別行動らしい。
冷血と噂される男爵がどんな公務をしているのか、いまいち想像がつかないが、私はそれを深く問わないことにした。
(お互い干渉し合わないのが“白い結婚”の基本でしょう?)
自分自身に言い聞かせつつも、昨夜の言葉が胸をかすめる。
数軒の家を回ってわかったのは、皆、想像以上に私に対して好意的だということだった。
「これまでアルグレイン男爵は公務で忙しかったですからね。新しい奥様がいらして、とても嬉しいですわ」
「男爵様は無口ですが、領地の管理は素晴らしいのですよ」
口々にそう語られ、まるで男爵は慕われているようだ。冷血とか非情とかいった噂とは、ずいぶん印象が違う。
そういった褒め言葉を聞くたびに、私の胸にかすかな違和感が生じる。
(冷酷と言われているのは、ただの表向きの噂にすぎないのかしら……?)
もっとも、それだけでジークフリートに完全な信頼を寄せられるわけではない。だが、少なくとも理不尽な暴力や冷遇を加えられることはなさそうだ、と安堵もする。
午後、挨拶回りを終えて屋敷に戻った頃には、私は予想以上に疲れを感じていた。
意外なほど歓迎ムードであることは確かだが、やはり一日に何軒も訪問するのは骨が折れる。特に、王太子との婚約破棄が世間に知れ渡った後だけに、無遠慮な視線や質問を浴びせられたりもした。
「王太子殿下とのこと、本当にお気の毒でしたね」
「でも、真実の愛に生きる王太子殿下、素敵ですよね!」
表向きは私を労わるように見せながら、好奇心丸出しで探りを入れてくる人間もいる。そんなとき、私はひたすら微笑を湛えることしかできない。
屋敷に帰り着いた途端、私は部屋着に着替えてベッドに倒れ込んだ。
頭の中に浮かぶのは、王太子殿下と彼が選んだミーナなる平民の少女のこと。
国中の噂によれば、彼らはまるで“伝説の恋人”のようにもてはやされているらしい。私を振り捨てるという大罪を犯してまでも選んだ愛は、美化され、熱狂的に称賛されているようだ。
(どうでもいい……早く忘れてしまいたいのに)
それでも、私の心は完全には割り切れない。長年、未来を夢見た相手だったのだから。
そのまま小一時間ほど休んでいると、コンコン、と部屋の扉がノックされた。
「失礼いたします。奥様、そろそろお茶はいかがでしょう?」
侍女がトレイを下げて入ってくる。湯気の立つハーブティーと、ほかほかの焼き菓子の香りが鼻をくすぐった。
「ありがとうございます……助かります」
私はベッドから起き上がり、侍女に勧められるまま椅子に腰掛けた。
「奥様、少し顔色が優れないようにお見受けします。今日はごゆっくりお休みになられたほうが……」
「ええ、そうしたいところなんだけど」
そう言いかけた瞬間、またも扉がノックされる。そして開いたのは、意外にもジークフリートだった。
「……疲れているのか?」
侍女が慌てて頭を下げ、部屋から出ていく。私たち二人きりになると、ジークフリートは少し居心地悪そうに視線をさまよわせていた。
「ええ、少し挨拶回りがハードだったものですから」
私は苦笑いを浮かべる。
「……無理をさせてすまない。初日から詰め込みすぎだったかもしれない」
その言葉に、私は少し驚いた。公務の合間とはいえ、私の体調を気遣ってくれるとは思わなかったのだ。
「お気になさらずに。夫人として役目を果たすのは当然ですわ」
強がり半分、本音半分。私はそう付け加える。
だが、ジークフリートの眉は微かに寄ったままだ。
「……午後の予定はキャンセルにしよう。しばらく休むといい」
「はい……? でも、予定はどうするのですか?」
突然の申し出に、私は戸惑った。
「公務なら、俺だけで事足りる。夫人がいつも必要というわけでもない。必要なら改めて日程を組み直す」
あまりにも簡潔に言い切るので、私は思わず言葉を失ってしまう。男爵家の仕事を軽視しているわけではないのだろう。けれど、私には意外すぎるほど私優先の判断だ。
「……わかりました。少し、甘えさせていただきますね」
礼を言うと、彼は短くうなずいた。
ジークフリートが去った後、私はもう一度ベッドに横になった。
頭の中で、さまざまな思いが交錯する。
「冷血」「非情」……そんな噂が信じられないほど、彼は私を気遣ってくれる。もしかしたら、ただの打算かもしれない。私を味方につけることで、何らかの政治的なメリットがあるのかもしれない。
けれど、それを差し引いても、これほどまでに優しい言葉をかけられるのは初めてだ。
私は穏やかなハーブティーの香りに包まれながら、いつの間にかまどろみ始めていた。
そうして迎えた夜。今夜の夕食は、ジークフリートが公務で遅くなるということで、私は先に済ませてしまった。
部屋に戻って手持ちの本を眺めていると、またも控えめなノックの音がする。
侍女かと思って「どうぞ」と答えると、ドアから顔を覗かせたのはジークフリートだった。
「もう休むところか?」
「いえ、本を読んでいただけです。どうかしましたか?」
妙に遠慮がちに部屋の中を見回す彼の姿に、私は不思議な印象を抱く。
「……明日、少し遠方の館に行く用事がある。おまえは休んでいてくれ」
「……私を連れて行く必要はない、ということでしょうか」
「そうだ。せっかく嫁いできてもらったのに、こんなことばかりで悪い。……本当に、疲れを癒すことを優先してくれ」
そこまで言う彼の眼差しは、どこか真剣だ。その瞳を見ていると、私は微妙に胸がざわつく。
(私を何だと思っているのだろう?)
私をただの政略結婚の駒にするなら、もっとぞんざいに扱ったっていいはずだ。最低限の礼は守りつつも、深くは干渉しない──それが“白い結婚”の基本形ではないか。
なのにジークフリートは、私を雑に扱わないばかりか、気遣いさえ見せてくる。
戸惑いつつも、悪い気はしない。……むしろ、心のどこかで安堵している自分に気づいてしまう。
「わかりました。お気遣いに感謝します」
私が頭を下げると、彼は少しだけ表情を和らげたようだった。
「何かあれば、使用人に言いつけるなり、手紙を出すなりしてくれ。戻りは明後日夜になる予定だが……」
そう言いながらも、彼はまだ何か言いたげだ。
私はしばらく待ったが、結局、彼は言葉を飲み込んで「それでは」とだけ言い残し、部屋を出ていった。
ひとり残された部屋で、私は溜息をつく。
これがただの“優しい人”なら、素直に好意を抱いていたかもしれない。
けれど私は、あまりにも大きな失望を婚約破棄で味わったばかりだ。誰かを心から信じることなど、そう簡単にはできない。
まして、私たちは“白い結婚”のはず。深入りせず、干渉しない。それが取り決めだと思っていたのに、ジークフリートはそれとは異なる行動をとっている。
(彼はいったい、私に何を望んでいるの……?)
それから二日ほど、ジークフリートが留守にしている間、私は屋敷でゆっくりと過ごすことになった。
侍女に勧められて屋敷内を散策したり、庭の花を観賞したり。使用人たちは皆、礼儀正しく、私に敬意を払ってくれている。
お茶の時間になると、私が好むフルーツタルトや焼き菓子を用意してくれた。
(これは……ジークフリート様が指示しているのだろうか)
そう思わず考えてしまうほど、私の好みに合わせたものが揃っていた。
そのうちに、ジークフリートの留守を不思議に思う使用人に訊ねてみた。
「旦那様は普段、どんなお仕事をなさっているのですか?」
すると返ってきた答えは、「領地の視察や、王都との折衝など、公的な用事を多くこなされている」というもの。
そのあたりは男爵として当然の職務とも思えるが、彼が王宮内でどの程度の影響力を持つのかはわからない。
ただ、使用人が口を濁すことからも、何かしら人に話せないような職務があるのかもしれない……そんな勘繰りが頭をかすめる。
三日目の夕刻、ジークフリートは予定どおり屋敷に戻ってきた。
私は玄関ホールで出迎え、軽く会釈する。
「おかえりなさいませ。お疲れになったでしょう」
「……ああ」
簡潔な返事だが、彼は私の姿を認めると、少しだけ目を細めたように見えた。
「明日、少し一緒に出掛けないか。領内の視察の一環だが、緑が多くて空気がうまい場所だ」
唐突な誘いに、私は思わずきょとんとしてしまう。
「私も……同行してよいのですか?」
「夫婦である以上、無論だ。無理にとは言わないが、気分転換になると思う」
確かに、屋敷にこもってばかりよりはいいかもしれない。ここ最近の慌ただしさで、私も少しは気晴らしがしたい気分になっていた。
「それでは、ご一緒させていただきます」
そう答えると、ジークフリートは再び控えめにうなずいた。
こうして始まった“新婚生活”は、私の想像していたものとあまりにもかけ離れている。
“冷酷”なはずの夫は、私を気遣ってくれる。使用人たちは皆、私に親切にしてくれる。
もちろん、まだ心の内をさらけ出せるほど打ち解けてはいない。ジークフリートも多くを語る人ではなく、基本は無口だ。
けれど、その沈黙は不快なものではない……という不思議。
一方、王都では、私の婚約破棄と王太子殿下の平民との恋が引き続き話題になっているらしい。
“真実の愛を貫く王太子アレクシオン殿下と美しき平民ミーナの物語”──誰が言い出したのか、そんな噂までまことしやかに広まっているという。
複雑な気分だが、ここにいて私がそれをどうこう言っても始まらない。
私はただ、流れに身を任せるように、生きていくしかなかった。
“白い結婚”でいい──そう思っていたはずが、ジークフリートの優しさは私の心を乱す。
この先、私は彼とどう向き合えばいいのか。
王太子殿下とのことを完全に忘れられる日は来るのだろうか。
そんな疑問を抱えながらも、私は新たな人生の序章を歩み出していた。
--
空には雲ひとつなく、青く澄んだ空気が広がっている。どこか祝福のようにすら思える穏やかな陽の中で、私はひとり鏡台の前に立っていた。
名はクレスタ・エルバンシュ。
エルバンシュ侯爵家の令嬢として、私は幼少の頃から厳格な教育を受けてきた。貴族令嬢としての作法、礼節、言葉遣い──。社交界に出る日を夢見ながらも、当主である父の教えを守り、決して恥をかかぬよう日々を過ごしてきた。
そして、長く続いていた王太子アレクシオン殿下との婚約。
名門侯爵家と王太子殿下の婚約は、周囲から“この国で最も相応しい結びつき”と言われ、誰もが祝福していた。いつか私は、王太子妃になり、将来は王妃となる。その道を、疑いなく歩むと信じていたのだ。
しかし──。
その未来は、ある日、唐突に失われた。
「クレスタ、すまない。僕は本当に愛する人と結ばれたいんだ」
王太子殿下は私にそう告げ、私を見つめた。その目には、かつて向けられていた優しさではなく、どこか思い詰めたような決意が宿っていた。
「愛する人……とは」
問い返す私に、アレクシオン殿下は言ったのだ。平民の少女ミーナという女性を愛している、と。
聞けば、近頃の殿下は城下町の視察や慈善活動に積極的に赴き、その過程で出会った少女に心惹かれたらしい。私との婚約は“義務”であり、真実の愛はその平民の少女にこそあるのだ、と。
私は、一瞬、言葉を失った。
愛のない結婚は確かに苦しいものかもしれない。けれど、王家と侯爵家の婚約は国家にとって重要な意味を持つ。
その責任を投げ出して、私との縁を切り捨てるというのか。
怒りというよりは、現実感のない虚脱感。ずっと続いていた“当然の未来”が、あっけなく崩れ去る。私はただ、それを見ているしかなかった。
けれど、その場で涙を流すことはしなかった。
泣いてすがったところで、殿下の意思が変わることはないだろう。むしろ私がみっともなく取り乱したとあっては、エルバンシュ家の誇りにも傷がつく。
「……わかりました」
それだけを答えるのが、精いっぱいだった。
それからしばらくして、アレクシオン殿下は宮廷を通じて正式に私との婚約破棄を宣言した。
名門侯爵家の令嬢と婚約破棄してまで、平民の少女を娶ると決めた殿下の行動は、瞬く間に王都全体の話題となった。
ある者は“愛に生きる王太子”と美談のように語り、ある者は“無責任すぎる”と非難する。どちらにせよ、私の元には同情や興味本位の視線が降りかかり、それを避ける日々が続いた。
そして、“元婚約者”という立場になった私には、冷たい噂の視線もある。
「平民の少女に負けた可哀想な令嬢」
「王太子様から愛されなかった女」
そんな囁きを耳にするたび、胸がきゅっと締めつけられる。
でも、それでも私は泣かない。私はエルバンシュの令嬢として誇りを持ち、決して人前では卑屈にならないと決めていたから。
転機は、私が宮廷を極力避けていたある日のこと。
父、エルバンシュ侯爵が慌ただしい足取りで私の部屋を訪れた。
「クレスタ……今度、新たな縁談の話が浮上している。おまえはどう思う?」
そう切り出した父の顔には、深い苦悩の色が浮かんでいた。
聞けば、相手は男爵家の当主。名をジークフリート・アルグレインといい、まだ二十代後半の若き男爵だという。
だが、彼にはあまり良い噂はない。
「冷血」「非情」「近寄りがたい」──そんな評判ばかり。
なのになぜ、わざわざ私との結婚を希望しているのか。誰もその真意を測りかねているらしい。
「政略結婚、ということか……」
私はそう呟いた。いや、実際には政略というより“救済”に近いのかもしれない。婚約破棄で立場を落とした私を、ある程度の地位を持つ男爵家が迎え入れる。それによって私の家の面目は守られ、相手にも何らかのメリットがあるのだろう。
父も、ジークフリート男爵が私を道具扱いしているわけではなさそうだ、と言うが、それはただの希望的観測にすぎない。
それでも、私に断るという選択肢はほぼなかった。
王家との結びつきが消えた今、侯爵家の名誉を守る道は限られている。父の顔を思えば、この話に乗るほうが得策だろう。私自身も、自宅に閉じこもり“元婚約者”のまま生きていくことに意味を見出せなくなっていた。
こうして、私はあっさりと第二の結婚話を受け入れた。
「わかりました、お父様。お引き受けいたします」
そう告げたとき、父は複雑そうな表情をしながら、それでもほっと安堵の息を吐いた。
「すまない、クレスタ……。だが、おまえの幸せを願っていることに嘘はない」
「わかっています」
私も、父を責めることはできない。誰もがこの嵐の中で必死なのだ。
それから一週間も経たないうちに、私とジークフリート・アルグレインとの結婚が決まった。
本来ならもっと時間をかけて婚約期間を経るものだが、焦るように急いでいるのはアルグレイン男爵家のほうらしい。理由はわからない。
ただ一つ言えるのは、私に選択肢などない、ということ。
私が生きていくうえで、今はこの政略結婚を受け入れ、次の人生を歩む以外の道が見えないのだから。
さて、そうして迎えた結婚式当日。
私はこう考えていた。「きっとこれは、一種の仮面夫婦にすぎない」。
噂に聞く男爵は冷酷で非情。周囲に対しても近寄りがたい雰囲気を纏っているという。
私もまた、彼に心を預ける気はない。これは飽くまで政略結婚。形式だけのもの。それでいい。お互い干渉せずにいられれば、それでかまわない……。
結婚式は小規模ながらも滞りなく行われた。
王太子殿下との婚約時には、より大掛かりで華やかな式を準備するはずだったが、今回の式はそれに比べてはるかに質素だ。出席者も、エルバンシュ侯爵家の関係者や、アルグレイン男爵家のごく身内の人々だけ。
だが、その小ささがむしろ私にはありがたかった。大勢の人々から好奇の視線を向けられることもなく、無駄に疲弊しないですむ。
祭壇に立つ私の隣で、ジークフリート・アルグレインは微かに口を結んでいた。
浅黒い髪、やや吊り上がった鋭い瞳、引き締まった体躯。まるで訓練を積んだ軍人のような印象を受ける。なるほど、噂の「冷血」とやらは、その鋭い目つきから来るものかもしれない。
表情には感情の起伏が乏しく、私に対しても特別な感情を見せることはなかった。ただ、時折私を見やるとき、その瞳の奥で何かが揺れているようにも感じる……が、気のせいかもしれない。
「……これより、アルグレイン男爵ジークフリートと、エルバンシュ侯爵令嬢クレスタの婚姻を宣言する」
司祭の重々しい声に続き、誓いの言葉を交わす。
ジークフリートは終始無表情で、私もまた努めて感情を表に出さず、ただ毅然と振る舞った。
式の途中、ちらりと参列席に目をやると、父が瞳を潤ませていた。隣には私の妹がいて、こちらを心配そうに見ている。
けれど、祝いの場であるはずなのに、そこに心からの幸福感はない。私の胸にも、ぽっかりとした空洞が広がるばかりだった。
そして、式が終わると同時に、私は“アルグレイン男爵夫人”となった。
かつて王太子妃になるはずだった身でありながら、今こうして、別の相手の妻になるという現実。何とも言えない寂寞を感じるが、それでも運命を受け入れるしかない。
私は心を固く閉ざしながら、新居であるアルグレイン邸に向かった。
アルグレイン邸は、男爵領の管理を行いつつ、王都でも屋敷を構えている。その一つがこの街はずれにあるらしい。
黒鉄の門をくぐると、石造りの重厚な建物が迎えてくれた。外観こそ質実剛健だが、敷地はかなり広い。さすがに貴族の邸宅だけあり、周囲には手入れされた庭木が整然と立ち並んでいた。
玄関では、使用人たちが一列に並んで私たちを出迎えた。
「お帰りなさいませ、旦那様。そして……奥様」
皆、一斉に頭を下げる。その様子には一切の乱れがなく、きびきびとした雰囲気だ。
ジークフリートは特に言葉を発することもなく、一度だけうなずいた。私も「はじめまして」とだけ挨拶する。
私は勝手に“もっと冷たい空気”を想像していたが、使用人たちは意外なほど親切そうな目で私を見つめていた。
(……なんだろう、この感じ)
私は戸惑いを覚えながらも、素直に微笑みを返してしまう。
その後、私たちは新婚の“お披露目”として、邸宅内を一通り案内された。
重厚な内装の応接室や書斎、奥に控える秘書室、広々としたダイニングとキッチン。食器の数々も上等で、少なくとも男爵家としてはかなり裕福な部類だろうとわかる。
「こちらが、奥様のお部屋になります」
侍女のひとりが案内してくれた部屋は、私が普段暮らす寝室であるらしい。薄いピンク色のカーテンと柔らかな絨毯が敷き詰められ、家具類には上品な彫刻が施されている。まるで私好みに合わせたかのような優美な雰囲気だった。
「あの……こちらのお部屋は、もとからこういう内装だったのですか?」
思わず尋ねると、侍女は微笑んで首を横に振る。
「いえ、数日前まで空き部屋でしたので、一から準備いたしました。旦那様が『暖色系で落ち着ける雰囲気にしてほしい』とおっしゃったのですよ」
「……ジークフリート様が?」
少なからず驚きだった。冷血だとばかり噂されている夫が、私のために気を配ったというのだろうか。いや、政略結婚とわかっていても、最低限の礼儀だと言われればそれまでかもしれない。
だが、これは正直、礼儀としては上出来すぎる対応だ。
私はなんとも言えない気持ちで、その部屋を見回した。
確かに、私が好む淡い色合いと、落ち着いた調度品の組み合わせ。かといって派手すぎない。気味が悪いほどに私の好みが反映されているのを感じる。
心のどこかで「こんなはずはない」という疑念が渦巻きつつも、「これは何かの間違いかも」と思わずにいられない。
夕方になり、使用人が夕食の準備を整えたと知らせに来た。
私は侍女の助けを借りて、軽く着替えてから食堂へと向かう。
そこには先に席についていたジークフリートの姿があった。
私の足音に気づいたのか、彼は顔を上げて目が合う。ほんの一瞬だけ、ジークフリートの眉がわずかに和らいだように見えたが、すぐに無表情に戻ってしまった。
夕食は豪華すぎず、けれど充実したメニューが並んでいた。ローストした肉料理や新鮮な野菜、温かいスープに香り高いパン。デザートには優しい甘さのフルーツタルトが添えられている。
私は黙々とナイフとフォークを動かしながら、ちらりとジークフリートの様子をうかがった。すると彼は、私がタルトにフォークを入れるのを確認してから、低く静かな声で尋ねてきた。
「……そのタルトの味はどうだ?」
「え?」
思いがけない問いかけに、つい声が裏返りそうになってしまう。
「気に入らなければ、別の菓子も用意させる」
「いえ、美味しいです」
私は慌てて答える。事実、とても美味しかった。フルーツの香りが口いっぱいに広がって、程よい甘さが疲れを和らげてくれるようだった。
すると、ジークフリートはそれ以上何も言わなかった。ただ、その表情がほんのわずか緩んだようにも見える。
(……本当に無表情だな、この人)
内心、そう思わずにはいられない。だが、少なくとも嫌味を言ってくるわけでもないし、私を追い詰めるような態度もない。
むしろ、私が喜んでいることを少しだけ嬉しく思っているような──そんな雰囲気すら感じるのは気のせいなのだろうか。
食事を終える頃には、日はすっかり暮れていた。
侍女が明日の予定を説明しに来る。どうやら明日から早速、男爵夫人としての挨拶回りが始まるらしい。もっとも、男爵家というのは公爵や侯爵に比べれば下の階級。挨拶回りの相手も数は多くないと聞く。
「ですが、奥様のことをお待ちしている方も多いかと。皆さまにぜひ、ご挨拶をなさってくださいね」
まるで歓迎されているかのような言い方だったが、それが真実なのかはわからない。
私は小さくうなずいて了承した。
夕食後、廊下を歩いて寝室へ戻ろうとしたとき、ジークフリートが私の名を呼び止める。
「……クレスタ」
初めて直接、名前を呼ばれた気がして、なぜか胸が微かに高鳴る。でもその理由は自分でもわからない。
「な、なんでしょうか」
振り向いた私に、ジークフリートは言いにくそうに切り出した。
「その……何か困ったことがあれば、遠慮なく言ってくれ。できることなら、手を貸す」
「え……」
一瞬、私は返事に詰まった。あまりに意外な申し出だったからだ。
「私との結婚は、そちらにとっても思惑があってのことでしょう? お気遣いは無用ですわ」
「そういうわけでもない。……確かに俺には俺の事情があるが、君を道具扱いするつもりはない」
それだけ言うと、ジークフリートはどこか急いでいるように踵を返した。
私はその背中を見送りながら、言い表せない胸のざわめきを抱え込む。
政略結婚、それも急いで決まった結婚。私はてっきり、もっと無関心に扱われると思っていた。けれど、そうではないらしい。
“道具扱いするつもりはない”と言ったあの言葉は、どれほどの真実味を伴っているのだろう。
私は少し疲れを覚えながら、自室に戻り、ゆっくりとドレスを脱いで眠りの支度を始めた。
ベッドに横たわると、柔らかな寝具が私の身体を優しく包む。
それなのに、不思議と眠れない。
頭に浮かぶのは、王太子殿下のこと。そして今こうして私の夫となったジークフリートのこと。
(私は、どうなるんだろう……)
心配の種は尽きないが、今日はもう考えないようにしよう。私は無理やり目を閉じた。
翌朝、侍女が起こしに来てから、早速挨拶回りが始まった。
アルグレイン邸の車に乗って、私は幾つかの男爵領近くの貴族家や関連施設を訪れる。ジークフリートは同席しない。どうやら公務のようなものがあって別行動らしい。
冷血と噂される男爵がどんな公務をしているのか、いまいち想像がつかないが、私はそれを深く問わないことにした。
(お互い干渉し合わないのが“白い結婚”の基本でしょう?)
自分自身に言い聞かせつつも、昨夜の言葉が胸をかすめる。
数軒の家を回ってわかったのは、皆、想像以上に私に対して好意的だということだった。
「これまでアルグレイン男爵は公務で忙しかったですからね。新しい奥様がいらして、とても嬉しいですわ」
「男爵様は無口ですが、領地の管理は素晴らしいのですよ」
口々にそう語られ、まるで男爵は慕われているようだ。冷血とか非情とかいった噂とは、ずいぶん印象が違う。
そういった褒め言葉を聞くたびに、私の胸にかすかな違和感が生じる。
(冷酷と言われているのは、ただの表向きの噂にすぎないのかしら……?)
もっとも、それだけでジークフリートに完全な信頼を寄せられるわけではない。だが、少なくとも理不尽な暴力や冷遇を加えられることはなさそうだ、と安堵もする。
午後、挨拶回りを終えて屋敷に戻った頃には、私は予想以上に疲れを感じていた。
意外なほど歓迎ムードであることは確かだが、やはり一日に何軒も訪問するのは骨が折れる。特に、王太子との婚約破棄が世間に知れ渡った後だけに、無遠慮な視線や質問を浴びせられたりもした。
「王太子殿下とのこと、本当にお気の毒でしたね」
「でも、真実の愛に生きる王太子殿下、素敵ですよね!」
表向きは私を労わるように見せながら、好奇心丸出しで探りを入れてくる人間もいる。そんなとき、私はひたすら微笑を湛えることしかできない。
屋敷に帰り着いた途端、私は部屋着に着替えてベッドに倒れ込んだ。
頭の中に浮かぶのは、王太子殿下と彼が選んだミーナなる平民の少女のこと。
国中の噂によれば、彼らはまるで“伝説の恋人”のようにもてはやされているらしい。私を振り捨てるという大罪を犯してまでも選んだ愛は、美化され、熱狂的に称賛されているようだ。
(どうでもいい……早く忘れてしまいたいのに)
それでも、私の心は完全には割り切れない。長年、未来を夢見た相手だったのだから。
そのまま小一時間ほど休んでいると、コンコン、と部屋の扉がノックされた。
「失礼いたします。奥様、そろそろお茶はいかがでしょう?」
侍女がトレイを下げて入ってくる。湯気の立つハーブティーと、ほかほかの焼き菓子の香りが鼻をくすぐった。
「ありがとうございます……助かります」
私はベッドから起き上がり、侍女に勧められるまま椅子に腰掛けた。
「奥様、少し顔色が優れないようにお見受けします。今日はごゆっくりお休みになられたほうが……」
「ええ、そうしたいところなんだけど」
そう言いかけた瞬間、またも扉がノックされる。そして開いたのは、意外にもジークフリートだった。
「……疲れているのか?」
侍女が慌てて頭を下げ、部屋から出ていく。私たち二人きりになると、ジークフリートは少し居心地悪そうに視線をさまよわせていた。
「ええ、少し挨拶回りがハードだったものですから」
私は苦笑いを浮かべる。
「……無理をさせてすまない。初日から詰め込みすぎだったかもしれない」
その言葉に、私は少し驚いた。公務の合間とはいえ、私の体調を気遣ってくれるとは思わなかったのだ。
「お気になさらずに。夫人として役目を果たすのは当然ですわ」
強がり半分、本音半分。私はそう付け加える。
だが、ジークフリートの眉は微かに寄ったままだ。
「……午後の予定はキャンセルにしよう。しばらく休むといい」
「はい……? でも、予定はどうするのですか?」
突然の申し出に、私は戸惑った。
「公務なら、俺だけで事足りる。夫人がいつも必要というわけでもない。必要なら改めて日程を組み直す」
あまりにも簡潔に言い切るので、私は思わず言葉を失ってしまう。男爵家の仕事を軽視しているわけではないのだろう。けれど、私には意外すぎるほど私優先の判断だ。
「……わかりました。少し、甘えさせていただきますね」
礼を言うと、彼は短くうなずいた。
ジークフリートが去った後、私はもう一度ベッドに横になった。
頭の中で、さまざまな思いが交錯する。
「冷血」「非情」……そんな噂が信じられないほど、彼は私を気遣ってくれる。もしかしたら、ただの打算かもしれない。私を味方につけることで、何らかの政治的なメリットがあるのかもしれない。
けれど、それを差し引いても、これほどまでに優しい言葉をかけられるのは初めてだ。
私は穏やかなハーブティーの香りに包まれながら、いつの間にかまどろみ始めていた。
そうして迎えた夜。今夜の夕食は、ジークフリートが公務で遅くなるということで、私は先に済ませてしまった。
部屋に戻って手持ちの本を眺めていると、またも控えめなノックの音がする。
侍女かと思って「どうぞ」と答えると、ドアから顔を覗かせたのはジークフリートだった。
「もう休むところか?」
「いえ、本を読んでいただけです。どうかしましたか?」
妙に遠慮がちに部屋の中を見回す彼の姿に、私は不思議な印象を抱く。
「……明日、少し遠方の館に行く用事がある。おまえは休んでいてくれ」
「……私を連れて行く必要はない、ということでしょうか」
「そうだ。せっかく嫁いできてもらったのに、こんなことばかりで悪い。……本当に、疲れを癒すことを優先してくれ」
そこまで言う彼の眼差しは、どこか真剣だ。その瞳を見ていると、私は微妙に胸がざわつく。
(私を何だと思っているのだろう?)
私をただの政略結婚の駒にするなら、もっとぞんざいに扱ったっていいはずだ。最低限の礼は守りつつも、深くは干渉しない──それが“白い結婚”の基本形ではないか。
なのにジークフリートは、私を雑に扱わないばかりか、気遣いさえ見せてくる。
戸惑いつつも、悪い気はしない。……むしろ、心のどこかで安堵している自分に気づいてしまう。
「わかりました。お気遣いに感謝します」
私が頭を下げると、彼は少しだけ表情を和らげたようだった。
「何かあれば、使用人に言いつけるなり、手紙を出すなりしてくれ。戻りは明後日夜になる予定だが……」
そう言いながらも、彼はまだ何か言いたげだ。
私はしばらく待ったが、結局、彼は言葉を飲み込んで「それでは」とだけ言い残し、部屋を出ていった。
ひとり残された部屋で、私は溜息をつく。
これがただの“優しい人”なら、素直に好意を抱いていたかもしれない。
けれど私は、あまりにも大きな失望を婚約破棄で味わったばかりだ。誰かを心から信じることなど、そう簡単にはできない。
まして、私たちは“白い結婚”のはず。深入りせず、干渉しない。それが取り決めだと思っていたのに、ジークフリートはそれとは異なる行動をとっている。
(彼はいったい、私に何を望んでいるの……?)
それから二日ほど、ジークフリートが留守にしている間、私は屋敷でゆっくりと過ごすことになった。
侍女に勧められて屋敷内を散策したり、庭の花を観賞したり。使用人たちは皆、礼儀正しく、私に敬意を払ってくれている。
お茶の時間になると、私が好むフルーツタルトや焼き菓子を用意してくれた。
(これは……ジークフリート様が指示しているのだろうか)
そう思わず考えてしまうほど、私の好みに合わせたものが揃っていた。
そのうちに、ジークフリートの留守を不思議に思う使用人に訊ねてみた。
「旦那様は普段、どんなお仕事をなさっているのですか?」
すると返ってきた答えは、「領地の視察や、王都との折衝など、公的な用事を多くこなされている」というもの。
そのあたりは男爵として当然の職務とも思えるが、彼が王宮内でどの程度の影響力を持つのかはわからない。
ただ、使用人が口を濁すことからも、何かしら人に話せないような職務があるのかもしれない……そんな勘繰りが頭をかすめる。
三日目の夕刻、ジークフリートは予定どおり屋敷に戻ってきた。
私は玄関ホールで出迎え、軽く会釈する。
「おかえりなさいませ。お疲れになったでしょう」
「……ああ」
簡潔な返事だが、彼は私の姿を認めると、少しだけ目を細めたように見えた。
「明日、少し一緒に出掛けないか。領内の視察の一環だが、緑が多くて空気がうまい場所だ」
唐突な誘いに、私は思わずきょとんとしてしまう。
「私も……同行してよいのですか?」
「夫婦である以上、無論だ。無理にとは言わないが、気分転換になると思う」
確かに、屋敷にこもってばかりよりはいいかもしれない。ここ最近の慌ただしさで、私も少しは気晴らしがしたい気分になっていた。
「それでは、ご一緒させていただきます」
そう答えると、ジークフリートは再び控えめにうなずいた。
こうして始まった“新婚生活”は、私の想像していたものとあまりにもかけ離れている。
“冷酷”なはずの夫は、私を気遣ってくれる。使用人たちは皆、私に親切にしてくれる。
もちろん、まだ心の内をさらけ出せるほど打ち解けてはいない。ジークフリートも多くを語る人ではなく、基本は無口だ。
けれど、その沈黙は不快なものではない……という不思議。
一方、王都では、私の婚約破棄と王太子殿下の平民との恋が引き続き話題になっているらしい。
“真実の愛を貫く王太子アレクシオン殿下と美しき平民ミーナの物語”──誰が言い出したのか、そんな噂までまことしやかに広まっているという。
複雑な気分だが、ここにいて私がそれをどうこう言っても始まらない。
私はただ、流れに身を任せるように、生きていくしかなかった。
“白い結婚”でいい──そう思っていたはずが、ジークフリートの優しさは私の心を乱す。
この先、私は彼とどう向き合えばいいのか。
王太子殿下とのことを完全に忘れられる日は来るのだろうか。
そんな疑問を抱えながらも、私は新たな人生の序章を歩み出していた。
--
0
あなたにおすすめの小説

政略結婚した夫に殺される夢を見た翌日、裏庭に深い穴が掘られていました
伊織
恋愛
夫に殺される夢を見た。
冷え切った青い瞳で見下ろされ、血に染まった寝室で命を奪われる――あまりにも生々しい悪夢。
夢から覚めたセレナは、政略結婚した騎士団長の夫・ルシアンとの冷えた関係を改めて実感する。
彼は宝石ばかり買う妻を快く思っておらず、セレナもまた、愛のない結婚に期待などしていなかった。
だがその日、夢の中で自分が埋められていたはずの屋敷の裏庭で、
「深い穴を掘るために用意されたようなスコップ」を目にしてしまう。
これは、ただの悪夢なのか。
それとも――現実に起こる未来の予兆なのか。
闇魔法を受け継ぐ公爵令嬢と、彼女を疎む騎士団長。
不穏な夢から始まる、夫婦の物語。
男女の恋愛小説に挑戦しています。
楽しんでいただけたら嬉しいです。

私を簡単に捨てられるとでも?―君が望んでも、離さない―
喜雨と悲雨
恋愛
私の名前はミラン。街でしがない薬師をしている。
そして恋人は、王宮騎士団長のルイスだった。
二年前、彼は魔物討伐に向けて遠征に出発。
最初は手紙も返ってきていたのに、
いつからか音信不通に。
あんなにうっとうしいほど構ってきた男が――
なぜ突然、私を無視するの?
不安を抱えながらも待ち続けた私の前に、
突然ルイスが帰還した。
ボロボロの身体。
そして隣には――見知らぬ女。
勝ち誇ったように彼の隣に立つその女を見て、
私の中で何かが壊れた。
混乱、絶望、そして……再起。
すがりつく女は、みっともないだけ。
私は、潔く身を引くと決めた――つもりだったのに。
「私を簡単に捨てられるとでも?
――君が望んでも、離さない」
呪いを自ら解き放ち、
彼は再び、執着の目で私を見つめてきた。
すれ違い、誤解、呪い、執着、
そして狂おしいほどの愛――
二人の恋のゆくえは、誰にもわからない。
過去に書いた作品を修正しました。再投稿です。

「お前みたいな卑しい闇属性の魔女など側室でもごめんだ」と言われましたが、私も殿下に嫁ぐ気はありません!
野生のイエネコ
恋愛
闇の精霊の加護を受けている私は、闇属性を差別する国で迫害されていた。いつか私を受け入れてくれる人を探そうと夢に見ていたデビュタントの舞踏会で、闇属性を差別する王太子に罵倒されて心が折れてしまう。
私が国を出奔すると、闇精霊の森という場所に住まう、不思議な男性と出会った。なぜかその男性が私の事情を聞くと、国に与えられた闇精霊の加護が消滅して、国は大混乱に。
そんな中、闇精霊の森での生活は穏やかに進んでいく。
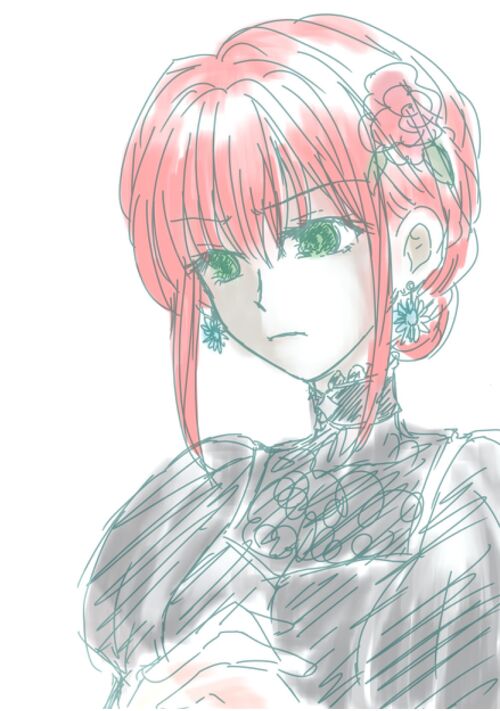
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

婚約破棄して泥を投げつけた元婚約者が「無能」と笑う中、光り輝く幼なじみの王子に掠め取られました。
ムラサメ
恋愛
「お前のような無能、我が家には不要だ。今すぐ消えろ!」
婚約者・エドワードのために身を粉にして尽くしてきたフィオナは、卒業パーティーの夜、雨の中に放り出される。
泥にまみれ、絶望に沈む彼女の前に現れたのは、かつての幼なじみであり、今や国中から愛される「黄金の王子」シリルだった。
「やっと見つけた。……ねえ、フィオナ。あんなゴミに君を傷つけさせるなんて、僕の落ち度だね」
汚れを厭わずフィオナを抱き上げたシリルは、彼女を自分の屋敷へと連れ帰る。
「自分には価値がない」と思い込むフィオナを、シリルは異常なまでの執着と甘い言葉で、とろけるように溺愛し始めて――。
一方で、フィオナを捨てたエドワードは気づいていなかった。
自分の手柄だと思っていた仕事も、領地の繁栄も、すべてはフィオナの才能によるものだったということに。
ボロボロになっていく元婚約者。美しく着飾られ、シリルの腕の中で幸せに微笑むフィオナ。
「僕の星を捨てた報い、たっぷりと受けてもらうよ?」
圧倒的な光を放つ幼なじみによる、最高に華やかな逆転劇がいま始まる!

王子様への置き手紙
あおき華
恋愛
フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯
小説家になろうにも掲載しています。

聖女の座を追われた私は田舎で畑を耕すつもりが、辺境伯様に「君は畑担当ね」と強引に任命されました
さら
恋愛
王都で“聖女”として人々を癒やし続けてきたリーネ。だが「加護が弱まった」と政争の口実にされ、無慈悲に追放されてしまう。行き場を失った彼女が選んだのは、幼い頃からの夢――のんびり畑を耕す暮らしだった。
ところが辺境の村にたどり着いた途端、無骨で豪胆な領主・辺境伯に「君は畑担当だ」と強引に任命されてしまう。荒れ果てた土地、困窮する領民たち、そして王都から伸びる陰謀の影。追放されたはずの聖女は、鍬を握り、祈りを土に注ぐことで再び人々に希望を芽吹かせていく。
「畑担当の聖女さま」と呼ばれながら笑顔を取り戻していくリーネ。そして彼女を真っ直ぐに支える辺境伯との距離も、少しずつ近づいて……?
畑から始まるスローライフと、不器用な辺境伯との恋。追放された聖女が見つけた本当の居場所は、王都の玉座ではなく、土と緑と温かな人々に囲まれた辺境の畑だった――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















