2 / 4
第2章:仮面夫婦のはずが、なぜか優しい旦那様
しおりを挟む
翌朝。
私──クレスタ・エルバンシュ、もといアルグレイン男爵夫人は、夫であるジークフリート・アルグレインの誘いに従い、彼とともに屋敷を出た。
行き先は王都から離れた、アルグレイン男爵領の端にある小さな村。緑豊かな場所で、空気も美味しいらしい。
もともと領地視察という名目なのだが、どうやらジークフリートは私に気晴らしをさせようと思ってくれているらしく、「あまり難しく考えずに来い」と言ってくれた。
朝早くの出発だったけれど、馬車で移動している間、退屈することはなかった。
道すがら見える景色は、まだ私が知らない王国の姿を映し出している。緩やかな丘や、野を駆ける小川、遠くに見える山並み。
高い建物が並ぶ王都の眺望とはまた違う、のどかな自然の美しさが心を落ち着かせてくれた。
視察というには簡素だが、近衛らしき護衛が数名同行している。彼らは馬に乗り、馬車の周りを警護していた。
ジークフリートの冷酷な噂を聞いたときは「護衛にも厳しく当たるのだろうか」と思っていたけれど、皆、彼を尊敬しているような面持ちだ。
道中、ジークフリートが短く声をかけると、護衛たちは「はい、旦那様」「承知しました」ときびきび返事をする。その様子には、命令への忠実さ以上に、強い信頼が感じられた。
(やはり、あの“冷血”という噂は、何か別の理由で流されたものなのかしら……)
最近になって、私はそんな疑問が頭から離れない。
今のところ、ジークフリートが私に乱暴な態度をとることは一度もない。むしろ、私の体調を気遣ったり、好みのスイーツを用意してくれたりと、優しさが目立つくらいだ。
どれもこれも計算や打算から来る偽りなのかもしれないし、あるいは本心なのかもしれない。
わからないまま、時間だけがゆっくりと流れている。
「どうした? 疲れたか」
馬車の揺れが少し大きくなった時、ジークフリートは私に気づかいを見せた。
私は軽く首を振る。
「いえ、大丈夫です。馬車の旅は初めてではありませんし、特に問題はありませんわ」
「ならいい」
淡々とした返事。しかし、その横顔は少しだけ心配そうに見える。
こうした小さな優しさに、私は戸惑うばかりだ。
しばらくすると、馬車は小さな村の入口に差し掛かった。
広がる畑と、点在する素朴な家々。あちこちに鶏や家畜の姿が見え、遠くから牛の鳴き声が聞こえる。王都の華やかさとは対極にあるのどかな風景だった。
村人たちは、馬車の姿に気づくと、慌ただしく出てきて一列に並ぶ。どうやら男爵の視察を歓迎しているらしい。
私は馬車の窓からその様子を見つつ、「これが領主への儀礼なのだな」と密かに納得する。
馬車が止まり、ジークフリートが先に降り立つ。続いて私も侍女の手を借りながら地面に足をつけた。
硬い土の感触が伝わってくる。靴に多少の埃がかかっても気にしない。
ジークフリートは村長らしき老人に声をかけた。
「みな、変わりないか」
「はい、男爵様。特に大きな不作もなく、今年も作物は順調でございます」
老人は深々と頭を下げ、恭しく挨拶をする。その横で、村の人々が口々に「奥様もいらしたのですね」と私を見て微笑んでいた。
私は少し照れくさくなりながらも、にこやかに会釈を返す。
(ここでは“男爵夫人”として立ち振る舞わなくては)
婚約破棄の痛手を引きずっているとはいえ、今の私には新しい立場がある。皆に愛想よく笑顔を向け、「よろしくお願いしますわ」と柔らかな口調で応じると、村の人々は一気に和んだ様子を見せた。
村長の案内で、私たちは畑のほうへと向かう。
穀物や野菜がすくすくと育っているのがわかる。今は青々とした段階で、もう少しで収穫期を迎えるそうだ。
「今年は雨の巡りも悪くなく、害虫も少ないんです。男爵様の助成金があったおかげで、新しい農具も揃えることができました」
村長が感謝の言葉を述べるたびに、私は横目でジークフリートを見やる。彼は無表情だが、どこか穏やかに頷いているように見えた。
(こういう地道な支援が、彼の“本当の姿”なのかしら……)
王太子殿下と婚約していた頃は、私も領地経営についてある程度の知識を仕込まれていたが、まさかこうして“自分が夫人として携わる”立場になるとは思っていなかった。
私の隣で、ジークフリートはふと足を止め、育ちかけの作物に視線を落とす。
すると、近くで作業していた若い農夫が「あの……男爵様、もしよろしければこの畑をもう少し見ていただけませんか?」と声をかけてきた。
「これまでは害虫対策に昔ながらの方法を使ってきたのですが……最近、新しい種子を入手しまして、育て方が少し違うようなのです」
農夫が説明する内容は、私にはやや専門的すぎて理解しづらい。しかし、ジークフリートは真剣な面持ちで聞き入り、時折うなずきながら的確な質問を投げかけている。
私は驚く。男爵と言っても、貴族がここまで農業に精通しているとは思わなかったのだ。
「なるほど、種子の出どころが違えば土や水の管理も違うだろう。村長にも協力を仰いで、試験区を作るのがいい。結果を見ながら徐々に広げていけば、リスクは抑えられる」
ジークフリートの提案を聞いて、農夫は目を輝かせた。
「ありがとうございます、男爵様! その方法なら安心です!」
こうして領地の農民と直接やり取りし、具体的な指示を出している姿……。私は、思わず見とれてしまった。
人の話をちゃんと聞き、適切な助言を与える。これが本当に“冷血”などと呼ばれる人物だろうか?
「クレスタ、少しこちらへ来てくれ」
名前を呼ばれて、はっと我に返る。
「はい……どうかしましたか?」
ジークフリートが指し示したのは、片隅にある花畑のような場所。野菜や穀物とは別に、色とりどりの花が咲き乱れていた。
「ここは何のための花畑なのですか?」
興味を引かれ、私は村長に尋ねる。すると村長は笑顔で答えた。
「ここは昔、土が痩せていた場所なのです。野菜を育てるには不向きで……でも、花なら強い品種を植えられるということで、こうして観賞用の畑にしておりましてね。観光というほど大げさなものではありませんが、村人が少しでも楽しめるようにと、男爵様が資金を出してくださいました」
「へえ……素敵ですね」
私がそう返すと、ジークフリートは足元の花を一瞥し、「今度、改良品種の種を手に入れる予定だ。色ももっと増やせるかもしれない」と呟いた。
彼は決して感情豊かに語るわけではないが、その言葉の裏にある優しさが、何となく伝わってくる。
作業を続ける農民たちに挨拶を済ませたあと、私たちは村の小さな集会所のような建物に向かった。そこで村長や数名の代表と雑談を交えながら、改めて領内の問題点や予算の話をする。
私はほとんど聞き役に徹していたが、たまにジークフリートが「クレスタ、おまえの意見はどうだ?」と話を振ってくれることがあった。
さすがに農業関連の専門的なことは口を挟めないが、かつて父のもとで学んだ知識から、少しは役立ちそうなことを話すと、村長たちは感心した様子を見せてくれた。
「男爵様がお迎えになったご夫人は、大変お聡明でいらっしゃるのですね」
ある女性がそう言ってくれたとき、私は恐縮しながら微笑む。
ジークフリートは表情こそ変わらないが、視線の端がわずかに柔らいだ気がした。
(まるで誇らしげに思っているような……?)
自意識過剰かもしれないけれど、そんな風にも感じてしまう。胸が妙にくすぐったい。
昼を少し回ったあたりで、私たちは村で用意された素朴な食事をいただくことになった。採れたての野菜を煮込んだスープや、自家製のパン、ハーブで香りづけした鶏肉など、王都の華やかな料理とはまた違う素朴な味わいだ。
「大したおもてなしはできませんが、どうかお召し上がりくださいませ」
「いえ、とても美味しそうですわ」
私はそう言ってスープを口に運ぶ。じんわりと旨味が広がり、心も身体もほっと温まる。
王宮で出されるような贅沢な食事ではないけれど、これはこれでまた別の美味しさがある。
ジークフリートも無言でスープをすすっているが、悪い顔はしていない。
彼も王都育ちの貴族としては珍しいほど、質素な場所に慣れているのか、特に嫌そうな素振りを見せない。
淡々としつつも、こういう田舎の生活にちゃんと寄り添えるのは、ある意味で貴重な資質だろう。
私はその横顔を眺めながら、不意に心に湧いた疑問を押し殺す。
(あなたは、いったい何者なの……ジークフリート)
食事を終え、ひと通りの視察を済ませる頃には、すっかり日が傾き始めていた。
「では皆、また近いうちに状況を見に来る。何かあれば連絡を寄こせ」
ジークフリートがそう言うと、村長や農民たちは一斉に頭を下げる。
私は名残惜しさを感じながら、優しい笑顔で手を振り、「ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします」と告げた。
村の空気は穏やかで、暖かかった。心のどこかがふっと軽くなったような気がする。
馬車に戻ると、すでに護衛が帰り支度を整えていた。
「男爵様、奥様、お疲れになったでしょう。王都まで戻る間、どうかゆっくりお休みください」
使用人の一人がそう言って馬車の扉を開いてくれる。私はジークフリートとともに中へと乗り込んだ。
馬車がゆるやかに走り始め、村の風景が遠ざかっていく。
柔らかな夕陽が射し込み、車内はほんのりとオレンジ色に染まっていた。
しばらく黙って窓の外を眺めていた私に、ジークフリートが声をかける。
「どうだった?」
短い問いかけ。けれど、何を聞かれているのかはすぐわかった。
私は素直に感想を述べる。
「はい、とても良かったです。村の方々はみんな温かくて、自然も綺麗で……。それに、ジークフリート様がこんなふうに領地をちゃんと見ておられるなんて、少し意外でした」
「意外、か」
無表情の彼が、すっと目を伏せる。
私は慌てて言い訳のように続ける。
「失礼を承知で言えば、男爵様の評判は“冷酷”でしたから……。でも今日見た限り、そんな風には思えなかったものですから」
するとジークフリートは、微かに苦笑のような表情を浮かべた。普段の仏頂面からは想像しにくい表情に、私は少しだけ驚く。
「……俺にも事情がある。あまり深く考えるな」
「事情、ですか」
「そうだ。いずれ話す機会があるかもしれない。だが今はそれで勘弁してほしい」
そう言われると、それ以上追及できない。
馬車の揺れが続く中、私たちは再び沈黙する。
外を見れば、夕陽が赤く染まり、夜の気配がゆっくりと迫ってきていた。
やがてジークフリートは窓に目をやり、ふっと息をつく。
「おまえが嫌でなければ、またこうして領地を見に行ってくれないか」
「わたしと……ですか?」
「ああ。村人たちも、おまえが来るなら歓迎してくれるだろうし、領内を知っておくことは悪くないだろう」
私は少し迷ったが、心のどこかで嬉しさを感じていた。
――私をただの飾りにするつもりはないのかもしれない。
白い結婚という言葉から連想した“形だけ”の夫婦関係ではなく、少なくとも領主とその夫人として協力していく姿勢を示してくれている。
「……わかりました。よろこんでご一緒します」
そう答えると、ジークフリートは黙ったまま頷いた。微かに、安心したような気配が伝わってくるのは気のせいだろうか。
その夜、屋敷に戻った私たちは別々に夕食をとった。
ジークフリートには別の用事があるらしく、私は先に済ませて部屋でくつろいでいた。
ひとりの時間に浸っていると、村での光景が頭をよぎる。
私に親しみをもって接してくれた人々、素朴な食事の温かさ、そして真剣に領民の意見に耳を傾けるジークフリートの姿……。
――何もかもが、私の知る“貴族の常識”を少しだけ超えているように感じた。
その後、就寝の準備をしていると、侍女が「旦那様がお呼びです」と声をかけてきた。
「私を……? こんな夜更けに何の用かしら」
少し疑問を抱きつつも、私はガウンを羽織り、侍女の案内でジークフリートの部屋へと向かう。
途中、廊下の窓から月が見えた。澄んだ夜空に浮かぶ月は、やけに明るく感じられる。
(何だか、少し胸が高鳴ってる……)
自分でも理由がわからない。だけど、妙に緊張してしまう。
ノックをして部屋に入ると、そこは広めの書斎だった。机や本棚が整然と並び、壁には地図や書類らしきものが貼られている。
ジークフリートは机の向こうに立っていた。私の顔を見ると、ほんの少し表情がほころぶ。
「夜分にすまない。少し見てほしいものがあってな」
そう言って彼が差し出したのは、一枚の紙。近寄ってみると、そこには領地の地形図といくつかの施設が書き込まれていた。
「これは……」
「男爵領の略図だ。今日行った村の位置も載っている。今後、視察を増やすにあたって、おまえにも地理を把握しておいてほしいと思ってな」
私は頷き、紙を両手で持って眺める。そこには複数の村や町が点在しており、川の流れや森林の位置まで詳しく記されている。
「こんなに広い領地を、ジークフリート様は一人で管理しておられるのですか?」
「正確には、補佐役や役人と分担している。俺がやるのはあくまで方針決定と重要事項の監督。それでも、少しでも時間ができれば、直に足を運んだほうが早いこともある」
その言葉に、再び“冷血”との噂は何だったのかと思わずにいられない。
「ありがとう。こういう地図があると、とてもわかりやすいですわ」
私が率直に感謝を述べると、ジークフリートは視線を地図に落としながら、ぽつりと呟いた。
「……おまえが王太子との婚約を破棄されたと聞いたとき、正直、驚いた。だが、こうして迎え入れてみて思うのは、おまえは想像以上に強く、そして優秀だということだ」
不意打ちの言葉に、私は目を見開く。
「そ、それは……。わたしはただ、侯爵家の教育を受けてきただけですし。優秀なんてとんでもない」
少し照れくさい。ジークフリートは私を褒めようとしているのか?
「いや、王太子の件があったにもかかわらず、ひるまずに今日のように立ち回れるのは大したものだ。俺には、おまえが“王族の花嫁”として育ってきた誇りと強さが見える」
そのまっすぐな言葉に、私は困惑しながらも、どこかくすぐったい気持ちになった。
(こんな風に素直に褒められたのは、いつ以来だろう……)
王太子殿下と婚約していた頃、表向きに褒められることはあっても、真意を感じられた記憶はあまりない。
それを思うと、ジークフリートの言葉はどこか実感がこもっている気がした。
沈黙が少しだけ続く。紙を手渡されたまま、私はその地図を見下ろし、彼の言葉の余韻を感じていた。
そのとき、ジークフリートがふっと顔を上げ、私をまっすぐ見据える。
「クレスタ……おまえは、ここに来てから不満はないか」
「え……不満、ですか?」
予想外の問いに、私は瞬きする。
不満と言われても、思いつくものは特にない。確かに結婚自体は政略めいていたし、王太子殿下に捨てられた屈辱もまだ完全には晴れない。
けれど、アルグレイン邸での暮らしそのものには、なんの不満も感じていなかった。
「いえ、特にありませんわ。むしろ、わたしなどにはもったいないくらいの待遇を受けている気がします」
「そうか……よかった」
彼はそれだけ言うと、少しホッとしたような顔をした。
普段は沈着冷静で、こちらに余計な感情を見せないジークフリートが、こうしてはっきり安心した様子を示すのは珍しい。
(私のことを、ちゃんと気にかけてくれている?)
なんだか気恥ずかしくなって、私はわざと視線を地図に戻す。
するとジークフリートが小さく咳払いをして、「……遅い時間に呼び出して悪かったな。地図は好きなときに眺めてくれ。おまえが興味を持ってくれれば、領地のことも理解が早いだろう」
そう言いながら机の引き出しを開け、別の書類も取り出す。
「ここに記してあるのは領内の収支や人口、作物の収穫量などだ。一度に目を通すのは大変かもしれないが、時間があるときにでも眺めてみてくれ」
「は、はい……」
膨大な量に見えるが、私は嫌ではない。むしろ、少しやる気が湧いてきた自分に気づく。
ジークフリートと二人きりの書斎。微かにインクの香りと紙の匂いが混じり合う。
静かな夜の空気の中、私たちはしばし言葉を交わし続けた。領地経営のこと、視察で気づいたこと、そして今日感じたこと……。
これがいわゆる“夫婦の会話”なのかはわからない。けれど、一緒に同じ目線で何かを考える時間があるのは、思いのほか悪い気がしない。
――ふと、扉の外から控えめなノックの音がした。
「失礼します。旦那様、奥様。夜も更けてまいりましたので……」
侍女が控えめに促すようにしてくる。気づけば、もう時計の針は深夜に近いところを指していた。
「もうこんな時間。……ごめんなさい、わたしが話し込んでしまって」
私が急いで書類をまとめようとすると、ジークフリートは首を横に振る。
「いや、こちらこそ引き止めて悪かった。今夜はもう休め。また続きは明日にでも聞くとしよう」
そう言って書類を受け取りながら、ジークフリートはちらりと私をうかがう。
その視線に、私はどこかドキリとした。書斎の明かりが薄暗いせいか、彼の瞳がやけに深く感じられる。
「……おやすみなさい、ジークフリート様」
どうにかそれだけを言って、私は書斎を後にした。胸の鼓動が少し早まっているのを感じながら、自分の部屋へと戻る。
翌日から、私は少しずつアルグレイン男爵領の資料に目を通すようになった。
詳しいところまではわからなくても、地図や数値データを眺めるのは意外と楽しい。村での光景を思い出しながら、「ここではこんな作物が育つのか」「この川はあの川に繋がっているのか」とイメージを膨らませる。
ジークフリートからの簡単な説明もあり、私の中で領地の様子が少しずつ形作られていくようだった。
そんなある日、私は使用人が持ってきた新聞を何気なく読んでいて、思わず硬直してしまう。
――そこには、王太子アレクシオン殿下と平民の少女ミーナが、王宮で親密な様子を見せているという記事が載っていたのだ。
“民衆に慕われるミーナ嬢” “王太子の真実の愛” “婚約破棄から始まるロマンティックな恋”――そういった見出しが紙面を踊っている。
無責任な記事だとわかっていても、胸が苦しくなるのを抑えられない。私への配慮など微塵もない、あまりに能天気な報道に苛立ちすら覚える。
あの夜、王太子から婚約破棄を告げられた光景が、ふいに脳裏に甦る。
“僕は本当に愛する人と結ばれたいんだ”――そんな身勝手な言葉。
それを王都の人々は“美談”のように取り上げている。
たしかに、平民の少女を選んだ王太子は、一部からは非難されていると聞くが、それ以上に恋愛至上主義的な若者層から熱烈に支持されているとも聞く。
(……馬鹿らしい。そんなきれいごとで済むわけがないのに)
さらに記事を読み進めると、“ミーナ嬢は絶世の美女で性格も清らか”、“王太子殿下は彼女を慈しみ守り抜くと宣言”など、まるでおとぎ話のように書き連ねられていた。
(私の立場は何だったの? 長年の婚約者はこんな形で捨てられ、それでも彼らは“真実の愛”を謳っている……)
胸が熱くなり、新聞を握りしめる手が震える。忘れたつもりでも、傷はまだ癒えていない。
こんな記事を見るたびに、私は自分の感情が揺さぶられるのだ。
ドアがノックされ、私は慌てて新聞をたたむ。
「どうぞ」
声をかけると、入ってきたのはジークフリートだった。彼の瞳が、私の手にある新聞に一瞬目を止める。
「……その記事を読んでいたのか」
「ええ。ちょうど目に入っただけで、特別な意味はありませんわ」
嘘ではない。けれど、嘘でもある。私は内心で動揺を抑えようと必死だった。
ジークフリートは私の表情をそっとうかがい、静かな声で問いかける。
「……辛いのなら、無理に読む必要はない」
ドキリとする。私は彼に弱みを見せたくないと思い、そっけなく返す。
「大丈夫ですわ。もう過ぎたことですから」
――しかし、自分の声が少しだけ震えていたことに気づいて、慌てて言葉を噤んだ。
ジークフリートはそんな私の様子を見ても、あえて何も言わない。ただ、その瞳には静かな憂いが宿っている気がする。
しばらく気まずい沈黙が漂ったあと、彼は私の机上にある領地の資料に視線を向けて話題を変えた。
「領地の資料、どこまで読んだ?」
「あ……ええと、このあたりです。人口動態と、主要農作物のデータは大体目を通しました」
「そうか。じゃあ、それを踏まえておまえが気になった点を教えてくれ」
彼が淡々と領地の話をしてくれるおかげで、私も何とか気持ちを切り替えることができた。
30分ほど領地の話をしていると、少しずつ平常心を取り戻してくる。
ジークフリートは、私が細かな疑問を投げかけるたびに的確な答えを返してくれる。その集中力と知識量には正直驚かされる。
「なるほど……そこは別の村の収穫時期との調整が必要なのですね」
「そうだ。いずれ、本格的に地図上にスケジュールを落とし込んでみようと思っている。作業分担を明確にすることで、働き手の不足を補えるかもしれない」
彼の話を聞いていると、先ほどまで私の心を苛んでいた王太子のことが、少しだけ遠のいていくような気がした。
その日の夕方、私は侍女に頼んで王都の商業区まで出かけることにした。
領地の資料を読み進めるうちに、どうしても実物を見てみたい本や道具が出てきたのだ。
ジークフリートも「自分の仕事で遅くなるから、護衛をつけるから好きに行ってこい」と言ってくれたので、気軽に外出することにした。
馬車で王都の繁華街に着くと、多くの店が軒を連ね、通りを大勢の人々が行き交っている。
かつては王太子妃候補として、こうした場所にも公務で出向いたものだが、今は立場が変わった。
(あの頃は、平民の中に入るだけで護衛が厳重で、ゆっくり店など見られなかったけれど……今日は少し自由に動けそう)
護衛がついているとはいえ、それほど大人数ではないから目立ちにくい。私は軽く胸を弾ませながら書店や雑貨屋を覗いていった。
やがて、広場を歩いていたとき、思わぬ人影を見かけて足が止まる。
――あれは、王宮の侍女をしていた頃に顔を合わせた貴婦人たちではないか。
彼女たちは私に気づくと、一瞬はっとした顔をして、それから気まずそうに笑いかけてきた。
「まあ、クレスタ様? お久しぶりですわね」
「アルグレイン男爵家に嫁がれたそうで……その後はいかがですか?」
表面上は柔らかな社交辞令。しかし、その目にはどこか探るような光がある。
私はなるべく穏やかに微笑んで答える。
「ええ、おかげさまで平穏に過ごしております。皆さまもお変わりなく?」
会話自体はあたりさわりのないものだが、やがて一人の夫人が遠慮がちに、しかし好奇心に満ちた声で尋ねてくる。
「ところで……王太子殿下とミーナ嬢の件、ご存じですか? 最近とても話題になっておりますの」
――やはり、そこへ来るのか。私は心がざわつくのを感じながら、平静を装う。
「ええ、新聞や噂話で耳にはしておりますわ。もうわたくしとは無関係のことですので」
できるだけ素っ気なく答える。夫人たちはちらちらと視線を交わし合い、微妙な沈黙が落ちる。
(ほら、やっぱり……私の反応を面白がっているのかもしれない)
王太子に婚約破棄された令嬢。その後どうなったのか、噂のネタにしたいだけなのだろう。
そんな風に思うと、やるせない気持ちになる。
「まあ……そう、ですわよね。確かにあれから時間も経ちましたし」
夫人の一人が話を合わせるように言う。続けて、もう一人が尋ねてくる。
「ところで、アルグレイン男爵は噂ではとても冷徹だと聞きますが……本当のところはいかがですの?」
余計なお世話、と思いつつ、私はできるだけ角を立てないように返事をする。
「いいえ、意外にも優しくしてくださいます。領地のことにも真摯に取り組んでおられて……噂ほど冷たいお方ではございませんわ」
それだけ言うと、今度は夫人たちの表情が微妙に変化した。
「そうですの……それは、よかったですわね」
「お幸せそうで何よりですわ」
内心どう思っているのかはわからない。けれど、こうして私を嘲笑するでもなく、一応は祝福の言葉をかけてくれるだけマシなのかもしれない。
私はその場を穏便に切り上げ、「ではまた」と挨拶して立ち去った。
広場から離れたあと、護衛が心配そうに近づいてくる。
「奥様、大丈夫でしたか? 少し不愉快そうに見えましたが……」
「ええ、何でもないわ。ありがとう」
少しだけ、ため息が漏れる。
――王太子殿下の話題は、私が望まなくても耳に飛び込んでくる。
それは、この国にいる限り、あるいはまだしばらく続くのだろう。
だけど、もう私は王太子を追いかける必要も、彼の行動に心を乱される必要もない。
私は私の道を歩む。ジークフリートのもとで、アルグレイン男爵夫人として――そう決めたはずだ。
そう自分に言い聞かせながら、午後のうちに必要な物を買い集め、屋敷へと帰った。
帰宅すると、ジークフリートは書斎にこもって書類を読んでいたが、私が戻ったと聞くと足早にやってきた。
「買い物はうまくいったか」
「はい、本も購入できましたし、道具もいくつか買えました」
「そうか、それはよかった」
私が曖昧に微笑むと、ジークフリートは少しだけ表情を曇らせる。
「……何かあったのか? あまり明るくないように見えるが」
言い当てられて、一瞬言葉に詰まる。まさか、王太子の話題で少し動揺したなどと言いたくない。
「いえ、大したことではありません。少し疲れたのかもしれませんわ」
そう答えると、ジークフリートは黙って私の様子を見つめる。
浅黒い瞳が、まるで私の心を見透かそうとしているかのように深く感じる。
やがて彼は微かにうなずいて、「ならば、晩餐の前に少し休むといい。侍女に申し付けろ」と言った。
私は「そうさせていただきます」と頭を下げ、早めに部屋に戻ることにした。
ベッドに横たわって目を閉じると、今日の出来事が頭の中を駆け巡る。
(王太子殿下……私はもう、あの方とは何の関係もない。それでも、わずかな未練が残っているの?)
悔しい。彼に捨てられた事実はもちろん、捨てられた私のほうがまだ心を乱されているという現実にも。
今の私は、アルグレイン男爵夫人として生きていくと決めたはず。それに、ジークフリートは……本当に不思議なほど私を大切に扱ってくれる。
なのに、過去への囚われを断ち切りきれない自分が、どうしようもなく歯がゆかった。
ふと、扉の向こうで物音がしたような気がして、私は頭を上げる。
侍女が様子を見に来たのかと思って「どうぞ」と声をかけたが、反応はない。
気のせいかもしれない。少し神経質になっているのかも……。
(……寝よう)
そう思ってまぶたを閉じると、心地よい眠気がじわじわ押し寄せてきた。
どれくらい経ったのか。しばらくして目を覚ますと、窓の外は完全に夜の帳が下りていた。
(しまった、結構寝てしまったかも)
いつの間にかぐっすり眠っていたようだ。侍女が起こしに来てくれなかったところを見ると、ジークフリートが「寝かせてやれ」とでも言ってくれたのかもしれない。
少し身体をほぐしてから、ダイニングに向かう。
すでに遅い時刻だが、ディナーの準備は整っていた。侍女によれば、ジークフリートはまだ書斎にいるという。
(なら、わたしも後で書斎に行ってみようかしら……)
そう思いつつ、軽く胃に負担の少ない食事を取り、侍女に頼んでジークフリートの書斎へと向かった。
廊下を歩いて行くと、扉の下から燈火の明かりが漏れているのが見える。
コンコン、とノックすると中から声がした。
「どうぞ」
部屋に入ると、ジークフリートが机の上に広げた書類に目を落としながら、立ち上がりかけていた。
「……大丈夫か? 眠れていたようだが」
「ええ、おかげさまで。少しスッキリしました。夕食もいただきましたし」
私がそう言うと、彼は軽く頷く。
「それならよかった。食事は……俺は後で取るつもりだ。もう少し仕事が残っていてな」
彼の机上には、領地の財政報告書や何かの契約書らしきものが散らばっていた。
最近、私も一部の書類を見せてもらっているが、その膨大さは想像以上だ。真面目に全部に目を通すだけでも相当な労力だろう。
「いつもこんなに夜遅くまでお仕事をしているのですか?」
「余裕があるときは早めに休むが、緊急の連絡が入れば対応が必要だ。さっきも一通、報告が届いたばかりでな」
そう言ってジークフリートが示すのは、封を開けたばかりの手紙。王都の役所から送られてきたらしく、何か問題があったようだ。
「大変ですね……。何か手伝えることはありませんか?」
少しでも助けになりたいと思って聞いてみる。
しかし、ジークフリートは静かに首を振った。
「気持ちはありがたいが、これは王都側との細かな取り決めが含まれている。詳しい事情を共有していない以上、説明がややこしい。……もう少し、今後の段取りが固まってから助けを借りたい」
彼なりに配慮しているのだろう。私は「わかりました」と素直に身を退いた。
――やるせなさを感じないわけではない。私だって、もっと力になりたい気持ちがある。
けれど、彼には彼の領分がある。そもそも私たちは、まだ結婚して間もないのだから、今すぐすべてを共有できるはずがないのも当然だ。
(焦らずに、今はできることを少しずつやっていこう)
そう思い直し、「それでは、邪魔をしてはいけませんね。わたしは部屋に戻りますわ。お仕事、がんばってください」と告げる。
ジークフリートは「すまないな」と申し訳なさそうに言い、私を見送った。
扉を閉める直前にちらりと振り返ると、彼は机に向かい書類をめくり始めていた。少し疲れがたまっているようにも見える。
(寝不足にならなければいいけど……)
心配しつつも、私にできることはあまりない。
最近は、私のことをかなり大事に扱ってくれているのに、彼自身のこととなると、自分で抱え込んでしまうタイプなのかもしれない。
部屋に戻り、手持ちの本を開いても、なかなか集中できない。
王太子のこと、今日の貴婦人たちとの会話、そしてジークフリートの働きぶり……様々な思考が頭の中を駆けめぐり、落ち着かない。
――気づけば、窓の外で月が高く昇っていた。
私は深呼吸して、そろそろ就寝の支度に取りかかる。明日もいろいろなことがあるだろう。
だけど、この胸のざわめきは、いったいいつになったら収まるのか……。それがわからないまま、私は静かに夜を過ごしていく。
こうして日々は過ぎていく。
ジークフリートとの“白い結婚”は、いまだ境界線がはっきりしないまま。それでも、まるで仮面夫婦のはずが、なぜかお互いに少しずつ距離を縮めている気もする。
――王太子殿下とミーナの噂はますます盛り上がりを見せているようだが、私がそこに割り込む余地はないし、割り込むつもりもない。
とはいえ、まだ完全に吹っ切れたわけでもなく、どこかに残るわだかまりを抱えつつ、私はジークフリートの屋敷での生活に少しずつ慣れていくのだった。
その陰で、王宮をはじめとする貴族社会では、少しずつ“あるさざ波”が立ち始めていたことを、私はまだ知らない。
私が婚約破棄された真の理由と、ジークフリートの“本当の顔”が垣間見えるのは、もう少し先の話になる。
このときはまだ、私自身が“夫の優しさ”に戸惑いながらも救われていることを感じつつ、平穏な日常にひそむ気配を見過ごしていた。
そして、これが更なる波乱への布石とも知らずに……。
私──クレスタ・エルバンシュ、もといアルグレイン男爵夫人は、夫であるジークフリート・アルグレインの誘いに従い、彼とともに屋敷を出た。
行き先は王都から離れた、アルグレイン男爵領の端にある小さな村。緑豊かな場所で、空気も美味しいらしい。
もともと領地視察という名目なのだが、どうやらジークフリートは私に気晴らしをさせようと思ってくれているらしく、「あまり難しく考えずに来い」と言ってくれた。
朝早くの出発だったけれど、馬車で移動している間、退屈することはなかった。
道すがら見える景色は、まだ私が知らない王国の姿を映し出している。緩やかな丘や、野を駆ける小川、遠くに見える山並み。
高い建物が並ぶ王都の眺望とはまた違う、のどかな自然の美しさが心を落ち着かせてくれた。
視察というには簡素だが、近衛らしき護衛が数名同行している。彼らは馬に乗り、馬車の周りを警護していた。
ジークフリートの冷酷な噂を聞いたときは「護衛にも厳しく当たるのだろうか」と思っていたけれど、皆、彼を尊敬しているような面持ちだ。
道中、ジークフリートが短く声をかけると、護衛たちは「はい、旦那様」「承知しました」ときびきび返事をする。その様子には、命令への忠実さ以上に、強い信頼が感じられた。
(やはり、あの“冷血”という噂は、何か別の理由で流されたものなのかしら……)
最近になって、私はそんな疑問が頭から離れない。
今のところ、ジークフリートが私に乱暴な態度をとることは一度もない。むしろ、私の体調を気遣ったり、好みのスイーツを用意してくれたりと、優しさが目立つくらいだ。
どれもこれも計算や打算から来る偽りなのかもしれないし、あるいは本心なのかもしれない。
わからないまま、時間だけがゆっくりと流れている。
「どうした? 疲れたか」
馬車の揺れが少し大きくなった時、ジークフリートは私に気づかいを見せた。
私は軽く首を振る。
「いえ、大丈夫です。馬車の旅は初めてではありませんし、特に問題はありませんわ」
「ならいい」
淡々とした返事。しかし、その横顔は少しだけ心配そうに見える。
こうした小さな優しさに、私は戸惑うばかりだ。
しばらくすると、馬車は小さな村の入口に差し掛かった。
広がる畑と、点在する素朴な家々。あちこちに鶏や家畜の姿が見え、遠くから牛の鳴き声が聞こえる。王都の華やかさとは対極にあるのどかな風景だった。
村人たちは、馬車の姿に気づくと、慌ただしく出てきて一列に並ぶ。どうやら男爵の視察を歓迎しているらしい。
私は馬車の窓からその様子を見つつ、「これが領主への儀礼なのだな」と密かに納得する。
馬車が止まり、ジークフリートが先に降り立つ。続いて私も侍女の手を借りながら地面に足をつけた。
硬い土の感触が伝わってくる。靴に多少の埃がかかっても気にしない。
ジークフリートは村長らしき老人に声をかけた。
「みな、変わりないか」
「はい、男爵様。特に大きな不作もなく、今年も作物は順調でございます」
老人は深々と頭を下げ、恭しく挨拶をする。その横で、村の人々が口々に「奥様もいらしたのですね」と私を見て微笑んでいた。
私は少し照れくさくなりながらも、にこやかに会釈を返す。
(ここでは“男爵夫人”として立ち振る舞わなくては)
婚約破棄の痛手を引きずっているとはいえ、今の私には新しい立場がある。皆に愛想よく笑顔を向け、「よろしくお願いしますわ」と柔らかな口調で応じると、村の人々は一気に和んだ様子を見せた。
村長の案内で、私たちは畑のほうへと向かう。
穀物や野菜がすくすくと育っているのがわかる。今は青々とした段階で、もう少しで収穫期を迎えるそうだ。
「今年は雨の巡りも悪くなく、害虫も少ないんです。男爵様の助成金があったおかげで、新しい農具も揃えることができました」
村長が感謝の言葉を述べるたびに、私は横目でジークフリートを見やる。彼は無表情だが、どこか穏やかに頷いているように見えた。
(こういう地道な支援が、彼の“本当の姿”なのかしら……)
王太子殿下と婚約していた頃は、私も領地経営についてある程度の知識を仕込まれていたが、まさかこうして“自分が夫人として携わる”立場になるとは思っていなかった。
私の隣で、ジークフリートはふと足を止め、育ちかけの作物に視線を落とす。
すると、近くで作業していた若い農夫が「あの……男爵様、もしよろしければこの畑をもう少し見ていただけませんか?」と声をかけてきた。
「これまでは害虫対策に昔ながらの方法を使ってきたのですが……最近、新しい種子を入手しまして、育て方が少し違うようなのです」
農夫が説明する内容は、私にはやや専門的すぎて理解しづらい。しかし、ジークフリートは真剣な面持ちで聞き入り、時折うなずきながら的確な質問を投げかけている。
私は驚く。男爵と言っても、貴族がここまで農業に精通しているとは思わなかったのだ。
「なるほど、種子の出どころが違えば土や水の管理も違うだろう。村長にも協力を仰いで、試験区を作るのがいい。結果を見ながら徐々に広げていけば、リスクは抑えられる」
ジークフリートの提案を聞いて、農夫は目を輝かせた。
「ありがとうございます、男爵様! その方法なら安心です!」
こうして領地の農民と直接やり取りし、具体的な指示を出している姿……。私は、思わず見とれてしまった。
人の話をちゃんと聞き、適切な助言を与える。これが本当に“冷血”などと呼ばれる人物だろうか?
「クレスタ、少しこちらへ来てくれ」
名前を呼ばれて、はっと我に返る。
「はい……どうかしましたか?」
ジークフリートが指し示したのは、片隅にある花畑のような場所。野菜や穀物とは別に、色とりどりの花が咲き乱れていた。
「ここは何のための花畑なのですか?」
興味を引かれ、私は村長に尋ねる。すると村長は笑顔で答えた。
「ここは昔、土が痩せていた場所なのです。野菜を育てるには不向きで……でも、花なら強い品種を植えられるということで、こうして観賞用の畑にしておりましてね。観光というほど大げさなものではありませんが、村人が少しでも楽しめるようにと、男爵様が資金を出してくださいました」
「へえ……素敵ですね」
私がそう返すと、ジークフリートは足元の花を一瞥し、「今度、改良品種の種を手に入れる予定だ。色ももっと増やせるかもしれない」と呟いた。
彼は決して感情豊かに語るわけではないが、その言葉の裏にある優しさが、何となく伝わってくる。
作業を続ける農民たちに挨拶を済ませたあと、私たちは村の小さな集会所のような建物に向かった。そこで村長や数名の代表と雑談を交えながら、改めて領内の問題点や予算の話をする。
私はほとんど聞き役に徹していたが、たまにジークフリートが「クレスタ、おまえの意見はどうだ?」と話を振ってくれることがあった。
さすがに農業関連の専門的なことは口を挟めないが、かつて父のもとで学んだ知識から、少しは役立ちそうなことを話すと、村長たちは感心した様子を見せてくれた。
「男爵様がお迎えになったご夫人は、大変お聡明でいらっしゃるのですね」
ある女性がそう言ってくれたとき、私は恐縮しながら微笑む。
ジークフリートは表情こそ変わらないが、視線の端がわずかに柔らいだ気がした。
(まるで誇らしげに思っているような……?)
自意識過剰かもしれないけれど、そんな風にも感じてしまう。胸が妙にくすぐったい。
昼を少し回ったあたりで、私たちは村で用意された素朴な食事をいただくことになった。採れたての野菜を煮込んだスープや、自家製のパン、ハーブで香りづけした鶏肉など、王都の華やかな料理とはまた違う素朴な味わいだ。
「大したおもてなしはできませんが、どうかお召し上がりくださいませ」
「いえ、とても美味しそうですわ」
私はそう言ってスープを口に運ぶ。じんわりと旨味が広がり、心も身体もほっと温まる。
王宮で出されるような贅沢な食事ではないけれど、これはこれでまた別の美味しさがある。
ジークフリートも無言でスープをすすっているが、悪い顔はしていない。
彼も王都育ちの貴族としては珍しいほど、質素な場所に慣れているのか、特に嫌そうな素振りを見せない。
淡々としつつも、こういう田舎の生活にちゃんと寄り添えるのは、ある意味で貴重な資質だろう。
私はその横顔を眺めながら、不意に心に湧いた疑問を押し殺す。
(あなたは、いったい何者なの……ジークフリート)
食事を終え、ひと通りの視察を済ませる頃には、すっかり日が傾き始めていた。
「では皆、また近いうちに状況を見に来る。何かあれば連絡を寄こせ」
ジークフリートがそう言うと、村長や農民たちは一斉に頭を下げる。
私は名残惜しさを感じながら、優しい笑顔で手を振り、「ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします」と告げた。
村の空気は穏やかで、暖かかった。心のどこかがふっと軽くなったような気がする。
馬車に戻ると、すでに護衛が帰り支度を整えていた。
「男爵様、奥様、お疲れになったでしょう。王都まで戻る間、どうかゆっくりお休みください」
使用人の一人がそう言って馬車の扉を開いてくれる。私はジークフリートとともに中へと乗り込んだ。
馬車がゆるやかに走り始め、村の風景が遠ざかっていく。
柔らかな夕陽が射し込み、車内はほんのりとオレンジ色に染まっていた。
しばらく黙って窓の外を眺めていた私に、ジークフリートが声をかける。
「どうだった?」
短い問いかけ。けれど、何を聞かれているのかはすぐわかった。
私は素直に感想を述べる。
「はい、とても良かったです。村の方々はみんな温かくて、自然も綺麗で……。それに、ジークフリート様がこんなふうに領地をちゃんと見ておられるなんて、少し意外でした」
「意外、か」
無表情の彼が、すっと目を伏せる。
私は慌てて言い訳のように続ける。
「失礼を承知で言えば、男爵様の評判は“冷酷”でしたから……。でも今日見た限り、そんな風には思えなかったものですから」
するとジークフリートは、微かに苦笑のような表情を浮かべた。普段の仏頂面からは想像しにくい表情に、私は少しだけ驚く。
「……俺にも事情がある。あまり深く考えるな」
「事情、ですか」
「そうだ。いずれ話す機会があるかもしれない。だが今はそれで勘弁してほしい」
そう言われると、それ以上追及できない。
馬車の揺れが続く中、私たちは再び沈黙する。
外を見れば、夕陽が赤く染まり、夜の気配がゆっくりと迫ってきていた。
やがてジークフリートは窓に目をやり、ふっと息をつく。
「おまえが嫌でなければ、またこうして領地を見に行ってくれないか」
「わたしと……ですか?」
「ああ。村人たちも、おまえが来るなら歓迎してくれるだろうし、領内を知っておくことは悪くないだろう」
私は少し迷ったが、心のどこかで嬉しさを感じていた。
――私をただの飾りにするつもりはないのかもしれない。
白い結婚という言葉から連想した“形だけ”の夫婦関係ではなく、少なくとも領主とその夫人として協力していく姿勢を示してくれている。
「……わかりました。よろこんでご一緒します」
そう答えると、ジークフリートは黙ったまま頷いた。微かに、安心したような気配が伝わってくるのは気のせいだろうか。
その夜、屋敷に戻った私たちは別々に夕食をとった。
ジークフリートには別の用事があるらしく、私は先に済ませて部屋でくつろいでいた。
ひとりの時間に浸っていると、村での光景が頭をよぎる。
私に親しみをもって接してくれた人々、素朴な食事の温かさ、そして真剣に領民の意見に耳を傾けるジークフリートの姿……。
――何もかもが、私の知る“貴族の常識”を少しだけ超えているように感じた。
その後、就寝の準備をしていると、侍女が「旦那様がお呼びです」と声をかけてきた。
「私を……? こんな夜更けに何の用かしら」
少し疑問を抱きつつも、私はガウンを羽織り、侍女の案内でジークフリートの部屋へと向かう。
途中、廊下の窓から月が見えた。澄んだ夜空に浮かぶ月は、やけに明るく感じられる。
(何だか、少し胸が高鳴ってる……)
自分でも理由がわからない。だけど、妙に緊張してしまう。
ノックをして部屋に入ると、そこは広めの書斎だった。机や本棚が整然と並び、壁には地図や書類らしきものが貼られている。
ジークフリートは机の向こうに立っていた。私の顔を見ると、ほんの少し表情がほころぶ。
「夜分にすまない。少し見てほしいものがあってな」
そう言って彼が差し出したのは、一枚の紙。近寄ってみると、そこには領地の地形図といくつかの施設が書き込まれていた。
「これは……」
「男爵領の略図だ。今日行った村の位置も載っている。今後、視察を増やすにあたって、おまえにも地理を把握しておいてほしいと思ってな」
私は頷き、紙を両手で持って眺める。そこには複数の村や町が点在しており、川の流れや森林の位置まで詳しく記されている。
「こんなに広い領地を、ジークフリート様は一人で管理しておられるのですか?」
「正確には、補佐役や役人と分担している。俺がやるのはあくまで方針決定と重要事項の監督。それでも、少しでも時間ができれば、直に足を運んだほうが早いこともある」
その言葉に、再び“冷血”との噂は何だったのかと思わずにいられない。
「ありがとう。こういう地図があると、とてもわかりやすいですわ」
私が率直に感謝を述べると、ジークフリートは視線を地図に落としながら、ぽつりと呟いた。
「……おまえが王太子との婚約を破棄されたと聞いたとき、正直、驚いた。だが、こうして迎え入れてみて思うのは、おまえは想像以上に強く、そして優秀だということだ」
不意打ちの言葉に、私は目を見開く。
「そ、それは……。わたしはただ、侯爵家の教育を受けてきただけですし。優秀なんてとんでもない」
少し照れくさい。ジークフリートは私を褒めようとしているのか?
「いや、王太子の件があったにもかかわらず、ひるまずに今日のように立ち回れるのは大したものだ。俺には、おまえが“王族の花嫁”として育ってきた誇りと強さが見える」
そのまっすぐな言葉に、私は困惑しながらも、どこかくすぐったい気持ちになった。
(こんな風に素直に褒められたのは、いつ以来だろう……)
王太子殿下と婚約していた頃、表向きに褒められることはあっても、真意を感じられた記憶はあまりない。
それを思うと、ジークフリートの言葉はどこか実感がこもっている気がした。
沈黙が少しだけ続く。紙を手渡されたまま、私はその地図を見下ろし、彼の言葉の余韻を感じていた。
そのとき、ジークフリートがふっと顔を上げ、私をまっすぐ見据える。
「クレスタ……おまえは、ここに来てから不満はないか」
「え……不満、ですか?」
予想外の問いに、私は瞬きする。
不満と言われても、思いつくものは特にない。確かに結婚自体は政略めいていたし、王太子殿下に捨てられた屈辱もまだ完全には晴れない。
けれど、アルグレイン邸での暮らしそのものには、なんの不満も感じていなかった。
「いえ、特にありませんわ。むしろ、わたしなどにはもったいないくらいの待遇を受けている気がします」
「そうか……よかった」
彼はそれだけ言うと、少しホッとしたような顔をした。
普段は沈着冷静で、こちらに余計な感情を見せないジークフリートが、こうしてはっきり安心した様子を示すのは珍しい。
(私のことを、ちゃんと気にかけてくれている?)
なんだか気恥ずかしくなって、私はわざと視線を地図に戻す。
するとジークフリートが小さく咳払いをして、「……遅い時間に呼び出して悪かったな。地図は好きなときに眺めてくれ。おまえが興味を持ってくれれば、領地のことも理解が早いだろう」
そう言いながら机の引き出しを開け、別の書類も取り出す。
「ここに記してあるのは領内の収支や人口、作物の収穫量などだ。一度に目を通すのは大変かもしれないが、時間があるときにでも眺めてみてくれ」
「は、はい……」
膨大な量に見えるが、私は嫌ではない。むしろ、少しやる気が湧いてきた自分に気づく。
ジークフリートと二人きりの書斎。微かにインクの香りと紙の匂いが混じり合う。
静かな夜の空気の中、私たちはしばし言葉を交わし続けた。領地経営のこと、視察で気づいたこと、そして今日感じたこと……。
これがいわゆる“夫婦の会話”なのかはわからない。けれど、一緒に同じ目線で何かを考える時間があるのは、思いのほか悪い気がしない。
――ふと、扉の外から控えめなノックの音がした。
「失礼します。旦那様、奥様。夜も更けてまいりましたので……」
侍女が控えめに促すようにしてくる。気づけば、もう時計の針は深夜に近いところを指していた。
「もうこんな時間。……ごめんなさい、わたしが話し込んでしまって」
私が急いで書類をまとめようとすると、ジークフリートは首を横に振る。
「いや、こちらこそ引き止めて悪かった。今夜はもう休め。また続きは明日にでも聞くとしよう」
そう言って書類を受け取りながら、ジークフリートはちらりと私をうかがう。
その視線に、私はどこかドキリとした。書斎の明かりが薄暗いせいか、彼の瞳がやけに深く感じられる。
「……おやすみなさい、ジークフリート様」
どうにかそれだけを言って、私は書斎を後にした。胸の鼓動が少し早まっているのを感じながら、自分の部屋へと戻る。
翌日から、私は少しずつアルグレイン男爵領の資料に目を通すようになった。
詳しいところまではわからなくても、地図や数値データを眺めるのは意外と楽しい。村での光景を思い出しながら、「ここではこんな作物が育つのか」「この川はあの川に繋がっているのか」とイメージを膨らませる。
ジークフリートからの簡単な説明もあり、私の中で領地の様子が少しずつ形作られていくようだった。
そんなある日、私は使用人が持ってきた新聞を何気なく読んでいて、思わず硬直してしまう。
――そこには、王太子アレクシオン殿下と平民の少女ミーナが、王宮で親密な様子を見せているという記事が載っていたのだ。
“民衆に慕われるミーナ嬢” “王太子の真実の愛” “婚約破棄から始まるロマンティックな恋”――そういった見出しが紙面を踊っている。
無責任な記事だとわかっていても、胸が苦しくなるのを抑えられない。私への配慮など微塵もない、あまりに能天気な報道に苛立ちすら覚える。
あの夜、王太子から婚約破棄を告げられた光景が、ふいに脳裏に甦る。
“僕は本当に愛する人と結ばれたいんだ”――そんな身勝手な言葉。
それを王都の人々は“美談”のように取り上げている。
たしかに、平民の少女を選んだ王太子は、一部からは非難されていると聞くが、それ以上に恋愛至上主義的な若者層から熱烈に支持されているとも聞く。
(……馬鹿らしい。そんなきれいごとで済むわけがないのに)
さらに記事を読み進めると、“ミーナ嬢は絶世の美女で性格も清らか”、“王太子殿下は彼女を慈しみ守り抜くと宣言”など、まるでおとぎ話のように書き連ねられていた。
(私の立場は何だったの? 長年の婚約者はこんな形で捨てられ、それでも彼らは“真実の愛”を謳っている……)
胸が熱くなり、新聞を握りしめる手が震える。忘れたつもりでも、傷はまだ癒えていない。
こんな記事を見るたびに、私は自分の感情が揺さぶられるのだ。
ドアがノックされ、私は慌てて新聞をたたむ。
「どうぞ」
声をかけると、入ってきたのはジークフリートだった。彼の瞳が、私の手にある新聞に一瞬目を止める。
「……その記事を読んでいたのか」
「ええ。ちょうど目に入っただけで、特別な意味はありませんわ」
嘘ではない。けれど、嘘でもある。私は内心で動揺を抑えようと必死だった。
ジークフリートは私の表情をそっとうかがい、静かな声で問いかける。
「……辛いのなら、無理に読む必要はない」
ドキリとする。私は彼に弱みを見せたくないと思い、そっけなく返す。
「大丈夫ですわ。もう過ぎたことですから」
――しかし、自分の声が少しだけ震えていたことに気づいて、慌てて言葉を噤んだ。
ジークフリートはそんな私の様子を見ても、あえて何も言わない。ただ、その瞳には静かな憂いが宿っている気がする。
しばらく気まずい沈黙が漂ったあと、彼は私の机上にある領地の資料に視線を向けて話題を変えた。
「領地の資料、どこまで読んだ?」
「あ……ええと、このあたりです。人口動態と、主要農作物のデータは大体目を通しました」
「そうか。じゃあ、それを踏まえておまえが気になった点を教えてくれ」
彼が淡々と領地の話をしてくれるおかげで、私も何とか気持ちを切り替えることができた。
30分ほど領地の話をしていると、少しずつ平常心を取り戻してくる。
ジークフリートは、私が細かな疑問を投げかけるたびに的確な答えを返してくれる。その集中力と知識量には正直驚かされる。
「なるほど……そこは別の村の収穫時期との調整が必要なのですね」
「そうだ。いずれ、本格的に地図上にスケジュールを落とし込んでみようと思っている。作業分担を明確にすることで、働き手の不足を補えるかもしれない」
彼の話を聞いていると、先ほどまで私の心を苛んでいた王太子のことが、少しだけ遠のいていくような気がした。
その日の夕方、私は侍女に頼んで王都の商業区まで出かけることにした。
領地の資料を読み進めるうちに、どうしても実物を見てみたい本や道具が出てきたのだ。
ジークフリートも「自分の仕事で遅くなるから、護衛をつけるから好きに行ってこい」と言ってくれたので、気軽に外出することにした。
馬車で王都の繁華街に着くと、多くの店が軒を連ね、通りを大勢の人々が行き交っている。
かつては王太子妃候補として、こうした場所にも公務で出向いたものだが、今は立場が変わった。
(あの頃は、平民の中に入るだけで護衛が厳重で、ゆっくり店など見られなかったけれど……今日は少し自由に動けそう)
護衛がついているとはいえ、それほど大人数ではないから目立ちにくい。私は軽く胸を弾ませながら書店や雑貨屋を覗いていった。
やがて、広場を歩いていたとき、思わぬ人影を見かけて足が止まる。
――あれは、王宮の侍女をしていた頃に顔を合わせた貴婦人たちではないか。
彼女たちは私に気づくと、一瞬はっとした顔をして、それから気まずそうに笑いかけてきた。
「まあ、クレスタ様? お久しぶりですわね」
「アルグレイン男爵家に嫁がれたそうで……その後はいかがですか?」
表面上は柔らかな社交辞令。しかし、その目にはどこか探るような光がある。
私はなるべく穏やかに微笑んで答える。
「ええ、おかげさまで平穏に過ごしております。皆さまもお変わりなく?」
会話自体はあたりさわりのないものだが、やがて一人の夫人が遠慮がちに、しかし好奇心に満ちた声で尋ねてくる。
「ところで……王太子殿下とミーナ嬢の件、ご存じですか? 最近とても話題になっておりますの」
――やはり、そこへ来るのか。私は心がざわつくのを感じながら、平静を装う。
「ええ、新聞や噂話で耳にはしておりますわ。もうわたくしとは無関係のことですので」
できるだけ素っ気なく答える。夫人たちはちらちらと視線を交わし合い、微妙な沈黙が落ちる。
(ほら、やっぱり……私の反応を面白がっているのかもしれない)
王太子に婚約破棄された令嬢。その後どうなったのか、噂のネタにしたいだけなのだろう。
そんな風に思うと、やるせない気持ちになる。
「まあ……そう、ですわよね。確かにあれから時間も経ちましたし」
夫人の一人が話を合わせるように言う。続けて、もう一人が尋ねてくる。
「ところで、アルグレイン男爵は噂ではとても冷徹だと聞きますが……本当のところはいかがですの?」
余計なお世話、と思いつつ、私はできるだけ角を立てないように返事をする。
「いいえ、意外にも優しくしてくださいます。領地のことにも真摯に取り組んでおられて……噂ほど冷たいお方ではございませんわ」
それだけ言うと、今度は夫人たちの表情が微妙に変化した。
「そうですの……それは、よかったですわね」
「お幸せそうで何よりですわ」
内心どう思っているのかはわからない。けれど、こうして私を嘲笑するでもなく、一応は祝福の言葉をかけてくれるだけマシなのかもしれない。
私はその場を穏便に切り上げ、「ではまた」と挨拶して立ち去った。
広場から離れたあと、護衛が心配そうに近づいてくる。
「奥様、大丈夫でしたか? 少し不愉快そうに見えましたが……」
「ええ、何でもないわ。ありがとう」
少しだけ、ため息が漏れる。
――王太子殿下の話題は、私が望まなくても耳に飛び込んでくる。
それは、この国にいる限り、あるいはまだしばらく続くのだろう。
だけど、もう私は王太子を追いかける必要も、彼の行動に心を乱される必要もない。
私は私の道を歩む。ジークフリートのもとで、アルグレイン男爵夫人として――そう決めたはずだ。
そう自分に言い聞かせながら、午後のうちに必要な物を買い集め、屋敷へと帰った。
帰宅すると、ジークフリートは書斎にこもって書類を読んでいたが、私が戻ったと聞くと足早にやってきた。
「買い物はうまくいったか」
「はい、本も購入できましたし、道具もいくつか買えました」
「そうか、それはよかった」
私が曖昧に微笑むと、ジークフリートは少しだけ表情を曇らせる。
「……何かあったのか? あまり明るくないように見えるが」
言い当てられて、一瞬言葉に詰まる。まさか、王太子の話題で少し動揺したなどと言いたくない。
「いえ、大したことではありません。少し疲れたのかもしれませんわ」
そう答えると、ジークフリートは黙って私の様子を見つめる。
浅黒い瞳が、まるで私の心を見透かそうとしているかのように深く感じる。
やがて彼は微かにうなずいて、「ならば、晩餐の前に少し休むといい。侍女に申し付けろ」と言った。
私は「そうさせていただきます」と頭を下げ、早めに部屋に戻ることにした。
ベッドに横たわって目を閉じると、今日の出来事が頭の中を駆け巡る。
(王太子殿下……私はもう、あの方とは何の関係もない。それでも、わずかな未練が残っているの?)
悔しい。彼に捨てられた事実はもちろん、捨てられた私のほうがまだ心を乱されているという現実にも。
今の私は、アルグレイン男爵夫人として生きていくと決めたはず。それに、ジークフリートは……本当に不思議なほど私を大切に扱ってくれる。
なのに、過去への囚われを断ち切りきれない自分が、どうしようもなく歯がゆかった。
ふと、扉の向こうで物音がしたような気がして、私は頭を上げる。
侍女が様子を見に来たのかと思って「どうぞ」と声をかけたが、反応はない。
気のせいかもしれない。少し神経質になっているのかも……。
(……寝よう)
そう思ってまぶたを閉じると、心地よい眠気がじわじわ押し寄せてきた。
どれくらい経ったのか。しばらくして目を覚ますと、窓の外は完全に夜の帳が下りていた。
(しまった、結構寝てしまったかも)
いつの間にかぐっすり眠っていたようだ。侍女が起こしに来てくれなかったところを見ると、ジークフリートが「寝かせてやれ」とでも言ってくれたのかもしれない。
少し身体をほぐしてから、ダイニングに向かう。
すでに遅い時刻だが、ディナーの準備は整っていた。侍女によれば、ジークフリートはまだ書斎にいるという。
(なら、わたしも後で書斎に行ってみようかしら……)
そう思いつつ、軽く胃に負担の少ない食事を取り、侍女に頼んでジークフリートの書斎へと向かった。
廊下を歩いて行くと、扉の下から燈火の明かりが漏れているのが見える。
コンコン、とノックすると中から声がした。
「どうぞ」
部屋に入ると、ジークフリートが机の上に広げた書類に目を落としながら、立ち上がりかけていた。
「……大丈夫か? 眠れていたようだが」
「ええ、おかげさまで。少しスッキリしました。夕食もいただきましたし」
私がそう言うと、彼は軽く頷く。
「それならよかった。食事は……俺は後で取るつもりだ。もう少し仕事が残っていてな」
彼の机上には、領地の財政報告書や何かの契約書らしきものが散らばっていた。
最近、私も一部の書類を見せてもらっているが、その膨大さは想像以上だ。真面目に全部に目を通すだけでも相当な労力だろう。
「いつもこんなに夜遅くまでお仕事をしているのですか?」
「余裕があるときは早めに休むが、緊急の連絡が入れば対応が必要だ。さっきも一通、報告が届いたばかりでな」
そう言ってジークフリートが示すのは、封を開けたばかりの手紙。王都の役所から送られてきたらしく、何か問題があったようだ。
「大変ですね……。何か手伝えることはありませんか?」
少しでも助けになりたいと思って聞いてみる。
しかし、ジークフリートは静かに首を振った。
「気持ちはありがたいが、これは王都側との細かな取り決めが含まれている。詳しい事情を共有していない以上、説明がややこしい。……もう少し、今後の段取りが固まってから助けを借りたい」
彼なりに配慮しているのだろう。私は「わかりました」と素直に身を退いた。
――やるせなさを感じないわけではない。私だって、もっと力になりたい気持ちがある。
けれど、彼には彼の領分がある。そもそも私たちは、まだ結婚して間もないのだから、今すぐすべてを共有できるはずがないのも当然だ。
(焦らずに、今はできることを少しずつやっていこう)
そう思い直し、「それでは、邪魔をしてはいけませんね。わたしは部屋に戻りますわ。お仕事、がんばってください」と告げる。
ジークフリートは「すまないな」と申し訳なさそうに言い、私を見送った。
扉を閉める直前にちらりと振り返ると、彼は机に向かい書類をめくり始めていた。少し疲れがたまっているようにも見える。
(寝不足にならなければいいけど……)
心配しつつも、私にできることはあまりない。
最近は、私のことをかなり大事に扱ってくれているのに、彼自身のこととなると、自分で抱え込んでしまうタイプなのかもしれない。
部屋に戻り、手持ちの本を開いても、なかなか集中できない。
王太子のこと、今日の貴婦人たちとの会話、そしてジークフリートの働きぶり……様々な思考が頭の中を駆けめぐり、落ち着かない。
――気づけば、窓の外で月が高く昇っていた。
私は深呼吸して、そろそろ就寝の支度に取りかかる。明日もいろいろなことがあるだろう。
だけど、この胸のざわめきは、いったいいつになったら収まるのか……。それがわからないまま、私は静かに夜を過ごしていく。
こうして日々は過ぎていく。
ジークフリートとの“白い結婚”は、いまだ境界線がはっきりしないまま。それでも、まるで仮面夫婦のはずが、なぜかお互いに少しずつ距離を縮めている気もする。
――王太子殿下とミーナの噂はますます盛り上がりを見せているようだが、私がそこに割り込む余地はないし、割り込むつもりもない。
とはいえ、まだ完全に吹っ切れたわけでもなく、どこかに残るわだかまりを抱えつつ、私はジークフリートの屋敷での生活に少しずつ慣れていくのだった。
その陰で、王宮をはじめとする貴族社会では、少しずつ“あるさざ波”が立ち始めていたことを、私はまだ知らない。
私が婚約破棄された真の理由と、ジークフリートの“本当の顔”が垣間見えるのは、もう少し先の話になる。
このときはまだ、私自身が“夫の優しさ”に戸惑いながらも救われていることを感じつつ、平穏な日常にひそむ気配を見過ごしていた。
そして、これが更なる波乱への布石とも知らずに……。
0
あなたにおすすめの小説

政略結婚した夫に殺される夢を見た翌日、裏庭に深い穴が掘られていました
伊織
恋愛
夫に殺される夢を見た。
冷え切った青い瞳で見下ろされ、血に染まった寝室で命を奪われる――あまりにも生々しい悪夢。
夢から覚めたセレナは、政略結婚した騎士団長の夫・ルシアンとの冷えた関係を改めて実感する。
彼は宝石ばかり買う妻を快く思っておらず、セレナもまた、愛のない結婚に期待などしていなかった。
だがその日、夢の中で自分が埋められていたはずの屋敷の裏庭で、
「深い穴を掘るために用意されたようなスコップ」を目にしてしまう。
これは、ただの悪夢なのか。
それとも――現実に起こる未来の予兆なのか。
闇魔法を受け継ぐ公爵令嬢と、彼女を疎む騎士団長。
不穏な夢から始まる、夫婦の物語。
男女の恋愛小説に挑戦しています。
楽しんでいただけたら嬉しいです。

私を簡単に捨てられるとでも?―君が望んでも、離さない―
喜雨と悲雨
恋愛
私の名前はミラン。街でしがない薬師をしている。
そして恋人は、王宮騎士団長のルイスだった。
二年前、彼は魔物討伐に向けて遠征に出発。
最初は手紙も返ってきていたのに、
いつからか音信不通に。
あんなにうっとうしいほど構ってきた男が――
なぜ突然、私を無視するの?
不安を抱えながらも待ち続けた私の前に、
突然ルイスが帰還した。
ボロボロの身体。
そして隣には――見知らぬ女。
勝ち誇ったように彼の隣に立つその女を見て、
私の中で何かが壊れた。
混乱、絶望、そして……再起。
すがりつく女は、みっともないだけ。
私は、潔く身を引くと決めた――つもりだったのに。
「私を簡単に捨てられるとでも?
――君が望んでも、離さない」
呪いを自ら解き放ち、
彼は再び、執着の目で私を見つめてきた。
すれ違い、誤解、呪い、執着、
そして狂おしいほどの愛――
二人の恋のゆくえは、誰にもわからない。
過去に書いた作品を修正しました。再投稿です。

「お前みたいな卑しい闇属性の魔女など側室でもごめんだ」と言われましたが、私も殿下に嫁ぐ気はありません!
野生のイエネコ
恋愛
闇の精霊の加護を受けている私は、闇属性を差別する国で迫害されていた。いつか私を受け入れてくれる人を探そうと夢に見ていたデビュタントの舞踏会で、闇属性を差別する王太子に罵倒されて心が折れてしまう。
私が国を出奔すると、闇精霊の森という場所に住まう、不思議な男性と出会った。なぜかその男性が私の事情を聞くと、国に与えられた闇精霊の加護が消滅して、国は大混乱に。
そんな中、闇精霊の森での生活は穏やかに進んでいく。
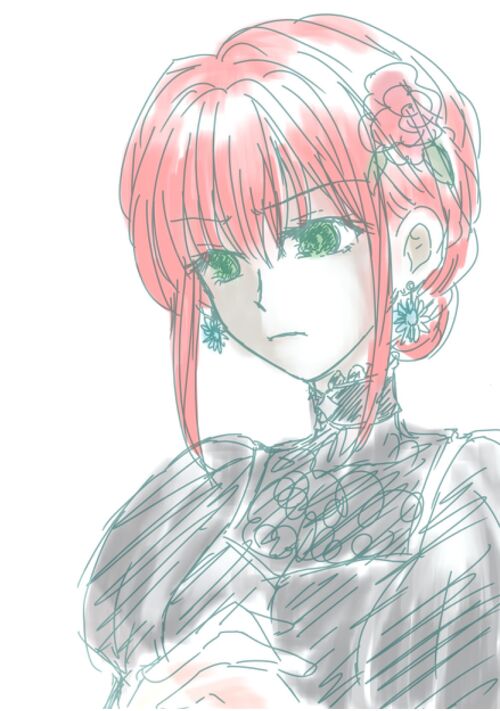
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

婚約破棄して泥を投げつけた元婚約者が「無能」と笑う中、光り輝く幼なじみの王子に掠め取られました。
ムラサメ
恋愛
「お前のような無能、我が家には不要だ。今すぐ消えろ!」
婚約者・エドワードのために身を粉にして尽くしてきたフィオナは、卒業パーティーの夜、雨の中に放り出される。
泥にまみれ、絶望に沈む彼女の前に現れたのは、かつての幼なじみであり、今や国中から愛される「黄金の王子」シリルだった。
「やっと見つけた。……ねえ、フィオナ。あんなゴミに君を傷つけさせるなんて、僕の落ち度だね」
汚れを厭わずフィオナを抱き上げたシリルは、彼女を自分の屋敷へと連れ帰る。
「自分には価値がない」と思い込むフィオナを、シリルは異常なまでの執着と甘い言葉で、とろけるように溺愛し始めて――。
一方で、フィオナを捨てたエドワードは気づいていなかった。
自分の手柄だと思っていた仕事も、領地の繁栄も、すべてはフィオナの才能によるものだったということに。
ボロボロになっていく元婚約者。美しく着飾られ、シリルの腕の中で幸せに微笑むフィオナ。
「僕の星を捨てた報い、たっぷりと受けてもらうよ?」
圧倒的な光を放つ幼なじみによる、最高に華やかな逆転劇がいま始まる!

王子様への置き手紙
あおき華
恋愛
フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯
小説家になろうにも掲載しています。

聖女の座を追われた私は田舎で畑を耕すつもりが、辺境伯様に「君は畑担当ね」と強引に任命されました
さら
恋愛
王都で“聖女”として人々を癒やし続けてきたリーネ。だが「加護が弱まった」と政争の口実にされ、無慈悲に追放されてしまう。行き場を失った彼女が選んだのは、幼い頃からの夢――のんびり畑を耕す暮らしだった。
ところが辺境の村にたどり着いた途端、無骨で豪胆な領主・辺境伯に「君は畑担当だ」と強引に任命されてしまう。荒れ果てた土地、困窮する領民たち、そして王都から伸びる陰謀の影。追放されたはずの聖女は、鍬を握り、祈りを土に注ぐことで再び人々に希望を芽吹かせていく。
「畑担当の聖女さま」と呼ばれながら笑顔を取り戻していくリーネ。そして彼女を真っ直ぐに支える辺境伯との距離も、少しずつ近づいて……?
畑から始まるスローライフと、不器用な辺境伯との恋。追放された聖女が見つけた本当の居場所は、王都の玉座ではなく、土と緑と温かな人々に囲まれた辺境の畑だった――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















