3 / 4
第3章:暴かれる真実と静かなる“ざまぁ”
しおりを挟む
それは、私──クレスタ・アルグレインが、新しい生活を始めてからひと月ほど経った頃のことだった。
アルグレイン男爵家の屋敷での日々は、思ったより穏やかで、夫であるジークフリート・アルグレインも淡々としながら私を大切に扱ってくれている。
かつて王太子アレクシオン殿下から婚約破棄を言い渡されたときの傷は、まだ完全に癒えたわけではない。けれど、少しずつ、私は新しい人生を受け入れつつあった。
ジークフリートとともに領地の状況を学んだり、村々を視察したり、使用人たちと談笑したり──そうした日常は、私が思い描いていた“政略結婚”とは違って、どこか温かみを帯びていた。
「冷血」と噂されている夫は、実際には領民をよく見ており、控えめながらも私を気遣う優しさを持っている。
私はまだ完全に彼を信用しきれてはいない……それでも、彼と向き合うほどに胸がほっとする場面が増えていた。
――しかし、その静かな日常は、私が知らないところで少しずつ亀裂を見せ始めていた。
ある日、私は屋敷の一角にある書庫で資料を読んでいた。
ジークフリートに借りた領地関連の古い記録をめくりながら、先代男爵の治世や歴史をざっと追っている。
そこへ、軽いノックの音。ドアを開けて入ってきたのは侍女のモニカだった。
「奥様、失礼します。少しお時間をよろしいでしょうか?」
「ええ、かまいませんよ。どうかしたの?」
使い慣れた椅子から腰を上げ、私はモニカに向き直った。すると、彼女は紙片を私に差し出す。
「先ほど、街の知り合いからこっそり回ってきた情報がありまして……奥様にもお伝えしたほうがいいかと思い」
紙片を受け取ると、そこには短い文章が綴られていた。
『王太子アレクシオン殿下が、再び旧エルバンシュ侯爵家に関する調査を行っている。何を探っているのか不明だが、クレスタ様との縁を再度話題にしている可能性がある』
――思わず息が詰まる。王太子は私を捨てたはずなのに、今になって何を……?
「……これは、確かな情報なの?」
「噂レベルかもしれませんが、街の商人や官吏から同じ話が何度か上がっているようです。殿下の命で記録を漁っているらしく……」
モニカは言いづらそうに、けれど誠実な目で私を見つめていた。
「もし、このまま放っておくと、また王太子殿下が奥様に絡むようなことが起きるかもしれません。念のため、お知らせを……」
私は紙片を握りしめ、胸の奥が妙にざわつくのを感じる。
(王太子が、私を今さら何のために? 平民の少女ミーナを選んだのは彼自身。私など放っておけばいいのに)
嫌な予感がする。まだ何の根拠もないけれど、胸が落ち着かない。
「ありがとう、モニカ。念のためジークフリートにも伝えておくわ」
「はい、何かあればすぐお申し付けください」
彼女が頭を下げて部屋を出ていくと、私はもう一度その紙片に視線を落とした。
王太子アレクシオンとミーナの“美談”は、今も一部では支持されている。けれど、近頃は“あまりの身勝手”だという批判もちらほら聞こえてくる、と聞いたことがある。
(王太子の名声は決して盤石ではない。むしろ最近は、周囲の反発も強まっているらしい……)
その鬱憤を晴らすために、再び私を引き合いに出そうというのだろうか。
私は書庫の窓から外を見やる。晴れ渡る空が、どこか不穏に感じられた。
その日の夕方、ジークフリートが書斎にいると聞き、私は紙片を持って報告に行った。
ノックをして中へ入ると、ジークフリートは机に山積みの書類を前にして軽く眉をひそめていた。
「ジークフリート様、少しよろしいですか?」
私が控えめに声をかけると、彼はすぐに顔を上げる。
「どうした? 表情が優れないな」
その一言に、少しだけ気持ちがほぐれる。彼はいつだって、私の様子をきちんと見ていてくれるのだ。
私はモニカから受け取った紙片を差し出し、王太子が私やエルバンシュ家を再度調べているという噂を伝えた。
ジークフリートは黙ってそれを読み、眉をひそめたまま考え込む。
「……どうして、今さら。また何か仕掛けるつもりなのか」
私がそう問うと、彼は少し表情を曇らせ、「わからない」と静かに首を横に振った。
「だが、王太子が徒に動くなら、こちらも備えておいたほうがいいだろう。エルバンシュ侯爵家への干渉は、今さら正当化できないはずだが……念のため、情報を集める必要がある」
その声音には、怒りにも似た冷たさが含まれていた。
じっと紙片を見つめるジークフリートの横顔は、いつも以上に険しい。
「……ジークフリート様?」
思わず呼びかけると、彼は目を閉じ、低くため息をついた。
「クレスタ、もし王太子がまたおまえに接触を試みるようなことがあれば、決してひとりで動かないでくれ。かならず俺か、侍女たちに報告するんだ」
「わかりました……」
不安が胸を締めつける。王太子が私に何の用があるのかはわからない。けれど、決して良い意図でないことだけは確信できる。
その翌日、私は用事で街へ出た。
買い付けや領地運営に必要な細々とした雑務を済ませるため、侍女と護衛を連れての外出だ。
先日までは、少しずつ自由な買い物を楽しめるようになっていた私だったが、今日はどこか浮かない気持ちだ。
モニカや屋敷の者たちが懸命に空気を和ませようとしてくれるものの、やはり王太子が私を調べているという事実が頭から離れない。
広場の一角、私は王都の雑踏の中でふと足を止めた。
「奥様、いかがなさいましたか?」
護衛の騎士が心配そうに声をかける。私は首を横に振り、微笑もうとする。
「ごめんなさい。少し疲れてしまっただけ。……もう用事はすんだから、屋敷に戻りましょう」
そう伝え、私たちは馬車に乗り込む。
そのとき、どこからか私を見つめる視線を感じたが、振り向いても人混みがあるだけで、誰が見ているのかはわからなかった。
(……気のせいかもしれない。過剰に警戒しているだけ)
自分にそう言い聞かせながら、私は馬車の揺れに身を任せる。屋敷に着くまでの道のりが、いつになく長く感じられた。
そんな私の不安をさらにかき立てる出来事が起きたのは、その翌週のことである。
夜更け、私は寝室で本を読んでいた。ジークフリートはまだ仕事があるのか書斎にこもったまま。
すると廊下でばたばたと駆け足の音がし、ドアが激しくノックされた。
「奥様、失礼します! 大変です、旦那様が……!」
慌てた声は侍女ではない。屋敷の下男が、青ざめた表情で立っている。
「旦那様がどうかしたの?」
胸がざわつく。彼に何かあったというの?
「先ほど緊急の使いが来て、旦那様は王宮へ向かわれました。あまりに急だったので、詳しい状況をお聞きする間もなく……。ただ、“王太子の命令”とだけはうかがいました」
「王太子、ですって……?」
言葉が詰まる。なぜこんな深夜に王宮から呼び出しが?
先日の情報と繋がっているのだろうか。嫌な胸騒ぎが止まらない。
そのまま、屋敷はざわついた空気に包まれた。ジークフリートは護衛を最小限だけ連れて王宮へ行ったまま、まるで音沙汰がない。
私は不安に耐えきれず、廊下を行ったり来たりするが、今はただ待つしかない。
(こんな真夜中に呼び出して、一体何をするつもりなの……?)
王太子殿下は、平民のミーナとの恋に酔いしれたまま、私を放り出したはずだ。今さら彼がジークフリートを呼びつける理由がわからない。
胸の奥で、不吉な予感が膨らんでいく。
夜が明ける頃、ようやくジークフリートが屋敷に戻った。
急ぎ駆け寄った私の目に映ったのは、疲れ切った表情の彼。いつもは崩さない無表情が、どこか険しさを帯びている。
「ジークフリート様、無事でよかった……! 一体何があったのですか?」
私は早口で問いかける。すると彼は短く息をつき、低い声で言った。
「すまない、少し休む。……話は後でしよう」
そう言い残して足早に自室へ向かう姿は、どこか不機嫌かつ落ち着きを欠いているように見えた。
私は心配と混乱を抱えたまま、彼が休むのを待つ。
侍女たちも、「今は旦那様をそっとしておいてください」と口をそろえる。
(よほど神経をすり減らす出来事があったに違いない)
静かに祈るような気持ちで、私は自室のベッドに腰掛け、夜が明けきった空を見つめる。
外では小鳥がさえずっているのに、屋敷の空気は重く張り詰めていた。
数時間後、私はジークフリートから「書斎へ来てくれ」と呼ばれた。
扉を開けると、彼は窓辺に立って外を見やっている。隠しきれない疲労の影が、その背中に滲んでいた。
「……お加減はいかがですか?」
おずおずと尋ねると、ジークフリートは振り向いて小さく首を振る。
「問題ない。少し仮眠をとったから、もう大丈夫だ。……おまえに、話しておかなくてはならないことがある」
そう言って彼は椅子を勧めてくれた。私が腰を下ろすと、彼も向かいの椅子に深く座る。
「昨夜、王宮から急に召喚を受けた。俺だけでなく、他にも何人かの貴族が呼び出された。言い出したのは――王太子、アレクシオン殿下だ」
私は無意識に喉を鳴らす。
「王太子殿下が……そんな深夜に、一体何を?」
ジークフリートの表情は険しいままだ。
「彼が言うには、“近頃、王宮内で不可解な動きがあり、その捜査に協力してほしい”ということだった。だが実際には、俺を含む特定の貴族に向けて、何やら嫌がらせのような尋問が行われたんだ」
「尋問……?」
胸がざわつく。まさか、ジークフリートが苦しい目に遭ったのだろうか。
彼は続ける。
「王太子は、“クレスタ・エルバンシュとの婚約破棄に関わる不正があったのではないか”などと、的外れなことを言い始めた。自分の意志で破棄したはずなのに、どうやら何者かに仕組まれたと信じたいらしい」
「……馬鹿らしい」
私は思わず嘆息する。破棄したのは彼自身だというのに、今になって責任転嫁をしているのだろうか。
「王太子は、“クレスタは自分に相応しくないと示唆した者がいた”とか、“アルグレイン男爵が裏で工作した”などと……根拠のない言いがかりを並べていた」
「……それ、本気で言っているんですか?」
ジークフリートは静かにうなずく。
「腹立たしいが、王太子は何かしら焦っているのだろう。周囲の支援を得られないどころか、不満が高まっている。だからこそ、自分の婚約破棄を正当化するために、誰かを悪者に仕立てあげたいんだ」
その言葉に、私は激しい怒りを覚えると同時に、得体の知れない恐怖も感じる。
(そんな無茶苦茶な言い分に、何かしら裏があるのでは……?)
ジークフリートは、私の不安を察したように小さく息を吐く。
「今のところ、王太子はまだ公式な手続きを踏んでいない。ただの“任意協力”という名目で、俺たちを呼びつけた。だが、あまりに強引すぎる。王太子にも、まだ表立って動けない事情があるのだろう」
仮にもこの国の次期国王候補である王太子が、こんな不当なやり方をしているとは信じ難い。
「……王様や他の王族方は、これをどうご覧になっているんでしょうか」
「国王は近頃ご体調を崩されていて、政務を取り仕切るのは王太子が中心になっているらしい。だが、その王太子の独善的な行動に対して、周囲の貴族や重臣たちも反感を募らせている。すべてが混乱している状況だ」
そう言って、ジークフリートは拳を握りしめた。まるで堪えきれない怒りを抑えているようにも見える。
「それに、もう一つ厄介なことがある」
ジークフリートの声が低くなる。私はぎゅっと唇を結んだまま聞き入る。
「王太子は、おまえの存在を再び持ち出している。まるで“クレスタが何らかの不正を働いた”かのように吹聴している節がある。具体的な罪名も証拠もないが、噂だけを先行させようとしているようだ」
「……私が不正を?」
バカバカしいにもほどがある。婚約破棄されたのは私のほうで、王太子から一方的に切られただけなのに。
「彼は必死なんだろう。“自分は被害者で、本当はクレスタと何者かが結託して自分を陥れた”とでも言いたいのかもしれない。だが、そんな主張はまともに取り合ってもらえないはずだ」
それでも、王太子という地位を利用して、私にあることないことを吹っかけてくる可能性がある。
私は怒りと恐怖で震えながら、ジークフリートを見つめた。
「……もし、本当に私が何か罪に問われるような事態になったら、どうしましょう」
「それはさせない。俺がいる」
即答するジークフリートの言葉は力強く、しかしその眼差しはどこか苦悩に満ちている。
しばし沈黙が落ちる。部屋に差し込む朝の光が、まるで冷たい影を際立たせているかのようだ。
やがて、ジークフリートは意を決したように椅子から立ち上がった。
「……クレスタ。おまえに話しておきたいことがある。正直、まだ話さなくてもいいと思っていたが、状況が変わった。遅かれ早かれ、おまえも知る必要がある」
「え……?」
彼の声の調子が変わる。まるで、今から重大な秘密を明かすかのように。
「俺が“冷酷な男爵”などと噂されている理由は、単に態度が無愛想だからではない。俺は王国直属の特務機関……その一部を担う立場にある。言うなれば、王国の裏の実務を処理する組織だ」
「特務機関……!」
驚きに思わず息を呑む。確かに、領地運営だけでは説明がつかないほど忙しそうなときがあったし、深夜に書斎で何やら極秘の書類を扱っているような気配も感じていた。
けれど、まさかそんな裏の仕事をしているとは……。
ジークフリートは淡々と続ける。
「先代の国王が治世を安定させるために秘密裏に設けた機関で、貴族や官吏の汚職調査、外部勢力の排除、場合によっては極秘の交渉なども行う。表向きは存在しないことになっているが、実際には国政を影で支える重要な役目だ」
「ということは、ジークフリート様は……国家にとって大切な役職を担っているということですよね」
「そういう言い方もできる。だが、表に出ることはできない。だからこそ“冷徹”や“非情”といった噂を一部で流してきた。下手に人脈を広げられても困るし、近づく者を減らすことで動きやすくなるからな」
私は唇を噛みしめる。そんな事情があったのなら、ジークフリートの不思議な行動にも合点がいく。
「……でも、どうして私との政略結婚を?」
彼はほんの少し黙り、それからゆっくりとした口調で言葉を紡いだ。
「王太子の婚約破棄が決まったと聞いたとき、俺は放っておけなかった。おまえが不当に扱われるのはわかっていたし、何より……」
そこで言葉を切り、彼は表情を伏せる。
「俺は、おまえのことをずっと気にかけていたんだ。貴族社会の裏側を眺める立場として、エルバンシュ侯爵家の令嬢がどれほど王太子の“義務的な婚約”に苦労していたか、少しだけ知っていた」
――私が、王太子殿下の正妃候補として厳しい教育を受け、社交界の表舞台で消耗している。
ときには嫉妬に満ちた女性から陰口を叩かれ、ときには王太子周辺の派閥争いに巻き込まれかけたこともある。
「おまえの姿を見ていて、なんとか助けになりたいと思っていた。だが、王太子の婚約者である以上、俺の立場で手を差し伸べることは難しかった。……だから、婚約破棄の話を聞いたとき、俺はすぐに動いたんだ」
ジークフリートの声には静かな決意が滲んでいる。
「もちろん、アルグレイン男爵家としてもエルバンシュ家との結びつきは悪い話ではない。おまえを迎え入れることは、政治的にも利点があると思った。しかし、その裏には俺の個人的な……愛情、というには浅ましいかもしれないが、そういう想いもあった」
愛情。
その言葉に、私の胸がドキリと大きく鼓動する。
ジークフリートが私に想いを寄せていたというのか。
たしかに、彼が私をいたわるような視線を向けてくれる場面は何度もあった。だけど、その正体が“愛情”だなんて思いもよらなかった。
「冷血だと呼ばれながら、こうして私を……救ってくださったのですね」
思わず呟くと、彼は苦笑まじりに短く息を吐く。
「救ったなどと大層なものではないさ。おまえのほうがむしろ強かった。あの王太子の婚約破棄を受けても、それを表に出さず気丈に振る舞っていた。……だが、それが余計に胸に刺さったんだ。人知れず痛みに耐えている姿が」
ジークフリートの声は低く、けれどどこか優しい。
私は思わず目を伏せ、こみ上げる想いをこらえる。
「……ありがとうございます。こんな形で真相を知ることになるなんて想像もしなかったけれど、私には、あなたの言葉がとても嬉しいです」
正直、今は頭が混乱している。国家の裏を担う特務機関、偽りの冷血イメージ、そして“愛情”という言葉──すべてが衝撃的すぎる。
けれど、ジークフリートが不器用ながら私を守りたいと思ってくれていたのは、確かに伝わった。
私は彼の瞳をじっと見つめ、はっきりと口にする。
「ジークフリート様、わたし……信じます。あなたは決して悪い人ではない。裏の仕事が何であれ、私はあなたを信じます」
そこには偽りのない気持ちがあった。
ジークフリートは驚いたように目を見張り、それから小さくうなずく。
「すまない。こんな危険な立場に巻き込んでしまって。それでもおまえを守りたいと願ったのは、俺のわがままだ」
「わがままだなんて。……そのおかげで、わたしはこうして生きる道を見つけられました。王太子殿下の婚約破棄で人生が暗転すると思っていたのに、あなたが手を差し伸べてくれたから」
そう言い終えると、ジークフリートは微かに目を細め、私の肩にそっと手を置く。
その温もりは、決して冷たいものではない。むしろ、私の不安をすくい上げるような力強さがあった。
しばし、言葉のない時間が流れる。
けれど、深い沈黙の中で、私たちは互いにわかり合えたような気がした。
――しかし、現実は甘いだけではない。王太子が動き出した今、何らかの圧力が私たちに降りかかる可能性は高い。
やがてジークフリートは手を離し、改めて姿勢を正して言う。
「……王太子が仕掛けてくるのであれば、こちらにも手がある。今の宮廷には、俺の同僚たちが水面下で情報を収集している。いずれ必ず、やつの不正や矛盾が露呈するはずだ」
私の胸に、小さな希望が灯る。
「つまり、王太子が勝手に私を陥れようとしても、その裏付けはすべて崩れる、と……?」
「そうだ。もし彼がさらに強引に出るなら、こっちも準備を整えて“ざまぁ”と言わんばかりに反撃させてもらおう。……国の裏を担う者として、これ以上は黙っていられない」
“ざまぁ”という言葉に、私は思わず小さく笑みをこぼす。
「この国には正義がないのかと、ずっと思っていました。……あの婚約破棄も、王太子のわがままで許されるのかと」
「正義というより、バランスだ。王太子が暴走すれば、いつか必ず揺り戻しが来る。俺たちがその揺り戻しを後押ししてやるだけさ」
ジークフリートの瞳が鋭い光を帯びる。そこには、冷静な怒りと決意が垣間見えた。
私はそっとまぶたを閉じ、胸の奥にわいてくる感情を確かめる。
(あの方から受けた屈辱を、私は望んで仕返ししたいわけではない。でも……もうこれ以上、私を傷つけるのはやめてほしい)
もし王太子が、いまの私たちを壊そうとするなら、それは許せない。
思わず手を握りしめると、ジークフリートがその手に軽く触れてくれた。
「大丈夫だ、クレスタ。怖がることはない。……最後には、やつを静かに追い詰めてやる」
その言葉を聞いて、私は深くうなずいた。
そう、もう私は逃げない。過去の痛みに縛られ続けるのではなく、今はジークフリートとともに歩んでいく。
――そして、王太子アレクシオンが引き起こそうとしている混乱は、やがて自らの首を絞めることになるだろう。
彼の無責任な“真実の愛”とやらの代償を、まもなく自分の身をもって思い知るに違いないのだから。
◇◇◇
その数日後。
王宮の一角では、小さな会合が開かれていた。そこに顔をそろえたのは、今の王太子政権に対して批判的な立場を持つ貴族や軍関係者ばかり。
参加者の大半は口には出さないものの、王太子の婚約破棄から今日までの言動に疑問を持ち、“真実の愛”を謳う彼に不信感を抱いている。
「あの平民の少女、ミーナは本当に清廉潔白なのか……?」
「王太子殿下の身辺調査をすれば、妙な出費や動きが見えると聞く」
そんな囁きが広がり始めていたのだ。
実際、この数か月、王太子のもとには大量の資金が流れ込み、それがどこへ消えているのか不透明という噂がある。
さらに、ミーナという少女の正体についても、ただの平民ではなく、何らかの組織に繋がっている可能性があるという声が密かに上がっていた。
それを裏付ける証拠はまだ乏しいものの、火のないところに煙は立たないとも言う。
「このまま王太子殿下が次期国王となるのは、いささか危ういのではないか」
そんな不安が、各方面で噴出し始めていた。
――そして、その会合の場には、ジークフリート・アルグレインの姿もあった。
公式には姿を見せず、密かに情報を交換する。彼は王太子に直接対立するというより、冷静に証拠を集め、いざというとき動けるよう準備を進めている。
「……殿下がクレスタ様に罪を着せようとしているらしいが、その裏には何がある?」
「おそらく、王太子の焦りだろう。クレスタだけではなく、いくつかの家にも根拠のない嫌疑をかけている。王太子自身が追い詰められている証拠だ」
低い声で交わされる密談。そこには確かな“ざまぁ”の兆しが見えつつあった。
なぜならば。
“真実の愛”を掲げ、婚約破棄を強行した王太子とミーナに対し、最初はロマンチックだと支持していた人々でさえ、その矛盾に気づき始めているのだ。
王族としての責務を放棄し、国政を混乱に陥れ、無責任な言動を繰り返す。いくら恋愛感情を盾にしても、それでは国民の支持を得られない。
加えて、先代国王の配下だった特務機関が水面下で動いている。王太子の不正な金の流れや、ミーナの真の姿を暴くのは、もはや時間の問題だ。
◇◇◇
一方その頃、私はアルグレイン邸でやるべきことを粛々と進めていた。
ジークフリートや使用人たちの助けもあり、領地関連の書類整理や収支の見直しを行ったり、時折田舎の村を訪れて住民の声を聞いたり。
そうした日常が、私に安定感を与えてくれていた。
(あの王太子が、今さら何を言おうとも、私は堂々としていよう)
そう心に決め、先日のような恐怖は薄れつつある。
そんな折、ひとつ朗報が舞い込んできた。
数日前、王宮の重臣がジークフリートに密書を送り、近々“王太子の挙動に関する正式な協議”が行われる見込みだと伝えてきたのだ。
つまり、王太子の独裁的な振る舞いが看過できない段階に来ているということ。
ジークフリートによれば、その協議の場で王太子の不正が事実として示されれば、彼の立場は急速に悪化し、最悪の場合、王太子の地位を失う可能性すらあるという。
「これまで、自分こそが正しいと唱えてきた王太子が、どんな表情をするのか……考えるだけで空恐ろしいですね」
私がそう呟くと、ジークフリートは静かな目を細める。
「王太子自身がどう転落するかはわからないが、少なくともおまえを陥れる口実はなくなるだろう。俺たちが集めた証拠を使えば、奴が真に追及される立場だと証明できる」
その言葉に、私は胸を撫で下ろす。
(あのわがままな殿下が、ようやく自分の蒔いた種の責任を負う時が来るのかもしれない)
しかし、私の穏やかな気持ちとは裏腹に、運命はさらに大きく動いた。
――協議が行われるという連絡から数日後、王太子は突然、自らの“正当性”を主張するための集会を開くと宣言したのだ。
「殿下が、平民のミーナ嬢との婚約を正式に発表し、さらに自身に向けられた疑惑を全否定する場を設けるらしい」
その知らせを聞いたとき、私はジークフリートと顔を見合わせ、嫌な予感に駆られた。
王太子が公の場で一方的に話をするということは、そこに私たちを“引っ張り出して”何らかのスキャンダルを仕掛ける恐れもある。
ジークフリートも警戒を強め、「俺が先に行って様子を探る。おまえは屋敷で待機していてくれ」と言った。
私はそれに従い、なるべく目立たないよう屋敷で状況を見守る。
(王太子がどんな主張をするにせよ、もう揺るがない証拠を私たちは握っている。……大丈夫)
そう自分に言い聞かせるしかなかった。
そして集会当日。
ジークフリートと少数の部下が王宮へ向かったまま、連絡は途絶えている。
私は大きな窓から外を見つめながら、祈るような気持ちで一人待ち続けた。部屋には侍女のモニカが心配そうに控えている。
やがて夕刻。思ったよりも早く足音が聞こえ、扉が開いた。
「奥様! 旦那様が戻られました。……何かすごい数の馬車と人だかりが玄関先に!」
驚いた調子の侍女の声に、私も慌てて立ち上がる。
廊下を駆けると、玄関ホールにはジークフリートが立っていた。背後には数名の兵士らしき男たちがいて、皆一様に厳しい面持ちをしている。
「ジークフリート様、これは……?」
私が問いかけると、彼は深いため息をつきながら苦々しげに言い放った。
「王太子は自滅したよ。……あれだけ声高に“自分は正しい”と主張した矢先、俺たちが集めた証拠を逆に突きつけられ、周囲の貴族たちから総攻撃を受けた。金の不正流用や、ミーナの黒い噂も引きずり出されたんだ」
「そ、それで、どうなったんですか?」
彼は唇をきつく引き結び、言葉を続ける。
「王太子は取り乱して、ついに本性を剥き出しにした。ミーナも“わたしは悪くない!”と泣き叫び、周囲に牙をむいた。結局、王太子の地位は一時停止となり、正式な査問が行われることになった」
胸がざわつく。あの王太子が……。
かつて私を一方的に捨てた人物が、こうして自ら泥沼にはまりこんでいるのだ。
「当然だな。あれだけ周りを裏切り、責任転嫁ばかりしてきたんだ。いずれこうなる運命だった」
ジークフリートの厳しい声音からは、溜め込んだ怒りと呆れが滲んでいる。
「じゃあ、あのミーナという平民の少女は……」
「彼女も追及を免れないだろう。今は王太子の愛人のような立場しかなく、正式な貴族の籍も得ていない。証拠次第では犯罪に問われる可能性もある。……ざまぁと言うのは下品かもしれないが、自業自得だ」
私の心には複雑な想いが渦巻く。けれど、彼らに対して同情はわかない。
「あの方たちは、“真実の愛”などと美化して、周囲を振り回していた。無責任な行為の代償が、こうして訪れたのですね」
そう呟くと、ジークフリートは疲れた表情で微かに笑う。
「おまえが何も手を下さなくても、勝手に破滅の道を選んでいるわけだ。……まあ、これから正式な裁定が下るまでに、多少の時間はかかるだろうが、王太子が以前のように権勢を振るうことはもうない」
私は安堵とともに、長年抱えてきたわだかまりが少しだけ溶けていくのを感じた。
――ざまぁ。
心の中でそう呟く。
王太子とミーナがどう転落するか、私は直接見届けようとは思わない。ただ、私の人生を台無しにしかけた二人が、自ら破滅の道に足を突っ込んだことは、少なからず“因果応報”だと思う。
そう、私は何もせず、ただ幸せに生きようと決めた。だからこそ、あの人たちは勝手に転落していくのだ。
ジークフリートが私の肩にそっと手を置く。
「クレスタ……おまえはもう、自由だ。王太子とのことに縛られる必要はない。俺も“特務機関”として、彼らが逃げられないように最後まで監視する。おまえに危害が及ぶこともないだろう」
その言葉に、私は素直に微笑む。頬に涙が伝いそうになるのを、なんとかこらえて。
「ありがとう、ジークフリート様。……あなたのおかげで、私はもう大丈夫です」
この瞬間、私の中から王太子への未練や恐れがきれいに消え去った気がした。
王太子とミーナは、国中に喧伝した“真実の愛”の正体を自ら暴かれ、信頼も尊厳も失った。
私にとっては、まさに静かなる“ざまぁ”だったのだろう。復讐のために手を染めることなく、ただ歩みを進めた先で、彼らが勝手に奈落へと落ちていく。
こうして、私の心は確かに軽くなっていく。過去の婚約破棄で負った傷が、すっと薄れていくのを感じる。
――私をいたわってくれる人がいる。私はもう、ひとりじゃない。
「疲れただろう? 今日のことは一度忘れて、今夜は休め。……明日からは、領地の視察を再開できるぞ」
ジークフリートが優しい声音で言う。私は微笑みながらうなずき、彼の胸へ少しだけ身を寄せる。
「はい……。あなたと一緒に、いろんなところを見て回りたいです」
その言葉に、彼の腕がほんのわずか強く私を抱き留める。
抑えきれない涙が、一筋だけこぼれ落ちた。今度はうれしい涙だ。
こうして、私を踏み台にした王太子とミーナは自滅した。
私とジークフリートの人生は、ここから本当の意味で始まろうとしている。
“白い結婚”のはずだったのに、仮面夫婦のつもりだったのに。いつの間にか、私たちはお互いを気遣い合い、守り合う関係になっていた。
(私の心が、確かに彼へと傾いている……)
そんな自覚が、私にあたたかな光を注いでくれる。
そして、王太子とミーナが正式に処罰されるかどうかは、まだ今後の裁定次第。
だが、少なくとも彼らが二度と私を苦しめることはないだろう。そう確信できるだけで、私は十分だった。
アルグレイン男爵家の屋敷での日々は、思ったより穏やかで、夫であるジークフリート・アルグレインも淡々としながら私を大切に扱ってくれている。
かつて王太子アレクシオン殿下から婚約破棄を言い渡されたときの傷は、まだ完全に癒えたわけではない。けれど、少しずつ、私は新しい人生を受け入れつつあった。
ジークフリートとともに領地の状況を学んだり、村々を視察したり、使用人たちと談笑したり──そうした日常は、私が思い描いていた“政略結婚”とは違って、どこか温かみを帯びていた。
「冷血」と噂されている夫は、実際には領民をよく見ており、控えめながらも私を気遣う優しさを持っている。
私はまだ完全に彼を信用しきれてはいない……それでも、彼と向き合うほどに胸がほっとする場面が増えていた。
――しかし、その静かな日常は、私が知らないところで少しずつ亀裂を見せ始めていた。
ある日、私は屋敷の一角にある書庫で資料を読んでいた。
ジークフリートに借りた領地関連の古い記録をめくりながら、先代男爵の治世や歴史をざっと追っている。
そこへ、軽いノックの音。ドアを開けて入ってきたのは侍女のモニカだった。
「奥様、失礼します。少しお時間をよろしいでしょうか?」
「ええ、かまいませんよ。どうかしたの?」
使い慣れた椅子から腰を上げ、私はモニカに向き直った。すると、彼女は紙片を私に差し出す。
「先ほど、街の知り合いからこっそり回ってきた情報がありまして……奥様にもお伝えしたほうがいいかと思い」
紙片を受け取ると、そこには短い文章が綴られていた。
『王太子アレクシオン殿下が、再び旧エルバンシュ侯爵家に関する調査を行っている。何を探っているのか不明だが、クレスタ様との縁を再度話題にしている可能性がある』
――思わず息が詰まる。王太子は私を捨てたはずなのに、今になって何を……?
「……これは、確かな情報なの?」
「噂レベルかもしれませんが、街の商人や官吏から同じ話が何度か上がっているようです。殿下の命で記録を漁っているらしく……」
モニカは言いづらそうに、けれど誠実な目で私を見つめていた。
「もし、このまま放っておくと、また王太子殿下が奥様に絡むようなことが起きるかもしれません。念のため、お知らせを……」
私は紙片を握りしめ、胸の奥が妙にざわつくのを感じる。
(王太子が、私を今さら何のために? 平民の少女ミーナを選んだのは彼自身。私など放っておけばいいのに)
嫌な予感がする。まだ何の根拠もないけれど、胸が落ち着かない。
「ありがとう、モニカ。念のためジークフリートにも伝えておくわ」
「はい、何かあればすぐお申し付けください」
彼女が頭を下げて部屋を出ていくと、私はもう一度その紙片に視線を落とした。
王太子アレクシオンとミーナの“美談”は、今も一部では支持されている。けれど、近頃は“あまりの身勝手”だという批判もちらほら聞こえてくる、と聞いたことがある。
(王太子の名声は決して盤石ではない。むしろ最近は、周囲の反発も強まっているらしい……)
その鬱憤を晴らすために、再び私を引き合いに出そうというのだろうか。
私は書庫の窓から外を見やる。晴れ渡る空が、どこか不穏に感じられた。
その日の夕方、ジークフリートが書斎にいると聞き、私は紙片を持って報告に行った。
ノックをして中へ入ると、ジークフリートは机に山積みの書類を前にして軽く眉をひそめていた。
「ジークフリート様、少しよろしいですか?」
私が控えめに声をかけると、彼はすぐに顔を上げる。
「どうした? 表情が優れないな」
その一言に、少しだけ気持ちがほぐれる。彼はいつだって、私の様子をきちんと見ていてくれるのだ。
私はモニカから受け取った紙片を差し出し、王太子が私やエルバンシュ家を再度調べているという噂を伝えた。
ジークフリートは黙ってそれを読み、眉をひそめたまま考え込む。
「……どうして、今さら。また何か仕掛けるつもりなのか」
私がそう問うと、彼は少し表情を曇らせ、「わからない」と静かに首を横に振った。
「だが、王太子が徒に動くなら、こちらも備えておいたほうがいいだろう。エルバンシュ侯爵家への干渉は、今さら正当化できないはずだが……念のため、情報を集める必要がある」
その声音には、怒りにも似た冷たさが含まれていた。
じっと紙片を見つめるジークフリートの横顔は、いつも以上に険しい。
「……ジークフリート様?」
思わず呼びかけると、彼は目を閉じ、低くため息をついた。
「クレスタ、もし王太子がまたおまえに接触を試みるようなことがあれば、決してひとりで動かないでくれ。かならず俺か、侍女たちに報告するんだ」
「わかりました……」
不安が胸を締めつける。王太子が私に何の用があるのかはわからない。けれど、決して良い意図でないことだけは確信できる。
その翌日、私は用事で街へ出た。
買い付けや領地運営に必要な細々とした雑務を済ませるため、侍女と護衛を連れての外出だ。
先日までは、少しずつ自由な買い物を楽しめるようになっていた私だったが、今日はどこか浮かない気持ちだ。
モニカや屋敷の者たちが懸命に空気を和ませようとしてくれるものの、やはり王太子が私を調べているという事実が頭から離れない。
広場の一角、私は王都の雑踏の中でふと足を止めた。
「奥様、いかがなさいましたか?」
護衛の騎士が心配そうに声をかける。私は首を横に振り、微笑もうとする。
「ごめんなさい。少し疲れてしまっただけ。……もう用事はすんだから、屋敷に戻りましょう」
そう伝え、私たちは馬車に乗り込む。
そのとき、どこからか私を見つめる視線を感じたが、振り向いても人混みがあるだけで、誰が見ているのかはわからなかった。
(……気のせいかもしれない。過剰に警戒しているだけ)
自分にそう言い聞かせながら、私は馬車の揺れに身を任せる。屋敷に着くまでの道のりが、いつになく長く感じられた。
そんな私の不安をさらにかき立てる出来事が起きたのは、その翌週のことである。
夜更け、私は寝室で本を読んでいた。ジークフリートはまだ仕事があるのか書斎にこもったまま。
すると廊下でばたばたと駆け足の音がし、ドアが激しくノックされた。
「奥様、失礼します! 大変です、旦那様が……!」
慌てた声は侍女ではない。屋敷の下男が、青ざめた表情で立っている。
「旦那様がどうかしたの?」
胸がざわつく。彼に何かあったというの?
「先ほど緊急の使いが来て、旦那様は王宮へ向かわれました。あまりに急だったので、詳しい状況をお聞きする間もなく……。ただ、“王太子の命令”とだけはうかがいました」
「王太子、ですって……?」
言葉が詰まる。なぜこんな深夜に王宮から呼び出しが?
先日の情報と繋がっているのだろうか。嫌な胸騒ぎが止まらない。
そのまま、屋敷はざわついた空気に包まれた。ジークフリートは護衛を最小限だけ連れて王宮へ行ったまま、まるで音沙汰がない。
私は不安に耐えきれず、廊下を行ったり来たりするが、今はただ待つしかない。
(こんな真夜中に呼び出して、一体何をするつもりなの……?)
王太子殿下は、平民のミーナとの恋に酔いしれたまま、私を放り出したはずだ。今さら彼がジークフリートを呼びつける理由がわからない。
胸の奥で、不吉な予感が膨らんでいく。
夜が明ける頃、ようやくジークフリートが屋敷に戻った。
急ぎ駆け寄った私の目に映ったのは、疲れ切った表情の彼。いつもは崩さない無表情が、どこか険しさを帯びている。
「ジークフリート様、無事でよかった……! 一体何があったのですか?」
私は早口で問いかける。すると彼は短く息をつき、低い声で言った。
「すまない、少し休む。……話は後でしよう」
そう言い残して足早に自室へ向かう姿は、どこか不機嫌かつ落ち着きを欠いているように見えた。
私は心配と混乱を抱えたまま、彼が休むのを待つ。
侍女たちも、「今は旦那様をそっとしておいてください」と口をそろえる。
(よほど神経をすり減らす出来事があったに違いない)
静かに祈るような気持ちで、私は自室のベッドに腰掛け、夜が明けきった空を見つめる。
外では小鳥がさえずっているのに、屋敷の空気は重く張り詰めていた。
数時間後、私はジークフリートから「書斎へ来てくれ」と呼ばれた。
扉を開けると、彼は窓辺に立って外を見やっている。隠しきれない疲労の影が、その背中に滲んでいた。
「……お加減はいかがですか?」
おずおずと尋ねると、ジークフリートは振り向いて小さく首を振る。
「問題ない。少し仮眠をとったから、もう大丈夫だ。……おまえに、話しておかなくてはならないことがある」
そう言って彼は椅子を勧めてくれた。私が腰を下ろすと、彼も向かいの椅子に深く座る。
「昨夜、王宮から急に召喚を受けた。俺だけでなく、他にも何人かの貴族が呼び出された。言い出したのは――王太子、アレクシオン殿下だ」
私は無意識に喉を鳴らす。
「王太子殿下が……そんな深夜に、一体何を?」
ジークフリートの表情は険しいままだ。
「彼が言うには、“近頃、王宮内で不可解な動きがあり、その捜査に協力してほしい”ということだった。だが実際には、俺を含む特定の貴族に向けて、何やら嫌がらせのような尋問が行われたんだ」
「尋問……?」
胸がざわつく。まさか、ジークフリートが苦しい目に遭ったのだろうか。
彼は続ける。
「王太子は、“クレスタ・エルバンシュとの婚約破棄に関わる不正があったのではないか”などと、的外れなことを言い始めた。自分の意志で破棄したはずなのに、どうやら何者かに仕組まれたと信じたいらしい」
「……馬鹿らしい」
私は思わず嘆息する。破棄したのは彼自身だというのに、今になって責任転嫁をしているのだろうか。
「王太子は、“クレスタは自分に相応しくないと示唆した者がいた”とか、“アルグレイン男爵が裏で工作した”などと……根拠のない言いがかりを並べていた」
「……それ、本気で言っているんですか?」
ジークフリートは静かにうなずく。
「腹立たしいが、王太子は何かしら焦っているのだろう。周囲の支援を得られないどころか、不満が高まっている。だからこそ、自分の婚約破棄を正当化するために、誰かを悪者に仕立てあげたいんだ」
その言葉に、私は激しい怒りを覚えると同時に、得体の知れない恐怖も感じる。
(そんな無茶苦茶な言い分に、何かしら裏があるのでは……?)
ジークフリートは、私の不安を察したように小さく息を吐く。
「今のところ、王太子はまだ公式な手続きを踏んでいない。ただの“任意協力”という名目で、俺たちを呼びつけた。だが、あまりに強引すぎる。王太子にも、まだ表立って動けない事情があるのだろう」
仮にもこの国の次期国王候補である王太子が、こんな不当なやり方をしているとは信じ難い。
「……王様や他の王族方は、これをどうご覧になっているんでしょうか」
「国王は近頃ご体調を崩されていて、政務を取り仕切るのは王太子が中心になっているらしい。だが、その王太子の独善的な行動に対して、周囲の貴族や重臣たちも反感を募らせている。すべてが混乱している状況だ」
そう言って、ジークフリートは拳を握りしめた。まるで堪えきれない怒りを抑えているようにも見える。
「それに、もう一つ厄介なことがある」
ジークフリートの声が低くなる。私はぎゅっと唇を結んだまま聞き入る。
「王太子は、おまえの存在を再び持ち出している。まるで“クレスタが何らかの不正を働いた”かのように吹聴している節がある。具体的な罪名も証拠もないが、噂だけを先行させようとしているようだ」
「……私が不正を?」
バカバカしいにもほどがある。婚約破棄されたのは私のほうで、王太子から一方的に切られただけなのに。
「彼は必死なんだろう。“自分は被害者で、本当はクレスタと何者かが結託して自分を陥れた”とでも言いたいのかもしれない。だが、そんな主張はまともに取り合ってもらえないはずだ」
それでも、王太子という地位を利用して、私にあることないことを吹っかけてくる可能性がある。
私は怒りと恐怖で震えながら、ジークフリートを見つめた。
「……もし、本当に私が何か罪に問われるような事態になったら、どうしましょう」
「それはさせない。俺がいる」
即答するジークフリートの言葉は力強く、しかしその眼差しはどこか苦悩に満ちている。
しばし沈黙が落ちる。部屋に差し込む朝の光が、まるで冷たい影を際立たせているかのようだ。
やがて、ジークフリートは意を決したように椅子から立ち上がった。
「……クレスタ。おまえに話しておきたいことがある。正直、まだ話さなくてもいいと思っていたが、状況が変わった。遅かれ早かれ、おまえも知る必要がある」
「え……?」
彼の声の調子が変わる。まるで、今から重大な秘密を明かすかのように。
「俺が“冷酷な男爵”などと噂されている理由は、単に態度が無愛想だからではない。俺は王国直属の特務機関……その一部を担う立場にある。言うなれば、王国の裏の実務を処理する組織だ」
「特務機関……!」
驚きに思わず息を呑む。確かに、領地運営だけでは説明がつかないほど忙しそうなときがあったし、深夜に書斎で何やら極秘の書類を扱っているような気配も感じていた。
けれど、まさかそんな裏の仕事をしているとは……。
ジークフリートは淡々と続ける。
「先代の国王が治世を安定させるために秘密裏に設けた機関で、貴族や官吏の汚職調査、外部勢力の排除、場合によっては極秘の交渉なども行う。表向きは存在しないことになっているが、実際には国政を影で支える重要な役目だ」
「ということは、ジークフリート様は……国家にとって大切な役職を担っているということですよね」
「そういう言い方もできる。だが、表に出ることはできない。だからこそ“冷徹”や“非情”といった噂を一部で流してきた。下手に人脈を広げられても困るし、近づく者を減らすことで動きやすくなるからな」
私は唇を噛みしめる。そんな事情があったのなら、ジークフリートの不思議な行動にも合点がいく。
「……でも、どうして私との政略結婚を?」
彼はほんの少し黙り、それからゆっくりとした口調で言葉を紡いだ。
「王太子の婚約破棄が決まったと聞いたとき、俺は放っておけなかった。おまえが不当に扱われるのはわかっていたし、何より……」
そこで言葉を切り、彼は表情を伏せる。
「俺は、おまえのことをずっと気にかけていたんだ。貴族社会の裏側を眺める立場として、エルバンシュ侯爵家の令嬢がどれほど王太子の“義務的な婚約”に苦労していたか、少しだけ知っていた」
――私が、王太子殿下の正妃候補として厳しい教育を受け、社交界の表舞台で消耗している。
ときには嫉妬に満ちた女性から陰口を叩かれ、ときには王太子周辺の派閥争いに巻き込まれかけたこともある。
「おまえの姿を見ていて、なんとか助けになりたいと思っていた。だが、王太子の婚約者である以上、俺の立場で手を差し伸べることは難しかった。……だから、婚約破棄の話を聞いたとき、俺はすぐに動いたんだ」
ジークフリートの声には静かな決意が滲んでいる。
「もちろん、アルグレイン男爵家としてもエルバンシュ家との結びつきは悪い話ではない。おまえを迎え入れることは、政治的にも利点があると思った。しかし、その裏には俺の個人的な……愛情、というには浅ましいかもしれないが、そういう想いもあった」
愛情。
その言葉に、私の胸がドキリと大きく鼓動する。
ジークフリートが私に想いを寄せていたというのか。
たしかに、彼が私をいたわるような視線を向けてくれる場面は何度もあった。だけど、その正体が“愛情”だなんて思いもよらなかった。
「冷血だと呼ばれながら、こうして私を……救ってくださったのですね」
思わず呟くと、彼は苦笑まじりに短く息を吐く。
「救ったなどと大層なものではないさ。おまえのほうがむしろ強かった。あの王太子の婚約破棄を受けても、それを表に出さず気丈に振る舞っていた。……だが、それが余計に胸に刺さったんだ。人知れず痛みに耐えている姿が」
ジークフリートの声は低く、けれどどこか優しい。
私は思わず目を伏せ、こみ上げる想いをこらえる。
「……ありがとうございます。こんな形で真相を知ることになるなんて想像もしなかったけれど、私には、あなたの言葉がとても嬉しいです」
正直、今は頭が混乱している。国家の裏を担う特務機関、偽りの冷血イメージ、そして“愛情”という言葉──すべてが衝撃的すぎる。
けれど、ジークフリートが不器用ながら私を守りたいと思ってくれていたのは、確かに伝わった。
私は彼の瞳をじっと見つめ、はっきりと口にする。
「ジークフリート様、わたし……信じます。あなたは決して悪い人ではない。裏の仕事が何であれ、私はあなたを信じます」
そこには偽りのない気持ちがあった。
ジークフリートは驚いたように目を見張り、それから小さくうなずく。
「すまない。こんな危険な立場に巻き込んでしまって。それでもおまえを守りたいと願ったのは、俺のわがままだ」
「わがままだなんて。……そのおかげで、わたしはこうして生きる道を見つけられました。王太子殿下の婚約破棄で人生が暗転すると思っていたのに、あなたが手を差し伸べてくれたから」
そう言い終えると、ジークフリートは微かに目を細め、私の肩にそっと手を置く。
その温もりは、決して冷たいものではない。むしろ、私の不安をすくい上げるような力強さがあった。
しばし、言葉のない時間が流れる。
けれど、深い沈黙の中で、私たちは互いにわかり合えたような気がした。
――しかし、現実は甘いだけではない。王太子が動き出した今、何らかの圧力が私たちに降りかかる可能性は高い。
やがてジークフリートは手を離し、改めて姿勢を正して言う。
「……王太子が仕掛けてくるのであれば、こちらにも手がある。今の宮廷には、俺の同僚たちが水面下で情報を収集している。いずれ必ず、やつの不正や矛盾が露呈するはずだ」
私の胸に、小さな希望が灯る。
「つまり、王太子が勝手に私を陥れようとしても、その裏付けはすべて崩れる、と……?」
「そうだ。もし彼がさらに強引に出るなら、こっちも準備を整えて“ざまぁ”と言わんばかりに反撃させてもらおう。……国の裏を担う者として、これ以上は黙っていられない」
“ざまぁ”という言葉に、私は思わず小さく笑みをこぼす。
「この国には正義がないのかと、ずっと思っていました。……あの婚約破棄も、王太子のわがままで許されるのかと」
「正義というより、バランスだ。王太子が暴走すれば、いつか必ず揺り戻しが来る。俺たちがその揺り戻しを後押ししてやるだけさ」
ジークフリートの瞳が鋭い光を帯びる。そこには、冷静な怒りと決意が垣間見えた。
私はそっとまぶたを閉じ、胸の奥にわいてくる感情を確かめる。
(あの方から受けた屈辱を、私は望んで仕返ししたいわけではない。でも……もうこれ以上、私を傷つけるのはやめてほしい)
もし王太子が、いまの私たちを壊そうとするなら、それは許せない。
思わず手を握りしめると、ジークフリートがその手に軽く触れてくれた。
「大丈夫だ、クレスタ。怖がることはない。……最後には、やつを静かに追い詰めてやる」
その言葉を聞いて、私は深くうなずいた。
そう、もう私は逃げない。過去の痛みに縛られ続けるのではなく、今はジークフリートとともに歩んでいく。
――そして、王太子アレクシオンが引き起こそうとしている混乱は、やがて自らの首を絞めることになるだろう。
彼の無責任な“真実の愛”とやらの代償を、まもなく自分の身をもって思い知るに違いないのだから。
◇◇◇
その数日後。
王宮の一角では、小さな会合が開かれていた。そこに顔をそろえたのは、今の王太子政権に対して批判的な立場を持つ貴族や軍関係者ばかり。
参加者の大半は口には出さないものの、王太子の婚約破棄から今日までの言動に疑問を持ち、“真実の愛”を謳う彼に不信感を抱いている。
「あの平民の少女、ミーナは本当に清廉潔白なのか……?」
「王太子殿下の身辺調査をすれば、妙な出費や動きが見えると聞く」
そんな囁きが広がり始めていたのだ。
実際、この数か月、王太子のもとには大量の資金が流れ込み、それがどこへ消えているのか不透明という噂がある。
さらに、ミーナという少女の正体についても、ただの平民ではなく、何らかの組織に繋がっている可能性があるという声が密かに上がっていた。
それを裏付ける証拠はまだ乏しいものの、火のないところに煙は立たないとも言う。
「このまま王太子殿下が次期国王となるのは、いささか危ういのではないか」
そんな不安が、各方面で噴出し始めていた。
――そして、その会合の場には、ジークフリート・アルグレインの姿もあった。
公式には姿を見せず、密かに情報を交換する。彼は王太子に直接対立するというより、冷静に証拠を集め、いざというとき動けるよう準備を進めている。
「……殿下がクレスタ様に罪を着せようとしているらしいが、その裏には何がある?」
「おそらく、王太子の焦りだろう。クレスタだけではなく、いくつかの家にも根拠のない嫌疑をかけている。王太子自身が追い詰められている証拠だ」
低い声で交わされる密談。そこには確かな“ざまぁ”の兆しが見えつつあった。
なぜならば。
“真実の愛”を掲げ、婚約破棄を強行した王太子とミーナに対し、最初はロマンチックだと支持していた人々でさえ、その矛盾に気づき始めているのだ。
王族としての責務を放棄し、国政を混乱に陥れ、無責任な言動を繰り返す。いくら恋愛感情を盾にしても、それでは国民の支持を得られない。
加えて、先代国王の配下だった特務機関が水面下で動いている。王太子の不正な金の流れや、ミーナの真の姿を暴くのは、もはや時間の問題だ。
◇◇◇
一方その頃、私はアルグレイン邸でやるべきことを粛々と進めていた。
ジークフリートや使用人たちの助けもあり、領地関連の書類整理や収支の見直しを行ったり、時折田舎の村を訪れて住民の声を聞いたり。
そうした日常が、私に安定感を与えてくれていた。
(あの王太子が、今さら何を言おうとも、私は堂々としていよう)
そう心に決め、先日のような恐怖は薄れつつある。
そんな折、ひとつ朗報が舞い込んできた。
数日前、王宮の重臣がジークフリートに密書を送り、近々“王太子の挙動に関する正式な協議”が行われる見込みだと伝えてきたのだ。
つまり、王太子の独裁的な振る舞いが看過できない段階に来ているということ。
ジークフリートによれば、その協議の場で王太子の不正が事実として示されれば、彼の立場は急速に悪化し、最悪の場合、王太子の地位を失う可能性すらあるという。
「これまで、自分こそが正しいと唱えてきた王太子が、どんな表情をするのか……考えるだけで空恐ろしいですね」
私がそう呟くと、ジークフリートは静かな目を細める。
「王太子自身がどう転落するかはわからないが、少なくともおまえを陥れる口実はなくなるだろう。俺たちが集めた証拠を使えば、奴が真に追及される立場だと証明できる」
その言葉に、私は胸を撫で下ろす。
(あのわがままな殿下が、ようやく自分の蒔いた種の責任を負う時が来るのかもしれない)
しかし、私の穏やかな気持ちとは裏腹に、運命はさらに大きく動いた。
――協議が行われるという連絡から数日後、王太子は突然、自らの“正当性”を主張するための集会を開くと宣言したのだ。
「殿下が、平民のミーナ嬢との婚約を正式に発表し、さらに自身に向けられた疑惑を全否定する場を設けるらしい」
その知らせを聞いたとき、私はジークフリートと顔を見合わせ、嫌な予感に駆られた。
王太子が公の場で一方的に話をするということは、そこに私たちを“引っ張り出して”何らかのスキャンダルを仕掛ける恐れもある。
ジークフリートも警戒を強め、「俺が先に行って様子を探る。おまえは屋敷で待機していてくれ」と言った。
私はそれに従い、なるべく目立たないよう屋敷で状況を見守る。
(王太子がどんな主張をするにせよ、もう揺るがない証拠を私たちは握っている。……大丈夫)
そう自分に言い聞かせるしかなかった。
そして集会当日。
ジークフリートと少数の部下が王宮へ向かったまま、連絡は途絶えている。
私は大きな窓から外を見つめながら、祈るような気持ちで一人待ち続けた。部屋には侍女のモニカが心配そうに控えている。
やがて夕刻。思ったよりも早く足音が聞こえ、扉が開いた。
「奥様! 旦那様が戻られました。……何かすごい数の馬車と人だかりが玄関先に!」
驚いた調子の侍女の声に、私も慌てて立ち上がる。
廊下を駆けると、玄関ホールにはジークフリートが立っていた。背後には数名の兵士らしき男たちがいて、皆一様に厳しい面持ちをしている。
「ジークフリート様、これは……?」
私が問いかけると、彼は深いため息をつきながら苦々しげに言い放った。
「王太子は自滅したよ。……あれだけ声高に“自分は正しい”と主張した矢先、俺たちが集めた証拠を逆に突きつけられ、周囲の貴族たちから総攻撃を受けた。金の不正流用や、ミーナの黒い噂も引きずり出されたんだ」
「そ、それで、どうなったんですか?」
彼は唇をきつく引き結び、言葉を続ける。
「王太子は取り乱して、ついに本性を剥き出しにした。ミーナも“わたしは悪くない!”と泣き叫び、周囲に牙をむいた。結局、王太子の地位は一時停止となり、正式な査問が行われることになった」
胸がざわつく。あの王太子が……。
かつて私を一方的に捨てた人物が、こうして自ら泥沼にはまりこんでいるのだ。
「当然だな。あれだけ周りを裏切り、責任転嫁ばかりしてきたんだ。いずれこうなる運命だった」
ジークフリートの厳しい声音からは、溜め込んだ怒りと呆れが滲んでいる。
「じゃあ、あのミーナという平民の少女は……」
「彼女も追及を免れないだろう。今は王太子の愛人のような立場しかなく、正式な貴族の籍も得ていない。証拠次第では犯罪に問われる可能性もある。……ざまぁと言うのは下品かもしれないが、自業自得だ」
私の心には複雑な想いが渦巻く。けれど、彼らに対して同情はわかない。
「あの方たちは、“真実の愛”などと美化して、周囲を振り回していた。無責任な行為の代償が、こうして訪れたのですね」
そう呟くと、ジークフリートは疲れた表情で微かに笑う。
「おまえが何も手を下さなくても、勝手に破滅の道を選んでいるわけだ。……まあ、これから正式な裁定が下るまでに、多少の時間はかかるだろうが、王太子が以前のように権勢を振るうことはもうない」
私は安堵とともに、長年抱えてきたわだかまりが少しだけ溶けていくのを感じた。
――ざまぁ。
心の中でそう呟く。
王太子とミーナがどう転落するか、私は直接見届けようとは思わない。ただ、私の人生を台無しにしかけた二人が、自ら破滅の道に足を突っ込んだことは、少なからず“因果応報”だと思う。
そう、私は何もせず、ただ幸せに生きようと決めた。だからこそ、あの人たちは勝手に転落していくのだ。
ジークフリートが私の肩にそっと手を置く。
「クレスタ……おまえはもう、自由だ。王太子とのことに縛られる必要はない。俺も“特務機関”として、彼らが逃げられないように最後まで監視する。おまえに危害が及ぶこともないだろう」
その言葉に、私は素直に微笑む。頬に涙が伝いそうになるのを、なんとかこらえて。
「ありがとう、ジークフリート様。……あなたのおかげで、私はもう大丈夫です」
この瞬間、私の中から王太子への未練や恐れがきれいに消え去った気がした。
王太子とミーナは、国中に喧伝した“真実の愛”の正体を自ら暴かれ、信頼も尊厳も失った。
私にとっては、まさに静かなる“ざまぁ”だったのだろう。復讐のために手を染めることなく、ただ歩みを進めた先で、彼らが勝手に奈落へと落ちていく。
こうして、私の心は確かに軽くなっていく。過去の婚約破棄で負った傷が、すっと薄れていくのを感じる。
――私をいたわってくれる人がいる。私はもう、ひとりじゃない。
「疲れただろう? 今日のことは一度忘れて、今夜は休め。……明日からは、領地の視察を再開できるぞ」
ジークフリートが優しい声音で言う。私は微笑みながらうなずき、彼の胸へ少しだけ身を寄せる。
「はい……。あなたと一緒に、いろんなところを見て回りたいです」
その言葉に、彼の腕がほんのわずか強く私を抱き留める。
抑えきれない涙が、一筋だけこぼれ落ちた。今度はうれしい涙だ。
こうして、私を踏み台にした王太子とミーナは自滅した。
私とジークフリートの人生は、ここから本当の意味で始まろうとしている。
“白い結婚”のはずだったのに、仮面夫婦のつもりだったのに。いつの間にか、私たちはお互いを気遣い合い、守り合う関係になっていた。
(私の心が、確かに彼へと傾いている……)
そんな自覚が、私にあたたかな光を注いでくれる。
そして、王太子とミーナが正式に処罰されるかどうかは、まだ今後の裁定次第。
だが、少なくとも彼らが二度と私を苦しめることはないだろう。そう確信できるだけで、私は十分だった。
0
あなたにおすすめの小説

政略結婚した夫に殺される夢を見た翌日、裏庭に深い穴が掘られていました
伊織
恋愛
夫に殺される夢を見た。
冷え切った青い瞳で見下ろされ、血に染まった寝室で命を奪われる――あまりにも生々しい悪夢。
夢から覚めたセレナは、政略結婚した騎士団長の夫・ルシアンとの冷えた関係を改めて実感する。
彼は宝石ばかり買う妻を快く思っておらず、セレナもまた、愛のない結婚に期待などしていなかった。
だがその日、夢の中で自分が埋められていたはずの屋敷の裏庭で、
「深い穴を掘るために用意されたようなスコップ」を目にしてしまう。
これは、ただの悪夢なのか。
それとも――現実に起こる未来の予兆なのか。
闇魔法を受け継ぐ公爵令嬢と、彼女を疎む騎士団長。
不穏な夢から始まる、夫婦の物語。
男女の恋愛小説に挑戦しています。
楽しんでいただけたら嬉しいです。

私を簡単に捨てられるとでも?―君が望んでも、離さない―
喜雨と悲雨
恋愛
私の名前はミラン。街でしがない薬師をしている。
そして恋人は、王宮騎士団長のルイスだった。
二年前、彼は魔物討伐に向けて遠征に出発。
最初は手紙も返ってきていたのに、
いつからか音信不通に。
あんなにうっとうしいほど構ってきた男が――
なぜ突然、私を無視するの?
不安を抱えながらも待ち続けた私の前に、
突然ルイスが帰還した。
ボロボロの身体。
そして隣には――見知らぬ女。
勝ち誇ったように彼の隣に立つその女を見て、
私の中で何かが壊れた。
混乱、絶望、そして……再起。
すがりつく女は、みっともないだけ。
私は、潔く身を引くと決めた――つもりだったのに。
「私を簡単に捨てられるとでも?
――君が望んでも、離さない」
呪いを自ら解き放ち、
彼は再び、執着の目で私を見つめてきた。
すれ違い、誤解、呪い、執着、
そして狂おしいほどの愛――
二人の恋のゆくえは、誰にもわからない。
過去に書いた作品を修正しました。再投稿です。

「お前みたいな卑しい闇属性の魔女など側室でもごめんだ」と言われましたが、私も殿下に嫁ぐ気はありません!
野生のイエネコ
恋愛
闇の精霊の加護を受けている私は、闇属性を差別する国で迫害されていた。いつか私を受け入れてくれる人を探そうと夢に見ていたデビュタントの舞踏会で、闇属性を差別する王太子に罵倒されて心が折れてしまう。
私が国を出奔すると、闇精霊の森という場所に住まう、不思議な男性と出会った。なぜかその男性が私の事情を聞くと、国に与えられた闇精霊の加護が消滅して、国は大混乱に。
そんな中、闇精霊の森での生活は穏やかに進んでいく。
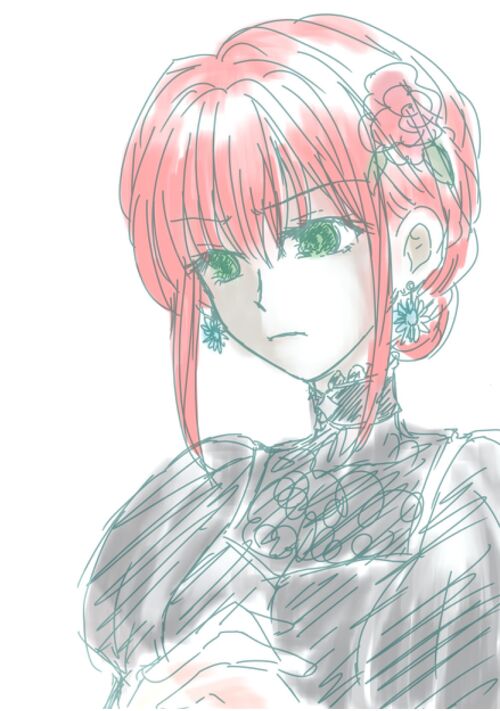
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

婚約破棄して泥を投げつけた元婚約者が「無能」と笑う中、光り輝く幼なじみの王子に掠め取られました。
ムラサメ
恋愛
「お前のような無能、我が家には不要だ。今すぐ消えろ!」
婚約者・エドワードのために身を粉にして尽くしてきたフィオナは、卒業パーティーの夜、雨の中に放り出される。
泥にまみれ、絶望に沈む彼女の前に現れたのは、かつての幼なじみであり、今や国中から愛される「黄金の王子」シリルだった。
「やっと見つけた。……ねえ、フィオナ。あんなゴミに君を傷つけさせるなんて、僕の落ち度だね」
汚れを厭わずフィオナを抱き上げたシリルは、彼女を自分の屋敷へと連れ帰る。
「自分には価値がない」と思い込むフィオナを、シリルは異常なまでの執着と甘い言葉で、とろけるように溺愛し始めて――。
一方で、フィオナを捨てたエドワードは気づいていなかった。
自分の手柄だと思っていた仕事も、領地の繁栄も、すべてはフィオナの才能によるものだったということに。
ボロボロになっていく元婚約者。美しく着飾られ、シリルの腕の中で幸せに微笑むフィオナ。
「僕の星を捨てた報い、たっぷりと受けてもらうよ?」
圧倒的な光を放つ幼なじみによる、最高に華やかな逆転劇がいま始まる!

王子様への置き手紙
あおき華
恋愛
フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯
小説家になろうにも掲載しています。

聖女の座を追われた私は田舎で畑を耕すつもりが、辺境伯様に「君は畑担当ね」と強引に任命されました
さら
恋愛
王都で“聖女”として人々を癒やし続けてきたリーネ。だが「加護が弱まった」と政争の口実にされ、無慈悲に追放されてしまう。行き場を失った彼女が選んだのは、幼い頃からの夢――のんびり畑を耕す暮らしだった。
ところが辺境の村にたどり着いた途端、無骨で豪胆な領主・辺境伯に「君は畑担当だ」と強引に任命されてしまう。荒れ果てた土地、困窮する領民たち、そして王都から伸びる陰謀の影。追放されたはずの聖女は、鍬を握り、祈りを土に注ぐことで再び人々に希望を芽吹かせていく。
「畑担当の聖女さま」と呼ばれながら笑顔を取り戻していくリーネ。そして彼女を真っ直ぐに支える辺境伯との距離も、少しずつ近づいて……?
畑から始まるスローライフと、不器用な辺境伯との恋。追放された聖女が見つけた本当の居場所は、王都の玉座ではなく、土と緑と温かな人々に囲まれた辺境の畑だった――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















