4 / 4
第4章:契約から真実の愛へ
しおりを挟む
――王太子アレクシオンと、平民の少女ミーナの“真実の愛”が崩れ去り、彼らが自らの不正や傲慢によって失墜したあの日から、幾日かが過ぎた。
私はアルグレイン男爵家の屋敷で、夫であるジークフリート・アルグレインとともに、穏やかな朝を迎えている。
「おはようございます、クレスタ」
執務前に私の部屋を訪れたジークフリートは、相変わらず落ち着いた声で言う。
――けれど、以前のような冷淡さはもう感じない。
彼は私が眠っている間に領地の報告書を読み込んでいたようで、やや寝不足の顔をしているものの、その瞳にはどこか柔らかな光が宿っていた。
「おはようございます、ジークフリート様。今朝はだいぶ早いのですね。もうお仕事を?」
そう尋ねると、彼はわずかに苦笑しながらうなずく。
「領地から届いた書簡を確認していた。最近は王太子関連の混乱も落ち着き始めているし、そろそろ俺たちも本格的に次の手を打たなければならない」
「そう、ですね……。王太子殿下の“査問”は続いているようですが、いまのところもう私たちを陥れるような動きはないですし」
――あの日、王太子が主導した集会で、彼は自らの不正や矛盾を暴かれて自滅した。
当然、私への理不尽な疑惑など一蹴され、逆に「王太子こそが不正を働き、平民のミーナを利用した」とまで言われる始末。
ミーナも大衆の前で“清廉潔白の平民”などではなく、裏金の流れに関係した可能性が高いと疑われ、今や王宮の外れで保護──という名の監視を受けているらしい。
もう、あの二人が私たちの前に立ちはだかることはない。むしろ、王太子としての地位を剥奪される危険さえある。
私はかすかに首を振りつつ、心の中で呟く。
(……これで本当に終わったんだ。長かった婚約破棄の呪縛も、あの二人の無責任に振り回される日々も)
胸に広がるのは解放感と、そしてジークフリートへの感謝。
彼こそが私を守り、二度と傷つかないよう手を尽くしてくれた。
そんな彼の横顔を眺めていると、不意にジークフリートが口を開く。
「今日の午後、少し時間が取れそうだ。天気もいいし、以前話していた“丘の上の砦”を見に行かないか?」
「丘の上の砦……ですか? そういえば、領地の古い地図に載っていましたね」
もともと戦乱の時代に国境沿いを守るために築かれた砦が、今は半ば観光資源のように残されているのだと、彼から聞いたことがある。
「遠くまで見渡せる場所だ。うちの領地だけでなく、隣接する地域の様子もわかる。……少し景色を眺めながら、ゆっくり話をしよう」
「はい、ぜひご一緒したいです」
以前の私なら、“仮面夫婦”の距離感を保とうとして、こういう誘いを遠慮したかもしれない。
でも今は違う。私は彼といろいろな景色を見て、いろいろな話をしてみたい。
その思いを素直に口にできるようになったのは、きっとあの日の出来事──特務機関や彼の想いを打ち明けられた日が大きいのだろう。
ジークフリートはわずかに微笑んで「じゃあ昼過ぎに馬車を用意させる」と言い、書斎へ戻っていった。
◇◇◇
午後、準備を整えた馬車が屋敷の前に停まり、私とジークフリートは領の北側にある丘へ向かった。
護衛は最小限にし、使用人の侍女が一名同行するだけの控えめな行程だ。
馬車が軽やかに走り出し、少しずつ標高の高い道を進んでいく。道端には緑が生い茂り、小川や農地、遠くの集落がのどかな風景を織りなしていた。
「クレスタ、おまえは王都以外の土地をゆっくり見るのは初めてだろう」
「はい。婚約者だったころは、王太子殿下の行事に合わせてしか動けず、こうして自由に各地を回ることはできませんでしたから……。すごく新鮮ですわ」
窓から外を眺めながら答えると、ジークフリートは小さく頷く。
「これだけの広さがある国だ。王都での権力争いだけがすべてではない。人々の暮らしは、こうした自然の中でも日々営まれている。……おまえが一歩ずつ目を向けてくれれば、俺としても嬉しい」
その言葉に、私は心が温かくなるのを感じる。
やがて馬車は丘の麓で停まり、あとは馬を下男に預けて短い坂道を歩くことになった。
人が通る道は整備されており、両側には低い柵が設けられている。
木漏れ日の差し込む道を、私とジークフリートは肩を並べてゆっくり進んだ。
侍女は少し後ろを歩き、必要があれば助けてくれるよう待機している。
「結構、息があがりますね……普段はこんな坂道を歩くことがないから」
「焦らずにゆっくり行こう。砦の跡地まで登れば、素晴らしい景色が広がっているはずだ」
ジークフリートはそう言いながら、私の腕を支えてくれる。手のひらから伝わる体温が、妙に心強い。
王太子との婚約時代、“手を貸します”と形式的に差し伸べられた手とはまるで違う。ここには確かな優しさがあった。
程なくして、丘の上の広場のような場所に出る。そこに石造りの古い壁と塔が見え、かつての砦の名残を感じさせた。
さすがに戦乱の時代からは大きく改装されているようで、一部は展望台のようになっている。
ジークフリートと私はそこへ上がり、遠くを見晴らす。
「わあ……!」
思わず小さく声をあげた。どこまでも続く木立と畑、そこに点在する村々。その先には山並みが連なり、さらに遠くには川のきらめきが見えた。
「すごい……こんなに遠くまで見渡せるんですね」
「ここは国境近くの要衝だったからな。見晴らしが良いのは当然だ。……だが、今は平和な景色しかない。俺はそのことが、何よりも嬉しいよ」
ジークフリートが深く息をつく。風に揺れる髪が、彼の引き締まった横顔を彩っている。
私も同じように目を細めながら、この景色を胸に刻み込むように眺めた。
「そういえば、昔はここで兵士たちが国境を守っていたんですよね。今はもう使われていない……?」
「最小限の駐留はあるが、ほとんど観光施設のようにして開放している。毎年、子どもたちの遠足にも使われているらしい。歴史を学ぶにはいい場所だ」
そう説明してくれたジークフリートの声には、自分の領地に対する誇りのようなものが滲んでいた。
――ふと、私は思う。彼はどんな思いで、この領地を守ってきたのだろうか。特務機関として動きながら、冷血の仮面をかぶりながら……。
「ジークフリート様」
私が彼の名前を呼ぶと、彼は視線だけを私に向ける。
「あなたは、私との結婚を“政略結婚”と呼ばせたけれど、実際にはあなたの想いがあった……そう言っていましたよね」
「ああ」
短く答える彼に、私は一歩近づいて、続ける。
「本当は、いつ頃から私を……気にかけていたのですか? もし失礼でなければ、教えてもらえませんか」
ジークフリートは、一瞬戸惑うように目を伏せる。
しかし、やがて小さく息を吐き、穏やかな声で答えを紡いだ。
「正確に言えば、ずっと前からおまえの存在を知ってはいた。王太子の婚約者として周囲から注目されていたからな。だけど、本当に意識し始めたのは……おまえが社交界の裏で苦しんでいた頃かもしれない」
「私が苦しんでいた……?」
王太子妃になるべく、私は厳しい教育を受けながら、社交の場では嫉妬や冷たい視線にさらされていた。そういうことだろうか。
「ある晩、貴族たちの集まりの後で、君が一人で庭を歩いているのを見かけた。うつむいて、泣くのを必死にこらえているようだった」
「……そんなこと、ありましたね」
確かに記憶にある。王太子の周囲の取り巻き女性たちに嫌味を言われ、私のメイドを侮辱され……何も言い返せず、夜の庭を彷徨ったことがあった。
「その姿を見て、なぜか胸が痛んだ。特務の仕事で王都に来ていた俺は、本来なら関わらないほうがいいとわかっていたが……どうしても目を背けられなかった」
ジークフリートの瞳は遠くを見つめるように細められている。あの夜の光景を思い出しているのかもしれない。
「だけど、王太子の婚約者に手を差し伸べるなど、俺の立場では許されない。だからこそ、冷血の仮面を被りながら、ただ遠巻きに見守るしかなかった。……もし俺があのとき、自分の気持ちに正直になっていたら、少しはおまえを楽にできたのかもしれないが」
「……そんなこと、ありません。ジークフリート様が直接出てきたら、きっともっと混乱が広がっていたわ。だから、それでよかったんです。わたしも何とか耐えられたから」
そう答えると、彼は切なげに微笑む。
「耐えられた、か……。すまない、もっと早く救ってやりたかった」
私は首を振り、そっと彼の袖を握る。
「もう十分です。あのときのわたしはきっと、誰かから助けを差し伸べられても受け取れないほど意地を張っていました。それに、結果的にこうしてあなたに救われましたし」
その言葉に、ジークフリートは深いため息をつき、私の手を包み込むようにそっと触れた。
「ありがとう、クレスタ。俺は、おまえが強い女性で本当によかったと思っている。でなければ、今の王太子との騒動に心を折られていたかもしれない」
「いえ……強いなんて。あなたが支えてくれたから、わたしは折れずにいられたんです」
私たちは互いを見つめ合う。風が吹き抜け、木々がざわめく音だけが周囲に響いている。
やがて、ジークフリートは私の手をほんの少し引き寄せ、そっと囁いた。
「クレスタ。いつか……本当の意味で、夫婦になろう」
「……え」
驚きに息を飲む。形式的には私たちはすでに結婚している。だが、それは“白い結婚”という条件付きの政略結婚だった。
――身体の関係を持たず、互いに干渉し合わない契約で始まった仮面夫婦。
しかし今、私たちは紛れもなく心を通わせつつある。
ジークフリートの言葉は、その“契約”を解いて真実の愛を誓おう、という意味に違いない。
私が黙ったまま固まっていると、彼は少し戸惑いながら続ける。
「……無理に強要するつもりはない。おまえも、いろいろな傷を負ってきただろうから。だけど、俺はおまえを心から愛している。もしおまえがそれを受け入れてくれるなら、もう一度……本当の結婚式を挙げたいと思っているんだ」
胸が熱くなる。
(まさか、こんな形でプロポーズされるなんて……)
目頭が熱くなるのを感じ、私は必死に涙をこらえる。
王太子の婚約者だった頃、あの方から“愛”という言葉を聞いたことはなかった。常に義務、責務、そして周囲の目……そんなものばかりだった。
けれどジークフリートは違う。彼は私を見ていてくれた。私を傷つけないよう配慮しながら、遠巻きにでも支えてくれていた。
今こそ、その想いに答えたい。そして私もまた、自分の本当の気持ちを確かめたい。
「……わたしも、あなたのことを大切に思っています」
涙声になりそうな自分をごまかすように、私は答える。
「婚約破棄されて、ずっと心が冷えきっていました。誰も信じたくない、何も失いたくない……そんな気持ちでいっぱいで。でも、ジークフリート様と過ごすうちに、少しずつ溶けていきました」
遠くで鳥が鳴き、草のざわめきが耳に優しく響く。
「あなたの優しさに触れるたび、わたしは心が救われたんです。だから……もしよければ、こちらこそ、あなたと本物の夫婦になりたい。わたしもあなたを愛していると、そう言いたい」
それだけで、ジークフリートの表情が目に見えて和らいだ。
まるで厳しい冬の氷が一気に溶けていくように、彼の瞳には温かな光が広がっていく。
「……ありがとう。おまえがそう言ってくれたことが、俺にとってどれほど嬉しいか、言葉では言い尽くせない」
そして彼は、私をそっと抱き寄せた。
普段、感情をあまり表に出さない彼が、こんなにもはっきりと胸の中へ迎え入れてくれる。その事実が、私の心を満たしていく。
もう、私にとって“白い結婚”はただの過去の契約でしかない。
私はもう一度、彼の名前を小さく呼ぶ。
「ジークフリート様……」
胸が高鳴り、涙が一筋こぼれる。過去の傷はもう痛まない。
私たちは緑の丘の上で、静かに抱き合い、互いの体温を確かめあった。
◇◇◇
砦を後にして、屋敷に戻った私たちは、さっそく再度の結婚式について準備を始めることにした。
とはいえ、盛大な儀式を今すぐ執り行うというわけではない。むしろ、親しい人々だけを招いて、小規模でも心から祝福してもらえる式にしようという話になったのだ。
「大々的な結婚式は、実は苦手で……」
そう私が打ち明けると、ジークフリートは笑って答える。
「俺も派手な式は好まない。だからこそ、家族や信頼できる仲間たちだけを呼んで、ささやかに祝ってもらおう。今回は“真実の愛”に基づく結婚だからな」
この言葉に、私は思わず苦笑する。
“真実の愛”というフレーズは、あの王太子とミーナが散々使い倒して、結局は自滅したワードでもある。
けれど、私たちはそれを大仰に叫ぶ必要はない。静かに、確かな愛を築けばいいだけだ。
「わかりました。じゃあ、落ち着いた頃合いを見て、父や妹たちにも声をかけましょう。みんな、びっくりするでしょうね……もう結婚しているのに、今さらまた式を挙げるなんて」
「いいじゃないか。形だけの結婚式ではなく、俺たちが本当に望む式をやるんだ。誰に遠慮することもない」
ジークフリートがそう言って微笑む姿に、私は思わず胸が熱くなる。
ああ、私はようやく、本当の意味で“婚約”あるいは“結婚”を体験するのだ。
過去の王太子との結婚準備は、すべて王宮の儀式であり、私の意思が反映される余地はほとんどなかった。
だけど今度は違う。私とジークフリートが望む形で、私たち自身の幸せを形にできる。
そのことに、なんとも言えない幸福感が込み上げてくる。
◇◇◇
そんな中、王宮では王太子の“査問”がさらに進展していた。
宮廷内の人々から聞こえてくるのは、彼とミーナが不正蓄財を企てていた事実や、王族の地位を利用して裏で賄賂を受け取っていた疑惑など、黒い噂が次々と確証を伴って出てきたという話。
アレクシオン殿下はすでに王太子としての公務を一切取り上げられ、表向きは“休職”という形で事実上軟禁状態にあると聞く。
ミーナもまた、いまだ王宮の一室に押し込められ、自由に外出できないらしい。
私はそれを聞いても、もはや心を痛めることはなかった。
彼らが自ら蒔いた種だ。私が積極的に報復しなくても、世界はちゃんと“落とし前”をつける。
それでも、あの恋に狂った王太子とミーナが、少しでも自分たちの行いを反省してくれればいいと思う。私を踏み台にしたこと、国を混乱させたこと……その代償の重さを、きちんと理解してほしい。
けれど、私の気持ちはもう、過去に囚われていない。これから先、私は私の幸せを大切にする。それだけのことだ。
◇◇◇
新たな結婚式の話は、すぐにエルバンシュ侯爵家へと伝わった。
ある日、父であるエルバンシュ侯爵と妹が屋敷を訪ねてくる。久々に見る家族の顔に、私は少し緊張しながらも胸を弾ませた。
「クレスタ……本当に、よかったなあ」
父は入って早々、私の手を握りしめ、目頭を押さえている。昔は厳格な父だったが、あの王太子との婚約破棄騒動を経て、ずいぶん丸くなった気がする。
「お父様、ご迷惑をおかけしました。……でも、こうしてジークフリート様と改めて式を挙げることになりましたので」
そう言うと、父はこくこくとうなずくばかりだ。
「ジークフリート殿、改めてうちの娘をよろしく頼む。私のほうこそ、婚約破棄のときは不甲斐なくてすまなかった。……クレスタが幸せになってくれるなら、それでいい」
ジークフリートは父に向かって礼を述べる。
「こちらこそ、クレスタを迎えられて光栄です。自分の立場ゆえ、なかなか詳しい事情をお話しできなかったことはお詫びしますが、必ず彼女を幸せにします」
「兄嫁様……じゃなかった、姉上様、おめでとうございます!」
元気いっぱいに言ってきたのは妹のレティシアだ。彼女は私にそっくりのブラウンの髪と瞳を持ち、以前から私を慕ってくれていた。
「ありがとう、レティ。あなたこそ元気そうで安心したわ」
「はい! あの王太子殿下の騒動で、実は私もハラハラしていたけど……お姉さまがジークフリート様と幸せになったと聞いて、すごくうれしいんです!」
妹の輝くような笑顔に、私まで微笑みがこぼれる。
家族との再会は、私の胸に温かな感情を湧き上がらせた。
王太子に婚約破棄されたとき、家名の威厳を保つために必死だった父と衝突しそうになったこともあった。
でも、今はみんながほっとした表情で私を見守ってくれる。ジークフリートが傍にいることもあり、私の居場所が大きく変化したのを肌で感じた。
◇◇◇
それから数週間が過ぎ、私たちの“本当の結婚式”の準備が着々と進んでいく。
といっても、派手な招待状をばらまくわけではなく、親族や親しい友人、そしてジークフリートの特務仲間などが、こっそり声をかけ合って集まる程度。
場所はアルグレイン男爵家の広々とした庭を使うことにした。
秋の始まりの涼やかな空気の中、庭園には可憐な花々が咲き、澄んだ空が晴れやかに広がっている。きっと素敵な式になるだろう。
挙式当日、私は白く美しいドレスを身にまとって、屋敷の一室で静かに息を整えていた。
かつて王太子との婚約中に仕立ててもらったものとはまるで違う、軽やかで柔らかな素材。胸元には小さく花の飾りがあしらわれ、まるで私自身が再生するような印象を与えてくれる。
鏡に映る自分の姿は、以前の“王太子妃候補”のころのようにぎこちなくはなく、どこか自然体に見えた。
コンコン、とノックの音がして、侍女が顔を出す。
「奥様、旦那様が入口でお待ちです。みなさまもそろそろお揃いになられますよ」
「ありがとう。今行きます」
胸の奥が高鳴る。
(仮面夫婦でもなく、形式的でもない。本当の意味での結婚式……私は今から、それを迎えるんだ)
私はゆっくりと立ち上がり、ドアを開けて廊下へ出る。
ホールを抜けて庭へと続く回廊に差しかかったとき、私の視線の先にジークフリートの姿があった。
いつもと違う礼服に身を包んだ彼は、引き締まった体躯と浅黒い髪がより一層引き立って、堂々とした雰囲気を放っている。
だが、その瞳には私を見た瞬間、はっきりとわかる優しい輝きが宿っていた。
「……クレスタ」
彼の低く柔らかな声を聞くだけで、私は心が甘く溶けていくのを感じる。
「ジークフリート様……私、変ではありませんか?」
照れくさくて尋ねると、彼は微かな笑みを浮かべてかぶりを振る。
「とても美しい。……言葉では足りないほどだ」
その言葉に、私の頬はかっと熱くなる。まだ慣れない甘い台詞に、どう返事をしていいか迷う。
だけど、彼の瞳が真剣で、決してからかっているわけではないことは、はっきりと伝わってきた。
「……ありがとう、ございます」
ようやくそう答えると、彼は私の手を取って回廊を進み始める。
ドアの向こう、ガーデンには簡素だけれど飾り付けが施され、参列者の皆が待っている。
父や妹をはじめ、アルグレイン家の使用人や、ジークフリートの仕事仲間たち。それに、先日村でお世話になった農民の代表まで、こっそり招かれているのを見て、私は少し驚いた。
(こんなにたくさんの人が、私たちのために集まってくれたんだ……)
胸がいっぱいになる。以前、王太子との婚約で挙げようとしていた式は、はるかに多くの招待客がいたはずなのに、私の心は常に不安と義務感で押しつぶされそうだった。
でも、今日は違う。温かい祝福の空気が、私たちを包み込んでいる。
ジークフリートと手を繋ぎながら、私は祭壇へとゆっくり歩みを進める。
「皆さま、本日は私たちのためにお集まりいただきありがとうございます。……私はクレスタ・エルバンシュ、そして、これより真の夫婦として、ジークフリート・アルグレインと新たな誓いを交わします」
震える声でそう告げると、ゲストの中から温かな拍手が湧き上がった。
私の目には、うっすらと涙が浮かぶ。でも、決して悲しい涙じゃない。
ジークフリートが祭壇に立ち、私の前に向き直る。司祭役を務める老紳士が、静かに言葉を紡いだ。
「ジークフリート・アルグレイン、あなたはクレスタ・エルバンシュを、真実の妻として愛し、敬い、慈しみ、そして守ることを誓いますか?」
沈黙が降りた庭で、彼の声がはっきりと響く。
「誓います。……私のすべてを懸けて、彼女を幸せに導くことを」
その言葉のひとつひとつが、私の胸に深く刻み込まれる。
司祭が私のほうに視線を向ける。
「クレスタ・エルバンシュ、あなたはジークフリート・アルグレインを、真実の夫として愛し、助け合い、そして彼の歩む道をともに進むことを誓いますか?」
私は大きく息を吸い、涙を拭いながら答える。
「はい、誓います。彼を愛し、共に生きていくと」
そう口にした瞬間、自分の中の不安や迷いが消え去り、胸いっぱいに充足感が広がった。
王太子との結婚準備のころ、私は“誓います”という言葉をなかなか言えずにいた。それが義務でしかなかったから。しかし、今は心からそう言える。
司祭が「よろしい、では指輪を」と促すと、ジークフリートは私の左手を取り、小さな指輪をはめる。
銀色に光るリングには、先日選んだばかりの上品な細工が施されている。
私もまた、彼の左手薬指に指輪をはめた。
すると、ゲストたちから拍手が鳴り、使用人たちが歓声を上げる。
父や妹も涙ぐみながら、心から喜んでくれているのがわかる。
「……クレスタ」
ジークフリートが微かに笑んで、私を抱き寄せた。
拍手喝采の中、私は恥ずかしさと幸福感でいっぱいになる。
もうこれが、私たちの“真実の結婚”なのだ。過去の痛みとは無縁の、純粋な愛の証。
まわりで花びらが舞い散り、明るい陽光が差し込む中、私たちは静かに唇を重ねる。
その瞬間、ゲストたちの歓声と拍手がさらに高まった。
(私は今、人生で一番幸せな瞬間を迎えているのかもしれない……)
思わずそう感じ、頬を赤らめながらも、私はジークフリートの背に腕を回した。
甘くて、切なくて、だけど確かな温もりが、私の全身を包み込む。
――これこそが、私がずっと欲しかったもの。
◇◇◇
簡素だけれど温かい披露宴が、庭の一角で続く。
参列者それぞれが酒を酌み交わし、私たち夫婦を祝いの言葉で包んでくれる。
ジークフリートも普段よりは口数が多くなり、客人たちに「ありがとう」と何度も返している。
特に、特務機関の仲間たちと笑顔で言葉を交わす姿は、私がまだ知らない彼の一面かもしれない。
「ジークフリート様が笑っていらっしゃる……!」
侍女のモニカが驚いたように口を押さえるのを見て、私は思わず笑ってしまった。
やがて日が傾き、披露宴もお開きに近づく頃、父が私たち夫婦のもとへやってくる。
「ジークフリート殿、クレスタ……このたびは本当におめでとう。王太子とやらに振り回された日々も、これですべて報われたな」
「ええ、お父様のおかげでここまで来れました」
深く頭を下げると、父は少し恥ずかしそうに目をそらす。
「わしは何もしていない。おまえが立ち直ったのは、ジークフリート殿の力だ。……それに、おまえ自身の強さでもある。今度こそ、幸せになれよ」
妹のレティシアも、手を振りながら笑顔でエールを送る。
「あんなにきれいなお姉さまを見られて、私まで幸せです! ジークフリート様、どうかよろしくお願いしますね!」
ジークフリートは「もちろんだ」と返し、穏やかなまなざしを向ける。
ふと、私たちの背後で特務の仲間らしき男性が手招きしているのが見えた。どうやら、ジークフリートに何か伝えたいらしい。
「少し行ってくる。……クレスタ、後でまた迎えに来るから」
「わかりました。行ってらっしゃい」
彼が離れたあと、私は父や妹たちに軽く挨拶をして席を外す。
庭の隅には、簡易のテーブルが用意されており、私はそこに腰掛けて、一息ついた。
晴れやかな疲れと、心地よい余韻が全身を包む。
――どれだけの苦難をくぐり抜けたことだろう。
思えば、王太子から婚約破棄を言い渡されたあの日、私の未来は真っ暗に思えた。
でも今、この瞬間はこんなにも眩しい。人生とはわからないものだ。
小鳥のさえずりに耳を傾けながら、私は木漏れ日の中にたたずむ。
すると、視界の端にジークフリートの姿が映った。談笑を終えたのか、彼がこちらへ戻ってくる。
私の目と合うと、彼は軽く手を振りながら微笑んだ。
その笑顔が、私の胸をさらに満たしてくれる。
――もう、私は決して一人じゃない。どんな嵐が来ても、この人となら乗り越えられる。
そう思っただけで、目頭がまた熱くなる。
「クレスタ、疲れていないか。少し散歩でもしてくるか?」
テーブルまで来たジークフリートが私に問いかける。
私は短く首を振った後、彼の手を取る。
「散歩というか、もう少しあなたと静かにお話ししたい。みんなのお祝いも嬉しいけど、せっかくの結婚式ですもの……あなたとの時間がもう少しほしいわ」
その言葉に、彼は「そうだな」とうなずいて、私を軽く抱き寄せた。
「では、少しだけ抜け出すとしよう。……皆には、あとで戻ると伝えればいい」
私たちは人々の視線を逃れるように庭の奥へ歩く。そこは小さな噴水と並木があり、夕日の色に染まった木々が風にそよいでいた。
行き止まりのようなその先にはベンチがあり、私はそこに腰を下ろすと、ジークフリートも隣に座る。
「……まだ実感が湧きません。こうして穏やかな結婚式ができるなんて、夢のようです」
そう呟くと、彼は私の手を再び握りしめ、指先を絡める。
「俺も同じだ。おまえとこうして、誰にも邪魔されずに人生を歩める日が来るなんてな。……特務の仕事ばかりで、結婚など考えたこともなかった」
笑みを交わす私たちを、夕日のオレンジ色が優しく照らす。
ふと、私は問いを口にする。
「ねえ、これからはあなたの特務の仕事も、私が少しは理解できるようにお手伝いしてもいいのかしら? もちろん、機密を漏らさない範囲で、ですけど……」
ジークフリートは一瞬目を丸くして、それから頷いた。
「そうだな。おまえなら領地運営の知識もあるし、危険を伴わない範囲で助けてもらえると助かる。……ただし、無茶はさせられない。俺たちはこれから夫婦として生きていくんだから、何よりおまえを守ることを優先したい」
「もちろんです。わたしだって、あなたに負担ばかりかけるのは嫌ですもの。夫婦は助け合うものだと、私は信じてますから」
そう言って笑うと、ジークフリートは照れくさそうに視線を逸らす。
「……ありがとう。おまえは本当に頼もしいよ」
微かな沈黙。
風が髪をくすぐり、二人の間に穏やかな空気が流れる。
やがて、彼が少し躊躇うように口を開く。
「クレスタ……実は、もう一つだけわがままを言っていいだろうか」
「わがまま?」
ジークフリートは私をまっすぐに見つめ、その瞳に切なる思いを宿す。
「おまえに、本当の愛を示せるのは言葉だけじゃない。俺は……おまえと夫婦としての営みも、いつかちゃんと結ばれたいと思っている。だが、無理強いする気はない。おまえが望んでくれるのなら……」
(ああ、そういう意味での“白い結婚”の解消、か)
私は頬を染めながら、けれど迷いなく首を振る。
「大丈夫です。わたしも……あなたと、心も身体も本当の意味で結ばれたいと思っています。今日の式を終えて、そう強く思いましたから」
すると、ジークフリートの表情は安堵と喜びで和らいだ。
「そうか……。ありがとう、クレスタ。おまえが嫌がるなら、一生契約のままでもいいと覚悟していたが……正直、嬉しいよ」
私もまた、静かに彼の胸に身を寄せる。
「わたしのほうこそ……あなたを信じたい。何も恐れずに、すべてを委ねてみたいと思っています」
そう呟く私を、ジークフリートは優しく抱きしめる。彼の鼓動がゆっくりと伝わり、穏やかな幸福感が胸を満たす。
これこそ、私の探し求めていた“愛”の姿。
誰かに押しつけられた義務でもなく、虚飾に満ちた王族の美談でもない。私と彼、二人で紡ぐ誠実な愛。
私は目を閉じ、しばし彼の鼓動に耳を傾ける。
すると、遠くから歓声や笑い声が聞こえてきた。披露宴が盛り上がっているのだろう。
私たちは顔を見合わせ、小さく笑う。
「そろそろ戻りましょうか。皆さんが、私たちのいないところで何か企んでいるかもしれませんし」
「そうだな。今夜は俺たちの門出を祝う宴だ。最後まで楽しもう」
そう言って手を取り合い、私たちは夕日に染まる庭を歩き出す。
もう“白い結婚”という縛りはどこにもない。過去の傷を持ちながらも、それを包み込み、乗り越え、二人で未来へ踏み出そうとしている。
王太子アレクシオンとミーナの転落劇など、私たちとは別の場所で勝手に進んでいくだろう。彼らの姿を見て、私は思う。愛を利用すれば、必ず報いを受ける。偽りで飾った愛に、本当の幸せなど生まれない。
それに比べて、私たちは嘘のない愛を選んだ。その果てには、きっと多くの笑顔や喜びが待っているはずだ。
門へ戻る途中、ジークフリートはふと足を止め、私の手をそっと引き寄せる。
「クレスタ……改めて、愛している。どんな困難が来ても、必ずおまえを守る」
「わたしも……愛しています。あなたに出会えて、本当によかった」
短い言葉を交わすだけで、胸が甘くとろけそうになる。
私たちはもう一度だけ、そっと唇を重ね合い、互いの体温を感じながら微笑んだ。
遠くで歓声が起こる。きっと誰かが私たちを見つけて、からかっているのだろう。
けれど、そんな茶化しなんて気にならない。
私たちが選び取ったこの愛は、確かなものだから。嘘も隠し事もない。傷ついていた私たちがお互いを支え合う、その尊い絆は、もう誰にも壊せないのだから。
――こうして、私たちの契約結婚は終わりを告げ、真実の愛へと生まれ変わった。
あの不誠実な王太子とミーナには“ざまぁ”の結末が待っている一方、私たちはあくまで穏やかに、互いを思いやりながら未来を歩む。
これが、私の人生の再出発。もう苦しむことはない。
今ここにあるのは、何よりも甘く、優しく、そして尊い愛の形……それが私たちの“本当の結婚”だ。
私はアルグレイン男爵家の屋敷で、夫であるジークフリート・アルグレインとともに、穏やかな朝を迎えている。
「おはようございます、クレスタ」
執務前に私の部屋を訪れたジークフリートは、相変わらず落ち着いた声で言う。
――けれど、以前のような冷淡さはもう感じない。
彼は私が眠っている間に領地の報告書を読み込んでいたようで、やや寝不足の顔をしているものの、その瞳にはどこか柔らかな光が宿っていた。
「おはようございます、ジークフリート様。今朝はだいぶ早いのですね。もうお仕事を?」
そう尋ねると、彼はわずかに苦笑しながらうなずく。
「領地から届いた書簡を確認していた。最近は王太子関連の混乱も落ち着き始めているし、そろそろ俺たちも本格的に次の手を打たなければならない」
「そう、ですね……。王太子殿下の“査問”は続いているようですが、いまのところもう私たちを陥れるような動きはないですし」
――あの日、王太子が主導した集会で、彼は自らの不正や矛盾を暴かれて自滅した。
当然、私への理不尽な疑惑など一蹴され、逆に「王太子こそが不正を働き、平民のミーナを利用した」とまで言われる始末。
ミーナも大衆の前で“清廉潔白の平民”などではなく、裏金の流れに関係した可能性が高いと疑われ、今や王宮の外れで保護──という名の監視を受けているらしい。
もう、あの二人が私たちの前に立ちはだかることはない。むしろ、王太子としての地位を剥奪される危険さえある。
私はかすかに首を振りつつ、心の中で呟く。
(……これで本当に終わったんだ。長かった婚約破棄の呪縛も、あの二人の無責任に振り回される日々も)
胸に広がるのは解放感と、そしてジークフリートへの感謝。
彼こそが私を守り、二度と傷つかないよう手を尽くしてくれた。
そんな彼の横顔を眺めていると、不意にジークフリートが口を開く。
「今日の午後、少し時間が取れそうだ。天気もいいし、以前話していた“丘の上の砦”を見に行かないか?」
「丘の上の砦……ですか? そういえば、領地の古い地図に載っていましたね」
もともと戦乱の時代に国境沿いを守るために築かれた砦が、今は半ば観光資源のように残されているのだと、彼から聞いたことがある。
「遠くまで見渡せる場所だ。うちの領地だけでなく、隣接する地域の様子もわかる。……少し景色を眺めながら、ゆっくり話をしよう」
「はい、ぜひご一緒したいです」
以前の私なら、“仮面夫婦”の距離感を保とうとして、こういう誘いを遠慮したかもしれない。
でも今は違う。私は彼といろいろな景色を見て、いろいろな話をしてみたい。
その思いを素直に口にできるようになったのは、きっとあの日の出来事──特務機関や彼の想いを打ち明けられた日が大きいのだろう。
ジークフリートはわずかに微笑んで「じゃあ昼過ぎに馬車を用意させる」と言い、書斎へ戻っていった。
◇◇◇
午後、準備を整えた馬車が屋敷の前に停まり、私とジークフリートは領の北側にある丘へ向かった。
護衛は最小限にし、使用人の侍女が一名同行するだけの控えめな行程だ。
馬車が軽やかに走り出し、少しずつ標高の高い道を進んでいく。道端には緑が生い茂り、小川や農地、遠くの集落がのどかな風景を織りなしていた。
「クレスタ、おまえは王都以外の土地をゆっくり見るのは初めてだろう」
「はい。婚約者だったころは、王太子殿下の行事に合わせてしか動けず、こうして自由に各地を回ることはできませんでしたから……。すごく新鮮ですわ」
窓から外を眺めながら答えると、ジークフリートは小さく頷く。
「これだけの広さがある国だ。王都での権力争いだけがすべてではない。人々の暮らしは、こうした自然の中でも日々営まれている。……おまえが一歩ずつ目を向けてくれれば、俺としても嬉しい」
その言葉に、私は心が温かくなるのを感じる。
やがて馬車は丘の麓で停まり、あとは馬を下男に預けて短い坂道を歩くことになった。
人が通る道は整備されており、両側には低い柵が設けられている。
木漏れ日の差し込む道を、私とジークフリートは肩を並べてゆっくり進んだ。
侍女は少し後ろを歩き、必要があれば助けてくれるよう待機している。
「結構、息があがりますね……普段はこんな坂道を歩くことがないから」
「焦らずにゆっくり行こう。砦の跡地まで登れば、素晴らしい景色が広がっているはずだ」
ジークフリートはそう言いながら、私の腕を支えてくれる。手のひらから伝わる体温が、妙に心強い。
王太子との婚約時代、“手を貸します”と形式的に差し伸べられた手とはまるで違う。ここには確かな優しさがあった。
程なくして、丘の上の広場のような場所に出る。そこに石造りの古い壁と塔が見え、かつての砦の名残を感じさせた。
さすがに戦乱の時代からは大きく改装されているようで、一部は展望台のようになっている。
ジークフリートと私はそこへ上がり、遠くを見晴らす。
「わあ……!」
思わず小さく声をあげた。どこまでも続く木立と畑、そこに点在する村々。その先には山並みが連なり、さらに遠くには川のきらめきが見えた。
「すごい……こんなに遠くまで見渡せるんですね」
「ここは国境近くの要衝だったからな。見晴らしが良いのは当然だ。……だが、今は平和な景色しかない。俺はそのことが、何よりも嬉しいよ」
ジークフリートが深く息をつく。風に揺れる髪が、彼の引き締まった横顔を彩っている。
私も同じように目を細めながら、この景色を胸に刻み込むように眺めた。
「そういえば、昔はここで兵士たちが国境を守っていたんですよね。今はもう使われていない……?」
「最小限の駐留はあるが、ほとんど観光施設のようにして開放している。毎年、子どもたちの遠足にも使われているらしい。歴史を学ぶにはいい場所だ」
そう説明してくれたジークフリートの声には、自分の領地に対する誇りのようなものが滲んでいた。
――ふと、私は思う。彼はどんな思いで、この領地を守ってきたのだろうか。特務機関として動きながら、冷血の仮面をかぶりながら……。
「ジークフリート様」
私が彼の名前を呼ぶと、彼は視線だけを私に向ける。
「あなたは、私との結婚を“政略結婚”と呼ばせたけれど、実際にはあなたの想いがあった……そう言っていましたよね」
「ああ」
短く答える彼に、私は一歩近づいて、続ける。
「本当は、いつ頃から私を……気にかけていたのですか? もし失礼でなければ、教えてもらえませんか」
ジークフリートは、一瞬戸惑うように目を伏せる。
しかし、やがて小さく息を吐き、穏やかな声で答えを紡いだ。
「正確に言えば、ずっと前からおまえの存在を知ってはいた。王太子の婚約者として周囲から注目されていたからな。だけど、本当に意識し始めたのは……おまえが社交界の裏で苦しんでいた頃かもしれない」
「私が苦しんでいた……?」
王太子妃になるべく、私は厳しい教育を受けながら、社交の場では嫉妬や冷たい視線にさらされていた。そういうことだろうか。
「ある晩、貴族たちの集まりの後で、君が一人で庭を歩いているのを見かけた。うつむいて、泣くのを必死にこらえているようだった」
「……そんなこと、ありましたね」
確かに記憶にある。王太子の周囲の取り巻き女性たちに嫌味を言われ、私のメイドを侮辱され……何も言い返せず、夜の庭を彷徨ったことがあった。
「その姿を見て、なぜか胸が痛んだ。特務の仕事で王都に来ていた俺は、本来なら関わらないほうがいいとわかっていたが……どうしても目を背けられなかった」
ジークフリートの瞳は遠くを見つめるように細められている。あの夜の光景を思い出しているのかもしれない。
「だけど、王太子の婚約者に手を差し伸べるなど、俺の立場では許されない。だからこそ、冷血の仮面を被りながら、ただ遠巻きに見守るしかなかった。……もし俺があのとき、自分の気持ちに正直になっていたら、少しはおまえを楽にできたのかもしれないが」
「……そんなこと、ありません。ジークフリート様が直接出てきたら、きっともっと混乱が広がっていたわ。だから、それでよかったんです。わたしも何とか耐えられたから」
そう答えると、彼は切なげに微笑む。
「耐えられた、か……。すまない、もっと早く救ってやりたかった」
私は首を振り、そっと彼の袖を握る。
「もう十分です。あのときのわたしはきっと、誰かから助けを差し伸べられても受け取れないほど意地を張っていました。それに、結果的にこうしてあなたに救われましたし」
その言葉に、ジークフリートは深いため息をつき、私の手を包み込むようにそっと触れた。
「ありがとう、クレスタ。俺は、おまえが強い女性で本当によかったと思っている。でなければ、今の王太子との騒動に心を折られていたかもしれない」
「いえ……強いなんて。あなたが支えてくれたから、わたしは折れずにいられたんです」
私たちは互いを見つめ合う。風が吹き抜け、木々がざわめく音だけが周囲に響いている。
やがて、ジークフリートは私の手をほんの少し引き寄せ、そっと囁いた。
「クレスタ。いつか……本当の意味で、夫婦になろう」
「……え」
驚きに息を飲む。形式的には私たちはすでに結婚している。だが、それは“白い結婚”という条件付きの政略結婚だった。
――身体の関係を持たず、互いに干渉し合わない契約で始まった仮面夫婦。
しかし今、私たちは紛れもなく心を通わせつつある。
ジークフリートの言葉は、その“契約”を解いて真実の愛を誓おう、という意味に違いない。
私が黙ったまま固まっていると、彼は少し戸惑いながら続ける。
「……無理に強要するつもりはない。おまえも、いろいろな傷を負ってきただろうから。だけど、俺はおまえを心から愛している。もしおまえがそれを受け入れてくれるなら、もう一度……本当の結婚式を挙げたいと思っているんだ」
胸が熱くなる。
(まさか、こんな形でプロポーズされるなんて……)
目頭が熱くなるのを感じ、私は必死に涙をこらえる。
王太子の婚約者だった頃、あの方から“愛”という言葉を聞いたことはなかった。常に義務、責務、そして周囲の目……そんなものばかりだった。
けれどジークフリートは違う。彼は私を見ていてくれた。私を傷つけないよう配慮しながら、遠巻きにでも支えてくれていた。
今こそ、その想いに答えたい。そして私もまた、自分の本当の気持ちを確かめたい。
「……わたしも、あなたのことを大切に思っています」
涙声になりそうな自分をごまかすように、私は答える。
「婚約破棄されて、ずっと心が冷えきっていました。誰も信じたくない、何も失いたくない……そんな気持ちでいっぱいで。でも、ジークフリート様と過ごすうちに、少しずつ溶けていきました」
遠くで鳥が鳴き、草のざわめきが耳に優しく響く。
「あなたの優しさに触れるたび、わたしは心が救われたんです。だから……もしよければ、こちらこそ、あなたと本物の夫婦になりたい。わたしもあなたを愛していると、そう言いたい」
それだけで、ジークフリートの表情が目に見えて和らいだ。
まるで厳しい冬の氷が一気に溶けていくように、彼の瞳には温かな光が広がっていく。
「……ありがとう。おまえがそう言ってくれたことが、俺にとってどれほど嬉しいか、言葉では言い尽くせない」
そして彼は、私をそっと抱き寄せた。
普段、感情をあまり表に出さない彼が、こんなにもはっきりと胸の中へ迎え入れてくれる。その事実が、私の心を満たしていく。
もう、私にとって“白い結婚”はただの過去の契約でしかない。
私はもう一度、彼の名前を小さく呼ぶ。
「ジークフリート様……」
胸が高鳴り、涙が一筋こぼれる。過去の傷はもう痛まない。
私たちは緑の丘の上で、静かに抱き合い、互いの体温を確かめあった。
◇◇◇
砦を後にして、屋敷に戻った私たちは、さっそく再度の結婚式について準備を始めることにした。
とはいえ、盛大な儀式を今すぐ執り行うというわけではない。むしろ、親しい人々だけを招いて、小規模でも心から祝福してもらえる式にしようという話になったのだ。
「大々的な結婚式は、実は苦手で……」
そう私が打ち明けると、ジークフリートは笑って答える。
「俺も派手な式は好まない。だからこそ、家族や信頼できる仲間たちだけを呼んで、ささやかに祝ってもらおう。今回は“真実の愛”に基づく結婚だからな」
この言葉に、私は思わず苦笑する。
“真実の愛”というフレーズは、あの王太子とミーナが散々使い倒して、結局は自滅したワードでもある。
けれど、私たちはそれを大仰に叫ぶ必要はない。静かに、確かな愛を築けばいいだけだ。
「わかりました。じゃあ、落ち着いた頃合いを見て、父や妹たちにも声をかけましょう。みんな、びっくりするでしょうね……もう結婚しているのに、今さらまた式を挙げるなんて」
「いいじゃないか。形だけの結婚式ではなく、俺たちが本当に望む式をやるんだ。誰に遠慮することもない」
ジークフリートがそう言って微笑む姿に、私は思わず胸が熱くなる。
ああ、私はようやく、本当の意味で“婚約”あるいは“結婚”を体験するのだ。
過去の王太子との結婚準備は、すべて王宮の儀式であり、私の意思が反映される余地はほとんどなかった。
だけど今度は違う。私とジークフリートが望む形で、私たち自身の幸せを形にできる。
そのことに、なんとも言えない幸福感が込み上げてくる。
◇◇◇
そんな中、王宮では王太子の“査問”がさらに進展していた。
宮廷内の人々から聞こえてくるのは、彼とミーナが不正蓄財を企てていた事実や、王族の地位を利用して裏で賄賂を受け取っていた疑惑など、黒い噂が次々と確証を伴って出てきたという話。
アレクシオン殿下はすでに王太子としての公務を一切取り上げられ、表向きは“休職”という形で事実上軟禁状態にあると聞く。
ミーナもまた、いまだ王宮の一室に押し込められ、自由に外出できないらしい。
私はそれを聞いても、もはや心を痛めることはなかった。
彼らが自ら蒔いた種だ。私が積極的に報復しなくても、世界はちゃんと“落とし前”をつける。
それでも、あの恋に狂った王太子とミーナが、少しでも自分たちの行いを反省してくれればいいと思う。私を踏み台にしたこと、国を混乱させたこと……その代償の重さを、きちんと理解してほしい。
けれど、私の気持ちはもう、過去に囚われていない。これから先、私は私の幸せを大切にする。それだけのことだ。
◇◇◇
新たな結婚式の話は、すぐにエルバンシュ侯爵家へと伝わった。
ある日、父であるエルバンシュ侯爵と妹が屋敷を訪ねてくる。久々に見る家族の顔に、私は少し緊張しながらも胸を弾ませた。
「クレスタ……本当に、よかったなあ」
父は入って早々、私の手を握りしめ、目頭を押さえている。昔は厳格な父だったが、あの王太子との婚約破棄騒動を経て、ずいぶん丸くなった気がする。
「お父様、ご迷惑をおかけしました。……でも、こうしてジークフリート様と改めて式を挙げることになりましたので」
そう言うと、父はこくこくとうなずくばかりだ。
「ジークフリート殿、改めてうちの娘をよろしく頼む。私のほうこそ、婚約破棄のときは不甲斐なくてすまなかった。……クレスタが幸せになってくれるなら、それでいい」
ジークフリートは父に向かって礼を述べる。
「こちらこそ、クレスタを迎えられて光栄です。自分の立場ゆえ、なかなか詳しい事情をお話しできなかったことはお詫びしますが、必ず彼女を幸せにします」
「兄嫁様……じゃなかった、姉上様、おめでとうございます!」
元気いっぱいに言ってきたのは妹のレティシアだ。彼女は私にそっくりのブラウンの髪と瞳を持ち、以前から私を慕ってくれていた。
「ありがとう、レティ。あなたこそ元気そうで安心したわ」
「はい! あの王太子殿下の騒動で、実は私もハラハラしていたけど……お姉さまがジークフリート様と幸せになったと聞いて、すごくうれしいんです!」
妹の輝くような笑顔に、私まで微笑みがこぼれる。
家族との再会は、私の胸に温かな感情を湧き上がらせた。
王太子に婚約破棄されたとき、家名の威厳を保つために必死だった父と衝突しそうになったこともあった。
でも、今はみんながほっとした表情で私を見守ってくれる。ジークフリートが傍にいることもあり、私の居場所が大きく変化したのを肌で感じた。
◇◇◇
それから数週間が過ぎ、私たちの“本当の結婚式”の準備が着々と進んでいく。
といっても、派手な招待状をばらまくわけではなく、親族や親しい友人、そしてジークフリートの特務仲間などが、こっそり声をかけ合って集まる程度。
場所はアルグレイン男爵家の広々とした庭を使うことにした。
秋の始まりの涼やかな空気の中、庭園には可憐な花々が咲き、澄んだ空が晴れやかに広がっている。きっと素敵な式になるだろう。
挙式当日、私は白く美しいドレスを身にまとって、屋敷の一室で静かに息を整えていた。
かつて王太子との婚約中に仕立ててもらったものとはまるで違う、軽やかで柔らかな素材。胸元には小さく花の飾りがあしらわれ、まるで私自身が再生するような印象を与えてくれる。
鏡に映る自分の姿は、以前の“王太子妃候補”のころのようにぎこちなくはなく、どこか自然体に見えた。
コンコン、とノックの音がして、侍女が顔を出す。
「奥様、旦那様が入口でお待ちです。みなさまもそろそろお揃いになられますよ」
「ありがとう。今行きます」
胸の奥が高鳴る。
(仮面夫婦でもなく、形式的でもない。本当の意味での結婚式……私は今から、それを迎えるんだ)
私はゆっくりと立ち上がり、ドアを開けて廊下へ出る。
ホールを抜けて庭へと続く回廊に差しかかったとき、私の視線の先にジークフリートの姿があった。
いつもと違う礼服に身を包んだ彼は、引き締まった体躯と浅黒い髪がより一層引き立って、堂々とした雰囲気を放っている。
だが、その瞳には私を見た瞬間、はっきりとわかる優しい輝きが宿っていた。
「……クレスタ」
彼の低く柔らかな声を聞くだけで、私は心が甘く溶けていくのを感じる。
「ジークフリート様……私、変ではありませんか?」
照れくさくて尋ねると、彼は微かな笑みを浮かべてかぶりを振る。
「とても美しい。……言葉では足りないほどだ」
その言葉に、私の頬はかっと熱くなる。まだ慣れない甘い台詞に、どう返事をしていいか迷う。
だけど、彼の瞳が真剣で、決してからかっているわけではないことは、はっきりと伝わってきた。
「……ありがとう、ございます」
ようやくそう答えると、彼は私の手を取って回廊を進み始める。
ドアの向こう、ガーデンには簡素だけれど飾り付けが施され、参列者の皆が待っている。
父や妹をはじめ、アルグレイン家の使用人や、ジークフリートの仕事仲間たち。それに、先日村でお世話になった農民の代表まで、こっそり招かれているのを見て、私は少し驚いた。
(こんなにたくさんの人が、私たちのために集まってくれたんだ……)
胸がいっぱいになる。以前、王太子との婚約で挙げようとしていた式は、はるかに多くの招待客がいたはずなのに、私の心は常に不安と義務感で押しつぶされそうだった。
でも、今日は違う。温かい祝福の空気が、私たちを包み込んでいる。
ジークフリートと手を繋ぎながら、私は祭壇へとゆっくり歩みを進める。
「皆さま、本日は私たちのためにお集まりいただきありがとうございます。……私はクレスタ・エルバンシュ、そして、これより真の夫婦として、ジークフリート・アルグレインと新たな誓いを交わします」
震える声でそう告げると、ゲストの中から温かな拍手が湧き上がった。
私の目には、うっすらと涙が浮かぶ。でも、決して悲しい涙じゃない。
ジークフリートが祭壇に立ち、私の前に向き直る。司祭役を務める老紳士が、静かに言葉を紡いだ。
「ジークフリート・アルグレイン、あなたはクレスタ・エルバンシュを、真実の妻として愛し、敬い、慈しみ、そして守ることを誓いますか?」
沈黙が降りた庭で、彼の声がはっきりと響く。
「誓います。……私のすべてを懸けて、彼女を幸せに導くことを」
その言葉のひとつひとつが、私の胸に深く刻み込まれる。
司祭が私のほうに視線を向ける。
「クレスタ・エルバンシュ、あなたはジークフリート・アルグレインを、真実の夫として愛し、助け合い、そして彼の歩む道をともに進むことを誓いますか?」
私は大きく息を吸い、涙を拭いながら答える。
「はい、誓います。彼を愛し、共に生きていくと」
そう口にした瞬間、自分の中の不安や迷いが消え去り、胸いっぱいに充足感が広がった。
王太子との結婚準備のころ、私は“誓います”という言葉をなかなか言えずにいた。それが義務でしかなかったから。しかし、今は心からそう言える。
司祭が「よろしい、では指輪を」と促すと、ジークフリートは私の左手を取り、小さな指輪をはめる。
銀色に光るリングには、先日選んだばかりの上品な細工が施されている。
私もまた、彼の左手薬指に指輪をはめた。
すると、ゲストたちから拍手が鳴り、使用人たちが歓声を上げる。
父や妹も涙ぐみながら、心から喜んでくれているのがわかる。
「……クレスタ」
ジークフリートが微かに笑んで、私を抱き寄せた。
拍手喝采の中、私は恥ずかしさと幸福感でいっぱいになる。
もうこれが、私たちの“真実の結婚”なのだ。過去の痛みとは無縁の、純粋な愛の証。
まわりで花びらが舞い散り、明るい陽光が差し込む中、私たちは静かに唇を重ねる。
その瞬間、ゲストたちの歓声と拍手がさらに高まった。
(私は今、人生で一番幸せな瞬間を迎えているのかもしれない……)
思わずそう感じ、頬を赤らめながらも、私はジークフリートの背に腕を回した。
甘くて、切なくて、だけど確かな温もりが、私の全身を包み込む。
――これこそが、私がずっと欲しかったもの。
◇◇◇
簡素だけれど温かい披露宴が、庭の一角で続く。
参列者それぞれが酒を酌み交わし、私たち夫婦を祝いの言葉で包んでくれる。
ジークフリートも普段よりは口数が多くなり、客人たちに「ありがとう」と何度も返している。
特に、特務機関の仲間たちと笑顔で言葉を交わす姿は、私がまだ知らない彼の一面かもしれない。
「ジークフリート様が笑っていらっしゃる……!」
侍女のモニカが驚いたように口を押さえるのを見て、私は思わず笑ってしまった。
やがて日が傾き、披露宴もお開きに近づく頃、父が私たち夫婦のもとへやってくる。
「ジークフリート殿、クレスタ……このたびは本当におめでとう。王太子とやらに振り回された日々も、これですべて報われたな」
「ええ、お父様のおかげでここまで来れました」
深く頭を下げると、父は少し恥ずかしそうに目をそらす。
「わしは何もしていない。おまえが立ち直ったのは、ジークフリート殿の力だ。……それに、おまえ自身の強さでもある。今度こそ、幸せになれよ」
妹のレティシアも、手を振りながら笑顔でエールを送る。
「あんなにきれいなお姉さまを見られて、私まで幸せです! ジークフリート様、どうかよろしくお願いしますね!」
ジークフリートは「もちろんだ」と返し、穏やかなまなざしを向ける。
ふと、私たちの背後で特務の仲間らしき男性が手招きしているのが見えた。どうやら、ジークフリートに何か伝えたいらしい。
「少し行ってくる。……クレスタ、後でまた迎えに来るから」
「わかりました。行ってらっしゃい」
彼が離れたあと、私は父や妹たちに軽く挨拶をして席を外す。
庭の隅には、簡易のテーブルが用意されており、私はそこに腰掛けて、一息ついた。
晴れやかな疲れと、心地よい余韻が全身を包む。
――どれだけの苦難をくぐり抜けたことだろう。
思えば、王太子から婚約破棄を言い渡されたあの日、私の未来は真っ暗に思えた。
でも今、この瞬間はこんなにも眩しい。人生とはわからないものだ。
小鳥のさえずりに耳を傾けながら、私は木漏れ日の中にたたずむ。
すると、視界の端にジークフリートの姿が映った。談笑を終えたのか、彼がこちらへ戻ってくる。
私の目と合うと、彼は軽く手を振りながら微笑んだ。
その笑顔が、私の胸をさらに満たしてくれる。
――もう、私は決して一人じゃない。どんな嵐が来ても、この人となら乗り越えられる。
そう思っただけで、目頭がまた熱くなる。
「クレスタ、疲れていないか。少し散歩でもしてくるか?」
テーブルまで来たジークフリートが私に問いかける。
私は短く首を振った後、彼の手を取る。
「散歩というか、もう少しあなたと静かにお話ししたい。みんなのお祝いも嬉しいけど、せっかくの結婚式ですもの……あなたとの時間がもう少しほしいわ」
その言葉に、彼は「そうだな」とうなずいて、私を軽く抱き寄せた。
「では、少しだけ抜け出すとしよう。……皆には、あとで戻ると伝えればいい」
私たちは人々の視線を逃れるように庭の奥へ歩く。そこは小さな噴水と並木があり、夕日の色に染まった木々が風にそよいでいた。
行き止まりのようなその先にはベンチがあり、私はそこに腰を下ろすと、ジークフリートも隣に座る。
「……まだ実感が湧きません。こうして穏やかな結婚式ができるなんて、夢のようです」
そう呟くと、彼は私の手を再び握りしめ、指先を絡める。
「俺も同じだ。おまえとこうして、誰にも邪魔されずに人生を歩める日が来るなんてな。……特務の仕事ばかりで、結婚など考えたこともなかった」
笑みを交わす私たちを、夕日のオレンジ色が優しく照らす。
ふと、私は問いを口にする。
「ねえ、これからはあなたの特務の仕事も、私が少しは理解できるようにお手伝いしてもいいのかしら? もちろん、機密を漏らさない範囲で、ですけど……」
ジークフリートは一瞬目を丸くして、それから頷いた。
「そうだな。おまえなら領地運営の知識もあるし、危険を伴わない範囲で助けてもらえると助かる。……ただし、無茶はさせられない。俺たちはこれから夫婦として生きていくんだから、何よりおまえを守ることを優先したい」
「もちろんです。わたしだって、あなたに負担ばかりかけるのは嫌ですもの。夫婦は助け合うものだと、私は信じてますから」
そう言って笑うと、ジークフリートは照れくさそうに視線を逸らす。
「……ありがとう。おまえは本当に頼もしいよ」
微かな沈黙。
風が髪をくすぐり、二人の間に穏やかな空気が流れる。
やがて、彼が少し躊躇うように口を開く。
「クレスタ……実は、もう一つだけわがままを言っていいだろうか」
「わがまま?」
ジークフリートは私をまっすぐに見つめ、その瞳に切なる思いを宿す。
「おまえに、本当の愛を示せるのは言葉だけじゃない。俺は……おまえと夫婦としての営みも、いつかちゃんと結ばれたいと思っている。だが、無理強いする気はない。おまえが望んでくれるのなら……」
(ああ、そういう意味での“白い結婚”の解消、か)
私は頬を染めながら、けれど迷いなく首を振る。
「大丈夫です。わたしも……あなたと、心も身体も本当の意味で結ばれたいと思っています。今日の式を終えて、そう強く思いましたから」
すると、ジークフリートの表情は安堵と喜びで和らいだ。
「そうか……。ありがとう、クレスタ。おまえが嫌がるなら、一生契約のままでもいいと覚悟していたが……正直、嬉しいよ」
私もまた、静かに彼の胸に身を寄せる。
「わたしのほうこそ……あなたを信じたい。何も恐れずに、すべてを委ねてみたいと思っています」
そう呟く私を、ジークフリートは優しく抱きしめる。彼の鼓動がゆっくりと伝わり、穏やかな幸福感が胸を満たす。
これこそ、私の探し求めていた“愛”の姿。
誰かに押しつけられた義務でもなく、虚飾に満ちた王族の美談でもない。私と彼、二人で紡ぐ誠実な愛。
私は目を閉じ、しばし彼の鼓動に耳を傾ける。
すると、遠くから歓声や笑い声が聞こえてきた。披露宴が盛り上がっているのだろう。
私たちは顔を見合わせ、小さく笑う。
「そろそろ戻りましょうか。皆さんが、私たちのいないところで何か企んでいるかもしれませんし」
「そうだな。今夜は俺たちの門出を祝う宴だ。最後まで楽しもう」
そう言って手を取り合い、私たちは夕日に染まる庭を歩き出す。
もう“白い結婚”という縛りはどこにもない。過去の傷を持ちながらも、それを包み込み、乗り越え、二人で未来へ踏み出そうとしている。
王太子アレクシオンとミーナの転落劇など、私たちとは別の場所で勝手に進んでいくだろう。彼らの姿を見て、私は思う。愛を利用すれば、必ず報いを受ける。偽りで飾った愛に、本当の幸せなど生まれない。
それに比べて、私たちは嘘のない愛を選んだ。その果てには、きっと多くの笑顔や喜びが待っているはずだ。
門へ戻る途中、ジークフリートはふと足を止め、私の手をそっと引き寄せる。
「クレスタ……改めて、愛している。どんな困難が来ても、必ずおまえを守る」
「わたしも……愛しています。あなたに出会えて、本当によかった」
短い言葉を交わすだけで、胸が甘くとろけそうになる。
私たちはもう一度だけ、そっと唇を重ね合い、互いの体温を感じながら微笑んだ。
遠くで歓声が起こる。きっと誰かが私たちを見つけて、からかっているのだろう。
けれど、そんな茶化しなんて気にならない。
私たちが選び取ったこの愛は、確かなものだから。嘘も隠し事もない。傷ついていた私たちがお互いを支え合う、その尊い絆は、もう誰にも壊せないのだから。
――こうして、私たちの契約結婚は終わりを告げ、真実の愛へと生まれ変わった。
あの不誠実な王太子とミーナには“ざまぁ”の結末が待っている一方、私たちはあくまで穏やかに、互いを思いやりながら未来を歩む。
これが、私の人生の再出発。もう苦しむことはない。
今ここにあるのは、何よりも甘く、優しく、そして尊い愛の形……それが私たちの“本当の結婚”だ。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

政略結婚した夫に殺される夢を見た翌日、裏庭に深い穴が掘られていました
伊織
恋愛
夫に殺される夢を見た。
冷え切った青い瞳で見下ろされ、血に染まった寝室で命を奪われる――あまりにも生々しい悪夢。
夢から覚めたセレナは、政略結婚した騎士団長の夫・ルシアンとの冷えた関係を改めて実感する。
彼は宝石ばかり買う妻を快く思っておらず、セレナもまた、愛のない結婚に期待などしていなかった。
だがその日、夢の中で自分が埋められていたはずの屋敷の裏庭で、
「深い穴を掘るために用意されたようなスコップ」を目にしてしまう。
これは、ただの悪夢なのか。
それとも――現実に起こる未来の予兆なのか。
闇魔法を受け継ぐ公爵令嬢と、彼女を疎む騎士団長。
不穏な夢から始まる、夫婦の物語。
男女の恋愛小説に挑戦しています。
楽しんでいただけたら嬉しいです。

私を簡単に捨てられるとでも?―君が望んでも、離さない―
喜雨と悲雨
恋愛
私の名前はミラン。街でしがない薬師をしている。
そして恋人は、王宮騎士団長のルイスだった。
二年前、彼は魔物討伐に向けて遠征に出発。
最初は手紙も返ってきていたのに、
いつからか音信不通に。
あんなにうっとうしいほど構ってきた男が――
なぜ突然、私を無視するの?
不安を抱えながらも待ち続けた私の前に、
突然ルイスが帰還した。
ボロボロの身体。
そして隣には――見知らぬ女。
勝ち誇ったように彼の隣に立つその女を見て、
私の中で何かが壊れた。
混乱、絶望、そして……再起。
すがりつく女は、みっともないだけ。
私は、潔く身を引くと決めた――つもりだったのに。
「私を簡単に捨てられるとでも?
――君が望んでも、離さない」
呪いを自ら解き放ち、
彼は再び、執着の目で私を見つめてきた。
すれ違い、誤解、呪い、執着、
そして狂おしいほどの愛――
二人の恋のゆくえは、誰にもわからない。
過去に書いた作品を修正しました。再投稿です。

「お前みたいな卑しい闇属性の魔女など側室でもごめんだ」と言われましたが、私も殿下に嫁ぐ気はありません!
野生のイエネコ
恋愛
闇の精霊の加護を受けている私は、闇属性を差別する国で迫害されていた。いつか私を受け入れてくれる人を探そうと夢に見ていたデビュタントの舞踏会で、闇属性を差別する王太子に罵倒されて心が折れてしまう。
私が国を出奔すると、闇精霊の森という場所に住まう、不思議な男性と出会った。なぜかその男性が私の事情を聞くと、国に与えられた闇精霊の加護が消滅して、国は大混乱に。
そんな中、闇精霊の森での生活は穏やかに進んでいく。
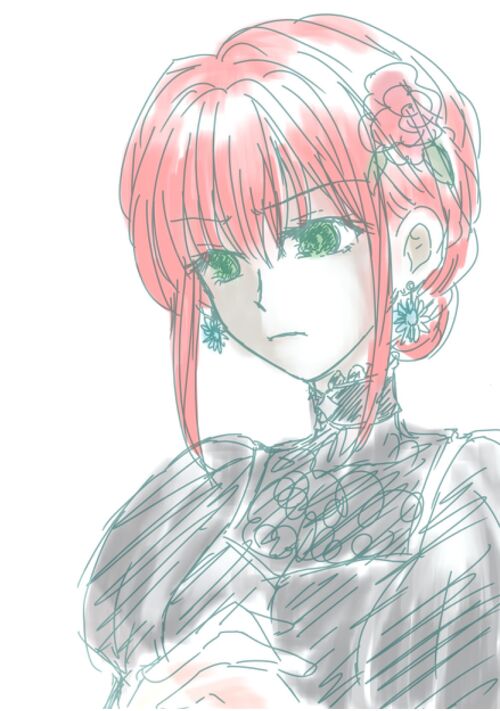
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

婚約破棄して泥を投げつけた元婚約者が「無能」と笑う中、光り輝く幼なじみの王子に掠め取られました。
ムラサメ
恋愛
「お前のような無能、我が家には不要だ。今すぐ消えろ!」
婚約者・エドワードのために身を粉にして尽くしてきたフィオナは、卒業パーティーの夜、雨の中に放り出される。
泥にまみれ、絶望に沈む彼女の前に現れたのは、かつての幼なじみであり、今や国中から愛される「黄金の王子」シリルだった。
「やっと見つけた。……ねえ、フィオナ。あんなゴミに君を傷つけさせるなんて、僕の落ち度だね」
汚れを厭わずフィオナを抱き上げたシリルは、彼女を自分の屋敷へと連れ帰る。
「自分には価値がない」と思い込むフィオナを、シリルは異常なまでの執着と甘い言葉で、とろけるように溺愛し始めて――。
一方で、フィオナを捨てたエドワードは気づいていなかった。
自分の手柄だと思っていた仕事も、領地の繁栄も、すべてはフィオナの才能によるものだったということに。
ボロボロになっていく元婚約者。美しく着飾られ、シリルの腕の中で幸せに微笑むフィオナ。
「僕の星を捨てた報い、たっぷりと受けてもらうよ?」
圧倒的な光を放つ幼なじみによる、最高に華やかな逆転劇がいま始まる!

王子様への置き手紙
あおき華
恋愛
フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯
小説家になろうにも掲載しています。

聖女の座を追われた私は田舎で畑を耕すつもりが、辺境伯様に「君は畑担当ね」と強引に任命されました
さら
恋愛
王都で“聖女”として人々を癒やし続けてきたリーネ。だが「加護が弱まった」と政争の口実にされ、無慈悲に追放されてしまう。行き場を失った彼女が選んだのは、幼い頃からの夢――のんびり畑を耕す暮らしだった。
ところが辺境の村にたどり着いた途端、無骨で豪胆な領主・辺境伯に「君は畑担当だ」と強引に任命されてしまう。荒れ果てた土地、困窮する領民たち、そして王都から伸びる陰謀の影。追放されたはずの聖女は、鍬を握り、祈りを土に注ぐことで再び人々に希望を芽吹かせていく。
「畑担当の聖女さま」と呼ばれながら笑顔を取り戻していくリーネ。そして彼女を真っ直ぐに支える辺境伯との距離も、少しずつ近づいて……?
畑から始まるスローライフと、不器用な辺境伯との恋。追放された聖女が見つけた本当の居場所は、王都の玉座ではなく、土と緑と温かな人々に囲まれた辺境の畑だった――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















