58 / 87
第1章 ◆ はじまりと出会いと
58. フォルトとリリー
しおりを挟む
「クリスちゃん、大丈夫かしら?」
ぽつりと呟いたのは、リリー。
それに『大丈夫だろ』と返事をすると、リリーは無意識で言ったのか、はっと口を押える仕草をした。
今、俺達はセントラルガーデンのベンチでのんびり寛いでいる。
リリーが持ってきたバスケットには、サンドイッチとフルーツが詰められている。
それを時折つまみながら、久しぶりのゆっくりとした時間を満喫していた。
ゆっくりまったりしすぎて、肝心のプレゼントは渡せないままでいるんだけどな…。
「フォルト、クリスちゃんのこと心配じゃないの?…あの人、ちょっと怖いわ」
俺のそっけない返事に不満を感じたのか、リリーは不機嫌な顔で言う。
『心配じゃないって言えば嘘になるな。でも、クリスがうれしそうにしてたんだから、何にも言えねーだろ』
俺達が一体何の話をしているのかというと、事の発端は時間を少し遡る。
「リィちゃん、今日はフォルトをよろしくね」
「ええ。クリスちゃんもお茶会楽しんでね」
俺とクリスは、このセントラルガーデンでリリーと待ち合わせをしていた。
クリスの迎えもここに来る、とレガロから伝言をもらったからだ。
俺達は迎えの時間よりも少し早く待ち合わせて、その迎えを待った。
他愛もない話をして待っていると、突然地面が光り出して紋章が現れた。
俺達はそれに驚いてクリスを庇った。
だが、クリスはその紋章術の何かに気がついたのか、目を輝かせた。
「クリス、迎えに来た」
「ライゼンさん!」
光が収まると、そこには黒髪の無表情の少年が立っていた。
いや、少年…なのか?
子どもにしては、あまりにも纏う空気がおかしい。いや、大人でもいねーよ、こんな奴。
クリスにライゼンと呼ばれた少年の姿をしたそいつは、全てを飲み込むような圧倒的な空気を持っていた。
これは、ゼロとは違う方向でヤバい奴だ。
俺の本能が頭の中でそう告げた。
隣で目を見開いているリリーも言葉を発せないでいる。
そんな俺達とは裏腹に、クリスはその少年にとても懐いているようだった。
「ライゼンさんがお迎えに来てくれたってことは…一緒にお茶会に参加してくれるんですか?」
「ああ。もちろんだ」
微笑みを含んだ返事に、クリスはとても喜んだ。勢い余って少年に抱きつくほど。
その光景に俺とリリーは言わずもがな驚いた。
ちょっと待て。クリス、そんな得体の知れない奴にホイホイ抱きつくな。
ゼロみたいな奴だったらどうするんだ!?
威嚇するように睨みつけていたら、急にそいつの纏う空気が変わった。
変わったと言うより、変えられたという方が正しいかもしれない。
クリスが抱き着いた途端、その空気が緩和されたんだ。
クリスが笑う度にその空気は花びらが舞うような温かいものに変わっていく。
そんな光景を目の当たりにした俺とリリーは、「どういうことだ?」とお互いに顔を見合わせた。
クリスに抱きつかれているそいつは、こっちに気がつくと小さく礼をした。
釣られて俺達も礼を返してしまった。ちくしょう。
「それじゃあ、リィちゃん、フォルト、行ってくるね!」
『あ、ああ…行って来い』
「いってらっしゃい、クリスちゃん」
あまりにもうれしそうにクリスが言うから、俺達はもう見送るしかなかった。
あの得体の知れない少年と抱き合いながら行ったのは、ムカつくけどな。
という顛末があっての、さっきの俺達の会話だ。
「それにしたって、あの人は何なの?ライゼンさんって、確かクリスちゃんに魔導具のことを教えてくれた人だったわよね?」
よく覚えてんな、リリー。
そんな話すっかり忘れてたぞ。
リリーの記憶力に感謝しつつ、小さく頷く。
『クリスがあんなに懐いてんだから、大丈夫だろ。リリーはあの空気が怖いんだろ?』
「……」
リリーは俺の言葉に一瞬強張ったように体を竦めた。
じっと見つめれば、リリーは観念したようにため息を吐く。
「…あの空気が怖いのは…そうね、否定しないわ」
『あれは、まあ…稀に見るヤバい空気だよな』
あいつが纏う空気は、そうだな…人間の言葉で言うなら支配者、王の気だ。
その気に呑まれれば、絶対服従させられるようなそんな絶対的な力だ。
精霊獣の俺でさえも一瞬怯んだくらいだからな。魔力量も相当ヤバいだろう。
俺が知りうる中では、精霊王に最も近い奴なんじゃないのか?
「…あの服従させられるような空気…嫌いよ」
『…リリー…』
リリーが不快な顔でそう呟いた。
それに肯定も否定もしない。ただ、リリーの横顔を見つめた。
リリーは…いや、フラワーエルフは、実はエルフの中では希少種だ。
その理由はフラワーエルフの起源が関係している。
フラワーエルフは、花から生まれる。それも、魔力を込めた花から。
魔力を込められた花は、何度も咲かせられ、枯れては魔力を込め直してまた咲くを繰り返しながら、途方もない年月をかけてその球根に魔力を少しずつ溜めていく。
けど、そうやって花が十分な魔力を持ったとしても、必ずエルフが生まれるとは限らない。
ここまで来たら、大体察しはつくだろう。
フラワーエルフは人に作られた存在だということだ。
愛玩用、時には戦闘用、従属用…その存在は、よく言えば身近な者、悪く言えば使い捨ての道具。
今はそんなことはないが、やはり非合法的な奴はいつの時代にだっている。
フラワーエルフは他のエルフとは違い、従属契約ができるから高く売れるのだ。
エルフとしての寿命、魔力もあり、しかも見た目が子どものままで大人の姿になることはない。
子どもの護衛としてなら、まだマシな待遇だ。
変な奴の趣向のためにとか、敵国のスパイとしての道具となると最悪だ。
そうしたこともあり、フラワーエルフ達はあまり進んで自分たちの素性を明かそうとしない。
「従属させられたことはないけど…あの空気は生理的に無理」
おそらく、フラワーエルフの本能なんだろうなと思う。
そうでなくても、理不尽に他人に従属させられるのは誰だって嫌だろ。
自分が「この人になら」って思うのと思わないのとでは、気持ちの持ちようが全く違うからな。
ちなみに、エヴァンから聞いたことだが、フラワーエルフは結婚すると、お互いの魔力を一つの球根に込めて我が子を育む。
不思議なことにフラワーエルフの番だと必ずエルフが生まれるそうだ。
もう、それは答えがわかりきってることじゃねーか。
フラワーエルフ達の境遇を思いながらため息を吐く。
そして、隣に座るリリーに近づいて鼻を寄せて囁く。
周りに聞こえないように、リリーにだけ聞こえるように。
『…リリー、嘘つくな。じゃあ何でクリスと従属契約を結んだんだ?』
「……っ!」
リリーが目を見開いて、俺を見る。
その顔は驚きもあったが、「どうして知ってるの?」という疑問も含んだものだった。
この様子だと、どうやらクリスに何も言わずに従属契約をしたみてーだな。
『俺を誰だと思ってんだ。魔力が変われば気付くぞ。クリスの魔力にリリーの魔力が加わってたからな』
「そう…フォルトにはわかるのね。……クリスちゃんには内緒にしてね?」
少し困り笑いでそう言ったリリーは、遠くを見るような目で空を見上げた。
今日は薄曇りで、太陽の日差しはいつもより弱い。
フラワーエルフの本能なのか、リリーはよく光の方へ目を向けることが多い。
それは、太陽だけに限らないけどな。
「言ったら、きっとクリスちゃんには断られると思うの。クリスちゃんは優しいから…」
『…そうだな』
絶対泣いて、リリーを抱きしめて、嫌だと首を振るかもな。
リリーもそんな姿を思い浮かべていたのか、少し沈んだ顔になっている。
でも、すぐにその表情は消えて、唐突に笑いだした。
「ふふ。フォルトとの契約、失敗してよかった」
そう言ったリリーの顔はとても穏やかで、眩しいものだった。
リリーとの契約に至った経緯は、まあ、簡単に言うと俺の正体がばれて、お互いの秘密を共有したから。
リリーは、見た目のふわふわな容姿とは裏腹に意外と活発な奴だ。
でも、組の中ではおとなしめのおっとりとした女の子というキャラだった。
俺と関わるようになってからは、素の自分が出せるようになって何でもズバズバ言い合える仲になった。
そんなリリーとの信頼関係がとても心地よかった。
今ならよくわかる、俺はずっとそれに甘えていた。俺とリリーなら大丈夫だと根拠のない自信が駄目だった。
契約は失敗だった。根本的なもののせいだった。
契約のためにリリーの精神世界に入ろうとすると、リリーが苦しんだ。
その精神が壊れる寸前までになった時、俺達の契約は不可能だと知った。
どんなに信頼関係があっても、そこには越えられない壁があった。
『…あの時は、苦しませて悪かったな』
「気にしないでよ。もう終わったことだし。それに、そのおかげで諦めとか踏ん切りがついたから、全然気にならないわ」
そう答えたリリーは、少し目を伏せた。
そして、間を置いて呟くように言った。
「…たぶん、フラワーエルフは従属させられるけど、それ以外の契約ができないんだわ」
理不尽に従属させられるのに、自分が優位の立場になることはない。
対等な契約もできない。
それは、元が作られた存在だからなのかもしれない。
リリーもいろんなものを諦めてるよな。
俺の心配してくれるのはいいけどよ、人のこと言えねーぞ。
「それでも、いいの。私はクリスちゃんに出会えたから。クリスちゃんがピンチの時は、従属契約のおかげですぐに駆けつけられるもの」
リリーの顔はとても晴れやかで、うれしそうで、こっちが泣きたくなった。
リリーは、どうにもならない自分の境遇を一番の武器にしたんだ。
大好きな親友のために、自分が一番嫌うことを差し出した。
親友を生涯護るために従属契約を結ぶ…それは自分のすべてを差し出すことと同じだ。
それは並大抵の覚悟じゃねえ。
『リリーが幸せなら、それでいい』
「ええ。とても幸せよ」
リリーのふわふわな髪が風に揺れてその頬を撫でた。
その横顔を見ながら、俺達はどこまで行っても平行線なんだなと思った。
この、想いさえも。
この親友がクリスと共にあるのなら、俺達は同じ思いを持つ者同士だ。
だから、リリーにとって一番頼りになる仲間になってやろう。
そう、心に決めた。
結局、プレゼントは渡すタイミングを完全に逃してしまった。
慣れないことはするもんじゃねーな…。
ぽつりと呟いたのは、リリー。
それに『大丈夫だろ』と返事をすると、リリーは無意識で言ったのか、はっと口を押える仕草をした。
今、俺達はセントラルガーデンのベンチでのんびり寛いでいる。
リリーが持ってきたバスケットには、サンドイッチとフルーツが詰められている。
それを時折つまみながら、久しぶりのゆっくりとした時間を満喫していた。
ゆっくりまったりしすぎて、肝心のプレゼントは渡せないままでいるんだけどな…。
「フォルト、クリスちゃんのこと心配じゃないの?…あの人、ちょっと怖いわ」
俺のそっけない返事に不満を感じたのか、リリーは不機嫌な顔で言う。
『心配じゃないって言えば嘘になるな。でも、クリスがうれしそうにしてたんだから、何にも言えねーだろ』
俺達が一体何の話をしているのかというと、事の発端は時間を少し遡る。
「リィちゃん、今日はフォルトをよろしくね」
「ええ。クリスちゃんもお茶会楽しんでね」
俺とクリスは、このセントラルガーデンでリリーと待ち合わせをしていた。
クリスの迎えもここに来る、とレガロから伝言をもらったからだ。
俺達は迎えの時間よりも少し早く待ち合わせて、その迎えを待った。
他愛もない話をして待っていると、突然地面が光り出して紋章が現れた。
俺達はそれに驚いてクリスを庇った。
だが、クリスはその紋章術の何かに気がついたのか、目を輝かせた。
「クリス、迎えに来た」
「ライゼンさん!」
光が収まると、そこには黒髪の無表情の少年が立っていた。
いや、少年…なのか?
子どもにしては、あまりにも纏う空気がおかしい。いや、大人でもいねーよ、こんな奴。
クリスにライゼンと呼ばれた少年の姿をしたそいつは、全てを飲み込むような圧倒的な空気を持っていた。
これは、ゼロとは違う方向でヤバい奴だ。
俺の本能が頭の中でそう告げた。
隣で目を見開いているリリーも言葉を発せないでいる。
そんな俺達とは裏腹に、クリスはその少年にとても懐いているようだった。
「ライゼンさんがお迎えに来てくれたってことは…一緒にお茶会に参加してくれるんですか?」
「ああ。もちろんだ」
微笑みを含んだ返事に、クリスはとても喜んだ。勢い余って少年に抱きつくほど。
その光景に俺とリリーは言わずもがな驚いた。
ちょっと待て。クリス、そんな得体の知れない奴にホイホイ抱きつくな。
ゼロみたいな奴だったらどうするんだ!?
威嚇するように睨みつけていたら、急にそいつの纏う空気が変わった。
変わったと言うより、変えられたという方が正しいかもしれない。
クリスが抱き着いた途端、その空気が緩和されたんだ。
クリスが笑う度にその空気は花びらが舞うような温かいものに変わっていく。
そんな光景を目の当たりにした俺とリリーは、「どういうことだ?」とお互いに顔を見合わせた。
クリスに抱きつかれているそいつは、こっちに気がつくと小さく礼をした。
釣られて俺達も礼を返してしまった。ちくしょう。
「それじゃあ、リィちゃん、フォルト、行ってくるね!」
『あ、ああ…行って来い』
「いってらっしゃい、クリスちゃん」
あまりにもうれしそうにクリスが言うから、俺達はもう見送るしかなかった。
あの得体の知れない少年と抱き合いながら行ったのは、ムカつくけどな。
という顛末があっての、さっきの俺達の会話だ。
「それにしたって、あの人は何なの?ライゼンさんって、確かクリスちゃんに魔導具のことを教えてくれた人だったわよね?」
よく覚えてんな、リリー。
そんな話すっかり忘れてたぞ。
リリーの記憶力に感謝しつつ、小さく頷く。
『クリスがあんなに懐いてんだから、大丈夫だろ。リリーはあの空気が怖いんだろ?』
「……」
リリーは俺の言葉に一瞬強張ったように体を竦めた。
じっと見つめれば、リリーは観念したようにため息を吐く。
「…あの空気が怖いのは…そうね、否定しないわ」
『あれは、まあ…稀に見るヤバい空気だよな』
あいつが纏う空気は、そうだな…人間の言葉で言うなら支配者、王の気だ。
その気に呑まれれば、絶対服従させられるようなそんな絶対的な力だ。
精霊獣の俺でさえも一瞬怯んだくらいだからな。魔力量も相当ヤバいだろう。
俺が知りうる中では、精霊王に最も近い奴なんじゃないのか?
「…あの服従させられるような空気…嫌いよ」
『…リリー…』
リリーが不快な顔でそう呟いた。
それに肯定も否定もしない。ただ、リリーの横顔を見つめた。
リリーは…いや、フラワーエルフは、実はエルフの中では希少種だ。
その理由はフラワーエルフの起源が関係している。
フラワーエルフは、花から生まれる。それも、魔力を込めた花から。
魔力を込められた花は、何度も咲かせられ、枯れては魔力を込め直してまた咲くを繰り返しながら、途方もない年月をかけてその球根に魔力を少しずつ溜めていく。
けど、そうやって花が十分な魔力を持ったとしても、必ずエルフが生まれるとは限らない。
ここまで来たら、大体察しはつくだろう。
フラワーエルフは人に作られた存在だということだ。
愛玩用、時には戦闘用、従属用…その存在は、よく言えば身近な者、悪く言えば使い捨ての道具。
今はそんなことはないが、やはり非合法的な奴はいつの時代にだっている。
フラワーエルフは他のエルフとは違い、従属契約ができるから高く売れるのだ。
エルフとしての寿命、魔力もあり、しかも見た目が子どものままで大人の姿になることはない。
子どもの護衛としてなら、まだマシな待遇だ。
変な奴の趣向のためにとか、敵国のスパイとしての道具となると最悪だ。
そうしたこともあり、フラワーエルフ達はあまり進んで自分たちの素性を明かそうとしない。
「従属させられたことはないけど…あの空気は生理的に無理」
おそらく、フラワーエルフの本能なんだろうなと思う。
そうでなくても、理不尽に他人に従属させられるのは誰だって嫌だろ。
自分が「この人になら」って思うのと思わないのとでは、気持ちの持ちようが全く違うからな。
ちなみに、エヴァンから聞いたことだが、フラワーエルフは結婚すると、お互いの魔力を一つの球根に込めて我が子を育む。
不思議なことにフラワーエルフの番だと必ずエルフが生まれるそうだ。
もう、それは答えがわかりきってることじゃねーか。
フラワーエルフ達の境遇を思いながらため息を吐く。
そして、隣に座るリリーに近づいて鼻を寄せて囁く。
周りに聞こえないように、リリーにだけ聞こえるように。
『…リリー、嘘つくな。じゃあ何でクリスと従属契約を結んだんだ?』
「……っ!」
リリーが目を見開いて、俺を見る。
その顔は驚きもあったが、「どうして知ってるの?」という疑問も含んだものだった。
この様子だと、どうやらクリスに何も言わずに従属契約をしたみてーだな。
『俺を誰だと思ってんだ。魔力が変われば気付くぞ。クリスの魔力にリリーの魔力が加わってたからな』
「そう…フォルトにはわかるのね。……クリスちゃんには内緒にしてね?」
少し困り笑いでそう言ったリリーは、遠くを見るような目で空を見上げた。
今日は薄曇りで、太陽の日差しはいつもより弱い。
フラワーエルフの本能なのか、リリーはよく光の方へ目を向けることが多い。
それは、太陽だけに限らないけどな。
「言ったら、きっとクリスちゃんには断られると思うの。クリスちゃんは優しいから…」
『…そうだな』
絶対泣いて、リリーを抱きしめて、嫌だと首を振るかもな。
リリーもそんな姿を思い浮かべていたのか、少し沈んだ顔になっている。
でも、すぐにその表情は消えて、唐突に笑いだした。
「ふふ。フォルトとの契約、失敗してよかった」
そう言ったリリーの顔はとても穏やかで、眩しいものだった。
リリーとの契約に至った経緯は、まあ、簡単に言うと俺の正体がばれて、お互いの秘密を共有したから。
リリーは、見た目のふわふわな容姿とは裏腹に意外と活発な奴だ。
でも、組の中ではおとなしめのおっとりとした女の子というキャラだった。
俺と関わるようになってからは、素の自分が出せるようになって何でもズバズバ言い合える仲になった。
そんなリリーとの信頼関係がとても心地よかった。
今ならよくわかる、俺はずっとそれに甘えていた。俺とリリーなら大丈夫だと根拠のない自信が駄目だった。
契約は失敗だった。根本的なもののせいだった。
契約のためにリリーの精神世界に入ろうとすると、リリーが苦しんだ。
その精神が壊れる寸前までになった時、俺達の契約は不可能だと知った。
どんなに信頼関係があっても、そこには越えられない壁があった。
『…あの時は、苦しませて悪かったな』
「気にしないでよ。もう終わったことだし。それに、そのおかげで諦めとか踏ん切りがついたから、全然気にならないわ」
そう答えたリリーは、少し目を伏せた。
そして、間を置いて呟くように言った。
「…たぶん、フラワーエルフは従属させられるけど、それ以外の契約ができないんだわ」
理不尽に従属させられるのに、自分が優位の立場になることはない。
対等な契約もできない。
それは、元が作られた存在だからなのかもしれない。
リリーもいろんなものを諦めてるよな。
俺の心配してくれるのはいいけどよ、人のこと言えねーぞ。
「それでも、いいの。私はクリスちゃんに出会えたから。クリスちゃんがピンチの時は、従属契約のおかげですぐに駆けつけられるもの」
リリーの顔はとても晴れやかで、うれしそうで、こっちが泣きたくなった。
リリーは、どうにもならない自分の境遇を一番の武器にしたんだ。
大好きな親友のために、自分が一番嫌うことを差し出した。
親友を生涯護るために従属契約を結ぶ…それは自分のすべてを差し出すことと同じだ。
それは並大抵の覚悟じゃねえ。
『リリーが幸せなら、それでいい』
「ええ。とても幸せよ」
リリーのふわふわな髪が風に揺れてその頬を撫でた。
その横顔を見ながら、俺達はどこまで行っても平行線なんだなと思った。
この、想いさえも。
この親友がクリスと共にあるのなら、俺達は同じ思いを持つ者同士だ。
だから、リリーにとって一番頼りになる仲間になってやろう。
そう、心に決めた。
結局、プレゼントは渡すタイミングを完全に逃してしまった。
慣れないことはするもんじゃねーな…。
0
あなたにおすすめの小説

あなたの片想いを聞いてしまった夜
柴田はつみ
恋愛
「『好きな人がいる』——その一言で、私の世界は音を失った。」
公爵令嬢リリアーヌの初恋は、隣家の若き公爵アレクシスだった。
政務や領地行事で顔を合わせるたび、言葉少なな彼の沈黙さえ、彼女には優しさに聞こえた。——毎日会える。それだけで十分幸せだと信じていた。
しかしある日、回廊の陰で聞いてしまう。
「好きな人がいる。……片想いなんだ」
名前は出ない。だから、リリアーヌの胸は残酷に結論を作る。自分ではないのだ、と。
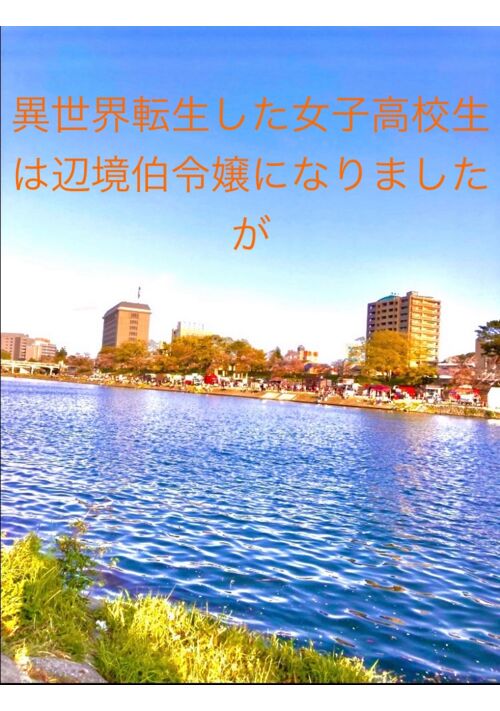
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

魔物に嫌われる「レベル0」の魔物使い。命懸けで仔犬を助けたら―実は神域クラスしかテイムできない規格外でした
たつき
ファンタジー
魔物使いでありながらスライム一匹従えられないカイルは、3年間尽くしたギルドを「無能」として追放される。 同世代のエリートたちに「魔物避けの道具」として危険な遺跡に連れ出され、最後は森の主(ヌシ)を前に囮として見捨てられた。
死を覚悟したカイルが崩落した壁の先で見つけたのは、今にも息絶えそうな一匹の白い仔犬。 「自分と同じように、理不尽に見捨てられたこの子だけは助けたい」 自分の命を顧みず、カイルが全魔力を込めて「テイム」を試みた瞬間、眠っていた真の才能が目覚める。

追放された味噌カス第7王子の異種族たちと,のんびり辺境地開発
ハーフのクロエ
ファンタジー
アテナ王国の末っ子の第7王子に産まれたルーファスは魔力が0で無能者と言われ、大陸の妖精族や亜人やモンスターの多い大陸から離れた無人島に追放される。だが前世は万能スキル持ちで魔王を倒し英雄と呼ばれていたのを隠し生まれ変わってスローライフを送る為に無能者を装っていたのだ。そんなルーファスはスローライフを送るつもりが、無人島には人間族以外の種族の独自に進化した先住民がおり、周りの人たちが勝手に動いて気が付けば豊かで平和な強国を起こしていく物語です。

「魔物の討伐で拾われた少年――アイト・グレイモント」
(イェイソン・マヌエル・ジーン)
ファンタジー
魔物の討伐中に見つかった黄金の瞳の少年、アイト・グレイモント。
王宮で育てられながらも、本当の冒険を求める彼は7歳で旅に出る。
風の魔法を操り、師匠と幼なじみの少女リリアと共に世界を巡る中、古代の遺跡で隠された力に触れ——。

ボクが追放されたら飢餓に陥るけど良いですか?
音爽(ネソウ)
ファンタジー
美味しい果実より食えない石ころが欲しいなんて、人間て変わってますね。
役に立たないから出ていけ?
わかりました、緑の加護はゴッソリ持っていきます!
さようなら!
5月4日、ファンタジー1位!HOTランキング1位獲得!!ありがとうございました!

三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。

大ッ嫌いな英雄様達に告ぐ
鮭とば
ファンタジー
剣があって、魔法があって、けれども機械はない世界。妖魔族、俗に言う魔族と人間族の、原因は最早誰にもわからない、終わらない小競り合いに、いつからあらわれたのかは皆わからないが、一旦の終止符をねじ込んだ聖女様と、それを守る5人の英雄様。
それが約50年前。
聖女様はそれから2回代替わりをし、数年前に3回目の代替わりをしたばかりで、英雄様は数え切れないぐらい替わってる。
英雄の座は常に5つで、基本的にどこから英雄を選ぶかは決まってる。
俺は、なんとしても、聖女様のすぐ隣に居たい。
でも…英雄は5人もいらないな。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















