60 / 87
第1章 ◆ はじまりと出会いと
60. 進級
しおりを挟む
「…クリスさんの思いはわかった。先生達は応援するよ」
リスト先生がため息を吐きながら、そう言いました。
それは、海組へ行くための適正に問題はないことを意味していました。
「クリスさん、きっといろんな人に反対されたでしょう?」
「う…っ、はい…」
ミリア先生が困り笑いで言いました。
その通り過ぎて、肯定するしかありません。
しかも魔導具研究科のクレスト様も困らせてます。さすがにそれは言えませんでしたが。
「私達は、いろいろ言ったけど…意地悪で言っているわけではないことをわかってほしいの」
「はい。わかってます」
先生達は私のことをとても心配してくれているということを。
先生達の顔や質問の内容から、それは痛いほど伝わります。
…クレスト様もライゼンさんもそうでした。
ミリア先生は私の手を握って、諭すように話を続けます。
「今の小さなあなたにはできないことも多いし、経験も足りない。でも、逆に言えば、これから手に入れることもできる。それでも私達がこうやって言うのは、道は一つだけではないということを知っていてほしいからよ。海組は、女の子にはつらいことの方が多いかもしれないわ」
海組に行くのは大半が男の子だと聞きます。
それは、騎士や魔術師、傭兵を目指す人が多いからです。
女の子も少人数いますが、卒業できる人は片手で数えるほどにまで減るそうです。
それでも海組が男女平等に受け入れるのは、公平な判断ができるから。それぞれに合った能力を伸ばすことに特化しているからです。
その点は、空組も花組も同じですが、海組は特にそれが強いのです。
「先生達の言葉もわかります。きっと、私みたいなのは、花組や空組に行った方がいいんだと思います。でも、そこだと自由に魔法も使えないし、自分の実力や限界を知ることもできない。海組に比べたら圧倒的に魔法経験が足りないと思います」
「…そこまでわかってるなんて…。クリスさん、本当に七歳なの?」
目を丸くするミリア先生に苦笑いで答えます。
「それを言われると、答えようがないです。これが私ですから」
そう、これが今の私。
私には、足りないものが多すぎる。
だから、今はこのままの私でいることにしたんだ。
そうぼんやりと思いながら無意識に浮かべた笑みは、私の本心だったのか、よくわかりませんでした。
その後は、いろいろと先生達に注意と心配事を言われて、海組に入るための書類一式をもらいました。
職員室を出て窓の外を見れば、いつの間にか空は真っ暗になっていて、星が輝いていました。
ずいぶんと長い時間お話ししていたみたいです。
一年生の下校時間、とっくに過ぎちゃってるけど、大丈夫かな…。
お父さん達、心配してるかもしれない。
「クリス、よかったですね。海組で勉強するのは大変だと思いますが、私や兄上がいますから、いつでも頼ってくださいね」
隣を歩くレガロお兄ちゃんが穏やかに笑いながら言いました。
「お兄ちゃんは、海組に行くことには反対じゃないんだね」
「ええ。海組は、兄上が行った組ですからね。魔法が苦手だった兄上が『無血の英雄』と呼ばれるようになったのは、海組での鍛錬と魔法経験があったからこそです。それを知っているので、クリスの魔力を見極めるには一番適しているところだと私は思っていますよ」
ええ!?クロードお兄ちゃん、魔法が苦手だったんだ!?
レガロお兄ちゃんが言うには、クロードお兄ちゃんは幼い頃、魔力量が多すぎてうまくコントロールできなかったのだそうです。
だけど、お兄ちゃんは海組で学んでいる間に自分に合った魔法を見つけて、それを伸ばしていったんだとか。
それがお兄ちゃんが「無血の英雄」「戦う聖職者」と呼ばれることになった、光魔法なのです。
今でもあまり魔法は得意ではないと言うのですが…そんなの信じられません。
攻撃に特化した魔法を使えるようになったのは、本当にすごいことです。
「…うん、ありがとう、お兄ちゃん!私、頑張るよ!」
レガロお兄ちゃんの力強い後押しに、笑顔で頷きました。
その数日後、必要書類を揃えて海組へ進級するための手続きを終えました。
海組に進級する日が決まった時、組のみんなはとても喜んでくれました。
魔法が苦手な私がどの組に進級するか、心配してくれていたようです。
みんなの優しさに、胸があったかくなりました。
クロードお兄ちゃんは最後まで納得していなさそうでしたが、それは私のこれからの頑張りでお兄ちゃんに証明していかなければならないと思いました。
小さな私がどこまでできるかはわからないけど、独りじゃない。それがわかっているから、大丈夫です。
クロードお兄ちゃんにも認めてもらえるように頑張る。
そして、魔導具研究科のクレスト様、ライゼンさんにちょっとでも近づけるように、魔導具の勉強も頑張ります!
海組に組替えする二日前の放課後、リスト先生から大事な用があると言われて、職員室へ行きました。
「組替えのことかな?」と思いながら職員室まで行くと、すでに扉の前でリスト先生が待っていました。
「突然呼び出してごめんな。エヴァン先生がクリスさんを呼んでる」
「エヴァン先生が?」
リスト先生はちょっとだけ困り笑いをして、頷きます。
そのままリスト先生に連れられてエヴァン先生がいるところへ行きました。
向かった先は、教育科の敷地にある森に囲まれた、古びた木造二階建ての建物でした。
扉には「深緑の館」と書かれてあって、その下に一回り小さい字で「野外学習専用校舎」とも書かれていました。
教育科の森の中にこんな建物があったなんて知りませんでした。
中に入ると、エヴァン先生が笑顔で迎えてくれました。
「いらっしゃい、クリスさん、リスト」
「エヴァン先生!」
久しぶりに会えた喜びで、思わずエヴァン先生に抱きついてしまいました。あの校外学習以来、手紙のやり取りだけでずっと会っていなかったからです。
エヴァン先生とリスト先生はびっくりした顔をしていましたが、そう経たないうちに笑い声が降ってきて、私も一緒になって笑いました。
「クリスさん、元気そうでよかったです。フォルト様もお元気ですか?」
「ありがとうございます。フォルトも元気です。今は学園のどこかでひなたぼっこしてると思います」
「それを聞いて安心しました」
エヴァン先生が穏やかに笑うので、釣られて私も微笑みます。
でも、どうしてこんなところに呼ばれたんだろう?
エヴァン先生に訊いてみると、ちょっとだけ沈んだ顔になります。
「フェルーテのことが気になっているかと思いまして、療養しているここに呼んだのですよ」
「そうだったんですね。フェルーテちゃん…まだ目を覚まさないですか?」
フェルーテちゃんのことは、お手紙のやり取りでちょっとだけ様子を教えてもらっていました。
怪我は治ったそうなのですが、あのきれいな羽は光を失ったままで、ずっと眠っているのだそうです。
「妖精は魔力回復に時間がかかると言われていますが、いくらなんでもかかりすぎです。おそらく、あの異形のゼロとの戦いで生命を維持するための魔力までも使い切ってしまったのでしょう」
「……そう、なんですね…」
命の危険にまでなっても、ゼロに抵抗し続けていたフェルーテちゃんの姿を思い出して、涙が出そうになりました。
それに気がついたのか、エヴァン先生は優しく私の頭を撫でてくれました。
ううっ。エヴァン先生のさり気ない優しさにも涙が出そうになりますっ。
「…何も持って来てないですけど…フェルーテちゃんのお見舞いをしてもいいですか?」
「ええ。もちろんです。フェルーテは眠っていますが、喜んでくれると思いますよ」
「はい…」
ここではっとして後ろにいる存在に振り向きます。
リスト先生は、何事もないような顔で私達の話を聴いていました。
あれっ!?もしかしてフェルーテちゃんのこと知ってるのかな!?
妖精が見えることはリスト先生に話していなかったので、びっくりされていると思ったのですが…。
私が戸惑っていることに気がついたのか、リスト先生がくすりと笑います。
「クリスさん、妖精が見えていることはエヴァンから聞いている。エヴァンの奥さんのことも知ってるから、気にしなくていいぞ。まあ、俺は見えてないけどな」
「あ、はい。そうだったんですね……っええ!!?」
なんだ。リスト先生、フェルーテちゃんのこと知ってたんだと思って頷いたら、衝撃の事実を言われたことに後から気がつきます。
ちょっと待って!!
奥さん!?今、エヴァン先生の奥さんって言った!?
えっ、あれ!?フェルーテちゃん、エヴァン先生の奥さんだったの!?
「リスト…クリスさんが驚きすぎて固まってしまったじゃないですか」
「え?エヴァン、クリスさんにフェルーテさんが自分の妻だって言ってなかったのか?」
「言ってませんよ。だから、今日言おうと思っていたところだったのに…」
「うわ。悪かったよ。クリスさんはフェルーテさんのお気に入りだと聞いてたから、てっきり知ってるかと思ってたんだよ」
衝撃が大きすぎて、頭の上で飛び交う先生達の会話は全く耳に入ってきませんでした。
私がいつまでも放心状態のままだったので、リスト先生に背中をぐいぐい押されて、エヴァン先生が私の手を引きました。
通された部屋は、あの調理実習室の奥にあった準備室のように、大きな樹が部屋の中心から生えていて、鱗粉が舞うように光がキラキラと降り注いでいました。
その下に、フェルーテちゃんが眠っているベッドがあります。
その光景を見て、飛んでいた意識を取り戻します。
そっとベッドまで近づいて見ると、フェルーテちゃんの胸が小さく上下していて、本当に眠っているだけでした。
傷だらけだった体も、すっかり治っていてほっとします。
でも、エヴァン先生が言っていたように、その羽は光を失って真っ黒のままでした。
「フェルーテちゃん…お見舞いに来たよ」
声を掛けますが、その瞼が開くことはありません。
エヴァン先生とリスト先生は、私の後ろに立ってその様子を見つめています。
「エヴァン先生、ちょっとだけフェルーテちゃんを撫でてもいいですか?」
「ええ、いいですよ。ですが羽には触らないでくださいね」
エヴァン先生の許可をもらって、そっとフェルーテちゃんの頭を撫でます。
フェルーテちゃんの髪は、まるで絹糸のようにサラサラで、とても触り心地がよかったです。
フォルトの毛並みとは違う柔らかさは、ずっと触っていたいほどです。
「フェルーテちゃん。早く元気になってね。―――――元気になあれ」
フェルーテちゃんの頭を撫でながら、祈るようにそう呟くと、羽がピクリと小さく動いたような気がしました。
それにびっくりしましたが、先生達が何も言わなかったので、私の気のせいだったようです。
そうして、しばらく撫でたら、先生達と静かに部屋を後にしました。
遠くで一年生の下校を知らせる鐘が鳴ります。
エヴァン先生がちょっとだけさみしそうな顔で私とリスト先生を見送ります。
「クリスさん、来てくれてありがとう。またいつでもここへ遊びに来てくださいね」
「こちらこそ、ありがとうございます。また会いに来ます」
笑顔で返せば、エヴァン先生はほっとしたような顔になって微笑んでくれました。
「こんなことしか言えませんが、海組に行っても頑張ってください」
「はい。頑張ります!」
エヴァン先生に別れを告げて、リスト先生と光組の教室へ帰ります。
その途中で、リスト先生が何か呟きました。
それを聞き取ることができなくて振り返れば、その目はどこか苦しげなものでした。
「リスト先生、どうしたんですか?」
「…いや、別になんでもない。クリスさん、海組での勉強、頑張るんだぞ?」
「? はい」
取り繕うように笑ったリスト先生を見て、首を傾げそうになりましたが、素直に頷くだけにしました。
二日後、期待と不安を胸に海組へと進級しました。
リスト先生がため息を吐きながら、そう言いました。
それは、海組へ行くための適正に問題はないことを意味していました。
「クリスさん、きっといろんな人に反対されたでしょう?」
「う…っ、はい…」
ミリア先生が困り笑いで言いました。
その通り過ぎて、肯定するしかありません。
しかも魔導具研究科のクレスト様も困らせてます。さすがにそれは言えませんでしたが。
「私達は、いろいろ言ったけど…意地悪で言っているわけではないことをわかってほしいの」
「はい。わかってます」
先生達は私のことをとても心配してくれているということを。
先生達の顔や質問の内容から、それは痛いほど伝わります。
…クレスト様もライゼンさんもそうでした。
ミリア先生は私の手を握って、諭すように話を続けます。
「今の小さなあなたにはできないことも多いし、経験も足りない。でも、逆に言えば、これから手に入れることもできる。それでも私達がこうやって言うのは、道は一つだけではないということを知っていてほしいからよ。海組は、女の子にはつらいことの方が多いかもしれないわ」
海組に行くのは大半が男の子だと聞きます。
それは、騎士や魔術師、傭兵を目指す人が多いからです。
女の子も少人数いますが、卒業できる人は片手で数えるほどにまで減るそうです。
それでも海組が男女平等に受け入れるのは、公平な判断ができるから。それぞれに合った能力を伸ばすことに特化しているからです。
その点は、空組も花組も同じですが、海組は特にそれが強いのです。
「先生達の言葉もわかります。きっと、私みたいなのは、花組や空組に行った方がいいんだと思います。でも、そこだと自由に魔法も使えないし、自分の実力や限界を知ることもできない。海組に比べたら圧倒的に魔法経験が足りないと思います」
「…そこまでわかってるなんて…。クリスさん、本当に七歳なの?」
目を丸くするミリア先生に苦笑いで答えます。
「それを言われると、答えようがないです。これが私ですから」
そう、これが今の私。
私には、足りないものが多すぎる。
だから、今はこのままの私でいることにしたんだ。
そうぼんやりと思いながら無意識に浮かべた笑みは、私の本心だったのか、よくわかりませんでした。
その後は、いろいろと先生達に注意と心配事を言われて、海組に入るための書類一式をもらいました。
職員室を出て窓の外を見れば、いつの間にか空は真っ暗になっていて、星が輝いていました。
ずいぶんと長い時間お話ししていたみたいです。
一年生の下校時間、とっくに過ぎちゃってるけど、大丈夫かな…。
お父さん達、心配してるかもしれない。
「クリス、よかったですね。海組で勉強するのは大変だと思いますが、私や兄上がいますから、いつでも頼ってくださいね」
隣を歩くレガロお兄ちゃんが穏やかに笑いながら言いました。
「お兄ちゃんは、海組に行くことには反対じゃないんだね」
「ええ。海組は、兄上が行った組ですからね。魔法が苦手だった兄上が『無血の英雄』と呼ばれるようになったのは、海組での鍛錬と魔法経験があったからこそです。それを知っているので、クリスの魔力を見極めるには一番適しているところだと私は思っていますよ」
ええ!?クロードお兄ちゃん、魔法が苦手だったんだ!?
レガロお兄ちゃんが言うには、クロードお兄ちゃんは幼い頃、魔力量が多すぎてうまくコントロールできなかったのだそうです。
だけど、お兄ちゃんは海組で学んでいる間に自分に合った魔法を見つけて、それを伸ばしていったんだとか。
それがお兄ちゃんが「無血の英雄」「戦う聖職者」と呼ばれることになった、光魔法なのです。
今でもあまり魔法は得意ではないと言うのですが…そんなの信じられません。
攻撃に特化した魔法を使えるようになったのは、本当にすごいことです。
「…うん、ありがとう、お兄ちゃん!私、頑張るよ!」
レガロお兄ちゃんの力強い後押しに、笑顔で頷きました。
その数日後、必要書類を揃えて海組へ進級するための手続きを終えました。
海組に進級する日が決まった時、組のみんなはとても喜んでくれました。
魔法が苦手な私がどの組に進級するか、心配してくれていたようです。
みんなの優しさに、胸があったかくなりました。
クロードお兄ちゃんは最後まで納得していなさそうでしたが、それは私のこれからの頑張りでお兄ちゃんに証明していかなければならないと思いました。
小さな私がどこまでできるかはわからないけど、独りじゃない。それがわかっているから、大丈夫です。
クロードお兄ちゃんにも認めてもらえるように頑張る。
そして、魔導具研究科のクレスト様、ライゼンさんにちょっとでも近づけるように、魔導具の勉強も頑張ります!
海組に組替えする二日前の放課後、リスト先生から大事な用があると言われて、職員室へ行きました。
「組替えのことかな?」と思いながら職員室まで行くと、すでに扉の前でリスト先生が待っていました。
「突然呼び出してごめんな。エヴァン先生がクリスさんを呼んでる」
「エヴァン先生が?」
リスト先生はちょっとだけ困り笑いをして、頷きます。
そのままリスト先生に連れられてエヴァン先生がいるところへ行きました。
向かった先は、教育科の敷地にある森に囲まれた、古びた木造二階建ての建物でした。
扉には「深緑の館」と書かれてあって、その下に一回り小さい字で「野外学習専用校舎」とも書かれていました。
教育科の森の中にこんな建物があったなんて知りませんでした。
中に入ると、エヴァン先生が笑顔で迎えてくれました。
「いらっしゃい、クリスさん、リスト」
「エヴァン先生!」
久しぶりに会えた喜びで、思わずエヴァン先生に抱きついてしまいました。あの校外学習以来、手紙のやり取りだけでずっと会っていなかったからです。
エヴァン先生とリスト先生はびっくりした顔をしていましたが、そう経たないうちに笑い声が降ってきて、私も一緒になって笑いました。
「クリスさん、元気そうでよかったです。フォルト様もお元気ですか?」
「ありがとうございます。フォルトも元気です。今は学園のどこかでひなたぼっこしてると思います」
「それを聞いて安心しました」
エヴァン先生が穏やかに笑うので、釣られて私も微笑みます。
でも、どうしてこんなところに呼ばれたんだろう?
エヴァン先生に訊いてみると、ちょっとだけ沈んだ顔になります。
「フェルーテのことが気になっているかと思いまして、療養しているここに呼んだのですよ」
「そうだったんですね。フェルーテちゃん…まだ目を覚まさないですか?」
フェルーテちゃんのことは、お手紙のやり取りでちょっとだけ様子を教えてもらっていました。
怪我は治ったそうなのですが、あのきれいな羽は光を失ったままで、ずっと眠っているのだそうです。
「妖精は魔力回復に時間がかかると言われていますが、いくらなんでもかかりすぎです。おそらく、あの異形のゼロとの戦いで生命を維持するための魔力までも使い切ってしまったのでしょう」
「……そう、なんですね…」
命の危険にまでなっても、ゼロに抵抗し続けていたフェルーテちゃんの姿を思い出して、涙が出そうになりました。
それに気がついたのか、エヴァン先生は優しく私の頭を撫でてくれました。
ううっ。エヴァン先生のさり気ない優しさにも涙が出そうになりますっ。
「…何も持って来てないですけど…フェルーテちゃんのお見舞いをしてもいいですか?」
「ええ。もちろんです。フェルーテは眠っていますが、喜んでくれると思いますよ」
「はい…」
ここではっとして後ろにいる存在に振り向きます。
リスト先生は、何事もないような顔で私達の話を聴いていました。
あれっ!?もしかしてフェルーテちゃんのこと知ってるのかな!?
妖精が見えることはリスト先生に話していなかったので、びっくりされていると思ったのですが…。
私が戸惑っていることに気がついたのか、リスト先生がくすりと笑います。
「クリスさん、妖精が見えていることはエヴァンから聞いている。エヴァンの奥さんのことも知ってるから、気にしなくていいぞ。まあ、俺は見えてないけどな」
「あ、はい。そうだったんですね……っええ!!?」
なんだ。リスト先生、フェルーテちゃんのこと知ってたんだと思って頷いたら、衝撃の事実を言われたことに後から気がつきます。
ちょっと待って!!
奥さん!?今、エヴァン先生の奥さんって言った!?
えっ、あれ!?フェルーテちゃん、エヴァン先生の奥さんだったの!?
「リスト…クリスさんが驚きすぎて固まってしまったじゃないですか」
「え?エヴァン、クリスさんにフェルーテさんが自分の妻だって言ってなかったのか?」
「言ってませんよ。だから、今日言おうと思っていたところだったのに…」
「うわ。悪かったよ。クリスさんはフェルーテさんのお気に入りだと聞いてたから、てっきり知ってるかと思ってたんだよ」
衝撃が大きすぎて、頭の上で飛び交う先生達の会話は全く耳に入ってきませんでした。
私がいつまでも放心状態のままだったので、リスト先生に背中をぐいぐい押されて、エヴァン先生が私の手を引きました。
通された部屋は、あの調理実習室の奥にあった準備室のように、大きな樹が部屋の中心から生えていて、鱗粉が舞うように光がキラキラと降り注いでいました。
その下に、フェルーテちゃんが眠っているベッドがあります。
その光景を見て、飛んでいた意識を取り戻します。
そっとベッドまで近づいて見ると、フェルーテちゃんの胸が小さく上下していて、本当に眠っているだけでした。
傷だらけだった体も、すっかり治っていてほっとします。
でも、エヴァン先生が言っていたように、その羽は光を失って真っ黒のままでした。
「フェルーテちゃん…お見舞いに来たよ」
声を掛けますが、その瞼が開くことはありません。
エヴァン先生とリスト先生は、私の後ろに立ってその様子を見つめています。
「エヴァン先生、ちょっとだけフェルーテちゃんを撫でてもいいですか?」
「ええ、いいですよ。ですが羽には触らないでくださいね」
エヴァン先生の許可をもらって、そっとフェルーテちゃんの頭を撫でます。
フェルーテちゃんの髪は、まるで絹糸のようにサラサラで、とても触り心地がよかったです。
フォルトの毛並みとは違う柔らかさは、ずっと触っていたいほどです。
「フェルーテちゃん。早く元気になってね。―――――元気になあれ」
フェルーテちゃんの頭を撫でながら、祈るようにそう呟くと、羽がピクリと小さく動いたような気がしました。
それにびっくりしましたが、先生達が何も言わなかったので、私の気のせいだったようです。
そうして、しばらく撫でたら、先生達と静かに部屋を後にしました。
遠くで一年生の下校を知らせる鐘が鳴ります。
エヴァン先生がちょっとだけさみしそうな顔で私とリスト先生を見送ります。
「クリスさん、来てくれてありがとう。またいつでもここへ遊びに来てくださいね」
「こちらこそ、ありがとうございます。また会いに来ます」
笑顔で返せば、エヴァン先生はほっとしたような顔になって微笑んでくれました。
「こんなことしか言えませんが、海組に行っても頑張ってください」
「はい。頑張ります!」
エヴァン先生に別れを告げて、リスト先生と光組の教室へ帰ります。
その途中で、リスト先生が何か呟きました。
それを聞き取ることができなくて振り返れば、その目はどこか苦しげなものでした。
「リスト先生、どうしたんですか?」
「…いや、別になんでもない。クリスさん、海組での勉強、頑張るんだぞ?」
「? はい」
取り繕うように笑ったリスト先生を見て、首を傾げそうになりましたが、素直に頷くだけにしました。
二日後、期待と不安を胸に海組へと進級しました。
0
あなたにおすすめの小説

あなたの片想いを聞いてしまった夜
柴田はつみ
恋愛
「『好きな人がいる』——その一言で、私の世界は音を失った。」
公爵令嬢リリアーヌの初恋は、隣家の若き公爵アレクシスだった。
政務や領地行事で顔を合わせるたび、言葉少なな彼の沈黙さえ、彼女には優しさに聞こえた。——毎日会える。それだけで十分幸せだと信じていた。
しかしある日、回廊の陰で聞いてしまう。
「好きな人がいる。……片想いなんだ」
名前は出ない。だから、リリアーヌの胸は残酷に結論を作る。自分ではないのだ、と。
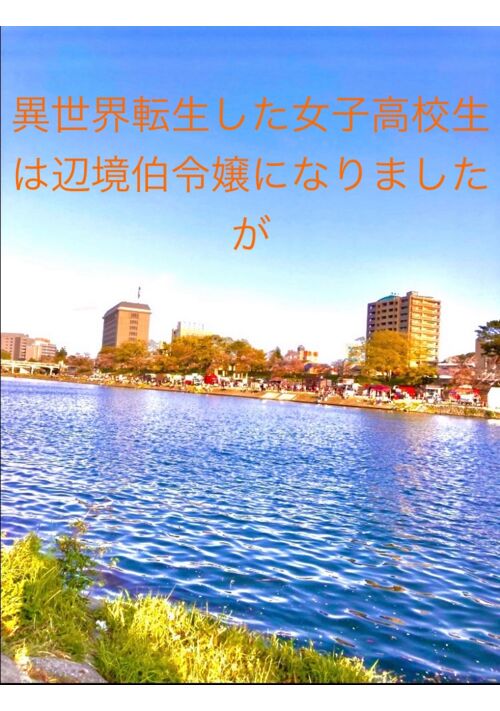
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

魔物に嫌われる「レベル0」の魔物使い。命懸けで仔犬を助けたら―実は神域クラスしかテイムできない規格外でした
たつき
ファンタジー
魔物使いでありながらスライム一匹従えられないカイルは、3年間尽くしたギルドを「無能」として追放される。 同世代のエリートたちに「魔物避けの道具」として危険な遺跡に連れ出され、最後は森の主(ヌシ)を前に囮として見捨てられた。
死を覚悟したカイルが崩落した壁の先で見つけたのは、今にも息絶えそうな一匹の白い仔犬。 「自分と同じように、理不尽に見捨てられたこの子だけは助けたい」 自分の命を顧みず、カイルが全魔力を込めて「テイム」を試みた瞬間、眠っていた真の才能が目覚める。

追放された味噌カス第7王子の異種族たちと,のんびり辺境地開発
ハーフのクロエ
ファンタジー
アテナ王国の末っ子の第7王子に産まれたルーファスは魔力が0で無能者と言われ、大陸の妖精族や亜人やモンスターの多い大陸から離れた無人島に追放される。だが前世は万能スキル持ちで魔王を倒し英雄と呼ばれていたのを隠し生まれ変わってスローライフを送る為に無能者を装っていたのだ。そんなルーファスはスローライフを送るつもりが、無人島には人間族以外の種族の独自に進化した先住民がおり、周りの人たちが勝手に動いて気が付けば豊かで平和な強国を起こしていく物語です。

「魔物の討伐で拾われた少年――アイト・グレイモント」
(イェイソン・マヌエル・ジーン)
ファンタジー
魔物の討伐中に見つかった黄金の瞳の少年、アイト・グレイモント。
王宮で育てられながらも、本当の冒険を求める彼は7歳で旅に出る。
風の魔法を操り、師匠と幼なじみの少女リリアと共に世界を巡る中、古代の遺跡で隠された力に触れ——。

ボクが追放されたら飢餓に陥るけど良いですか?
音爽(ネソウ)
ファンタジー
美味しい果実より食えない石ころが欲しいなんて、人間て変わってますね。
役に立たないから出ていけ?
わかりました、緑の加護はゴッソリ持っていきます!
さようなら!
5月4日、ファンタジー1位!HOTランキング1位獲得!!ありがとうございました!

三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。

大ッ嫌いな英雄様達に告ぐ
鮭とば
ファンタジー
剣があって、魔法があって、けれども機械はない世界。妖魔族、俗に言う魔族と人間族の、原因は最早誰にもわからない、終わらない小競り合いに、いつからあらわれたのかは皆わからないが、一旦の終止符をねじ込んだ聖女様と、それを守る5人の英雄様。
それが約50年前。
聖女様はそれから2回代替わりをし、数年前に3回目の代替わりをしたばかりで、英雄様は数え切れないぐらい替わってる。
英雄の座は常に5つで、基本的にどこから英雄を選ぶかは決まってる。
俺は、なんとしても、聖女様のすぐ隣に居たい。
でも…英雄は5人もいらないな。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















