10 / 25
2-4
しおりを挟む
ふくれる彼女を横目に、いつの間にか彼女の腕からするりと抜け出していた白猫の目前に、ルーカスはしゃがみ込んでいた。
「ようシリル、元気にしてたか」
すました顔で彼を見上げる真っ赤な瞳と目を合わせて、一体何をする気なのだろうか。
少女が見守っていれば、彼が胸元のポケットから一枚の写真を取り出した。真っ白な毛と首に巻かれたリボンを見るまでもなく、それは眼前の子猫を映したものだ。
手に持った写真を白猫の目の前にやる気なさげに掲げた彼は、それを顎でしゃくってみせた。
「一応聞くけど、これってお前だよな?」
その思わぬ行動に、彼女はふくれていたことも忘れて目を瞬かせた。
しゃがんだことによりほとんど同じ高さにあるその顔を、ジトッとした目で見て、ロッテは呟く。
「…ルカ、この子に聞いても分からぬのではないか」
「一応だよ、一応」
「何が一応なのだ」
「ほら、人違い…じゃなくて猫違いだったら意味ねえし」
「理解できていなければ意味がないではないか」
二人がそんな会話を交わしている間、白猫は目の前に突き出された写真をじっと眺めていた。
しばらくそうしていたかと思うと、白猫は不意に、みゃあ、と一声鳴いた。
─いかにも。
そう答えているようにも見えるその様は、どことなく誇らしげであった。
「な…!?」
「ん、なら良かった」
言った通りだろ?、と自慢げに振り返られるのもそれはそれで憎たらしいが、さも当然のことであるかのように平然としているのもそれはそれで何となく気に食わないものだ。
平然とした様子で写真をポケットに仕舞うルーカスを後目に、ロッテは白猫の目の前にへたり込むように座った。
「そ、そなた、人間の言葉が分かるのか!?」
慌てたように放たれた少女の言葉は、理解しているのかいないのか。
白猫は、こてんと首を傾げるばかりだった。
◇◇◇
「…お前ら、いつまでそうしてるつもりだ?そろそろ帰るぞ」
ルーカスは少女の目の前で首を傾げる白猫に手を差し伸べる。しかし、当のシリルは彼の手には見向きもしない。そして、ロッテの腕の中へと滑り込むように収まった。
小さな腕の中にぽすっと収まった猫は、彼女を見上げては、甘えるようにごろごろと声を上げる。
「お前、そこがいいのか」
不満そうなルーカスに尋ねられ、白猫はまた、みゃう、と声を上げる。
「…しゃあねえなあ」と頭を掻きながら、彼はその場で立ち上がった。
「悪いんだが、そいつ連れて来てくれるか」
「ああ!」
腕の中にシリルを抱えて、彼女はそっと立ち上がった。
いくら子猫とはいえ、腕の中の小さな生命は想像以上に温かく、ずっしり重たい。彼女の足取りは普段以上に遅くなっていた。
そんな彼女にさりげなく歩幅を合わせながら、ルーカスはこの白猫について話してくれた。
曰く、この白猫はシリルという名前のオス猫で、ルーカスの知り合いが営む喫茶店によく出入りしている猫なのだという。
元は飼い猫ではなかったらしいが、あまりにも頻繁に店に居着くようになったことから店主が世話をするようになり、今ではすっかり店の看板猫として可愛がられるようになった。
しかし近頃はめっきり顔を出さなくなり、店主もひどく心配していたそうだ。
「それでその店主がうちに捜索願出しやがったってわけ。こいつがいないなんざよくある事だし、心配しなくてもいいのになあ」
煙草の煙をふかしつつ、彼はそうぼやいた。
二度寝(彼女はやらせてもらったことはあまり無いからよく分からないが)を邪魔されたのなら、そう言いたくなるのも分からなくはない。でもそれがお前の仕事だろう、とも言いたくなる。
そんな彼女の内心はいざ知らず。
自分の斜め後ろをついてくる一人と一匹を眺めて、彼は口元に笑みを浮かべた。
「なんかお前ら似てると思ってたんだが。なるほどなあ、目が似てる」
「…!そなたもそう思うか!私もそう思ってたんだ!」
「色合いとか似てるよな」
思わぬ所で同意が得られて、彼女は先程までの不満も忘れ、目を輝かせる。
「では、この毛はルカ似だな!」
「…俺はこんな猫っ毛じゃねえよ」
彼女が次に発した言葉に、彼はすぐに顔を顰めた。
ロッテの言う通り、ルーカスの髪は癖っ毛である。ふわふわした手触りとは裏腹にひどく頑固なその髪は、本人曰く生まれつきらしい。
実際どう足掻いても直らないらしく、櫛を通そうが水で濡らそうが、しばらくすれば元に戻ってしまう。
当人は『とっくの昔に諦めた』とは言っているが、今でもそれなりに気にしてはいるらしく、この話題になるとこうして年甲斐もなく拗ねるのである。
「まあそう言うな。私は良いと思うぞ、その髪も」
「…そりゃどーも」
目の横に伸びる銀の髪を鬱陶しそうに弄る彼に、彼女はそう告げた。
どことなくひねくれているように見えて、頑固で意思は固い。
そんな彼の性質をそのまま映し出したようで、この上ないくらいに彼らしい髪だと、彼女は思うのだ。
「ようシリル、元気にしてたか」
すました顔で彼を見上げる真っ赤な瞳と目を合わせて、一体何をする気なのだろうか。
少女が見守っていれば、彼が胸元のポケットから一枚の写真を取り出した。真っ白な毛と首に巻かれたリボンを見るまでもなく、それは眼前の子猫を映したものだ。
手に持った写真を白猫の目の前にやる気なさげに掲げた彼は、それを顎でしゃくってみせた。
「一応聞くけど、これってお前だよな?」
その思わぬ行動に、彼女はふくれていたことも忘れて目を瞬かせた。
しゃがんだことによりほとんど同じ高さにあるその顔を、ジトッとした目で見て、ロッテは呟く。
「…ルカ、この子に聞いても分からぬのではないか」
「一応だよ、一応」
「何が一応なのだ」
「ほら、人違い…じゃなくて猫違いだったら意味ねえし」
「理解できていなければ意味がないではないか」
二人がそんな会話を交わしている間、白猫は目の前に突き出された写真をじっと眺めていた。
しばらくそうしていたかと思うと、白猫は不意に、みゃあ、と一声鳴いた。
─いかにも。
そう答えているようにも見えるその様は、どことなく誇らしげであった。
「な…!?」
「ん、なら良かった」
言った通りだろ?、と自慢げに振り返られるのもそれはそれで憎たらしいが、さも当然のことであるかのように平然としているのもそれはそれで何となく気に食わないものだ。
平然とした様子で写真をポケットに仕舞うルーカスを後目に、ロッテは白猫の目の前にへたり込むように座った。
「そ、そなた、人間の言葉が分かるのか!?」
慌てたように放たれた少女の言葉は、理解しているのかいないのか。
白猫は、こてんと首を傾げるばかりだった。
◇◇◇
「…お前ら、いつまでそうしてるつもりだ?そろそろ帰るぞ」
ルーカスは少女の目の前で首を傾げる白猫に手を差し伸べる。しかし、当のシリルは彼の手には見向きもしない。そして、ロッテの腕の中へと滑り込むように収まった。
小さな腕の中にぽすっと収まった猫は、彼女を見上げては、甘えるようにごろごろと声を上げる。
「お前、そこがいいのか」
不満そうなルーカスに尋ねられ、白猫はまた、みゃう、と声を上げる。
「…しゃあねえなあ」と頭を掻きながら、彼はその場で立ち上がった。
「悪いんだが、そいつ連れて来てくれるか」
「ああ!」
腕の中にシリルを抱えて、彼女はそっと立ち上がった。
いくら子猫とはいえ、腕の中の小さな生命は想像以上に温かく、ずっしり重たい。彼女の足取りは普段以上に遅くなっていた。
そんな彼女にさりげなく歩幅を合わせながら、ルーカスはこの白猫について話してくれた。
曰く、この白猫はシリルという名前のオス猫で、ルーカスの知り合いが営む喫茶店によく出入りしている猫なのだという。
元は飼い猫ではなかったらしいが、あまりにも頻繁に店に居着くようになったことから店主が世話をするようになり、今ではすっかり店の看板猫として可愛がられるようになった。
しかし近頃はめっきり顔を出さなくなり、店主もひどく心配していたそうだ。
「それでその店主がうちに捜索願出しやがったってわけ。こいつがいないなんざよくある事だし、心配しなくてもいいのになあ」
煙草の煙をふかしつつ、彼はそうぼやいた。
二度寝(彼女はやらせてもらったことはあまり無いからよく分からないが)を邪魔されたのなら、そう言いたくなるのも分からなくはない。でもそれがお前の仕事だろう、とも言いたくなる。
そんな彼女の内心はいざ知らず。
自分の斜め後ろをついてくる一人と一匹を眺めて、彼は口元に笑みを浮かべた。
「なんかお前ら似てると思ってたんだが。なるほどなあ、目が似てる」
「…!そなたもそう思うか!私もそう思ってたんだ!」
「色合いとか似てるよな」
思わぬ所で同意が得られて、彼女は先程までの不満も忘れ、目を輝かせる。
「では、この毛はルカ似だな!」
「…俺はこんな猫っ毛じゃねえよ」
彼女が次に発した言葉に、彼はすぐに顔を顰めた。
ロッテの言う通り、ルーカスの髪は癖っ毛である。ふわふわした手触りとは裏腹にひどく頑固なその髪は、本人曰く生まれつきらしい。
実際どう足掻いても直らないらしく、櫛を通そうが水で濡らそうが、しばらくすれば元に戻ってしまう。
当人は『とっくの昔に諦めた』とは言っているが、今でもそれなりに気にしてはいるらしく、この話題になるとこうして年甲斐もなく拗ねるのである。
「まあそう言うな。私は良いと思うぞ、その髪も」
「…そりゃどーも」
目の横に伸びる銀の髪を鬱陶しそうに弄る彼に、彼女はそう告げた。
どことなくひねくれているように見えて、頑固で意思は固い。
そんな彼の性質をそのまま映し出したようで、この上ないくらいに彼らしい髪だと、彼女は思うのだ。
0
あなたにおすすめの小説

勇者の様子がおかしい
しばたろう
ファンタジー
勇者は、少しおかしい。
そう思ったのは、王宮で出会ったその日からだった。
神に選ばれ、魔王討伐の旅に出た勇者マルク。
線の細い優男で、実力は確かだが、人と距離を取り、馴れ合いを嫌う奇妙な男。
だが、ある夜。
仲間のひとりは、決定的な違和感に気づいてしまう。
――勇者は、男ではなかった。
女であることを隠し、勇者として剣を振るうマルク。
そして、その秘密を知りながら「知らないふり」を選んだ仲間。
正体を隠す者と、真実を抱え込む者。
交わらぬはずの想いを抱えたまま、旅は続いていく。
これは、
「勇者であること」と
「自分であること」のあいだで揺れる物語。

追放された味噌カス第7王子の異種族たちと,のんびり辺境地開発
ハーフのクロエ
ファンタジー
アテナ王国の末っ子の第7王子に産まれたルーファスは魔力が0で無能者と言われ、大陸の妖精族や亜人やモンスターの多い大陸から離れた無人島に追放される。だが前世は万能スキル持ちで魔王を倒し英雄と呼ばれていたのを隠し生まれ変わってスローライフを送る為に無能者を装っていたのだ。そんなルーファスはスローライフを送るつもりが、無人島には人間族以外の種族の独自に進化した先住民がおり、周りの人たちが勝手に動いて気が付けば豊かで平和な強国を起こしていく物語です。
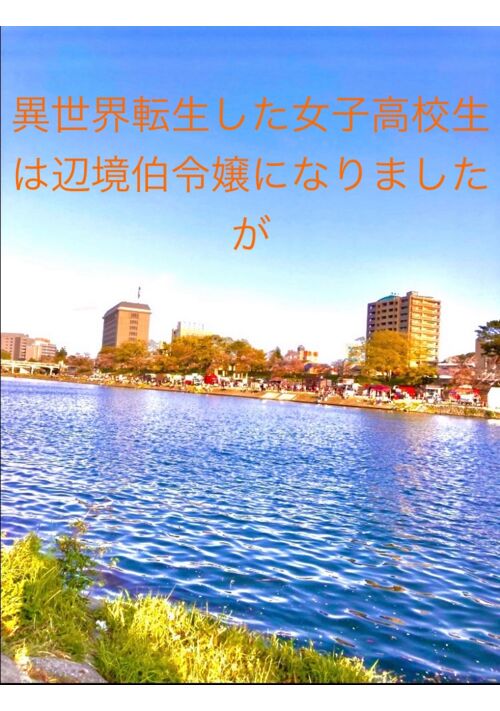
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

ゲーム未登場の性格最悪な悪役令嬢に転生したら推しの妻だったので、人生の恩人である推しには離婚して私以外と結婚してもらいます!
クナリ
ファンタジー
江藤樹里は、かつて画家になることを夢見ていた二十七歳の女性。
ある日気がつくと、彼女は大好きな乙女ゲームであるハイグランド・シンフォニーの世界へ転生していた。
しかし彼女が転生したのは、ヘビーユーザーであるはずの自分さえ知らない、ユーフィニアという女性。
ユーフィニアがどこの誰なのかが分からないまま戸惑う樹里の前に、ユーフィニアに仕えているメイドや、樹里がゲーム内で最も推しているキャラであり、どん底にいたときの自分の心を救ってくれたリルベオラスらが現れる。
そして樹里は、絶世の美貌を持ちながらもハイグラの世界では稀代の悪女とされているユーフィニアの実情を知っていく。
国政にまで影響をもたらすほどの悪名を持つユーフィニアを、最愛の恩人であるリルベオラスの妻でいさせるわけにはいかない。
樹里は、ゲーム未登場ながら圧倒的なアクの強さを持つユーフィニアをリルベオラスから引き離すべく、離婚を目指して動き始めた。

大ッ嫌いな英雄様達に告ぐ
鮭とば
ファンタジー
剣があって、魔法があって、けれども機械はない世界。妖魔族、俗に言う魔族と人間族の、原因は最早誰にもわからない、終わらない小競り合いに、いつからあらわれたのかは皆わからないが、一旦の終止符をねじ込んだ聖女様と、それを守る5人の英雄様。
それが約50年前。
聖女様はそれから2回代替わりをし、数年前に3回目の代替わりをしたばかりで、英雄様は数え切れないぐらい替わってる。
英雄の座は常に5つで、基本的にどこから英雄を選ぶかは決まってる。
俺は、なんとしても、聖女様のすぐ隣に居たい。
でも…英雄は5人もいらないな。


第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

通りすがりのエルフに求婚された貧乏男爵令嬢です〜初対面なのに激重感情を向けられています〜
東雲暁
恋愛
時はヴィトリア朝時代後期のイングランド。幻想が消え、文明と科学が世界を塗り替えようとしていた時代。
エヴェリーナ・エイヴェリーはコッツウォルズ地方の小さな領地で慎ましく暮らす、17歳の貧乏男爵令嬢。ある日父親が嘘の投資話に騙されて、払えないほどの借金を背負うはめに。
借金返済と引き換えに舞い込んできたのは、実業家との婚約。彼はただ高貴な血筋が欲しいだけ。
「本当は、お父様とお母様みたいに愛し合って結婚したいのに……」
その婚約式に乱入してきたのはエルフを名乗る貴公子、アルサリオン。
「この婚約は無効です。なぜなら彼女は私のものですから。私……?通りすがりのエルフです」
......いや、ロンドンのど真ん中にエルフって通り過ぎるものですか!?っていうか貴方誰!?
エルフの常識はイングランドの非常識!私は普通に穏やかに領地で暮らしたいだけなのに。
貴方のことなんか、絶対に好きにならないわ!
ティーカップの底に沈む、愛と執着と少しの狂気。甘いお菓子と一緒に飲み干して。
これは、貧乏男爵令嬢と通りすがりのエルフの、互いの人生を掛けた365日の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















