5 / 6
5.いい加減、気づいてくれる?
しおりを挟む
ぐっすりと眠って、気分壮快で目覚めると、蔵田課長はいなかった。
そっと寝室を出ると、リビングのソファーで寝てた。
「……起きたんだ」
「えっ、あっ、はい!」
突然、蔵田課長の目が開いて、慌ててしまった。
手近においてあった眼鏡をかけると、まるで猫でも撫でるみたいに私のあたまを撫でてくる。
「よく眠れた?」
「……はい。
その、ベッド、」
「なに?
一緒に寝た方がよかった?」
くすり、いつも通りの意地悪な笑顔になる。
昨日のあれは、きっと私の見間違いに違いない。
「朝ご飯作るから、ちょっと待ってて」
あたまをぽんぽんすると、蔵田課長はソファーを立ってキッチンに向かった。
待っててと云われても。
なにをしていいのかわからない。
ふと、携帯を没収されていたのでそのあいだ、西田ママから何件着信が入っているのかとか考えてしまって、怖くなった。
「蔵田課長。
その、携帯……」
「ああ。
あれはしばらく、僕が没収しとくよ」
「ないと困るんですけど……」
「ほとんど西田さんからだよね。
君、友達いないから。
それともそんなに、西田さんとおしゃべりしたいの?」
――そんなに淋しいんだー?
くすくす笑ってる蔵田課長にかっと頬が熱くなる。
「そんなこと、ある訳ないでしょ!」
「ふーん、そう。
……ごはん、できたから」
「……」
ムカつくほど楽しそうに蔵田課長が並べた朝食を思わず睨んでしまう。
「……嫌いなんですけど、お粥」
「君が食欲がないって云うから、食べやすいようにお粥にしてあげたのに」
まあ、厚意には感謝するが。
嫌いなものは嫌いだし。
「味がしないから嫌いっていうか」
「梅干しおかずに食べればいいよね」
「梅干しも嫌いなんです」
「はぁっ。
だったら君は、なにが食べられるの?」
――ほんとわがままだよね、君は。
ため息ついて席を立った蔵田課長は、五分ほどでマグカップ片手に戻ってきた。
「これなら食べられるよね」
マグカップの中身は黄色い……プリン?
「あ、熱いからフーフーしてあげた方がいい?」
「子供扱い、すんなっ!」
思わず噛みついたら、レンズの向こうの瞳がにっこりと笑った。
帰ろうと思ったら、ミーティングだって引き留められ。
淹れられたカフェオレに紅茶派なんですけどってけちつけたら、文句云いながらミルクティを淹れてくれた。
「佐々くんはどうしたい?」
「その。
……もう会社、辞めようかな、なんて」
はぁっ。
いつものように、小さく蔵田課長の口からため息が落ちる。
……呆れること、なのかな。
でも、私もう、限界で。
「あのさ。
……もうちょっと僕を、頼ってくれないかな」
そう云われても。
いつも人を莫迦にしてるくせに、毎月愚痴を聞いてくれるのには、感謝してるし。
「上司としてじゃなくて、ひとりの男として、頼ってくれないかなぁ?」
「はいっ?」
意味がわかんなくてまじまじと蔵田課長の顔を見たら、またはぁって小さく、ため息をつかれた。
「一年、アプローチしてるんだよ?そろそろいい加減に気づいてくれない?」
「あの、えっと?」
再びはぁって、蔵田課長の口からため息が落ちる。
「いくら部下のメンタルケアも仕事のうちだからって、好きじゃなきゃ、ここまでこまめにケアしたりしないよ」
「あの、でも、いっつも私のこと、莫迦にしてますよね?」
「だって君、すぐムキになって面白いから」
……え?
そんな理由?
「それに、気分転換になってくれればいいかなって」
「えっと……」
そう云われれば、蔵田課長にからかわれるとそれまであった小さな悩みは忘れてた。
まさか、そんな気遣いがあったなんて気づかなかった。
「まあ確かに、本とか食とかあわないことは多いけど。
でも、君にだったらあわせてもいいかなって思うし」
「はあ」
確かに、いつも意見はあわないけど。
なんだかんだ云いながら、私の希望を通してくれてた。
「それに、君がおいしそうに食べてる方が、自分の好きなもの食べてるときより嬉しいし」
「はあ」
「だからさ。
……鳴海。
いい加減、俺に落ちろよ」
急に口調が変わった蔵田課長の指が顎を持ち上げ、レンズの向こうの、燃えるような瞳が私を見つめる。
どこを見ていいのかわからなくて視線を彷徨わせたものの。
「どこ見てるんだ。
俺を見ろ」
おそるおそる、蔵田課長と視線を合わせる。
やけどしそうなほどに熱い、その瞳に私はとうとう。
「ふぇ、ふぇーん」
「あ、泣いた」
蔵田課長は私から手を離すと、おかしそうにくすくす笑ってる。
そういうのにやっぱり腹が立つな、とか思いながらも、泣きながら涙と一緒に気持ちをぽろぽろこぼれ落としてた。
「あなたのことは気になってるけど、そんな怖い顔で迫られたら、なにも云えないし」
「うん」
「確かに、云うことには腹が立つけど、嫌いではないし。
仕事の面ではむしろ、尊敬してるし」
「うん」
「いつも私の愚痴や弱音を聞いてくれるのは嬉しかったし。
というか、あのときだけ優しい顔で笑うのは、反則だって思ってたし」
「うん」
「だから、総合すると、その、……好きってことで、間違いないんだと思います」
「ナルは可愛いな」
唐突にちゅっと柔らかいものが唇にふれ、涙が止まる。
みるみるうちにあたまのてっぺんまで上がっていった熱で、黙ってしまった私にやっぱり、蔵田課長はおかしそうにくすくす笑ってる。
「ナルの顔、もっとよく見たい。
それに」
蔵田課長の手が眼鏡を引き抜くと、顔が傾きながら近づいてきた。
唇にふれた柔らかいそれは、まるで感触を楽しむかのように、私の唇を啄んでる。
たまんなくなってはぁっと小さく甘い吐息を漏らしたら、あたたかくぬめった感触が入ってきた。
求められてぎこちなく求め返すと、肩を掴んでいた蔵田課長の手に力が入る。
唇の角度が変わるたび、どちらのものともわからない熱い吐息が漏れる。
溺れてしまいそうで怖くなって、思わず蔵田課長のシャツを掴んだら、右手で後ろあたまを押さえ込まれた。
身体中を駆け回る熱は出口を求め、涙になって落ちていく。
唇が離れると、指で涙を拭ってくれた。
じっと私を見つめる濡れた瞳はいつもと違ってて、いつまでたっても心臓は落ち着かない。
「いいよな?
一年もお預け喰らってたうえに、昨日は据え膳、我慢したんだぞ。
俺、もう待てない」
耳元で囁いて離れた蔵田課長の目は、いつもの草食動物から、ギラギラと獰猛な肉食獣の目に変わってて、……ゾクリとした。
そっと寝室を出ると、リビングのソファーで寝てた。
「……起きたんだ」
「えっ、あっ、はい!」
突然、蔵田課長の目が開いて、慌ててしまった。
手近においてあった眼鏡をかけると、まるで猫でも撫でるみたいに私のあたまを撫でてくる。
「よく眠れた?」
「……はい。
その、ベッド、」
「なに?
一緒に寝た方がよかった?」
くすり、いつも通りの意地悪な笑顔になる。
昨日のあれは、きっと私の見間違いに違いない。
「朝ご飯作るから、ちょっと待ってて」
あたまをぽんぽんすると、蔵田課長はソファーを立ってキッチンに向かった。
待っててと云われても。
なにをしていいのかわからない。
ふと、携帯を没収されていたのでそのあいだ、西田ママから何件着信が入っているのかとか考えてしまって、怖くなった。
「蔵田課長。
その、携帯……」
「ああ。
あれはしばらく、僕が没収しとくよ」
「ないと困るんですけど……」
「ほとんど西田さんからだよね。
君、友達いないから。
それともそんなに、西田さんとおしゃべりしたいの?」
――そんなに淋しいんだー?
くすくす笑ってる蔵田課長にかっと頬が熱くなる。
「そんなこと、ある訳ないでしょ!」
「ふーん、そう。
……ごはん、できたから」
「……」
ムカつくほど楽しそうに蔵田課長が並べた朝食を思わず睨んでしまう。
「……嫌いなんですけど、お粥」
「君が食欲がないって云うから、食べやすいようにお粥にしてあげたのに」
まあ、厚意には感謝するが。
嫌いなものは嫌いだし。
「味がしないから嫌いっていうか」
「梅干しおかずに食べればいいよね」
「梅干しも嫌いなんです」
「はぁっ。
だったら君は、なにが食べられるの?」
――ほんとわがままだよね、君は。
ため息ついて席を立った蔵田課長は、五分ほどでマグカップ片手に戻ってきた。
「これなら食べられるよね」
マグカップの中身は黄色い……プリン?
「あ、熱いからフーフーしてあげた方がいい?」
「子供扱い、すんなっ!」
思わず噛みついたら、レンズの向こうの瞳がにっこりと笑った。
帰ろうと思ったら、ミーティングだって引き留められ。
淹れられたカフェオレに紅茶派なんですけどってけちつけたら、文句云いながらミルクティを淹れてくれた。
「佐々くんはどうしたい?」
「その。
……もう会社、辞めようかな、なんて」
はぁっ。
いつものように、小さく蔵田課長の口からため息が落ちる。
……呆れること、なのかな。
でも、私もう、限界で。
「あのさ。
……もうちょっと僕を、頼ってくれないかな」
そう云われても。
いつも人を莫迦にしてるくせに、毎月愚痴を聞いてくれるのには、感謝してるし。
「上司としてじゃなくて、ひとりの男として、頼ってくれないかなぁ?」
「はいっ?」
意味がわかんなくてまじまじと蔵田課長の顔を見たら、またはぁって小さく、ため息をつかれた。
「一年、アプローチしてるんだよ?そろそろいい加減に気づいてくれない?」
「あの、えっと?」
再びはぁって、蔵田課長の口からため息が落ちる。
「いくら部下のメンタルケアも仕事のうちだからって、好きじゃなきゃ、ここまでこまめにケアしたりしないよ」
「あの、でも、いっつも私のこと、莫迦にしてますよね?」
「だって君、すぐムキになって面白いから」
……え?
そんな理由?
「それに、気分転換になってくれればいいかなって」
「えっと……」
そう云われれば、蔵田課長にからかわれるとそれまであった小さな悩みは忘れてた。
まさか、そんな気遣いがあったなんて気づかなかった。
「まあ確かに、本とか食とかあわないことは多いけど。
でも、君にだったらあわせてもいいかなって思うし」
「はあ」
確かに、いつも意見はあわないけど。
なんだかんだ云いながら、私の希望を通してくれてた。
「それに、君がおいしそうに食べてる方が、自分の好きなもの食べてるときより嬉しいし」
「はあ」
「だからさ。
……鳴海。
いい加減、俺に落ちろよ」
急に口調が変わった蔵田課長の指が顎を持ち上げ、レンズの向こうの、燃えるような瞳が私を見つめる。
どこを見ていいのかわからなくて視線を彷徨わせたものの。
「どこ見てるんだ。
俺を見ろ」
おそるおそる、蔵田課長と視線を合わせる。
やけどしそうなほどに熱い、その瞳に私はとうとう。
「ふぇ、ふぇーん」
「あ、泣いた」
蔵田課長は私から手を離すと、おかしそうにくすくす笑ってる。
そういうのにやっぱり腹が立つな、とか思いながらも、泣きながら涙と一緒に気持ちをぽろぽろこぼれ落としてた。
「あなたのことは気になってるけど、そんな怖い顔で迫られたら、なにも云えないし」
「うん」
「確かに、云うことには腹が立つけど、嫌いではないし。
仕事の面ではむしろ、尊敬してるし」
「うん」
「いつも私の愚痴や弱音を聞いてくれるのは嬉しかったし。
というか、あのときだけ優しい顔で笑うのは、反則だって思ってたし」
「うん」
「だから、総合すると、その、……好きってことで、間違いないんだと思います」
「ナルは可愛いな」
唐突にちゅっと柔らかいものが唇にふれ、涙が止まる。
みるみるうちにあたまのてっぺんまで上がっていった熱で、黙ってしまった私にやっぱり、蔵田課長はおかしそうにくすくす笑ってる。
「ナルの顔、もっとよく見たい。
それに」
蔵田課長の手が眼鏡を引き抜くと、顔が傾きながら近づいてきた。
唇にふれた柔らかいそれは、まるで感触を楽しむかのように、私の唇を啄んでる。
たまんなくなってはぁっと小さく甘い吐息を漏らしたら、あたたかくぬめった感触が入ってきた。
求められてぎこちなく求め返すと、肩を掴んでいた蔵田課長の手に力が入る。
唇の角度が変わるたび、どちらのものともわからない熱い吐息が漏れる。
溺れてしまいそうで怖くなって、思わず蔵田課長のシャツを掴んだら、右手で後ろあたまを押さえ込まれた。
身体中を駆け回る熱は出口を求め、涙になって落ちていく。
唇が離れると、指で涙を拭ってくれた。
じっと私を見つめる濡れた瞳はいつもと違ってて、いつまでたっても心臓は落ち着かない。
「いいよな?
一年もお預け喰らってたうえに、昨日は据え膳、我慢したんだぞ。
俺、もう待てない」
耳元で囁いて離れた蔵田課長の目は、いつもの草食動物から、ギラギラと獰猛な肉食獣の目に変わってて、……ゾクリとした。
22
あなたにおすすめの小説
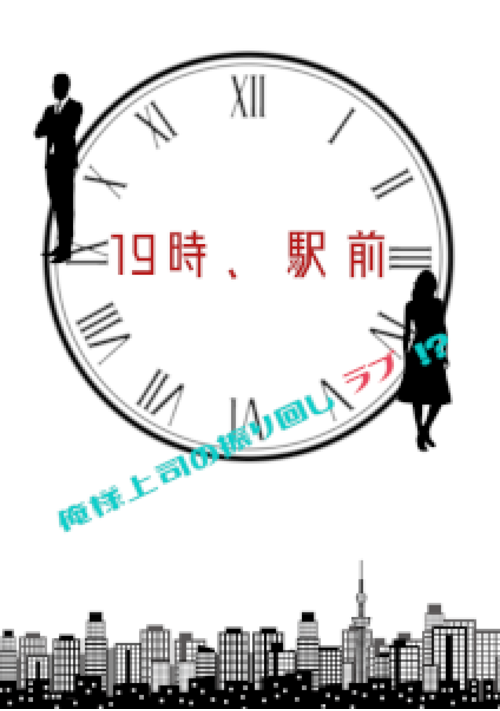
19時、駅前~俺様上司の振り回しラブ!?~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
【19時、駅前。片桐】
その日、机の上に貼られていた付箋に戸惑った。
片桐っていうのは隣の課の俺様課長、片桐課長のことでいいんだと思う。
でも私と片桐課長には、同じ営業部にいるってこと以外、なにも接点がない。
なのに、この呼び出しは一体、なんですか……?
笹岡花重
24歳、食品卸会社営業部勤務。
真面目で頑張り屋さん。
嫌と言えない性格。
あとは平凡な女子。
×
片桐樹馬
29歳、食品卸会社勤務。
3課課長兼部長代理
高身長・高学歴・高収入と昔の三高を満たす男。
もちろん、仕事できる。
ただし、俺様。
俺様片桐課長に振り回され、私はどうなっちゃうの……!?

契約結婚に初夜は必要ですか?
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
勤めていた会社から突然、契約を切られて失業中の私が再会したのは、前の会社の人間、飛田でした。
このままでは預金がつきてアパートを追い出されそうな私と、会社を変わるので寮を出なければならず食事その他家事が困る飛田。
そんな私たちは利害が一致し、恋愛感情などなく結婚したのだけれど。
……なぜか結婚初日に、迫られています。

そういう目で見ています
如月 そら
恋愛
プロ派遣社員の月蔵詩乃。
今の派遣先である会社社長は
詩乃の『ツボ』なのです。
つい、目がいってしまう。
なぜって……❤️
(11/1にお話を追記しました💖)

チョコレートは澤田
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
「食えば?」
突然、目の前に差し出された板チョコに驚いた。
同僚にきつく当たられ、つらくてトイレで泣いて出てきたところ。
戸惑ってる私を無視して、黒縁眼鏡の男、澤田さんは私にさらに板チョコを押しつけた。
……この日から。
私が泣くといつも、澤田さんは板チョコを差し出してくる。
彼は一体、なにがしたいんだろう……?

Promise Ring
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
浅井夕海、OL。
下請け会社の社長、多賀谷さんを社長室に案内する際、ふたりっきりのエレベーターで突然、うなじにキスされました。
若くして独立し、業績も上々。
しかも独身でイケメン、そんな多賀谷社長が地味で無表情な私なんか相手にするはずなくて。
なのに次きたとき、やっぱりふたりっきりのエレベーターで……。

残り香
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
水城野乃花は煙草のにおいで目が覚めた。
自分は煙草を吸わないのになぜだろうと部屋の中を見渡すと、足下に男が座っている。
フードの付いた長い黒マントを纏う男は死神だと名乗った。
片思いの相手を事故で亡くし、自暴自棄になる野乃花と、彼女の元に現れた死神の、ある朝の話。
【短編】

昨日、彼を振りました。
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
「三峰が、好きだ」
四つ年上の同僚、荒木さんに告白された。
でも、いままでの関係でいたかった私は彼を――振ってしまった。
なのに、翌日。
眼鏡をかけてきた荒木さんに胸がきゅんと音を立てる。
いやいや、相手は昨日、振った相手なんですが――!!
三峰未來
24歳
会社員
恋愛はちょっぴり苦手。
恋愛未満の関係に甘えていたいタイプ
×
荒木尚尊
28歳
会社員
面倒見のいい男
嫌われるくらいなら、恋人になれなくてもいい?
昨日振った人を好きになるとかあるのかな……?

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















