2 / 3
第一章 塔の下のカガリ ― Kagari Beneath the Ash-Iron Tower ―
第一話 塔が人間だった頃の話 ― Episode 1: When the Tower Was Still Human ―
しおりを挟む
人の心って、どこにあるんだろう。
ちゃんと考えたのなんて、たぶん一回きりだ。
教本には「心臓ではない」と書いてあった。
心臓はただ、血を送り出すポンプ――鼓動を生むエンジンだ、と。
はいテストに出ます、ってやつだ。
じゃあ、胸の奥でぎゅうぎゅう鳴ってるこの感じは、何なんだよって話だ。
授業で一番えらそうな教官が、自分の胸をこんっと叩いて言った。
「体全体だ。
骨には、生きる意味が沈み込み、
血には、生きた理由が混ざる。
そしてそれらが、いつか灰と鉄になる」
そのときの俺は、後ろの席でノートに落書きしながら、
(出た、“名言っぽいこと言いたい病”)
って、内心であくびしてただけだった。
――まさか、その“灰”と“鉄”の中に、
自分の鼓動が混ざる日が来るなんて、思ってもいなかったから。
顔を上げる。
どーん、と視界を全部持っていく灰色の巨塔。
雲なんて知らねえとばかりに突き刺して、
降ってくる雪は、勝手に弾き返している。
街の真ん中に座り込んだ、でっかい機嫌の悪い心臓。
それが――灰鉄塔アストラ。
ひびだらけの灰鉄の外壁には、
何百年分の祈りと罵声と、
数えきれない終わり際の息が、薄い層になって貼り付いているらしい。
俺たちの街の象徴。
そして、俺にとっては、ずっと避けて通りたかった場所。
その塔が、もとは人間だった――なんて話を、初めて聞かされたとき、
俺は、盛大に笑ってしまった。
「はは。塔が人間って、それ、酔っぱらいが盛り上がるやつだろ」
実際にそれを言ったのは、酒場の酔っぱらいじゃなくて、
街で一番古い教会の神官だったんだけど。
「笑っていい。信じなくてもいい。
でも、お前は一度、その“中身”に触れているはずだよ、カガリ」
あの日の返事を、俺はまだ返していない。
……というか、返せないでいる。
塔の“中身”――その言葉を聞いただけで、
胸の奥で、なにかがひゅっと縮こまる感覚が蘇る。
八つのとき、塔に触れた。
あれは、まだ戦争がここまで酷くなる前の年だ。
好奇心からじゃない。塔守の兵士に腕を引かれた。
「怖くないよ。ほら、手をあててみろ。
ここは、お前を守ってくれた人たちの“墓”なんだ」
冷たい、と思った。
冬の石より、ずっと深いところまで冷えている感じがした。
指先から腕の骨の奥まで、すうっと熱が抜けていく。
なのに、そのくせ――
ドン、と。
塔の奥のどこかで、巨大な何かが一度だけ脈打った。
押し寄せる血潮みたいな音が、耳の内側を埋め尽くす。
視界が真っ白に弾けて、世界が一瞬、誰かの心臓の内側になった。
知らない誰かの、最後の一撃。
知らない誰かの、ちぎれそうなほど強く握りしめた銃。
知らない誰かの、「まだ死にたくない」という、本気の叫び。
それら全部が、まとめて俺の胸に叩きつけられた。
俺の鼓動の列に、知らない鼓動が無理やり割り込んできて、
「お前もこっちにこいよ」と引っ張るみたいに響く。
塔に塗り込められた“誰かの終わり”が、
生きている俺の心臓を、墓標の中へと引きずりこもうとする。
その一拍で、世界の温度が反転した。
――やめろ。
そう思うより早く、膝から力が抜けた。
気がついたときには、俺は雪の上に倒れていて、
息を吸うたび、肺の奥が氷みたいに痛んだ。
視界の端で、塔守の兵士が、俺を庇うように横たわっていた。
彼の胸には、エコー暴走で砕けた石柱の欠片が、
ありえない角度で深く突き刺さっていた。
「……よかった。
お前だけは、間に合ったな」
そう言って、彼は笑った。
白い息が途切れ途切れになりながらも、ちゃんと笑おうとしていた。
そして、そのまま二度と起き上がらなかった。
兵士の遺体は、その日のうちに灰にされ、
塔の上部へ運ばれていったと聞く。
あのとき聞いた、塔の奥の一拍と、
あの人の最後の笑い方は、いまだに同じ場所で重なっている。
それ以来だ。
俺は、塔が嫌いになった。
塔が怖くなった。
塔は俺を守ってくれた。
でも同時に、俺から“何か”を奪った。
それが何なのか、うまく言葉にはできない。
ただ、あの日からずっと、俺の鼓動は「俺だけのものじゃない」みたいな顔をしている。
十年近く、塔を見上げるたびに、首の奥が重くなる日々を過ごした。
そんな俺が、よりによって、今は塔を守る側の兵士をやっている。
「――また、塔見上げてる」
背中から声が飛んできた。
振り向くと、雪の上にしゃがみこんだユラが、
ぬれた手袋をぱんぱん叩きながら、こちらを見上げていた。
目元までマフラーを巻いていても分かる。
どう考えても笑っている。
「癖になってるよ、それ。塔見て黙るやつ」
「別に。立ってるもんがでかいと、ぼーっとしたくなるだけだ」
「ふーん? こっちから見ると、“塔に睨まれて固まってる人”にしか見えないけど」
ユラの後ろで、シンが荷箱を蹴りながら笑った。
「お前なぁ、“塔下”ってあだ名、本人の前で言うのやめろっての」
「言ってないでしょ。まだ心の中」
「いや、口から出てんだよ、それが」
第十三小隊スノウライン。
灰鉄塔アストラの麓を担当する、塔下防衛小隊の朝は、だいたいこんな調子だ。
雪かき。塔下の見回り。
塔の影から吹き込む風は、骨に刺さるほど冷たいのに、
ユラとシンの口だけは、どれだけでもよく回る。
「でもさ、ほんと不思議だよね」
ユラが、ふいに真面目な声になった。
「同じ塔の下で育って、同じ雪道走って、
同じ訓練受けてきたのに――」
「またその話?」
シンが肩をすくめる。
「出たよ、“なんで塔はカガリだけ選んだのか問題”」
「だって気になるでしょ。
あの日の訓練のあと、塔の近くでふらっと倒れたの、カガリだけだよ?」
「言い方」
俺は深くため息をつき、マフラーを鼻の上まで引き上げた。
「選ばれてない。
勝手に近寄って、勝手に具合悪くなってるだけだ」
「そうかなぁ」
ユラは立ち上がり、塔を見上げた。
その瞳には、幼いころから変わらない好奇心と、
少しだけ混じった恐怖が揺れている。
「塔がもし、本当に昔は人間だったのならさ。
誰か一人くらい、自分のことを覚えててほしいって思うんじゃない?」
その言葉は、軽い調子で出てきたはずなのに、
俺の耳には、やけに重く落ちてきた。
「……気持ち悪いこと言うな」
そう返しながらも、完全には否定しきれない自分がいる。
塔のそばに立つと、胸がざわつく。
鼓動がひとつ、ふたつ、数えやすくなる。
そのリズムに、時々、“別の何か”が一拍だけ割り込んでくる。
それが、誰のものなのか。
俺はまだ、聞き分けられない。
ただ、その一拍だけ、やけに静かで、やけに必死だ。
――ここにいる。忘れるな。
そんなふうに訴えているような気がして、
自分の鼓動まで、どっちが本物か分からなくなる。
けれど――。
「おーい、第十三小隊! 集合!」
塔下の詰め所から、太い声が飛んだ。
デイル小隊長だ。
「臨時の通達だ! いいニュースじゃねぇ顔しとけよ!」
「うわ、絶対ろくな話じゃないね」
ユラが、小さく肩をすくめる。
シンは「賭けるか? 前線か補給地変更か」とか言いながら、荷物を抱え直した。
俺たちは、雪を蹴って詰め所に向かう。
灰鉄塔の影は、さっきより少しだけ長く伸びていた。
そのとき――塔の上の方から、かすかな軋む音が聞こえた気がした。
気のせいだ、と思う。
そう思おうとする。
それでも、胸の奥でエンジンが一拍だけ跳ねた。
――生きている。
“墓標代わりの塔”のくせに、まだどこかが脈打っている。
俺だけが、その鼓動を聞いてしまったような気がして、
首の後ろが、ひやりと冷たくなった。
灰鉄戦役の末期。
塔の下で、俺たちの“順番”が、ようやく回ってこようとしていた。
ちゃんと考えたのなんて、たぶん一回きりだ。
教本には「心臓ではない」と書いてあった。
心臓はただ、血を送り出すポンプ――鼓動を生むエンジンだ、と。
はいテストに出ます、ってやつだ。
じゃあ、胸の奥でぎゅうぎゅう鳴ってるこの感じは、何なんだよって話だ。
授業で一番えらそうな教官が、自分の胸をこんっと叩いて言った。
「体全体だ。
骨には、生きる意味が沈み込み、
血には、生きた理由が混ざる。
そしてそれらが、いつか灰と鉄になる」
そのときの俺は、後ろの席でノートに落書きしながら、
(出た、“名言っぽいこと言いたい病”)
って、内心であくびしてただけだった。
――まさか、その“灰”と“鉄”の中に、
自分の鼓動が混ざる日が来るなんて、思ってもいなかったから。
顔を上げる。
どーん、と視界を全部持っていく灰色の巨塔。
雲なんて知らねえとばかりに突き刺して、
降ってくる雪は、勝手に弾き返している。
街の真ん中に座り込んだ、でっかい機嫌の悪い心臓。
それが――灰鉄塔アストラ。
ひびだらけの灰鉄の外壁には、
何百年分の祈りと罵声と、
数えきれない終わり際の息が、薄い層になって貼り付いているらしい。
俺たちの街の象徴。
そして、俺にとっては、ずっと避けて通りたかった場所。
その塔が、もとは人間だった――なんて話を、初めて聞かされたとき、
俺は、盛大に笑ってしまった。
「はは。塔が人間って、それ、酔っぱらいが盛り上がるやつだろ」
実際にそれを言ったのは、酒場の酔っぱらいじゃなくて、
街で一番古い教会の神官だったんだけど。
「笑っていい。信じなくてもいい。
でも、お前は一度、その“中身”に触れているはずだよ、カガリ」
あの日の返事を、俺はまだ返していない。
……というか、返せないでいる。
塔の“中身”――その言葉を聞いただけで、
胸の奥で、なにかがひゅっと縮こまる感覚が蘇る。
八つのとき、塔に触れた。
あれは、まだ戦争がここまで酷くなる前の年だ。
好奇心からじゃない。塔守の兵士に腕を引かれた。
「怖くないよ。ほら、手をあててみろ。
ここは、お前を守ってくれた人たちの“墓”なんだ」
冷たい、と思った。
冬の石より、ずっと深いところまで冷えている感じがした。
指先から腕の骨の奥まで、すうっと熱が抜けていく。
なのに、そのくせ――
ドン、と。
塔の奥のどこかで、巨大な何かが一度だけ脈打った。
押し寄せる血潮みたいな音が、耳の内側を埋め尽くす。
視界が真っ白に弾けて、世界が一瞬、誰かの心臓の内側になった。
知らない誰かの、最後の一撃。
知らない誰かの、ちぎれそうなほど強く握りしめた銃。
知らない誰かの、「まだ死にたくない」という、本気の叫び。
それら全部が、まとめて俺の胸に叩きつけられた。
俺の鼓動の列に、知らない鼓動が無理やり割り込んできて、
「お前もこっちにこいよ」と引っ張るみたいに響く。
塔に塗り込められた“誰かの終わり”が、
生きている俺の心臓を、墓標の中へと引きずりこもうとする。
その一拍で、世界の温度が反転した。
――やめろ。
そう思うより早く、膝から力が抜けた。
気がついたときには、俺は雪の上に倒れていて、
息を吸うたび、肺の奥が氷みたいに痛んだ。
視界の端で、塔守の兵士が、俺を庇うように横たわっていた。
彼の胸には、エコー暴走で砕けた石柱の欠片が、
ありえない角度で深く突き刺さっていた。
「……よかった。
お前だけは、間に合ったな」
そう言って、彼は笑った。
白い息が途切れ途切れになりながらも、ちゃんと笑おうとしていた。
そして、そのまま二度と起き上がらなかった。
兵士の遺体は、その日のうちに灰にされ、
塔の上部へ運ばれていったと聞く。
あのとき聞いた、塔の奥の一拍と、
あの人の最後の笑い方は、いまだに同じ場所で重なっている。
それ以来だ。
俺は、塔が嫌いになった。
塔が怖くなった。
塔は俺を守ってくれた。
でも同時に、俺から“何か”を奪った。
それが何なのか、うまく言葉にはできない。
ただ、あの日からずっと、俺の鼓動は「俺だけのものじゃない」みたいな顔をしている。
十年近く、塔を見上げるたびに、首の奥が重くなる日々を過ごした。
そんな俺が、よりによって、今は塔を守る側の兵士をやっている。
「――また、塔見上げてる」
背中から声が飛んできた。
振り向くと、雪の上にしゃがみこんだユラが、
ぬれた手袋をぱんぱん叩きながら、こちらを見上げていた。
目元までマフラーを巻いていても分かる。
どう考えても笑っている。
「癖になってるよ、それ。塔見て黙るやつ」
「別に。立ってるもんがでかいと、ぼーっとしたくなるだけだ」
「ふーん? こっちから見ると、“塔に睨まれて固まってる人”にしか見えないけど」
ユラの後ろで、シンが荷箱を蹴りながら笑った。
「お前なぁ、“塔下”ってあだ名、本人の前で言うのやめろっての」
「言ってないでしょ。まだ心の中」
「いや、口から出てんだよ、それが」
第十三小隊スノウライン。
灰鉄塔アストラの麓を担当する、塔下防衛小隊の朝は、だいたいこんな調子だ。
雪かき。塔下の見回り。
塔の影から吹き込む風は、骨に刺さるほど冷たいのに、
ユラとシンの口だけは、どれだけでもよく回る。
「でもさ、ほんと不思議だよね」
ユラが、ふいに真面目な声になった。
「同じ塔の下で育って、同じ雪道走って、
同じ訓練受けてきたのに――」
「またその話?」
シンが肩をすくめる。
「出たよ、“なんで塔はカガリだけ選んだのか問題”」
「だって気になるでしょ。
あの日の訓練のあと、塔の近くでふらっと倒れたの、カガリだけだよ?」
「言い方」
俺は深くため息をつき、マフラーを鼻の上まで引き上げた。
「選ばれてない。
勝手に近寄って、勝手に具合悪くなってるだけだ」
「そうかなぁ」
ユラは立ち上がり、塔を見上げた。
その瞳には、幼いころから変わらない好奇心と、
少しだけ混じった恐怖が揺れている。
「塔がもし、本当に昔は人間だったのならさ。
誰か一人くらい、自分のことを覚えててほしいって思うんじゃない?」
その言葉は、軽い調子で出てきたはずなのに、
俺の耳には、やけに重く落ちてきた。
「……気持ち悪いこと言うな」
そう返しながらも、完全には否定しきれない自分がいる。
塔のそばに立つと、胸がざわつく。
鼓動がひとつ、ふたつ、数えやすくなる。
そのリズムに、時々、“別の何か”が一拍だけ割り込んでくる。
それが、誰のものなのか。
俺はまだ、聞き分けられない。
ただ、その一拍だけ、やけに静かで、やけに必死だ。
――ここにいる。忘れるな。
そんなふうに訴えているような気がして、
自分の鼓動まで、どっちが本物か分からなくなる。
けれど――。
「おーい、第十三小隊! 集合!」
塔下の詰め所から、太い声が飛んだ。
デイル小隊長だ。
「臨時の通達だ! いいニュースじゃねぇ顔しとけよ!」
「うわ、絶対ろくな話じゃないね」
ユラが、小さく肩をすくめる。
シンは「賭けるか? 前線か補給地変更か」とか言いながら、荷物を抱え直した。
俺たちは、雪を蹴って詰め所に向かう。
灰鉄塔の影は、さっきより少しだけ長く伸びていた。
そのとき――塔の上の方から、かすかな軋む音が聞こえた気がした。
気のせいだ、と思う。
そう思おうとする。
それでも、胸の奥でエンジンが一拍だけ跳ねた。
――生きている。
“墓標代わりの塔”のくせに、まだどこかが脈打っている。
俺だけが、その鼓動を聞いてしまったような気がして、
首の後ろが、ひやりと冷たくなった。
灰鉄戦役の末期。
塔の下で、俺たちの“順番”が、ようやく回ってこようとしていた。
0
あなたにおすすめの小説

碧天のノアズアーク
世良シンア
ファンタジー
両親の顔を知らない双子の兄弟。
あらゆる害悪から双子を守る二人の従者。
かけがえのない仲間を失った若き女冒険者。
病に苦しむ母を救うために懸命に生きる少女。
幼い頃から血にまみれた世界で生きる幼い暗殺者。
両親に売られ生きる意味を失くした女盗賊。
一族を殺され激しい復讐心に囚われた隻眼の女剣士。
Sランク冒険者の一人として活躍する亜人国家の第二王子。
自分という存在を心底嫌悪する龍人の男。
俗世とは隔絶して生きる最強の一族族長の息子。
強い自責の念に蝕まれ自分を見失った青年。
性別も年齢も性格も違う十三人。決して交わることのなかった者たちが、ノア=オーガストの不思議な引力により一つの方舟へと乗り込んでいく。そして方舟はいくつもの荒波を越えて、飽くなき探究心を原動力に世界中を冒険する。この方舟の終着点は果たして……
※『side〇〇』という風に、それぞれのキャラ視点を通して物語が進んでいきます。そのため主人公だけでなく様々なキャラの視点が入り混じります。視点がコロコロと変わりますがご容赦いただけると幸いです。
※一話ごとの字数がまちまちとなっています。ご了承ください。
※物語が進んでいく中で、投稿済みの話を修正する場合があります。ご了承ください。
※初執筆の作品です。誤字脱字など至らぬ点が多々あると思いますが、温かい目で見守ってくださると大変ありがたいです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
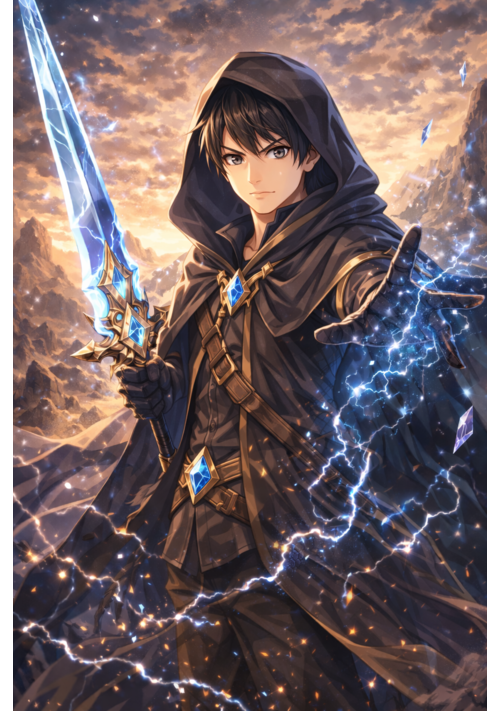
R・P・G ~転生して不死にされた俺は、最強の英雄たちと滅ぼすはずだった異世界を統治する~
イット
ファンタジー
オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の取材中、異世界の大地の女神と接触する。
そのまま半ば強制的に異世界へと転生させられた彼は、惑星そのものと同化し、“星骸の主”として不死の存在へと変貌した。
だが女神から与えられた使命は、この世界の生命を滅ぼし、星を「リセット」すること。
凛人はその命令を、拒否する。
不死であっても無敵ではない。
戦いでは英雄王に殴り倒される始末。しかし一つ選択を誤れば国が滅びる危うい存在。
それでも彼は、星を守るために戦う道を選んだ。
女神の使命を「絶対拒否」する不死者と、裏ボス級の従者たち。
これは、世界を滅ぼさず、統治することを選んだ男の英雄譚である。

悪徳貴族の、イメージ改善、慈善事業
ウィリアム・ブロック
ファンタジー
現代日本から死亡したラスティは貴族に転生する。しかしその世界では貴族はあんまり良く思われていなかった。なのでノブリス・オブリージュを徹底させて、貴族のイメージ改善を目指すのだった。

【もうダメだ!】貧乏大学生、絶望から一気に成り上がる〜もし、無属性でFランクの俺が異文明の魔道兵器を担いでダンジョンに潜ったら〜
KEINO
ファンタジー
貧乏大学生の探索者はダンジョンに潜り、全てを覆す。
~あらすじ~
世界に突如出現した異次元空間「ダンジョン」。
そこから産出される魔石は人類に無限のエネルギーをもたらし、アーティファクトは魔法の力を授けた。
しかし、その恩恵は平等ではなかった。
富と力はダンジョン利権を牛耳る企業と、「属性適性」という特別な才能を持つ「選ばれし者」たちに独占され、世界は新たな格差社会へと変貌していた。
そんな歪んだ現代日本で、及川翔は「無属性」という最底辺の烙印を押された青年だった。
彼には魔法の才能も、富も、未来への希望もない。
あるのは、両親を失った二年前のダンジョン氾濫で、原因不明の昏睡状態に陥った最愛の妹、美咲を救うという、ただ一つの願いだけだった。
妹を治すため、彼は最先端の「魔力生体学」を学ぶが、学費と治療費という冷酷な現実が彼の行く手を阻む。
希望と絶望の狭間で、翔に残された道はただ一つ――危険なダンジョンに潜り、泥臭く魔石を稼ぐこと。
英雄とも呼べるようなSランク探索者が脚光を浴びる華やかな世界とは裏腹に、翔は今日も一人、薄暗いダンジョンの奥へと足を踏み入れる。
これは、神に選ばれなかった「持たざる者」が、絶望的な現実にもがきながら、たった一つの希望を掴むために抗い、やがて世界の真実と向き合う、戦いの物語。
彼の「無属性」の力が、世界を揺るがす光となることを、彼はまだ知らない。
テンプレのダンジョン物を書いてみたくなり、手を出しました。
SF味が増してくるのは結構先の予定です。
スローペースですが、しっかりと世界観を楽しんでもらえる作品になってると思います。
良かったら読んでください!

異世界でカイゼン
soue kitakaze
ファンタジー
作者:北風 荘右衛(きたかぜ そうえ)
この物語は、よくある「異世界転生」ものです。
ただ
・転生時にチート能力はもらえません
・魔物退治用アイテムももらえません
・そもそも魔物退治はしません
・農業もしません
・でも魔法が当たり前にある世界で、魔物も魔王もいます
そこで主人公はなにをするのか。
改善手法を使った問題解決です。
主人公は現世にて「問題解決のエキスパート」であり、QC手法、IE手法、品質工学、ワークデザイン法、発想法など、問題解決技術に習熟しており、また優れた発想力を持つ人間です。ただそれを正統に評価されていないという鬱屈が溜まっていました。
そんな彼が飛ばされた異世界で、己の才覚ひとつで異世界を渡って行く。そういうお話をギャグを中心に描きます。簡単に言えば。
「人の死なない邪道ファンタジーな、異世界でカイゼンをするギャグ物語」
ということになります。

最強無敗の少年は影を従え全てを制す
ユースケ
ファンタジー
不慮の事故により死んでしまった大学生のカズトは、異世界に転生した。
産まれ落ちた家は田舎に位置する辺境伯。
カズトもといリュートはその家系の長男として、日々貴族としての教養と常識を身に付けていく。
しかし彼の力は生まれながらにして最強。
そんな彼が巻き起こす騒動は、常識を越えたものばかりで……。

大ッ嫌いな英雄様達に告ぐ
鮭とば
ファンタジー
剣があって、魔法があって、けれども機械はない世界。妖魔族、俗に言う魔族と人間族の、原因は最早誰にもわからない、終わらない小競り合いに、いつからあらわれたのかは皆わからないが、一旦の終止符をねじ込んだ聖女様と、それを守る5人の英雄様。
それが約50年前。
聖女様はそれから2回代替わりをし、数年前に3回目の代替わりをしたばかりで、英雄様は数え切れないぐらい替わってる。
英雄の座は常に5つで、基本的にどこから英雄を選ぶかは決まってる。
俺は、なんとしても、聖女様のすぐ隣に居たい。
でも…英雄は5人もいらないな。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















