841 / 1,289
第35話
(18)
しおりを挟む
鷹津は何も言わず緩く腰を動かし始める。電話の向こうの俊哉に悟られまいと、和彦は声を押し殺しながら必死に逃れようとするが、睡眠薬の効き目はどんどん和彦の体と意識を侵食していく。
『お前に言いたいことはいろいろあるが、今はやめておこう。ただ、これだけは言っておく。――お前をずっと自由にはさせていたが、お前を手放すつもりは、まったくない。わたしそっくりの、大事で可愛い息子だからな。この言葉がウソでないことは、お前自身、よくわかっているだろう?』
電話から聞こえてくる俊哉の言葉が恐ろしかった。必死に記憶の片隅に追いやってきた光景が生々しく蘇り、当時、自分が抱いた感情すらも、思い出してしまう。
唇を戦慄かせ、呼吸すらも止めてしまいそうになっていると、和彦の異変に気づいた鷹津が、強く頬を撫でてくる。それでは足りないと思ったのか、内奥を強く突き上げてきた。
和彦は我に返り、うろたえる。意識を、電話の向こうにいる俊哉に向ければいいのか、目の前の鷹津に向ければいいのか、混乱していた。
「今は、やめてくれ。父さんに――」
何をしているか悟られてしまう、と言いたかったが、鷹津は酷薄な笑みを浮かべた。
「安心しろ。お前の父親は全部知っている。お前が長嶺の男たちのオンナになっていることも、俺とも寝ていることも。直接会って話したが、さすが、切れ者大物官僚……いや、お前の父親だな。顔色一つ変えなかった」
和彦が、自分の現状を実家に知られたくなかったのは、家族に迷惑をかけたくないという気持ちは当然だが、何より、佐伯家――俊哉が、長嶺の男たちを敵として認識することを恐れていたからだ。何もかも知られたとき、自分の扱いについて無難な解決がなされることはありえないと、和彦はよくわかっている。
佐伯家と接触するのは自分一人で、万が一にも、長嶺組や総和会の存在は一切匂わせてはいけないと考えていたが、和彦の希望は楽観的であり、悠長だったのだろう。
思いがけない人物に、先手を打たれてしまった。
「……どうして、あんたがそんなことを……」
鷹津は一瞬苦しげに顔をしかめたあと、携帯電話をちらりと見遣った。
「先に、自分の父親との話を済ませろ」
和彦はのろのろと片手を伸ばし、携帯電話を切ろうとしたが、あっさり鷹津に取り上げられる。
「話せよ。もうすぐ、口が回らなくなるぞ。久しぶりだろう。父親と話すのは」
「ぼくは――」
『長嶺守光と聞いて、懐かしい気持ちになった。あの男と関わりを持つとは、なかなか因縁めいたものを感じたな。どれだけ捜そうが、見つからないはずだと感心した。総和会や長嶺組の庇護下にいてはな……。しかも、交渉事をするには、これ以上なく厄介な相手だ』
そう言う俊哉の声は、ひたすら柔らかだった。不始末という一言では到底収まらない状況にいる和彦に対して、怒りも苛立ちも感じている様子はない。物心ついた頃から、俊哉はこうなのだ。息子に関心がないからこそ寛容であり、それが過ぎて、冷淡である。
しかし、さきほど俊哉が言った『大事で可愛い息子』という表現もまた、本人にとっては偽らざる本心だろう。
俊哉にとって和彦とは、血が繋がっているという理由以外でも、〈特別〉な存在なのだ。
『お前の居場所がわかったから、すぐに奪い返すというわけにはいかない。そう、単純な話ではないからな。あの男――化け狐は、取引相手としては誠実で有能だが……、ふん、少々欲深い。さすがのわたしも、慎重にならざるをえない』
睡眠薬で鈍くなっている和彦の意識を、何かが一瞬、鋭く刺した。それがなんであるか考えようにも、強烈な眠気に押し流され、自分が何を気にしたのかすらもわからなくなる。そんな和彦に、俊哉は核心を突くような質問をぶつけてきた。
『〈そちら〉ではずいぶん大事にされているようだが、お前は、元の生活に戻りたくないか? 佐伯家の次男坊として、気楽にふわふわと生活して、ときどき、佐伯家の人間としての義務を果たす生活だ。それなりに気に入っていただろう』
「ぼくは――……」
和彦が即答しなかったことが、俊哉にとっては何よりもの答えになっていたようだった。柔らかな声をいくぶん低め、まるで子供を窘めるような口調で言った。
『優しくしてくれて、餌をくれるなら、相手がヤクザでもいいか? 犬猫ならそれでもいいだろうが、お前は佐伯家の人間だ。髪一本、爪の一欠片でも他人に自由にさせるな。お前は、わたしの言うことにのみ従っていればいい――と、言いたいところだが、肝心のお前が長嶺守光のもとにいるなら、どうしようもない。今のところは』
『お前に言いたいことはいろいろあるが、今はやめておこう。ただ、これだけは言っておく。――お前をずっと自由にはさせていたが、お前を手放すつもりは、まったくない。わたしそっくりの、大事で可愛い息子だからな。この言葉がウソでないことは、お前自身、よくわかっているだろう?』
電話から聞こえてくる俊哉の言葉が恐ろしかった。必死に記憶の片隅に追いやってきた光景が生々しく蘇り、当時、自分が抱いた感情すらも、思い出してしまう。
唇を戦慄かせ、呼吸すらも止めてしまいそうになっていると、和彦の異変に気づいた鷹津が、強く頬を撫でてくる。それでは足りないと思ったのか、内奥を強く突き上げてきた。
和彦は我に返り、うろたえる。意識を、電話の向こうにいる俊哉に向ければいいのか、目の前の鷹津に向ければいいのか、混乱していた。
「今は、やめてくれ。父さんに――」
何をしているか悟られてしまう、と言いたかったが、鷹津は酷薄な笑みを浮かべた。
「安心しろ。お前の父親は全部知っている。お前が長嶺の男たちのオンナになっていることも、俺とも寝ていることも。直接会って話したが、さすが、切れ者大物官僚……いや、お前の父親だな。顔色一つ変えなかった」
和彦が、自分の現状を実家に知られたくなかったのは、家族に迷惑をかけたくないという気持ちは当然だが、何より、佐伯家――俊哉が、長嶺の男たちを敵として認識することを恐れていたからだ。何もかも知られたとき、自分の扱いについて無難な解決がなされることはありえないと、和彦はよくわかっている。
佐伯家と接触するのは自分一人で、万が一にも、長嶺組や総和会の存在は一切匂わせてはいけないと考えていたが、和彦の希望は楽観的であり、悠長だったのだろう。
思いがけない人物に、先手を打たれてしまった。
「……どうして、あんたがそんなことを……」
鷹津は一瞬苦しげに顔をしかめたあと、携帯電話をちらりと見遣った。
「先に、自分の父親との話を済ませろ」
和彦はのろのろと片手を伸ばし、携帯電話を切ろうとしたが、あっさり鷹津に取り上げられる。
「話せよ。もうすぐ、口が回らなくなるぞ。久しぶりだろう。父親と話すのは」
「ぼくは――」
『長嶺守光と聞いて、懐かしい気持ちになった。あの男と関わりを持つとは、なかなか因縁めいたものを感じたな。どれだけ捜そうが、見つからないはずだと感心した。総和会や長嶺組の庇護下にいてはな……。しかも、交渉事をするには、これ以上なく厄介な相手だ』
そう言う俊哉の声は、ひたすら柔らかだった。不始末という一言では到底収まらない状況にいる和彦に対して、怒りも苛立ちも感じている様子はない。物心ついた頃から、俊哉はこうなのだ。息子に関心がないからこそ寛容であり、それが過ぎて、冷淡である。
しかし、さきほど俊哉が言った『大事で可愛い息子』という表現もまた、本人にとっては偽らざる本心だろう。
俊哉にとって和彦とは、血が繋がっているという理由以外でも、〈特別〉な存在なのだ。
『お前の居場所がわかったから、すぐに奪い返すというわけにはいかない。そう、単純な話ではないからな。あの男――化け狐は、取引相手としては誠実で有能だが……、ふん、少々欲深い。さすがのわたしも、慎重にならざるをえない』
睡眠薬で鈍くなっている和彦の意識を、何かが一瞬、鋭く刺した。それがなんであるか考えようにも、強烈な眠気に押し流され、自分が何を気にしたのかすらもわからなくなる。そんな和彦に、俊哉は核心を突くような質問をぶつけてきた。
『〈そちら〉ではずいぶん大事にされているようだが、お前は、元の生活に戻りたくないか? 佐伯家の次男坊として、気楽にふわふわと生活して、ときどき、佐伯家の人間としての義務を果たす生活だ。それなりに気に入っていただろう』
「ぼくは――……」
和彦が即答しなかったことが、俊哉にとっては何よりもの答えになっていたようだった。柔らかな声をいくぶん低め、まるで子供を窘めるような口調で言った。
『優しくしてくれて、餌をくれるなら、相手がヤクザでもいいか? 犬猫ならそれでもいいだろうが、お前は佐伯家の人間だ。髪一本、爪の一欠片でも他人に自由にさせるな。お前は、わたしの言うことにのみ従っていればいい――と、言いたいところだが、肝心のお前が長嶺守光のもとにいるなら、どうしようもない。今のところは』
55
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
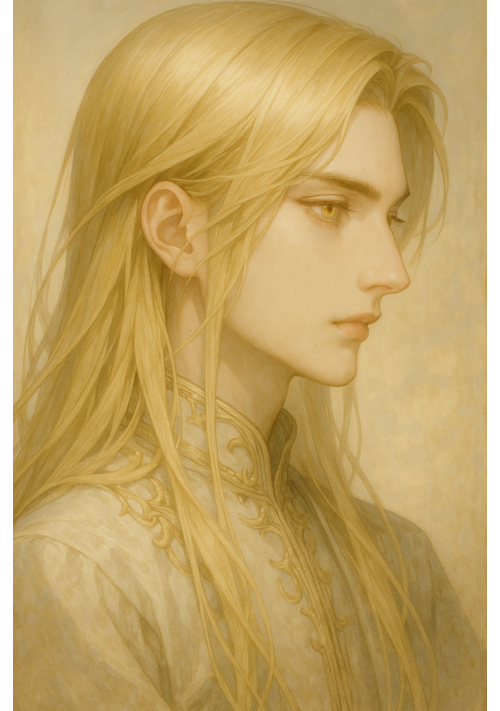
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















