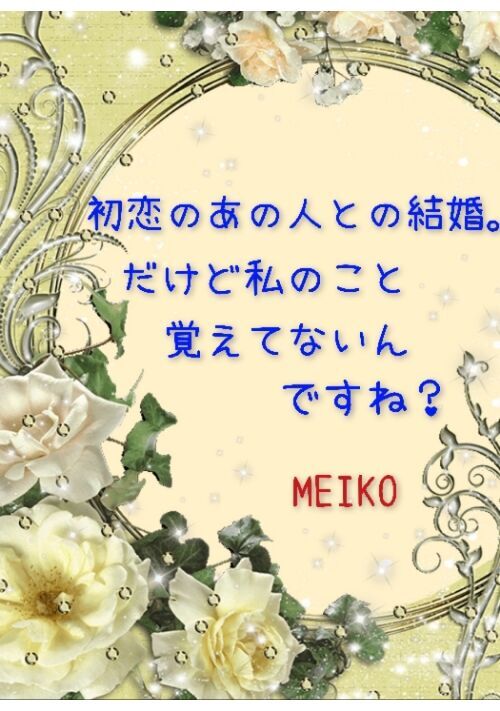328 / 515
第14章 LV999 STAMPEDE
第328話:【急募】LV999の新戦力
しおりを挟む守りに入ってはいけない──こちらから討って出る!
これが夜を徹した会議の末、導き出された結論だった。
無論、各盟主が治める保護領域の防備は疎かにはできない。バッドデッドエンズが束になって襲ってきても守り切れる防衛能力を確保し、国で暮らす住民の安全を確約できるほど備えなければならない。
住民の安全――これは最優先事項である。
相手は108人ものLV999、廉価版とはいえ油断は禁物だ。
どんなに強固な結界を何重に張り巡らせても気休めに等しい。真っ向から対処するとなれば、こちらもLV999で迎え撃つ必要がある。
四神同盟もそれぞれの陣営に、複数のLV999を迎撃要員として配置せざるを得ない。不測の事態も考えて人数は多いほど望ましい。
しかし、圧倒的な人材不足。
LV999の数がまったく足りていなかった。
バンダユウを加えても、四神同盟に属するLV999と足して12人。
限定的にLV999となれるダグ(“巨鎧甲殻”と合体して誕生する豊穣巨神王ダグザディオン)を数えても、13人がいいところだ。
四神同盟に属するプレイヤーは、全員LV900は超えている。
LV950を数えた人材も出揃ってきているし、まだ寝込んでいる穂村組が復活すれば、マリやレイジも参戦してくれるはずだ。
それでも――足りない。
最悪にして絶死をもたらす終焉の動きは、よくわからない。
108人もいるのだから組織的に動いている、という推測はできる。穂村組を襲撃したリードたちのように、10人程度の部隊に別れて各地で暴れていると仮定していいはずだ。
もしも四神同盟いずれかの保護領域へ攻め込んでくるとしたら、同等かそれ以上の数で攻め込んでくるに違いない。
対抗する戦力がどうしても不足していた。
この解決策は、バンダユウとレオナルドから提示される。
「穂村組みたいなのを引き込むしかねぇな」
「ロンドさんが動き出した今、被害を被ったプレイヤーは穂村組に限った話ではないはずだ。彼らに反感を抱く勢力を取り込むには好機と言える」
ピンチはチャンス! とミロも寝言で喚いた。
最悪にして絶死をもたらす終焉は、こうしている今も真なる世界のどこかで大量虐殺と破壊活動に励んでいる。犠牲者と被害者、どちらも計り知れない。
だが、やられっぱなしではあるまい。
穂村組におけるバンダユウがそれだ。まだ出会っていないLV999は抵抗しているだろうし、殺戮集団を返り討ちにすることもあるはずだ。
「力ってのはな──使わんもんや」
口を挟んできたのはノラシンハだった。
「兄ちゃんたちみたいに、しっかりTPOを弁えて行使するんが正しい力の在り方や。己の力を極みまで持ってった者は、それを本能的に理解して、無意識に使い分けとる。せなやないと、力んでばっかじゃあ疲れるさかいな」
もしも、新しいLV999と出会えたら──。
彼らが最悪にして絶死をもたらす終焉と遭遇していたら──。
「十中八九、兄ちゃんたちに協力するやろ。よっぽど性根のねじくれた阿呆でない限り、連中と意気投合なんてせんはずや」
LV999のプレイヤーを仲間に入れて戦力UPを目指す。
──これがバンダユウの提案。
戦力に取り込みたい者たちがロンドの勢力によって追い立てられている今、説得や交渉が容易であり、打倒ロンドを掲げれば協力体制が敷きやすい。
──これがレオナルドの憶測。
独力でLV999になるまで己を磨き上げた者ならば、真っ当な精神の持ち主である可能性が高い。ロンドではなく、ツバサたちに味方するはず。
──これがノラシンハの予測。
「主戦力となる人員の増強は急務か……」
「今後を考えれば、ますます必要となるだろうからな」
ツバサが(そろそろハトホルミルクが漏れそうな)爆乳を押し上げるように、胸の下で腕を組んで嘆息すると、アハウが背中を押すように言った。
そう、これも最優先といえるかも知れない。
もし“最悪にして絶死をもたらす終焉”の騒動がなかったとしても、この世界は数え切れないほどの蕃神に狙われている。
最近は停滞気味だが、気を許したところへ急襲でもされたら堪らない。
最悪の場合──ロンドと蕃神をいっぺんに相手取ることもある。
三つ巴になれば、戦力不足の四神同盟は最弱勢力だ。
ロンドと蕃神が手を組むかはさておき、何らかの形で挟撃されるような事態に陥れば、双方から物量で押し潰されるのは目に見えている。
戦力については喫緊の課題でもあった。
アハウはかぎ爪の目立つ人差し指を立てて注意を促す。
「戦力増員を急ぐ必要があるのは間違いありませんが……その人品を見定めることを忘れてはなりません。羊の皮を被った狼じゃありませんが、物腰丁寧な極悪人もいますからね」
アハウはバンダユウたちの言葉に賛意を示すものの、仲間に引き入れるべき人間については慎重になることを付け加えた。
然もありなん、彼ほど煮え湯を飲まされた者はいない。
開闢の使徒――ナアク・ミラビリス。
そう名乗る狂的科学者がしたり顔で仲間に加わり、アハウが家族と誇れる仲間を恐ろしい実験で二目と見られぬ姿に変えた事件があった。
殺して……と訴える異形と化した仲間たち。
泣き叫びながら彼らを手にかけた、とアハウに告解された。
この話はミサキやクロウも聞いているので、アハウからの進言を重く受け止めるようにしっかり頷いた。
クロウは両手を持ち上げ、ふんわりまとめる仕草をする。
「では、こちらから討って出るという方針が固まったところで……具体的な計画を練りますか。我々が着手すべきは大きくまとめて2つ」
ひとつ、四神同盟の保護領域。その防衛を今まで以上に強化。
ふたつ、バッドデッドエンズに対抗する戦力。その増員と増強。
「この2つに重点を置いて、計画をまとめていきましょう」
気付けば──障子の向こうが明るい。
夜が白々と明け、日が昇ってきたようだ。とうとう完徹である。
「夜明かししてしまいましたが……皆さん、もう少し頑張りましょう。計画の内容まで組んでしまい、明日から急ピッチで取り掛かるべきです」
クロウの言葉に異を唱える者はいなかった。
まだ起きている者は目元にうっすら隈を作っているが、それでも同意する頷きを返すと、さっそく計画の具体案を詳細に詰めていった。
~~~~~~~~~~~~
結局、二徹してしまった。
すっかり夜が明けたところで本格的な小休止を挟み、一度みんな自分の保護領域へ……いや、そろそろ呼び方を改めてもいい頃合いだろう。
ツバサたちもそうだが、各盟主も本格的な国家運営を始めている。
もう“国”と呼んでもいいはずだ。
そんなわけで、お昼前に一度それぞれの“国”へ戻って異常がないか確認。会議の内容を仲間たちへ簡単に伝えてきた。
お昼から、ハトホル国にて四神同盟会議の続きを再開。
国家防衛の強化と、他の勢力(個人か複数かわからないが、LV999の能力はもはや勢力といっても過言ではない)を戦力として取り込む。
この2つをメインに据えた計画を話し合った。
大筋でまとまった頃、時計の針は午前2時を回っていた。
いつもなら会議の後には、打ち上げめいた会食や宴をするものだが、今回ばかりは会議が長引きすぎてヘトヘトになってしまい、おまけに大損害を受けた穂村組の手前、「自重しよ」という流れになった。
何より――緊急事態である。
宴をやりたきゃ騒動が終わってから! ということだ。
明日から陣営を越えた協力体制を敷いて計画に沿った行動を始めよう、と取り決めたところで会議はお開きとなった。
いくら神族は寝なくて平気でも、二徹となれば精神的にきつい。
まぶたの下にちゃんと隈もできるくらいだ。
この日はさしものツバサも日課である早朝起床ができず、朝寝をさせてもらうことで精神力の回復に費やさせてもらった。
朝の雑事や家族への朝食は、クロコのメイド人形部隊に任せておく。
クロコにも休息を取らせる必要を感じた。
「メイドに休息など不要です! もっと過酷に、さらに苛烈に、激しく甚振るように嬲るように虐げるように……過労死寸前まで追い込んでくださいませ!」
「寝ろ。いいから寝ろ」
マゾをぶっちぎってブラック企業に魂を売ったようなクロコだったが、アイアンクローからの裸締めで落として、自室に放り込んでおいた。
最低8時間は寝るよう睡眠魔法も忘れない。
肉体的な疲労ではなく精神的な疲労、どちらかといえば気疲れか。
こういった疲労感は蔑ろにしておくと、仕事にしろ戦闘にしろ精度が落ちる原因となる。早めに回復させておくに越したことはない。
「……1人で眠るのは久し振りだな」
ツバサが床についたのは午前3時前――。
いつもなら同衾や添い寝を求めてくる子供たちも、会議の邪魔をしてはいけないと先に就寝していた。会議中に寝落ちしたミロも言わずもがなだ。
そんなわけで──独り寝は久々だった。
大きなベッドに1人で横たわると寂寥感に悩まされる。
「子供がいなくて寂しいとか、神々の乳母に毒されてるな……」
心中で肥大化の一途をたどる神々の乳母という名の母性本能。自覚しているが、性衝動のように抑えがたく、抗いがたい感情の揺らぎなのだ。
男心が自己嫌悪を覚えながらウトウトとする……。
「――センセイ! おはようございます!」
かと思いきや、可愛らしい娘の声で眠りの静寂を破られた。
ガバッ! と跳ね起きた拍子にバルンバルンと爆乳が暴れたが、最近は胸筋から働きかけることで揺れをいくらか制御できるようになった。
それでも豪快に揺れる爆乳だが――。
声をする方に振り向けば、枕元に笑顔のマリナが立っていた。
さっき寝たばかりと思いきや、日が高々と昇るまで朝寝を決め込んでしまったらしい。チラリと時計を横目にすれば朝の9時45分。
毎朝5時半に起きるのが習慣のツバサにすれば寝過ぎたくらいだ。
「おはよう、マリナ……ちょっとお寝坊さんだったな」
起こさせたことを詫びるように返事をしたツバサは、寝ぼけ眼をこすって気怠げに起き上がる。この怠さは疲れではなく寝起き特有のものだ。
ざっと6時間強は寝たらしい。
あまり褒められた睡眠時間ではないが、神族なら十分だ。況してやツバサは過大能力で天然のエネルギー無限増殖炉を持っているようなものだから、おかげで精神的な疲労感も吹き飛んでいた。
寝ぼけて着崩した寝間着の浴衣を直していると、マリナの雰囲気がいつもと違うことに気付かされた。あちらからアピールしているから尚更だ。
お姫様風のドレスと王冠デザインの帽子はいつも通り。
いや、これはマリナにとっての正装であり戦闘コスチュームだ。
普段着ではないこと、自信満々な笑顔にはフミカのものとよく似た眼鏡をかけていること、フミカの【魔導書】を大事そうに抱えていること。
この三点に違和感を覚えた。
「……どうした、フミカの真似っこか?」
「フフーン、真似っこじゃありません。今日はフミカさんの代わりです!」
そういってマリナは誇らしげに胸を張った。
大胆な成長期を迎えるにはまだ早い。乙女らしい慎ましやかな胸元には、見慣れぬネームプレートが付いていた。書いてあるのは役職名。
秘書――と記されている。
「今日からセンセイの秘書はワタシのお仕事です!」
「……あー、そういえば」
~~~~~~~~~~~~
本日から四神同盟はバッドデッドエンズ対策のため、防衛能力の強化や新戦力を探すための準備などを計画的に推し進めていく。
これに伴い、各陣営のプレイヤーは計画の過程で必要とされる“職能”によっては、4つの国を行き来して計画内容の作業に勤しむ。
中でも工作者であるジン、ダイン、ヨイチは大忙しだ。
各陣営には1人か2人、強固な結界を張れる防御系に長けた者がいる。
そのため“専守防衛”という点では問題ない。
しかし、今回はできる限りのことはやっておきたいので、先制攻撃も視野に入れた“迎撃”や“邀撃”にも力を入れたかった。
結界に触れるとダメージを与える攻性結界や、踏み込んだ者に敵意があれば発動する爆裂魔法陣など、魔法による迎撃システムにも力を入れる。
他にも、機械的な迎撃システムを完成させるつもりだ。
迎撃ドローン、自動砲台、弾道ミサイル……。
敵性物体を感知したら自動で攻撃してくれる迎撃システムの配備について、以前からダインが具申されていたが、これを正式採用する。
しかし、工作系に秀でた者は前述の3人しかおらず、その中でも特化しているのはダインとジンのみ。最新鋭の兵器、配備したそれらを自動化するシステムを造るとなれば、メカにもロボにも強いダインの独壇場である。
掛け値なしで誇れる──ウチの長男は優秀だ。
このためダインはハトホル国に限らず、全陣営の防衛システムを再考して、迎撃能力を高める計画を一任されていた。
今回の計画において、割り振られた仕事量は最大かも知れない。
──そこで内助の功である。
ツバサはフミカに「計画中はダインのサポートを優先しなさい」と命じたのだ。当然、愛妻を自認するフミカは喜んで応じてくれた。
フミカは最近、ツバサの秘書として働く機会が多い。
『秘書がいないと俺の能率が落ちそうだな』
『じゃあ、明日からはウチの見込んだ秘書を配属するッス』
冗談めかしたツバサにフミカも微笑んでいた。
その見込んだ秘書というのが──マリナのことらしい。
「……ま、順当なチョイスだわな」
子供たちの中で秘書が務まる事務能力があるのは、フミカとダインの次に来るのはマリナしかいない。彼女は年の割に聡明なのだ。
他の子供たちもこんなサバイバルな異世界で1年も生き抜いてきたから、大人びた成長を遂げているのだが、まだまだ子供である。おまけに長女はアホ、三女はダメ人間、四女はバカで野生児……秘書以前の問題だった。
次男ヴァトと六女イヒコはどちらも出来た子だ。
だが、中身はまだ普通にお子様なので秘書は無理だろう。
七女ジャジャは見た目こそ7歳の幼女だが、中身は15歳の少年である。
頑張れば秘書も務まりそうだ。
しかし、ジャジャは意識を共有した分身を各地に派遣し、忍者らしく諜報活動をさせている。秘書なんてやらせたらオーバーワークになりかねない。
末っ娘のジョカも中身は起源龍なので、人間の細かい仕事は任せにくい。
やっぱり消去法でマリナになるようだ。
マリナだってまだ10歳、お手伝いが精々だろう。
「わかった、今日からよろしくな秘書さん」
それでも彼女のやる気を尊重して、ツバサは笑顔で迎えた。
「はい、こちらこそです! よろしくお願いしますセンセイ!」
マリナは元気いっぱい挨拶すると、胸に抱いていた【魔導書】を広げてパラパラとめくった。フミカが貸してあげたものだろう。
中身はツバサのスケジュール帳になっているに違いない。
フミカから貰った“アンチョコ”である。
「では秘書としてセンセイの1日のスケジュール管理をしますね。まずは、朝起きてからすること……えーっと、えーっと……」
スケジュール帳な【魔導書】とにらめっこするマリナ。
ツバサは柔らかく制しようとする。
「朝起きたら顔洗って歯磨きだろ、スケジュール通り動くにはまだ……」
「うん、まずは特別室でハトホルミルクの搾乳ですね!」
無邪気な声が突き刺さる。
白眼になって「バフッ!?」と噴き出してしまった。
いや、浴衣からまろびおちそうな爆乳から、毎朝ミルク缶ひとつを満タンにするほどハトホルミルクを搾乳できることは、女性陣にはバレている。だが、こうして改めて口頭で突きつけられると来るものがあった。
意識したためか、爆乳の重さに乳腺の張る痛みまで湧き上がってきた。
目覚めた時はそんなに張った感じがしなかったのだが……?
回復したはずの疲労感とは違う、精神的な頭痛に苛まれる。
「……それ、【魔導書】に書いてあるの?」
ツバサは引きつった顔を片手で隠すと、一生懸命に秘書の仕事を頑張ろうとするマリナの眩しさを直視できず、顔を背けてしまった。
「はい、センセイが起きたら真っ先にやることと書いてあります」
「……そうか、わかった」
あの博覧強記ムスメめ──後で制裁してやる。
しかし、誤魔化しても今更だ。
毎朝の日課なのは事実だし、昨日までは夜通しの会議続きで搾乳のタイミングがズレまくりだから、今朝のミルク貯蓄量はかなり多いと見た。
ため息をついてマリナに申し付ける。
「はぁ……じゃあスケジュール通りに行動するけど、その……搾乳、する部屋へは俺1人で行くから。朝食を済ませるまでは自由にしてていいぞ」
「いえ、それには及びません。ワタシ、デキる秘書ですから」
マリナは伊達眼鏡をクイッと持ち上げた。
どういう意味だろう? とツバサはちょっと疑問に思ったのだが、彼女の後ろにある物が見つけた途端、その意味を思い知らされた。
ツバサ専用の完全防音された搾乳室――にあるはずの搾乳機。
クロコが開発した優れたものの逸品で、乳房、乳首、乳輪の形を変えることなく肌を傷めることもない。なのに搾乳効率は高く、おまけに「これHなオモチャじゃないの!?」ってレベルで声を上げるくらい気持ちよくなれる。
その搾乳機が──マリナの後ろにあった。
しかも使用済みだ。横には溢れそうなミルク缶も見える。
マリナは満面の笑顔を浮かべているが、よく見るとその頬は興奮からかほんのり紅を帯びており、口の周りにはミルクを飲んだ形跡が残っている。
ケプ、と可愛らしいゲップをするマリナ。
そして、小さな鼻からタラリとこぼれる鼻血。
慌ててティッシュで拭うマリナだが、後から後から垂れてくる。
もういい――大体わかった。
だが、マリナは幼稚な敬礼から喜々として説明してくる。
「お疲れのセンセイがちょっとでも長く寝ていれるようにと、寝ている間にワタシがハトホルミルクを搾乳しておきました! 幸い、センセイはぐっすり眠られていたので、ワタシがおっぱいに吸いついても……いえ、寝ながらの搾乳でも気持ちいいのか、あられもない声を上げて……いえいえ! お乳を搾られても目覚める気配がなかったので、起こさないようにこっそり…………ぷぎゅるッ!?」
マリナの小さな顔を鷲掴んだ。
隠し事ができない素直な性分のおかげで手間が省けた。
……いや、洗いざらい吐いてマリナが自爆したせいで、寝ている間に何があったかの子細がわかった分、ツバサの羞恥心が燃え上がるのだが!
寝ながらマリナに授乳されて、彼女が満腹になったら今度は搾乳機で酪農牛よろしく搾乳されて、すっかり眠り込んでいたツバサは快感を受け入れ、眠りこけたまま身悶えると、嬌声のような寝言を上げていたに相違ない。
それを全部マリナに目撃されたわけだ。発狂するくらい恥ずかしい。
道理で朝起きた時に感じる乳房の張りがなくて、すっきりしてるいるわけだ。今気付いたが、股間や太ももの付け根がニチャニチャと湿っている。
……これ、何回かイッてるみたいだ。
愛しい娘の前でどれだけの痴態をさらしたというのか?
「ミロのせいかクロコのせいか……マリナもおませさんになったもんだ」
ツバサは震える声でアイアンクローを締め上げる。
途中、掴む指の形を変えていく。
親指と人差し指で、マリナのプニプニほっぺを挟む込む。
唇を突き出す“タコチュー”の顔にしてやる。
顔を真っ赤にしたツバサは、恥ずかしさに唇を戦慄かせて涙目で凄む。
「……顔が“タコチュー”になるまでこうしててやろうか?」
「むぎゅるぅぅ! ぼ、ぼべんばばいべんべぇーッ!?」
調子に乗りましたー! とマリナが泣きが入るまで頬を大型クリップで留めたみたいに挟んでやった。タコチューでも可愛いだろうと思いながら。
~~~~~~~~~~~~
お昼過ぎ──ハトホル国執務室。
休憩時に寛げ、打ち合わせもできる大型ソファ一式。
その上座にツバサは座っていた。
後ろには「秘書ですから」とマリナが控えている。朝の“タコチュー”がまだ効いているのか、時折ほっぺや唇を気にする仕種をしていた。
左右のソファには──妖人衆とスプリガン族。
その代表者たちが向かい合う形で座っているが、どちらもツバサの方へ顔を向けている。深刻な話を打ち明けられているから片時も聞き逃せないのだろう。どちらのトップも固唾を飲んで、次の言葉を待っている。
ツバサから見て右側にはスプリガン族──。
若き総司令官ダグ・ブリジット。
「滅びを願う神族や魔族がいるなんて、そんな……」
赤と青を基調とした「司令官!」と呼びたくなる軍服に身を固めた青年は、息をするのも忘れて、膝の上に置いた拳をギュッと握り締めた。
「誰もが皆、ツバサ様たちのようにはいかないとはいえ……」
「どうして……そんな悲しいことができるのでしょうか?」
「心にでっかい闇が巣食うちょっとしか思えもはんな」
副司令官ブリカ・ブリジット。
司令官補佐ディア・ブリジット。
防衛総隊長ガンザブロン・ガンファスト。
相変わらず女将軍といった格好のブリカと、以前より軍服のデザインを取り入れているがドレスの淑女といった感じのディア。対照的な双子姉妹だ。
ガンザブロンも警備員らしい軍装が板についてきた。
彼女たちに配給した制服は、服飾師であるホクトとハルカの師弟コンビがそれぞれの個性に合わせてデザインした、“ハルクイン”ブランドだ。
無論、ダグの軍服もである。
まだ高校生くらいの司令官を支えるスプリガン族の幹部たちは、ソファに腰を下ろさず、ダグの後ろに軍人らしい佇まいで立ち尽くしている。
口々に感想をつぶやく彼らの表情もまた、緊張のあまり強張っていた。
ツバサから見て左側には妖人衆──。
彼らが巫女姫と奉るイヨ・ヤマタイ。
そして、政を取り仕切る乙将オリベ・ソウオク。
眷族として神族化した際、ツバサが名前の下に姓を付けるよう勧めた結果、それぞれ思い入れのある名前を付けたのだ。
巫女姫と讃えるに相応しい可憐な装束を身につけた小柄な少女と、涼しげな緑をちりばめた着物を洒落に着込んだチョイ悪親父。
いつも朗らかな2人だが、今日は表情に陰が差している。
「いつの世にも滅びを求める者はいるのですね……」
「姫様、こればっかりは時代ではありません。パッと咲いてパッと散る、それを己のみならず、明日を夢見る者にまで強いる者は常におるものなのです」
イヨは弥生時代、オリベは戦国から江戸時代。
それぞれ大なり小なりではあるが、一国を為政者として治めた経験があり、またいくつもの血で血を洗う戦争に参加した経験がある。
なればこそ、うんざりするに違いない。
平穏を望まず、戦乱を望む愚か者の振る舞いに――。
ツバサに助けられたダグは、同じ出自であるはずの神族や魔族となったプレイヤーが、すべてを滅ぼそうという行動に出たことを受け止めきれないらしい。
目敏いオリベがそこに気付き、アドバイスを送る。
「ダグ殿はお若い。なればこそ、この機会に学ばれると良い。いつの時代にもこの手の輩は現れる。すべてを滅ぼして、自らも滅ぶことを望む者がな……嗚呼、思い返せば、大坂の陣もそうであった……」
オリベは郷愁を帯びた眼差しを虚空に向けた。
「斜陽の豊臣家と、飛ぶ鳥を落とす勢いの徳川家。勝敗も優劣も目に見えているというのに……明日をも知れぬ浪人たちは豊臣家に味方して、徳川を討とうと躍起になったものでしてな……当人たちもわかっておったはずです」
豊臣に与しても勝ち目はない――死ぬだけだ。
「浪人たちもそれは覚悟の上……1人でも多くの徳川勢を道連れにして、あわよくば家康公を討ち取り、諸共に地獄へ堕ちようとしておった……」
人は時として――滅びに悦楽を見出す。
「人間、誰しもが一度や二度は思うことよ。“すべてを無かったことにしたい”とな……その想いを拗らせる者もまた、少なくないのでござるよ」
「オレには……その気持ちがわかりません」
ダグは苦しそうに頭を振った。
オリベは穏やかな表情で慰めの言葉を贈る。
「わからぬならば、それに超したことははないのですぞ。滅びを求める気持ちなぞ抱くものではない。だが、納得できなくとも……理解しなされ」
「そういった人々に狙われているのは事実ですからね……」
苦悩する若者に、イヨも慈しみの言葉を投げ掛ける。
ソファに並んで腰を下ろすイヨとオリベ(勿論、イヨのが上座寄りだ)。孫娘とお爺ちゃんみたいな2人の後ろには、三将が居並んでいる。
彼らはオリベの家臣、妖人衆における幹部ポジションだ。
「あれかー、食い詰めた傾き者の集まりみたいだな」
「傾き者の範疇に収まるか? それこそ厄災その物じゃないか」
妙剣将──ウネメ・マリア
鍛鉄将──オサフネ・ナガミツ
自らも傾き者みたいな女武者な格好しているウネメが毒突き、それを刀匠らしい白地の着物で正装したオサフネが疑問を呈しながら正す。
この2人も生まれた時代に即した格好だが、どちらも“ハルクイン”製の衣装だ。確か、オリベもデザイナーとして参加しているとか……。
「――ツバサ様、よろしいですか?」
聞き惚れそうなボーイソプラノで尋ねられる。
それがケハヤのようにむくつけき大男から発せられると、誰もが一瞬ギョッとするものだが、さすがにこの場にいる者は驚きも笑いもしない。
すっかり馴れてしまったのだ。
覇脚将――ケハヤ・タギマ
野人と呼びたくなる頃の野性味は残っているが、精悍な巨漢となったケハヤは、江戸時代の“奴さん”みたいな衣装を着込んでいた。
手を上げて質問するケハヤに「どうぞ」と促す。
折り目正しく会釈をしてからケハヤは口を開く。
オリベが「三将もちゃんと躾けてますぞ」と威張る成果だ。
「……その、ばっどでっどえんずという輩どもが大挙して、このハトホル国へ攻め入ってきた場合、俺たちも迎え撃つべきですか? それとも……」
「それとも、の方です。今回ばかりは我慢してください」
戦わず逃げろ、とツバサは婉曲に言い渡した。
「襲ってくる者たちは程度の差こそあれ、LVは999を超えている。いくら神族化したケハヤさんたちでも荷が重すぎる……先日攻めてきた穂村組、その1人であるマリさんがLV980程度でした。つまり……」
「なるほど――それは勝てん」
ケハヤは悔しげに唇を緩ませた。
マリ1人にケハヤたち三将は総掛かりでも勝てなかった。
マリが(というより穂村組が)本気の殺し合いにしなかったため、手合わせ程度の小競り合いで終わったが、ケハヤたちは鼻であしらわれたのだ。
「わかった、出過ぎた真似はしないと約束します」
「……ええ、お願いします」
素直に引き下がるケハヤだが、こちらは素直に受け取れない。
隣ではウネメも乳房の下で腕を組み、「うんうん」と同意しているが、こっちも信じる気にはなれなかった。
ケハヤやウネメは天性の戦士だ。
ツバサやドンカイにセイメイといった面子もそうだが、強敵を前にすると「勝てない!」と肌で感じても、戦士の本能が「戦りてえ!」と騒ぎ、負け戦になるとわかっていても、身体が勝手に動いてしまうのだ。
どうしょうもない人種である。
それは守護者な彼らも同じようで――。
「ではツバサ様、どうしてオレたちを招集されたんですか?」
ダグは呼び出された理由を訊いてくる。
それこそ本題だ。ツバサは座り直してから話を切り出した。
「呼んだのは他でもない。最悪にして絶死をもたらす終焉との悶着が片付くまで、防衛に携わる君たちの仕事内容をいくつか改編したいんだ」
まずはスプリガン族――。
「防衛面での警戒レベルは最大に引き上げる」
蕃神に加えて、LV999の集団が来るかもしれないという想定の下、明確な敵意を持って接近する正体不明の神族や魔族がいたら、決して接触しないことを約束させる。見つけた瞬間、即時撤退することもだ。
応戦など以ての外である。
発見次第、ツバサたちへの緊急連絡を徹底させるのも忘れない。
「メンヒル型高速艦での遠征も控えてくれ。今まで襲われなかったからといって、今後も襲われないとは限らないからな」
世界樹の跡地への見回り、未だ荒野を彷徨う種族の保護、拠点を持たずに旅をするプレイヤーの捜索、その他etc……。
こういった仕事も当面お預けだ。
「しばらく結界内の哨戒任務のみに徹底してくれ。俺たちも結界の強度を極限まで高めておくから、おいそれとは破られないはずだ。敵影を見たら、すぐに引き返すこと。足止めとか絶対に考えちゃダメだ、いいな?」
スプリガンたちの眼を見据え、言い聞かせておく。
彼らは生粋の守護者――我が身を呈して大切なものを守ろうとする。
なので、厳しく命じておく必要があった。
さもなくば、いつぞやのガンザブロンみたいに「自爆上等!」と特攻をしかねない者ばかりだ。そんなことされたらツバサは心労で倒れてしまう。
だから「命を粗末にするな!」と厳命する。
「いいですか、ガンザブロンさんなんて前科持ちなんですからね? みんなのためにも、決して早まった行動はしないでくださいよ?」
「面目なか……穴があったや入ろごたっじゃ」
ツバサが念を押すと、ガンザブロンは肩身が狭そうだった。
ブリカやディア、そしてダグも苦笑する。
かつて蕃神との戦いでダグや娘たちを守るため、自爆特攻を仕掛けたガンザブロンを目の当たりにしているので、どうしても苦いものが走るらしい。
ダグは表情を引き締め、ツバサに進言する。
「わかりましたツバサ様、ハトホル国のみんなを守るのと同じように、自分たちの身も守ると約束します。守護者としての使命を果たすために……」
ツバサは安堵の微笑みで頷き返した。
「妖人衆が呼ばれたのも、やはり国防に関する指示ですかな?」
オリベは察しのついた顔で尋ねてくる。
乙将などと自己評価の低い彼だが、立派な武将である。
ツバサの頼みも把握しているはずだ。
「ええ、妖人衆の皆さんはオリベさんや三将の元、警備兵を務めている者が多い。万が一、LV999が国内にまで侵入してきた場合、彼らにも応戦させず、住民の避難と自分の安全を優先するように指導してください」
彼らは自警団であり、警察官も兼ねている。
妖人衆は身体能力に優れた者が多く、場合によっては魔術に近い特殊能力を備えているので、蕃神の眷族くらいならば相手をできる者もいる。
しかし、最悪にして絶死をもたらす終焉は別だ。
間違っても手を出すな――と命じておく。
「それと、国内の警備兵として戦える地力を持った者を新たに選抜し、ウネメさんやケハヤさんが鍛えてやってください」
先日、新たに加わったナンディン族とヴァラハ族。
神の牛と神の猪の末裔である彼らは、神族の血を引いているだけあって他の種族より膂力に恵まれている。鍛えれば優秀な戦士となるはずだ。
「警備兵を増やせば、彼らに配給する武具や防具も入り用となる。これはオサフネさんたち鍛冶職人たちに増産に励んでもらいたい」
「はっ、承知いたしました」
オサフネは一も二もなく引き受けてくれた。
こういう時、オサフネは私見めいたことを口にしない。短い言葉できっちり返事のみを返してくる。やはり根が真面目なのだ。
すると、ウネメが手を上げて確認を求めてくる。
「住民を避難誘導するための手勢を増やしたい、ってことっすか?」
「それもありますけど……この機に乗じて、蕃神が攻め込んでこないとも限らない。それに、連中の中には大量の使い魔を操る者もいるそうです」
国内でツバサたちがバッドデッドエンズとの戦闘に入った場合、そういった雑兵の始末にまで手が回らない。
その雑兵の始末を、ウネメたちに頼みたいのだ。
「どちらが嗾けてくる雑魚にしても、優に数万を超えるはず……そのためにも警備兵が多いに越したことはない。これもまた戦いといえば戦いだ。皆さんには守るための戦いに専念してもらいたい……」
お願いできますか? とツバサはウネメたちの眼を覗き込んだ。
ウネメは気丈に鼻で笑い、ケハヤは目を閉じて頷いた。
「オリベの大将じゃないけどさ、王様として命じてくださいよツバサ様。アンタは俺たちの総大将、お願いってのはこそばゆいぜ」
「ウネメに同感だ……命令として引き受けましょう」
2人の返事にツバサはキョトンとしたが、オリベに「一本取られましたな」と歯を剥いた笑顔を向けられ、妙に納得してしまった。
今のやり取りは――散々オリベに叱られてきたことだ。
どうもツバサは、まだ“ハトホル国の女王”という実感がない。
だから、年上のオリベたちには敬語で話しかけてしまうし、ダグやガンザブロンにも同僚みたいな言葉遣いで接してしまう。
「――我らが神王様はお優しい」
オリベはチョビ髭をつまんで整える。
その仕草のまま、戯けた調子ながら敬うような言葉を続けた。
「猛悪なる破滅主義者の軍団は自分たちが全身全霊を賭して食い止めるから、家臣であるおまえたちは民草を守り、我が身を守ることに専念しろと仰る……普通は逆ですぞ。我らが盾となり、神王たるツバサ様を守るものです」
「いや、しかし……」
「――なればこそ!」
オリベたちを矢面に立たせるわけにはいかない、と説明しようとして言い淀むツバサを、オリベの力強い一喝が遮った。
「それがしたちは――あなたについていきたいのです」
一瞬、言葉の意味は理解できなかった。
見渡せば、誰もがオリベと似たような微笑みを浮かべている。敬意、尊敬、思慕、信頼、忠義……温かくも熱いものを感じる。
呆然とするツバサに、イヨが微笑みかけてきた。
「わたしたちはツバサ様の優しさに救われ、助けられ、守られてきました。今度もまた、わたしたちのことを第一に慮ってくださっております……あなたの想いは、ちゃんとわたしたちに伝わっておりますよ」
大丈夫――心配しないで。
「みんな、ツバサ様が悲しむようなことはいたしません。だから、もっとしっかり命じてあげてくださいませ……この国の主人らしく、ね?」
怖がる孫をなだめる祖母のような声。
知らず知らずのうちにまとわりついていた不安がいっぺんに吹き飛んだような気分にさせられた。不覚にも涙腺まで熱くなってくる。
ツバサは目頭を押さえて、流れそうになる涙を抑え込む。
「王様ってのは……未だに馴れないんですけどね」
震える声で減らず口を叩くのが精一杯のツバサだった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
562
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる