2 / 4
の
しおりを挟む
中学二年の時、私は失恋した。
告白する前に、私の恋は実らないことに気付いて、失恋した。
「水元さんってさ、ハルカちゃんと仲良いよね?」
その一言で、この男子は私に何を求めているのかが分かった。
ちょっとだけ私も思い上がっていた。クラスメイトの、サッカー部の男子。焼けた肌と白い歯のコントラストが素敵で、私よりもちょこっとだけ高い背丈が、好きだった。優しくて、隣の席になったときからちょくちょく話していた。
他愛もない話。担任の癖とか、明日の天気とか、宿題の難易度とか、そういう。
はじめて男子を異性として見ていた。恋愛ドラマが流行していたこともあるけれど、それなりに恋をしていた。
手を繋いだら、とか。
デートに行ったら、とか。
キス、したら、とか。
そんな妄想をしては、ドキドキさせていた。勝手に頬は熱くなるし、その人と話す度にちょっと声が上ずったりするし、苦しくも楽しいそんな一時を過ごしていた。
けれど、「ハルカちゃんと仲良いよね?」っていう言葉で恋心はがらがらと崩れ去った。そのに彼の本当の気持ちが隠されていたのだ。
ハルカと仲良くなるための、私だった。
私は、ハルカの踏み台だった。
私がハルカのオマケだって気が付いて――本当はとっくの昔に気が付いていたのだけれど、第三者からそういう風に扱われて、初めて自分の立場に気が付いた。
承認欲求と自意識の塊の私は、完璧な女の子の金魚の糞だったのだ。
「ウタちゃん、どうしたの?」
そう。こうやってハルカは私に毒を与えるのだ。
私が一人で泣いていると、ハルカはどこからともなく現れて、私を慰める。
確かあれは体育館の裏。移動教室の途中。
着替えている途中に急に泣きたくなって、暗くてジメジメした体育館の裏側で、しゃっくりを上げていた。
失恋と、カーストと、己の醜さがぐちゃぐちゃになって思春期の頭を覆い尽くした。私は誰からも認められないし、誰からも愛されないのだ。
そう考えれば考えられるほど、涙が溢れた。もうこれは止められないのだ。
そんなときに女神は現れる。
他の人にはお腹が痛いから保健室に行くと言っておいたのに。ハルカだけは私の後を追ってきたようだった。
「大丈夫だよ。誰にも言わないし、ウタちゃんが何も言いたくないなら、わたしも戻る」
縮こまって泣いている私の背中を優しくさすりながら、ハルカは歌うような声で囁く。
「私、怖いの」
「怖い?」
「怖い。これからどうなっちゃうのか怖い。高校も、どこ行けばいいのかわからないし、多分彼氏とかも出来ないし、お母さん怖いし、バカだし、怖い」
ぽろぽろ零れた声は全部本音だった。ゴッチャゴチャの感情が、脳の中で乱雑に積み上げられて取り留めも無い言葉になって、全部そのままハルカの前で零してしまった。
意味、わかんないだろうな。
私のグチャグチャを聞いたハルカは優しく背中をさすり続けていた。
「大丈夫。全部大丈夫だよ」
何が大丈夫なのだろうか。わからない。でも、ハルカは心の底から「大丈夫」だと言っているのだろうということはわかった。
「わたしがいるからね。ウタちゃん」
ああ、私にはハルカがいるんだ。
ハルカが親の代わりに、彼氏の代わりに、友達の代わりにたっぷりと愛を注いでくれるのだ。
私は涙と鼻水でまみれた顔面を擦りながら、ハルカを見た。にっこりと微笑みを浮かべている。お母さんが優しかったらこんな感じなんだろうな。
「わたしはウタちゃん、大好きだから」
大好き。
その言葉で脳がとろけた。
ぐちゃぐちゃの感情がほろほろにほどけ、もう悩んでいたのがバカらしくなった。
涙もひっこんで、小さいしゃっくりだけが残った。ハルカはそんな私を見て、にっこり笑った。安心させる笑顔に、私も釣られて口の端っこを上げた。
「ねえ、大人になったら一緒に暮らそうよ。そこで、わたしとウタちゃんだけのお城を作ろうよ」
完璧な女の子に与えられた完璧になる権利。私はそれに食いついた。
「うん、一緒に暮らす」
私は嗚咽を零しながら何度も頷いた。頷きながら、震えた。
私とハルカで、二人だけ。その世界のなんと素晴らしいことか!
「ウタちゃん、約束。絶対わたしと一緒にいてね」
ハルカが私の名前を呼ぶ度に、ここにいていいんだって思えた。ハルカが私を大好きなように、私もハルカが大好きだった。
告白する前に、私の恋は実らないことに気付いて、失恋した。
「水元さんってさ、ハルカちゃんと仲良いよね?」
その一言で、この男子は私に何を求めているのかが分かった。
ちょっとだけ私も思い上がっていた。クラスメイトの、サッカー部の男子。焼けた肌と白い歯のコントラストが素敵で、私よりもちょこっとだけ高い背丈が、好きだった。優しくて、隣の席になったときからちょくちょく話していた。
他愛もない話。担任の癖とか、明日の天気とか、宿題の難易度とか、そういう。
はじめて男子を異性として見ていた。恋愛ドラマが流行していたこともあるけれど、それなりに恋をしていた。
手を繋いだら、とか。
デートに行ったら、とか。
キス、したら、とか。
そんな妄想をしては、ドキドキさせていた。勝手に頬は熱くなるし、その人と話す度にちょっと声が上ずったりするし、苦しくも楽しいそんな一時を過ごしていた。
けれど、「ハルカちゃんと仲良いよね?」っていう言葉で恋心はがらがらと崩れ去った。そのに彼の本当の気持ちが隠されていたのだ。
ハルカと仲良くなるための、私だった。
私は、ハルカの踏み台だった。
私がハルカのオマケだって気が付いて――本当はとっくの昔に気が付いていたのだけれど、第三者からそういう風に扱われて、初めて自分の立場に気が付いた。
承認欲求と自意識の塊の私は、完璧な女の子の金魚の糞だったのだ。
「ウタちゃん、どうしたの?」
そう。こうやってハルカは私に毒を与えるのだ。
私が一人で泣いていると、ハルカはどこからともなく現れて、私を慰める。
確かあれは体育館の裏。移動教室の途中。
着替えている途中に急に泣きたくなって、暗くてジメジメした体育館の裏側で、しゃっくりを上げていた。
失恋と、カーストと、己の醜さがぐちゃぐちゃになって思春期の頭を覆い尽くした。私は誰からも認められないし、誰からも愛されないのだ。
そう考えれば考えられるほど、涙が溢れた。もうこれは止められないのだ。
そんなときに女神は現れる。
他の人にはお腹が痛いから保健室に行くと言っておいたのに。ハルカだけは私の後を追ってきたようだった。
「大丈夫だよ。誰にも言わないし、ウタちゃんが何も言いたくないなら、わたしも戻る」
縮こまって泣いている私の背中を優しくさすりながら、ハルカは歌うような声で囁く。
「私、怖いの」
「怖い?」
「怖い。これからどうなっちゃうのか怖い。高校も、どこ行けばいいのかわからないし、多分彼氏とかも出来ないし、お母さん怖いし、バカだし、怖い」
ぽろぽろ零れた声は全部本音だった。ゴッチャゴチャの感情が、脳の中で乱雑に積み上げられて取り留めも無い言葉になって、全部そのままハルカの前で零してしまった。
意味、わかんないだろうな。
私のグチャグチャを聞いたハルカは優しく背中をさすり続けていた。
「大丈夫。全部大丈夫だよ」
何が大丈夫なのだろうか。わからない。でも、ハルカは心の底から「大丈夫」だと言っているのだろうということはわかった。
「わたしがいるからね。ウタちゃん」
ああ、私にはハルカがいるんだ。
ハルカが親の代わりに、彼氏の代わりに、友達の代わりにたっぷりと愛を注いでくれるのだ。
私は涙と鼻水でまみれた顔面を擦りながら、ハルカを見た。にっこりと微笑みを浮かべている。お母さんが優しかったらこんな感じなんだろうな。
「わたしはウタちゃん、大好きだから」
大好き。
その言葉で脳がとろけた。
ぐちゃぐちゃの感情がほろほろにほどけ、もう悩んでいたのがバカらしくなった。
涙もひっこんで、小さいしゃっくりだけが残った。ハルカはそんな私を見て、にっこり笑った。安心させる笑顔に、私も釣られて口の端っこを上げた。
「ねえ、大人になったら一緒に暮らそうよ。そこで、わたしとウタちゃんだけのお城を作ろうよ」
完璧な女の子に与えられた完璧になる権利。私はそれに食いついた。
「うん、一緒に暮らす」
私は嗚咽を零しながら何度も頷いた。頷きながら、震えた。
私とハルカで、二人だけ。その世界のなんと素晴らしいことか!
「ウタちゃん、約束。絶対わたしと一緒にいてね」
ハルカが私の名前を呼ぶ度に、ここにいていいんだって思えた。ハルカが私を大好きなように、私もハルカが大好きだった。
0
あなたにおすすめの小説
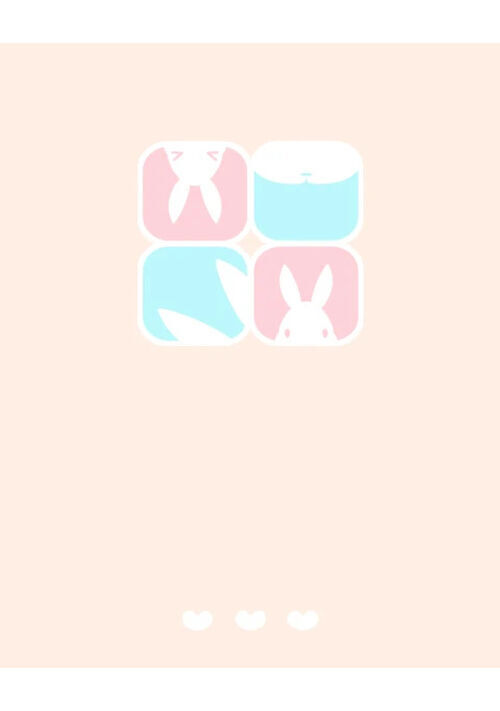
私が彼から離れた七つの理由・完結
まほりろ
恋愛
私とコニーの両親は仲良しで、コニーとは赤ちゃんの時から縁。
初めて読んだ絵本も、初めて乗った馬も、初めてお絵描きを習った先生も、初めてピアノを習った先生も、一緒。
コニーは一番のお友達で、大人になっても一緒だと思っていた。
だけど学園に入学してからコニーの様子がおかしくて……。
※初恋、失恋、ライバル、片思い、切ない、自分磨きの旅、地味→美少女、上位互換ゲット、ざまぁ。
※無断転載を禁止します。
※朗読動画の無断配信も禁止します。
※他サイトにも投稿しています。
※表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2022-九頭竜坂まほろん」
※小説家になろうで2022年11月19日昼日間ランキング総合7位まで上がった作品です!

行き場を失った恋の終わらせ方
当麻月菜
恋愛
「君との婚約を白紙に戻してほしい」
自分の全てだったアイザックから別れを切り出されたエステルは、どうしてもこの恋を終わらすことができなかった。
避け続ける彼を求めて、復縁を願って、あの日聞けなかった答えを得るために、エステルは王城の夜会に出席する。
しかしやっと再会できた、そこには見たくない現実が待っていて……
恋の終わりを見届ける貴族青年と、行き場を失った恋の中をさ迷う令嬢の終わりと始まりの物語。
※他のサイトにも重複投稿しています。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

9時から5時まで悪役令嬢
西野和歌
恋愛
「お前は動くとロクな事をしない、だからお前は悪役令嬢なのだ」
婚約者である第二王子リカルド殿下にそう言われた私は決意した。
ならば私は願い通りに動くのをやめよう。
学園に登校した朝九時から下校の夕方五時まで
昼休憩の一時間を除いて私は椅子から動く事を一切禁止した。
さあ望むとおりにして差し上げました。あとは王子の自由です。
どうぞ自らがヒロインだと名乗る彼女たちと仲良くして下さい。
卒業パーティーもご自身でおっしゃった通りに、彼女たちから選ぶといいですよ?
なのにどうして私を部屋から出そうとするんですか?
嫌です、私は初めて自分のためだけの自由の時間を手に入れたんです。
今まで通り、全てあなたの願い通りなのに何が不満なのか私は知りません。
冷めた伯爵令嬢と逆襲された王子の話。
☆別サイトにも掲載しています。
※感想より続編リクエストがありましたので、突貫工事並みですが、留学編を追加しました。
これにて完結です。沢山の皆さまに感謝致します。

15年目のホンネ ~今も愛していると言えますか?~
深冬 芽以
恋愛
交際2年、結婚15年の柚葉《ゆずは》と和輝《かずき》。
2人の子供に恵まれて、どこにでもある普通の家族の普通の毎日を過ごしていた。
愚痴は言い切れないほどあるけれど、それなりに幸せ……のはずだった。
「その時計、気に入ってるのね」
「ああ、初ボーナスで買ったから思い出深くて」
『お揃いで』ね?
夫は知らない。
私が知っていることを。
結婚指輪はしないのに、その時計はつけるのね?
私の名前は呼ばないのに、あの女の名前は呼ぶのね?
今も私を好きですか?
後悔していませんか?
私は今もあなたが好きです。
だから、ずっと、後悔しているの……。
妻になり、強くなった。
母になり、逞しくなった。
だけど、傷つかないわけじゃない。


悪意には悪意で
12時のトキノカネ
恋愛
私の不幸はあの女の所為?今まで穏やかだった日常。それを壊す自称ヒロイン女。そしてそのいかれた女に悪役令嬢に指定されたミリ。ありがちな悪役令嬢ものです。
私を悪意を持って貶めようとするならば、私もあなたに同じ悪意を向けましょう。
ぶち切れ気味の公爵令嬢の一幕です。

届かぬ温もり
HARUKA
恋愛
夫には忘れられない人がいた。それを知りながら、私は彼のそばにいたかった。愛することで自分を捨て、夫の隣にいることを選んだ私。だけど、その恋に答えはなかった。すべてを失いかけた私が選んだのは、彼から離れ、自分自身の人生を取り戻す道だった·····
◆◇◆◇◆◇◆
読んでくださり感謝いたします。
すべてフィクションです。不快に思われた方は読むのを止めて下さい。
ゆっくり更新していきます。
誤字脱字も見つけ次第直していきます。
よろしくお願いします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















