10 / 50
第1章
第10話
しおりを挟む
まぶたの裏に、淡い光が差し込んできた。
アスカはゆっくりと目を開ける。
まだどこか夢のなかにいるような心地で、しばし天井を見つめた。
──あれ。
見慣れない天蓋。柔らかな寝具。綿の香り。
それらが、徐々に現実を引き戻す。
次の瞬間、はっとして上体を起こした。
「……っ」
ここがどこなのかを思い出し、アスカは急に胸の鼓動が早まるのを感じた。
そうだ、昨夜、あのまま……殿下の寝殿で──。
頬がじわりと熱を帯びてゆく。
そんなところで気安く眠ってしまっていた自分が信じられず、思わず布団をきゅっと握りしめた。
「わ、私……っ、なんてことを……!」
昨夜の記憶が、途切れ途切れに蘇る。
寒さに震えていた自分に、リオールがそっと手を差し出してくれて。
そして、眠るまで傍にいると仰ってくださった。
アスカはそっと横を見やる。
そこには、変わらず穏やかな寝息を立てるリオールの姿があった。
椅子に凭れたまま、少し身を傾けて眠っている。
その顔には疲労の色が滲んでいて、胸がきゅうっと痛んだ。
──本当に、ずっと……。
アスカはそっと布団を押しのけ、なるべく音を立てぬように体を動かしたのだが、その気配に気づいたのか、リオールがふいにまぶたを開いた。
「……もう起きたのか」
掠れた、けれどどこか安心したような声だった。
「あっ……も、申し訳ございません……っ、起こしてしまって……!」
慌てて頭を下げたアスカに、リオールはゆっくり首を横に振る。
「構わぬ。……そなたがよく眠れたのなら、それでいい」
その穏やかな声音に、胸の奥がじんわりと熱くなる。
アスカは俯いたまま、小さく呟いた。
「……殿下こそ、お身体を冷やしてしまったのでは……? 私のために……」
「それは、私が望んだことだ。謝ることではない」
変わらぬ口調。
けれど、そこに込められた優しさに、アスカの胸がふわりと揺れた。
「……ありがとうございます」
そう零れた言葉に、リオールは柔く微笑んだ。
リオールは執務があるらしく、名残惜しくも朝はあっさりと別れることになった。
アスカは薄氷と従者に付き添われ、仮住まいの宮へと戻る。
「薄氷さん」
「はい」
歩みながら、アスカは薄氷に声をかけた。
「貴方のおかげで、殿下とよく話すことができました。ありがとうございます」
「いえ、それは全てアスカ様の努力の賜物です」
「そんな……。貴方がいなければ、今も私は一人、燻っていただけでしたよ」
一人では、決して踏み出せなかった。
薄氷が優しく背中を押してくれなければ、何も始まらなかったに違いない。
「ありがとうございます」
「……では、そのお言葉、有難く頂戴いたしましょう」
立ち止まり、深々と頭を下げる薄氷に、アスカは自然と表情をほころばせた。
これからも、ずっとそばで見守っていてほしい。心からそう思う。
宮に戻ると、そこには清夏がいた。
相変わらず愛想はないが、それでも「おはようございます」と形式的な挨拶を欠かさないのが、彼女らしかった。
朝食が用意され、アスカはいつものように席につく。
だが今朝は、これまでと少しだけ違っていた。
口にした食事を、心から「美味しい」と思えたのだ。
これまでは、誰かに見張られているようで、味わう余裕すらなかった。
けれど、リオールと語らい、胸のつかえが少しほどけた今は、心の軽さとともに、食事の味もしっかりと感じられる。
「アスカ様」
「はい」
清夏の声に顔を上げると、彼女は淡々と告げた。
「昨日、ヴェルデ様の任が解かれました。つきましては、次の指導者が決まるまで、少々お時間をいただくことになります」
「あ……はい」
「何かご希望はございますか?」
問われても、誰がどんな人物かもわからない。アスカは困ったように、苦笑を浮かべた。
「お任せします。私には、どなたが適任か……まだわかりません」
「かしこまりました。それでは、そのように」
まだまだ、知らないことばかりだ。
早く、この王宮のことを理解しなければいけないのに──。
「清夏さん」
「はい」
「……私に、王宮のことを教えていただけませんか」
「……」
清夏は僅かに眉を動かし、アスカをまっすぐに見つめた。
その視線は、どこか品定めするようで、居心地の悪さが肩をすくませる。
それでも、アスカは視線を逸らさなかった。
「──承知しました」
「ぁ、ありがとうございます」
アスカはそっと胸をなで下ろした。
清夏は、食事を終え後片付けの済んだアスカの前に、一枚の簡略図を差し出した。
墨の線が丁寧に引かれたそれは、王宮の構造を示す地図だった。
「こちらが政務宮。国王陛下をはじめ、大臣方や文官たちが執務にあたる場所です。殿下も、通常はこちらでお務めをされています」
「……すごく、広いですね」
「はい。そしてこちらが後宮──かつては多くの方が生活をされていましたが、今はほとんど使われていません」
アスカは小さく首を傾けた。
「使われていない、とは……?」
「殿下がお生まれになり、殿下のお母上様が王宮を去られてから、国王陛下は新たな后を娶っておられません。殿下が実質的な後継者として定められているのは、そのためでもあります」
静かに告げられた言葉に、アスカは視線を落とした。
リオールがひとり、静かな部屋で執務をしている姿がふと脳裏に浮かぶ。
「……あの、殿下の宮はこちら、ですよね?」
アスカが地図の一角を指差すと、清夏は頷いた。
「はい。王宮の東寄り、やや離れた場所にございます。こうして離れた場所にあるのは、殿下ご自身の意思でもあり──陛下との距離が、そのまま物理的にも現れていると見る者もいるようです」
清夏は一瞬、目を伏せて、どこか悲しげな表情で言葉を続ける。
「──あのお方ほど、王宮に在りながら孤独な方を、私は知りません」
しかし淡々と言い切る清夏の言葉に、アスカは身じろぎした。
「……王宮には、見えないものが多すぎます」
「それが王宮です。見えるものだけで判断しては、命を落とします。噂も、人も、行動も──すべてに気をつけなければなりません」
その口調には、まるで何かを見てきたような確信があった。
「……では、私はどうすればいいんでしょう。何を信じて、どう動けば……」
「それを探すのは、アスカ様のお役目です」
「……」
アスカは言葉を失った。けれど、逃げる気にはなれなかった。
「どなたを守りたいのでしょう。どなたと共に生きたいですか? それを念頭に、賢く生きなければ未来は明るくはないでしょう」
清夏の言葉に思い浮かぶのは、大切な家族と、リオールだ。
深く息を吐き目を閉じたアスカは、再びゆっくりと目を開ける。
「……教えてくださって、ありがとうございます。今日から、できることをひとつずつ覚えます」
「その覚悟があれば、きっと道は開けます」
清夏は、ほんのわずかに口の端を動かした。
それは、彼女なりの微笑だったのかもしれない。
優しく丁寧に教えてくれた清夏。
アスカの中で、彼女の印象が少し変わった。
「清夏さんは、私のことがお嫌いですよね」
「……」
「それなのに、こうして優しく教えてくださったこと、感謝します」
アスカが感謝を伝えると、清夏は黙り込み、しばし考えたのちに口を開いた。
「……私には、アスカ様が何を仰っているのかわかりません」
「えっと……」
「私は貴方様に『嫌いだ』とお伝えしたことがありましたか。それであれば申し訳ございません。記憶にございません」
小さく頭を下げる清夏の姿に、アスカは驚き、慌てて否定した。
「そう言われたことはありません! ただ、そうなのだろうと思って」
「……アスカ様は誤解されています。私は貴方様を嫌ってなどおりません」
「でも……」
「私の顔つきが固いせいで、そう思わせてしまったのかもしれません。──これは、私がここで生き残るために身に付けたものです」
清夏にも、語りたくない事情があるのだろう。
アスカはそれを察し、そっと視線を床に落とした。
「決して、嫌いではありません。むしろ私は、アスカ様のお力になりたいと思っておりますよ」
「!」
うそだ、と否定しかけたが、寸前で言葉を飲み込む。
「本心です。あの孤独な皇太子殿下のお心の支えになっておられる。私は、殿下が幼い頃よりここにおります。あの方には幸せになって頂きたい。──そのためには、貴方様が必要不可欠だと思っております」
清夏と視線が交わる。
その瞳の奥に、強い意志が宿っている──アスカは、そう初めて感じたのだった。
アスカはゆっくりと目を開ける。
まだどこか夢のなかにいるような心地で、しばし天井を見つめた。
──あれ。
見慣れない天蓋。柔らかな寝具。綿の香り。
それらが、徐々に現実を引き戻す。
次の瞬間、はっとして上体を起こした。
「……っ」
ここがどこなのかを思い出し、アスカは急に胸の鼓動が早まるのを感じた。
そうだ、昨夜、あのまま……殿下の寝殿で──。
頬がじわりと熱を帯びてゆく。
そんなところで気安く眠ってしまっていた自分が信じられず、思わず布団をきゅっと握りしめた。
「わ、私……っ、なんてことを……!」
昨夜の記憶が、途切れ途切れに蘇る。
寒さに震えていた自分に、リオールがそっと手を差し出してくれて。
そして、眠るまで傍にいると仰ってくださった。
アスカはそっと横を見やる。
そこには、変わらず穏やかな寝息を立てるリオールの姿があった。
椅子に凭れたまま、少し身を傾けて眠っている。
その顔には疲労の色が滲んでいて、胸がきゅうっと痛んだ。
──本当に、ずっと……。
アスカはそっと布団を押しのけ、なるべく音を立てぬように体を動かしたのだが、その気配に気づいたのか、リオールがふいにまぶたを開いた。
「……もう起きたのか」
掠れた、けれどどこか安心したような声だった。
「あっ……も、申し訳ございません……っ、起こしてしまって……!」
慌てて頭を下げたアスカに、リオールはゆっくり首を横に振る。
「構わぬ。……そなたがよく眠れたのなら、それでいい」
その穏やかな声音に、胸の奥がじんわりと熱くなる。
アスカは俯いたまま、小さく呟いた。
「……殿下こそ、お身体を冷やしてしまったのでは……? 私のために……」
「それは、私が望んだことだ。謝ることではない」
変わらぬ口調。
けれど、そこに込められた優しさに、アスカの胸がふわりと揺れた。
「……ありがとうございます」
そう零れた言葉に、リオールは柔く微笑んだ。
リオールは執務があるらしく、名残惜しくも朝はあっさりと別れることになった。
アスカは薄氷と従者に付き添われ、仮住まいの宮へと戻る。
「薄氷さん」
「はい」
歩みながら、アスカは薄氷に声をかけた。
「貴方のおかげで、殿下とよく話すことができました。ありがとうございます」
「いえ、それは全てアスカ様の努力の賜物です」
「そんな……。貴方がいなければ、今も私は一人、燻っていただけでしたよ」
一人では、決して踏み出せなかった。
薄氷が優しく背中を押してくれなければ、何も始まらなかったに違いない。
「ありがとうございます」
「……では、そのお言葉、有難く頂戴いたしましょう」
立ち止まり、深々と頭を下げる薄氷に、アスカは自然と表情をほころばせた。
これからも、ずっとそばで見守っていてほしい。心からそう思う。
宮に戻ると、そこには清夏がいた。
相変わらず愛想はないが、それでも「おはようございます」と形式的な挨拶を欠かさないのが、彼女らしかった。
朝食が用意され、アスカはいつものように席につく。
だが今朝は、これまでと少しだけ違っていた。
口にした食事を、心から「美味しい」と思えたのだ。
これまでは、誰かに見張られているようで、味わう余裕すらなかった。
けれど、リオールと語らい、胸のつかえが少しほどけた今は、心の軽さとともに、食事の味もしっかりと感じられる。
「アスカ様」
「はい」
清夏の声に顔を上げると、彼女は淡々と告げた。
「昨日、ヴェルデ様の任が解かれました。つきましては、次の指導者が決まるまで、少々お時間をいただくことになります」
「あ……はい」
「何かご希望はございますか?」
問われても、誰がどんな人物かもわからない。アスカは困ったように、苦笑を浮かべた。
「お任せします。私には、どなたが適任か……まだわかりません」
「かしこまりました。それでは、そのように」
まだまだ、知らないことばかりだ。
早く、この王宮のことを理解しなければいけないのに──。
「清夏さん」
「はい」
「……私に、王宮のことを教えていただけませんか」
「……」
清夏は僅かに眉を動かし、アスカをまっすぐに見つめた。
その視線は、どこか品定めするようで、居心地の悪さが肩をすくませる。
それでも、アスカは視線を逸らさなかった。
「──承知しました」
「ぁ、ありがとうございます」
アスカはそっと胸をなで下ろした。
清夏は、食事を終え後片付けの済んだアスカの前に、一枚の簡略図を差し出した。
墨の線が丁寧に引かれたそれは、王宮の構造を示す地図だった。
「こちらが政務宮。国王陛下をはじめ、大臣方や文官たちが執務にあたる場所です。殿下も、通常はこちらでお務めをされています」
「……すごく、広いですね」
「はい。そしてこちらが後宮──かつては多くの方が生活をされていましたが、今はほとんど使われていません」
アスカは小さく首を傾けた。
「使われていない、とは……?」
「殿下がお生まれになり、殿下のお母上様が王宮を去られてから、国王陛下は新たな后を娶っておられません。殿下が実質的な後継者として定められているのは、そのためでもあります」
静かに告げられた言葉に、アスカは視線を落とした。
リオールがひとり、静かな部屋で執務をしている姿がふと脳裏に浮かぶ。
「……あの、殿下の宮はこちら、ですよね?」
アスカが地図の一角を指差すと、清夏は頷いた。
「はい。王宮の東寄り、やや離れた場所にございます。こうして離れた場所にあるのは、殿下ご自身の意思でもあり──陛下との距離が、そのまま物理的にも現れていると見る者もいるようです」
清夏は一瞬、目を伏せて、どこか悲しげな表情で言葉を続ける。
「──あのお方ほど、王宮に在りながら孤独な方を、私は知りません」
しかし淡々と言い切る清夏の言葉に、アスカは身じろぎした。
「……王宮には、見えないものが多すぎます」
「それが王宮です。見えるものだけで判断しては、命を落とします。噂も、人も、行動も──すべてに気をつけなければなりません」
その口調には、まるで何かを見てきたような確信があった。
「……では、私はどうすればいいんでしょう。何を信じて、どう動けば……」
「それを探すのは、アスカ様のお役目です」
「……」
アスカは言葉を失った。けれど、逃げる気にはなれなかった。
「どなたを守りたいのでしょう。どなたと共に生きたいですか? それを念頭に、賢く生きなければ未来は明るくはないでしょう」
清夏の言葉に思い浮かぶのは、大切な家族と、リオールだ。
深く息を吐き目を閉じたアスカは、再びゆっくりと目を開ける。
「……教えてくださって、ありがとうございます。今日から、できることをひとつずつ覚えます」
「その覚悟があれば、きっと道は開けます」
清夏は、ほんのわずかに口の端を動かした。
それは、彼女なりの微笑だったのかもしれない。
優しく丁寧に教えてくれた清夏。
アスカの中で、彼女の印象が少し変わった。
「清夏さんは、私のことがお嫌いですよね」
「……」
「それなのに、こうして優しく教えてくださったこと、感謝します」
アスカが感謝を伝えると、清夏は黙り込み、しばし考えたのちに口を開いた。
「……私には、アスカ様が何を仰っているのかわかりません」
「えっと……」
「私は貴方様に『嫌いだ』とお伝えしたことがありましたか。それであれば申し訳ございません。記憶にございません」
小さく頭を下げる清夏の姿に、アスカは驚き、慌てて否定した。
「そう言われたことはありません! ただ、そうなのだろうと思って」
「……アスカ様は誤解されています。私は貴方様を嫌ってなどおりません」
「でも……」
「私の顔つきが固いせいで、そう思わせてしまったのかもしれません。──これは、私がここで生き残るために身に付けたものです」
清夏にも、語りたくない事情があるのだろう。
アスカはそれを察し、そっと視線を床に落とした。
「決して、嫌いではありません。むしろ私は、アスカ様のお力になりたいと思っておりますよ」
「!」
うそだ、と否定しかけたが、寸前で言葉を飲み込む。
「本心です。あの孤独な皇太子殿下のお心の支えになっておられる。私は、殿下が幼い頃よりここにおります。あの方には幸せになって頂きたい。──そのためには、貴方様が必要不可欠だと思っております」
清夏と視線が交わる。
その瞳の奥に、強い意志が宿っている──アスカは、そう初めて感じたのだった。
60
あなたにおすすめの小説

【完結】愛されたかった僕の人生
Kanade
BL
✯オメガバース
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。
今日も《夫》は帰らない。
《夫》には僕以外の『番』がいる。
ねぇ、どうしてなの?
一目惚れだって言ったじゃない。
愛してるって言ってくれたじゃないか。
ねぇ、僕はもう要らないの…?
独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。

〈完結〉【書籍化・取り下げ予定】「他に愛するひとがいる」と言った旦那様が溺愛してくるのですが、そういうのは不要です
ごろごろみかん。
恋愛
「私には、他に愛するひとがいます」
「では、契約結婚といたしましょう」
そうして今の夫と結婚したシドローネ。
夫は、シドローネより四つも年下の若き騎士だ。
彼には愛するひとがいる。
それを理解した上で政略結婚を結んだはずだったのだが、だんだん夫の様子が変わり始めて……?

夫には好きな相手がいるようです。愛されない僕は針と糸で未来を縫い直します。
伊織
BL
裕福な呉服屋の三男・桐生千尋(きりゅう ちひろ)は、行商人の家の次男・相馬誠一(そうま せいいち)と結婚した。
子どもの頃に憧れていた相手との結婚だったけれど、誠一はほとんど笑わず、冷たい態度ばかり。
ある日、千尋は誠一宛てに届いた女性からの恋文を見つけてしまう。
――自分はただ、家からの援助目当てで選ばれただけなのか?
失望と涙の中で、千尋は気づく。
「誠一に頼らず、自分の力で生きてみたい」
針と糸を手に、幼い頃から得意だった裁縫を活かして、少しずつ自分の居場所を築き始める。
やがて町の人々に必要とされ、笑顔を取り戻していく千尋。
そんな千尋を見て、誠一の心もまた揺れ始めて――。
涙から始まる、すれ違い夫婦の再生と恋の物語。
※本作は明治時代初期~中期をイメージしていますが、BL作品としての物語性を重視し、史実とは異なる設定や表現があります。
※誤字脱字などお気づきの点があるかもしれませんが、温かい目で読んでいただければ嬉しいです。

【完結】可愛いあの子は番にされて、もうオレの手は届かない
天田れおぽん
BL
劣性アルファであるオズワルドは、劣性オメガの幼馴染リアンを伴侶に娶りたいと考えていた。
ある日、仕えている王太子から名前も知らないオメガのうなじを噛んだと告白される。
運命の番と王太子の言う相手が落としていったという髪飾りに、オズワルドは見覚えがあった――――
※他サイトにも掲載中
★⌒*+*⌒★ ☆宣伝☆ ★⌒*+*⌒★
「婚約破棄された不遇令嬢ですが、イケオジ辺境伯と幸せになります!」
が、レジーナブックスさまより発売中です。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

愛しい番に愛されたいオメガなボクの奮闘記
天田れおぽん
BL
ボク、アイリス・ロックハートは愛しい番であるオズワルドと出会った。
だけどオズワルドには初恋の人がいる。
でもボクは負けない。
ボクは愛しいオズワルドの唯一になるため、番のオメガであることに甘えることなく頑張るんだっ!
※「可愛いあの子は番にされて、もうオレの手は届かない」のオズワルド君の番の物語です。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
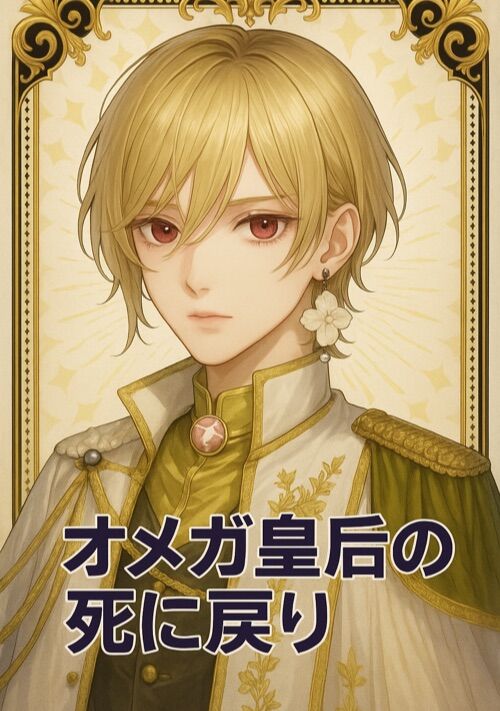
【完結・ルート分岐あり】オメガ皇后の死に戻り〜二度と思い通りにはなりません〜
ivy
BL
魔術師の家門に生まれながら能力の発現が遅く家族から虐げられて暮らしていたオメガのアリス。
そんな彼を国王陛下であるルドルフが妻にと望み生活は一変する。
幸せになれると思っていたのに生まれた子供共々ルドルフに殺されたアリスは目が覚めると子供の頃に戻っていた。
もう二度と同じ轍は踏まない。
そう決心したアリスの戦いが始まる。

流れる星、どうかお願い
ハル
BL
羽水 結弦(うすい ゆずる)
オメガで高校中退の彼は国内の財閥の一つ、羽水本家の次男、羽水要と番になって約8年
高層マンションに住み、気兼ねなくスーパーで買い物をして好きな料理を食べられる。同じ性の人からすれば恵まれた生活をしている彼
そんな彼が夜、空を眺めて流れ星に祈る願いはただ一つ
”要が幸せになりますように”
オメガバースの世界を舞台にしたアルファ×オメガ
王道な関係の二人が織りなすラブストーリーをお楽しみに!
一応、更新していきますが、修正が入ることは多いので
ちょっと読みづらくなったら申し訳ないですが
お付き合いください!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















