12 / 16
12.毒杯とアザミ
しおりを挟む
舞踏会の夜、私は完璧な淑女であった。
透き通るような白銀のドレスを纏い、月光を宿したような髪は緩やかに編み込まれていた。私の手を取ったのは、この国の次期公爵、ユージン・フォン・ヘーゲル殿下。彼の金色の髪は夜会の光を反射し、漆黒の燕尾服は彼の彫りの深い顔立ちを一層際立たせていた。社交界の誰もが認める理想のカップル。それはまるで、遠い星の上で描かれた絵画のようだった。
「エリザベス、今夜の君は、まるで白百合のようだ」
彼はそう言って、私の手の甲に優しく口づけをした。彼の眼差しは純粋で、悪意のかけらもない。だからこそ、私はその言葉を素直に受け取ることができなかった。白百合。それは清らかで、無垢で、いかなる穢れも知らない娘を象徴する。私はそんな私を、とうの昔に殺してしまったというのに。
舞踏会が終わり、自室に戻った私は、鏡の前でドレスを脱ぎ捨てた。華やかな仮面が剥がれ落ち、そこには本来の私がいた。蝋燭の炎が揺れる書斎の机に向かい、私は一冊の黒い革装丁の日記を開いた。
『一月二十三日。晴れ、のち曇り。』
私は万年筆を手に取り、なめらかな羊皮紙に言葉を刻み始める。
『殿下は私を「白百合」と仰いました。彼の瞳には、私の着飾った姿しか映っていないのでしょう。いえ、それ以前に、彼は「白百合」という言葉の意味さえも、深くは考えていない。ただ、社交辞令として、最も無難で、最も無害な言葉を選んだに過ぎないのです。その無垢なまでの無知が、私にとっては最も深い侮辱である。私は毒を含んだ薔薇であり、彼の無邪気な好意は、その棘をさらに鋭くする。』
ペンを置き、私は深い溜息をついた。ユージン殿下は、本当に良い人だ。世間の評判通り、いや、それ以上に。しかし、その「良い人」であることが、私を苦しめる。彼は私の好きな作家の名前も、私がお気に入りの秘密の書庫の場所も、私が静かに過ごすことを好むことも、何一つとして知らない。いや、知ろうとすらしていない。ただ、目の前の「理想の婚約者」に、無邪気な好意を注いでいるだけなのだ。
翌日、朝食の席で、執事から花束が差し出された。鮮やかな紅色の薔薇の花束。
「ユージン殿下から、エリザベス様へ」
執事はそう告げ、恭しく頭を下げた。私は花束を受け取り、その棘を指先でなぞった。
『二月十日。曇り、のち雪。』
私は日記に言葉を綴る。
『殿下から、紅い薔薇が贈られてきました。何と無垢で、そして何と無神経な贈り物でしょう。薔薇は愛を象徴すると言われますが、この花束には、殿下が私の本質を理解していないことの証明が詰まっているのです。私の好きな花は、アザミです。あの孤独で、それでいて力強い紫の花を、私は愛してやまない。しかし、殿下の目に映るのは、ただひたすらに華やかな薔薇のみ。彼は私の魂の内に咲くアザミの存在に、気づきもしないのです。』
私は花瓶に活けられた薔薇を、冷たい目で眺めた。その華やかさが、私の心を一層冷え込ませる。ユージン殿下は、私を「白百合」と呼び、「薔薇」を贈る。彼は私を、ただの美しい装飾品として見ているのではないか。そんな疑念が、私の心を黒く蝕んでいく。
その日の午後、私は友人のマリー・フォン・シュヴァルツと二人きりでティータイムを過ごしていた。マリーは私の心の内を理解している数少ない人物だった。
「ユージン殿下、素敵な方じゃない」
マリーは微笑みながら、紅茶のカップを傾けた。
「ええ、とても」
私は当たり障りのない返事をした。マリーは私の本心を悟り、静かに言葉を続けた。
「ねえ、エリザベス。人は、他人の全てを理解することなんてできないわ。特に、ユージン殿下のように、常に人々に囲まれている方は。彼は、あなたの美しさと、周りの人々があなたに求める姿を愛している。それだけのことよ」
マリーの言葉は、私の心の棘をさらに鋭くした。
「それは、私自身を愛しているのではないということでしょう? 彼は、私の影を愛している。私の作り上げた虚像を」
私は紅茶のカップを置き、窓の外の雪を眺めた。雪は全てを白く覆い隠す。私の心の内にあるアザミも、ユージン殿下には決して見えないのだろう。
翌週、私はユージン殿下とのお忍びのデートへと赴いた。彼は私に、サプライズでプレゼントをしたいと告げた。私は何一つも期待していなかった。どうせまた、社交界の話題に上るような、無難な贈り物だろうと。
「エリザベス、君のために選んだんだ」
殿下はそう言って、一冊の本を差し出した。それは、当時の社交界で流行していた、甘ったるい恋愛小説であった。私は心の中で深い溜息をついた。私は推理小説や、哲学書を好む。しかし、殿下の無垢な瞳は、この本が私を喜ばせるだろうと、純粋に信じている。
『三月五日。曇り。』
日記には、またその日の出来事を記す。
『殿下は私に、ありふれた恋愛小説を贈りました。私の好きな作家の作品とは全く異なるものです。かの作家の描く退廃的な美や、人間の心の闇に、私は惹かれます。殿下が選んだこの本は、私にとって毒です。彼が私に与えようとする幸福は、与えられるたびに私から何かを奪い、そして私を窒息させる。私は、彼の無邪気な善意を、毒杯としか思えないのです。』
私は日記を閉じ、この婚約を解消するべきではないだろうかと、真剣に考え始めた。彼の優しさは、私にとってあまりにも重い。彼が愛しているのは私ではなく、社交界の偶像だ。私はそう確信していた。
しかし、この婚約は家と家の契約なのだから、簡単に反故にすることなど出来はしない。
私の気は重くなるばかりだった。
その日の夜、私の屋敷にユージン殿下が訪れた。
「エリザベス、すまなかった」
彼はそう言って、頭を下げた。
「あの本、君の好みじゃなかっただろう? マリーから聞いたんだ。君は、もっと奥深く、知的なものを好むだろう、と」
私は驚き、言葉を失った。
「君の真実を知りたい。君が愛するものが何なのか、君の心がどこにあるのか。それを知りたいんだ、エリザベス」
彼の瞳は、初めて私自身を映しているように見えた。彼は私の手に、小さなアザミのブローチをそっと乗せた。
「これは、君のために特別に作らせたんだ。君が愛する花だと聞いて…」
私はブローチを握りしめ、胸が締め付けられるような痛みを感じた。毒杯のように思っていた彼の善意が、今、私の心の奥に深く染み渡っていく。
彼はただひどく不器用なだけの人だった。
『三月六日。雨、のち晴れ。』
私は日記に最後の言葉を綴る。
『毒杯だと思っていた彼の善意は、私自身の心を映し出す鏡だったのかもしれない。私の心に毒を塗っていたのは、他でもない私自身だ。アザミは、私の心に咲く花。そして、彼は、その棘を知りながら、私を愛そうとしてくれているのかもしれない。』
私は日記を閉じ、静かに微笑んだ。
透き通るような白銀のドレスを纏い、月光を宿したような髪は緩やかに編み込まれていた。私の手を取ったのは、この国の次期公爵、ユージン・フォン・ヘーゲル殿下。彼の金色の髪は夜会の光を反射し、漆黒の燕尾服は彼の彫りの深い顔立ちを一層際立たせていた。社交界の誰もが認める理想のカップル。それはまるで、遠い星の上で描かれた絵画のようだった。
「エリザベス、今夜の君は、まるで白百合のようだ」
彼はそう言って、私の手の甲に優しく口づけをした。彼の眼差しは純粋で、悪意のかけらもない。だからこそ、私はその言葉を素直に受け取ることができなかった。白百合。それは清らかで、無垢で、いかなる穢れも知らない娘を象徴する。私はそんな私を、とうの昔に殺してしまったというのに。
舞踏会が終わり、自室に戻った私は、鏡の前でドレスを脱ぎ捨てた。華やかな仮面が剥がれ落ち、そこには本来の私がいた。蝋燭の炎が揺れる書斎の机に向かい、私は一冊の黒い革装丁の日記を開いた。
『一月二十三日。晴れ、のち曇り。』
私は万年筆を手に取り、なめらかな羊皮紙に言葉を刻み始める。
『殿下は私を「白百合」と仰いました。彼の瞳には、私の着飾った姿しか映っていないのでしょう。いえ、それ以前に、彼は「白百合」という言葉の意味さえも、深くは考えていない。ただ、社交辞令として、最も無難で、最も無害な言葉を選んだに過ぎないのです。その無垢なまでの無知が、私にとっては最も深い侮辱である。私は毒を含んだ薔薇であり、彼の無邪気な好意は、その棘をさらに鋭くする。』
ペンを置き、私は深い溜息をついた。ユージン殿下は、本当に良い人だ。世間の評判通り、いや、それ以上に。しかし、その「良い人」であることが、私を苦しめる。彼は私の好きな作家の名前も、私がお気に入りの秘密の書庫の場所も、私が静かに過ごすことを好むことも、何一つとして知らない。いや、知ろうとすらしていない。ただ、目の前の「理想の婚約者」に、無邪気な好意を注いでいるだけなのだ。
翌日、朝食の席で、執事から花束が差し出された。鮮やかな紅色の薔薇の花束。
「ユージン殿下から、エリザベス様へ」
執事はそう告げ、恭しく頭を下げた。私は花束を受け取り、その棘を指先でなぞった。
『二月十日。曇り、のち雪。』
私は日記に言葉を綴る。
『殿下から、紅い薔薇が贈られてきました。何と無垢で、そして何と無神経な贈り物でしょう。薔薇は愛を象徴すると言われますが、この花束には、殿下が私の本質を理解していないことの証明が詰まっているのです。私の好きな花は、アザミです。あの孤独で、それでいて力強い紫の花を、私は愛してやまない。しかし、殿下の目に映るのは、ただひたすらに華やかな薔薇のみ。彼は私の魂の内に咲くアザミの存在に、気づきもしないのです。』
私は花瓶に活けられた薔薇を、冷たい目で眺めた。その華やかさが、私の心を一層冷え込ませる。ユージン殿下は、私を「白百合」と呼び、「薔薇」を贈る。彼は私を、ただの美しい装飾品として見ているのではないか。そんな疑念が、私の心を黒く蝕んでいく。
その日の午後、私は友人のマリー・フォン・シュヴァルツと二人きりでティータイムを過ごしていた。マリーは私の心の内を理解している数少ない人物だった。
「ユージン殿下、素敵な方じゃない」
マリーは微笑みながら、紅茶のカップを傾けた。
「ええ、とても」
私は当たり障りのない返事をした。マリーは私の本心を悟り、静かに言葉を続けた。
「ねえ、エリザベス。人は、他人の全てを理解することなんてできないわ。特に、ユージン殿下のように、常に人々に囲まれている方は。彼は、あなたの美しさと、周りの人々があなたに求める姿を愛している。それだけのことよ」
マリーの言葉は、私の心の棘をさらに鋭くした。
「それは、私自身を愛しているのではないということでしょう? 彼は、私の影を愛している。私の作り上げた虚像を」
私は紅茶のカップを置き、窓の外の雪を眺めた。雪は全てを白く覆い隠す。私の心の内にあるアザミも、ユージン殿下には決して見えないのだろう。
翌週、私はユージン殿下とのお忍びのデートへと赴いた。彼は私に、サプライズでプレゼントをしたいと告げた。私は何一つも期待していなかった。どうせまた、社交界の話題に上るような、無難な贈り物だろうと。
「エリザベス、君のために選んだんだ」
殿下はそう言って、一冊の本を差し出した。それは、当時の社交界で流行していた、甘ったるい恋愛小説であった。私は心の中で深い溜息をついた。私は推理小説や、哲学書を好む。しかし、殿下の無垢な瞳は、この本が私を喜ばせるだろうと、純粋に信じている。
『三月五日。曇り。』
日記には、またその日の出来事を記す。
『殿下は私に、ありふれた恋愛小説を贈りました。私の好きな作家の作品とは全く異なるものです。かの作家の描く退廃的な美や、人間の心の闇に、私は惹かれます。殿下が選んだこの本は、私にとって毒です。彼が私に与えようとする幸福は、与えられるたびに私から何かを奪い、そして私を窒息させる。私は、彼の無邪気な善意を、毒杯としか思えないのです。』
私は日記を閉じ、この婚約を解消するべきではないだろうかと、真剣に考え始めた。彼の優しさは、私にとってあまりにも重い。彼が愛しているのは私ではなく、社交界の偶像だ。私はそう確信していた。
しかし、この婚約は家と家の契約なのだから、簡単に反故にすることなど出来はしない。
私の気は重くなるばかりだった。
その日の夜、私の屋敷にユージン殿下が訪れた。
「エリザベス、すまなかった」
彼はそう言って、頭を下げた。
「あの本、君の好みじゃなかっただろう? マリーから聞いたんだ。君は、もっと奥深く、知的なものを好むだろう、と」
私は驚き、言葉を失った。
「君の真実を知りたい。君が愛するものが何なのか、君の心がどこにあるのか。それを知りたいんだ、エリザベス」
彼の瞳は、初めて私自身を映しているように見えた。彼は私の手に、小さなアザミのブローチをそっと乗せた。
「これは、君のために特別に作らせたんだ。君が愛する花だと聞いて…」
私はブローチを握りしめ、胸が締め付けられるような痛みを感じた。毒杯のように思っていた彼の善意が、今、私の心の奥に深く染み渡っていく。
彼はただひどく不器用なだけの人だった。
『三月六日。雨、のち晴れ。』
私は日記に最後の言葉を綴る。
『毒杯だと思っていた彼の善意は、私自身の心を映し出す鏡だったのかもしれない。私の心に毒を塗っていたのは、他でもない私自身だ。アザミは、私の心に咲く花。そして、彼は、その棘を知りながら、私を愛そうとしてくれているのかもしれない。』
私は日記を閉じ、静かに微笑んだ。
2
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

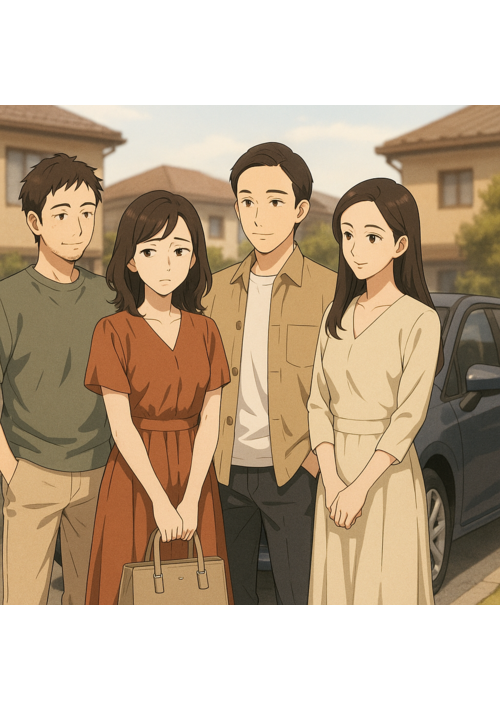

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。


極上イケメン先生が秘密の溺愛教育に熱心です
朝陽七彩
恋愛
私は。
「夕鶴、こっちにおいで」
現役の高校生だけど。
「ずっと夕鶴とこうしていたい」
担任の先生と。
「夕鶴を誰にも渡したくない」
付き合っています。
♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡
神城夕鶴(かみしろ ゆづる)
軽音楽部の絶対的エース
飛鷹隼理(ひだか しゅんり)
アイドル的存在の超イケメン先生
♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡
彼の名前は飛鷹隼理くん。
隼理くんは。
「夕鶴にこうしていいのは俺だけ」
そう言って……。
「そんなにも可愛い声を出されたら……俺、止められないよ」
そして隼理くんは……。
……‼
しゅっ……隼理くん……っ。
そんなことをされたら……。
隼理くんと過ごす日々はドキドキとわくわくの連続。
……だけど……。
え……。
誰……?
誰なの……?
その人はいったい誰なの、隼理くん。
ドキドキとわくわくの連続だった私に突如現れた隼理くんへの疑惑。
その疑惑は次第に大きくなり、私の心の中を不安でいっぱいにさせる。
でも。
でも訊けない。
隼理くんに直接訊くことなんて。
私にはできない。
私は。
私は、これから先、一体どうすればいいの……?


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















