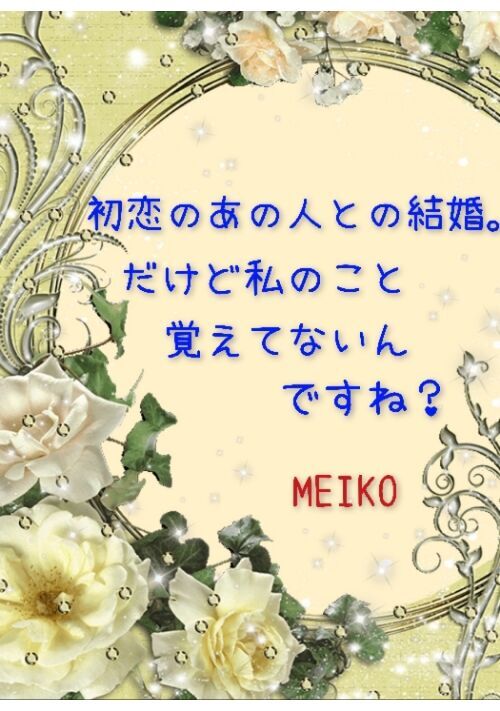29 / 56
29
しおりを挟む
バイユエの屋敷には、美しい庭が設けられている。ヨーリン川から水を引くことによって、まるで庭の中に湖があるかのような錯覚を抱く風景を生み出している。水面には蓮が浮き、美しい花の姿を見せてくれていた。だが、そろそろ蓮の季節も終わってしまう。この景色が見られるのも、あと少しだ。そんなことを考えながら石で作られた橋の上を歩いた。私の数歩離れた場所で、レンが私を見守っている。
散歩がしたい気分だったのだ。ここ最近は考えてばかりで、頭の中が忙しなかった。私の悩みの種は、弟たちのことだ。どちらの弟を選ぶのか。そんな選択肢で悩まされる日が来るとは思っていなかった。立ち止まって足元を見つめる。美しい蓮ではなく、足元の石畳を眺めていたい気分だったのだ。
「トーカ様」
レンのものではない声に驚いて、ぱっと顔を上げる。私の視線の先に、ヤザが立っていた。少しばかり驚く。彼が私に話しかけてくることが、とても珍しいからだ。穏やかで落ち着いた風貌だけを見ていれば、この男を背の者だと判断する人間は少ないだろう。だがその実、この人はとても恐ろしい。その恐ろしさが私に向けられたことは一度もないが、それでも屋敷の中で漏れ聞こえる話だけでも、ヤザの恐ろしさは十分に理解が出来るのだ。私は微かに警戒しながら、ヤザと対峙した。
「少し、二人きりでお話しさせて頂けないでしょうか」
一体、何の用なのかと身構えていた私は、肩透かしを喰らう。わざわざ庭にやって来たということは、それなりに私を探したということだ。それほどの労力をかけて私に会いに来て、話がしたいとは。
二人きりで、と誇張するようにヤザは言った。それに従うように、私はレンへと視線を送る。それでもレンは立ち去ろうとはしなかった。私の視線の意味が分かっていないわけではないのだろう。分かった上で、分からないふりをしているのだ。こうなってしまえば、言葉を使ってレンに伝える以外に手段がない。私は口を開いた。
「レン、先に戻っていて。レンが入れてくれたお茶が飲みたいな。喉が乾いているから、冷たいお茶だととても嬉しい」
本当は喉など乾いていないし、冷たいお茶も苦手だ。それでも、こう言わなければレンは私の言葉に従ってくれなかっただろう。冷たいお茶を用意すると言うのは、とても面倒なことなのだ。一度、熱いお茶を作り、その後でそれを扇であおいで冷まさなければならない。時間のかかることだ。それをして来て欲しい、と私は口実のために懇願する。
レンとしては、あまり私をヤザと二人きりにさせたくないのだろう。それは、私がヤザを苦手としていることを知っているからだ。だが、冷たいお茶を、と私が言った瞬間に不服そうな顔をしながらも、どこか諦めたような表情を見せた。
「……わかった」
そうして、レンは数度こちらを振り返りながらも去っていく。まっすぐに私たちの部屋へと戻ることだろう。二人きりになったところで、私はヤザに向かって歩き出した。そしてヤザも身を翻して、進み出す。結果、二人で肩を並べながら庭園の石橋を歩くことになった。
「シア様の命日の件、頭目からお聞きになりましたか?」
「はい。今年は同行してもらえないと」
「すみません、色々と立て込んでおりまして」
「いえいえ、レンも一緒ですし、問題ないですよ」
少し寒くなり始めるこの頃に、毎年、母の墓参りに行っていた。母の墓は王都にある父の邸宅にあり、そこで丁重に弔われているのだ。墓参りに行く際には、大抵ヤザが同行していた。私の護衛という側面もあるのだろうが、ヤザの真の目的はきっと父に会うためなのだ。今年も父に会いに行くのだろうと思っていたら、予想が覆された。
だがもともと、護衛としてはレンがいてくれるために、ヤザまで護衛としてついてくるのは過剰だと思っていたのだ。問題ない、という言葉は強がりでも何でもなく、事実として私の口から出て行った言葉だった。会話が止まり、私は訝しい気持ちでヤザを見る。
「二人きりになってしたかった話が、それですか……?」
「まさか」
肩を竦めてヤザは小さく笑った。彼の足は止まることなく進み続け、私もその動きに合わせて歩を進める。一体何のためにこの男はここにやってきて、私の隣で歩いているのだろうか。考えを巡らせていた私に、ついに答えが与えられる。
「あの犬を、選んで差し上げたら如何ですか?」
その言葉の意味を理解した瞬間に、私は目を見開いて隣のヤザを見ていた。あの犬。つまりそれは、レンのことを指している。ヤザはどこまで私たちのことを知っているのだろうか。口を開いた時、己の唇が少しばかり震えている音に気付く。
「スイに聞いたんですか」
「えぇ……まぁ。こう見えて、意外と頭目とは気さくな関係なんですよ。恋の悩みをよく聞いたりしています」
どうにも、ヤザの発言をそのまま鵜呑みにすることが出来なかった。スイが己の心の内側を、他人に話すという光景が思い描けないのだ。だが、ヤザは私が二人の弟に選択を迫られていることを把握している。やはり、スイがヤザに語ったのだろうか。私たちの状況をヤザが知っているとすると、彼の言葉に私は違和感を抱く。
「あなたであれば、スイの願いが叶うことを望むのでは?」
「基本的には頭目の願いの成就を祈りますが、この一件に関しては、私には私の意見があるのですよ」
ヤザは、スイに仕えている。そんな彼であれば、スイの願いが成就することを祈ると思ったのだ。だが、ヤザは私にレンを選ぶようにと勧めている。それはスイの願いに反することだ。私とレンが結ばれること。ヤザは己の意見に基づいて、そうなれば良いと考えていた。
「とても個人的な想いで恐縮ですが、私はフユン様の血が絶えて欲しくないのです」
「……父には、私やレン以外にも、たくさんの子がいます。絶えることはないのでは?」
「もちろん、承知しています。あの方は次から次へと女を孕ませ、多くのご子息、ご息女を産ませた。正直に言って、多過ぎます。我々、傍で仕えていた者たちでも把握できないほどに。きっと、取りこぼしている子供もいることでしょう。けれど、それほどまでに子がいても、フユン様が実子だと認め、バイユエの籍に入れたお子様方は少ない」
会ったこともない兄弟姉妹たちのことを考えた。否、兄はいない。私が父の子の中の、長子とされている。だが、ヤザの言う通り子として認められていないだけで、私より年上の子も父にはいるのではないだろうか。好色で節操のなかった父の子種は、広く撒かれている。だが、その撒かれた種たちの中でも、バイユエに連なることを許された者は殆どいないのだ。
「中でも、頭目は優秀で、色濃くフユン様の素質を受け継いでおられる。私は、他の誰でもなく、頭目がフユン様の血を継いで、次の世代を生み出して頂きたいのです」
スイには女を娶り妻として、子を作ってもらいたい。ヤザが言っているのは、そういうことだ。子を身篭れない私では、ヤザの願いは叶えられない。
「だから、私はレンを選び、スイと距離を取れ……と?」
「そこまで具体的な願いを申し上げれば、私は頭目に殺されることでしょう。……ただ、偽ることの出来ない願いは、確かにそのお言葉に近いものなのです」
演技であっても、ヤザは私とスイを祝福しないだろう。スイの忠実な部下ではあるが、心の全てを明け渡しているわけではないということが、よく分かる。この人は、どこまでも父の下僕なのだ。父のために生き、父のためにバイユエを守り、父の血が続くことを祈っている。
「とはいえ、頭目からトーカ様を遠ざけたとしても、あの方が突如、女に目覚めるわけでもなし……、頭目にはトーカ様がそばにいて頂い方が御し易いとも思う。……あなたたちの関係は、本当に面倒臭いですね」
溜息混じりに吐き捨てられた言葉は、嫌味でもなんでもなく、心からの吐露であると感じ取れた。面倒臭いとは、私自身も思っている。ただの兄弟でいられたら。ただ、慈しみあうだけの関係であれたら、ここまで私が悩むことも、ヤザに面倒臭いと溜息を吐かれることもなかっただろう。ついつい私は笑ってしまった。笑いながら、ヤザに問いを投げかける。
「誰かを強く欲するほど、愛したことはありますか?」
「ありませんよ、そんな経験」
心底下らない話題だと言うように、ヤザは軽く返した。それだけでなく、鼻で小さく笑うのだ。私には、そんなこと出来ない。誰かを深く愛するという感覚を知りたくて藻搔いている私は、ヤザの態度に驚いてしまう。
「淡白なのでしょうね。男よりは断然女が好きですが、とはいえ必要な時に抱く程度で、常にそばに侍らせるような気には到底なりません」
必要な時というのはつまり、そういった気分になるということだろう。女が必要になった時だけ、女を抱く。ヤザはそういう主義であるようだ。それは愛ではなく、欲の処理。そういう人間もいるということを私は学ぶ。淡々と語ったヤザを、横目でちらりと見た。
「正直なことを言うと、あなたは父を愛しているのかと思っていました。いつも、父に会う時のあなたは、とても幸せそうだったから」
「私がフユン様を? ご冗談を。私に男色の気はありませんよ。それに、あの方は好きだとか、嫌いだとか、そういった尺度で測れるお方ではないのです。頭がおかしいと思われるかもしれませんが、私にとってフユン様は神にも等しい方なんです」
それは愛情ではなく、信仰に近い感覚であるように思えた。愛とは異なる感情を、ヤザは父に向けている。世の中に流布している恋物語の中にある愛の形は、容易い形をしていた。相手を深く思慕し、それが愛し合う結末へと向かう。その愛情は確かに分かりやすい。だが実際、他人の心の中を覗いてみれば、そのような整った形の愛は少ないのだと私は知った。
「ある意味で言えば、私はあなたたちのことを理解することが出来ない。それほどまでの愛情を、誰に対しても抱いたことがないからです。頭目は、重責全てを背負ってでもあなたを守るためにバイユエの頭を務めている。レンは、命の全てを使ってあなたに献身している。その根幹にある感情が、彼らは愛なんです。欲深く、浅ましく、酷い執着じみた愛。……私には到底、理解出来ない。理解が出来ずとも、トーカ様がどちらかを選ばなければいけないということは分かります」
私はゆっくりと頷く。弟たちが、現状のままであることを許してくれたのならば、選択など不要だった。だが、弟たちは許してくれなかった。選ばなければならない。進まなければならない。どちらかの手を離し、どちらかの手を握る。己の手を見る。手は二つあるのに、二人の弟と手を繋いだまま歩くことは出来ないのだ。
「もし仮に、トーカ様がレンを選んだとしても、頭目はあの男を殺すようなことはないと思います。あなたが大切にする犬を、頭目は絶対に殺せない」
「だから、安心してレンを選べと……?」
「そう聞こえてしまいましたか? おや失敬」
なんとわざとらしい言い方だろうか。こういう側面さえなければ、少しは常識的な人間であるように思えるのに。だが、こういった物言いをするからこそ、ヤザはヤザたり得るのだろう。
「トーカ」
長く話をした私とヤザは、庭園を一周してしまっていたらしい。散歩の始点であり終点である場所で、レンが私を待ち構えていた。隣に立つヤザの方には一瞥もくれず、私だけを見ている。
「冷たい茶が用意できた」
なんのことだろう、と首を傾げてしまったが、慌てて頷いた。そうだ。私が冷たい茶を飲みたいなどという我儘を言ってレンを遠ざけたのだった。ありがとう、と返すとレンは私の手首を握る。早く部屋に戻ろう、という仕草であることにはすぐに気付く。
「相変わらず、あなたの忠犬は過ぎるほどに懸命ですね」
「あなたもそうなのでは? スイの犬なのか、父の犬なのかは分かりませんが……、あなただって、とても懸命に見えますよ」
レンのことを忠犬だと言うが、私の目から見ればヤザも負けてはいないと思う。素直な気持ちでそう言うと、ヤザは目を見開いて驚いた顔をした。そして額に手を当てながら呵々と笑う。ひとしきり笑い終わった頃には、目尻に涙が浮いていた。
「嫌味で言っているわけではないところがまた、嫌味に感じますね」
随分と捻くれた言葉を言い残して、ヤザは去っていった。庭を一周まわる。長くもあり、短くもあるその散歩。けれど、これほどの時間をヤザと二人きりで過ごしたことはない。きっと、父の子でなければヤザは私など歯牙にもかけなかっただろう。だが、父の息子であったために、こうして言葉を交わすことが出来た。ぞんざいな言い方ではあったが、彼の言っていたことは私の中に小さな光明を与えたような気がする。
「トーカ、何の話をしてたの」
「……秘密」
唇に人差し指を押し当てて、内緒だと態度で示す。レンはあからさまに不服そうな顔をして、私を笑わせた。部屋へ戻るため、歩き出す。この庭にやってくる前よりは、足取りが軽くなっているような気がした。
愛にはさまざまな形がある。そんなことは、きっと誰しもが理解していることだったのだろう。私だけが知らなかった。レンが抱く愛を、私がレンに抱けなくてもいい。スイが私に向ける愛を、私がスイに向けられなくてもいい。私の愛が、私の愛として、この胸の中にあれば良いのだ。自分の胸に根付く愛をじっくりと見つめて、その奥の奥に視線が届いた時、私はきっと、どちらかの弟に手を伸ばすのだろう。
散歩がしたい気分だったのだ。ここ最近は考えてばかりで、頭の中が忙しなかった。私の悩みの種は、弟たちのことだ。どちらの弟を選ぶのか。そんな選択肢で悩まされる日が来るとは思っていなかった。立ち止まって足元を見つめる。美しい蓮ではなく、足元の石畳を眺めていたい気分だったのだ。
「トーカ様」
レンのものではない声に驚いて、ぱっと顔を上げる。私の視線の先に、ヤザが立っていた。少しばかり驚く。彼が私に話しかけてくることが、とても珍しいからだ。穏やかで落ち着いた風貌だけを見ていれば、この男を背の者だと判断する人間は少ないだろう。だがその実、この人はとても恐ろしい。その恐ろしさが私に向けられたことは一度もないが、それでも屋敷の中で漏れ聞こえる話だけでも、ヤザの恐ろしさは十分に理解が出来るのだ。私は微かに警戒しながら、ヤザと対峙した。
「少し、二人きりでお話しさせて頂けないでしょうか」
一体、何の用なのかと身構えていた私は、肩透かしを喰らう。わざわざ庭にやって来たということは、それなりに私を探したということだ。それほどの労力をかけて私に会いに来て、話がしたいとは。
二人きりで、と誇張するようにヤザは言った。それに従うように、私はレンへと視線を送る。それでもレンは立ち去ろうとはしなかった。私の視線の意味が分かっていないわけではないのだろう。分かった上で、分からないふりをしているのだ。こうなってしまえば、言葉を使ってレンに伝える以外に手段がない。私は口を開いた。
「レン、先に戻っていて。レンが入れてくれたお茶が飲みたいな。喉が乾いているから、冷たいお茶だととても嬉しい」
本当は喉など乾いていないし、冷たいお茶も苦手だ。それでも、こう言わなければレンは私の言葉に従ってくれなかっただろう。冷たいお茶を用意すると言うのは、とても面倒なことなのだ。一度、熱いお茶を作り、その後でそれを扇であおいで冷まさなければならない。時間のかかることだ。それをして来て欲しい、と私は口実のために懇願する。
レンとしては、あまり私をヤザと二人きりにさせたくないのだろう。それは、私がヤザを苦手としていることを知っているからだ。だが、冷たいお茶を、と私が言った瞬間に不服そうな顔をしながらも、どこか諦めたような表情を見せた。
「……わかった」
そうして、レンは数度こちらを振り返りながらも去っていく。まっすぐに私たちの部屋へと戻ることだろう。二人きりになったところで、私はヤザに向かって歩き出した。そしてヤザも身を翻して、進み出す。結果、二人で肩を並べながら庭園の石橋を歩くことになった。
「シア様の命日の件、頭目からお聞きになりましたか?」
「はい。今年は同行してもらえないと」
「すみません、色々と立て込んでおりまして」
「いえいえ、レンも一緒ですし、問題ないですよ」
少し寒くなり始めるこの頃に、毎年、母の墓参りに行っていた。母の墓は王都にある父の邸宅にあり、そこで丁重に弔われているのだ。墓参りに行く際には、大抵ヤザが同行していた。私の護衛という側面もあるのだろうが、ヤザの真の目的はきっと父に会うためなのだ。今年も父に会いに行くのだろうと思っていたら、予想が覆された。
だがもともと、護衛としてはレンがいてくれるために、ヤザまで護衛としてついてくるのは過剰だと思っていたのだ。問題ない、という言葉は強がりでも何でもなく、事実として私の口から出て行った言葉だった。会話が止まり、私は訝しい気持ちでヤザを見る。
「二人きりになってしたかった話が、それですか……?」
「まさか」
肩を竦めてヤザは小さく笑った。彼の足は止まることなく進み続け、私もその動きに合わせて歩を進める。一体何のためにこの男はここにやってきて、私の隣で歩いているのだろうか。考えを巡らせていた私に、ついに答えが与えられる。
「あの犬を、選んで差し上げたら如何ですか?」
その言葉の意味を理解した瞬間に、私は目を見開いて隣のヤザを見ていた。あの犬。つまりそれは、レンのことを指している。ヤザはどこまで私たちのことを知っているのだろうか。口を開いた時、己の唇が少しばかり震えている音に気付く。
「スイに聞いたんですか」
「えぇ……まぁ。こう見えて、意外と頭目とは気さくな関係なんですよ。恋の悩みをよく聞いたりしています」
どうにも、ヤザの発言をそのまま鵜呑みにすることが出来なかった。スイが己の心の内側を、他人に話すという光景が思い描けないのだ。だが、ヤザは私が二人の弟に選択を迫られていることを把握している。やはり、スイがヤザに語ったのだろうか。私たちの状況をヤザが知っているとすると、彼の言葉に私は違和感を抱く。
「あなたであれば、スイの願いが叶うことを望むのでは?」
「基本的には頭目の願いの成就を祈りますが、この一件に関しては、私には私の意見があるのですよ」
ヤザは、スイに仕えている。そんな彼であれば、スイの願いが成就することを祈ると思ったのだ。だが、ヤザは私にレンを選ぶようにと勧めている。それはスイの願いに反することだ。私とレンが結ばれること。ヤザは己の意見に基づいて、そうなれば良いと考えていた。
「とても個人的な想いで恐縮ですが、私はフユン様の血が絶えて欲しくないのです」
「……父には、私やレン以外にも、たくさんの子がいます。絶えることはないのでは?」
「もちろん、承知しています。あの方は次から次へと女を孕ませ、多くのご子息、ご息女を産ませた。正直に言って、多過ぎます。我々、傍で仕えていた者たちでも把握できないほどに。きっと、取りこぼしている子供もいることでしょう。けれど、それほどまでに子がいても、フユン様が実子だと認め、バイユエの籍に入れたお子様方は少ない」
会ったこともない兄弟姉妹たちのことを考えた。否、兄はいない。私が父の子の中の、長子とされている。だが、ヤザの言う通り子として認められていないだけで、私より年上の子も父にはいるのではないだろうか。好色で節操のなかった父の子種は、広く撒かれている。だが、その撒かれた種たちの中でも、バイユエに連なることを許された者は殆どいないのだ。
「中でも、頭目は優秀で、色濃くフユン様の素質を受け継いでおられる。私は、他の誰でもなく、頭目がフユン様の血を継いで、次の世代を生み出して頂きたいのです」
スイには女を娶り妻として、子を作ってもらいたい。ヤザが言っているのは、そういうことだ。子を身篭れない私では、ヤザの願いは叶えられない。
「だから、私はレンを選び、スイと距離を取れ……と?」
「そこまで具体的な願いを申し上げれば、私は頭目に殺されることでしょう。……ただ、偽ることの出来ない願いは、確かにそのお言葉に近いものなのです」
演技であっても、ヤザは私とスイを祝福しないだろう。スイの忠実な部下ではあるが、心の全てを明け渡しているわけではないということが、よく分かる。この人は、どこまでも父の下僕なのだ。父のために生き、父のためにバイユエを守り、父の血が続くことを祈っている。
「とはいえ、頭目からトーカ様を遠ざけたとしても、あの方が突如、女に目覚めるわけでもなし……、頭目にはトーカ様がそばにいて頂い方が御し易いとも思う。……あなたたちの関係は、本当に面倒臭いですね」
溜息混じりに吐き捨てられた言葉は、嫌味でもなんでもなく、心からの吐露であると感じ取れた。面倒臭いとは、私自身も思っている。ただの兄弟でいられたら。ただ、慈しみあうだけの関係であれたら、ここまで私が悩むことも、ヤザに面倒臭いと溜息を吐かれることもなかっただろう。ついつい私は笑ってしまった。笑いながら、ヤザに問いを投げかける。
「誰かを強く欲するほど、愛したことはありますか?」
「ありませんよ、そんな経験」
心底下らない話題だと言うように、ヤザは軽く返した。それだけでなく、鼻で小さく笑うのだ。私には、そんなこと出来ない。誰かを深く愛するという感覚を知りたくて藻搔いている私は、ヤザの態度に驚いてしまう。
「淡白なのでしょうね。男よりは断然女が好きですが、とはいえ必要な時に抱く程度で、常にそばに侍らせるような気には到底なりません」
必要な時というのはつまり、そういった気分になるということだろう。女が必要になった時だけ、女を抱く。ヤザはそういう主義であるようだ。それは愛ではなく、欲の処理。そういう人間もいるということを私は学ぶ。淡々と語ったヤザを、横目でちらりと見た。
「正直なことを言うと、あなたは父を愛しているのかと思っていました。いつも、父に会う時のあなたは、とても幸せそうだったから」
「私がフユン様を? ご冗談を。私に男色の気はありませんよ。それに、あの方は好きだとか、嫌いだとか、そういった尺度で測れるお方ではないのです。頭がおかしいと思われるかもしれませんが、私にとってフユン様は神にも等しい方なんです」
それは愛情ではなく、信仰に近い感覚であるように思えた。愛とは異なる感情を、ヤザは父に向けている。世の中に流布している恋物語の中にある愛の形は、容易い形をしていた。相手を深く思慕し、それが愛し合う結末へと向かう。その愛情は確かに分かりやすい。だが実際、他人の心の中を覗いてみれば、そのような整った形の愛は少ないのだと私は知った。
「ある意味で言えば、私はあなたたちのことを理解することが出来ない。それほどまでの愛情を、誰に対しても抱いたことがないからです。頭目は、重責全てを背負ってでもあなたを守るためにバイユエの頭を務めている。レンは、命の全てを使ってあなたに献身している。その根幹にある感情が、彼らは愛なんです。欲深く、浅ましく、酷い執着じみた愛。……私には到底、理解出来ない。理解が出来ずとも、トーカ様がどちらかを選ばなければいけないということは分かります」
私はゆっくりと頷く。弟たちが、現状のままであることを許してくれたのならば、選択など不要だった。だが、弟たちは許してくれなかった。選ばなければならない。進まなければならない。どちらかの手を離し、どちらかの手を握る。己の手を見る。手は二つあるのに、二人の弟と手を繋いだまま歩くことは出来ないのだ。
「もし仮に、トーカ様がレンを選んだとしても、頭目はあの男を殺すようなことはないと思います。あなたが大切にする犬を、頭目は絶対に殺せない」
「だから、安心してレンを選べと……?」
「そう聞こえてしまいましたか? おや失敬」
なんとわざとらしい言い方だろうか。こういう側面さえなければ、少しは常識的な人間であるように思えるのに。だが、こういった物言いをするからこそ、ヤザはヤザたり得るのだろう。
「トーカ」
長く話をした私とヤザは、庭園を一周してしまっていたらしい。散歩の始点であり終点である場所で、レンが私を待ち構えていた。隣に立つヤザの方には一瞥もくれず、私だけを見ている。
「冷たい茶が用意できた」
なんのことだろう、と首を傾げてしまったが、慌てて頷いた。そうだ。私が冷たい茶を飲みたいなどという我儘を言ってレンを遠ざけたのだった。ありがとう、と返すとレンは私の手首を握る。早く部屋に戻ろう、という仕草であることにはすぐに気付く。
「相変わらず、あなたの忠犬は過ぎるほどに懸命ですね」
「あなたもそうなのでは? スイの犬なのか、父の犬なのかは分かりませんが……、あなただって、とても懸命に見えますよ」
レンのことを忠犬だと言うが、私の目から見ればヤザも負けてはいないと思う。素直な気持ちでそう言うと、ヤザは目を見開いて驚いた顔をした。そして額に手を当てながら呵々と笑う。ひとしきり笑い終わった頃には、目尻に涙が浮いていた。
「嫌味で言っているわけではないところがまた、嫌味に感じますね」
随分と捻くれた言葉を言い残して、ヤザは去っていった。庭を一周まわる。長くもあり、短くもあるその散歩。けれど、これほどの時間をヤザと二人きりで過ごしたことはない。きっと、父の子でなければヤザは私など歯牙にもかけなかっただろう。だが、父の息子であったために、こうして言葉を交わすことが出来た。ぞんざいな言い方ではあったが、彼の言っていたことは私の中に小さな光明を与えたような気がする。
「トーカ、何の話をしてたの」
「……秘密」
唇に人差し指を押し当てて、内緒だと態度で示す。レンはあからさまに不服そうな顔をして、私を笑わせた。部屋へ戻るため、歩き出す。この庭にやってくる前よりは、足取りが軽くなっているような気がした。
愛にはさまざまな形がある。そんなことは、きっと誰しもが理解していることだったのだろう。私だけが知らなかった。レンが抱く愛を、私がレンに抱けなくてもいい。スイが私に向ける愛を、私がスイに向けられなくてもいい。私の愛が、私の愛として、この胸の中にあれば良いのだ。自分の胸に根付く愛をじっくりと見つめて、その奥の奥に視線が届いた時、私はきっと、どちらかの弟に手を伸ばすのだろう。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
131
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる