38 / 61
第4章 騎士の忠義
6 味方
しおりを挟む
座り込んで苦しげな呼吸を繰り返すナーガの唇に、シユリーは自分の唇を合わせた。わずかに口を開き、彼女の体内に満ちる力を彼の体へと流し込む。シユリーの力がナーガの体内に侵入し、水に白い乳を垂らしたときのように、ふわりと薄まり溶け広がる。
わずかな間のあと、ナーガは乱暴にシユリーを振り払った。驚いて下がったシユリーから顔をそむけ、彼は激しく咳込み嘔吐する。
吐瀉物の異臭の中、苦しさに顔を歪ませてナーガは何度も咳込んだ。それによって、体内に侵入したシユリーの力のほとんどが体外に吐き出される。
荒い息を繰り返すナーガの背を、シユリーはいたわりをもってさすった。
「ナッちゃん、大丈夫?」
ナーガは青ざめた顔を上げて、シユリーを見た。
「ああ、なんとか……やはり、自分のでないと体が反発するな」
ぐったりと、ナーガは薄暗い鍾乳洞の壁に体をもたせかける。
「そろそろ限界かな」
シユリーは不安な瞳で彼を見た。
「行くの?」
「このままでは、じきに力の行使ができなくなる」
「竜王の命は長いわ。不便かもしれないけど、ルーファンスが死を迎えるまで待つことだってできるのよ」
少し間があって、ナーガは小声で言った。
「エフィを開放してあげたい」
シユリーは小さくため息をついた。
「それが、ナッちゃんの本心なのね」
あわれっぽく笑って、ナーガはシユリーを見た。
「協力してくれるかい」
寄り添うように、シユリーはナーガの胸に体をうずめた。
「あたしは、ずっとナッちゃんについていくわ」
六十年前、傷ついた白竜を見つけて恋した日から、シユリーはそう決めていた。
☫
顔全体の見える大きな手鏡を覗き込み、エフィミアは肩より上で切りそろえられた自分の髪に触れてみた。
「上手ね」
背後で鋏を鞘に収めているアレクスに鏡越しで言うと、彼は気のない声で応えた。
「そうか?」
「うん。ずいぶん器用じゃない」
「だといいが」
エフィミアの称賛に、アレクスは危ぶむようすで言った。ぞんざいに切り落とされていたエフィミアの髪は、今しがた彼の手によって綺麗に切りそろえられたところだった。
髪の短い自分に違和感を覚えながら、エフィミアは椅子に座ったまま銀ぶちの鏡を眺めた。
「なんだか頭が軽い」
「中身が、か」
「どういう意味よ」
頬を膨らませてエフィミアが睨みつけると、アレクスはかすかにおかしがる笑み見せた。
「冗談だ。よく似合っている」
「そう? ありがとう」
あっさり機嫌を直したエフィミアにアレクスは苦笑を噛み殺しながら、彼女の首に巻きつけて体を覆っていた布をはずした。
「片づけるから、少しどいていろ」
「はーい」
エフィミアは子供っぽく返事をすると、服についた髪を払いながら弾むように立ち上がり、長椅子へ移動した。アレクスは髪を払い落とした椅子をどけて、その下に敷いておいた布に落ちた髪を集めて包んだ。
そんな彼の姿を、エフィミアは興味深く眺めた。
「偉いわりには、下働きみたいなことも平気でできるのね」
「わたしは元々、それほどいい生まれではない」
アレクスは平然と答え、エフィミアはやや目を瞠った。
「そうなの?」
「わたしの親は、王家に仕える従僕でしかない」
「ふーん。つまりあなたは出世頭ってわけね」
エフィミアは感心して言ったが、それに関してアレクスはなにも言わなかった。
あらかた片づけ終わると、アレクスはエフィミアの隣に腰を下ろした。エフィミアは体を傾けて、彼の肩に頭を預けた。アレクスがごく自然な動作でエフィミアの肩を抱く。
そのまましばらく、二人は黙って寄り添っていた。決して気まずいものではない、相手を信頼しているからこその穏やかな静寂。
不思議なものだと、エフィミアは思った。数日前まで彼ほどの敵はいないと思っていたのに、今ではアレクス以上の味方はいないと思える。彼は生真面目に過ぎるきらいはあるが、きつい印象の顔の下に優しい心を持っていることが、今のエフィミアには知れた。
不意にアレクスに髪をつままれ、エフィミアは彼を上目遣いに見た。
「なに?」
「もったいないな。せっかく綺麗な髪をしているのに」
エフィミアはほほ笑むと、さらにアレクスに体を寄せた。
「平気よ。髪の毛ならまた伸びるもの」
明るく言ったエフィミアを、アレクスがいたわるように抱き締めた。愛情にあふれた彼の腕を、エフィミアは感じた。
「……ねえ。昨夜ルーファンスが言っていたことは、本気だと思う?」
エフィミアとルーファンスの間でなにがあったかは、すでにアレクスに話してあった。彼は一瞬だけ沈黙して、呟く声で答える。
「分からない……今のルーファンスを理解している者は、おそらくひとりもいない」
エフィミアから体を離して深く長椅子に身を沈めると、アレクスは自嘲じみた笑みを浮かべた。
「情けないな。昔はあんなにも、あいつの考えていることが手にとるように分かったっていうのに」
エフィミアも座り直しながら、アレクスを見た。
「昔?」
「わたしと陛下は、物心つく前から一緒に育っている」
「幼馴染みってこと?」
「世間的に言えばそうだ」
「ルーファンスは子供のときからあんなふうだったの?」
少し考えながらエフィミアが問うと、アレクスは過去を振り返る間をとってから静かな声音で言った。
「昔は、あんな風ではなかった」
遠くを見るように、アレクスは目を細めた。
「ルーファンスは人一倍臆病で、寂しがりやで、わたしがいないといつも泣いていた。王太子という立場にありながら、人前に立つのも苦手で、委縮するあいつを励ますのは随分と苦労した」
懐かしみながら、アレクスはつい苦笑した。
「庭で蝶の死骸を見つけて、かわいそうだと泣きながら土にうめていたこともあったな。それが、いつ変わってしまったのか……」
エフィミアは昨夜の、人の死をなんとも思わないルーファンスの言葉の数々と、そのときの声音や表情を思い返した。あの彼から、小さな虫の死にさえ涙する少年の姿を思い浮かべることができる者が、果たしているだろうか。
「……彼がお父さんに憎まれていたっていうのは、本当なの?」
エフィミアが問えば、アレクスの目元が険しさを帯びた。
「ルーファンスにしてみれば、そういうふうにとらえても不思議はなかったのかもしれない」
「本当は違うの?」
わずかにうつむいて、アレクスは答えた。
「わたしもルーファンスが生まれる以前のことはよく知らないが、先王が王妃をとても溺愛していたと聞いている。そして王妃が出産で亡くなったのも事実だ。だが、先王はルーファンスを憎んではいなかった」
長椅子の布地に手を突いて、エフィミアはわずかに身を乗り出した。
「じゃあ、どうしてルーファンスは……」
アレクスは無表情にエフィミアを見た。
「王妃の死によって、先王は気負い過ぎた」
「どういうこと?」
正面に顔を戻して、アレクスは低く言った。
「自分がルーファンスを立派な王に育て上げなければと、先王は度々こぼしていた。そして、それにこだわり、ルーファンスに厳しく接していた――だが、わたしの目から見ても、先王のやり方は度が過ぎていた」
よく分からずにエフィミアがアレクスを見ていると、彼は説明した。
「先王はルーファンスを規律で縛りつけたんだ。ルーファンスの傍に置く者を厳選し、生活すべてを管理した。日による時間割り、食事内容に学習内容。そのほかすべて、父親の管理下でルーファンスは生活していた。ひとつでも落度があれば、厳しい罰が与えられた。少し時間に遅れた、食事を残した。そんな些細なものであってもだ。言い訳は許されず、逆らえば地下水路に閉じ込められた。許しを得てそこから出してやるのは、大抵わたしの役目だった」
「そんな……」
なんと言ったらいいのか分からず、エフィミアは言葉に詰まった。
確かに規則的な生活をすることは人にとって大切なことだし、食事だって同じだ。だからといって、そこまで厳格に接する必要があるのだろうか。
エフィミアの親は、叱るときには必ず本人の言い分を訊いた上で彼女の落度を叱った。だから理由も訊かずにいきなり厳罰を与えるというのは、どうにも理解できなかった。エフィミアの親が、子供にそんな接し方をすることがなかったから。
「いつもそうだったわけじゃ、ないんでしょう?」
わずかな希望を求めてエフィミアは言ってみたが、アレクスはため息混じりに返した。
「それが常だった。わたしは当事者ではなかったが、幼心に先王を恐いと思うことも多かった。わたしも、これで努力を強いられたんだ。ルーファンスの傍にいるにあたって、無能は許されない――先王はルーファンスに理想を押しつけ過ぎた。ルーファンスにとって、父親は恐怖の対象でしかなかっただろう……他のことなら、尊敬にあたいする王だったんだがな」
言い終わると共にアレクスはエフィミアの肩を抱き寄せ、エフィミアも彼に体を預けた。
理解の範疇を越えた話に、エフィミアはついていけずにいた。ただ漠然と、ルーファンスが辛い思いをしただろうことが分かるだけだった。
エフィミアはルーファンスとは相反する環境で育った。だからルーファンスの本当の心を見ることはできない。それだけは悟った。
エフィミアがぼんやりしていると、アレクスが囁くように呟いた。
「さっきのエフィを見たとき、少し昔を思い出した。ルーファンスは父王に手を上げられるたびに、わたしのところに泣きつきにきていた……いつの間にか、そんなこともなくなっていたな」
「……そっか」
エフィミアが小さく言うと、アレクスは顔を寄せた。
「君のことは、ようすを見てわたしの方からとり合ってみる。わたしとて、これ以上の事態は避けたい」
エフィミアは真っ直ぐ、アレクスの鈍色の瞳を見詰めた。
「うん。信じてる」
二人はそっと触れ合うだけの口づけを交わした。窓の外はいつの間にか赤く染まり始めており、アレクスは職務に戻るため部屋をあとにした。
エフィミアはアレクスの出ていった扉を名残惜しく見詰めていたが、やがて息をひとつ吐いた。
問題はなにひとつ解決してはいなかったが、今は不思議と、さほど思い煩わずにいられた。味方と思える者がいるのといないのとでは、こんなにも心持ちが違う。
(きっと、なんとかなる)
今は、そう思うことができた。
☫
思うことが多すぎて、アレクスはぼんやりしながら廊下を歩いていた。
思考の多くを占めるのは当然のごとく、先ほどまで顔を合わせていたエフィミアと、自分の主君であるルーファンスのことだった。
今では素直に愛しいと思える女性の色々な面を、アレクスは知りつつあった。逆に、今まですべてを理解していたと思っていた幼馴染みのことがなにも分からなくなっていた。
気づいたときには、臆病だった王は内に秘めていただろう残虐性をむき出し始めていた。その事実に、内心で愕然とする。どこで食い違ってしまったのかと、アレクスは思い悩んだ。
いつも泣いてばかりいた少年。いつからか泣かなくなった若年の王。昔と今、ふたつの面影を浮かべながら、アレクスの思考は堂々巡りを繰り返す。
「ブライアント隊長」
不意に呼びかけられて、アレクスは足を止めて振り返った。声の主は、騎竜隊の部下のひとりだった。
黒い制服をきっちり着込んだを部下は、素早く礼をとってから口を開いた。
「隊長の竜のことでご報告が」
「セスがどうした」
不穏なものを感じて、問う声は無意識にきついものになった。部下は臆さず続きを言った。
「先ごろからようすがおかしいのです。すぐに竜舎まできていただけますか」
アレクスは顔色を変えると、返答する間も惜しく駆け出した。
竜舎の小部屋に着くと、若い赤竜がぐったりと床に伏していた。
「セス!」
アレクスが駆け寄って呼びかけると、愛騎セスは閉じていた目を開き、苦しげに呼吸しながら喉を鳴らして顔を上げた。口から唾液の泡を吐き出すセスの頭をアレクスは抱えた。
「無理をするな。どうした、苦しいのか?」
セスはぜいぜいと喉から音をさせながら、痙攣するように体を動かしていた。黄色い目は視点が定まっておらず、鱗には覚えのない傷がある。見れば、セスが直前まで暴れていたろう痕跡が小部屋の中には残っていた。
餌桶がひっくり返って中身が散乱し、竜の巨体がぶつかったらしい壁が、筋状にけずれている。床には食べたものが吐き出されて、異臭が舎内にただよっていた。
アレクスはもがき苦しむセスの体をさすった。なにが起きたのか、さっぱり分からない。朝の定例訓練のときには、なんともなかったはずだ。
これほどいきなり、体に異変をきたすことがあるだろうか。しかし竜の生態について明かされていないことも多いので、明確なことは言えない。
処置をするための道具をそろえさせた上で、アレクスは辛抱強くセスの体を温めながらさすってやった。他人にセスを任せるつもりはなかった。
セスは荒い呼吸を繰り返し、時おり思い出したように体を震わせた。これほど苦しむセスの姿を見るのは初めてだった。様々な原因を考えてみる中で、失うかもしれないという思いがよぎる。
幼い頃からのつき合いになる友の体を、アレクスは祈る心地でさすり続けた。今さら別の竜に乗り換えるなど考えられない。多くの称賛を受けるアレクスの騎竜の技術も、以心伝心で通じ合えるセスとの信頼関係があってこそなのだ。
セスがいなければ、騎竜隊長アレクス・ブライアントはきっと存在しなかった。
どれだけそうしていたか分からない。格子のはまった窓の外から光が失われ始めたころになって、ゆるやかにセスの容態が安定してきた。苦しげだった呼吸も、次第に静かになっていく。
セスの穏やかな呼吸を聞いて、アレクスは小さく息をついた。しかし、まだ予断はできなかった。
(なぜ、今日はこんなことばかりが起こる)
セスの首元に額をあてた。すべらかな鱗の感触と、そこから伝わる確かなぬくもりに、動揺していたアレクスの心も静まっていく。
ふと、ひっくり返ったままの餌桶の中身が目にとまった。
セスから体を離し、泥にまみれた肉片のひとつを拾い上げる。今まで気づかなかったが、それには白い粉状のものがまばらに付着していた。見渡せば、散乱する他の肉片にも同様のものが見られる。
「これは……」
わずかな間のあと、ナーガは乱暴にシユリーを振り払った。驚いて下がったシユリーから顔をそむけ、彼は激しく咳込み嘔吐する。
吐瀉物の異臭の中、苦しさに顔を歪ませてナーガは何度も咳込んだ。それによって、体内に侵入したシユリーの力のほとんどが体外に吐き出される。
荒い息を繰り返すナーガの背を、シユリーはいたわりをもってさすった。
「ナッちゃん、大丈夫?」
ナーガは青ざめた顔を上げて、シユリーを見た。
「ああ、なんとか……やはり、自分のでないと体が反発するな」
ぐったりと、ナーガは薄暗い鍾乳洞の壁に体をもたせかける。
「そろそろ限界かな」
シユリーは不安な瞳で彼を見た。
「行くの?」
「このままでは、じきに力の行使ができなくなる」
「竜王の命は長いわ。不便かもしれないけど、ルーファンスが死を迎えるまで待つことだってできるのよ」
少し間があって、ナーガは小声で言った。
「エフィを開放してあげたい」
シユリーは小さくため息をついた。
「それが、ナッちゃんの本心なのね」
あわれっぽく笑って、ナーガはシユリーを見た。
「協力してくれるかい」
寄り添うように、シユリーはナーガの胸に体をうずめた。
「あたしは、ずっとナッちゃんについていくわ」
六十年前、傷ついた白竜を見つけて恋した日から、シユリーはそう決めていた。
☫
顔全体の見える大きな手鏡を覗き込み、エフィミアは肩より上で切りそろえられた自分の髪に触れてみた。
「上手ね」
背後で鋏を鞘に収めているアレクスに鏡越しで言うと、彼は気のない声で応えた。
「そうか?」
「うん。ずいぶん器用じゃない」
「だといいが」
エフィミアの称賛に、アレクスは危ぶむようすで言った。ぞんざいに切り落とされていたエフィミアの髪は、今しがた彼の手によって綺麗に切りそろえられたところだった。
髪の短い自分に違和感を覚えながら、エフィミアは椅子に座ったまま銀ぶちの鏡を眺めた。
「なんだか頭が軽い」
「中身が、か」
「どういう意味よ」
頬を膨らませてエフィミアが睨みつけると、アレクスはかすかにおかしがる笑み見せた。
「冗談だ。よく似合っている」
「そう? ありがとう」
あっさり機嫌を直したエフィミアにアレクスは苦笑を噛み殺しながら、彼女の首に巻きつけて体を覆っていた布をはずした。
「片づけるから、少しどいていろ」
「はーい」
エフィミアは子供っぽく返事をすると、服についた髪を払いながら弾むように立ち上がり、長椅子へ移動した。アレクスは髪を払い落とした椅子をどけて、その下に敷いておいた布に落ちた髪を集めて包んだ。
そんな彼の姿を、エフィミアは興味深く眺めた。
「偉いわりには、下働きみたいなことも平気でできるのね」
「わたしは元々、それほどいい生まれではない」
アレクスは平然と答え、エフィミアはやや目を瞠った。
「そうなの?」
「わたしの親は、王家に仕える従僕でしかない」
「ふーん。つまりあなたは出世頭ってわけね」
エフィミアは感心して言ったが、それに関してアレクスはなにも言わなかった。
あらかた片づけ終わると、アレクスはエフィミアの隣に腰を下ろした。エフィミアは体を傾けて、彼の肩に頭を預けた。アレクスがごく自然な動作でエフィミアの肩を抱く。
そのまましばらく、二人は黙って寄り添っていた。決して気まずいものではない、相手を信頼しているからこその穏やかな静寂。
不思議なものだと、エフィミアは思った。数日前まで彼ほどの敵はいないと思っていたのに、今ではアレクス以上の味方はいないと思える。彼は生真面目に過ぎるきらいはあるが、きつい印象の顔の下に優しい心を持っていることが、今のエフィミアには知れた。
不意にアレクスに髪をつままれ、エフィミアは彼を上目遣いに見た。
「なに?」
「もったいないな。せっかく綺麗な髪をしているのに」
エフィミアはほほ笑むと、さらにアレクスに体を寄せた。
「平気よ。髪の毛ならまた伸びるもの」
明るく言ったエフィミアを、アレクスがいたわるように抱き締めた。愛情にあふれた彼の腕を、エフィミアは感じた。
「……ねえ。昨夜ルーファンスが言っていたことは、本気だと思う?」
エフィミアとルーファンスの間でなにがあったかは、すでにアレクスに話してあった。彼は一瞬だけ沈黙して、呟く声で答える。
「分からない……今のルーファンスを理解している者は、おそらくひとりもいない」
エフィミアから体を離して深く長椅子に身を沈めると、アレクスは自嘲じみた笑みを浮かべた。
「情けないな。昔はあんなにも、あいつの考えていることが手にとるように分かったっていうのに」
エフィミアも座り直しながら、アレクスを見た。
「昔?」
「わたしと陛下は、物心つく前から一緒に育っている」
「幼馴染みってこと?」
「世間的に言えばそうだ」
「ルーファンスは子供のときからあんなふうだったの?」
少し考えながらエフィミアが問うと、アレクスは過去を振り返る間をとってから静かな声音で言った。
「昔は、あんな風ではなかった」
遠くを見るように、アレクスは目を細めた。
「ルーファンスは人一倍臆病で、寂しがりやで、わたしがいないといつも泣いていた。王太子という立場にありながら、人前に立つのも苦手で、委縮するあいつを励ますのは随分と苦労した」
懐かしみながら、アレクスはつい苦笑した。
「庭で蝶の死骸を見つけて、かわいそうだと泣きながら土にうめていたこともあったな。それが、いつ変わってしまったのか……」
エフィミアは昨夜の、人の死をなんとも思わないルーファンスの言葉の数々と、そのときの声音や表情を思い返した。あの彼から、小さな虫の死にさえ涙する少年の姿を思い浮かべることができる者が、果たしているだろうか。
「……彼がお父さんに憎まれていたっていうのは、本当なの?」
エフィミアが問えば、アレクスの目元が険しさを帯びた。
「ルーファンスにしてみれば、そういうふうにとらえても不思議はなかったのかもしれない」
「本当は違うの?」
わずかにうつむいて、アレクスは答えた。
「わたしもルーファンスが生まれる以前のことはよく知らないが、先王が王妃をとても溺愛していたと聞いている。そして王妃が出産で亡くなったのも事実だ。だが、先王はルーファンスを憎んではいなかった」
長椅子の布地に手を突いて、エフィミアはわずかに身を乗り出した。
「じゃあ、どうしてルーファンスは……」
アレクスは無表情にエフィミアを見た。
「王妃の死によって、先王は気負い過ぎた」
「どういうこと?」
正面に顔を戻して、アレクスは低く言った。
「自分がルーファンスを立派な王に育て上げなければと、先王は度々こぼしていた。そして、それにこだわり、ルーファンスに厳しく接していた――だが、わたしの目から見ても、先王のやり方は度が過ぎていた」
よく分からずにエフィミアがアレクスを見ていると、彼は説明した。
「先王はルーファンスを規律で縛りつけたんだ。ルーファンスの傍に置く者を厳選し、生活すべてを管理した。日による時間割り、食事内容に学習内容。そのほかすべて、父親の管理下でルーファンスは生活していた。ひとつでも落度があれば、厳しい罰が与えられた。少し時間に遅れた、食事を残した。そんな些細なものであってもだ。言い訳は許されず、逆らえば地下水路に閉じ込められた。許しを得てそこから出してやるのは、大抵わたしの役目だった」
「そんな……」
なんと言ったらいいのか分からず、エフィミアは言葉に詰まった。
確かに規則的な生活をすることは人にとって大切なことだし、食事だって同じだ。だからといって、そこまで厳格に接する必要があるのだろうか。
エフィミアの親は、叱るときには必ず本人の言い分を訊いた上で彼女の落度を叱った。だから理由も訊かずにいきなり厳罰を与えるというのは、どうにも理解できなかった。エフィミアの親が、子供にそんな接し方をすることがなかったから。
「いつもそうだったわけじゃ、ないんでしょう?」
わずかな希望を求めてエフィミアは言ってみたが、アレクスはため息混じりに返した。
「それが常だった。わたしは当事者ではなかったが、幼心に先王を恐いと思うことも多かった。わたしも、これで努力を強いられたんだ。ルーファンスの傍にいるにあたって、無能は許されない――先王はルーファンスに理想を押しつけ過ぎた。ルーファンスにとって、父親は恐怖の対象でしかなかっただろう……他のことなら、尊敬にあたいする王だったんだがな」
言い終わると共にアレクスはエフィミアの肩を抱き寄せ、エフィミアも彼に体を預けた。
理解の範疇を越えた話に、エフィミアはついていけずにいた。ただ漠然と、ルーファンスが辛い思いをしただろうことが分かるだけだった。
エフィミアはルーファンスとは相反する環境で育った。だからルーファンスの本当の心を見ることはできない。それだけは悟った。
エフィミアがぼんやりしていると、アレクスが囁くように呟いた。
「さっきのエフィを見たとき、少し昔を思い出した。ルーファンスは父王に手を上げられるたびに、わたしのところに泣きつきにきていた……いつの間にか、そんなこともなくなっていたな」
「……そっか」
エフィミアが小さく言うと、アレクスは顔を寄せた。
「君のことは、ようすを見てわたしの方からとり合ってみる。わたしとて、これ以上の事態は避けたい」
エフィミアは真っ直ぐ、アレクスの鈍色の瞳を見詰めた。
「うん。信じてる」
二人はそっと触れ合うだけの口づけを交わした。窓の外はいつの間にか赤く染まり始めており、アレクスは職務に戻るため部屋をあとにした。
エフィミアはアレクスの出ていった扉を名残惜しく見詰めていたが、やがて息をひとつ吐いた。
問題はなにひとつ解決してはいなかったが、今は不思議と、さほど思い煩わずにいられた。味方と思える者がいるのといないのとでは、こんなにも心持ちが違う。
(きっと、なんとかなる)
今は、そう思うことができた。
☫
思うことが多すぎて、アレクスはぼんやりしながら廊下を歩いていた。
思考の多くを占めるのは当然のごとく、先ほどまで顔を合わせていたエフィミアと、自分の主君であるルーファンスのことだった。
今では素直に愛しいと思える女性の色々な面を、アレクスは知りつつあった。逆に、今まですべてを理解していたと思っていた幼馴染みのことがなにも分からなくなっていた。
気づいたときには、臆病だった王は内に秘めていただろう残虐性をむき出し始めていた。その事実に、内心で愕然とする。どこで食い違ってしまったのかと、アレクスは思い悩んだ。
いつも泣いてばかりいた少年。いつからか泣かなくなった若年の王。昔と今、ふたつの面影を浮かべながら、アレクスの思考は堂々巡りを繰り返す。
「ブライアント隊長」
不意に呼びかけられて、アレクスは足を止めて振り返った。声の主は、騎竜隊の部下のひとりだった。
黒い制服をきっちり着込んだを部下は、素早く礼をとってから口を開いた。
「隊長の竜のことでご報告が」
「セスがどうした」
不穏なものを感じて、問う声は無意識にきついものになった。部下は臆さず続きを言った。
「先ごろからようすがおかしいのです。すぐに竜舎まできていただけますか」
アレクスは顔色を変えると、返答する間も惜しく駆け出した。
竜舎の小部屋に着くと、若い赤竜がぐったりと床に伏していた。
「セス!」
アレクスが駆け寄って呼びかけると、愛騎セスは閉じていた目を開き、苦しげに呼吸しながら喉を鳴らして顔を上げた。口から唾液の泡を吐き出すセスの頭をアレクスは抱えた。
「無理をするな。どうした、苦しいのか?」
セスはぜいぜいと喉から音をさせながら、痙攣するように体を動かしていた。黄色い目は視点が定まっておらず、鱗には覚えのない傷がある。見れば、セスが直前まで暴れていたろう痕跡が小部屋の中には残っていた。
餌桶がひっくり返って中身が散乱し、竜の巨体がぶつかったらしい壁が、筋状にけずれている。床には食べたものが吐き出されて、異臭が舎内にただよっていた。
アレクスはもがき苦しむセスの体をさすった。なにが起きたのか、さっぱり分からない。朝の定例訓練のときには、なんともなかったはずだ。
これほどいきなり、体に異変をきたすことがあるだろうか。しかし竜の生態について明かされていないことも多いので、明確なことは言えない。
処置をするための道具をそろえさせた上で、アレクスは辛抱強くセスの体を温めながらさすってやった。他人にセスを任せるつもりはなかった。
セスは荒い呼吸を繰り返し、時おり思い出したように体を震わせた。これほど苦しむセスの姿を見るのは初めてだった。様々な原因を考えてみる中で、失うかもしれないという思いがよぎる。
幼い頃からのつき合いになる友の体を、アレクスは祈る心地でさすり続けた。今さら別の竜に乗り換えるなど考えられない。多くの称賛を受けるアレクスの騎竜の技術も、以心伝心で通じ合えるセスとの信頼関係があってこそなのだ。
セスがいなければ、騎竜隊長アレクス・ブライアントはきっと存在しなかった。
どれだけそうしていたか分からない。格子のはまった窓の外から光が失われ始めたころになって、ゆるやかにセスの容態が安定してきた。苦しげだった呼吸も、次第に静かになっていく。
セスの穏やかな呼吸を聞いて、アレクスは小さく息をついた。しかし、まだ予断はできなかった。
(なぜ、今日はこんなことばかりが起こる)
セスの首元に額をあてた。すべらかな鱗の感触と、そこから伝わる確かなぬくもりに、動揺していたアレクスの心も静まっていく。
ふと、ひっくり返ったままの餌桶の中身が目にとまった。
セスから体を離し、泥にまみれた肉片のひとつを拾い上げる。今まで気づかなかったが、それには白い粉状のものがまばらに付着していた。見渡せば、散乱する他の肉片にも同様のものが見られる。
「これは……」
0
あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました
大江戸ウメコ
恋愛
幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!
藤原ライラ
恋愛
ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。
ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。
解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。
「君は、おれに、一体何をくれる?」
呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?
強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。
※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~
双真満月
恋愛
不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。
なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。
※小説家になろうでも掲載中。
※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。
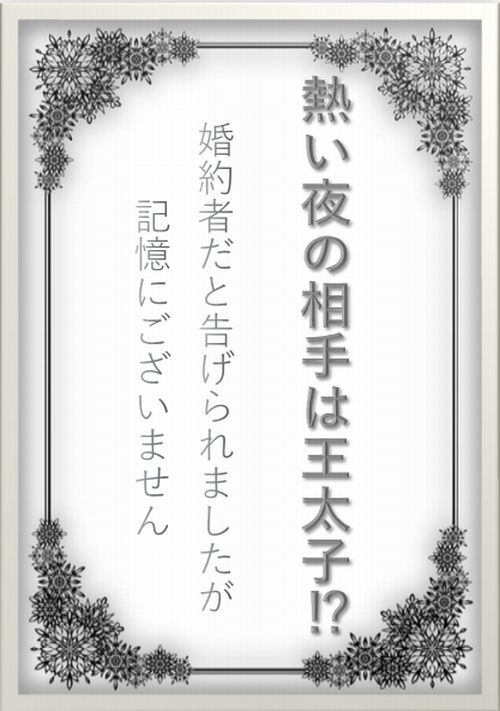
【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~
世界のボボブラ汁(エロル)
恋愛
激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。
──え……この方、誰?
相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。
けれど私は、自分の名前すら思い出せない。
訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。
「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」
……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?
しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。
もしかして、そのせいで私は命を狙われている?
公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。
全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!
※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟
飴爽かに
恋愛
この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。
彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。
クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。
悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~
花虎
恋愛
魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。
だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。
エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。
そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。
「やっと、あなたに復讐できる」
歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。
彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。
過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。
※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~
二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中
恋愛
政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。
彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。
そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。
幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。
そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















