57 / 61
第5章 竜の王国
9 望み
しおりを挟む
ルーファンスの動きが、ぴたりと止まった。アレクスの後頭部に向けて的確に振り下ろしたはずの刃は、もうひとつの刃の基部で行く手を阻まれていた。
「……おれはまだ終わるつもりはない」
ルーファンスの刃を弾きながら剣を回転させて持ち直すと、アレクスは無造作に、しかし素早く立ち上がった。バランスを崩したルーファンスの剣をさらに上へと跳ね上げ、無防備になった腹に十分重みを持たせた蹴りを繰り出す。
ルーファンスは簡単に後ろへ吹っ飛んで尻餅をつき、蹴られた腹部を押さえて何度も咳込んだ。その鼻先へ、アレクスは剣の切っ先を突きつけた。
「初めて意見が食い違ったな」
ルーファンスは尻餅をついたまま、驚いたというよりは呆けたような顔をしていた。だがアレクスと目が合うと、なぜかとても嬉しそうに目元を和ませた。
「違うよ、アレクス。意見が食い違ったことがないんじゃあなくて、いつもアレクスがぼくに合わせてくれていたんだ。……やっぱりアレクスは強いな。初めて君に勝てるかと思ったのに、簡単に全部やり返されちゃった」
「本気で来いと言ったのはお前だ」
アレクスが気のない調子で言えば、ルーファンスは本当に無邪気に笑いながら、そうだねと返した。剣を突きつけられているのを気にした風もなく、ルーファンスはアレクスにほほ笑みかけた。
「殺さないの? 反逆者は主君を殺すものだと、ぼくは思っていたけれど」
アレクスはつかの間黙って、ルーファンスを見据えた。ルーファンスの表情は穏和そのもので、彼が本当に自分が追い詰められていることを分かっているのか、アレクスははかりかねた。
「ルー。おれたちは一度、きちんと話したほうがいい」
ルー、と呼んだとき、ルーファンスの表情がわずかに動いたのが分かった。少し驚いたように目を見開き、だがすぐに、今度は無表情になってルーファンスはややうつむいた。
「アレクス、それを言うなら遅いよ。もうそれではすまないところまで来てしまった」
顔を上げたルーファンスは、睨む眼差しでアレクスを見据えた。
「見捨てたのは君だ――もう誰も信じない。みんな嫌いだ。君も、嫌いだ」
ひゅんと音をさせて、ルーファンスの剣が空を切った。
☫
ルーファンスがアレクスの刃に刃を叩きつけても、彼の手から剣が離れることはなかった。
やはりアレクスは強い。ルーファンスが素早く立ち上がるわずかな間に、もう剣を構え直している。
アレクスの隣にいて劣等感を感じないと言ったら、そんなもの嘘でしかない。
彼はこんなにも才気に満ちあふれているのに、なぜ自分にはなにひとつそれがないのだろう。なぜ彼ではなく、自分が王という位置にいるのだろう。そんな思いが、ぐるぐると頭の中を巡る。
(もう、いやだ)
肖像画でしか知らぬ母を恋しい思ったことはある。きっと母ならば、愚鈍なルーファンスを無条件で愛して守ってくれると思ったからだ。
ただその思い以上に、父が好きだった。恐かったけれど、どうしても嫌いになることだけはできなかった。
父に傷つけられてルーファンスは何度も死ぬ思いをしたけれど、叔父の毒牙からルーファンスの命を守ってくれていたのもまた父だったのだから。
優れた王だった父。我が子の非才を受け入れられなかった父。
好きだと言ってもらえなくていい。ただ一言「よくやった」と頭を撫で、抱き締めて貰えることを夢見て、ルーファンスは父の傍を離れずにいた。
母と間違えてベッドへ引き込まれたときでさえ、毒の蓄積で朦朧としつつあった父を嫌な気持ちにさせないように母の振りをしてみせたのに――一度も息子として頭を撫でてもらえないまま、父はいなくなってしまった。
(もう、いやだ……)
エフィミアのことが、ルーファンスは大嫌いだった。
彼女は親に、友に、恵まれて当たり前に愛情を享受してきた者だ。ルーファンスが欲してやまないものすべてを持っている。それなのに、ルーファンスが必死でつかんでいるもの、つかもうとしているものすべてを横から奪っていく。
だから、どうしても自分と同じにしてやりたかった。縋る先のない絶望に落としてやりたかった。彼女を殴ったこともレイプしたことも、後味が悪かったとしても行為そのものに対する罪悪感は微塵もない。
しかし何度突き落としても、何度でも彼女を救う者が現れて這い上がってきた――許せなかった。
ルーファンスが父に傷つけられたとき、アレクスは閉じ込められた場所から連れ出して傷の手当てをしてくれたけれど、やめろと声をあげて父を止めてくれたことは一度もなかった。
ところがエフィミアのためには、やめろ! と叫んだのだ。ルーファンスに向かって!
(もう、いやなんだ……)
ルーファンスはアレクスに向かって、無謀なほど強引な一歩を踏み出した。
(お願い、誰か)
ルーファンスの行動に驚いたのか、アレクスがわずかに目を見開いた。
(ぼくを――)
自分に向かって真っ直ぐ突き出される銀を、ルーファンスは見た。
(ぼくを、殺して)
ルーファンスの体の中心を、灼熱が貫いた。
☫
剣を握る掌に感じた感触と、目の前に散った赤に、アレクスの思考は停止した――なにが起こったのか、分からなかった。
構えるアレクスに向かって強引に突っ込んできたルーファンスに、剣を繰り出した。だが、傷つけるための一手ではなかった。はたから見ても分かるほどにごく単純で直線的なひと太刀。
アレクスに届かなくとも、ルーファンスの剣の腕が他に劣るわけではない。彼の実力があれば十分に避けられる。だから避けた隙を捕まえて、取り押さえようとした。そのはずの一手だった。
手の中にある剣は、ルーファンスの体を完全に刺し貫いていた。自分が刺されたとき以上の混乱が、アレクスを支配した。
高い音を響かせて、ルーファンスの手から剣が床に滑り落ちた。ぐったりともたれかかってきた幼馴染みの体を、アレクスは慌てて剣を放して抱きとめ、その細さに息をのんだ。
もともと痩せぎみの少年ではあった。だが今の彼は痩せ気味どころか、服越しにも関わらず細い骨格の形まで感じられた。
「ルー、これは、どういう……お前、なぜ……っ」
アレクスは思考停止状態から回復できず、うまく言葉が繋がらなかった。
ルーファンスの体が沈むようにずるずるとくずおれる。アレクスは咄嗟に膝を突いて、彼を抱きかかえることしかできなかった。
ルーファンスは口の端から血の混じった唾液をしたたらせ、か細い呼吸を繰り返しながら、自分の中心を貫いている剣の柄を握った。そのまま喉の奥から呻きをもらし、体から剣を引き抜く。それを見て、アレクスの頭の奥がようやく冴えた。
「よせっ」
やめさせようとしたが、もう遅かった。剣は肉をこするいやな音をさせて、ルーファンスの体から完全に引き抜かれた。傷口から真っ赤な鮮血が噴き出した。
「ルーっ!」
アレクスは急いで自分の上着を脱ぎ、ルーファンスの傷口に強く押しあてた。おそらく太い血管を傷つけたのだろう。必死なアレクスをあざ笑うように血はあふれ、こんな応急処置ではとても間に合わない。止血しようと押し当てた上着がまたたく間に重く濡れていく。
「誰か――」
「呼ばないでっ」
人を呼ぼうとしたアレクスを、ルーファンスが鋭く押し止めた。ルーファンスはかろうじて体勢を動かし、むき出しのアレクスの上半身にしがみついた。
「誰も呼ばないで」
「だがっ」
アレクスにしがみつく指に、わずかに力がこもった。
「いいんだ、これで……このままがいい。ぼくは、アレクスといたい……」
ルーファンスは求めるように、アレクスの胸へと顔をうずめた。熱い吐息と極細の金髪が、アレクスの素肌をかすめていく。
「アレクス……もうどこにもいかないで……ぼくを置いていかないで。ひとりにしないで……、ぼくは……なにもできないっ。……お願い、傍にいて……アレクス……アレク、ス…う……っ。父、上……父上、父上ぇ……っ」
後半ルーファンスの声は徐々に涙声となり、ぐすぐすと嗚咽を漏らし始め、ついにはアレクスの胸に顔を押しつけて慟哭した。縋りつく手に応えるようにアレクスはルーファンスの細い体に腕を回し、きつく抱き締めた。
何度もしゃくりあげ血を吐きながら、幼子のようにルーファンスは泣いた。長い年月、体内に蓄積し続けていたものが声となり涙となり、体外にあふれだす。泣きじゃくるルーファンスを、アレクスは昔そうしていたように、ただじっと抱き締めた。
ルーファンスは昔となにひとつ変わっていない。そのことにアレクスはようやく気づいた。
十八年前、自分に向かって伸ばされた小さな手をアレクスはとった。そのときに感じた胸の高鳴りを、大人になった今でも覚えている。自分に向けられる笑顔がまぶしくて、縋りつく手が愛しくて、気づけばいつも一緒にいた。ルーファンスも、アレクスの傍を離れようとしなかった。
だがいつしか、それではいけないとアレクスは思うようになった。
いつまでも馴れ合った関係のままでは、きっとルーファンスは成長してからもアレクスに頼りきりになってしまう。そのまま上下関係まであやふやになってしまっては、王家に仕えるはずの家臣たちにまでなめられることになるのだ。
次期王のルーファンスにとって、それはよくないことだ。だからアレクスはルーファンスから一歩距離を置き、幼馴染みではなくただの臣として振舞うようになった。
距離を置いたことで、ルーファンスの手はアレクスに届かなくなった。だがそれでも、ルーファンスは必死に手を伸ばし続けていた。臆病な少年は、その手をとってくれる者をひたすらに待ち続けていた。
そのことに、アレクスは今まで気づかなかった。ルーファンスが泣かなかったから。
いつからか泣かなくなったルーファンスを見て、強くなったのだと勝手に勘違いをしていた。けれどルーファンスは変わっていなかった。今でも臆病で泣き虫な少年のままだった。
泣かなくなった――泣けなくなった少年が、ようやく泣くことができた。今は存分に泣かせてやればいい。泣いて、泣いて、気づけば泣きつかれて、アレクスの腕の中で眠ってしまっている――いつものことだ。それが、二人の至福なのだ。
ふとアレクスは、腕の中で泣いていたルーファンスが静かになっていることに気づいた。優しく髪を撫でてやり、わずかに体を離してルーファンスの顔を覗き込んだ。
「ルー、寝たのか?」
アレクスにしがみついていたルーファンスの腕がはずれ、力なく垂れた。アレクスの体から離れるのに合わせてがくりと首がのけぞり、腕から滑り落ちそうになる。
「おい、ルーっ」
慌てて抱え直しながら、アレクスの心臓は凍りついていた。ルーファンスの全体重が、腕にのしかかってくる。ルーファンスの体を、アレクスはそっと揺すぶってみた。
「ルー、起きられるか? 少しでいい。少しだけ眠いのを我慢して、一度部屋に戻ろう。ここで寝てはだめだ。なあ、ルー……起きろ……」
呼びかけながら、アレクスは泣いたせいで汚れ切ったルーファンスの顔に触れた――息は、なかった。
若者の叫び声が、広大な部屋の隅々まで響き渡った。
「……おれはまだ終わるつもりはない」
ルーファンスの刃を弾きながら剣を回転させて持ち直すと、アレクスは無造作に、しかし素早く立ち上がった。バランスを崩したルーファンスの剣をさらに上へと跳ね上げ、無防備になった腹に十分重みを持たせた蹴りを繰り出す。
ルーファンスは簡単に後ろへ吹っ飛んで尻餅をつき、蹴られた腹部を押さえて何度も咳込んだ。その鼻先へ、アレクスは剣の切っ先を突きつけた。
「初めて意見が食い違ったな」
ルーファンスは尻餅をついたまま、驚いたというよりは呆けたような顔をしていた。だがアレクスと目が合うと、なぜかとても嬉しそうに目元を和ませた。
「違うよ、アレクス。意見が食い違ったことがないんじゃあなくて、いつもアレクスがぼくに合わせてくれていたんだ。……やっぱりアレクスは強いな。初めて君に勝てるかと思ったのに、簡単に全部やり返されちゃった」
「本気で来いと言ったのはお前だ」
アレクスが気のない調子で言えば、ルーファンスは本当に無邪気に笑いながら、そうだねと返した。剣を突きつけられているのを気にした風もなく、ルーファンスはアレクスにほほ笑みかけた。
「殺さないの? 反逆者は主君を殺すものだと、ぼくは思っていたけれど」
アレクスはつかの間黙って、ルーファンスを見据えた。ルーファンスの表情は穏和そのもので、彼が本当に自分が追い詰められていることを分かっているのか、アレクスははかりかねた。
「ルー。おれたちは一度、きちんと話したほうがいい」
ルー、と呼んだとき、ルーファンスの表情がわずかに動いたのが分かった。少し驚いたように目を見開き、だがすぐに、今度は無表情になってルーファンスはややうつむいた。
「アレクス、それを言うなら遅いよ。もうそれではすまないところまで来てしまった」
顔を上げたルーファンスは、睨む眼差しでアレクスを見据えた。
「見捨てたのは君だ――もう誰も信じない。みんな嫌いだ。君も、嫌いだ」
ひゅんと音をさせて、ルーファンスの剣が空を切った。
☫
ルーファンスがアレクスの刃に刃を叩きつけても、彼の手から剣が離れることはなかった。
やはりアレクスは強い。ルーファンスが素早く立ち上がるわずかな間に、もう剣を構え直している。
アレクスの隣にいて劣等感を感じないと言ったら、そんなもの嘘でしかない。
彼はこんなにも才気に満ちあふれているのに、なぜ自分にはなにひとつそれがないのだろう。なぜ彼ではなく、自分が王という位置にいるのだろう。そんな思いが、ぐるぐると頭の中を巡る。
(もう、いやだ)
肖像画でしか知らぬ母を恋しい思ったことはある。きっと母ならば、愚鈍なルーファンスを無条件で愛して守ってくれると思ったからだ。
ただその思い以上に、父が好きだった。恐かったけれど、どうしても嫌いになることだけはできなかった。
父に傷つけられてルーファンスは何度も死ぬ思いをしたけれど、叔父の毒牙からルーファンスの命を守ってくれていたのもまた父だったのだから。
優れた王だった父。我が子の非才を受け入れられなかった父。
好きだと言ってもらえなくていい。ただ一言「よくやった」と頭を撫で、抱き締めて貰えることを夢見て、ルーファンスは父の傍を離れずにいた。
母と間違えてベッドへ引き込まれたときでさえ、毒の蓄積で朦朧としつつあった父を嫌な気持ちにさせないように母の振りをしてみせたのに――一度も息子として頭を撫でてもらえないまま、父はいなくなってしまった。
(もう、いやだ……)
エフィミアのことが、ルーファンスは大嫌いだった。
彼女は親に、友に、恵まれて当たり前に愛情を享受してきた者だ。ルーファンスが欲してやまないものすべてを持っている。それなのに、ルーファンスが必死でつかんでいるもの、つかもうとしているものすべてを横から奪っていく。
だから、どうしても自分と同じにしてやりたかった。縋る先のない絶望に落としてやりたかった。彼女を殴ったこともレイプしたことも、後味が悪かったとしても行為そのものに対する罪悪感は微塵もない。
しかし何度突き落としても、何度でも彼女を救う者が現れて這い上がってきた――許せなかった。
ルーファンスが父に傷つけられたとき、アレクスは閉じ込められた場所から連れ出して傷の手当てをしてくれたけれど、やめろと声をあげて父を止めてくれたことは一度もなかった。
ところがエフィミアのためには、やめろ! と叫んだのだ。ルーファンスに向かって!
(もう、いやなんだ……)
ルーファンスはアレクスに向かって、無謀なほど強引な一歩を踏み出した。
(お願い、誰か)
ルーファンスの行動に驚いたのか、アレクスがわずかに目を見開いた。
(ぼくを――)
自分に向かって真っ直ぐ突き出される銀を、ルーファンスは見た。
(ぼくを、殺して)
ルーファンスの体の中心を、灼熱が貫いた。
☫
剣を握る掌に感じた感触と、目の前に散った赤に、アレクスの思考は停止した――なにが起こったのか、分からなかった。
構えるアレクスに向かって強引に突っ込んできたルーファンスに、剣を繰り出した。だが、傷つけるための一手ではなかった。はたから見ても分かるほどにごく単純で直線的なひと太刀。
アレクスに届かなくとも、ルーファンスの剣の腕が他に劣るわけではない。彼の実力があれば十分に避けられる。だから避けた隙を捕まえて、取り押さえようとした。そのはずの一手だった。
手の中にある剣は、ルーファンスの体を完全に刺し貫いていた。自分が刺されたとき以上の混乱が、アレクスを支配した。
高い音を響かせて、ルーファンスの手から剣が床に滑り落ちた。ぐったりともたれかかってきた幼馴染みの体を、アレクスは慌てて剣を放して抱きとめ、その細さに息をのんだ。
もともと痩せぎみの少年ではあった。だが今の彼は痩せ気味どころか、服越しにも関わらず細い骨格の形まで感じられた。
「ルー、これは、どういう……お前、なぜ……っ」
アレクスは思考停止状態から回復できず、うまく言葉が繋がらなかった。
ルーファンスの体が沈むようにずるずるとくずおれる。アレクスは咄嗟に膝を突いて、彼を抱きかかえることしかできなかった。
ルーファンスは口の端から血の混じった唾液をしたたらせ、か細い呼吸を繰り返しながら、自分の中心を貫いている剣の柄を握った。そのまま喉の奥から呻きをもらし、体から剣を引き抜く。それを見て、アレクスの頭の奥がようやく冴えた。
「よせっ」
やめさせようとしたが、もう遅かった。剣は肉をこするいやな音をさせて、ルーファンスの体から完全に引き抜かれた。傷口から真っ赤な鮮血が噴き出した。
「ルーっ!」
アレクスは急いで自分の上着を脱ぎ、ルーファンスの傷口に強く押しあてた。おそらく太い血管を傷つけたのだろう。必死なアレクスをあざ笑うように血はあふれ、こんな応急処置ではとても間に合わない。止血しようと押し当てた上着がまたたく間に重く濡れていく。
「誰か――」
「呼ばないでっ」
人を呼ぼうとしたアレクスを、ルーファンスが鋭く押し止めた。ルーファンスはかろうじて体勢を動かし、むき出しのアレクスの上半身にしがみついた。
「誰も呼ばないで」
「だがっ」
アレクスにしがみつく指に、わずかに力がこもった。
「いいんだ、これで……このままがいい。ぼくは、アレクスといたい……」
ルーファンスは求めるように、アレクスの胸へと顔をうずめた。熱い吐息と極細の金髪が、アレクスの素肌をかすめていく。
「アレクス……もうどこにもいかないで……ぼくを置いていかないで。ひとりにしないで……、ぼくは……なにもできないっ。……お願い、傍にいて……アレクス……アレク、ス…う……っ。父、上……父上、父上ぇ……っ」
後半ルーファンスの声は徐々に涙声となり、ぐすぐすと嗚咽を漏らし始め、ついにはアレクスの胸に顔を押しつけて慟哭した。縋りつく手に応えるようにアレクスはルーファンスの細い体に腕を回し、きつく抱き締めた。
何度もしゃくりあげ血を吐きながら、幼子のようにルーファンスは泣いた。長い年月、体内に蓄積し続けていたものが声となり涙となり、体外にあふれだす。泣きじゃくるルーファンスを、アレクスは昔そうしていたように、ただじっと抱き締めた。
ルーファンスは昔となにひとつ変わっていない。そのことにアレクスはようやく気づいた。
十八年前、自分に向かって伸ばされた小さな手をアレクスはとった。そのときに感じた胸の高鳴りを、大人になった今でも覚えている。自分に向けられる笑顔がまぶしくて、縋りつく手が愛しくて、気づけばいつも一緒にいた。ルーファンスも、アレクスの傍を離れようとしなかった。
だがいつしか、それではいけないとアレクスは思うようになった。
いつまでも馴れ合った関係のままでは、きっとルーファンスは成長してからもアレクスに頼りきりになってしまう。そのまま上下関係まであやふやになってしまっては、王家に仕えるはずの家臣たちにまでなめられることになるのだ。
次期王のルーファンスにとって、それはよくないことだ。だからアレクスはルーファンスから一歩距離を置き、幼馴染みではなくただの臣として振舞うようになった。
距離を置いたことで、ルーファンスの手はアレクスに届かなくなった。だがそれでも、ルーファンスは必死に手を伸ばし続けていた。臆病な少年は、その手をとってくれる者をひたすらに待ち続けていた。
そのことに、アレクスは今まで気づかなかった。ルーファンスが泣かなかったから。
いつからか泣かなくなったルーファンスを見て、強くなったのだと勝手に勘違いをしていた。けれどルーファンスは変わっていなかった。今でも臆病で泣き虫な少年のままだった。
泣かなくなった――泣けなくなった少年が、ようやく泣くことができた。今は存分に泣かせてやればいい。泣いて、泣いて、気づけば泣きつかれて、アレクスの腕の中で眠ってしまっている――いつものことだ。それが、二人の至福なのだ。
ふとアレクスは、腕の中で泣いていたルーファンスが静かになっていることに気づいた。優しく髪を撫でてやり、わずかに体を離してルーファンスの顔を覗き込んだ。
「ルー、寝たのか?」
アレクスにしがみついていたルーファンスの腕がはずれ、力なく垂れた。アレクスの体から離れるのに合わせてがくりと首がのけぞり、腕から滑り落ちそうになる。
「おい、ルーっ」
慌てて抱え直しながら、アレクスの心臓は凍りついていた。ルーファンスの全体重が、腕にのしかかってくる。ルーファンスの体を、アレクスはそっと揺すぶってみた。
「ルー、起きられるか? 少しでいい。少しだけ眠いのを我慢して、一度部屋に戻ろう。ここで寝てはだめだ。なあ、ルー……起きろ……」
呼びかけながら、アレクスは泣いたせいで汚れ切ったルーファンスの顔に触れた――息は、なかった。
若者の叫び声が、広大な部屋の隅々まで響き渡った。
0
あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました
大江戸ウメコ
恋愛
幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!
藤原ライラ
恋愛
ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。
ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。
解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。
「君は、おれに、一体何をくれる?」
呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?
強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。
※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~
双真満月
恋愛
不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。
なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。
※小説家になろうでも掲載中。
※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。
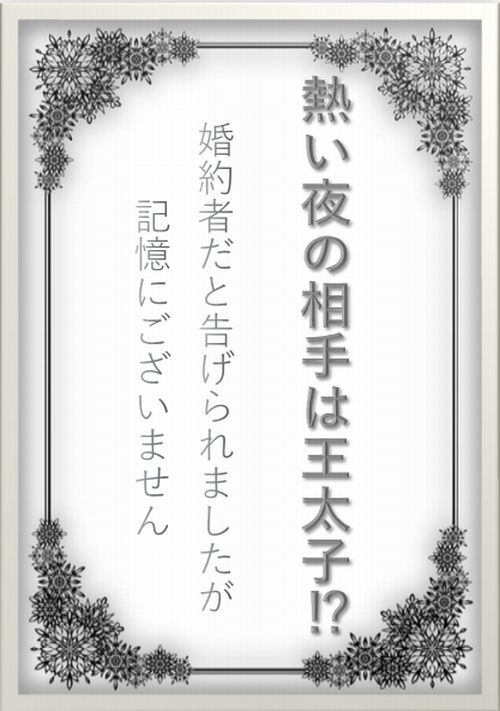
【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~
世界のボボブラ汁(エロル)
恋愛
激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。
──え……この方、誰?
相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。
けれど私は、自分の名前すら思い出せない。
訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。
「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」
……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?
しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。
もしかして、そのせいで私は命を狙われている?
公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。
全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!
※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟
飴爽かに
恋愛
この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。
彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。
クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。
悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~
花虎
恋愛
魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。
だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。
エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。
そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。
「やっと、あなたに復讐できる」
歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。
彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。
過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。
※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~
二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中
恋愛
政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。
彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。
そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。
幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。
そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















