2 / 5
2.彼が部活に入らない理由
しおりを挟む
時は少し遡り、五月の初旬。
季節で言えば梅雨の時期だが、全国的も雨の日は少なく、ここ舞台市でも強い日差しがさんさんと降り注いでいた。
そんなクソ熱い日のお昼時、俺は――、
「そろそろ出さないと不味いんだってば!」
「先生、その発言は色々と誤解を招くから止めた方がいいと思いますよ?」
人影のない学校の校舎の陰で、更に暑苦しい懇願を受けていた……。
相手は、俺の担任の垢嘗下手先生。
垢嘗先生は三十代前半の眼鏡をかけた男性教諭であり、今日は暑さの所為か、ワイシャツの長袖を腕まくりし、ネクタイを緩めていた。
俺は彼のその格好に、非難の目を向ける。
こっちは校則上、こんな真夏のような日でも『だらしないから』という理由で、学ランを脱いでれば注意されてしまう。
だというのに模範となる教師がこれでは、まるで説得力が無い。
だらしなさの権化だ。
とても教師には見えない。溶けたスライムのようだ。
垢嘗先生は、そんな格好でも熱いのか、開いたワイシャツの首元に指を突っ込み、ばさばさと動かし風を入れる。
「俺だって注意されてるよ。でも、こんなクソ暑い日にんなもん守れるかっての。お前も熱かったら脱げばいいだろ?」
「先生、発言がいちいちいかがわしいですよ」
「ふざけてる場合じゃないんだよ! 急かされてるのこっちの身にもなってくれよ!?」
「分かったから顔を近づけてこないでくださいよ……。暑苦しいな……」
本来の要件を思い出したらしく、垢嘗先生は俺の肩を掴むと、鼻息荒く隈が浮かぶ顔面を間近に近づけてきた。
勘弁してほしい……。
ただでさえ、人と目を合わせられないというのに、こんなに近づかれては困る。
しかも、相手は汗だくの冴えない男だ。余計、目に入れたくない……。
俺は垢嘗先生から視線を逸らした。
「入学してもう一ヶ月は経ってるのに、入部してないのはお前だけなんだからな? 流石にもうどの部活に入るか決まっただろ?」
「いやー、まだ迷ってまして。やっぱり部活動て入らなくちゃいけませんか?」
ダメ押しで確認してみるも、垢嘗先生は首を横に振る。
「劇場館高校の生徒全員入部するのが校則で決まってるんだよ。入学式に校長先生が講堂で話してたの聞いただろ?」
「いや、確かに言ってましたけど……」
俺の通う、『舞台私立劇場館高等学校』は、舞台市の中でも特に歴史の古い名門校だ。
そんな伝統あるこの学校で、今現在でもある校則の一つが、『全校生徒の部活動入部』。
帰宅部などという世迷い言は許されず、よほどの家庭的事情でも無い限りは、この校則は絶対であり、強力なまでの強制力を持つ。
俺もこれまでにどうにかして避けよう避けようとしていたが、遂に今日のお昼休みに入って早々に、昼食も食べられないまま垢嘗先生に捕まり、この人気の無い校舎の片隅まで連れて来られたというわけだ。
「でも入りたい部活とか特に無いんですよねぇ。流石にやる気も無いのに入部するのも不味いでしょ?」
「お前は考えすぎなんだよ。興味ありそうな所に適当に入って、後はそれなりにやってればいいんだってば。それで万事解決。俺も校長に呼び出されることもなくなる」
「それ、教師のアドバイスとしてどうなんすかね?」
俺の指摘を、垢嘗先生は鼻で笑った。
「はっ! 今時青春ドラマの真似事なんざできるかってんだよ! ただでさえテストの採点やら、部活動の顧問やら、厄介なモンスターの相手までして、その他もろもろの雑用があるっていうのに……っ。わざわざ部屋にまで呼びつけて『まだ入部していない生徒がいるようですねぇ~?』とか煽ってくるんだぞ!? あの野郎はァ……ッ!! くぁー! こっちはそれどころじゃないつぅーの!?」
よほどストレスがたまっているのだろう。
特定の名前は出していないものの、俺にはその人物が誰なのかが容易に想像できた。
担任教師ながら、少し同情してしまう。
「だから頼むよ! お前が入部届け出してくれるだけで、俺の業務が一つ減るんだよ! もう忙しい中、校長に呼びだされるのなんてごめんなんだ!!」
「せっかく伏せてたのに自分でバラしてどうするんですか」
「やべっ!? つい本音が!」
垢嘗先生は慌てて両手で口を押さえ、忙しそうに首を動かして周りを見渡した後、安堵の息を吐き出した。
どうやら、周りには誰もいなかったようだ。
普段パチンコで負けてるくせに、こういう時だけ運がいい。
「とにかく、入部に関しては絶対条件だ。どうしてもいやなら転校でもしろ。てか、入部が嫌なら、なんでこの学校に入ったんだよ?」
「家から近かったからに決まってるじゃないですか。高校なんてどれも同じだと思ってたら、とんだ罠っすよ」
「安直な理由で決めた、お前の自業自得だろうが……素直に諦めろ。ともかくだ、後一週間だけ待ってやる。その期間でなんとか決めろよ? もしそれでも決まらなかったら……」
「決まらなかったら?」
「お前を帰さない」
「その発言、モンスター召喚呪文になりません?」
「あ、やっべ。て、親御さんにチクるなよ? いや、振りとかじゃなくて絶対だからなマジで本当お願いします」
厄介ごとを避けるためならば、自分の生徒にすら敬語を使って頭を下げる。
それが、垢嘗という教師だった。
見てるこっちが悲しくなる。
そんな不憫な担任を俺は気の毒に感じ、長く伸びた前髪を右手で少し上げ、彼を軽く見た。
ふん、ふん、なるほどな。
「先生、いくら忙しいからって流石に四時間睡眠は不味いすよ。食生活もインスタント麺多めだし。後、教師なんだから風俗嬢と遊ぶのも程々にしといた方がいいすよ。んじゃ」
「んなこと言ったって、睡眠時間削らないと、逆に自分の時間がなくなるし、飯だって簡単に済ませた方が楽……て、おい待て、どうして風俗のこと知ってるんだ……? おい!?」
釈明するのも面倒なので、百目鬼はそそくさにその場を後にした。
◇◇◇
「調子乗って使うんじゃなかったかな。まあ、あの先生鈍い大丈夫だろう」
俺は再び目を前髪の中に隠し、先端を指でつまんでねじる。
髪をねじり遊ばせながら考えるのは先ほどの、部活動入部の話しだ。
俺だって何も、部活動そのものが嫌だというわけじゃない。
入ればきっとそれなりに楽しいだろうし、今しかできない経験だとも思うから入部できるなら、入部したい。
でも俺には、容易にそれを出来ない理由があった。
「この目がある以上、迂闊に何かやるわけにはいかないんだよなぁ……」
俺は先ほど髪先を掴んでた右手を下にスライドさせて、両目の近くをなぞる。
俺が部活動に入れない理由――それは、俺の『目』にはある特殊な能力が備わっていたからだ。
俺の目は、外見から得られた情報を光速で処理し、可視化して見ることができた。
つまり、人物や物の外見情報を文字にして読むことができる超観察能力。
同級生で友人の滑倉璃からは、『シャーロック・ホームズみたいだね』と表現されたこともあったが、あの世界的名探偵と俺の目の性質は、似て非なるものだ。
シャーロック・ホームズは、『観察をする』という過程を踏んだ上で、答えを導く。
だが、俺の目の場合は、見ただけで、『自動的』に答えが表示される。
どのような箇所を見て、そんなことが分かったのか。
どのような考えで、そんな結論に至ったのか。
俺には分からない。考えもつかない――だが、今までその答えが間違ったことはない。
外見から得られる情報ならば、どんなことでも見えるし分かる。
それが、俺の目の能力だ。
だから俺は先ほど、垢嘗先生の私生活を言い当てることができたというわけだ。
彼の周りには、以下の文字が表示されていた。
“睡眠時間:四時間から四時間半”
“食生活偏り気味、主食:カップ麺”
“昨晩、女性との性行為あり”
などなどだ。
風俗嬢云々に関しては簡単な推理だ。
あの先生に彼女はいない。
一件便利そうに見えるこの能力だが、全くもってそんなことはない。
迂闊に目を解放しようものなら、大量の外部情報が頭の中に飛び込んでくるんだ。
そうしたらとてもじゃないが、処理しきれない情報量に脳がパンクして、ぶっ倒れてしまう。
だからこんな真夏に近い暑さだろうと、俺は前髪を長く伸ばしたままだ。
こうすることで、前髪が気になり、それら情報をある程度処断することができた。
長さに関しても、頭髪検査に引っかからないギリギリのラインを心得ているので、注意もされることはない。そこら辺も完璧だ。
では本題だが、もしこんな厄介な目を持つ俺が、もし何かしらの部活動に参加したらどうなるか?
「目のことバレたら……絶対に酷使されるんだろうな……」
球技系統の部活に入れば、ボールの軌道や、相手の動きが事前に分かるので酷使される。
陸上系の部活に入れば、相手の残り体力や、走り方の軌道、ペース配分が分かるので、体力差や身体的な面を大きくカバー出来るため、結果的に酷使される。
文化部系の部活に入ったとしても、この目を使えば大概のことはどうにでもなるため、やっぱり酷使される。
つまるところ、俺の目を使えば大概の活動は簡単になってしまう。というわけだ。
でも、これにも問題がある。
先ほども言った通り、俺の目を解放すれば、大量の情報に耐えきれずオーバフローを起こして倒れてしまう。
部活動は、多かれ少なかれ集団行動。
目を使う事なんて殆どできないだろう。
だから現実問題、上記のような活躍はできないしないんだ。
むしろ、役に立たない方が多い。
出来ることといえば、雑用作業くらいだろうが、そんなことをしていては、それこそ何のために部活に入ったのか分からない。
結果、俺は完全に詰んでいた。
どの部活に入っても、どの活動をしてもお荷物。
だから、俺は入学して一ヶ月も経っているのに、入る部活を未だに決められないでいた。
「あーあ、この目を使っても大丈夫な部活ってなんだろうなぁ……」
空を仰いで見るも、都合のいい答えなど出るはずもない。
ただ、学校の廊下の白い天井が見えるだけだ。
そんな時だ。
「んがっ!?」
太陽の光が一直線に差す、階段の踊り場に差し掛かった時、突然俺の顔の上に一枚の紙が飛んできた。
「なんだこれ?」
俺は紙を顔から剥がす。
紙にはびっちりと文字が書かれており、普通なら何が書いてあるがすぐには分からないが、俺はその紙を直接『目』で見てしまったため、紙に書かれた内容がすぐに表示された。
「これは小説の原稿か。でもなんで一枚だけ……いや、違う」
周りを見渡すと、踊り場には大量にばらまかれた紙の束が散らばっていた。
この紙もきっと、その中の一枚だったんだろう。
その証拠に、少し離れたところには、この紙の束をまとめていたと思われるクリップが落ちていた。
俺は再び紙の内容を読もうとしたが、太陽の光に照らされていた原稿に、一気に陰を落ちた。
俺は上を見上げる。
すると、階段の中間地点からこちらを見下ろす、一つの長細い陰。
その陰は人の形をしていたが、顔を確認することは出来ない。
だが、三つ編みの髪型とスカートのシルエットから、その人物が女子であることは分かった。
女子生徒の陰は、上からゆっくりと一歩ずつ階段を降り、俺のいる踊り場に来てようやく、その顔を確認することができた。
華奢で、線の細い曲線で描かれたような顔をした、黒縁眼鏡をかけた少女。
その外見からして、『文学少女』という言葉がとても似合う女子生徒だった。
そんな彼女は、夏の暑さすら涼しげに感じてしまうほどの絶対零度の真顔が、俺を見ていた。
何かを確かめるように、ただじっと、俺を見ていた。
季節で言えば梅雨の時期だが、全国的も雨の日は少なく、ここ舞台市でも強い日差しがさんさんと降り注いでいた。
そんなクソ熱い日のお昼時、俺は――、
「そろそろ出さないと不味いんだってば!」
「先生、その発言は色々と誤解を招くから止めた方がいいと思いますよ?」
人影のない学校の校舎の陰で、更に暑苦しい懇願を受けていた……。
相手は、俺の担任の垢嘗下手先生。
垢嘗先生は三十代前半の眼鏡をかけた男性教諭であり、今日は暑さの所為か、ワイシャツの長袖を腕まくりし、ネクタイを緩めていた。
俺は彼のその格好に、非難の目を向ける。
こっちは校則上、こんな真夏のような日でも『だらしないから』という理由で、学ランを脱いでれば注意されてしまう。
だというのに模範となる教師がこれでは、まるで説得力が無い。
だらしなさの権化だ。
とても教師には見えない。溶けたスライムのようだ。
垢嘗先生は、そんな格好でも熱いのか、開いたワイシャツの首元に指を突っ込み、ばさばさと動かし風を入れる。
「俺だって注意されてるよ。でも、こんなクソ暑い日にんなもん守れるかっての。お前も熱かったら脱げばいいだろ?」
「先生、発言がいちいちいかがわしいですよ」
「ふざけてる場合じゃないんだよ! 急かされてるのこっちの身にもなってくれよ!?」
「分かったから顔を近づけてこないでくださいよ……。暑苦しいな……」
本来の要件を思い出したらしく、垢嘗先生は俺の肩を掴むと、鼻息荒く隈が浮かぶ顔面を間近に近づけてきた。
勘弁してほしい……。
ただでさえ、人と目を合わせられないというのに、こんなに近づかれては困る。
しかも、相手は汗だくの冴えない男だ。余計、目に入れたくない……。
俺は垢嘗先生から視線を逸らした。
「入学してもう一ヶ月は経ってるのに、入部してないのはお前だけなんだからな? 流石にもうどの部活に入るか決まっただろ?」
「いやー、まだ迷ってまして。やっぱり部活動て入らなくちゃいけませんか?」
ダメ押しで確認してみるも、垢嘗先生は首を横に振る。
「劇場館高校の生徒全員入部するのが校則で決まってるんだよ。入学式に校長先生が講堂で話してたの聞いただろ?」
「いや、確かに言ってましたけど……」
俺の通う、『舞台私立劇場館高等学校』は、舞台市の中でも特に歴史の古い名門校だ。
そんな伝統あるこの学校で、今現在でもある校則の一つが、『全校生徒の部活動入部』。
帰宅部などという世迷い言は許されず、よほどの家庭的事情でも無い限りは、この校則は絶対であり、強力なまでの強制力を持つ。
俺もこれまでにどうにかして避けよう避けようとしていたが、遂に今日のお昼休みに入って早々に、昼食も食べられないまま垢嘗先生に捕まり、この人気の無い校舎の片隅まで連れて来られたというわけだ。
「でも入りたい部活とか特に無いんですよねぇ。流石にやる気も無いのに入部するのも不味いでしょ?」
「お前は考えすぎなんだよ。興味ありそうな所に適当に入って、後はそれなりにやってればいいんだってば。それで万事解決。俺も校長に呼び出されることもなくなる」
「それ、教師のアドバイスとしてどうなんすかね?」
俺の指摘を、垢嘗先生は鼻で笑った。
「はっ! 今時青春ドラマの真似事なんざできるかってんだよ! ただでさえテストの採点やら、部活動の顧問やら、厄介なモンスターの相手までして、その他もろもろの雑用があるっていうのに……っ。わざわざ部屋にまで呼びつけて『まだ入部していない生徒がいるようですねぇ~?』とか煽ってくるんだぞ!? あの野郎はァ……ッ!! くぁー! こっちはそれどころじゃないつぅーの!?」
よほどストレスがたまっているのだろう。
特定の名前は出していないものの、俺にはその人物が誰なのかが容易に想像できた。
担任教師ながら、少し同情してしまう。
「だから頼むよ! お前が入部届け出してくれるだけで、俺の業務が一つ減るんだよ! もう忙しい中、校長に呼びだされるのなんてごめんなんだ!!」
「せっかく伏せてたのに自分でバラしてどうするんですか」
「やべっ!? つい本音が!」
垢嘗先生は慌てて両手で口を押さえ、忙しそうに首を動かして周りを見渡した後、安堵の息を吐き出した。
どうやら、周りには誰もいなかったようだ。
普段パチンコで負けてるくせに、こういう時だけ運がいい。
「とにかく、入部に関しては絶対条件だ。どうしてもいやなら転校でもしろ。てか、入部が嫌なら、なんでこの学校に入ったんだよ?」
「家から近かったからに決まってるじゃないですか。高校なんてどれも同じだと思ってたら、とんだ罠っすよ」
「安直な理由で決めた、お前の自業自得だろうが……素直に諦めろ。ともかくだ、後一週間だけ待ってやる。その期間でなんとか決めろよ? もしそれでも決まらなかったら……」
「決まらなかったら?」
「お前を帰さない」
「その発言、モンスター召喚呪文になりません?」
「あ、やっべ。て、親御さんにチクるなよ? いや、振りとかじゃなくて絶対だからなマジで本当お願いします」
厄介ごとを避けるためならば、自分の生徒にすら敬語を使って頭を下げる。
それが、垢嘗という教師だった。
見てるこっちが悲しくなる。
そんな不憫な担任を俺は気の毒に感じ、長く伸びた前髪を右手で少し上げ、彼を軽く見た。
ふん、ふん、なるほどな。
「先生、いくら忙しいからって流石に四時間睡眠は不味いすよ。食生活もインスタント麺多めだし。後、教師なんだから風俗嬢と遊ぶのも程々にしといた方がいいすよ。んじゃ」
「んなこと言ったって、睡眠時間削らないと、逆に自分の時間がなくなるし、飯だって簡単に済ませた方が楽……て、おい待て、どうして風俗のこと知ってるんだ……? おい!?」
釈明するのも面倒なので、百目鬼はそそくさにその場を後にした。
◇◇◇
「調子乗って使うんじゃなかったかな。まあ、あの先生鈍い大丈夫だろう」
俺は再び目を前髪の中に隠し、先端を指でつまんでねじる。
髪をねじり遊ばせながら考えるのは先ほどの、部活動入部の話しだ。
俺だって何も、部活動そのものが嫌だというわけじゃない。
入ればきっとそれなりに楽しいだろうし、今しかできない経験だとも思うから入部できるなら、入部したい。
でも俺には、容易にそれを出来ない理由があった。
「この目がある以上、迂闊に何かやるわけにはいかないんだよなぁ……」
俺は先ほど髪先を掴んでた右手を下にスライドさせて、両目の近くをなぞる。
俺が部活動に入れない理由――それは、俺の『目』にはある特殊な能力が備わっていたからだ。
俺の目は、外見から得られた情報を光速で処理し、可視化して見ることができた。
つまり、人物や物の外見情報を文字にして読むことができる超観察能力。
同級生で友人の滑倉璃からは、『シャーロック・ホームズみたいだね』と表現されたこともあったが、あの世界的名探偵と俺の目の性質は、似て非なるものだ。
シャーロック・ホームズは、『観察をする』という過程を踏んだ上で、答えを導く。
だが、俺の目の場合は、見ただけで、『自動的』に答えが表示される。
どのような箇所を見て、そんなことが分かったのか。
どのような考えで、そんな結論に至ったのか。
俺には分からない。考えもつかない――だが、今までその答えが間違ったことはない。
外見から得られる情報ならば、どんなことでも見えるし分かる。
それが、俺の目の能力だ。
だから俺は先ほど、垢嘗先生の私生活を言い当てることができたというわけだ。
彼の周りには、以下の文字が表示されていた。
“睡眠時間:四時間から四時間半”
“食生活偏り気味、主食:カップ麺”
“昨晩、女性との性行為あり”
などなどだ。
風俗嬢云々に関しては簡単な推理だ。
あの先生に彼女はいない。
一件便利そうに見えるこの能力だが、全くもってそんなことはない。
迂闊に目を解放しようものなら、大量の外部情報が頭の中に飛び込んでくるんだ。
そうしたらとてもじゃないが、処理しきれない情報量に脳がパンクして、ぶっ倒れてしまう。
だからこんな真夏に近い暑さだろうと、俺は前髪を長く伸ばしたままだ。
こうすることで、前髪が気になり、それら情報をある程度処断することができた。
長さに関しても、頭髪検査に引っかからないギリギリのラインを心得ているので、注意もされることはない。そこら辺も完璧だ。
では本題だが、もしこんな厄介な目を持つ俺が、もし何かしらの部活動に参加したらどうなるか?
「目のことバレたら……絶対に酷使されるんだろうな……」
球技系統の部活に入れば、ボールの軌道や、相手の動きが事前に分かるので酷使される。
陸上系の部活に入れば、相手の残り体力や、走り方の軌道、ペース配分が分かるので、体力差や身体的な面を大きくカバー出来るため、結果的に酷使される。
文化部系の部活に入ったとしても、この目を使えば大概のことはどうにでもなるため、やっぱり酷使される。
つまるところ、俺の目を使えば大概の活動は簡単になってしまう。というわけだ。
でも、これにも問題がある。
先ほども言った通り、俺の目を解放すれば、大量の情報に耐えきれずオーバフローを起こして倒れてしまう。
部活動は、多かれ少なかれ集団行動。
目を使う事なんて殆どできないだろう。
だから現実問題、上記のような活躍はできないしないんだ。
むしろ、役に立たない方が多い。
出来ることといえば、雑用作業くらいだろうが、そんなことをしていては、それこそ何のために部活に入ったのか分からない。
結果、俺は完全に詰んでいた。
どの部活に入っても、どの活動をしてもお荷物。
だから、俺は入学して一ヶ月も経っているのに、入る部活を未だに決められないでいた。
「あーあ、この目を使っても大丈夫な部活ってなんだろうなぁ……」
空を仰いで見るも、都合のいい答えなど出るはずもない。
ただ、学校の廊下の白い天井が見えるだけだ。
そんな時だ。
「んがっ!?」
太陽の光が一直線に差す、階段の踊り場に差し掛かった時、突然俺の顔の上に一枚の紙が飛んできた。
「なんだこれ?」
俺は紙を顔から剥がす。
紙にはびっちりと文字が書かれており、普通なら何が書いてあるがすぐには分からないが、俺はその紙を直接『目』で見てしまったため、紙に書かれた内容がすぐに表示された。
「これは小説の原稿か。でもなんで一枚だけ……いや、違う」
周りを見渡すと、踊り場には大量にばらまかれた紙の束が散らばっていた。
この紙もきっと、その中の一枚だったんだろう。
その証拠に、少し離れたところには、この紙の束をまとめていたと思われるクリップが落ちていた。
俺は再び紙の内容を読もうとしたが、太陽の光に照らされていた原稿に、一気に陰を落ちた。
俺は上を見上げる。
すると、階段の中間地点からこちらを見下ろす、一つの長細い陰。
その陰は人の形をしていたが、顔を確認することは出来ない。
だが、三つ編みの髪型とスカートのシルエットから、その人物が女子であることは分かった。
女子生徒の陰は、上からゆっくりと一歩ずつ階段を降り、俺のいる踊り場に来てようやく、その顔を確認することができた。
華奢で、線の細い曲線で描かれたような顔をした、黒縁眼鏡をかけた少女。
その外見からして、『文学少女』という言葉がとても似合う女子生徒だった。
そんな彼女は、夏の暑さすら涼しげに感じてしまうほどの絶対零度の真顔が、俺を見ていた。
何かを確かめるように、ただじっと、俺を見ていた。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
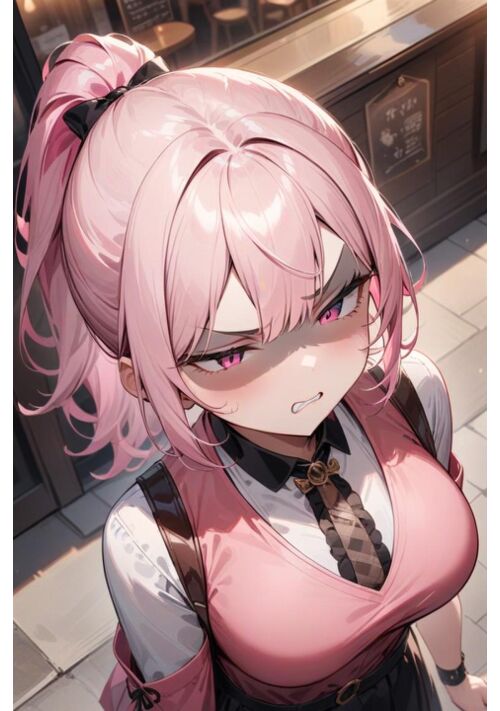
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。


俺を振ったはずの腐れ縁幼馴染が、俺に告白してきました。
true177
恋愛
一年前、伊藤 健介(いとう けんすけ)は幼馴染の多田 悠奈(ただ ゆうな)に振られた。それも、心無い手紙を下駄箱に入れられて。
それ以来悠奈を避けるようになっていた健介だが、二年生に進級した春になって悠奈がいきなり告白を仕掛けてきた。
これはハニートラップか、一年前の出来事を忘れてしまっているのか……。ともかく、健介は断った。
日常が一変したのは、それからである。やたらと悠奈が絡んでくるようになったのだ。
彼女の狙いは、いったい何なのだろうか……。
※小説家になろう、ハーメルンにも同一作品を投稿しています。
※内部進行完結済みです。毎日連載です。

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。
ピコサイクス
青春
大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。
真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。
引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。
偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。
ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。
優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。
大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。

SSS級の絶世の超絶美少女達がやたらと俺にだけ見え見えな好意を寄せてくる件について。〜絶対に俺を攻略したいSSS級の美少女たちの攻防戦〜
沢田美
恋愛
「ごめんね、八杉くん」
中学三年の夏祭り。一途な初恋は、花火と共に儚く散った。
それ以来、八杉裕一(やすぎ・ゆういち)は誓った。「高校では恋愛なんて面倒なものとは無縁の、平穏なオタク生活を送る」と。
だが、入学した紫水高校には《楽園の世代》と呼ばれる四人のSSS級美少女――通称《四皇》が君臨していた。
• 距離感バグり気味の金髪幼馴染・神行胱。
• 圧倒的カリスマで「恋の沼」に突き落とす銀髪美少女・銀咲明日香。
• 無自覚に男たちの初恋を奪う、おっとりした「女神」・足立模。
• オタクにも優しい一万年に一人の最高ギャル・川瀬優里。
恋愛から距離を置きたい裕一の願いも虚しく、彼女たちはなぜか彼にだけ、見え見えな好意を寄せ始める。
教室での「あーん」に、放課後のアニメイトでの遭遇、さらには女神からの「一緒にホラー漫画を買いに行かない?」というお誘いまで。
「俺の身にもなれ! 荷が重すぎるんだよ!」
鋼の意志でスルーしようとする裕一だが、彼女たちの純粋で猛烈なアプローチは止まらない。
恋愛拒否気味な少年と、彼を絶対に攻略したい最強美少女たちの、ちょっと面倒で、でも最高に心地よい「激推し」ラブコメ、開幕!

まずはお嫁さんからお願いします。
桜庭かなめ
恋愛
高校3年生の長瀬和真のクラスには、有栖川優奈という女子生徒がいる。優奈は成績優秀で容姿端麗、温厚な性格と誰にでも敬語で話すことから、学年や性別を問わず人気を集めている。和真は優奈とはこの2年間で挨拶や、バイト先のドーナッツ屋で接客する程度の関わりだった。
4月の終わり頃。バイト中に店舗の入口前の掃除をしているとき、和真は老齢の男性のスマホを見つける。その男性は優奈の祖父であり、日本有数の企業グループである有栖川グループの会長・有栖川総一郎だった。
総一郎は自分のスマホを見つけてくれた和真をとても気に入り、孫娘の優奈とクラスメイトであること、優奈も和真も18歳であることから優奈との結婚を申し出る。
いきなりの結婚打診に和真は困惑する。ただ、有栖川家の説得や、優奈が和真の印象が良く「結婚していい」「いつかは両親や祖父母のような好き合える夫婦になりたい」と思っていることを知り、和真は結婚を受け入れる。
デート、学校生活、新居での2人での新婚生活などを経て、和真と優奈の距離が近づいていく。交際なしで結婚した高校生の男女が、好き合える夫婦になるまでの温かくて甘いラブコメディ!
※特別編7が完結しました!(2026.1.29)
※小説家になろうとカクヨムでも公開しています。
※お気に入り登録、感想をお待ちしております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















