34 / 70
四章 英雄の花嫁
47:無自覚の信頼と彼女の生きる道:Sideオリオン
しおりを挟む夜が深まっていく中、オリオン=ホワイトディアは厨房にいた。今となっては甥の居城ではあるが、勝手知ったるなんとやら。先代辺境伯である彼は、かつて住んでいた城の厨房の竈に火を起こし、片手鍋に注いだワインを温めていく。
鍋をジッと見る彼の赤い双玉には、薪を燃やす竈の炎が揺らめいていた。背後では昔馴染みの料理人がリーフパイを焼いており、広い厨房のその一角には濃厚な甘い香りが漂っている。木べらでワインを掻き混ぜて、北の王と呼ばれたことのある男は静かに息を吐いた。
ローズハート姉妹の間に起きた温室での出来事は、侍女はもちろん、忍んでいた従者たちに報告されている。特殊な訓練を受けて常に冷静な従者たちはともかく、案内を任せた侍女である子爵家の三女は非常に憤慨した様子だった。
プリシア=ローズハートがホワイトディア家に嫁入りするアメリアに暴言を吐き、嘲笑した。しかし言われた張本人は、暴言ではなく熱に浮かされた妄言だったと異母妹を庇ったそうだ。
『いくら姉妹だからといって甘すぎます!』
異母姉妹の事情を知らない侍女は悔しそうにそう言っていた。
しかし甘いゆえに庇っているわけでないことを、オリオンはわかっている。これまで接してきたアメリアという女性は男爵家の家族への情は希薄だ。
(正確には男爵家の家族への情も、希薄だ、か)
彼女は誰に対しても――人間という生き物への興味関心が薄い。それは血の繋がりがあるからと例外ではなかった。おそらく本人は暴言で攻撃をされたという認識はなく、異母妹が声を荒げて何かを言っていた、くらいにしか思っていないのだろう。
オレンジの皮とクローブ、シナモンスティック、生姜、スターアニスを鍋に入れ、ワインと共にゆっくり温めていく。沸騰しないように掻き混ぜる手は止めない。
「オリオン様ぁ、リーフパイはいくつ持って行かれますぅ?」
後ろから間延びした声が投げられる。歳の近い料理人の男とは気心が知れた間柄のため、向こうに緊張感はない。
「そうだのう。そなたが必要な分を除き、あとは皿に乗せておいてくれ」
「この時間に全部食べるおつもりで? もう若くないんですから。明日の朝起きて胃がもたれていても知りませんよぉ」
「余計な心配だのう。ひとりで食べぬわ」
オリオンは鍋に顔を向けたまま話す。ワインの中にきび砂糖を加え、木べらで混ぜ溶かしていく。香りが一気に甘さを増した。順調にできあがっている。オリオンは口元に小さく笑みを浮かべた。
「ひとりでないとすると、なるほど。オリオン様の女王陛下とご一緒にですかぁ?」
「女王陛下? クィーンか?」
「いいえ、違いますよぉ。アメリア様のことですぅ」
「アメリア嬢が女王陛下? ふむ……その例えをしたのは、そなたが初めてだぞ」
「王の頭が上がらない存在はぁ、女王陛下くらいでしょう? 甲斐甲斐しく世話を焼いていると噂ですよぉ。こうして夜中にグロッグをこしらえるくらいですし、噂は本当のようですねぇ」
面白いと言わんばかりの声音だ。オリオンはフッと笑う。
「そうだのう。否定はせん」
「はぁぁぁ、お熱いですなぁ」
昔馴染みに「羨むな羨むな」とおかしそうに言い、オリオンは片手鍋を火から下ろした。そして傍らに用意していたザルで漉しながら、三つのカップにグロッグを注いでいく。カップからは白い湯気が立ち昇る。オレンジやシナモンの甘い香りが一層広がった。
後ろにいた料理人が「いい香りですねぇ」と漏らしながらオリオンの隣へ来る。標準的な体型だが、筋骨隆々としたオリオンの隣に立つと小柄に見えてしまう。彼はかつての主君の傍らで「おやぁ」と器用に肩眉を上げた。
「私めの分もあるのですかぁ?」
「好きであろう?」
「ええ、大好きですよぉ。手ずから作っていただけるなど光栄の至り。後片づけはこちらで引き取りましょう」
「ん? いいのか?」
「どうぞぉ、オリオン様の女王陛下の元へ、リーフパイとグロッグを献上しに行かれてください。冷める前に、ささ、お早くぅ」
「そうか。すまんな」
オリオンは、大小ふたつのカップとリーフパイをこんもり積んだ皿を銀のトレイに乗せる。にこやかな料理人に見送られ、悠々とした足取りで厨房をあとにした――。
彼がその足で向かったのは、温室だ。
灯りに照らされた温室は、日中とは違った顔を見せている。鳥籠の形をしたガゼボのテーブルにトレイを一旦置き、オリオンは奥へと進んだ。
甘い香りが充満する中、ランプの灯を頼りに彼女は絵を描いていた。
イーゼルに立てたキャンバスにこぼれんばかりの花が咲いている。甘い香りの出どころがそのキャンバスだと言われたら信じてしまうほど、彼女の手によって生み出された華は瑞々しく、艶やかで、鮮明だ。一番目に入ってくるのは大きく咲き誇る、大きな赤い花だ。橙色の灯に照らされた花弁の印影は、止まっているはずなのに灯の揺らぎすら感じさせる。
(見事なものだな)
オリオンは後ろに立ち、腕を組んで顎を撫でた。
アメリアが立つのは、昼に異母妹が倒れた場所だ。プリシアは高熱を出し、辺境伯家お抱え医師の弟子が診察をして、今は客室で眠っている。どうやら青い顔をした母親のマーガレットが付き添っているらしい。そういった事情もあり、予定されていた両家の顔合わせを目的とした晩餐会は中止になった。
(むしろそのほうが良かったのやもしれぬ)
昼間の出来事は侍女の口から辺境伯夫人――甥の妻であるテリーザに報告が上がっている。起きた事柄に不満を覚えた者からの報告は角が立つ。ただでさえ顔を顰めてしまう内容だ。そこに報告者の不満が混ざれば、どうなるかは明白だった。
オリオンは数時間前のことを思い出す――
――晩餐会が中止となり、ホワイトディア家の夕食の席へと変わった場。そこには辺境伯夫妻とふたりの子供、それからオリオンの姿があった。アメリアはいない。何やら描きたいものがあるらしく部屋にこもっている。
辺境伯夫人のテリーザが激怒していた。
「腹違いとはいえ、姉の嫁ぎ先の家であんなことを言うなんて! いくら仲が悪くても、言っていいこととそうでないことの区別もつかないのかしら!? 親も親! 妹がそんなことを考えて、口にしてしまう環境だったってことでしょう!? っ、絶対に許せないわ!」
アメリアを心底受け入れており、可愛がっているテリーザは怒りを抑えきれずにいる。もともと正義感の強い、真っ直ぐな性根の女性だ。
それに加えて、アメリアがこの場にいない理由として『食欲不振で部屋にこもっている』とオリオンが言ってしまったことも燃焼材の一端になっているのだろう。心に傷を負って食欲がない、と解釈されているようだ。
「なあ、何があったんだ?」
「わたくしも詳しくは知らないわ。ただ、その……アメリア様の妹が、酷い言葉をかけたって……」
「なんだと!? 許せねえな!」
アンタレスとミモザは侍女の報告を聞いていない。それにも関わらずミモザが曖昧にとはいえ、正しい筋道の情報を持っているのは大したものだと、オリオンは内心、感心する。王家との繋がりという大役を担う娘は、若干十六歳にして独自の人脈と情報源を得ているらしい。
一方、初耳だったアンタレスは、妹の言葉に目を丸くする。そして次の瞬間、勢いよく母親のテリーザを見た。
「母上! 乗り込むならオレも行くぜ!」
青年期を迎えたアンタレスの体躯はますます立派になり、日頃の鍛錬の成果が出ているのか腕っぷしもオリオンが一目置くほどになった。しかしどうにも、考えるより先に行動してしまう性質は少年の頃のままだ。今後、じっくり育てていかなければならないと、こちらに関してはオリオンは内心、溜め息をついていた。
「よく言ったわ、アンタレス! さあ、共に参りましょう!」
「おう!」
「ふたりとも待ちなさい」
夕食を中断して乗り込もうとする甥の妻と息子を制止する。ふたりの顔立ちはあまり似ていないが、オリオンに向けてくる『なんでですか』と言わんばかりの表情は同じだ。
「乗り込んで何を言うつもりだ?」
「もちろんアメリア様への暴言の真意を問い質し、今後二度とこのようなことがないようにしっかり言いつけますわ」
「ローズハート男爵家は王国の正式な貴族だぞ。北側の家でもなく、我が家の寄子でもない。その家に対して叱責すると言うのか?」
オリオンが静かに問えば、テリーザは言葉に詰まるように口を閉じた。
親戚でもなく、寄親として庇護を与えているわけでもないのに、他家の内情に口を挟むのは越権行為はなはだしい。家の力の差があればあるほど、何か裏があるのではないか――乗っ取りや吸収、領土の拡大を画策しているのではないかと疑われる可能性もある。
特に今回、北の辺境伯家であるホワイトディアが『王都と辺境伯領の間に領地を持つローズハート男爵家を奪おうとしている』と、仮に噂でも流れれば厄介だ。平和路線で一致している王家とホワイトディア家の間で結ばれた縁談に、良からぬ影を落としかねない。
テリーザが正義感からローズハート男爵家を叱責することには、そういった危険性を孕んでいる。少し落ちついた彼女は全てを語られずとも、オリオンの言葉の意味を悟り口を閉じた。
しかし、直情的で今後の教育が必須の彼は違う。
「ダメなことはダメって言わなきゃいけねえだろ?」
アンタレスが眉を寄せて不満を隠さず言った。
「ローズハート男爵家の……プ……プ……なんだっけ?」
「小兄様……プリシア、様よ」
兄は横の妹を見る。ミモザは嫌そうな顔でプリシアの名前に敬称をつけて、名前を覚えていないアンタレスへ教えてあげた。
「ああ、そうかプリシアか。まあ、そのプリシアが、姉のアメリア嬢に間違ったことを言ったんなら、そんなこと言うなって注意しないとダメだ! 本当は親の男爵たちがやらなきゃいけねえことだけど、やらないってんならオレたちがしないと! だって、オレたちがこれからアメリア嬢の家族になるんだから!」
一寸の曇りのない眼でアンタレス=ホワイトディアが言い切る。胸を張る、堂々とした立ち姿に寸分の迷いもなく、その言葉が彼の本心であると、その場にいる誰もがわかった。
若さゆえの、青く、単純で、いっそ清々しい正義感――彼が学園を卒業し、辺境伯家の人間としての教育を受けた上で、この眩いばかりの青臭さをなくさずにいてくれれば、北の王として君臨するホワイトディアへの信頼はより一層厚くなる。当主を継ぐ次代も、そんな弟が傍に在れば心強いだろう。
「アークトゥルス」
オリオンは甥の名を呼ぶ。
「はい。オジキ」
「青く、甘いな」
「そうですね。今後はビシバシ厳しくしていかねえと」
言葉ではそう言いながら、オリオンとアークトゥルスの口元には笑みが浮かんでいた。話題の張本人であるアンタレスは、大叔父と父の会話に目をまたたかせ、視線を行ったり来たりさせている。
「アンタレス、明日から学問の授業を増やすぞ」
「えっ!? なんで急に!?」
「学園に戻ってからも自主学習用の課題を持たせるから、しっかりやれよ。期限を決めて提出させるぞ。定期的に北へ送ってこい。ちゃんとやっとかねえと小遣いナシだからな?」
「だからっ、なんで急にそんな話になるんだよ!?」
混乱して声を上げる馬鹿正直な息子に、アークトゥルスはフンッと鼻を鳴らすと、口の片端を持ち上げた。
「テメェがバカだからだ」
「はあ!?」
「家族になるって免罪符で怒るって言うなら、誰よりもそれを行使する権利を持ってんのは、アンタレス、テメェじゃねえだろ?」
「あ……」
「オジキの嫁と、その家族の問題だ。酸いも甘いも噛み締めた大人の恋愛事情に、ガキがしゃしゃり出てんじゃねえぞ」
甥の言葉にオリオンは内心、苦笑した。
(恋愛事情か)
ホワイトディア領で、アメリアとオリオンの身分差と年齢差を越えた物語が広く流通し、概ね好意的に受け入れられているのは、彼も知るところだ。
今は画商のラファエルと名乗っている旧友――ティグルス=メザーフィールドが裏で糸を引いているゆえの成果であるのと同時、甥夫婦がいささか恋愛脳であることも要因になっているのだろう。甥夫婦――辺境伯夫妻だけではない。その子供たちも同じく、なんの躊躇もなく受け入れてくれている。
終生の友に『好色ジジイ』になってくれと頼まれ、引き受けた。そう呼ばれても仕方ないと思っていたが、現実はそうではなく、割合的に見ればほとんどの者たちから好意的な反応が返ってきている。
オリオンは口元に浮かんだ笑みを隠すように、切り分けた肉を口に運んだ。昔好んで食べていたソースだった。味わって食べたい気持ちもあったが、それよりも渦中に居ながらそれを気にしていない彼女の絵を見たい気持ちのほうが大きい。彼は早々に夕食を終えると、甥家族を残してアメリアの部屋を訪ねた――。
彼女は私室でスケッチブックに絵を描いていたが、途中でそれだけでは我慢できなくなったらしい。ソワソワとしているのがひと目見てわかった。だからオリオンは誘いの言葉を口にしたのだ。
『――共に温室へ参ろうか……』
と――。
――そして、今に至る。
辺りがすっかり暗くなり、日付けも変わった。後ろで見ていると、キャンバスと向き合っていたアメリアが深く息を吐き、肩の力を抜いたのがわかる。筆とパレットを置き、一歩離れて描いた絵を見ていた。
服の上に着ているエプロンは先日、ミモザやアンタレスと城下の街に降りて買ってきたものだ。それぞれアメリアに似合う物を選んだと言っていたが、今着用しているのはミモザが選択したエプロンだろう。ミルクをたっぷり注いだ紅茶のような色をした生地で、下の隅のほうに新芽の枝を咥えた鳥の刺繍が施されていた。
シンプルなデザインで、絵を描く時に視界に入っても邪魔をしないであろう自然な色合いだ。そこにミモザの気配りを感じさせる。
オリオンはアメリアを静かに見つめた。
彼女は気付いているのだろうか。アメリアにとって息をすることと同義の、絵を描くという行為。外界とは一線を画し、神聖さすら漂う彼女の世界に、第三者の特別な感情がこもった品がある。それにどんな意味があるのか、彼女は気付いて――
「アメリア嬢、ひと段落したようだのう」
静かな温室の空気を、オリオンの低い声が震わせる。アメリアがゆっくり振り返って、小さく頷いた。
「はい。描けました」
「美しく、瑞々しい、それでいて何故か恐ろしさを感じる絵だ。香りで誘き寄せ、虫を食らう花、か」
日中、花の奥――底には小さな虫が沈んでいた。その姿は今はもうない。そして、アメリアの描いた絵の中にもいない。しかし背中に薄ら寒いものを感じさせる雰囲気が、彼女の生み出した赤い花にはあった。
「申しわけ、ありません。正確にはわかりませんが、きっと、もう遅い時間なのですよね? オリオン様をつき合わせてしまって……」
「なぁに、気にせずともよい……と、言ったところで、そなたは気が咎めてしまうのであろうな」
わずかに目を伏せて申しわけなさそうな顔をするアメリアに、オリオンは微笑みながら大きな手を差し出す。
「ならば、私の夜食につき合っておくれ」
「え?」
「アメリア嬢、そなたの時間を私にくれまいか?」
手の平を差し出したまま待っていると、ゆっくりと上がったアメリアの小さな手が重なった。触れた指は冷たい。だが見る人が見ればわかる程度に、彼女の表情は柔らかく、了承の返事をする声も穏やかだ。
オリオンは、グロッグとリーフパイが待つガゼボへ、アメリアをエスコートするのだった――。
179
あなたにおすすめの小説

婚約破棄されたので、前世の知識で無双しますね?
ほーみ
恋愛
「……よって、君との婚約は破棄させてもらう!」
華やかな舞踏会の最中、婚約者である王太子アルベルト様が高らかに宣言した。
目の前には、涙ぐみながら私を見つめる金髪碧眼の美しい令嬢。確か侯爵家の三女、リリア・フォン・クラウゼルだったかしら。
──あら、デジャヴ?
「……なるほど」

三回目の人生も「君を愛することはない」と言われたので、今度は私も拒否します
冬野月子
恋愛
「君を愛することは、決してない」
結婚式を挙げたその夜、夫は私にそう告げた。
私には過去二回、別の人生を生きた記憶がある。
そうして毎回同じように言われてきた。
逃げた一回目、我慢した二回目。いずれも上手くいかなかった。
だから今回は。

【完結】20年後の真実
ゴールデンフィッシュメダル
恋愛
公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。
マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。
それから20年。
マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。
そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。
おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。
全4話書き上げ済み。

初夜に暴言を吐いた夫は後悔し続ける──10年後の償い【完結】
星森 永羽(ほしもりとわ)
恋愛
王命により、辺境伯ロキアのもとへ嫁いだのは、金髪翠眼の美しき公爵令嬢スフィア。
だが、初夜に彼が告げたのは、愛も権限も与えないという冷酷な宣言だった。噂に踊らされ、彼女を「穢れた花嫁」と罵ったロキア。
しかし、わずか一日でスフィアは姿を消し、教会から届いたのは婚姻無効と慰謝料請求の書状──。
王と公爵の怒りを買ったロキアは、爵位も領地も名誉も奪われ、ただの補佐官として生きることに。
そして十年後、運命のいたずらか、彼は被災地で再びスフィアと出会う。
地位も捨て、娘を抱えて生きる彼女の姿に、ロキアの胸に去来するのは、悔恨と赦しを乞う想い──。
⚠️本作はAIの生成した文章を一部に使用しています。

[完結]いらない子と思われていた令嬢は・・・・・・
青空一夏
恋愛
私は両親の目には映らない。それは妹が生まれてから、ずっとだ。弟が生まれてからは、もう私は存在しない。
婚約者は妹を選び、両親は当然のようにそれを喜ぶ。
「取られる方が悪いんじゃないの? 魅力がないほうが負け」
妹の言葉を肯定する家族達。
そうですか・・・・・・私は邪魔者ですよね、だから私はいなくなります。
※以前投稿していたものを引き下げ、大幅に改稿したものになります。

ため息ひとつ――王宮に散る花びらのように
柴田はつみ
恋愛
「離縁を、お願いしたいのです」
笑顔で、震えずに、エレナはそう言った。
夫は言葉を失った。泣いてくれれば、怒ってくれれば、まだ受け止め方があった。しかしあの静けさは、エレナがもう十分に泣き終わった後の顔だと、ヴィクトルにはわかった。
幼なじみと結ばれた三年間。すれ違いは静かに始まり、深紅のドレスの令嬢によって加速した。ため息を飲み込み、完璧な微笑みを保ち続けた公爵夫人が、最後に選んだのは――。
王宮に散る花びらのような、夫婦の崩壊と再生の物語。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし
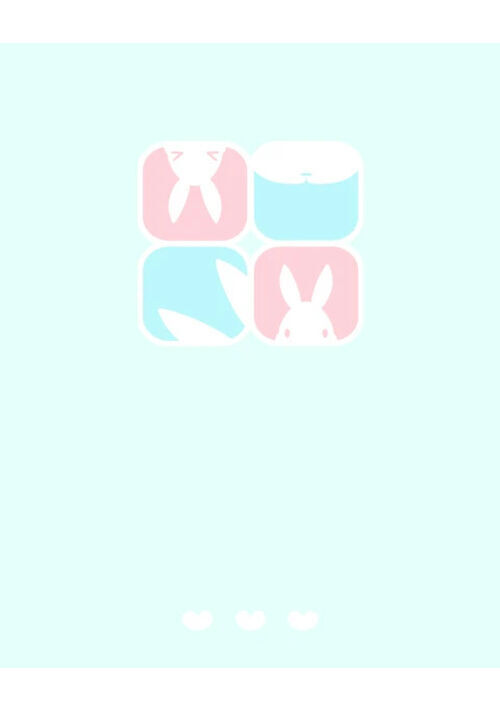
【完結】王太子に婚約破棄され、父親に修道院行きを命じられた公爵令嬢、もふもふ聖獣に溺愛される〜王太子が謝罪したいと思ったときには手遅れでした
まほりろ
恋愛
【完結済み】
公爵令嬢のアリーゼ・バイスは一学年の終わりの進級パーティーで、六年間婚約していた王太子から婚約破棄される。
壇上に立つ王太子の腕の中には桃色の髪と瞳の|庇護《ひご》欲をそそる愛らしい少女、男爵令嬢のレニ・ミュルべがいた。
アリーゼは男爵令嬢をいじめた|冤罪《えんざい》を着せられ、男爵令嬢の取り巻きの令息たちにののしられ、卵やジュースを投げつけられ、屈辱を味わいながらパーティー会場をあとにした。
家に帰ったアリーゼは父親から、貴族社会に向いてないと言われ修道院行きを命じられる。
修道院には人懐っこい仔猫がいて……アリーゼは仔猫の愛らしさにメロメロになる。
しかし仔猫の正体は聖獣で……。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
・ざまぁ有り(死ネタ有り)・ざまぁ回には「ざまぁ」と明記します。
・婚約破棄、アホ王子、モフモフ、猫耳、聖獣、溺愛。
2021/11/27HOTランキング3位、28日HOTランキング2位に入りました! 読んで下さった皆様、ありがとうございます!
誤字報告ありがとうございます! 大変助かっております!!
アルファポリスに先行投稿しています。他サイトにもアップしています。
過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている
と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
番外編を閲覧することが出来ません。
過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている
と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。




















