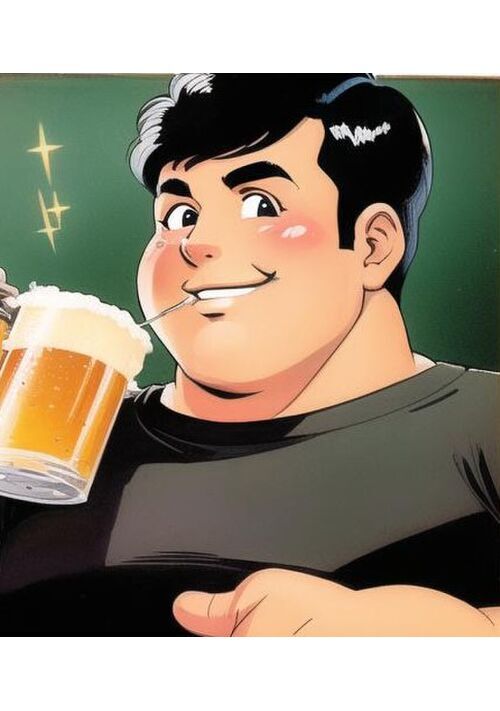3 / 62
1巻
1-3
しおりを挟む
本心からの言葉だったが、卯月は納得いかないらしい。じとりとした目で睨むように雅臣を見た。
「だ、だって……俺なんか……」
「俺なんかとか言って自分のこと卑下するのやめろ。龍太郎みたいな馬鹿どもの言うことなんて真に受けてんじゃねぇよ」
「……そうやって偉そうに命令してくるとこ、嫌い」
雅臣がそう言い切った瞬間、繋がれていた卯月の手がびくっと跳ねた。
思い切って、今までの不満もぶちまける。
「幼稚園のとき、俺の好きな絵本やおもちゃを横取りしてくるのも嫌だったし、俺が真理亜たちと遊んでると邪魔してくるのも嫌だった。小学生になっても意地悪ばっかだし……」
「そ、そんなの、俺はお前に構ってほしくて……それに、確かに前はそんなこともあったけど、最近は意地悪なんかしてないだろっ?」
「してるよ。最近だと……俺が図工の時間に作った猫の置物のことクマとか言って馬鹿にしてた」
「いや、あれは本当にクマにしか見えなかったんだって……あんな凶悪な見た目の猫なんているかよ……」
「ほらっ、またそうやって意地悪言う! あと……俺が泣くとうれしそうに笑うの、あれすごく怖い」
「そ、それは……お前のことが好きだから……泣いた顔がかわいくて、つい……」
――なんだそれ。
頬を赤らめながら少しばかり気まずそうに言う卯月に、雅臣は呆れと驚きを隠せなかった。
「ずっと嫌われてるんだと思ってた……」
「はぁ?」
雅臣の言葉に、卯月は不機嫌そうに顔をしかめる。
心外だと言いたげな顔をされても、わかるはずがない。卯月の言動は雅臣にとって嫌がらせのようなものばかりだったのだ。
確かに卯月は、雅臣が他の子に取られたおもちゃを代わりに取り返してくれたり、この前のように馬鹿にされている場面で助けてくれることもあった。だが、卯月は誰に対してもそういう正義感を持っていたし、その反面嫌がらせのようなことをしているのは雅臣に対してだけだったのだ。
これで好かれていると思えるほど、雅臣はポジティブではない。むしろ、自尊心は人一倍低いのだ。
「大体、嫌いなやつに番になれとか婚約しろとか言う訳ないだろ?」
「俺のこと、一生いじめたいから傍に置いておきたいのかと……」
「お前のなかで俺の人間性どうなってんだよ……」
はぁ、と大きなため息をついた卯月はガシガシと頭を掻く。そして、気を取り直したように満足げな笑みを浮かべた。
「まあでも、これで誤解は解けたんだよな? 俺と婚約してくれるだろ?」
「え……なんでそうなるの……?」
「は? なんだよ、嫌なのか?」
嫌に決まっている。
雅臣はずっと卯月に嫌われていると思っていたのだ。いくら好かれているとわかったからといって、長年の苦手意識は消えない。
なにより、雅臣と卯月はすべてにおいて釣り合っていない。それは、他の誰かに言われたからではなく、初めて卯月と出会ったときに雅臣自身が感じ取ったことだ。
卯月は他の誰よりも特別で、眩しい。きっと、生まれたときから雅臣とは住んでいる世界が違うのだ。
けれど、それを言ったところで卯月はわかってはくれないだろう。
傲慢で、我が儘で、そのくせ真っ当なこの少年は、当然のように雅臣を自分と同等の存在だと思っている。自分は特別なのだと卯月がちゃんとした意味で理解していないことが、よりいっそう雅臣をちっぽけな存在にする。
「総真くんのことが嫌いな訳じゃないけど……でも、俺は総真くんと一緒にいるとつらいし、どっちも幸せになれないと思う」
「なんだよ、それ……」
卯月は目を見開いたあと、今にも泣き出しそうな顔で悔しそうに唇を噛んだ。
その顔から目を逸らして、雅臣は言葉を続ける。
「……それに、まだ子どもだから婚約のことなんてすぐには決められないよ。大人になってからじゃないと……」
「大人になったらっていつだよ」
「……十年後くらい?」
「はぁあああぁ?」
そこで、タイミングよくチャイムが鳴り響いた。
これ幸いと、雅臣は繋がれたままの卯月の手を引いて教室を出る。
「おい! まだ話はっ……」
「授業はじまっちゃうから」
そう言った雅臣がギュッと手を握ると、卯月は押し黙った。卯月の手のひらは汗ばみそうなほど熱を持っていて、痛いくらいの強さで雅臣の手を握り返してくる。
雅臣が卯月の教室の前で手を離すと、卯月は少し赤らんだ顔でフンとそっぽを向いた。
「まだ話は終わってないからなっ」
「じゃあね……」
都合の悪いことは聞かなかったふりをして、雅臣も自分のクラスへと戻った。
その後の時間は、休んでいたときの授業内容を真理亜たちに教わりながら普通に過ごすことができた。卯月が昼休みにやってきたが、雅臣が真理亜のノートを書き写している姿を見ると無言で帰っていった。この前のことがあったからか、室井たちが雅臣に近付いてくることもなく、平穏な一日だった。
放課後にも、今朝の話の続きをしようと、卯月が靴箱で雅臣を待ち構えていたが、祖父が車で迎えに来てくれていることを話すと渋々引き下がっていった。
そのとき、「俺は十年も待つ気はないからな!」と強く主張されたのだが、翌日になって状況が一変することになる。
「……十年待つ」
翌朝、前日と同じ空き教室に雅臣を連れ込んだ卯月が、ふてくされた表情でそんなことを言った。
昨日とは正反対の言葉に、雅臣は困惑する。
「……え?」
「昨日お前が言ったんだろ……大人になってからじゃないと決められないって」
「でも、昨日は嫌そうだったのに……」
「……親父に怒られた」
ふてくされた顔がさらに不機嫌そうに歪む。
そんな表情ですらかわいげがあって、やはりずるいなと雅臣は頭の片隅で思った。
「今まで嫌われてるって誤解させるような態度取ってた俺が悪いって……雅臣が俺と婚約したがらないのも当然だって……それで、反省の意味も込めて、お前の言う通り大人になるまで待つことにした……」
いつになく歯切れ悪く喋る卯月に、雅臣は首を傾げて尋ねた。
「よくわからないけど、つまり、婚約の話はなしってこと?」
「……まぁ、いったん白紙にはなる。……それと、十年待ってる間、なるべくお前に関わらないようにもするから……」
雅臣は驚いて目を丸くした。
もともと受け入れていなかった婚約云々の話よりも、そちらの方が雅臣にとってはよっぽど重要な話だ。
「か、関わらないって……もうこんな風に話したりしないってことだよね?」
しばしの沈黙のあと、卯月は無言で頷いた。
奥歯を噛み締め、叫び出すのを我慢しているような苦渋の表情は、到底それに納得しているようには見えない。
だが、頷いたということは紛れもなく肯定だ。
正直言って、雅臣には話の流れがまったくわからなかった。ただ、卯月父子の間でなんらかの取り決めがあったのは確かだろう。
学校行事で何度か卯月の父親を見たことがあるが、周りが甘やかすからなのかその分、卯月に厳しく接していた。傍若無人な卯月も多少反抗的ではあったが、父親の言うことには渋々従っていたような気がする。
卯月側の詳しい事情はわからないが、とにかくこれから十年は卯月と関わらなくてすむ――そう考えただけで、自然と雅臣の表情がパァッと華やいだ。
それを見て、今までしょぼくれていた卯月の目尻がキッと吊り上がる。
「だっ、だからって、俺がお前を諦めた訳じゃないからな! つか、うれしそうな顔すんな! 傷付くだろうがっ!」
「ご、ごめん」
それでも、雅臣にとっては十分だ。十年も猶予期間があれば、きっと卯月も雅臣が取るに足らない存在だと気付くだろう。雅臣は他の学校に進学するのだから、物理的に距離もできる。その間に卯月が他の誰かを気に入ったら、雅臣との婚約の話なんて自然消滅確定だ。
「……お前、なにあからさまにホッとしてんだよ。まさか、十年程度で俺が心変わりするとか思ってねぇよな?」
「べ、別にそういう訳じゃ……」
否定しつつも目は泳いでしまう。
卯月は怪訝そうな表情をしたままだったが、やがてハァとため息をついてから付け加えるように言った。
「……あと、俺も中学からは有流都学園に転校することにしたから」
「有流都学園?」
「アルファ専用の学校だよ。お前がいなくなるなら、こんなとこ通う意味もねぇしな」
雅臣は知らなかったが、オメガ専用の学校があるのだからアルファ専用の学校も当然あるだろう。
どちらにせよ、雅臣とは別々の学校だ。卯月からも、その他の悪意からも解放されるのだと思うと、胸がスッとした。
そんな雅臣とは対照的に、卯月はひどく浮かない顔をしてぼそぼそと呟く。
「……さっき言った通り、これから十年は、お前に話しかけたり絡んだりしない。本当は嫌だけど、俺が悪いし……お前、うれしそうだしな」
「……少しはさみしいよ」
「どうだかな」
肩を竦めた卯月は、雅臣よりもずっと寂しそうに力なく笑う。そして、細められた目が愛おしそうに雅臣を見つめた。
雅臣は軽く息を呑む。
卯月がそんな瞳で雅臣を見るのは初めてで――いや、本当にそうだろうか。
もしかしたら、今までもこんな風に卯月が雅臣を見つめたことはあったのかもしれない。雅臣がいつも俯いて、卯月を見ようとしなかったから知らないだけで、卯月はずっと雅臣を好きでいてくれたのかもしれない。
長い沈黙による静寂のせいなのか、いつもは気にならない自身の心臓の音がやけに大きく聞こえた。
やがて卯月の桜色の唇が、小さく笑みを浮かべる。
「お前が好きだ」
一瞬、時間が止まってしまったかのように、ふたり見つめ合っていた。
瞬きも、呼吸さえも忘れ、卯月のらしくない穏やかな微笑みに引き寄せられる。
それは天使みたいに綺麗で、卯月の顔を見慣れている雅臣ですら見惚れるほど美しかった。
「十年たったら会いに行く」
優しげで、真っ直ぐな視線から逃れることもできず、雅臣はなぜだか泣きそうな気分になりながら唇を震わせる。
「……きっと、覚えてないよ」
「お前が忘れても、俺は絶対覚えてるんだから関係ねぇよ」
そうじゃない。忘れるのはきっと、雅臣じゃなくて卯月の方だ。
雅臣はただ黙ったまま俯いた。先ほどの卯月の言葉に、らしくない表情に、心を揺さぶられた自分がいた。
けれど、これがなにを意味するのか、雅臣は知らないふりをする。
ただ、雅臣にとって卯月は特別だった。それだけは、雅臣も認める本当のことだ。
「……じゃあ、またな」
長いようで短い沈黙のあと、卯月はそう言い残し、走って教室を出ていく。
朝の淡い陽の光に照らされた廊下を走り抜けていくその後ろ姿を、雅臣は薄暗い教室のなかから呆然と見送った。
それが、学生時代の雅臣と卯月が言葉を交わした最後の日だった。
あのときの言葉通り、卯月が雅臣に話しかけてくることは一度もなく、そのままふたりは小学校を卒業して別々の学生時代を過ごした。
十年の間に雅臣が卯月のことを思い出すことは何度かあったが、雅臣はそのたびにすぐ忘れるようにしていた。
そうして、誠に出会い、恋をして。
卯月のことはずっと忘れていて、忘れたつもりでいて。
でも本当は、初めて発情期を迎えたときも、誠に告白されたときも、雅臣の脳裏には『お前が好きだ』と言ったときの卯月の顔がよぎっていた。
けれども、心が乱されたのはほんの一瞬だけ。
きっと、卯月は夢から覚めたように雅臣のことなんて忘れて、ちゃんとふさわしい相手に恋をしている。美しくて、優しくて、ちゃんと家族に愛されていて、卯月のことを心から幸せにできる特別なひとが、彼の傍にいる。そうに決まっている。
今もまだ雅臣を好きだなんて、そんなことはあるはずがないのだと、そう思っていた。
▽ ▽ ▽
全身が熱い。汗で肌に衣服が張り付くのが気持ち悪くて身動ぐと、かすかに衣擦れの音がした。
雅臣はうっすらと目を開く。眩しい視界のなか、白い天井とシャンデリアのような豪華な照明がぼんやりと認識できた。
口からハァ、とやけに熱を持った吐息が零れる。
「目ぇ覚めたのか?」
すぐ傍から聞こえた声に視線を動かすと、ベッドの縁に腰掛けた卯月が雅臣を見下ろしていた。
その顔に、あの日の卯月が重なる。
お前が好きだと言った、寂しげで、愛おしさに満ちた、あのときの瞳。
雅臣は寝ぼけ眼のまま引き寄せられるように手を伸ばし、卯月の指通りのいいサラサラとした黒髪に触れる。
卯月は驚いたのか軽く息を呑んだが、そのまま雅臣の好きにさせてくれた。
「まだ俺が好きなのか……?」
「……じゃなきゃここまでするかよ」
そんなはずはないだろうと思いながら口にした問いに、予想外にも肯定と取れる言葉を返されて、雅臣は閉口した。
十年も前の幼少期の恋を未だに大事に抱えているなんて――それも、あの卯月総真が、この悠木雅臣に。
雅臣の唇に自嘲的な笑みが浮かぶ。
どうかしている。もし雅臣が卯月だったら、絶対に雅臣なんて好きにならない。
どれでもお好きなものをお選びください、と色取り取りの宝石が並べられた宝石箱を差し出されたにもかかわらず、わざわざしゃがみ込んで道端の石ころを拾い上げるくらい馬鹿げた話だ。
あり得ない。そう言って笑ってやりたいのに、言葉は出てこなかった。
目の奥が熱くて、視界が歪む。
あのとき――卯月が雅臣に好きだと言ってくれたとき、本当は少しうれしかったのだと思う。親にも愛してもらえなかった大嫌いな自分を好きだと言ってくれるひとがいて。釣り合ってなくても、運命じゃなくても、それでも。
「……ほんと、は」
「うん」
「お前が優しいやつだって、わかってた。俺のこと、好きだって言ってくれて、嫌じゃなかった。だけど、だけど……」
まだ夢のなかにいるような感覚のまま、雅臣は掠れた声で懸命に言葉を紡いだ。今伝えなければ、これから先も伝えられない気がした。
「俺は、お前に好きになってもらえるような人間じゃないから……みんな不釣り合いだって、身の程知らずだって言ったけど、そんなこと、俺自身が一番思ってた。俺はずっと、お前が羨ましくて……妬ましくて、そんな自分が、嫌いで堪らなかった……運命でもない、親にも捨てられた失敗作の俺に、なんでお前がそんなにこだわるのか、今でもわからない……」
卯月の顔を見られず、片手で顔を覆い隠す。
アルファに産まれたかった。卯月みたいな、上級の、完璧なアルファに。
憧れていた。手を伸ばせばなんでも手に入る卯月が羨ましかった。両親に、周りのひとに愛されている卯月が妬ましかった。
そんなことを思う自分がいっそう醜く思えて、嫌いで、苦しくて。
それなのに、卯月が自分を好きだなどと言い出すから、訳がわからなかった。
雅臣が途切れ途切れに紡いだ言葉を、卯月は黙って聞いていた。そして、短い沈黙のあと、大きなため息をつく。
「お前ってやつは……いつまでそんなこと気にしてんだよ。俺もお前も、もうガキじゃねぇんだぞ」
ベッドの上に乗ってきた卯月が、馬乗りになって雅臣を見下ろした。
部屋に満ちていた花の香りに気付くと同時に、カッと今までよりも強い熱が全身に広がり、一気に呼吸が苦しくなる。
どくりどくりと心臓の音がうるさい。服越しに触れ合った肌がピリピリと痺れるような、不思議な感覚がした。
「はっ、あ、あ……」
「大体、俺に不釣り合いかどうかは俺が決めることだろ。俺がお前を好きだって言ってんだから、俺に釣り合うのはお前しかいねぇんだよ。あと、もう二度と自分のこと失敗作とか言うな」
「ま、まって……は、あッ……なんか変だ……っ」
「もう待てねぇよ。こっちは十年も大人しくしてたんだぞ。……その間にお前は、他の男と婚約までしてたけどな」
「し、しらないッ、あっ、おれ……いやだ、あっ……ンッ」
突然頭を押さえつけられ、奪うように深く口付けられた。卯月の舌が傍若無人に雅臣の口内を舐め回し、その舌を搦めとる。角度を変えながら強く舌を吸われるたび、脳がとろけそうなほど気持ちが良くて、下腹部のあたりがきゅうっと収縮するように疼いた。
それから、数十秒後なのか数分後なのか、それすらわからなくなった頃、ようやく名残惜しげに口付けが解かれる。
注ぎ込まれた無性に甘く感じる唾液を呑み下すと、潤んだ視界の向こう、卯月の喉もゴクリと上下する。
卯月はうっとりと目を細めた。
「めちゃくちゃ甘ぇな……」
「はっ、ぁあ……や、やめ」
「そんなトロ顔で言われても説得力ねぇよ」
ククッと笑った卯月が雅臣の耳元に唇を寄せた。
「お前だってわかってんだろ。発情期のオメガはアルファを拒めないって」
発情期――朦朧としていた頭に届いた言葉に、火照っていた雅臣の顔が一瞬でサッと青ざめた。
三ヶ月に一度が一般的とされる発情期が前回来たのは、二ヶ月前。周期はさほど安定していなかったが、遅れることがあっても早まることは一度もなかったため油断していた。
確かに、この熱さも体の昂りも発情期特有のそれに違いなく、今の今までなぜ気付かなかったのかが不思議なくらいだ。
そして、先ほどから香っていた甘い花の匂いが卯月のアルファのフェロモンなのだと気付いた瞬間、息を吸い込むだけで頭のなかがとろとろと溶けていくような、初めての感覚に落ちていく。
頭ではダメだとわかっているのに、体に力が入らない。這うように体を撫でる卯月の手を押し返すこともできず、雅臣はただ喉を震わせて幼子のように卯月に縋り付いた。
「ッ……ま、まて、だめ……ダメだ……」
「よしよし、もう大丈夫だからな。薬が効きにくい体質なのに、今までひとりで耐えてつらかったよな。これからはずーっと、俺が助けてやるから――二度と他の男に尻尾振るんじゃねぇぞ」
「ひっ!」
途中までの砂糖菓子のように甘ったるい声色を一変させ、最後は低い囁きとともに、卯月はシャツの裾から忍び込ませた指先で雅臣の下腹部を強く押した。
腹の内側が感じたこともないような快感で痺れ、投げ出された足の爪先がキュッと丸まる。
「ここにたっぷり中出ししてやるから、一緒に気持ち良くなろうな?」
そう言って邪気のない顔で笑った卯月は、子どもの頃と同じように天使みたいに綺麗だった。
弱々しい抵抗も虚しく、ゆったりとした手つきでシャツを脱がされる。
オメガらしくない厚みのある上半身を見られるのが嫌で雅臣は身を捩ったが、腰の上で馬乗りになっている卯月の視線から逃れる術などなかった。
晒された素肌にうっとりと目を細めた卯月の手が、雅臣の上半身の輪郭をそっとなぞる。そうして、当然のように雅臣の胸に触れた。
「んっ」
「見た目よりやわらけぇな」
わずかに隆起しただけの胸筋を両手で優しく揉まれる。女性のような丸い膨らみも柔らかさもない平らなそこだが、卯月はひどく楽しそうだった。
「っ、そこは……」
「嫌か?」
「ンッ、や、ぁ」
卯月の指が雅臣の乳首をキュッと摘み、指の腹でこねくり回すように弄んだ。痛みよりも、ヒリヒリと痺れるような快感に目が潤む。
全身が、特に下腹部が熱い。まだ触れられてすらいない後孔の奥からじわりと愛液が滲み出すのがわかって、雅臣は動揺した。
こんなことは良くないと理性が訴えても、雅臣のオメガの本能はそれを受け入れてくれない。卯月から香る甘い匂いが、雅臣の頭のなかも体の内側もすべてどろどろに溶かしてしまう。
理性が本能に塗り潰されていく――それが、恐ろしくて、なのに心地よくて、雅臣の視界が涙で歪んだ。
「や、も、ダメだ……ほんとに、もう……ああッ」
卯月を押しのけようとなんとか伸ばした手を掴まれ、今度は散々弄られて赤く尖った乳首に顔を寄せられた。舌でねぶられたあとに唇で吸い付かれ、軽く歯を立てられる。
「んッ……あっ、やめッ……んあっ、あ、あ……!」
「乳首いじめられるの好きなんだな……かわいい」
「ちがっ……」
「こんなに硬くしといてなにが違うんだよ」
「ッ」
服の上から、完全に勃起してしまっている性器を掴まれ、扱くような手つきでゆっくりと擦られた。痺れるような快感に目が眩む。
「ひッ……だ、だめ、本当にっ……」
「イっちゃいそう?」
「イっちゃうっ、イっちゃうから……!」
雅臣がそう叫んだ瞬間、卯月の手の動きが速まり、もう片方の手で服越しに亀頭をぐりぐりと押し潰した。
「ッ、あ……あっ、あああぁ……ッ!」
腰をビクビクと震わせ、そのまま下着のなかに射精してしまった。突然の感覚に呆然となり、雅臣はしばらく動くことができなかった。
その間に、卯月の手によってズボンと下着を一気に脱がされる。
そして、濡れた性器を今度は直に触れられた。
オメガにしては大きなそれも雅臣にとってはコンプレックスのひとつだったが、卯月がそれを気にしている様子はない。しげしげと眺めながら、硬さを失った性器の感触を手のなかで楽しんでいるようだった。
「……ああ、こっちも触ってやらなきゃな」
膝を押され、強引に足を開かされると、期待にひくつく後孔から蜜があふれた。
卯月の指がゆっくりと縁をなぞり、別の指で濡れた窄まりを軽くつつく。
「んっ……あ、やっ……だめ、だめだから……」
「すっげぇ濡れてる。ちょっと触っただけで穴クパクパさせて……ほら、簡単に入ってく……」
「あっ、あ、んあぁ……ッ」
恍惚とした表情を浮かべながら、卯月は指先を雅臣の後孔につぷりと挿し込んだ。
そのままなんの抵抗もなく、長い指が根元まで収まってしまう。
拒まなければとわかっているのに体が思い通りにならず、口から出る拒絶の言葉ですら単なる甘い嬌声にしかならない。
そもそも、本当に拒まなければいけないのか、雅臣にはわからなくなっていた。
こんなに気持ち良くて、心地よくて堪らないのに、どうして拒まなければいけないのか――そんな雅臣の葛藤を無視して、後孔はうれしそうに卯月の指を締め付け、咀嚼するように蠢く。
卯月は自身の指を咥え込むそこを見て楽しそうに笑い、ナカをかき混ぜるようにゆっくりと指を動かした。
「んっ……はぁ、あ、ああ……」
「……トロトロで、俺の指にきゅうきゅう絡み付いてくる……もう一本増やすな」
「やっ、あ……ッあ!」
あっという間に増やされた二本の指で、熱くとろけたナカを探るように掻き回される。
ひとりで発情期を過ごしたときも、薬では抑えきれず自身の指でナカを弄ったことは何度かあったが、それとは比べものにならないほど強い快感だった。
「っんあ!」
「ここ、好きなんだ?」
「ひっ! あッ、んんっ……ッあ、ああぁ!」
ある箇所に卯月の指が触れた瞬間、雅臣の喉から一際高い嬌声が漏れた。
それを聞いた卯月はニヤリと笑い、そこを二本の指でグリグリと押し潰すように何度も刺激する。
「前立腺ってそんな気持ちいいんだな。このまま指だけでイケそう?」
「やっ、んあッ、ひぅッ、あっ、やぁ……ッ」
雅臣はふるふると首を振ったが、卯月は意地の悪い顔をしたまま雅臣の前立腺を攻め立て続ける。
やがて雅臣の腰がびくりと跳ね、再び硬く勃ち上がっていた性器からとろとろと白濁混じりの透明な液体があふれた。
「あッ、ああッ、はっ、あ、んぁ……ふ……あ、あ……はぁ……」
軽くイかされた状態でゆっくりと指を抜かれる。
とろけた目をした雅臣があとを引く快感に体を震わせているうちに、卯月は服を脱ぎはじめた。興奮しているのか、ジャケットもシャツも投げつけるようにベッドの下に放っている。
しなやかな筋肉を纏ったその肉体は、彫刻のように美しかった。割れた腹筋や硬そうな二の腕を見れば、しっかりと体を鍛えているのがわかる。端麗な顔と同様、無駄なもののない完璧な体だ。
思いがけず雅臣も見惚れたが、すぐにそれ以上の衝撃に目を見開く。
「……や、やだ」
「雅臣、大丈夫だから」
「むり、むりだから……やっ」
卯月は少し困ったような顔をした。その表情はどこか幼かったが、そのずっと下に生えている凶器はまったくもって幼くない。
オメガにしては大きいと言われる雅臣の性器よりも二回り以上大きく見えた。子どもの腕くらいあるのではないだろうか。
高校生のとき、アルファの彼氏と経験ずみだった同級生が「アルファのアレは馬並み」なんて言っていたが、雅臣は信じていなかった。笑っていた他の同級生たちもそうだったと思う。
だって、こんなの無理だ。入るはずがない。いくらオメガが孕む性だと揶揄される存在だとしても限度がある。
「……本当に無理?」
「ひッ……!」
わざとらしく眉を下げて笑った卯月が、雅臣の下腹部を指の腹でトントンと叩いた。
下腹部が――子宮がキュンと痺れて、後孔からとぷりと愛液が零れ落ちる。
無理だと思ったのは本当だ。
しかし、卯月の勃ち上がった性器を見た瞬間に子宮が疼き、口内に唾液があふれたのも事実だった。理性や感情とは別の、本能と呼ぶべき欲望が卯月を――アルファを求めている。その長大な性器に突かれて、種付けされたいと望んでいる。
「っあ、あ……」
「わかるか? ちょっと先っぽ当てただけなのに、お前の方から欲しがって、吸い付いてきてる」
「ちがっ……あッ、ま、まって!」
「もう待てねぇよ。十年待ったんだ」
大きく足を開かされ、後孔に押し当てられた性器の先端がズルリと雅臣のナカに入り込んできた。熱を持った大きなそれが、ゆっくりと肉壁を押し広げながら、迷いなく奥へと進んでいく。
「ッは、あっ! ああぁッ……は、あ、ああっ……」
「ははッ、入れられただけでところてんとかエロすぎ……」
自分でも気付かぬうちに、雅臣の性器からとぷとぷと精液があふれていた。
勢いのない射精を卯月が愛おしそうに見つめている。
「ふっ……はぁ、あ、ああっ……」
あんなに大きなものが、痛みも苦しさもなく、ずぶずぶと奥へ入っていく。あるのはとろけそうな快感と多幸感だけだった。
頭がおかしくなりそうなくらい気持ちがいい――いや、もうおかしくなっているのだろうか。
雅臣は震える声で小さく喘いだ。
「んっ、あっ、だめ、とけちゃう……」
「ダメじゃねーだろ、そんなやらしい顔して……ッ」
「ッや、動いたら……あっ、ンッ……おっきいの、だめ……おく、あ、ああッ、ん……」
「おっきいので奥突かれるの気持ちいい?」
「あっ、ああっ…………きもちい、きもちいいからっ……」
「お前、発情期だとそんな風になっちゃうんだな……すっげぇかわいい……もっといっぱい気持ち良くしてやるからな」
「やっ、あ! んッ、ああ!」
深くまでハメられた性器で、小刻みに何度も奥を突かれる。みっちりと後孔を満たす性器が動くたび、浅い部分にある前立腺も刺激されるという二重の快感に、雅臣はどうにかなりそうだった。
上体を倒してきた卯月が触れるだけのキスをして、雅臣に微笑む。
「なあ、鍵は?」
――鍵?
「だ、だって……俺なんか……」
「俺なんかとか言って自分のこと卑下するのやめろ。龍太郎みたいな馬鹿どもの言うことなんて真に受けてんじゃねぇよ」
「……そうやって偉そうに命令してくるとこ、嫌い」
雅臣がそう言い切った瞬間、繋がれていた卯月の手がびくっと跳ねた。
思い切って、今までの不満もぶちまける。
「幼稚園のとき、俺の好きな絵本やおもちゃを横取りしてくるのも嫌だったし、俺が真理亜たちと遊んでると邪魔してくるのも嫌だった。小学生になっても意地悪ばっかだし……」
「そ、そんなの、俺はお前に構ってほしくて……それに、確かに前はそんなこともあったけど、最近は意地悪なんかしてないだろっ?」
「してるよ。最近だと……俺が図工の時間に作った猫の置物のことクマとか言って馬鹿にしてた」
「いや、あれは本当にクマにしか見えなかったんだって……あんな凶悪な見た目の猫なんているかよ……」
「ほらっ、またそうやって意地悪言う! あと……俺が泣くとうれしそうに笑うの、あれすごく怖い」
「そ、それは……お前のことが好きだから……泣いた顔がかわいくて、つい……」
――なんだそれ。
頬を赤らめながら少しばかり気まずそうに言う卯月に、雅臣は呆れと驚きを隠せなかった。
「ずっと嫌われてるんだと思ってた……」
「はぁ?」
雅臣の言葉に、卯月は不機嫌そうに顔をしかめる。
心外だと言いたげな顔をされても、わかるはずがない。卯月の言動は雅臣にとって嫌がらせのようなものばかりだったのだ。
確かに卯月は、雅臣が他の子に取られたおもちゃを代わりに取り返してくれたり、この前のように馬鹿にされている場面で助けてくれることもあった。だが、卯月は誰に対してもそういう正義感を持っていたし、その反面嫌がらせのようなことをしているのは雅臣に対してだけだったのだ。
これで好かれていると思えるほど、雅臣はポジティブではない。むしろ、自尊心は人一倍低いのだ。
「大体、嫌いなやつに番になれとか婚約しろとか言う訳ないだろ?」
「俺のこと、一生いじめたいから傍に置いておきたいのかと……」
「お前のなかで俺の人間性どうなってんだよ……」
はぁ、と大きなため息をついた卯月はガシガシと頭を掻く。そして、気を取り直したように満足げな笑みを浮かべた。
「まあでも、これで誤解は解けたんだよな? 俺と婚約してくれるだろ?」
「え……なんでそうなるの……?」
「は? なんだよ、嫌なのか?」
嫌に決まっている。
雅臣はずっと卯月に嫌われていると思っていたのだ。いくら好かれているとわかったからといって、長年の苦手意識は消えない。
なにより、雅臣と卯月はすべてにおいて釣り合っていない。それは、他の誰かに言われたからではなく、初めて卯月と出会ったときに雅臣自身が感じ取ったことだ。
卯月は他の誰よりも特別で、眩しい。きっと、生まれたときから雅臣とは住んでいる世界が違うのだ。
けれど、それを言ったところで卯月はわかってはくれないだろう。
傲慢で、我が儘で、そのくせ真っ当なこの少年は、当然のように雅臣を自分と同等の存在だと思っている。自分は特別なのだと卯月がちゃんとした意味で理解していないことが、よりいっそう雅臣をちっぽけな存在にする。
「総真くんのことが嫌いな訳じゃないけど……でも、俺は総真くんと一緒にいるとつらいし、どっちも幸せになれないと思う」
「なんだよ、それ……」
卯月は目を見開いたあと、今にも泣き出しそうな顔で悔しそうに唇を噛んだ。
その顔から目を逸らして、雅臣は言葉を続ける。
「……それに、まだ子どもだから婚約のことなんてすぐには決められないよ。大人になってからじゃないと……」
「大人になったらっていつだよ」
「……十年後くらい?」
「はぁあああぁ?」
そこで、タイミングよくチャイムが鳴り響いた。
これ幸いと、雅臣は繋がれたままの卯月の手を引いて教室を出る。
「おい! まだ話はっ……」
「授業はじまっちゃうから」
そう言った雅臣がギュッと手を握ると、卯月は押し黙った。卯月の手のひらは汗ばみそうなほど熱を持っていて、痛いくらいの強さで雅臣の手を握り返してくる。
雅臣が卯月の教室の前で手を離すと、卯月は少し赤らんだ顔でフンとそっぽを向いた。
「まだ話は終わってないからなっ」
「じゃあね……」
都合の悪いことは聞かなかったふりをして、雅臣も自分のクラスへと戻った。
その後の時間は、休んでいたときの授業内容を真理亜たちに教わりながら普通に過ごすことができた。卯月が昼休みにやってきたが、雅臣が真理亜のノートを書き写している姿を見ると無言で帰っていった。この前のことがあったからか、室井たちが雅臣に近付いてくることもなく、平穏な一日だった。
放課後にも、今朝の話の続きをしようと、卯月が靴箱で雅臣を待ち構えていたが、祖父が車で迎えに来てくれていることを話すと渋々引き下がっていった。
そのとき、「俺は十年も待つ気はないからな!」と強く主張されたのだが、翌日になって状況が一変することになる。
「……十年待つ」
翌朝、前日と同じ空き教室に雅臣を連れ込んだ卯月が、ふてくされた表情でそんなことを言った。
昨日とは正反対の言葉に、雅臣は困惑する。
「……え?」
「昨日お前が言ったんだろ……大人になってからじゃないと決められないって」
「でも、昨日は嫌そうだったのに……」
「……親父に怒られた」
ふてくされた顔がさらに不機嫌そうに歪む。
そんな表情ですらかわいげがあって、やはりずるいなと雅臣は頭の片隅で思った。
「今まで嫌われてるって誤解させるような態度取ってた俺が悪いって……雅臣が俺と婚約したがらないのも当然だって……それで、反省の意味も込めて、お前の言う通り大人になるまで待つことにした……」
いつになく歯切れ悪く喋る卯月に、雅臣は首を傾げて尋ねた。
「よくわからないけど、つまり、婚約の話はなしってこと?」
「……まぁ、いったん白紙にはなる。……それと、十年待ってる間、なるべくお前に関わらないようにもするから……」
雅臣は驚いて目を丸くした。
もともと受け入れていなかった婚約云々の話よりも、そちらの方が雅臣にとってはよっぽど重要な話だ。
「か、関わらないって……もうこんな風に話したりしないってことだよね?」
しばしの沈黙のあと、卯月は無言で頷いた。
奥歯を噛み締め、叫び出すのを我慢しているような苦渋の表情は、到底それに納得しているようには見えない。
だが、頷いたということは紛れもなく肯定だ。
正直言って、雅臣には話の流れがまったくわからなかった。ただ、卯月父子の間でなんらかの取り決めがあったのは確かだろう。
学校行事で何度か卯月の父親を見たことがあるが、周りが甘やかすからなのかその分、卯月に厳しく接していた。傍若無人な卯月も多少反抗的ではあったが、父親の言うことには渋々従っていたような気がする。
卯月側の詳しい事情はわからないが、とにかくこれから十年は卯月と関わらなくてすむ――そう考えただけで、自然と雅臣の表情がパァッと華やいだ。
それを見て、今までしょぼくれていた卯月の目尻がキッと吊り上がる。
「だっ、だからって、俺がお前を諦めた訳じゃないからな! つか、うれしそうな顔すんな! 傷付くだろうがっ!」
「ご、ごめん」
それでも、雅臣にとっては十分だ。十年も猶予期間があれば、きっと卯月も雅臣が取るに足らない存在だと気付くだろう。雅臣は他の学校に進学するのだから、物理的に距離もできる。その間に卯月が他の誰かを気に入ったら、雅臣との婚約の話なんて自然消滅確定だ。
「……お前、なにあからさまにホッとしてんだよ。まさか、十年程度で俺が心変わりするとか思ってねぇよな?」
「べ、別にそういう訳じゃ……」
否定しつつも目は泳いでしまう。
卯月は怪訝そうな表情をしたままだったが、やがてハァとため息をついてから付け加えるように言った。
「……あと、俺も中学からは有流都学園に転校することにしたから」
「有流都学園?」
「アルファ専用の学校だよ。お前がいなくなるなら、こんなとこ通う意味もねぇしな」
雅臣は知らなかったが、オメガ専用の学校があるのだからアルファ専用の学校も当然あるだろう。
どちらにせよ、雅臣とは別々の学校だ。卯月からも、その他の悪意からも解放されるのだと思うと、胸がスッとした。
そんな雅臣とは対照的に、卯月はひどく浮かない顔をしてぼそぼそと呟く。
「……さっき言った通り、これから十年は、お前に話しかけたり絡んだりしない。本当は嫌だけど、俺が悪いし……お前、うれしそうだしな」
「……少しはさみしいよ」
「どうだかな」
肩を竦めた卯月は、雅臣よりもずっと寂しそうに力なく笑う。そして、細められた目が愛おしそうに雅臣を見つめた。
雅臣は軽く息を呑む。
卯月がそんな瞳で雅臣を見るのは初めてで――いや、本当にそうだろうか。
もしかしたら、今までもこんな風に卯月が雅臣を見つめたことはあったのかもしれない。雅臣がいつも俯いて、卯月を見ようとしなかったから知らないだけで、卯月はずっと雅臣を好きでいてくれたのかもしれない。
長い沈黙による静寂のせいなのか、いつもは気にならない自身の心臓の音がやけに大きく聞こえた。
やがて卯月の桜色の唇が、小さく笑みを浮かべる。
「お前が好きだ」
一瞬、時間が止まってしまったかのように、ふたり見つめ合っていた。
瞬きも、呼吸さえも忘れ、卯月のらしくない穏やかな微笑みに引き寄せられる。
それは天使みたいに綺麗で、卯月の顔を見慣れている雅臣ですら見惚れるほど美しかった。
「十年たったら会いに行く」
優しげで、真っ直ぐな視線から逃れることもできず、雅臣はなぜだか泣きそうな気分になりながら唇を震わせる。
「……きっと、覚えてないよ」
「お前が忘れても、俺は絶対覚えてるんだから関係ねぇよ」
そうじゃない。忘れるのはきっと、雅臣じゃなくて卯月の方だ。
雅臣はただ黙ったまま俯いた。先ほどの卯月の言葉に、らしくない表情に、心を揺さぶられた自分がいた。
けれど、これがなにを意味するのか、雅臣は知らないふりをする。
ただ、雅臣にとって卯月は特別だった。それだけは、雅臣も認める本当のことだ。
「……じゃあ、またな」
長いようで短い沈黙のあと、卯月はそう言い残し、走って教室を出ていく。
朝の淡い陽の光に照らされた廊下を走り抜けていくその後ろ姿を、雅臣は薄暗い教室のなかから呆然と見送った。
それが、学生時代の雅臣と卯月が言葉を交わした最後の日だった。
あのときの言葉通り、卯月が雅臣に話しかけてくることは一度もなく、そのままふたりは小学校を卒業して別々の学生時代を過ごした。
十年の間に雅臣が卯月のことを思い出すことは何度かあったが、雅臣はそのたびにすぐ忘れるようにしていた。
そうして、誠に出会い、恋をして。
卯月のことはずっと忘れていて、忘れたつもりでいて。
でも本当は、初めて発情期を迎えたときも、誠に告白されたときも、雅臣の脳裏には『お前が好きだ』と言ったときの卯月の顔がよぎっていた。
けれども、心が乱されたのはほんの一瞬だけ。
きっと、卯月は夢から覚めたように雅臣のことなんて忘れて、ちゃんとふさわしい相手に恋をしている。美しくて、優しくて、ちゃんと家族に愛されていて、卯月のことを心から幸せにできる特別なひとが、彼の傍にいる。そうに決まっている。
今もまだ雅臣を好きだなんて、そんなことはあるはずがないのだと、そう思っていた。
▽ ▽ ▽
全身が熱い。汗で肌に衣服が張り付くのが気持ち悪くて身動ぐと、かすかに衣擦れの音がした。
雅臣はうっすらと目を開く。眩しい視界のなか、白い天井とシャンデリアのような豪華な照明がぼんやりと認識できた。
口からハァ、とやけに熱を持った吐息が零れる。
「目ぇ覚めたのか?」
すぐ傍から聞こえた声に視線を動かすと、ベッドの縁に腰掛けた卯月が雅臣を見下ろしていた。
その顔に、あの日の卯月が重なる。
お前が好きだと言った、寂しげで、愛おしさに満ちた、あのときの瞳。
雅臣は寝ぼけ眼のまま引き寄せられるように手を伸ばし、卯月の指通りのいいサラサラとした黒髪に触れる。
卯月は驚いたのか軽く息を呑んだが、そのまま雅臣の好きにさせてくれた。
「まだ俺が好きなのか……?」
「……じゃなきゃここまでするかよ」
そんなはずはないだろうと思いながら口にした問いに、予想外にも肯定と取れる言葉を返されて、雅臣は閉口した。
十年も前の幼少期の恋を未だに大事に抱えているなんて――それも、あの卯月総真が、この悠木雅臣に。
雅臣の唇に自嘲的な笑みが浮かぶ。
どうかしている。もし雅臣が卯月だったら、絶対に雅臣なんて好きにならない。
どれでもお好きなものをお選びください、と色取り取りの宝石が並べられた宝石箱を差し出されたにもかかわらず、わざわざしゃがみ込んで道端の石ころを拾い上げるくらい馬鹿げた話だ。
あり得ない。そう言って笑ってやりたいのに、言葉は出てこなかった。
目の奥が熱くて、視界が歪む。
あのとき――卯月が雅臣に好きだと言ってくれたとき、本当は少しうれしかったのだと思う。親にも愛してもらえなかった大嫌いな自分を好きだと言ってくれるひとがいて。釣り合ってなくても、運命じゃなくても、それでも。
「……ほんと、は」
「うん」
「お前が優しいやつだって、わかってた。俺のこと、好きだって言ってくれて、嫌じゃなかった。だけど、だけど……」
まだ夢のなかにいるような感覚のまま、雅臣は掠れた声で懸命に言葉を紡いだ。今伝えなければ、これから先も伝えられない気がした。
「俺は、お前に好きになってもらえるような人間じゃないから……みんな不釣り合いだって、身の程知らずだって言ったけど、そんなこと、俺自身が一番思ってた。俺はずっと、お前が羨ましくて……妬ましくて、そんな自分が、嫌いで堪らなかった……運命でもない、親にも捨てられた失敗作の俺に、なんでお前がそんなにこだわるのか、今でもわからない……」
卯月の顔を見られず、片手で顔を覆い隠す。
アルファに産まれたかった。卯月みたいな、上級の、完璧なアルファに。
憧れていた。手を伸ばせばなんでも手に入る卯月が羨ましかった。両親に、周りのひとに愛されている卯月が妬ましかった。
そんなことを思う自分がいっそう醜く思えて、嫌いで、苦しくて。
それなのに、卯月が自分を好きだなどと言い出すから、訳がわからなかった。
雅臣が途切れ途切れに紡いだ言葉を、卯月は黙って聞いていた。そして、短い沈黙のあと、大きなため息をつく。
「お前ってやつは……いつまでそんなこと気にしてんだよ。俺もお前も、もうガキじゃねぇんだぞ」
ベッドの上に乗ってきた卯月が、馬乗りになって雅臣を見下ろした。
部屋に満ちていた花の香りに気付くと同時に、カッと今までよりも強い熱が全身に広がり、一気に呼吸が苦しくなる。
どくりどくりと心臓の音がうるさい。服越しに触れ合った肌がピリピリと痺れるような、不思議な感覚がした。
「はっ、あ、あ……」
「大体、俺に不釣り合いかどうかは俺が決めることだろ。俺がお前を好きだって言ってんだから、俺に釣り合うのはお前しかいねぇんだよ。あと、もう二度と自分のこと失敗作とか言うな」
「ま、まって……は、あッ……なんか変だ……っ」
「もう待てねぇよ。こっちは十年も大人しくしてたんだぞ。……その間にお前は、他の男と婚約までしてたけどな」
「し、しらないッ、あっ、おれ……いやだ、あっ……ンッ」
突然頭を押さえつけられ、奪うように深く口付けられた。卯月の舌が傍若無人に雅臣の口内を舐め回し、その舌を搦めとる。角度を変えながら強く舌を吸われるたび、脳がとろけそうなほど気持ちが良くて、下腹部のあたりがきゅうっと収縮するように疼いた。
それから、数十秒後なのか数分後なのか、それすらわからなくなった頃、ようやく名残惜しげに口付けが解かれる。
注ぎ込まれた無性に甘く感じる唾液を呑み下すと、潤んだ視界の向こう、卯月の喉もゴクリと上下する。
卯月はうっとりと目を細めた。
「めちゃくちゃ甘ぇな……」
「はっ、ぁあ……や、やめ」
「そんなトロ顔で言われても説得力ねぇよ」
ククッと笑った卯月が雅臣の耳元に唇を寄せた。
「お前だってわかってんだろ。発情期のオメガはアルファを拒めないって」
発情期――朦朧としていた頭に届いた言葉に、火照っていた雅臣の顔が一瞬でサッと青ざめた。
三ヶ月に一度が一般的とされる発情期が前回来たのは、二ヶ月前。周期はさほど安定していなかったが、遅れることがあっても早まることは一度もなかったため油断していた。
確かに、この熱さも体の昂りも発情期特有のそれに違いなく、今の今までなぜ気付かなかったのかが不思議なくらいだ。
そして、先ほどから香っていた甘い花の匂いが卯月のアルファのフェロモンなのだと気付いた瞬間、息を吸い込むだけで頭のなかがとろとろと溶けていくような、初めての感覚に落ちていく。
頭ではダメだとわかっているのに、体に力が入らない。這うように体を撫でる卯月の手を押し返すこともできず、雅臣はただ喉を震わせて幼子のように卯月に縋り付いた。
「ッ……ま、まて、だめ……ダメだ……」
「よしよし、もう大丈夫だからな。薬が効きにくい体質なのに、今までひとりで耐えてつらかったよな。これからはずーっと、俺が助けてやるから――二度と他の男に尻尾振るんじゃねぇぞ」
「ひっ!」
途中までの砂糖菓子のように甘ったるい声色を一変させ、最後は低い囁きとともに、卯月はシャツの裾から忍び込ませた指先で雅臣の下腹部を強く押した。
腹の内側が感じたこともないような快感で痺れ、投げ出された足の爪先がキュッと丸まる。
「ここにたっぷり中出ししてやるから、一緒に気持ち良くなろうな?」
そう言って邪気のない顔で笑った卯月は、子どもの頃と同じように天使みたいに綺麗だった。
弱々しい抵抗も虚しく、ゆったりとした手つきでシャツを脱がされる。
オメガらしくない厚みのある上半身を見られるのが嫌で雅臣は身を捩ったが、腰の上で馬乗りになっている卯月の視線から逃れる術などなかった。
晒された素肌にうっとりと目を細めた卯月の手が、雅臣の上半身の輪郭をそっとなぞる。そうして、当然のように雅臣の胸に触れた。
「んっ」
「見た目よりやわらけぇな」
わずかに隆起しただけの胸筋を両手で優しく揉まれる。女性のような丸い膨らみも柔らかさもない平らなそこだが、卯月はひどく楽しそうだった。
「っ、そこは……」
「嫌か?」
「ンッ、や、ぁ」
卯月の指が雅臣の乳首をキュッと摘み、指の腹でこねくり回すように弄んだ。痛みよりも、ヒリヒリと痺れるような快感に目が潤む。
全身が、特に下腹部が熱い。まだ触れられてすらいない後孔の奥からじわりと愛液が滲み出すのがわかって、雅臣は動揺した。
こんなことは良くないと理性が訴えても、雅臣のオメガの本能はそれを受け入れてくれない。卯月から香る甘い匂いが、雅臣の頭のなかも体の内側もすべてどろどろに溶かしてしまう。
理性が本能に塗り潰されていく――それが、恐ろしくて、なのに心地よくて、雅臣の視界が涙で歪んだ。
「や、も、ダメだ……ほんとに、もう……ああッ」
卯月を押しのけようとなんとか伸ばした手を掴まれ、今度は散々弄られて赤く尖った乳首に顔を寄せられた。舌でねぶられたあとに唇で吸い付かれ、軽く歯を立てられる。
「んッ……あっ、やめッ……んあっ、あ、あ……!」
「乳首いじめられるの好きなんだな……かわいい」
「ちがっ……」
「こんなに硬くしといてなにが違うんだよ」
「ッ」
服の上から、完全に勃起してしまっている性器を掴まれ、扱くような手つきでゆっくりと擦られた。痺れるような快感に目が眩む。
「ひッ……だ、だめ、本当にっ……」
「イっちゃいそう?」
「イっちゃうっ、イっちゃうから……!」
雅臣がそう叫んだ瞬間、卯月の手の動きが速まり、もう片方の手で服越しに亀頭をぐりぐりと押し潰した。
「ッ、あ……あっ、あああぁ……ッ!」
腰をビクビクと震わせ、そのまま下着のなかに射精してしまった。突然の感覚に呆然となり、雅臣はしばらく動くことができなかった。
その間に、卯月の手によってズボンと下着を一気に脱がされる。
そして、濡れた性器を今度は直に触れられた。
オメガにしては大きなそれも雅臣にとってはコンプレックスのひとつだったが、卯月がそれを気にしている様子はない。しげしげと眺めながら、硬さを失った性器の感触を手のなかで楽しんでいるようだった。
「……ああ、こっちも触ってやらなきゃな」
膝を押され、強引に足を開かされると、期待にひくつく後孔から蜜があふれた。
卯月の指がゆっくりと縁をなぞり、別の指で濡れた窄まりを軽くつつく。
「んっ……あ、やっ……だめ、だめだから……」
「すっげぇ濡れてる。ちょっと触っただけで穴クパクパさせて……ほら、簡単に入ってく……」
「あっ、あ、んあぁ……ッ」
恍惚とした表情を浮かべながら、卯月は指先を雅臣の後孔につぷりと挿し込んだ。
そのままなんの抵抗もなく、長い指が根元まで収まってしまう。
拒まなければとわかっているのに体が思い通りにならず、口から出る拒絶の言葉ですら単なる甘い嬌声にしかならない。
そもそも、本当に拒まなければいけないのか、雅臣にはわからなくなっていた。
こんなに気持ち良くて、心地よくて堪らないのに、どうして拒まなければいけないのか――そんな雅臣の葛藤を無視して、後孔はうれしそうに卯月の指を締め付け、咀嚼するように蠢く。
卯月は自身の指を咥え込むそこを見て楽しそうに笑い、ナカをかき混ぜるようにゆっくりと指を動かした。
「んっ……はぁ、あ、ああ……」
「……トロトロで、俺の指にきゅうきゅう絡み付いてくる……もう一本増やすな」
「やっ、あ……ッあ!」
あっという間に増やされた二本の指で、熱くとろけたナカを探るように掻き回される。
ひとりで発情期を過ごしたときも、薬では抑えきれず自身の指でナカを弄ったことは何度かあったが、それとは比べものにならないほど強い快感だった。
「っんあ!」
「ここ、好きなんだ?」
「ひっ! あッ、んんっ……ッあ、ああぁ!」
ある箇所に卯月の指が触れた瞬間、雅臣の喉から一際高い嬌声が漏れた。
それを聞いた卯月はニヤリと笑い、そこを二本の指でグリグリと押し潰すように何度も刺激する。
「前立腺ってそんな気持ちいいんだな。このまま指だけでイケそう?」
「やっ、んあッ、ひぅッ、あっ、やぁ……ッ」
雅臣はふるふると首を振ったが、卯月は意地の悪い顔をしたまま雅臣の前立腺を攻め立て続ける。
やがて雅臣の腰がびくりと跳ね、再び硬く勃ち上がっていた性器からとろとろと白濁混じりの透明な液体があふれた。
「あッ、ああッ、はっ、あ、んぁ……ふ……あ、あ……はぁ……」
軽くイかされた状態でゆっくりと指を抜かれる。
とろけた目をした雅臣があとを引く快感に体を震わせているうちに、卯月は服を脱ぎはじめた。興奮しているのか、ジャケットもシャツも投げつけるようにベッドの下に放っている。
しなやかな筋肉を纏ったその肉体は、彫刻のように美しかった。割れた腹筋や硬そうな二の腕を見れば、しっかりと体を鍛えているのがわかる。端麗な顔と同様、無駄なもののない完璧な体だ。
思いがけず雅臣も見惚れたが、すぐにそれ以上の衝撃に目を見開く。
「……や、やだ」
「雅臣、大丈夫だから」
「むり、むりだから……やっ」
卯月は少し困ったような顔をした。その表情はどこか幼かったが、そのずっと下に生えている凶器はまったくもって幼くない。
オメガにしては大きいと言われる雅臣の性器よりも二回り以上大きく見えた。子どもの腕くらいあるのではないだろうか。
高校生のとき、アルファの彼氏と経験ずみだった同級生が「アルファのアレは馬並み」なんて言っていたが、雅臣は信じていなかった。笑っていた他の同級生たちもそうだったと思う。
だって、こんなの無理だ。入るはずがない。いくらオメガが孕む性だと揶揄される存在だとしても限度がある。
「……本当に無理?」
「ひッ……!」
わざとらしく眉を下げて笑った卯月が、雅臣の下腹部を指の腹でトントンと叩いた。
下腹部が――子宮がキュンと痺れて、後孔からとぷりと愛液が零れ落ちる。
無理だと思ったのは本当だ。
しかし、卯月の勃ち上がった性器を見た瞬間に子宮が疼き、口内に唾液があふれたのも事実だった。理性や感情とは別の、本能と呼ぶべき欲望が卯月を――アルファを求めている。その長大な性器に突かれて、種付けされたいと望んでいる。
「っあ、あ……」
「わかるか? ちょっと先っぽ当てただけなのに、お前の方から欲しがって、吸い付いてきてる」
「ちがっ……あッ、ま、まって!」
「もう待てねぇよ。十年待ったんだ」
大きく足を開かされ、後孔に押し当てられた性器の先端がズルリと雅臣のナカに入り込んできた。熱を持った大きなそれが、ゆっくりと肉壁を押し広げながら、迷いなく奥へと進んでいく。
「ッは、あっ! ああぁッ……は、あ、ああっ……」
「ははッ、入れられただけでところてんとかエロすぎ……」
自分でも気付かぬうちに、雅臣の性器からとぷとぷと精液があふれていた。
勢いのない射精を卯月が愛おしそうに見つめている。
「ふっ……はぁ、あ、ああっ……」
あんなに大きなものが、痛みも苦しさもなく、ずぶずぶと奥へ入っていく。あるのはとろけそうな快感と多幸感だけだった。
頭がおかしくなりそうなくらい気持ちがいい――いや、もうおかしくなっているのだろうか。
雅臣は震える声で小さく喘いだ。
「んっ、あっ、だめ、とけちゃう……」
「ダメじゃねーだろ、そんなやらしい顔して……ッ」
「ッや、動いたら……あっ、ンッ……おっきいの、だめ……おく、あ、ああッ、ん……」
「おっきいので奥突かれるの気持ちいい?」
「あっ、ああっ…………きもちい、きもちいいからっ……」
「お前、発情期だとそんな風になっちゃうんだな……すっげぇかわいい……もっといっぱい気持ち良くしてやるからな」
「やっ、あ! んッ、ああ!」
深くまでハメられた性器で、小刻みに何度も奥を突かれる。みっちりと後孔を満たす性器が動くたび、浅い部分にある前立腺も刺激されるという二重の快感に、雅臣はどうにかなりそうだった。
上体を倒してきた卯月が触れるだけのキスをして、雅臣に微笑む。
「なあ、鍵は?」
――鍵?
応援ありがとうございます!
4
お気に入りに追加
4,398
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。