10 / 13
第10話 鉄路の咆哮、あるいは構造の軋み
しおりを挟む
1998年、6月。修学旅行当日の朝は、霧雨を孕んだ重い雲が低く垂れ込めていた。
午前5時30分。俺は、自室のデスクで最終的な持ち物点検を行っていた。
「……写ルンです、予備を含めて3本。おやつは300円以内という建前だが、カロリーメイトとウィダーインゼリーで実利を取る。しおり、筆記用具。そして、緊急連絡用のテレホンカード」
俺は、彫りの深い貌を鏡に向けた。
荷物は、当時のスタンダードな大型リュックサックにまとめている。最近ではキャリーケースを引く生徒も増え始めていたが、段差の多い京都の寺社仏閣や、砂利道での機動性を考えれば、背負うタイプが正解だ。「階段で詰まる」「電車内で場所を取る」といった、集団行動におけるボトルネックを避けるのは、元銀行マンとしてのリスク管理の基本である。
当時の撮影事情は、デジタルカメラがまだ一般的ではなかった。
写真は、フジカラーの『写ルンです』のようなレンズ付きフィルムが主流だ。修学旅行の終わりには、クラス全員が同じような緑色のプラスチックの塊を手にし、現像に出して数日待たなければ結果がわからない。個人でカメラを持つ者は稀で、たまに親から借りたAPSカメラを持っている奴がいれば、それが羨望の的となる、そんな牧歌的な時代だった。
「任三郎、時間よ! お父さんが駅まで車で送ってくれるって」
階下から、母の声が響く。
リビングに降りると、そこには薄手のニットにタイトなスラックスを合わせた、早朝とは思えないほど完璧な美しさを湛えた美津子がいた。彼女のしなやかな肢体と、朝露のように瑞々しい肌は、八王子の静かな住宅街において、あまりに過剰な華やかさを放っている。
「……父さん、悪いな。仕事の前に」
「気にするな。任三郎、京都の歴史もいいが、今の関西がどう動いているか、しっかり見てこいよ。銀行員としての視点を忘れるな」
父が、ハンドルを握りながらバックミラー越しに息子を見た。
「……ああ。観光の皮を被った、実地監査だと思って見てくるよ」
午前6時45分。八王子駅の改札前は、巨大なリュックを背負った中学3年生たちで埋め尽くされていた。
同学年、約200人。クラスごとに整列し、担任による点呼が始まる。
「3年2組、全員いるか? ……一人足りないな。佐々木か?」
担任が、駅の公衆電話から親に連絡を入れる。まだ携帯電話が子供に普及していない時代、急な遅刻や欠席の確認には時間がかかる。結局、佐々木は急な高熱による病欠であることが判明した。
「……情報の伝達速度が、この時代の最大の脆弱性だな」
俺は心の中で呟いた。
「おい任三郎! 準備万端かよ。俺、昨日の夜興奮して全然寝れなかったぜ!」
門廻邦彦が、朝日を反射するような輝かしい笑顔で駆け寄ってきた。
日焼けした肌、清潔感のある短髪。彼はまさに1998年の太陽そのものだ。その後ろからは、クールな塩顔の北子直樹が、落ち着いた足取りで続いてくる。
「邦彦、騒ぐな。まだ八王子だぞ。……葛石、新幹線は何系に乗れるか聞いたか?」
直樹の鋭い視線が、ホームへと向けられる。
「……横浜線で新横浜へ向かい、そこから『のぞみ』か『ひかり』だ。ホームで待っているのは、300系あたりが自然だろうな。カモノハシのような先頭形状。あれが日本の高度経済成長の最後を象徴する『鉄路の怪物』だ」
「鉄路の怪物……。お前、相変わらず言い回しが独特だな」
俺たちは横浜線に揺られ、新横浜駅へ。
新幹線のホームに滑り込んできたのは、期待通りの300系新幹線だった。白地に青いライン、少し角張ったそのフォルムに、生徒たちから「うおー!」「速そう!」と歓声が上がる。
「見て! 私、お父さんからこれを借りてきたの」
東鶴襟華が、バッグから小さなシルバーのカメラを取り出した。
愛らしい笑顔と知的なショートカット。彼女の手には、当時最新鋭だった『Canon IXY』――APSカメラが握られていた。
「すごいわね、新幹線。横から見ると、本当に巨大な槍みたい。任三郎くん、一緒に撮ってあげる」
「……俺は、撮られるより撮る方が専門だ。シャッターチャンスは、歴史が動く瞬間にしか訪れないからな」
「もう、理屈ばっかり。はい、ポーズ!」
襟華の屈託のない笑顔に、俺の冷徹な仮面が微かに緩む。APSフィルムの「カシャッ」という軽快な巻き上げ音が、旅の始まりを告げていた。
新幹線の車内。
自由行動の班は、俺、邦彦、襟華、直樹、そして1組から合流した上波茜、日名川彩の6人で構成されていた。
「よろしくお願いします、葛石くん。門廻くん」
上波茜が、圧倒的な気品で、深々と頭を下げた。170cm近い長身に、陶器のような白い肌。野球部マネージャーとして鍛えられた彼女の背筋は、中学生とは思えない高潔なオーラを放っている。
「日名川です。移動中のお菓子、少し多めに作ってきちゃった。みんなで食べましょう」
日名川彩が、柔らかく透明感のある微笑みでタッパーを差し出す。彼女から漂うハーブと焼き菓子の香りが、殺伐とした新幹線の空気感を一瞬で「サロン」に変えてしまった。
「……賑やかな班になりそうだな。直樹、バランス調整を頼むぞ」
「了解した。俺はこの個性の強すぎる連中を、時間通りに京都へ届けることに全力を尽くすよ」
直樹が苦笑いしながら席を整える。
座席を回転させ、6人で向かい合わせになる。
窓の外、富士山がゆっくりと通り過ぎていく。1998年の景色。まだ高層ビルが少なく、空が広い。
「よし、新幹線といえばUNOだろ! 負けた奴は、好きな奴の名前を白状する。いいな!」
邦彦がカードを配り始める。
俺は配られたカードを、財務諸表を監査するように眺めた。
数字の増減。相手の残りの手札。表情の揺らぎ。
UNOという子供の遊びですら、俺にとっては情報の非対称性を利用したシミュレーションの場だ。
「葛石くん、さっきから全然表情が変わらないわね。……ドロー4を出された時も、まるで金利の上昇を見守る銀行員みたいに冷静なんだもの」
襟華が楽しそうに俺の顔を覗き込む。
「……カードの配分には確率論があるだけだ。そこに一喜一憂するコストは支払わない」
「ふふ、でも、日名川さんの『ワイルド』カードには勝てないみたいよ?」
茜が、涼しげな瞳で俺の敗北を予言した。
京都までの数時間。
UNOの応酬と、1998年の初夏の車窓。
俺の内側に潜む60歳の亡霊は、この「無価値な時間」こそが、2043年には失われていた最大の贅沢であることを、皮肉にも噛み締めていた。
京都に到着すると、駅前の喧騒は修学旅行生と外国人観光客で溢れかえっていた。
俺たちは団体用のバスに乗り込み、清水寺、金閣寺、銀閣寺を強行軍で巡った。
「金閣寺……。足利義満の権力誇示の極致だな。だが、この金箔の維持費に、どれだけの拝観料が投じられているのか」
俺が呟くと、後ろでスコアブックをつけていた茜が頷いた。
「規律ある美しさね。でも、どこか空虚だわ。……見られていることを意識しすぎている」
「私は銀閣寺の方が好きだな。わびさび……。時間をかけて色褪せていくものにしか宿らない価値があるわ」
彩が、静かな佇まいで、庭園の苔を見つめていた。
初日の観光を終え、俺たちが向かったのは京都市内の大規模な旅館だった。
長い回廊を通り、案内されたのは、100畳はあろうかという広い座敷。
そこには、200人の生徒たちが一堂に会して夕食を取るための、簡素な御膳が並べられていた。
「……いただきます」
一斉に食事が始まる。
だが、一口食べた瞬間、班の女子たちの表情が曇った。
「……味が、薄いというか。素材の味が死んでるわね」
彩が、職人気質の鋭い味覚で眉を寄せた。
「冷めてるわ。効率を重視して、数時間前から並べていたのが丸分かりね」
茜が、規律に厳しい視線で御膳を見つめる。
「京都の旅館って、もっと繊細なものだと思ってたんだけど……。ちょっと期待外れかな」
襟華が、愛らしい顔を少しだけ歪めた。
邦彦と直樹は「腹に入れば同じだぜ!」と豪快に食べていたが、俺は箸を置き、その光景を分析した。
(サービス低下……。一見客である修学旅行生を『効率的な処理対象』としてしか見ていない証拠だ。大量生産・大量消費の観光モデル。これが将来のリピーター減少を招き、宿泊産業を衰退させる毒になる)
俺は、2043年の地獄を思い出した。
(未来では、こうした伝統ある旅館の多くが外資に買い叩かれ、あるいは人手不足で廃墟と化していた。今、目の前にあるこの『手抜き』こそが、崩壊への不渡り手形だ)
「……任三郎くん。また、怖い目をしてるわよ」
襟華が、そっと俺の袖を引いた。
「……いや。この出汁の薄さは、今の日本経済の『体力のなさ』と同期しているようでな。……東鶴さん。この味を覚えておくといい。これが『失われる前』の、末期の輝きだ」
「……何それ、不吉ね」
俺は心の中で、自分自身の「裏の行程表」を更新した。
観光資源としての日本。それを再生するには、単なる「もてなし」の精神だけでは足りない。
圧倒的な資本による再編。そして、本物の価値を理解する者だけを顧客にする、会員制の極めて排他的なプラットフォームの構築。
(まずは、この修学旅行中に、京都の土地勘と『本物の価値』がどこに隠されているか、私の審美眼で再評価してやろう)
午前5時30分。俺は、自室のデスクで最終的な持ち物点検を行っていた。
「……写ルンです、予備を含めて3本。おやつは300円以内という建前だが、カロリーメイトとウィダーインゼリーで実利を取る。しおり、筆記用具。そして、緊急連絡用のテレホンカード」
俺は、彫りの深い貌を鏡に向けた。
荷物は、当時のスタンダードな大型リュックサックにまとめている。最近ではキャリーケースを引く生徒も増え始めていたが、段差の多い京都の寺社仏閣や、砂利道での機動性を考えれば、背負うタイプが正解だ。「階段で詰まる」「電車内で場所を取る」といった、集団行動におけるボトルネックを避けるのは、元銀行マンとしてのリスク管理の基本である。
当時の撮影事情は、デジタルカメラがまだ一般的ではなかった。
写真は、フジカラーの『写ルンです』のようなレンズ付きフィルムが主流だ。修学旅行の終わりには、クラス全員が同じような緑色のプラスチックの塊を手にし、現像に出して数日待たなければ結果がわからない。個人でカメラを持つ者は稀で、たまに親から借りたAPSカメラを持っている奴がいれば、それが羨望の的となる、そんな牧歌的な時代だった。
「任三郎、時間よ! お父さんが駅まで車で送ってくれるって」
階下から、母の声が響く。
リビングに降りると、そこには薄手のニットにタイトなスラックスを合わせた、早朝とは思えないほど完璧な美しさを湛えた美津子がいた。彼女のしなやかな肢体と、朝露のように瑞々しい肌は、八王子の静かな住宅街において、あまりに過剰な華やかさを放っている。
「……父さん、悪いな。仕事の前に」
「気にするな。任三郎、京都の歴史もいいが、今の関西がどう動いているか、しっかり見てこいよ。銀行員としての視点を忘れるな」
父が、ハンドルを握りながらバックミラー越しに息子を見た。
「……ああ。観光の皮を被った、実地監査だと思って見てくるよ」
午前6時45分。八王子駅の改札前は、巨大なリュックを背負った中学3年生たちで埋め尽くされていた。
同学年、約200人。クラスごとに整列し、担任による点呼が始まる。
「3年2組、全員いるか? ……一人足りないな。佐々木か?」
担任が、駅の公衆電話から親に連絡を入れる。まだ携帯電話が子供に普及していない時代、急な遅刻や欠席の確認には時間がかかる。結局、佐々木は急な高熱による病欠であることが判明した。
「……情報の伝達速度が、この時代の最大の脆弱性だな」
俺は心の中で呟いた。
「おい任三郎! 準備万端かよ。俺、昨日の夜興奮して全然寝れなかったぜ!」
門廻邦彦が、朝日を反射するような輝かしい笑顔で駆け寄ってきた。
日焼けした肌、清潔感のある短髪。彼はまさに1998年の太陽そのものだ。その後ろからは、クールな塩顔の北子直樹が、落ち着いた足取りで続いてくる。
「邦彦、騒ぐな。まだ八王子だぞ。……葛石、新幹線は何系に乗れるか聞いたか?」
直樹の鋭い視線が、ホームへと向けられる。
「……横浜線で新横浜へ向かい、そこから『のぞみ』か『ひかり』だ。ホームで待っているのは、300系あたりが自然だろうな。カモノハシのような先頭形状。あれが日本の高度経済成長の最後を象徴する『鉄路の怪物』だ」
「鉄路の怪物……。お前、相変わらず言い回しが独特だな」
俺たちは横浜線に揺られ、新横浜駅へ。
新幹線のホームに滑り込んできたのは、期待通りの300系新幹線だった。白地に青いライン、少し角張ったそのフォルムに、生徒たちから「うおー!」「速そう!」と歓声が上がる。
「見て! 私、お父さんからこれを借りてきたの」
東鶴襟華が、バッグから小さなシルバーのカメラを取り出した。
愛らしい笑顔と知的なショートカット。彼女の手には、当時最新鋭だった『Canon IXY』――APSカメラが握られていた。
「すごいわね、新幹線。横から見ると、本当に巨大な槍みたい。任三郎くん、一緒に撮ってあげる」
「……俺は、撮られるより撮る方が専門だ。シャッターチャンスは、歴史が動く瞬間にしか訪れないからな」
「もう、理屈ばっかり。はい、ポーズ!」
襟華の屈託のない笑顔に、俺の冷徹な仮面が微かに緩む。APSフィルムの「カシャッ」という軽快な巻き上げ音が、旅の始まりを告げていた。
新幹線の車内。
自由行動の班は、俺、邦彦、襟華、直樹、そして1組から合流した上波茜、日名川彩の6人で構成されていた。
「よろしくお願いします、葛石くん。門廻くん」
上波茜が、圧倒的な気品で、深々と頭を下げた。170cm近い長身に、陶器のような白い肌。野球部マネージャーとして鍛えられた彼女の背筋は、中学生とは思えない高潔なオーラを放っている。
「日名川です。移動中のお菓子、少し多めに作ってきちゃった。みんなで食べましょう」
日名川彩が、柔らかく透明感のある微笑みでタッパーを差し出す。彼女から漂うハーブと焼き菓子の香りが、殺伐とした新幹線の空気感を一瞬で「サロン」に変えてしまった。
「……賑やかな班になりそうだな。直樹、バランス調整を頼むぞ」
「了解した。俺はこの個性の強すぎる連中を、時間通りに京都へ届けることに全力を尽くすよ」
直樹が苦笑いしながら席を整える。
座席を回転させ、6人で向かい合わせになる。
窓の外、富士山がゆっくりと通り過ぎていく。1998年の景色。まだ高層ビルが少なく、空が広い。
「よし、新幹線といえばUNOだろ! 負けた奴は、好きな奴の名前を白状する。いいな!」
邦彦がカードを配り始める。
俺は配られたカードを、財務諸表を監査するように眺めた。
数字の増減。相手の残りの手札。表情の揺らぎ。
UNOという子供の遊びですら、俺にとっては情報の非対称性を利用したシミュレーションの場だ。
「葛石くん、さっきから全然表情が変わらないわね。……ドロー4を出された時も、まるで金利の上昇を見守る銀行員みたいに冷静なんだもの」
襟華が楽しそうに俺の顔を覗き込む。
「……カードの配分には確率論があるだけだ。そこに一喜一憂するコストは支払わない」
「ふふ、でも、日名川さんの『ワイルド』カードには勝てないみたいよ?」
茜が、涼しげな瞳で俺の敗北を予言した。
京都までの数時間。
UNOの応酬と、1998年の初夏の車窓。
俺の内側に潜む60歳の亡霊は、この「無価値な時間」こそが、2043年には失われていた最大の贅沢であることを、皮肉にも噛み締めていた。
京都に到着すると、駅前の喧騒は修学旅行生と外国人観光客で溢れかえっていた。
俺たちは団体用のバスに乗り込み、清水寺、金閣寺、銀閣寺を強行軍で巡った。
「金閣寺……。足利義満の権力誇示の極致だな。だが、この金箔の維持費に、どれだけの拝観料が投じられているのか」
俺が呟くと、後ろでスコアブックをつけていた茜が頷いた。
「規律ある美しさね。でも、どこか空虚だわ。……見られていることを意識しすぎている」
「私は銀閣寺の方が好きだな。わびさび……。時間をかけて色褪せていくものにしか宿らない価値があるわ」
彩が、静かな佇まいで、庭園の苔を見つめていた。
初日の観光を終え、俺たちが向かったのは京都市内の大規模な旅館だった。
長い回廊を通り、案内されたのは、100畳はあろうかという広い座敷。
そこには、200人の生徒たちが一堂に会して夕食を取るための、簡素な御膳が並べられていた。
「……いただきます」
一斉に食事が始まる。
だが、一口食べた瞬間、班の女子たちの表情が曇った。
「……味が、薄いというか。素材の味が死んでるわね」
彩が、職人気質の鋭い味覚で眉を寄せた。
「冷めてるわ。効率を重視して、数時間前から並べていたのが丸分かりね」
茜が、規律に厳しい視線で御膳を見つめる。
「京都の旅館って、もっと繊細なものだと思ってたんだけど……。ちょっと期待外れかな」
襟華が、愛らしい顔を少しだけ歪めた。
邦彦と直樹は「腹に入れば同じだぜ!」と豪快に食べていたが、俺は箸を置き、その光景を分析した。
(サービス低下……。一見客である修学旅行生を『効率的な処理対象』としてしか見ていない証拠だ。大量生産・大量消費の観光モデル。これが将来のリピーター減少を招き、宿泊産業を衰退させる毒になる)
俺は、2043年の地獄を思い出した。
(未来では、こうした伝統ある旅館の多くが外資に買い叩かれ、あるいは人手不足で廃墟と化していた。今、目の前にあるこの『手抜き』こそが、崩壊への不渡り手形だ)
「……任三郎くん。また、怖い目をしてるわよ」
襟華が、そっと俺の袖を引いた。
「……いや。この出汁の薄さは、今の日本経済の『体力のなさ』と同期しているようでな。……東鶴さん。この味を覚えておくといい。これが『失われる前』の、末期の輝きだ」
「……何それ、不吉ね」
俺は心の中で、自分自身の「裏の行程表」を更新した。
観光資源としての日本。それを再生するには、単なる「もてなし」の精神だけでは足りない。
圧倒的な資本による再編。そして、本物の価値を理解する者だけを顧客にする、会員制の極めて排他的なプラットフォームの構築。
(まずは、この修学旅行中に、京都の土地勘と『本物の価値』がどこに隠されているか、私の審美眼で再評価してやろう)
0
あなたにおすすめの小説

異世界帰りのハーレム王
ぬんまる兄貴
ファンタジー
俺、飯田雷丸。どこにでもいる普通の高校生……だったはずが、気づいたら異世界に召喚されて魔王を倒してた。すごいだろ?いや、自分でもびっくりしてる。異世界で魔王討伐なんて人生のピークじゃねぇか?でも、そのピークのまま現実世界に帰ってきたわけだ。
で、戻ってきたら、日常生活が平和に戻ると思うだろ?甘かったねぇ。何か知らんけど、妖怪とか悪魔とか幽霊とか、そんなのが普通に見えるようになっちまったんだよ!なんだこれ、チート能力の延長線上か?それとも人生ハードモードのお知らせか?
異世界で魔王を倒した俺が、今度は地球で恋と戦いとボールを転がす!最高にアツいハーレムバトル、開幕!
異世界帰りのハーレム王
朝7:00/夜21:00に各サイトで毎日更新中!

男女比1対5000世界で俺はどうすれバインダー…
アルファカッター
ファンタジー
ひょんな事から男女比1対5000の世界に移動した学生の忠野タケル。
そこで生活していく内に色々なトラブルや問題に巻き込まれながら生活していくものがたりである!

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

転生したら名家の次男になりましたが、俺は汚点らしいです
NEXTブレイブ
ファンタジー
ただの人間、野上良は名家であるグリモワール家の次男に転生したが、その次男には名家の人間でありながら、汚点であるが、兄、姉、母からは愛されていたが、父親からは嫌われていた

異世界翻訳者の想定外な日々 ~静かに読書生活を送る筈が何故か家がハーレム化し金持ちになったあげく黒覆面の最強怪傑となってしまった~
於田縫紀
ファンタジー
図書館の奥である本に出合った時、俺は思い出す。『そうだ、俺はかつて日本人だった』と。
その本をつい翻訳してしまった事がきっかけで俺の人生設計は狂い始める。気がつけば美少女3人に囲まれつつ仕事に追われる毎日。そして時々俺は悩む。本当に俺はこんな暮らしをしてていいのだろうかと。ハーレム状態なのだろうか。単に便利に使われているだけなのだろうかと。
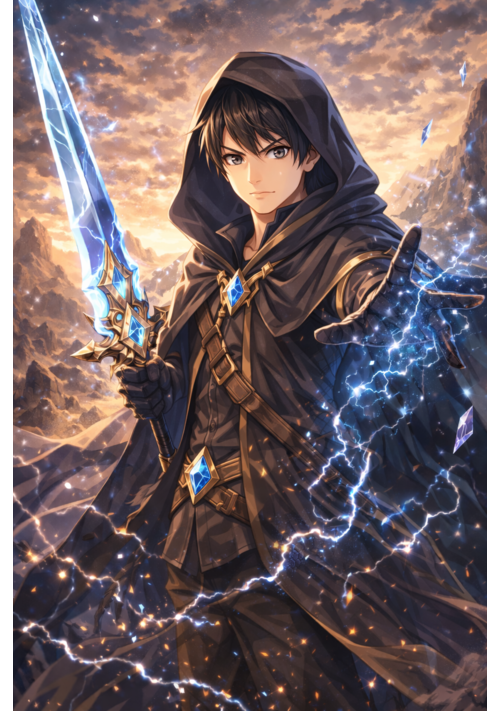
R・P・G ~転生して不死にされた俺は、最強の英雄たちと滅ぼすはずだった異世界を統治する~
イット
ファンタジー
オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の取材中、異世界の大地の女神と接触する。
半ば強制的に異世界へと転生させられた彼は、惑星そのものと同化し、“星骸の主”として不死の存在へと変貌した。
だが女神から与えられた使命は、この世界の生命を滅ぼし、星を「リセット」すること。凛人はその命令を、拒否する。
彼は、大地の女神により創造された星骸と呼ばれる伝説の六英雄の一人を従者とし、世界を知るため、そして残りの星骸を探すため旅に出る。
しかし一つ選択を誤れば世界が滅びる危うい存在……
女神の使命を「絶対拒否」する不死者と、裏ボス級の従者たち。
これは、世界を滅ぼさず、統治することを選んだ男の英雄譚である。

シシルナ島物語 少年薬師ノルド/ 荷運び人ノルド 蠱惑の魔剣
織部
ファンタジー
ノルドは、古き風の島、正式名称シシルナ・アエリア・エルダで育った。母セラと二人きりで暮らし。
背は低く猫背で、隻眼で、両手は動くものの、左腕は上がらず、左足もほとんど動かない、生まれつき障害を抱えていた。
母セラもまた、頭に毒薬を浴びたような痣がある。彼女はスカーフで頭を覆い、人目を避けてひっそりと暮らしていた。
セラ親子がシシルナ島に渡ってきたのは、ノルドがわずか2歳の時だった。
彼の中で最も古い記憶。船のデッキで、母セラに抱かれながら、この新たな島がゆっくりと近づいてくるのを見つめた瞬間だ。
セラの腕の中で、ぽつりと一言、彼がつぶやく。
「セラ、ウミ」
「ええ、そうよ。海」
ノルドの成長譚と冒険譚の物語が開幕します!
カクヨム様 小説家になろう様でも掲載しております。

転生先は上位貴族で土属性のスキルを手に入れ雑魚扱いだったものの職業は最強だった英雄異世界転生譚
熊虎屋
ファンタジー
現世で一度死んでしまったバスケットボール最強中学生の主人公「神崎 凪」は異世界転生をして上位貴族となったが魔法が土属性というハズレ属性に。
しかし職業は最強!?
自分なりの生活を楽しもうとするがいつの間にか世界の英雄に!?
ハズレ属性と最強の職業で英雄となった異世界転生譚。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















