11 / 25
本編
第十一話 長い夜がはじまる
しおりを挟む
デルウッド侯爵の変貌ぶりに、誰もが驚いていた。
だが、ゼファーにとって都合が良かった。渋い顔はしたが。
恐ろしいほどの速度で会議は進んだ。魔竜復活の際の最前線戦略の話から、討伐失敗時の采配まで。元より前線のことについては反論を許すつもりのなかったゼファーだが、その後についての全面的な支援までをデルウッド侯爵が言い出したことにより、他の貴族たちも追従して予想以上の収穫を得ることとなった。
「……ご苦労だった」
会議中もしきりにデルウッド侯爵に礼賛され尽くして疲弊したクロードに、労いの言葉をかける。クロードは不安げな顔で王を見上げた。
「あの、あの……本当に、大丈夫ですか?急に侯爵が正気に戻られたら、反故にされる可能性がありますが……」
「いや、あれは……大丈夫だろう」
デルウッド侯爵の変貌の経緯を聞いて、ゼファーは頭を抱える思いをすることになった。クロードへ向ける感情が、身に覚えのあるもの過ぎたためだ。
一日で破壊と癒炎両方を向けられればそうもなるか。ゼファーが心底から納得している一方、クロードは今だ解せぬ顔で狼狽している。
「完全に坊ちゃんにイカれてたもんな~」
「根拠のない好意を計画に組み込むのは危ないのでは……」
「根拠ならここにあるだろう」
言って、ゼファーはクロードの腰の神剣を手の甲で叩いて見せた。クロードはしばし悩んだ末に、心底の納得ではない表情ながら、頷いた。
「叔父上、クロード様」
「セシリア殿下」
「どうした?」
「戦勝のお祈りに、霊王廟に参ろうと思っております。もしよろしければお二人も……」
霊王廟。歴代の王と近しい親族が祀られる王家の霊廟である。有事に際し、死して神霊と化した先祖に、祈りを捧げるのは、通例として歴代の王が行ってきたことだった。
「いや、私はいい。クロード、代わりにセシリアの伴を頼む」
「はい」
「……叔父上、もうよろしいのではないですか?」
セシリアの言葉が、彼女の父のことを指しているのは歴然としていた。彼女の父にして、ゼファーの兄。ゼファーが命を断った先王は、霊王廟にて一番新しい墓の中にいる。
「私があそこに行くのは、勝ちを持ち帰った時だけと決めている。お前が憂う必要はない。シアン、騎士団の様子を見に行く。ついてこい」
まだ何か言いたげなセシリアの視線を振り切って、ゼファーは歩き出した。騎士団の様子を見に行く、というのはあらかじめ決めていた予定ではあったが、それほど急ぐものでもなかった。
廊下を曲がるまで、背中に姪の視線を感じながら、ゼファーは葬儀の日を思い出していた。
よく晴れた日だった。ただただ、セシリアの能面のような顔を覚えている。
「……陛下も行きゃよかったじゃないですか」
「馬鹿を言え。……セシリアは、立場故に父を殺した男に恨み言も言えん」
シアンはそれ以上何も言わなかった。
家族のことが王のひどく繊細な部分と知っているし、自分が踏み込める領域ではないとわかっているからだ。
戦場の信頼で道を共にする二人は、祈りを少年少女に任せて、騎士団の訓練所へと向かった。
霊王廟。
王宮の裏手にある岩山を切り拓いて作られたそこは、その入り口以外はほとんど洞窟と言ってよかった。
綺麗に整えられた墓標にセシリアが祈るのに従って、クロードも膝をついて祈った。碑銘を見れば、彼女の父の名がある。
祈りを終えたセシリアが、後ろのクロードをじっと見る。
「……クロード様」
「はい」
「叔父上とは、二年前より交流があるとか」
「はい。ほとんど手紙だけのことですが……」
「私は、これまで指折り数えるほどしか叔父と会ったことがありませんでした」
セシリアは、クロードから目を離して、独白のように告げた。前王とゼファーの不仲が明瞭となったのが七年前、ゼファーが迅雷剣ハルファドを抜いた頃。その時まだセシリアは八歳である。
「私は、叔父のことをよく知りません。……父のことも、皆が言うほど知りはしないのです。父は息子を切望していたので」
セシリアはその言葉の意味までは言わなかった。そうして曖昧に笑って、そのまま言葉を続ける。
「みな、私のことを……誤解しています。父の死に対し泣きもせず、仇である叔父にも礼儀を尽くす、気丈な女と。……あるいは、腰抜けのお姫様と」
「……殿下」
「ただ……父のことも、叔父のことも、知りもせずに泣けも恨みも出来ないだけなのです」
苦笑いで、セシリアは言った。等身大の少女の顔だった。
「セシリア殿下」
「すいません、湿っぽい話を」
「いえ。陛下とならばこれから何度でも機会があります。その中で、父君の話もお伺いする機会もあるでしょう」
「……ええ、そうですね」
「ーー…僕が、必ず殿下の元に陛下をお帰しします」
父の顔を、クロードは思い出す。
最近は、クロードが幼い頃の、穏やかな顔を思い出せるようになった父を。もう思い出の中でしか語り合えぬ父を。
もっと話せればよかった、という後悔を、クロードは目の前の少女にまでさせたくはなかった。少なくとも、ゼファーに関しては、クロードが力になれる部分があると、自負しているが故に。
「さすがは『白花の勇者』さまですね」
「……?白花…の、勇者、とは」
「この度の件で、クロード様に救われた民が、そう呼んでいるのだと聞きました。アレストの癒しの炎が、花のようだからだとか」
ふふ、とセシリアが笑った。クロードは返答に困って、曖昧に笑った。
王都に来て、アレストの使い手であることを明かしてから、その影響が思ったより遥かに大きく、クロードは戸惑うばかりである。
これを、王は一人で、七年も前から。
「クロード様。おそらくデルウッド侯爵は、その異名を広く喧伝して、あなたを英雄として送り出すつもりだと思います」
その異名を知った時のデルウッド侯爵の顔が目に浮かぶようだった。クロードは苦笑した。
「私も、この国難において、民の不安感を極力減らすためには……叔父上だけでなく、新たなカリスマが必要と思っております」
「僕がそれに耐えうる器かは、確信をもってお答えすることが出来ませんが……癒炎剣アレストの使い手として、恥じぬ生き方をすると誓います」
「その誓い、確かに受け取りました。……叔父上を、よろしくお願いいたします」
深く深く、セシリアは頭を下げた。
出立の日。
セシリアの言葉通り、クロードは『白花の勇者』の勇名を戴き王の隣に並ぶこととなった。
王の名を以て民に知らされた、救世主なき魔竜との対決をせねばならぬとの報は、いっそ『白花の勇者』の名に霞むほど。
王の隊列は多くの民に見送られ、来た時とは真逆に、華々しいものとなった。
「……大丈夫なのでしょうか」
外壁を抜け、王都の喧騒を離れてから、ようやくクロードはぽつりと呟いた。その顔に不安の影が掛かっている。
「やるだけのことはやった。万が一失敗した時には……お前も私も生きてはいまい。あとは生き残った者たちがどうにかすることだ」
王の相変わらずの言い方に、クロードは表情を緩めて笑った。
そうして、その表情が変わる。乞うようなその顔に、王は表情を変えないながら見惚れた。
「陛下は死なせません。なので、もし失敗したら、後のことはお願いいたしますね」
「……そこまでして生き残りたいとは思わんな」
クロードの言葉の意味を王も理解した。命を使い果たしてでも生かすと、奇跡の癒しの炎をもってして、どこまでも命をつなぐと。
「わかっております。……これは僕の、勝手な願いですから」
「勝手な願いか」
思わずゼファーの喉が鳴る。
願いというには、クロードのそれはあまりに無私の献身にすぎた。
だから、王は一つ、意地の悪い問いを投げた。
「ならば、私がこれ以上の苦痛に耐えられぬと、もう治すなと、戦えぬと言えば、お前は叶えてくれるか?ーー…その紅蓮で、慈悲をくれるか」
クロードは虚を突かれて、目を見開いた。それから、その眉をぐっと詰めて、視線を落とす。
「……、……陛下が、真に、それを望まれるのであれば」
常の穏やかさも忘れたような、冷たく暗い声が帰ってきて、王は一層上機嫌に笑った。
ギョッとしてクロードが顔を上げる。呆気にとられたその顔に、ゼファーは目を細めて笑った。
「冗談だ。私が、そのような安楽を得られるとは思っておらぬ」
「陛下、僕は本当に、」
「私の死が、お前の苦痛になるというなら……お前の苦痛とならぬよう、生きる甲斐もあるというものだ」
自分が生きているだけで、この少年を苦痛から遠ざけていると思えれば、それだけで。
ゼファーの心の内まで、クロードは全てを分かったわけではないだろう。
それでも、生きる理由の一つがクロードであることは伝わって、ほっと、安心したような微笑みを零すのだから、向けられる愛情があまりに心地よく、ゼファーは笑みを深めるのだった。
軍都に戻った王の隊列を出迎えたのは、髭の騎士団長が先頭に立つ軍都の精鋭たちであった。軍都将王宮に続く大通りを、王の帰還を待ち侘びていたかのように並び、騎士団の雰囲気に何事かと民たちもそれぞれの家屋や通りの隅から様子を覗いている。
「陛下、王都でのご活躍、お伺いしました。ユーノヴェルト辺境伯……いえ『白花の勇者』殿も」
「耳が早いな。では、この後我々が立ち向かう困難については?」
「ユリウス殿より、大方のことは。しかし、陛下より、ご下命頂ければと」
「……ふむ」
大柄の騎士団長の隣に、ヒョコ、とユリウスが顔を出した。その両隣に、弓騎士隊の新人であり、デルウッド侯爵の差し向けた間諜であったラウドとユーゴが並んでいる。
ほとんど首根っこを押さえられているような状況の二人に、クロードは同情した。
そして、王の言葉を待つ。
「ーー…魔竜を討つ」
王は、いきなりそう告げた。
大通りが、一瞬、静まり返る。それからそこここで聞こえる、民の不安げな声。
「二千年より前から、この国に居座ってきた、悪魔を排す時が来た」
王の言葉は、雷鳴のように響き渡った。くるりとユリウスが指先を動かす。魔術的関与があるのは明らかだったが、クロードにはそれよりも、王が、しかと心底からそう言っていることに、感銘を覚えずにはいられなかった。
かつて、王は『それは、この国が滅びる運命だったとでも思え』と言った。
その王が、このように自らの兵を、鼓舞するように語っている。
「その恐ろしさも、当然王家には伝わっている。建国王はこう記した。『有象無象の悪意の根源、逃れ得ぬ死毒の川を泳ぎ全てを奪わんと顕現す。黒き禍つの災厄、竜の形を以て死を振りまき、ならば拙速に排せねばと、封印の術法を施す。ーー…だがもし、ここに、ユーノヴェルトがいれば、あるいは』」
「…!」
王の視線が、クロードに向く。
だからクロードは応えた。かつて建国王が願ったアレストの使い手の、その再来が今ここにあると、示すために。
癒炎剣アレスト。その銀の刀身を抜く。
そうして、『白花の勇者』の由来となった、白き癒しの炎を、騎士たち一人一人へ送り出すような、そんなつもりで放った。
「癒炎剣アレストは、ここにある。二千年、誰の手にも届かなかった、奇跡の炎を当代ユーノヴェルト辺境伯クロードが手にした!ならば父祖が成し得なかった、恒久の平穏を手にすべきは今であると!!」
ゼファーの声で大気が震えた。それに応えるように、白炎が揺れる。
「やるならば、今しかあるまい。二千年の因縁を、我らの代で、終わらせる!!」
鳴り響いたのは、轟音。
勇猛を示す雄叫びが、一斉に上がった。元より、ゼファーの信の厚い勇士達である、王の号令に、昂らぬはずがなかった。
雄叫びと歓声を受けながら、クロードは王の横顔を盗み見る。金の瞳が、太陽の光を浴びて爛々と輝いていた。その輝きがあまりに眩しくて、クロードは目を細めた。
それから数日後のことである。
ゼファーとクロードが王都より戻ったとの報を聞き、ロベルトは限界まで高まった緊張を、溜息と吐き出したところだった。
二人の神剣使いが軍都に帰還した。その上、王の姉テミスの結界術師団の精鋭がロベルトの指揮下に入り、ユーノヴェルト辺境伯領における常駐監視の戦力としては申し分のないものとなった。
軍都からユーノヴェルト辺境伯領まで、二時間ほどである。ならば、事が起きても二時間、堪えればいいだけだ。傲慢とも言える自負は、確かな経験と幼馴染の置き土産故のことだった。
ユリウスは魔竜が目覚めた時に発動する、いくつかの魔術的仕掛けを残していた。飛んてくから安心しといて。特に詳しい解説はせずに告げた幼馴染に、ロベルトも特に問い返さなかった。
「ロベルト殿、お疲れ様です」
「ああ、どうも」
夕暮れ時、魔竜の遺跡を見下ろす監視塔から、ロベルトは眼下の風景を眺めていた。ユーノヴェルト辺境伯家の私兵が、主の生真面目さとよく似た真面目さできびきびと警備を続けているのが見える。
眼下を見下ろすロベルトに声をかけたのは、クロードの姉フローラだった。その手には軽食の入ったバスケットがある。
「いつもお手間かけてすいませんね」
「いえ」
フローラが、簡素なテーブルの上に、バスケットの中身を広げる。この監視塔にくる時にはほとんど男装のような装いのフローラがそれをやると、まるで中性的な印象の執事のようだった。
「ご不便はありませんか?監視が長期になる可能性を考えて、居住性もある程度考えては作らせましたが……」
「王弟時代の陛下について回ってた頃から考えたら天国みたいなもんですよ。天井も寝床もある上に、美味い食事もあるし」
この監視塔は、クロードが軍都に発ってから建築したものだ。その窓からは、魔竜の遺跡の中央にある、天井が崩落した箇所がよく見える。
そこには、床石に大きく広がる黒い竜の絵図があった。
封印されし魔竜、そのものである。封印が解ければ、この絵図は実体を持ち、黒い瘴気の炎をまき散らすという。
その周辺を小型の魔物がウロウロとうろついている。ロベルトは、食事に手を付ける前に、その魔物に向けて、弓を向けた。
そうして、一閃。
光が届くと共に、その小さな影は、黒い瘴気の粒となって消えた。
「まあ、こうして暇することもないんでね」
ロベルトは軽く言って、弓を置いて椅子に腰掛けた。
「ふふ。ならば良かった。どうぞ。今日は川魚のフライを挟んだサンドイッチとのことです」
「ありがたくいただきます」
ロベルトにとって、ユーノヴェルト伯爵家のシェフが作る料理には本当に助けられていた。
ここが最も優れた射撃地点のため、ロベルトは監視塔から離れられない。睡眠時の監視は部下に任せていたものの、退屈とそれに伴う緊張の緩みを避けるのはかなり困難であった。その中で、意識の切り替えとして、バリエーション豊富な美味というのは、かなり効果的だった。
「フローラ殿。これからはウチのに取りにいかせますから、無理してここまで上がってらっしゃらなくても大丈夫ですよ」
「無理と言うほどの階段ではありませんが……」
「いえ、妊娠してらっしゃると、ご心配も多いでしょう」
大口を開けてサンドイッチを口に入れたロベルトは、フローラからの返答がずいぶん遅いことに気づいた。驚いた顔をしたフローラが、気まずそうに微笑んでいる。
よく似た姉弟だ、とクロードのことを思い出しつつ、ロベルトはよく咀嚼したサンドイッチを飲み込んで、尋ねた。
「……もしかしてご懐妊のこと、伏せられてました?」
「いえ、隠していたわけではないのですが……よくお分かりになりましたね」
「ああ……妊娠している御婦人は魔力の流れ方が特殊なので」
懐妊など祝うべきだけのことで、フローラが何に気まずくなっているのか分からず、ロベルトはただ自分の発言の根拠だけを端的に口にした。
「このような時に、間が悪いとはわかっているのですが……」
このような時。フローラは七ヶ月前から、魔竜の封印が緩んでいることを知っていた。だが腹の様子からして、妊娠したのはそれよりも後のことだろう。だからそれを恥じているのだと、ようやくロベルトは思い至った。
「いや、こういう時だからこそ希望になるでしょう。魔竜が完全に過去になった第一世代、楽しみですよ、俺は」
先ほどまで相手の発言の意図を測りかねていたとは思えぬ反応で、ロベルトはそれを口にした。それは真に思っているからこそ出た言葉でもあるし、ロベルトのコミュニケーション能力の高さ故でもあった。
「俺たち世代は、丁度現役真っ盛りに魔竜の復活を迎えるのが分かっていましたからね。そんな思いをせずにいられる子が生まれると思えば、やる気もでますよ。俺なんか、騎士になる時には、親父に言われましたからね。魔竜封印の捨て駒になる気かって」
ロベルトが弓騎士を目指したのは、信念や理想があってのことではない。ただただ、弓を極めたい、と言う自分の欲求だけのことである。
だが、その道がいずれ魔竜との対決に繋がるのは必定だった。魔竜がこの国に、百年に一度の災厄を振りまく限り、それは永遠に続く。
断ち切れるのなら、それは今だ、とロベルトも強く思っていた。
「せっかくまあまあの才能、天から貰ってるんです。それなら、あのクソボケ竜にぶっ放してやって、二度と俺と親父みたいな喧嘩する親子がいなくなればいいでしょう」
「……ノブリス・オブリージュ、ですか?」
「いや、どっちかというと『人生なんでもやったもん勝ち』、ぐらいのもんです」
はは、とロベルトが笑って、フローラも笑った。そうして最後の一口を口の中に放り込むと、ロベルトは先ほどとは味が違う気がして、口を止めた。
いや違う、味じゃない。
ロベルトは咄嗟に弓に手を伸ばした。まだ、微かな違和感でしかないが、それを外したこともなかった。
いまだ異変に気付いていないフローラも、ロベルトの様子を見て、顔を険しいものにする。
二人の視線が、窓の外に向いた。一見、何の変化もないように見えた。
「ロベルト殿」
「少し集中します。目視での警戒はお任せします」
「はい」
フローラの言葉に、ロベルトは端的に答えて、すう、と息を大きく吸い込む。やはり、違う。ただの勘だけとも言えぬ、風まで読む弓兵の感性が危機を告げていた。
目を伏せて、自らの瞳に魔力を載せる。魔性の存在に焦点を合わせて超視力を引き出す『騎士の対魔法』は、遠距離射撃を本分とする弓騎士の本領の一つであった。
ゆっくりと、その目が開く。
ロベルトの翡翠の瞳が、尋常ではありえないほど遠くを映す。魔竜の遺跡の石床、その欠けの形まで見えるそれを、音も聞こえないほどの集中で調節して、ロベルトの瞳は、封印されし魔竜の絵図の些細を捉える。
その、絵図のひび割れが、血管のように胎動する様を、はっきりと。
「フローラ殿!緊急号令を!」
ばつん、と超視力の対魔法を取り消し、ロベルトは隣のフローラに告げた。
「魔竜を遺跡から出さぬよう、隊列を組ませます!ーー…ご武運を!!」
強く頷いたフローラが、足早に階段を降りる。その背を見送って、ロベルトは弓を大きく引く。
まだ、まだだ。
まだ、魔竜は絵図のまま実体を現していない。早まるな。ロベルトは息を吐き出す。
いち、に、さん。心拍を平静のものに戻すため、内心で数を数える。自分がしくじれば、何人死ぬかわからない。
魔竜は目覚めと共に、周辺を焼き尽くす黒炎を吐き出すという。その黒炎を吐き出す瞬間に、その魔力が集約する胸に、魔力を四散させる矢を、撃ち込まねばならない。
遠くで、鐘の音が鳴り響く。フローラの緊急号令の合図だ。
はじまる。
黒き竜の翼が、羽ばたく。だがその巨体を空に駆けさせはしない。
想定よりも遥かに大きいその体は、遺跡が子ども騙しのおもちゃに見えるほど。その目は真っ黒に染まり、咆哮を上げようとしていた。
その竜を、光の粒が覆う。ユリウスの『置き土産』である。
光の粒は、竜の巨体を覆うように柔らかく吸い付いた。
途端。
鎖の形となった光が、ギャリリ、と激しい金属音を上げて竜の四肢に巻き付き、その巨体を締め上げる。怒りの咆哮が上がる。
その胸元が、赤黒く、激しく燃えるように光る。
「……ここまでお膳立てされて、俺がやれねぇ訳ねえだろ!」
幼馴染へ向けての軽口と共に、ロベルトは矢を放った。
澄んだ翡翠を纏った矢は、吸い込まれるように竜の胸元へ。そうして、集まった熱量は行き場を失い、その場で大きな爆発を起こす。
新しい矢をつがえたロベルトの隣で、膨大な魔力が揺らぐ。その魔力の主が誰のものか知っているロベルトは、そちらを見もしなかった。
「ーー…【黎明よ、我が掲げる非情の冠よ】」
魔力の渦の中から、男が姿を現す。まるで世界の膜の狭間を潜り抜けてきたかのように、身を捻ってそこに現れた男の足元に、いくつもの魔法陣が輝いていた。
銀の髪に赤い目。魔術の大家、ラドウィン侯爵家当主ユリウス、その人である。
「【太陽よりも鮮烈に、月よりも静謐に、星より叡明に、すべての光を統べ、すべての獣を我が元に下せ」
挨拶も交わさず、ユリウスは詠唱を続けた。ほとんど魔法を使う時に詠唱など口にしないユリウスが、それを省略せずに声に魔力を乗せる。
竜の体が、ピタリとその動きを止める。
「【伏して拝せ、其は我が下僕である。我は力、我は支配、我は所有者にして全ての王、我が言葉は運命にして宿命の必然】」
ユリウスが詠唱を進めるごとに、新しい魔法陣が浮かび上がる。それは次々と重なり合って、もはや解読も出来ないほど。
ユリウスが、ゆっくりと腕を前に出した。
「ーー…【獣よ、口を開け】」
ぐぐ、と指先に力を込めて、そうしてユリウスが手を開いた瞬間。
竜はだらしなく舌を垂らして、支配者にその口内を晒した。
ユリウスの口から、荒い息がもれる。
かつて、封印こそ万全であれば魔竜を操ることも可能、と軽く言ったユリウスが、封印下でなくともそれを成し遂げた。
だが、それが長く保つわけでないのは、様子からして歴然であった。
「…撃て、ロベルト」
だから、温度のない、だが信頼の明らかな幼馴染の言葉に、ロベルトはすぐに応えた。眩しいほどの翡翠が駆けて、竜の顎を吹き飛ばす。
ぐらり、とその巨体が傾いた。
ドロドロと黒い血が地面を汚し、あたりに腐臭が広がる。その匂いはかなり距離のある監視塔まで届いた。それはまるで、元から死体であったような。
二千年、王国を苦しめた魔竜、その体が崩れ落ちる。
確かに魔竜を倒した。
だというのに、その黒い血が、その腐臭が、ロベルトの違和感を刺激して、鳥肌が立つほどの焦燥感が全身を襲った。
「ユリウス……本当に、これで、終わりか?」
「ロベルト、構えを解くな」
そう言うユリウスの周囲には、いくつもの魔法陣が浮かんでいる。ユリウスの目が、魔竜のいた場所から動かない。この稀代の天才が、魔術的な解析をしているのは明らかだった。
「こいつは……まだ奥に『いる』!」
それは、ユリウスの言葉と同時。
竜の腹を突き破り、黒い奔流が放たれた。
ぐちゃぐちゃと粘着質な音を立て、元の竜の大きさまで膨れ上がったその黒は、数多の眼球をその流体の狭間に浮かばせ、その視線の全てをロベルトとユリウスに向けていた。
その瞳が、赤黒く光るのを見て、反射的にロベルトは矢を放つ。
眼球から放たれる光線が、翡翠の矢とぶつかり合う。無数の光線は翡翠に射抜かれて、次々と爆発して霧散していく。
だが全てを捉えることは出来ずに、直撃ではないとロベルトが判断して優先順位を遅らせたそれらが、監視塔を破壊し、瓦礫に変えていった。
魔力の揺らぎを感じて、ロベルトはユリウスに任せることにした。そして問うた。
「『竜』じゃないのか!?」
「黒き禍つの災厄、有象無象の悪意の根源、逃れ得ぬ死毒の川……」
ロベルトの問いに言葉を返しつつ、ユリウスの指先から放たれたのは重力緩和魔法だった。着地までおよそ十メートル。土煙の向こうを警戒しながら、ロベルトはユリウスの言葉の続きを待つ。
「魔竜の権能だと思ってたけど、逆だ。この『黒い血そのもの』が竜の皮を被ってやったことだ。…やられたな。やっぱ実地に勝る解析はない」
ふぅ、と息を吐き出して、ユリウスは前方に魔力の壁を作り出す。
「あ~…なんだ、つまり、こっからが本番か?」
「そゆこと。危なかったな、うっかり神経系まで繋げる操作魔術使ってたら、逆に乗っ取られるとこだった」
「ゾッとする話すんなよ。お前の世話までやってられっか」
「だはは、ロベルトならどうにかなるっしょ」
「なるかよクソボケ」
軽口を交わしながら、ロベルトは前方にいくつもの矢を放つ。未だ土煙晴れぬその先で、それは敵性の魔力を穿って破裂した。
「作戦自体はあいつを遺跡から出さない、で変更なしでいいか?」
「それでよろしく。まだ仕掛けてた拘束魔術が効いてるから、そこから心臓の箇所を割り出して縫い留める。ロベルトは迎撃頼んだ」
ユリウスの言葉を聞きながら、ロベルトは魔力のゆらぎを感じて視線を走らせる。青白く薄い膜が、遺跡全体を覆う。テミスの配下の結界術師だ。
「結界術師も守っといてね。流れ弾だけでも外に漏れたらマズイ」
「おう」
「あとあの目玉減らしておいてくんない?」
「お……いや簡単に言うなよ、そもそも攻撃通るかもわかんねぇのに」
危うく気楽に頷きそうになって、ロベルトじっとりとした目つきでユリウスを睨む。すでに拘束と解析の魔術を展開しているユリウスは、ロベルトに視線を返さなかった。
「いやロベルトなら行けるかなって……」
「お前の中の俺はなんなんだよ」
呆れながら、ロベルトは弓を引く。土煙の狭間から、黒い血の目玉へと向かったそれは、だがその手前で光線に撃ち抜かれて空中で破裂した。
「行けそう?」
「わからん。でも攻撃のタイミングをコントロールすることは出来そうなんだよな。やってみるか」
「やっぱロベルトなんだよな~」
「何だそれ」
ふざけた物言いで信頼を向けるユリウスに、ロベルトは弓を放ちながら応える。ロベルトもユリウスも、普段と変わらぬ軽い口調ではあったが、互いに慎重になっていることを感じ取っていた。
「お前が死んだら終わりなんだからな。俺の腕、使い潰すつもりで使えよ」
「もちろん。陛下とクロード殿が来るまで、まあ、楽しくやろうよ」
長年の信頼を乗せて、その長い夜が始まった。
だが、ゼファーにとって都合が良かった。渋い顔はしたが。
恐ろしいほどの速度で会議は進んだ。魔竜復活の際の最前線戦略の話から、討伐失敗時の采配まで。元より前線のことについては反論を許すつもりのなかったゼファーだが、その後についての全面的な支援までをデルウッド侯爵が言い出したことにより、他の貴族たちも追従して予想以上の収穫を得ることとなった。
「……ご苦労だった」
会議中もしきりにデルウッド侯爵に礼賛され尽くして疲弊したクロードに、労いの言葉をかける。クロードは不安げな顔で王を見上げた。
「あの、あの……本当に、大丈夫ですか?急に侯爵が正気に戻られたら、反故にされる可能性がありますが……」
「いや、あれは……大丈夫だろう」
デルウッド侯爵の変貌の経緯を聞いて、ゼファーは頭を抱える思いをすることになった。クロードへ向ける感情が、身に覚えのあるもの過ぎたためだ。
一日で破壊と癒炎両方を向けられればそうもなるか。ゼファーが心底から納得している一方、クロードは今だ解せぬ顔で狼狽している。
「完全に坊ちゃんにイカれてたもんな~」
「根拠のない好意を計画に組み込むのは危ないのでは……」
「根拠ならここにあるだろう」
言って、ゼファーはクロードの腰の神剣を手の甲で叩いて見せた。クロードはしばし悩んだ末に、心底の納得ではない表情ながら、頷いた。
「叔父上、クロード様」
「セシリア殿下」
「どうした?」
「戦勝のお祈りに、霊王廟に参ろうと思っております。もしよろしければお二人も……」
霊王廟。歴代の王と近しい親族が祀られる王家の霊廟である。有事に際し、死して神霊と化した先祖に、祈りを捧げるのは、通例として歴代の王が行ってきたことだった。
「いや、私はいい。クロード、代わりにセシリアの伴を頼む」
「はい」
「……叔父上、もうよろしいのではないですか?」
セシリアの言葉が、彼女の父のことを指しているのは歴然としていた。彼女の父にして、ゼファーの兄。ゼファーが命を断った先王は、霊王廟にて一番新しい墓の中にいる。
「私があそこに行くのは、勝ちを持ち帰った時だけと決めている。お前が憂う必要はない。シアン、騎士団の様子を見に行く。ついてこい」
まだ何か言いたげなセシリアの視線を振り切って、ゼファーは歩き出した。騎士団の様子を見に行く、というのはあらかじめ決めていた予定ではあったが、それほど急ぐものでもなかった。
廊下を曲がるまで、背中に姪の視線を感じながら、ゼファーは葬儀の日を思い出していた。
よく晴れた日だった。ただただ、セシリアの能面のような顔を覚えている。
「……陛下も行きゃよかったじゃないですか」
「馬鹿を言え。……セシリアは、立場故に父を殺した男に恨み言も言えん」
シアンはそれ以上何も言わなかった。
家族のことが王のひどく繊細な部分と知っているし、自分が踏み込める領域ではないとわかっているからだ。
戦場の信頼で道を共にする二人は、祈りを少年少女に任せて、騎士団の訓練所へと向かった。
霊王廟。
王宮の裏手にある岩山を切り拓いて作られたそこは、その入り口以外はほとんど洞窟と言ってよかった。
綺麗に整えられた墓標にセシリアが祈るのに従って、クロードも膝をついて祈った。碑銘を見れば、彼女の父の名がある。
祈りを終えたセシリアが、後ろのクロードをじっと見る。
「……クロード様」
「はい」
「叔父上とは、二年前より交流があるとか」
「はい。ほとんど手紙だけのことですが……」
「私は、これまで指折り数えるほどしか叔父と会ったことがありませんでした」
セシリアは、クロードから目を離して、独白のように告げた。前王とゼファーの不仲が明瞭となったのが七年前、ゼファーが迅雷剣ハルファドを抜いた頃。その時まだセシリアは八歳である。
「私は、叔父のことをよく知りません。……父のことも、皆が言うほど知りはしないのです。父は息子を切望していたので」
セシリアはその言葉の意味までは言わなかった。そうして曖昧に笑って、そのまま言葉を続ける。
「みな、私のことを……誤解しています。父の死に対し泣きもせず、仇である叔父にも礼儀を尽くす、気丈な女と。……あるいは、腰抜けのお姫様と」
「……殿下」
「ただ……父のことも、叔父のことも、知りもせずに泣けも恨みも出来ないだけなのです」
苦笑いで、セシリアは言った。等身大の少女の顔だった。
「セシリア殿下」
「すいません、湿っぽい話を」
「いえ。陛下とならばこれから何度でも機会があります。その中で、父君の話もお伺いする機会もあるでしょう」
「……ええ、そうですね」
「ーー…僕が、必ず殿下の元に陛下をお帰しします」
父の顔を、クロードは思い出す。
最近は、クロードが幼い頃の、穏やかな顔を思い出せるようになった父を。もう思い出の中でしか語り合えぬ父を。
もっと話せればよかった、という後悔を、クロードは目の前の少女にまでさせたくはなかった。少なくとも、ゼファーに関しては、クロードが力になれる部分があると、自負しているが故に。
「さすがは『白花の勇者』さまですね」
「……?白花…の、勇者、とは」
「この度の件で、クロード様に救われた民が、そう呼んでいるのだと聞きました。アレストの癒しの炎が、花のようだからだとか」
ふふ、とセシリアが笑った。クロードは返答に困って、曖昧に笑った。
王都に来て、アレストの使い手であることを明かしてから、その影響が思ったより遥かに大きく、クロードは戸惑うばかりである。
これを、王は一人で、七年も前から。
「クロード様。おそらくデルウッド侯爵は、その異名を広く喧伝して、あなたを英雄として送り出すつもりだと思います」
その異名を知った時のデルウッド侯爵の顔が目に浮かぶようだった。クロードは苦笑した。
「私も、この国難において、民の不安感を極力減らすためには……叔父上だけでなく、新たなカリスマが必要と思っております」
「僕がそれに耐えうる器かは、確信をもってお答えすることが出来ませんが……癒炎剣アレストの使い手として、恥じぬ生き方をすると誓います」
「その誓い、確かに受け取りました。……叔父上を、よろしくお願いいたします」
深く深く、セシリアは頭を下げた。
出立の日。
セシリアの言葉通り、クロードは『白花の勇者』の勇名を戴き王の隣に並ぶこととなった。
王の名を以て民に知らされた、救世主なき魔竜との対決をせねばならぬとの報は、いっそ『白花の勇者』の名に霞むほど。
王の隊列は多くの民に見送られ、来た時とは真逆に、華々しいものとなった。
「……大丈夫なのでしょうか」
外壁を抜け、王都の喧騒を離れてから、ようやくクロードはぽつりと呟いた。その顔に不安の影が掛かっている。
「やるだけのことはやった。万が一失敗した時には……お前も私も生きてはいまい。あとは生き残った者たちがどうにかすることだ」
王の相変わらずの言い方に、クロードは表情を緩めて笑った。
そうして、その表情が変わる。乞うようなその顔に、王は表情を変えないながら見惚れた。
「陛下は死なせません。なので、もし失敗したら、後のことはお願いいたしますね」
「……そこまでして生き残りたいとは思わんな」
クロードの言葉の意味を王も理解した。命を使い果たしてでも生かすと、奇跡の癒しの炎をもってして、どこまでも命をつなぐと。
「わかっております。……これは僕の、勝手な願いですから」
「勝手な願いか」
思わずゼファーの喉が鳴る。
願いというには、クロードのそれはあまりに無私の献身にすぎた。
だから、王は一つ、意地の悪い問いを投げた。
「ならば、私がこれ以上の苦痛に耐えられぬと、もう治すなと、戦えぬと言えば、お前は叶えてくれるか?ーー…その紅蓮で、慈悲をくれるか」
クロードは虚を突かれて、目を見開いた。それから、その眉をぐっと詰めて、視線を落とす。
「……、……陛下が、真に、それを望まれるのであれば」
常の穏やかさも忘れたような、冷たく暗い声が帰ってきて、王は一層上機嫌に笑った。
ギョッとしてクロードが顔を上げる。呆気にとられたその顔に、ゼファーは目を細めて笑った。
「冗談だ。私が、そのような安楽を得られるとは思っておらぬ」
「陛下、僕は本当に、」
「私の死が、お前の苦痛になるというなら……お前の苦痛とならぬよう、生きる甲斐もあるというものだ」
自分が生きているだけで、この少年を苦痛から遠ざけていると思えれば、それだけで。
ゼファーの心の内まで、クロードは全てを分かったわけではないだろう。
それでも、生きる理由の一つがクロードであることは伝わって、ほっと、安心したような微笑みを零すのだから、向けられる愛情があまりに心地よく、ゼファーは笑みを深めるのだった。
軍都に戻った王の隊列を出迎えたのは、髭の騎士団長が先頭に立つ軍都の精鋭たちであった。軍都将王宮に続く大通りを、王の帰還を待ち侘びていたかのように並び、騎士団の雰囲気に何事かと民たちもそれぞれの家屋や通りの隅から様子を覗いている。
「陛下、王都でのご活躍、お伺いしました。ユーノヴェルト辺境伯……いえ『白花の勇者』殿も」
「耳が早いな。では、この後我々が立ち向かう困難については?」
「ユリウス殿より、大方のことは。しかし、陛下より、ご下命頂ければと」
「……ふむ」
大柄の騎士団長の隣に、ヒョコ、とユリウスが顔を出した。その両隣に、弓騎士隊の新人であり、デルウッド侯爵の差し向けた間諜であったラウドとユーゴが並んでいる。
ほとんど首根っこを押さえられているような状況の二人に、クロードは同情した。
そして、王の言葉を待つ。
「ーー…魔竜を討つ」
王は、いきなりそう告げた。
大通りが、一瞬、静まり返る。それからそこここで聞こえる、民の不安げな声。
「二千年より前から、この国に居座ってきた、悪魔を排す時が来た」
王の言葉は、雷鳴のように響き渡った。くるりとユリウスが指先を動かす。魔術的関与があるのは明らかだったが、クロードにはそれよりも、王が、しかと心底からそう言っていることに、感銘を覚えずにはいられなかった。
かつて、王は『それは、この国が滅びる運命だったとでも思え』と言った。
その王が、このように自らの兵を、鼓舞するように語っている。
「その恐ろしさも、当然王家には伝わっている。建国王はこう記した。『有象無象の悪意の根源、逃れ得ぬ死毒の川を泳ぎ全てを奪わんと顕現す。黒き禍つの災厄、竜の形を以て死を振りまき、ならば拙速に排せねばと、封印の術法を施す。ーー…だがもし、ここに、ユーノヴェルトがいれば、あるいは』」
「…!」
王の視線が、クロードに向く。
だからクロードは応えた。かつて建国王が願ったアレストの使い手の、その再来が今ここにあると、示すために。
癒炎剣アレスト。その銀の刀身を抜く。
そうして、『白花の勇者』の由来となった、白き癒しの炎を、騎士たち一人一人へ送り出すような、そんなつもりで放った。
「癒炎剣アレストは、ここにある。二千年、誰の手にも届かなかった、奇跡の炎を当代ユーノヴェルト辺境伯クロードが手にした!ならば父祖が成し得なかった、恒久の平穏を手にすべきは今であると!!」
ゼファーの声で大気が震えた。それに応えるように、白炎が揺れる。
「やるならば、今しかあるまい。二千年の因縁を、我らの代で、終わらせる!!」
鳴り響いたのは、轟音。
勇猛を示す雄叫びが、一斉に上がった。元より、ゼファーの信の厚い勇士達である、王の号令に、昂らぬはずがなかった。
雄叫びと歓声を受けながら、クロードは王の横顔を盗み見る。金の瞳が、太陽の光を浴びて爛々と輝いていた。その輝きがあまりに眩しくて、クロードは目を細めた。
それから数日後のことである。
ゼファーとクロードが王都より戻ったとの報を聞き、ロベルトは限界まで高まった緊張を、溜息と吐き出したところだった。
二人の神剣使いが軍都に帰還した。その上、王の姉テミスの結界術師団の精鋭がロベルトの指揮下に入り、ユーノヴェルト辺境伯領における常駐監視の戦力としては申し分のないものとなった。
軍都からユーノヴェルト辺境伯領まで、二時間ほどである。ならば、事が起きても二時間、堪えればいいだけだ。傲慢とも言える自負は、確かな経験と幼馴染の置き土産故のことだった。
ユリウスは魔竜が目覚めた時に発動する、いくつかの魔術的仕掛けを残していた。飛んてくから安心しといて。特に詳しい解説はせずに告げた幼馴染に、ロベルトも特に問い返さなかった。
「ロベルト殿、お疲れ様です」
「ああ、どうも」
夕暮れ時、魔竜の遺跡を見下ろす監視塔から、ロベルトは眼下の風景を眺めていた。ユーノヴェルト辺境伯家の私兵が、主の生真面目さとよく似た真面目さできびきびと警備を続けているのが見える。
眼下を見下ろすロベルトに声をかけたのは、クロードの姉フローラだった。その手には軽食の入ったバスケットがある。
「いつもお手間かけてすいませんね」
「いえ」
フローラが、簡素なテーブルの上に、バスケットの中身を広げる。この監視塔にくる時にはほとんど男装のような装いのフローラがそれをやると、まるで中性的な印象の執事のようだった。
「ご不便はありませんか?監視が長期になる可能性を考えて、居住性もある程度考えては作らせましたが……」
「王弟時代の陛下について回ってた頃から考えたら天国みたいなもんですよ。天井も寝床もある上に、美味い食事もあるし」
この監視塔は、クロードが軍都に発ってから建築したものだ。その窓からは、魔竜の遺跡の中央にある、天井が崩落した箇所がよく見える。
そこには、床石に大きく広がる黒い竜の絵図があった。
封印されし魔竜、そのものである。封印が解ければ、この絵図は実体を持ち、黒い瘴気の炎をまき散らすという。
その周辺を小型の魔物がウロウロとうろついている。ロベルトは、食事に手を付ける前に、その魔物に向けて、弓を向けた。
そうして、一閃。
光が届くと共に、その小さな影は、黒い瘴気の粒となって消えた。
「まあ、こうして暇することもないんでね」
ロベルトは軽く言って、弓を置いて椅子に腰掛けた。
「ふふ。ならば良かった。どうぞ。今日は川魚のフライを挟んだサンドイッチとのことです」
「ありがたくいただきます」
ロベルトにとって、ユーノヴェルト伯爵家のシェフが作る料理には本当に助けられていた。
ここが最も優れた射撃地点のため、ロベルトは監視塔から離れられない。睡眠時の監視は部下に任せていたものの、退屈とそれに伴う緊張の緩みを避けるのはかなり困難であった。その中で、意識の切り替えとして、バリエーション豊富な美味というのは、かなり効果的だった。
「フローラ殿。これからはウチのに取りにいかせますから、無理してここまで上がってらっしゃらなくても大丈夫ですよ」
「無理と言うほどの階段ではありませんが……」
「いえ、妊娠してらっしゃると、ご心配も多いでしょう」
大口を開けてサンドイッチを口に入れたロベルトは、フローラからの返答がずいぶん遅いことに気づいた。驚いた顔をしたフローラが、気まずそうに微笑んでいる。
よく似た姉弟だ、とクロードのことを思い出しつつ、ロベルトはよく咀嚼したサンドイッチを飲み込んで、尋ねた。
「……もしかしてご懐妊のこと、伏せられてました?」
「いえ、隠していたわけではないのですが……よくお分かりになりましたね」
「ああ……妊娠している御婦人は魔力の流れ方が特殊なので」
懐妊など祝うべきだけのことで、フローラが何に気まずくなっているのか分からず、ロベルトはただ自分の発言の根拠だけを端的に口にした。
「このような時に、間が悪いとはわかっているのですが……」
このような時。フローラは七ヶ月前から、魔竜の封印が緩んでいることを知っていた。だが腹の様子からして、妊娠したのはそれよりも後のことだろう。だからそれを恥じているのだと、ようやくロベルトは思い至った。
「いや、こういう時だからこそ希望になるでしょう。魔竜が完全に過去になった第一世代、楽しみですよ、俺は」
先ほどまで相手の発言の意図を測りかねていたとは思えぬ反応で、ロベルトはそれを口にした。それは真に思っているからこそ出た言葉でもあるし、ロベルトのコミュニケーション能力の高さ故でもあった。
「俺たち世代は、丁度現役真っ盛りに魔竜の復活を迎えるのが分かっていましたからね。そんな思いをせずにいられる子が生まれると思えば、やる気もでますよ。俺なんか、騎士になる時には、親父に言われましたからね。魔竜封印の捨て駒になる気かって」
ロベルトが弓騎士を目指したのは、信念や理想があってのことではない。ただただ、弓を極めたい、と言う自分の欲求だけのことである。
だが、その道がいずれ魔竜との対決に繋がるのは必定だった。魔竜がこの国に、百年に一度の災厄を振りまく限り、それは永遠に続く。
断ち切れるのなら、それは今だ、とロベルトも強く思っていた。
「せっかくまあまあの才能、天から貰ってるんです。それなら、あのクソボケ竜にぶっ放してやって、二度と俺と親父みたいな喧嘩する親子がいなくなればいいでしょう」
「……ノブリス・オブリージュ、ですか?」
「いや、どっちかというと『人生なんでもやったもん勝ち』、ぐらいのもんです」
はは、とロベルトが笑って、フローラも笑った。そうして最後の一口を口の中に放り込むと、ロベルトは先ほどとは味が違う気がして、口を止めた。
いや違う、味じゃない。
ロベルトは咄嗟に弓に手を伸ばした。まだ、微かな違和感でしかないが、それを外したこともなかった。
いまだ異変に気付いていないフローラも、ロベルトの様子を見て、顔を険しいものにする。
二人の視線が、窓の外に向いた。一見、何の変化もないように見えた。
「ロベルト殿」
「少し集中します。目視での警戒はお任せします」
「はい」
フローラの言葉に、ロベルトは端的に答えて、すう、と息を大きく吸い込む。やはり、違う。ただの勘だけとも言えぬ、風まで読む弓兵の感性が危機を告げていた。
目を伏せて、自らの瞳に魔力を載せる。魔性の存在に焦点を合わせて超視力を引き出す『騎士の対魔法』は、遠距離射撃を本分とする弓騎士の本領の一つであった。
ゆっくりと、その目が開く。
ロベルトの翡翠の瞳が、尋常ではありえないほど遠くを映す。魔竜の遺跡の石床、その欠けの形まで見えるそれを、音も聞こえないほどの集中で調節して、ロベルトの瞳は、封印されし魔竜の絵図の些細を捉える。
その、絵図のひび割れが、血管のように胎動する様を、はっきりと。
「フローラ殿!緊急号令を!」
ばつん、と超視力の対魔法を取り消し、ロベルトは隣のフローラに告げた。
「魔竜を遺跡から出さぬよう、隊列を組ませます!ーー…ご武運を!!」
強く頷いたフローラが、足早に階段を降りる。その背を見送って、ロベルトは弓を大きく引く。
まだ、まだだ。
まだ、魔竜は絵図のまま実体を現していない。早まるな。ロベルトは息を吐き出す。
いち、に、さん。心拍を平静のものに戻すため、内心で数を数える。自分がしくじれば、何人死ぬかわからない。
魔竜は目覚めと共に、周辺を焼き尽くす黒炎を吐き出すという。その黒炎を吐き出す瞬間に、その魔力が集約する胸に、魔力を四散させる矢を、撃ち込まねばならない。
遠くで、鐘の音が鳴り響く。フローラの緊急号令の合図だ。
はじまる。
黒き竜の翼が、羽ばたく。だがその巨体を空に駆けさせはしない。
想定よりも遥かに大きいその体は、遺跡が子ども騙しのおもちゃに見えるほど。その目は真っ黒に染まり、咆哮を上げようとしていた。
その竜を、光の粒が覆う。ユリウスの『置き土産』である。
光の粒は、竜の巨体を覆うように柔らかく吸い付いた。
途端。
鎖の形となった光が、ギャリリ、と激しい金属音を上げて竜の四肢に巻き付き、その巨体を締め上げる。怒りの咆哮が上がる。
その胸元が、赤黒く、激しく燃えるように光る。
「……ここまでお膳立てされて、俺がやれねぇ訳ねえだろ!」
幼馴染へ向けての軽口と共に、ロベルトは矢を放った。
澄んだ翡翠を纏った矢は、吸い込まれるように竜の胸元へ。そうして、集まった熱量は行き場を失い、その場で大きな爆発を起こす。
新しい矢をつがえたロベルトの隣で、膨大な魔力が揺らぐ。その魔力の主が誰のものか知っているロベルトは、そちらを見もしなかった。
「ーー…【黎明よ、我が掲げる非情の冠よ】」
魔力の渦の中から、男が姿を現す。まるで世界の膜の狭間を潜り抜けてきたかのように、身を捻ってそこに現れた男の足元に、いくつもの魔法陣が輝いていた。
銀の髪に赤い目。魔術の大家、ラドウィン侯爵家当主ユリウス、その人である。
「【太陽よりも鮮烈に、月よりも静謐に、星より叡明に、すべての光を統べ、すべての獣を我が元に下せ」
挨拶も交わさず、ユリウスは詠唱を続けた。ほとんど魔法を使う時に詠唱など口にしないユリウスが、それを省略せずに声に魔力を乗せる。
竜の体が、ピタリとその動きを止める。
「【伏して拝せ、其は我が下僕である。我は力、我は支配、我は所有者にして全ての王、我が言葉は運命にして宿命の必然】」
ユリウスが詠唱を進めるごとに、新しい魔法陣が浮かび上がる。それは次々と重なり合って、もはや解読も出来ないほど。
ユリウスが、ゆっくりと腕を前に出した。
「ーー…【獣よ、口を開け】」
ぐぐ、と指先に力を込めて、そうしてユリウスが手を開いた瞬間。
竜はだらしなく舌を垂らして、支配者にその口内を晒した。
ユリウスの口から、荒い息がもれる。
かつて、封印こそ万全であれば魔竜を操ることも可能、と軽く言ったユリウスが、封印下でなくともそれを成し遂げた。
だが、それが長く保つわけでないのは、様子からして歴然であった。
「…撃て、ロベルト」
だから、温度のない、だが信頼の明らかな幼馴染の言葉に、ロベルトはすぐに応えた。眩しいほどの翡翠が駆けて、竜の顎を吹き飛ばす。
ぐらり、とその巨体が傾いた。
ドロドロと黒い血が地面を汚し、あたりに腐臭が広がる。その匂いはかなり距離のある監視塔まで届いた。それはまるで、元から死体であったような。
二千年、王国を苦しめた魔竜、その体が崩れ落ちる。
確かに魔竜を倒した。
だというのに、その黒い血が、その腐臭が、ロベルトの違和感を刺激して、鳥肌が立つほどの焦燥感が全身を襲った。
「ユリウス……本当に、これで、終わりか?」
「ロベルト、構えを解くな」
そう言うユリウスの周囲には、いくつもの魔法陣が浮かんでいる。ユリウスの目が、魔竜のいた場所から動かない。この稀代の天才が、魔術的な解析をしているのは明らかだった。
「こいつは……まだ奥に『いる』!」
それは、ユリウスの言葉と同時。
竜の腹を突き破り、黒い奔流が放たれた。
ぐちゃぐちゃと粘着質な音を立て、元の竜の大きさまで膨れ上がったその黒は、数多の眼球をその流体の狭間に浮かばせ、その視線の全てをロベルトとユリウスに向けていた。
その瞳が、赤黒く光るのを見て、反射的にロベルトは矢を放つ。
眼球から放たれる光線が、翡翠の矢とぶつかり合う。無数の光線は翡翠に射抜かれて、次々と爆発して霧散していく。
だが全てを捉えることは出来ずに、直撃ではないとロベルトが判断して優先順位を遅らせたそれらが、監視塔を破壊し、瓦礫に変えていった。
魔力の揺らぎを感じて、ロベルトはユリウスに任せることにした。そして問うた。
「『竜』じゃないのか!?」
「黒き禍つの災厄、有象無象の悪意の根源、逃れ得ぬ死毒の川……」
ロベルトの問いに言葉を返しつつ、ユリウスの指先から放たれたのは重力緩和魔法だった。着地までおよそ十メートル。土煙の向こうを警戒しながら、ロベルトはユリウスの言葉の続きを待つ。
「魔竜の権能だと思ってたけど、逆だ。この『黒い血そのもの』が竜の皮を被ってやったことだ。…やられたな。やっぱ実地に勝る解析はない」
ふぅ、と息を吐き出して、ユリウスは前方に魔力の壁を作り出す。
「あ~…なんだ、つまり、こっからが本番か?」
「そゆこと。危なかったな、うっかり神経系まで繋げる操作魔術使ってたら、逆に乗っ取られるとこだった」
「ゾッとする話すんなよ。お前の世話までやってられっか」
「だはは、ロベルトならどうにかなるっしょ」
「なるかよクソボケ」
軽口を交わしながら、ロベルトは前方にいくつもの矢を放つ。未だ土煙晴れぬその先で、それは敵性の魔力を穿って破裂した。
「作戦自体はあいつを遺跡から出さない、で変更なしでいいか?」
「それでよろしく。まだ仕掛けてた拘束魔術が効いてるから、そこから心臓の箇所を割り出して縫い留める。ロベルトは迎撃頼んだ」
ユリウスの言葉を聞きながら、ロベルトは魔力のゆらぎを感じて視線を走らせる。青白く薄い膜が、遺跡全体を覆う。テミスの配下の結界術師だ。
「結界術師も守っといてね。流れ弾だけでも外に漏れたらマズイ」
「おう」
「あとあの目玉減らしておいてくんない?」
「お……いや簡単に言うなよ、そもそも攻撃通るかもわかんねぇのに」
危うく気楽に頷きそうになって、ロベルトじっとりとした目つきでユリウスを睨む。すでに拘束と解析の魔術を展開しているユリウスは、ロベルトに視線を返さなかった。
「いやロベルトなら行けるかなって……」
「お前の中の俺はなんなんだよ」
呆れながら、ロベルトは弓を引く。土煙の狭間から、黒い血の目玉へと向かったそれは、だがその手前で光線に撃ち抜かれて空中で破裂した。
「行けそう?」
「わからん。でも攻撃のタイミングをコントロールすることは出来そうなんだよな。やってみるか」
「やっぱロベルトなんだよな~」
「何だそれ」
ふざけた物言いで信頼を向けるユリウスに、ロベルトは弓を放ちながら応える。ロベルトもユリウスも、普段と変わらぬ軽い口調ではあったが、互いに慎重になっていることを感じ取っていた。
「お前が死んだら終わりなんだからな。俺の腕、使い潰すつもりで使えよ」
「もちろん。陛下とクロード殿が来るまで、まあ、楽しくやろうよ」
長年の信頼を乗せて、その長い夜が始まった。
0
あなたにおすすめの小説

猫カフェの溺愛契約〜獣人の甘い約束〜
なの
BL
人見知りの悠月――ゆづきにとって、叔父が営む保護猫カフェ「ニャンコの隠れ家」だけが心の居場所だった。
そんな悠月には昔から猫の言葉がわかる――という特殊な能力があった。
しかし経営難で閉店の危機に……
愛する猫たちとの別れが迫る中、運命を変える男が現れた。
猫のような美しい瞳を持つ謎の客・玲音――れお。
彼が差し出したのは「店を救う代わりに、お前と契約したい」という甘い誘惑。
契約のはずが、いつしか年の差を超えた溺愛に包まれて――
甘々すぎる生活に、だんだんと心が溶けていく悠月。
だけど玲音には秘密があった。
満月の夜に現れる獣の姿。猫たちだけが知る彼の正体、そして命をかけた契約の真実
「君を守るためなら、俺は何でもする」
これは愛なのか契約だけなのか……
すべてを賭けた禁断の恋の行方は?
猫たちが見守る小さなカフェで紡がれる、奇跡のハッピーエンド。

雪解けを待つ森で ―スヴェル森の鎮魂歌(レクイエム)―
なの
BL
百年に一度、森の魔物へ生贄を捧げる村。
その年の供物に選ばれたのは、誰にも必要とされなかった孤児のアシェルだった。
死を覚悟して踏み入れた森の奥で、彼は古の守護者である獣人・ヴァルと出会う。
かつて人に裏切られ、心を閉ざしたヴァル。
そして、孤独だったアシェル。
凍てつく森での暮らしは、二人の運命を少しずつ溶かしていく。
だが、古い呪いは再び動き出し、燃え盛る炎が森と二人を飲み込もうとしていた。
生贄の少年と孤独な獣が紡ぐ、絶望の果てにある再生と愛のファンタジー

地味メガネだと思ってた同僚が、眼鏡を外したら国宝級でした~無愛想な美人と、チャラ営業のすれ違い恋愛
中岡 始
BL
誰にも気づかれたくない。
誰の心にも触れたくない。
無表情と無関心を盾に、オフィスの隅で静かに生きる天王寺悠(てんのうじ・ゆう)。
その存在に、誰も興味を持たなかった――彼を除いて。
明るく人懐こい営業マン・梅田隼人(うめだ・はやと)は、
偶然見た「眼鏡を外した天王寺」の姿に、衝撃を受ける。
無機質な顔の奥に隠れていたのは、
誰よりも美しく、誰よりも脆い、ひとりの青年だった。
気づいてしまったから、もう目を逸らせない。
知りたくなったから、もう引き返せない。
すれ違いと無関心、
優しさと孤独、
微かな笑顔と、隠された心。
これは、
触れれば壊れそうな彼に、
それでも手を伸ばしてしまった、
不器用な男たちの恋のはなし。

人気作家は売り専男子を抱き枕として独占したい
白妙スイ@1/9新刊発売
BL
八架 深都は好奇心から売り専のバイトをしている大学生。
ある日、不眠症の小説家・秋木 晴士から指名が入る。
秋木の家で深都はもこもこの部屋着を着せられて、抱きもせず添い寝させられる。
戸惑った深都だったが、秋木は気に入ったと何度も指名してくるようになって……。
●八架 深都(はちか みと)
20歳、大学2年生
好奇心旺盛な性格
●秋木 晴士(あきぎ せいじ)
26歳、小説家
重度の不眠症らしいが……?
※性的描写が含まれます
完結いたしました!

虐げられている魔術師少年、悪魔召喚に成功したところ国家転覆にも成功する
あかのゆりこ
BL
主人公のグレン・クランストンは天才魔術師だ。ある日、失われた魔術の復活に成功し、悪魔を召喚する。その悪魔は愛と性の悪魔「ドーヴィ」と名乗り、グレンに契約の代償としてまさかの「口づけ」を提示してきた。
領民を守るため、王家に囚われた姉を救うため、グレンは致し方なく自分の唇(もちろん未使用)を差し出すことになる。
***
王家に虐げられて不遇な立場のトラウマ持ち不幸属性主人公がスパダリ系悪魔に溺愛されて幸せになるコメディの皮を被ったそこそこシリアスなお話です。
・ハピエン
・CP左右固定(リバありません)
・三角関係及び当て馬キャラなし(相手違いありません)
です。
べろちゅーすらないキスだけの健全ピュアピュアなお付き合いをお楽しみください。
***
2024.10.18 第二章開幕にあたり、第一章の2話~3話の間に加筆を行いました。小数点付きの話が追加分ですが、別に読まなくても問題はありません。

龍の無垢、狼の執心~跡取り美少年は侠客の愛を知らない〜
中岡 始
BL
「辰巳会の次期跡取りは、俺の息子――辰巳悠真や」
大阪を拠点とする巨大極道組織・辰巳会。その跡取りとして名を告げられたのは、一見するとただの天然ボンボンにしか見えない、超絶美貌の若き御曹司だった。
しかも、現役大学生である。
「え、あの子で大丈夫なんか……?」
幹部たちの不安をよそに、悠真は「ふわふわ天然」な言動を繰り返しながらも、確実に辰巳会を掌握していく。
――誰もが気づかないうちに。
専属護衛として選ばれたのは、寡黙な武闘派No.1・久我陣。
「命に代えても、お守りします」
そう誓った陣だったが、悠真の"ただの跡取り"とは思えない鋭さに次第に気づき始める。
そして辰巳会の跡目争いが激化する中、敵対組織・六波羅会が悠真の命を狙い、抗争の火種が燻り始める――
「僕、舐められるの得意やねん」
敵の思惑をすべて見透かし、逆に追い詰める悠真の冷徹な手腕。
その圧倒的な"跡取り"としての覚醒を、誰よりも近くで見届けた陣は、次第に自分の心が揺れ動くのを感じていた。
それは忠誠か、それとも――
そして、悠真自身もまた「陣の存在が自分にとって何なのか」を考え始める。
「僕、陣さんおらんと困る。それって、好きってことちゃう?」
最強の天然跡取り × 一途な忠誠心を貫く武闘派護衛。
極道の世界で交差する、戦いと策謀、そして"特別"な感情。
これは、跡取りが"覚醒"し、そして"恋を知る"物語。

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!
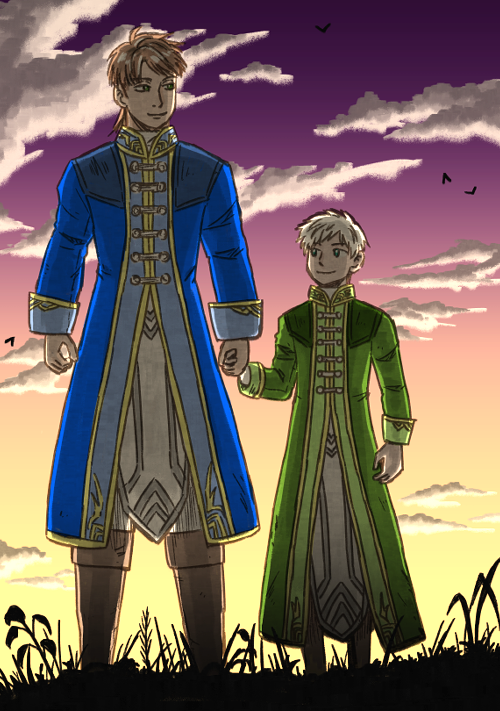
天涯孤独になった少年は、元軍人の優しいオジサンと幸せに生きる
ir(いる)
BL
※2025/11 プロローグを追加しました
ファンタジー。最愛の父を亡くした後、恋人(不倫相手)と再婚したい母に騙されて捨てられた12歳の少年。30歳の元軍人の男性との出会いで傷付いた心を癒してもらい、恋(主人公からの片思い)をする物語。
※序盤は主人公が悲しむシーンが多いです。
※主人公と相手が出会うまで、少しかかります(28話)
※BL的展開になるまでに、結構かかる予定です。主人公が恋心を自覚するようでしないのは51話くらい?
※女性は普通に登場しますが、他に明確な相手がいたり、恋愛目線で主人公たちを見ていない人ばかりです。
※同性愛者もいますが、異性愛が主流の世界です。なので主人公は、男なのに男を好きになる自分はおかしいのでは?と悩みます。
※主人公のお相手は、保護者として主人公を温かく見守り、支えたいと思っています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















