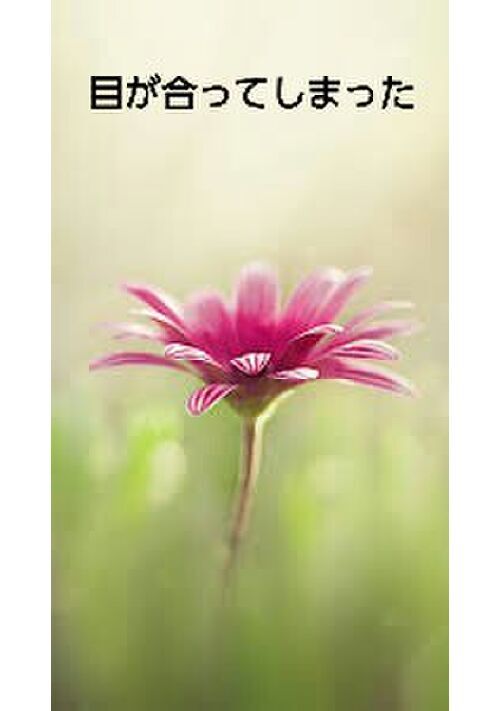1 / 1
妖精が連れてきた春
しおりを挟む王都の西部の城壁沿いには、安宿が連なる一角がある。そこには、田舎から出て来たばかりの者、身体が動かなくなった者、そして運の巡り合わせが悪かった者が身を寄せ合うようにして暮らしている。
他の区画は、石造りの建物がほとんどだったが、この一角だけは、木造の板張りの建物ばかりだった。
アパートメントと言うには、あまりにもみすぼらしい、打ち付けられただけの板から隙間風の吹き込む部屋で、数日前から体調の悪かったサラは、ついに、ベッドから起き上がる事すら出来なくなっていた。
サラは、自分が高熱を出している事は、よくわかっていた。
だが、毎日をやっと食べて行くだけが精一杯の彼女の実入りでは、薬や栄養の付く食べ物を買う事は難しかった。
お屋敷で褒められていた淡い藍色の髪にはすでに艶も無く、水気を失った肌はかさついてしまっていて、まだ17歳だというのに一気に十も老け込んだように見える。
「もう……ダメかな……。」
そうつぶやこうとしたが、乾いてしまった喉から出たのは、ゼイゼイと苦しそうな音だけだった。
昨日の昼、サラが、やっとの思いで換気しようと開けた窓は、陽が落ちる頃には、もう動けなくなってしまっていた彼女には閉める事すら出来ず、丸一日開け放たれたままだった。
サラが、こんな生活に身をやつしていたのは、単純に運が無かったからだった。
*
半年前まで、サラは貴族の屋敷で女中として働いていた。
村から出て来て、斡旋所での紹介を受け、初めて王都の郊外にある屋敷を見たサラは、その大きさと美しさに目を回しそうになった。
蔦の絡まる石造りの建物が、綺麗に整えられた芝生の上に浮かんでいるように見え、その庭に設けられた池には、透き通った水に、魚が泳いでいるのが見えた。
門を過ぎてからずっと続く石畳の道は、いつまで歩いても建物に着かない気にさせられた。
そんな屋敷の中で、サラは一緒に働く女中たちに可愛がられ、幸せな時間を過ごしていた。
部屋は先輩のアンナと一緒ではあったが、ふかふかの布団に暖かい部屋、そして舌がとろけそうな食事に、サラは自分がまるで姫様になったかのように感じられていた。
*
しかし、そんな生活は一年を過ぎたころ、突然終わりを告げた。
雇い主であるモルドレッド公爵が、王によってその身分を追われる事になってしまったからだ。
『謀反を企てた罪で、モルドレッド公爵の領地は没収。公は投獄された。』
街の人が知っているのはこのくらいだった。偉い貴族が失脚したと聞いも、ざまあみろと思う事が精々だろう。
だが、屋敷で働いていたサラたちは、いきなり働く場所と住む場所を失うこととなった。
前から能力を見込まれて、他の貴族や商人から声を掛けられていた女中頭のメアリや仲間のアリス。執事のハリスは行先が決まり、それぞれ新しい職場へと旅立って行った。
だが、経験の浅い者、身寄りの無い者、老齢で長く働くには厳しい者。そう言った人々は新しい職場に移る事も出来ずに路頭に迷った。
メイドとして働き始めて、まだ一年と少しのサラも、そんな中の一人だった。
なんとか見つけた小さなアパートメントの一室に、最初は女の子五人で住んでいた。みんなで蓄えと知恵を持ち寄り、何とか糊口を凌いだ。
だが、一人が女中として行先が決まり、二人が田舎に帰り、最後の一人も商家の見習いに決まって、最後にサラだけがここに残る事となってしまった。
それが、サラがここに居る理由だった。
サラは、八百屋のマーサの店に手伝いに行ったり、他のお屋敷の水くみを手伝いに行ったりして、お小遣いをもらっていた。
ギリギリだけれども、生きて行くだけなら何とかなっていた。
しかし、一度体調を崩して、日銭が入って来なくなった時、一気に生活は立ち行かなくなってしまった。
*
サラの枕元に置いてあった水差しの水は、もう朝方には無くなってしまっていた。
汲みに行かなきゃと思い、身体を起こそうとしたが、サラの身体には力が全然入らない。
しかも、身体を動かそうとする度に筋肉に激痛が走る。
食べるものは、もう三日も前から何も無かった。
───お母さんが作ってくれた、リンゴのピューレが食べたい……。
サラが思い出すのは、彼女が風邪を引いた時に、母が作ってくれたピューレの甘さだった。
農園の木から、一番熟れたリンゴの実を、丁寧に煮潰し、そして家の裏の川で冷やしたものだ。
額には、冷やした手拭いが当たり、母が一匙一匙掬っては食べさせてくれる、甘くてほんの少し酸っぱい、その味を、サラは何とか感じようとする。
だが、舌先に感じられるのは、渇ききった自分の口の中の感触だけ。
寂しくて、怖くて。そして自分の運命が悲しくて涙が流れそうになる。
サラが瞑っていた目を開けて、ふと見上げると、小さな丸い光の珠がくるくると回っていた。
───あ、妖精さん……。来てくれたんだ……。
サラは、声を出すのを諦めて、心の中で思うだけにした。
妖精と言っても、おとぎ話に出てくるような女の子に羽根が生えているようなものとは違う。
名前も別にあるようだったが、サラは小さな頃から妖精と言っていた。
光る羽根を持ち、透き通った身体をした小さな魔物。たまに人間の周りをくるくると回る以外には害も無いので、討伐される事はない。
サラが住んでいた田舎では、ありふれた姿だった。
この街に来てからは見たことが無かったが、その妖精は開け放したままになっていた窓から、ふいと入って来たのだった。
妖精が部屋に入って来た時には、お迎えが来たのかと思ってしまっていた。
懐かしい故郷の森。そんな木立の中で揺れる小さな淡い光。
そんな光景が思い出され、とうとう乾いてしまった瞳から涙が溢れる。
その魔物は、出来の悪い人形のような形をしていて、うっすらと透き通っている。身体の側面から生える羽根を、パタパタと動かしながら飛び、その身体の中央には小さな魔核が明滅しているのが見えた。
サラは村の事を思い出す。
───お父さん……お母さん……そして弟たち……。
サラは、家に何度帰りたいと思ったか知れない。
ただ、ここから馬車で十日も掛かる故郷に行くには旅費が必要だった。
それに、農家の口減らしで王都に出された娘が帰って来ても、良い顔はしないだろう。
───戻る場所なんて、最初から無い。
サラは、自分を売ろうとまで思い詰めて、娼館の前まで行った事もあった。
ただ、その時、裏口からたたき出されたのが、屋敷で一緒に働いていた女の子だったのを見て、サラは恐ろしくなって逃げ帰ってしまった。
むしろ、こうして動けなくなってしまった今となっては、自分の身体を売らなくて済んで良かったんだと思う。
サラの意識は段々と遠くなる。
外はもう陽が落ちて真っ暗になってしまっていた。
先ほどまで一匹だった妖精たちは、その数を増やし、部屋の中を無節操に飛び回り始めた。
赤や黄色。そして青。淡い光が部屋の中を乱舞する。
───まるでおとぎ話で聞く、大魔術を使う魔法使いみたい……。
部屋を照らす、妖精たちの光が、魔法陣が乱舞する大魔法のように、サラには見えた。
───王子様……助けてください……。
サラは、魔法使いが大魔術を使う時のように腕を上げ、思い切り念じてみた。
ふわふわとした気分に、自分が本当に魔法が使えている気になる。
「王都内での大魔法の使用は厳禁だ! 今すぐ止めよ! 」
ドアを蹴り破って入って来たのは、若い衛兵だった。
彼は、開け放たれた窓から見える光の乱舞に、こんな場所で大魔法を使おうとしている者が居ると思い、慌てて突入して来たのだった。
衛兵は彼女の姿を見て、周りを飛んでいたのが妖精だったことに気が付いた。
何事が起っていたか理解した彼は、衰弱していたサラにポーチから官給品の回復薬を取り出し、彼女をベッドから抱え上げて飲ませた。
「すぐに水を汲みに行ってくれ! ひどい熱だ! 」
手甲を慌てて外し、サラのおでこに手を当てて、熱がある事が解ると衛兵は一緒に来ていた同僚に叫んだ。
扉のあったところに立っていた、もう一人の衛兵が頷いて走り出す。
「おい! 意識はあるか!? 」
衛兵は、彼女の頬を軽く叩き、意識を何とか取り戻させようとした。
妖精たちは、その姿を見て、窓から飛び出して逃げて行く。
「大丈夫か!? 」
衛兵の不安そうな灰色の瞳が、抱えあげていたサラを見つめると、うっすらと彼女は目を開けた。
サラの目には、ピカピカに磨かれた鎧が目に入った。
「……王子……さま? 」
サラの回復薬で湿った喉が、声を絞り出した。
「……ああ。そうだ。迎えに来たぞ姫! 」
朦朧とするサラに、衛兵は答える。
こういう場合、落ち着くまでに気を失うとそのまま死んでしまう事がある。
それを知っていた衛兵は、サラに話しかけ続けた。
「おい! 水を汲んで来たぞ! 」
井戸に走ってもらっていた衛兵が走って帰って来た。
衛兵は、腰のポーチを開けて、三角巾を取り水に浸してサラの額に乗せた。
彼女が一刻を争う状態なのは、誰の目にも明らかだった。
「すまん! すぐに 治療術師を呼んで来てくれ! 」
「わかった! なんとしても死なせるなよ! 」
「任せろ! 」
もう一人の衛兵が、彼女を指差しあてから詰め所へと走りだす。
「本当に迎えに来てくれたのですね…。」
「ああ…そうだ。君の魔法に呼ばれて来たんだよ。」
───良かった……私の魔法は通じたんだ……。
サラは、自分の頬を叩かれる感触と、誰かが大声で姫と呼ぶ声を聞きながら、満ち足りた気分で、その瞳をゆっくりと閉じた。
*
「いってらっしゃい。あなた。」
サラは、腕に抱いた娘の口元を拭きながら、出勤する夫に手を振る。
歯の生え始めた娘の口には、離乳食のリンゴのピューレがまだついていた。
「いってくるよ。サラ。アリスはいい子にしてるんだよ。」
衛兵である彼の今日の勤務は昼番だったので、サラは明け六つの鐘が鳴る頃に送り出す。
衰弱して倒れていたサラを放っておけず、衛兵が面倒を見ると言うか、お節介を焼いているうちに、二人はそんな関係になっていた。
衛兵は、最初サラの事を、かなり年上の女だと思っていた。
だが、治療院でしっかり栄養を取るうちに、彼女はみるみるうちに回復し、その姿を美しい娘へと変えて行った。
そして一昨年に結婚して、今は娘のアリスが居た。
「よう。王子様。」
衛兵詰め所に向かう道すがら、彼に同僚のアランが声を掛けて来た。
サラの部屋に突入する際に、コンビを組んでいた男だった。
「だから、それは止めろって言ってるだろ? 」
一部始終を知っていたアランは、娘が回復して彼と付き合い出したころ、衛兵の間にこのエピソードを吹聴して回った。
おかげで彼は、その当時、しばらく隊長からも王子様と言われていた位だった。
アランが言うには、あんな可愛い子を手籠めにするなんて許せん。と言う義憤からだったらしい。
「それにしても、あの光が魔物のせいだったなんてな。」
ふと思い出したように同僚が言う。
「ああ…そうだな。確かに魔法としか思えんよな。」
衛兵も目を閉じて、光が乱舞する光景を思いだす。
「そうそう。明日からはこうやって話も出来なくなるな。宜しく頼んますぜ。隊長。」
そう言って笑いながら同僚はお先にと衛兵の肩を叩き、走って詰め所まで向かう。
あの魔物は、動物が死んだ瞬間に放出する魔力を吸収して生きている。
それで死にそうな動物が居ると、近くで回って仲間に教え合う習性があった。
小さいころに牧場で育った彼は、家畜が死ぬ前によくあの魔物が周りを舞っているところを見ていた。
部屋に入った瞬間に、サラの命が尽きようとしている事に気が付けたのは、そのためだった。
おかげでサラをすんでのところで助ける事が出来たのだった。
最近は王都の治安も良くなり、死にかけた人間が路地裏に倒れている事も無くなった。
もうあの魔物たちが王都で乱舞する事は無い。
ただ、あの魔物…いや、妖精には感謝しなくてはならないだろう。と、彼は思う。
彼にとって、大事な妻と子供を運んで来てくれたのだから。
『お父さんはね。妖精さんが魔法で連れて来てくれたんでしゅよー。』
衛兵は、娘に話しかける妻の姿を思い出す。
彼女の前では出来るだけ王子様であろうとしなくてはならないな。と彼は誓いを新たにして、衛兵詰所の扉を開けた。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
11
この作品の感想を投稿する
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる