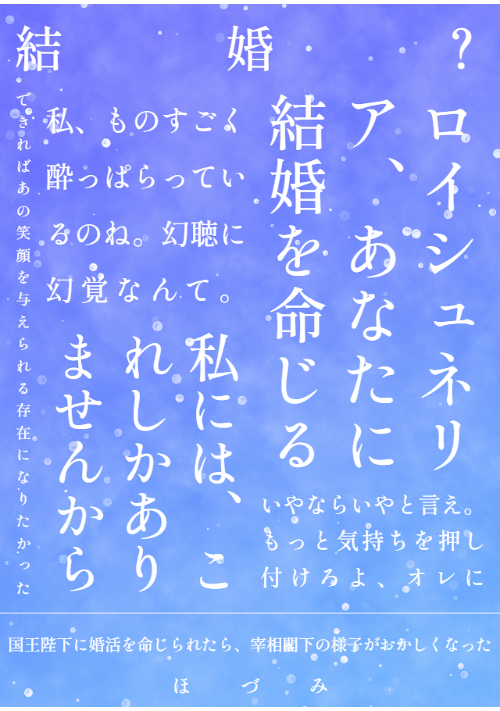20 / 39
第14話
しおりを挟む
「――どうなっているのだ?」
帝城のとある会議室に響く皇帝、ルドルフⅡ世の声音は、絶対零度の響きを帯びていた。
それもそのはずだ。本日行われた、闘技場でのオートマタ同士の試合結果――帝国のエースの中のエース、シャンディ・ガフがまさかの敗北。
しかもただの敗北ではない。先取制の三本試合の形式での戦いで、まさかのストレート負け。しかも、一本目の試合は10分もかからず、二本目の試合は3分にも満たない時間で敗北したのである。
この闘技場での試合を最初に提案した若い閣僚は、もはやすっかり血の気をなくし、真っ白な顔で席に座っていた。テーブルの下の両足は、生まれたての子鹿のようにがくがくと震えている。
「あの漆黒の機体『舞乙女』は、ランクの高い魔晶石をふんだんに使っている優れた機体である。だが、そのような機体を扱うともなれば、搭乗騎士へのフィードバック、負担は相当なものとなる……そのはずだったな?」
「そ、そのはずでございました……」
「では、今回の結果はどういうことか? 我が国が誇るシャンディ・ガフをああもやすやすと打ち負かしたのだぞ。いや、敗北などという言葉では生ぬるい。大人が幼児を相手どるかのように――まるで相手になっていなかったではないか!」
ルドルフⅡ世の怒声に、若い閣僚が「ひっ」と小さく悲鳴をあげて首をすくめる。
だが、ルドルフⅡ世も胸中では――これがただの八つ当たりに近いものであることは自覚していた。
彼の想定の内には、もしかするとあの機体が本当に自分たちの機体をも上回る性能を持ち、シャンディ・ガフに勝利をするかもしれない、という可能性も考慮していたのだ。だが、その予想は大幅に覆された。まさかのシャンディ・ガフのストレート負けという事態に、さすがのルドルフⅡ世も今は冷静ではいられなかったのである。
会議室の円卓は側近や大臣、閣僚たちでいっぱいではあったものの、その誰もが口を開こうとしなかった。しかし、しばらくしてから円卓に座っていたでっぷりとした腹の閣僚が、ゆっくりと口を開いた。
「しかし、陛下。今回の試合で分かったこともございます。……初めに我らが予想していた『獣王国の奸計』ではないかという可能性はなくなりました。つまりあれは、獣王国側の機体ではないということです」
「なぜそう思うのだ?」
でっぷりとした腹の閣僚の静かな言葉に、ルドルフⅡ世の気持ちがわずかに収まり、話を続けるように促す。
「単純に、シャンディ・ガフを相手にあれほどの力量と搭乗技量を持つものを獣王国側が我々に派遣する理由ございません。奸計をめぐらす必要すらないほどの強さですからな」
「……確かに、そうであるな」
ルドルフⅡ世の気持ちが幾分か冷静になったのを見てとり、傍らの側近もおずおずと話を切り出した。
「今回の試合でございましたが……戦ったフランツ・ベルンハルトからの報告がございます。報告をさせて頂いてもよろしいでしょうか?」
「……構わぬ」
「ありがとうございます。今回のベルンハルトからの報告ですが――『舞乙女』の機体のスピード。あの機体が軽量型のスピード重視の構成の機体とは言っても、我々の保有するオートマタと比較にならないほどの早さだそうです」
「…………」
「そして何より……『あの機体と比較してしまえば、帝国全ての戦闘騎士が旧世代である』と言っておられました」
「……どういうことだ?」
側近の言葉――帝国の誇るエース、フランツ・ベルンハルトからの報告に、ルドルフⅡ世と閣僚たちの顔がひきつる。
特に閣僚たちの顔に浮かんだ表情は「これ以上悪い報告があるの?」「もうやめて聞きたくない」と言わんばかりである。
「皆さん、あの『舞乙女』が一本目の試合で撃った胸部からの大砲撃は覚えていらっしゃいますでしょうか?」
「ああ……あれか。銃器を手持ちではなく、まさかあんな場所に設置してあるとは」
「あの砲撃がなければ、シャンディ・ガフだって勝利したのではないか?」
側近の言葉に、確かにそんなものがあったとざわめき始める閣僚たち。
「そうです、あの胸部砲撃……。威力もさるものでしたが、それよりも、その概念自体が素晴らしいとは思いませんか?」
「と、言うと?」
「胸部に砲弾を撃てる機能を備え付けるという観点でございます! たとえば、戦闘時に両手がふさがっている状況が生まれた時、あの胸部砲撃があるかないかで、搭乗騎士の命運の分かれ目となるでしょう」
「……確かに」
「……そうだな、あれがあるかないかで、だいぶ戦闘の幅が違う」
「接近戦で組み付かれた時、あの胸部砲撃があれば……」
「ベルンハルトの言葉はそれを指してのことです。あのような戦闘騎士機巧は、我が帝国にはまだ生まれていない――つまり、我々よりも一歩先をいっている世代の戦闘騎士なのです。例えば我々にも同じ程度の資金があれば、あの機体と同じ程度のスペックの戦闘騎士を作ることは可能やもしれません。ですが、戦闘概念は資金だけでは生み出せない。あの戦闘騎士を造りだした者たちは、資金力だけではなく、その概念力でさえ帝国や獣王国のはるか先を行っているのです」
どことなく興奮した面持ちで、口早に語る側近。その瞳には、まるで話題にしている『舞乙女』に憧れを抱いているような輝きがあった。
「……あの『舞乙女』を我らが帝国に送るということは、そのまったく新しい戦闘騎士概念を、我らが帝国に提供するにふさわしい行為ですな。ますます獣王国がそのようなことをする理由がなくなったというわけですか」
でっぷりとした腹の閣僚が肩をすくめて答える。
その隣の中年の閣僚が、おずおずと口を開いた。
「……それを含めて、我らを油断させる獣王国の奸計なのでは?」
「それであれば……むしろあの『舞乙女』は試合会場にいた王へその刃を向けていたはずでしょう。まぁ、正しくは王の身代わりへ、となりますが……」
そう――観覧席に座っている皇帝は、身代わりの皇帝であった。
あの『舞乙女』が獣王国の手の者であることを考慮し、観覧席には身代わりの皇帝をたて、ルドルフⅡ世は側近たちと共に、安全な場所から観戦を行っていた。
なお、隠し部屋での観戦は、ルドルフⅡ世の血縁であるノーマン整備班班長も共にいた。無論、帝国の誇る随一の戦闘騎士設計者でもあるノーマンに観戦を行わせ、『舞乙女』の機体とヤマトの実力をはかる目的のためである。
戦いが進むにつれ、ルドルフⅡ世の機嫌が急降下してくのに対し、ノーマンのテンションはうなぎのぼりになっていくため、「あれほど地獄のような時間はなかった」と後に側近の一人は語る。
「……ふむ。獣王国の尖兵ではない、ということが分かったのだから、得るものはあったということか」
いくぶんか穏やかになったルドルフⅡ世の声音に、ほっと側近や閣僚たちが一息をつく。特に、若い閣僚の真っ白な顔色はようやく血の気が戻ってきた。
「ふむ……ますます謎であるな。あの『舞乙女』を造り出した組織は、何を目的として、あのような高機能の機体と搭乗騎士をこのバルツァイ帝国へと派遣したのか……」
「ですが皇帝陛下。どんな思惑があるにせよ……あの『舞乙女』が、今は我らの帝国に所属する戦闘騎士であるのは確かでございます。何せ、あの搭乗騎士自身が公に帝国への移住を申し出てきたのですからな。陛下があの搭乗騎士へ移住をお認めになられたのは、やはり英断でございました」
腹のでっぷりとした閣僚が、この機会を逃すまいとばかりに、ルドルフⅡ世を持ち上げる。だが、その言葉は嘘ではなかった。あの機体がシャンディ・ガフをあっさりと打ち負かした今となっては、本心からの言葉でそう言える。
「ふむ、労せず能力の高い戦闘騎士と搭乗騎士を手に入れられたと考えれば損はない、ということか。むしろ、新しい戦闘騎士の戦闘概念すら提供してもらったのだからな。あの機巧は我らの保有する戦闘騎士に取り付けることもできそうなのだろう?」
「もちろんでございます! ノーマン殿はさっそく機巧の手配を進めているようです」
「あやつらしいことよ。では……あのヤマトという男の目的は分からぬが、あちらが我らを利用する腹積もりならば、こちらも利用するまでであるな」
「……と、おっしゃいますと?」
でっぷりとした腹の閣僚が、恐る恐るルドルフⅡ世に尋ねる。
ルドルフⅡ世は自らの白髭を片手で撫で付けながら、円卓に座る閣僚たちをぐるりと見渡して、厳かな声で告げた。
「あの『舞乙女』の搭乗騎士、ヤマトには――帝国戦闘騎士に所属してもらうこととする。報告では、第三部部隊隊長のヴァン・イホークはかなり懇意になることに成功したようだからな。理由としては、移住者であるあの者の立場を鑑みて、懇意の者がいる第三部隊への配属が適切であると判断した、と伝えよ」
ルドルフⅡ世の言葉に、会議室に座っていた人々の口からは「なっ……」と驚きの声が漏れた。
前代未聞だった。
通例では――オートマタ乗りは、帝国戦闘騎士第一部隊への配属になる。
第二番隊以下はマニュアルタイプの戦闘騎士が配備されている。そんな中に、シャンディ・ガフを打ち負かしたあの『舞乙女』を配属するというのは、もはやそれは左遷に近い。ルドルフⅡ世の告げた「懇意の者がいる第三部隊への配属が適切である」というのがただの名目であることは、あの搭乗騎士にもすぐに分かるだろう。
「無論、任務も分け隔てをすることはない。あの『舞乙女』には第三部隊の者たちと同様に、共に帝国内や国境周辺のモンスターの退治、素材採取に行ってもらうこととする」
会議室のざわめきはますます大きくなる。
帝国内や辺境、国境周辺のモンスターの退治や素材採取にオートマタ乗りを行かせるなど聞いたことがない。
オートマタ乗りは帝国内でも十人にも満たない。その貴重さと、搭乗中のフィードバック問題から、オートマタ乗りは国防を担うのが主な任務であり、外周のモンスター退治に行くことなどは滅多にない。
マニュアル部隊では対応しきれない高ランクのモンスターが出た、ということであれば出動もあるが、マニュアル部隊と共にモンスター退治へ行かせるなんていうことは前代未聞だった。
「そのような命令……あの男が頷くでしょうか?」
側近がこわごわと陛下に問いかける。
いかに皇帝陛下の命令と言えども、オートマタ乗りであれば、マニュアル部隊と共にモンスター退治に行かせられるなど、屈辱を感じずにはいられないだろう。
「頷かなければ、あのオートマタ乗りから情報を引き出す口実ができる。そも、今回はもとはと言えば、あの男から移住の申し入れがあったのだ。この帝国の民となった以上は、余の命令に従う義務がある。違うか?」
「……おっしゃる通りでございます」
そう。あの男が屈辱をどれほど感じようとも――陛下の命令には頷くしかないだろう。
どのような腹でこの帝国に来たにせよ、公に陛下から移住を認められた以上は、もはや帝国の一市民であるのだから。陛下からの命令に逆らうことはできない。
側近は、背筋をぶるりと震わせた。
……皇帝陛下は、あの男に駆け引きをしかけようとしているのだ。屈辱を与え、プライドを刺激し、向こうが音を上げるのを待ち、そして情報を引き出そうとしている。
「……陛下の深謀遠慮には感服しきりでございますな」
でっぷりとした腹の閣僚も、目を見張ってルドルフⅡ世を見る。ルドルフⅡ世は彼らに鷹揚に頷くと、再び厳かな声で彼らに告げた。
「さっそくこの配属の件を、あの搭乗騎士と第三部隊に通達せよ。並びに、引き続きあの『舞乙女』の搭乗騎士には厳重な監視を続けるのだ。――だが、決して、眠れる竜を目覚めさせるような愚昧を犯すのではないぞ!」
「「「「 ――ハッ! 」」」」
帝城のとある会議室に響く皇帝、ルドルフⅡ世の声音は、絶対零度の響きを帯びていた。
それもそのはずだ。本日行われた、闘技場でのオートマタ同士の試合結果――帝国のエースの中のエース、シャンディ・ガフがまさかの敗北。
しかもただの敗北ではない。先取制の三本試合の形式での戦いで、まさかのストレート負け。しかも、一本目の試合は10分もかからず、二本目の試合は3分にも満たない時間で敗北したのである。
この闘技場での試合を最初に提案した若い閣僚は、もはやすっかり血の気をなくし、真っ白な顔で席に座っていた。テーブルの下の両足は、生まれたての子鹿のようにがくがくと震えている。
「あの漆黒の機体『舞乙女』は、ランクの高い魔晶石をふんだんに使っている優れた機体である。だが、そのような機体を扱うともなれば、搭乗騎士へのフィードバック、負担は相当なものとなる……そのはずだったな?」
「そ、そのはずでございました……」
「では、今回の結果はどういうことか? 我が国が誇るシャンディ・ガフをああもやすやすと打ち負かしたのだぞ。いや、敗北などという言葉では生ぬるい。大人が幼児を相手どるかのように――まるで相手になっていなかったではないか!」
ルドルフⅡ世の怒声に、若い閣僚が「ひっ」と小さく悲鳴をあげて首をすくめる。
だが、ルドルフⅡ世も胸中では――これがただの八つ当たりに近いものであることは自覚していた。
彼の想定の内には、もしかするとあの機体が本当に自分たちの機体をも上回る性能を持ち、シャンディ・ガフに勝利をするかもしれない、という可能性も考慮していたのだ。だが、その予想は大幅に覆された。まさかのシャンディ・ガフのストレート負けという事態に、さすがのルドルフⅡ世も今は冷静ではいられなかったのである。
会議室の円卓は側近や大臣、閣僚たちでいっぱいではあったものの、その誰もが口を開こうとしなかった。しかし、しばらくしてから円卓に座っていたでっぷりとした腹の閣僚が、ゆっくりと口を開いた。
「しかし、陛下。今回の試合で分かったこともございます。……初めに我らが予想していた『獣王国の奸計』ではないかという可能性はなくなりました。つまりあれは、獣王国側の機体ではないということです」
「なぜそう思うのだ?」
でっぷりとした腹の閣僚の静かな言葉に、ルドルフⅡ世の気持ちがわずかに収まり、話を続けるように促す。
「単純に、シャンディ・ガフを相手にあれほどの力量と搭乗技量を持つものを獣王国側が我々に派遣する理由ございません。奸計をめぐらす必要すらないほどの強さですからな」
「……確かに、そうであるな」
ルドルフⅡ世の気持ちが幾分か冷静になったのを見てとり、傍らの側近もおずおずと話を切り出した。
「今回の試合でございましたが……戦ったフランツ・ベルンハルトからの報告がございます。報告をさせて頂いてもよろしいでしょうか?」
「……構わぬ」
「ありがとうございます。今回のベルンハルトからの報告ですが――『舞乙女』の機体のスピード。あの機体が軽量型のスピード重視の構成の機体とは言っても、我々の保有するオートマタと比較にならないほどの早さだそうです」
「…………」
「そして何より……『あの機体と比較してしまえば、帝国全ての戦闘騎士が旧世代である』と言っておられました」
「……どういうことだ?」
側近の言葉――帝国の誇るエース、フランツ・ベルンハルトからの報告に、ルドルフⅡ世と閣僚たちの顔がひきつる。
特に閣僚たちの顔に浮かんだ表情は「これ以上悪い報告があるの?」「もうやめて聞きたくない」と言わんばかりである。
「皆さん、あの『舞乙女』が一本目の試合で撃った胸部からの大砲撃は覚えていらっしゃいますでしょうか?」
「ああ……あれか。銃器を手持ちではなく、まさかあんな場所に設置してあるとは」
「あの砲撃がなければ、シャンディ・ガフだって勝利したのではないか?」
側近の言葉に、確かにそんなものがあったとざわめき始める閣僚たち。
「そうです、あの胸部砲撃……。威力もさるものでしたが、それよりも、その概念自体が素晴らしいとは思いませんか?」
「と、言うと?」
「胸部に砲弾を撃てる機能を備え付けるという観点でございます! たとえば、戦闘時に両手がふさがっている状況が生まれた時、あの胸部砲撃があるかないかで、搭乗騎士の命運の分かれ目となるでしょう」
「……確かに」
「……そうだな、あれがあるかないかで、だいぶ戦闘の幅が違う」
「接近戦で組み付かれた時、あの胸部砲撃があれば……」
「ベルンハルトの言葉はそれを指してのことです。あのような戦闘騎士機巧は、我が帝国にはまだ生まれていない――つまり、我々よりも一歩先をいっている世代の戦闘騎士なのです。例えば我々にも同じ程度の資金があれば、あの機体と同じ程度のスペックの戦闘騎士を作ることは可能やもしれません。ですが、戦闘概念は資金だけでは生み出せない。あの戦闘騎士を造りだした者たちは、資金力だけではなく、その概念力でさえ帝国や獣王国のはるか先を行っているのです」
どことなく興奮した面持ちで、口早に語る側近。その瞳には、まるで話題にしている『舞乙女』に憧れを抱いているような輝きがあった。
「……あの『舞乙女』を我らが帝国に送るということは、そのまったく新しい戦闘騎士概念を、我らが帝国に提供するにふさわしい行為ですな。ますます獣王国がそのようなことをする理由がなくなったというわけですか」
でっぷりとした腹の閣僚が肩をすくめて答える。
その隣の中年の閣僚が、おずおずと口を開いた。
「……それを含めて、我らを油断させる獣王国の奸計なのでは?」
「それであれば……むしろあの『舞乙女』は試合会場にいた王へその刃を向けていたはずでしょう。まぁ、正しくは王の身代わりへ、となりますが……」
そう――観覧席に座っている皇帝は、身代わりの皇帝であった。
あの『舞乙女』が獣王国の手の者であることを考慮し、観覧席には身代わりの皇帝をたて、ルドルフⅡ世は側近たちと共に、安全な場所から観戦を行っていた。
なお、隠し部屋での観戦は、ルドルフⅡ世の血縁であるノーマン整備班班長も共にいた。無論、帝国の誇る随一の戦闘騎士設計者でもあるノーマンに観戦を行わせ、『舞乙女』の機体とヤマトの実力をはかる目的のためである。
戦いが進むにつれ、ルドルフⅡ世の機嫌が急降下してくのに対し、ノーマンのテンションはうなぎのぼりになっていくため、「あれほど地獄のような時間はなかった」と後に側近の一人は語る。
「……ふむ。獣王国の尖兵ではない、ということが分かったのだから、得るものはあったということか」
いくぶんか穏やかになったルドルフⅡ世の声音に、ほっと側近や閣僚たちが一息をつく。特に、若い閣僚の真っ白な顔色はようやく血の気が戻ってきた。
「ふむ……ますます謎であるな。あの『舞乙女』を造り出した組織は、何を目的として、あのような高機能の機体と搭乗騎士をこのバルツァイ帝国へと派遣したのか……」
「ですが皇帝陛下。どんな思惑があるにせよ……あの『舞乙女』が、今は我らの帝国に所属する戦闘騎士であるのは確かでございます。何せ、あの搭乗騎士自身が公に帝国への移住を申し出てきたのですからな。陛下があの搭乗騎士へ移住をお認めになられたのは、やはり英断でございました」
腹のでっぷりとした閣僚が、この機会を逃すまいとばかりに、ルドルフⅡ世を持ち上げる。だが、その言葉は嘘ではなかった。あの機体がシャンディ・ガフをあっさりと打ち負かした今となっては、本心からの言葉でそう言える。
「ふむ、労せず能力の高い戦闘騎士と搭乗騎士を手に入れられたと考えれば損はない、ということか。むしろ、新しい戦闘騎士の戦闘概念すら提供してもらったのだからな。あの機巧は我らの保有する戦闘騎士に取り付けることもできそうなのだろう?」
「もちろんでございます! ノーマン殿はさっそく機巧の手配を進めているようです」
「あやつらしいことよ。では……あのヤマトという男の目的は分からぬが、あちらが我らを利用する腹積もりならば、こちらも利用するまでであるな」
「……と、おっしゃいますと?」
でっぷりとした腹の閣僚が、恐る恐るルドルフⅡ世に尋ねる。
ルドルフⅡ世は自らの白髭を片手で撫で付けながら、円卓に座る閣僚たちをぐるりと見渡して、厳かな声で告げた。
「あの『舞乙女』の搭乗騎士、ヤマトには――帝国戦闘騎士に所属してもらうこととする。報告では、第三部部隊隊長のヴァン・イホークはかなり懇意になることに成功したようだからな。理由としては、移住者であるあの者の立場を鑑みて、懇意の者がいる第三部隊への配属が適切であると判断した、と伝えよ」
ルドルフⅡ世の言葉に、会議室に座っていた人々の口からは「なっ……」と驚きの声が漏れた。
前代未聞だった。
通例では――オートマタ乗りは、帝国戦闘騎士第一部隊への配属になる。
第二番隊以下はマニュアルタイプの戦闘騎士が配備されている。そんな中に、シャンディ・ガフを打ち負かしたあの『舞乙女』を配属するというのは、もはやそれは左遷に近い。ルドルフⅡ世の告げた「懇意の者がいる第三部隊への配属が適切である」というのがただの名目であることは、あの搭乗騎士にもすぐに分かるだろう。
「無論、任務も分け隔てをすることはない。あの『舞乙女』には第三部隊の者たちと同様に、共に帝国内や国境周辺のモンスターの退治、素材採取に行ってもらうこととする」
会議室のざわめきはますます大きくなる。
帝国内や辺境、国境周辺のモンスターの退治や素材採取にオートマタ乗りを行かせるなど聞いたことがない。
オートマタ乗りは帝国内でも十人にも満たない。その貴重さと、搭乗中のフィードバック問題から、オートマタ乗りは国防を担うのが主な任務であり、外周のモンスター退治に行くことなどは滅多にない。
マニュアル部隊では対応しきれない高ランクのモンスターが出た、ということであれば出動もあるが、マニュアル部隊と共にモンスター退治へ行かせるなんていうことは前代未聞だった。
「そのような命令……あの男が頷くでしょうか?」
側近がこわごわと陛下に問いかける。
いかに皇帝陛下の命令と言えども、オートマタ乗りであれば、マニュアル部隊と共にモンスター退治に行かせられるなど、屈辱を感じずにはいられないだろう。
「頷かなければ、あのオートマタ乗りから情報を引き出す口実ができる。そも、今回はもとはと言えば、あの男から移住の申し入れがあったのだ。この帝国の民となった以上は、余の命令に従う義務がある。違うか?」
「……おっしゃる通りでございます」
そう。あの男が屈辱をどれほど感じようとも――陛下の命令には頷くしかないだろう。
どのような腹でこの帝国に来たにせよ、公に陛下から移住を認められた以上は、もはや帝国の一市民であるのだから。陛下からの命令に逆らうことはできない。
側近は、背筋をぶるりと震わせた。
……皇帝陛下は、あの男に駆け引きをしかけようとしているのだ。屈辱を与え、プライドを刺激し、向こうが音を上げるのを待ち、そして情報を引き出そうとしている。
「……陛下の深謀遠慮には感服しきりでございますな」
でっぷりとした腹の閣僚も、目を見張ってルドルフⅡ世を見る。ルドルフⅡ世は彼らに鷹揚に頷くと、再び厳かな声で彼らに告げた。
「さっそくこの配属の件を、あの搭乗騎士と第三部隊に通達せよ。並びに、引き続きあの『舞乙女』の搭乗騎士には厳重な監視を続けるのだ。――だが、決して、眠れる竜を目覚めさせるような愚昧を犯すのではないぞ!」
「「「「 ――ハッ! 」」」」
応援ありがとうございます!
20
お気に入りに追加
3,135
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる